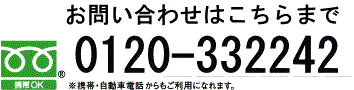労働者派遣事業関係業務取扱要領
※ 2020年4月1日施行
平成31年4月
厚生労働省職業安定局
目次
第1 労働者派遣事業の意義等……………………………………………………………………1
1 労働者派遣……………………………………………………………………………………1
(1)「労働者派遣」の意義……………………………………………………………………1
(2)「労働者」及び「雇用関係」の意義……………………………………………………1
(3)「指揮命令」の意義………………………………………………………………………1
* (労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準)…………… 3
(4) 出向との関係……………………………………………………………………………… 9
(5)労働者供給との関係………………………………………………………………………11
(6)ジョイント・ベンチャー(JV)との関係……………………………………………12
(7)派遣店員との関係…………………………………………………………………………15
(8)その他………………………………………………………………………………………15
2 派遣労働者……………………………………………………………………………………16
(1)「派遣労働者」の意義……………………………………………………………………16
(2)「事業主が雇用する労働者」の意義……………………………………………………16
(3)「労働者派遣の対象」の意義……………………………………………………………16
(4)有期雇用派遣労働者と無期雇用派遣労働者……………………………………………16
3 労働者派遣事業………………………………………………………………………………16
(1)「労働者派遣事業」の意義………………………………………………………………16
(2)「業として行う」の意義…………………………………………………………………17
(3)適用除外業務との関係……………………………………………………………………17
(4)「登録型派遣」と「常用型派遣」………………………………………………………17
4 紹介予定派遣…………………………………………………………………………………17
5 法の適用範囲…………………………………………………………………………………18
(1)法の適用範囲の原則………………………………………………………………………18
(2)公務員等に対する法の適用………………………………………………………………18
(3)船員に対する法の適用除外………………………………………………………………19
第2 適用除外業務等………………………………………………………………………………20
1 適用除外業務に係る制限……………………………………………………………………20
2 適用除外業務の範囲…………………………………………………………………………20
(1)港湾労働法第2条第1号に規定する港湾(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸
及び関門)における同条第2号に規定する港湾運送業務………………………………20
(2)港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送業務………22
(3)建設業務……………………………………………………………………………………24
(4)警備業務……………………………………………………………………………………25
(5)その他の業務………………………………………………………………………………26
6 労働者派遣事業所台帳及び労働者派遣事業主台帳の整備等………………………………99
(1)許可時の対応………………………………………………………………………………99
(2)更新時の対応………………………………………………………………………………99
(3)変更時の対応………………………………………………………………………………99
(4)廃止時の対応………………………………………………………………………………99
(5)事業所台帳等の保管………………………………………………………………………100
7 名義貸しの禁止…………………………………………………………………………………100
8 その他……………………………………………………………………………………………100
(1)個人事業主が死亡した場合の取扱い……………………………………………………100
(2)法人の合併等に際しての取扱い…………………………………………………………100
9 参考一覧表………………………………………………………………………………………103
(1)手数料の納付手続き一覧表………………………………………………………………103
(2)登録免許税の課税手続き一覧表…………………………………………………………103
(3)用語の整理…………………………………………………………………………………104
(4)事業主の行う手続の種類…………………………………………………………………107
(5)労働派遣事業関係手続提出書類一覧……………………………………………………108
第4 (旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置………………………………………………110
1 経過措置に関する概要………………………………………………………………………110
(1)(旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置……………………………………………110
(2)(旧)特定労働者派遣事業の欠格事由…………………………………………………112
(3)書類の備付け等……………………………………………………………………………112
2 経過措置に関する変更の届出手続…………………………………………………………113
(1)(旧)特定労働者派遣事業の変更の届出………………………………………………113
(2)変更届出関係書類…………………………………………………………………………114
(3)他局に移管した場合の受理番号関係……………………………………………………116
(4)(旧)特定労働者派遣事業届出受理番号の設定について……………………………116
(5)労働者派遣事業届出書の受理……………………………………………………………117
3 事業主の行う事業廃止の届出手続…………………………………………………………117
(1)(旧)特定労働者派遣事業の廃止の届出………………………………………………117
(2)事業廃止の届出の受理……………………………………………………………………118
(3)届出の効力…………………………………………………………………………………118
4 (旧)特定労働者派遣事業所台帳等の整備等……………………………………………118
5 名義貸しの禁止………………………………………………………………………………118
6 その他…………………………………………………………………………………………119
第5 事業報告等……………………………………………………………………………………120
1 事業報告書、収支決算書……………………………………………………………………120
(1)事業報告書…………………………………………………………………………………120
(2)収支決算書…………………………………………………………………………………121
2 関係派遣先に対する労働者派遣の制限等…………………………………………………122
(1)「関係派遣先」の範囲……………………………………………………………………122
(2)「派遣割合」の算出方法…………………………………………………………………123
(3)報告の方法…………………………………………………………………………………123
3 海外派遣の届出………………………………………………………………………………124
(1)法第23条第4項に規定する「海外派遣」の概要………………………………………124
(2)届出の方法…………………………………………………………………………………124
(3)海外派遣の届出の受理……………………………………………………………………125
4 事業所ごとの情報提供………………………………………………………………………125
(1)概要…………………………………………………………………………………………125
(2)情報提供すべき事項………………………………………………………………………125
(3)情報提供の方法等…………………………………………………………………………128
5 労働争議に対する不介入……………………………………………………………………128
(1)概要…………………………………………………………………………………………128
(2)労働争議に対する不介入の趣旨…………………………………………………………129
(3)現に同盟罷業又は作業所閉鎖の行われているときの規制……………………………129
(4)争議行為が発生しており、同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの
多いときの規制………………………………………………………………………………129
6 個人情報の保護………………………………………………………………………………130
(1)概要…………………………………………………………………………………………130
(2)個人情報の収集、保管及び使用…………………………………………………………130
(3)個人情報の適正管理………………………………………………………………………133
(4)個人情報の保護に関する法律の遵守等…………………………………………………134
(5)秘密を守る義務……………………………………………………………………………134
第6 労働者派遣契約………………………………………………………………………………136
1 意義……………………………………………………………………………………………136
2 契約の内容等…………………………………………………………………………………136
(1)契約内容……………………………………………………………………………………136
(2)派遣可能期間の制限に抵触する日の通知………………………………………………148
(3)比較対象労働者の待遇に関する情報の提供……………………………………………149
(4)派遣料金の配慮……………………………………………………………………………160
(5)海外派遣の場合の労働者派遣契約………………………………………………………160
(6)派遣元事業主であることの明示…………………………………………………………164
3 労働者派遣契約の解除の制限………………………………………………………………165
(1)概要…………………………………………………………………………………………165
(2)意義…………………………………………………………………………………………165
(3)労働者派遣契約の解除が禁止される事由………………………………………………165
4 派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等…………………………………166
(1)概要…………………………………………………………………………………………166
-日 4-
(2)意義…………………………………………………………………………………………166
(3)労働者派遣契約の解除等を行える具体的事由…………………………………………166
5 労働者派遣契約の解除の非遡及……………………………………………………………167
(1)概要…………………………………………………………………………………………167
(2)意義…………………………………………………………………………………………167
6 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置………………………………………167
(1)概要…………………………………………………………………………………………167
(2)派遣先の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置…………………167
(3)派遣元事業主の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置…………169
(4)その他………………………………………………………………………………………169
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等……………………………………………………………170
1 概要……………………………………………………………………………………………170
2 特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置………………………………170
(1)概要…………………………………………………………………………………………170
(2)意義…………………………………………………………………………………………171
(3)具体的な措置の内容………………………………………………………………………171
(4)対象者についての留意点…………………………………………………………………173
(5)講ずべき措置の内容についての留意点…………………………………………………174
(6)その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置に関する留意点…175
(7)労働契約法の適用について留意すべき事項……………………………………………176
3 派遣労働者に対するキャリアアップ措置…………………………………………………177
(1)概要…………………………………………………………………………………………177
(2)意義…………………………………………………………………………………………177
(3)段階的かつ体系的な教育訓練について…………………………………………………177
(4)段階的かつ体系的な教育訓練に関する留意点…………………………………………179
(5)希望者に対するキャリアコンサルティング等の実施について………………………180
(6)その他の留意事項…………………………………………………………………………180
4 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置………………………181
(1)概要…………………………………………………………………………………………181
(2)意義…………………………………………………………………………………………181
(3)均衡を考慮した待遇の確保のための措置に関する留意点……………………………182
(4)均衡を考慮した待遇の確保のための措置の実施………………………………………183
(5)均等な待遇の確保のための措置の考え方………………………………………………183
(6)均等な待遇の確保のための措置の実施…………………………………………………184
(7)同一労働同一賃金ガイドライン…………………………………………………………185
(8)短時間・有期雇用労働者である派遣労働者の短時間・有期雇用労働法の適用……185
(9)留意点………………………………………………………………………………………186
5 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保のための措置…………………………188
(1)概要…………………………………………………………………………………………188
-日 5-
(2)意義…………………………………………………………………………………………188
(3)労使協定の締結方法………………………………………………………………………188
(4)労使協定の保存……………………………………………………………………………190
(5)労使協定の対象とならない待遇…………………………………………………………190
(6)労使協定の記載事項………………………………………………………………………190
(7)労使協定の周知……………………………………………………………………………192
(8)行政機関への報告…………………………………………………………………………194
(9)協定対象派遣労働者に対する安全管理に関する措置及び給付………………………194
6 職務の内容等を勘案した賃金の決定………………………………………………………194
(1)概要…………………………………………………………………………………………194
(2)意義…………………………………………………………………………………………194
(3)職務の内容等を勘案した賃金の決定の対象外となる賃金……………………………194
(4)具体的な措置の内容………………………………………………………………………195
7 就業規則の作成等における派遣労働者の過半数を代表する者への意見聴取…………196
(1)概要…………………………………………………………………………………………196
(2)意義…………………………………………………………………………………………196
(3)具体的な措置の内容………………………………………………………………………196
8 派遣労働者等の福祉の増進…………………………………………………………………197
(1)概要…………………………………………………………………………………………197
(2)直接雇用の推進……………………………………………………………………………197
(3)派遣労働者等の福祉の増進に関する留意点……………………………………………198
(4)育児休業から復帰する際の就業条件の確保……………………………………………198
(5)障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている
事情の改善を図るための措置………………………………………………………………198
9 適正な派遣就業の確保………………………………………………………………………198
(1)概要…………………………………………………………………………………………198
(2)意義…………………………………………………………………………………………199
(3)具体的配慮の内容…………………………………………………………………………199
(4)法第44条第3項及び第4項並びに法第45条第6項及び第7項との関係……………200
(5)安全衛生に係る措置………………………………………………………………………200
10 待遇に関する事項等の説明…………………………………………………………………201
(1)派遣労働者として雇用しようとするときの説明………………………………………201
(2)派遣労働者として雇い入れようとするときの明示及び説明…………………………203
(3)労働者派遣をしようとするときの明示及び説明………………………………………205
(4)待遇の相違の内容及び理由等の説明……………………………………………………207
11派遣労働者であることの明示等……………………………………………………………209
(1)雇入れの際の明示…………………………………………………………………………209
(2)雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意……………………………………210
(3)派遣労働者であることの明示等に関する留意点………………………………………210
12 派遣労働者に係る雇用制限の禁止…………………………………………………………211
-日 6-
(1)概要…………………………………………………………………………………………211
(2)派遣労働者に係る雇用制限の禁止の意義………………………………………………212
(3)「正当な理由」の意義……………………………………………………………………212
13 就業条件等の明示……………………………………………………………………………212
(1)概要…………………………………………………………………………………………212
(2)意義…………………………………………………………………………………………213
(3)明示すべき就業条件等……………………………………………………………………213
(4)期間制限に抵触することとなる最初の日の明示………………………………………216
(5)明示の方法…………………………………………………………………………………220
(6)明示に関する留意点………………………………………………………………………221
14 労働者派遣に関する料金の額の明示………………………………………………………222
(1)概要…………………………………………………………………………………………222
(2)意義…………………………………………………………………………………………222
(3)明示すべき労働者派遣に関する料金の額………………………………………………222
(4)明示の方法…………………………………………………………………………………223
15 派遣先への通知………………………………………………………………………………223
(1)概要…………………………………………………………………………………………223
(2)通知の趣旨…………………………………………………………………………………223
(3)通知すべき事項……………………………………………………………………………224
(4)通知の方法…………………………………………………………………………………226
(5)通知の手続…………………………………………………………………………………226
(6)通知に際しての留意点……………………………………………………………………227
16 労働者派遣期間の制限の適切な運用………………………………………………………228
(1)概要…………………………………………………………………………………………228
(2)意義…………………………………………………………………………………………228
(3)派遣期間の制限の適切な運用のための留意点…………………………………………228
17 日雇労働者についての労働者派遣の禁止…………………………………………………229
(1)概要…………………………………………………………………………………………229
(2)意義…………………………………………………………………………………………230
(3)禁止の範囲…………………………………………………………………………………230
(4)禁止の例外…………………………………………………………………………………230
(5)要件の確認方法……………………………………………………………………………231
* 日雇派遣の禁止の例外として認められる令4条の業務……………………………233
18 離職した労働者についての労働者派遣の禁止……………………………………………244
(1)概要…………………………………………………………………………………………244
(2)意義…………………………………………………………………………………………244
(3)離職した労働者についての労働者派遣の禁止の留意点………………………………244
19 派遣元責任者の選任…………………………………………………………………………244
(1)概要…………………………………………………………………………………………244
(2)派遣元責任者の選任の方法等……………………………………………………………244
-日 7-
(3)派遣元責任者の職務………………………………………………………………………246
20 派遣元管理台帳………………………………………………………………………………248
(1)派遣元管理台帳の作成、記載……………………………………………………………248
(2)派遣元管理台帳の保存……………………………………………………………………253
21労働・社会保険の適用の促進………………………………………………………………253
(1)労働・社会保険への適切な加入…………………………………………………………253
(2)被保険者証等の写し等の提示……………………………………………………………253
(3)派遣労働者に対する未加入の理由の通知………………………………………………254
22 関係法令の関係者への周知…………………………………………………………………254
23 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等…………………254
24 性・障害の有無・年齢による差別的な取扱いの禁止等…………………………………255
(1)派遣労働者の性別の労働者派遣契約への記載の禁止等………………………………255
(2)障害者であることを理由とする不当な差別的取り扱いの禁止等……………………255
(3)年齢による不合理な差別的派遣に対する指導等………………………………………255
(4)派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の禁止に向けた取組……………………255
(5)紹介予定派遣における派遣労働者の特定に当たっての年齢、性別等による
差別防止に係る措置…………………………………………………………………………256
(6)「派遣労働者を特定することを目的とする行為への協力の禁止等」との関係……257
25 紹介予定派遣…………………………………………………………………………………257
(1)紹介予定派遣の期間………………………………………………………………………257
(2)派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由
の明示…………………………………………………………………………………………257
(3)派遣就業期間の短縮………………………………………………………………………257
(4)求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化……………258
(5)紹介予定派遣における派遣労働者を特定することを目的とする行為………………258
(6)その他………………………………………………………………………………………259
26 紹介予定派遣以外の派遣として派遣就業を開始した場合における
求人条件の明示等………………………………………………………………………………259
27 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針………………………………………………259
(1)概要…………………………………………………………………………………………259
(2)指針の公表…………………………………………………………………………………260
(3)無期雇用派遣労働者の募集………………………………………………………………260
28 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が
講ずべき措置に関する指針……………………………………………………………………260
(1)労働者派遣契約の期間の長期化(日雇派遣指針第2の2)…………………………260
(2)雇用契約の期間の長期化(日雇派遣指針第2の4)…………………………………260
(3)労働者派遣契約に定める就業条件の確保(日雇派遣指針第3)……………………261
(4)労働・社会保険の適用の促進(日雇派遣指針第4)……………………………………261
(5)関係法令等の関係者への周知(日雇派遣指針第7)…………………………………261
(6) 日雇派遣労働者の安全衛生の確保(日雇派遣指針第8)……………………………261
-日 8-
(7)派遣先への説明(日雇派遣指針第12)…………………………………………………261
29 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な
待遇の禁止等に関する指針……………………………………………………………………262
* 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針……………………………………………263
* 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が
講ずべき措置に関する指針…………………………………………………………………269
第8 派遣先の講ずべき措置等……………………………………………………………………273
1 概要……………………………………………………………………………………………273
2 労働者派遣契約に関する措置………………………………………………………………273
(1)概要…………………………………………………………………………………………273
(2)労働者派遣契約に定める就業条件の確保………………………………………………273
(3)労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等…………………274
(4)法第43条による準用………………………………………………………………………274
3 適正な派遣就業の確保………………………………………………………………………274
(1)概要…………………………………………………………………………………………274
(2)苦情の適切な処理…………………………………………………………………………274
(3)適正な就業環境の確保……………………………………………………………………276
(4)障害者である派遣労働者の適正な就業の確保…………………………………………276
(5)雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの労働者派遣の受け入れ…276
(6)安全衛生に係る措置………………………………………………………………………277
4 派遣先による均衡待遇の確保………………………………………………………………278
(1)概要…………………………………………………………………………………………278
(2)教育訓練・能力開発………………………………………………………………………278
(3)福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)…………………………………………279
(4)福利厚生((3)の施設を除く。)……………………………………………………279
(5)派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の職務遂行状況等の情幸酎こついて
提供する配慮義務……………………………………………………………………………279
(6)派遣先が業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を
実施せず、又は福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用
の機会を付与しない場合の取扱い…………………………………………………………280
5 派遣先の事業所単位の期間制限の適切な運用……………………………………………280
(1)概要…………………………………………………………………………………………280
(2)意義…………………………………………………………………………………………280
(3)派遣可能期間の考え方……………………………………………………………………281
(4)派遣可能期間の延長等……………………………………………………………………283
(5)派遣先の事業所単位の期間制限の適切な運用のための留意点………………………287
6 派遣労働者個人単位の期間制限の適切な運用……………………………………………287
(1)概要…………………………………………………………………………………………287
(2)意義…………………………………………………………………………………………287
-日 9-
(3)期間制限の考え方…………………………………………………………………………288
(4)その他………………………………………………………………………………………288
7 期間制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い……………………288
(1)概要…………………………………………………………………………………………288
(2)勧告、公表の内容…………………………………………………………………………289
(3)権限の委任…………………………………………………………………………………289
(4)勧告、公表の手続…………………………………………………………………………289
(5)労働契約申込みみなし制度………………………………………………………………289
8 特定有期派遣労働者の雇用…………………………………………………………………289
(1)概要…………………………………………………………………………………………289
(2)意義…………………………………………………………………………………………290
(3)優先雇用の努力義務………………………………………………………………………290
(4)労働者募集情報の提供……………………………………………………………………290
9 派遣先での正社員化の推進…………………………………………………………………291
(1)概要…………………………………………………………………………………………291
(2)意義…………………………………………………………………………………………291
(3)具体的な措置の内容………………………………………………………………………291
10 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止…………………292
(1)概要…………………………………………………………………………………………292
(2)意義…………………………………………………………………………………………292
(3)通知の方法…………………………………………………………………………………292
(4)離職して1年を経過していない労働者を派遣労働者として受け入れた場合の
取扱い…………………………………………………………………………………………292
11派遣先責任者の選任…………………………………………………………………………292
(1)概要…………………………………………………………………………………………292
(2)派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行……………………………………293
(3)派遣先責任者の選任の方法………………………………………………………………293
(4)派遣先責任者の職務………………………………………………………………………294
(5)派遣先責任者講習の受講…………………………………………………………………295
12 派遣先管理台帳………………………………………………………………………………295
(1)意義…………………………………………………………………………………………295
(2)派遣先管理台帳の作成、記載……………………………………………………………295
(3)派遣先管理台帳の保存……………………………………………………………………300
(4)派遣元事業主への通知……………………………………………………………………300
13 労働・社会保険の適用の促進………………………………………………………………300
14 関係法令の関係者への通知…………………………………………………………………301
15 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止……………………………………301
(1)概要…………………………………………………………………………………………301
(2)意義…………………………………………………………………………………………301
16 性別・年齢による差別的取扱いの禁止等…………………………………………………302
-日10-
(1)性別による差別的取扱いの禁止等………………………………………………………302
(2)障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いの禁止等………………………302
(3)年齢による差別的取扱いに対する指導等………………………………………………302
(4)派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の禁止に向けた取組……………………302
(5)15の「派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止等」との関係…………302
17 紹介予定派遣…………………………………………………………………………………302
(1)紹介予定派遣を受け入れる期間…………………………………………………………302
(2)職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示………303
(3)派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別による差別防止に係る措置……………303
(4)派遣労働者の特定…………………………………………………………………………307
(5)派遣就業期間の短縮………………………………………………………………………307
(6)求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化……………307
(7)その他………………………………………………………………………………………307
18 派遣労働者の判断で行う派遣就業開始前の事業所訪問等………………………………308
19 派遣先が講ずべき措置に関する指針………………………………………………………308
(1)概要…………………………………………………………………………………………308
(2)指針の公表…………………………………………………………………………………308
20 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が
講ずべき措置に関する指針……………………………………………………………………308
21短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する
不合理な待遇の禁止等に関する指針…………………………………………………………309
* 派遣先が講ずべき措置に関する指針……………………………………………………310
第9 労働基準法等の適用に関する特例等………………………………………………………316
1 概要……………………………………………………………………………………………316
2 労働基準法の適用に関する特例等…………………………………………………………322
3 労働安全衛生法の適用に関する特例等……………………………………………………324
4 じん肺法の適用に関する特例等……………………………………………………………326
5 作業環境測定法の適用の特例………………………………………………………………328
6 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用の特例…328
7 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律の適用の特例……………………………………………………………………………329
第10 紛争の解決……………………………………………………………………………………330
1 苦情の自主的解決……………………………………………………………………………330
(1)概要…………………………………………………………………………………………330
(2)意義…………………………………………………………………………………………330
2 紛争の解決の促進に関する特例……………………………………………………………330
3 紛争の解決の援助……………………………………………………………………………331
(1)概要…………………………………………………………………………………………331
(2)意義…………………………………………………………………………………………331
-日11-
(3)援助を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止…………………………………331
4 調停……………………………………………………………………………………………331
(1)概要…………………………………………………………………………………………331
(2)意義…………………………………………………………………………………………331
(3)調停の対象となる事案……………………………………………………………………332
(4)調停の申請をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止……………………………332
(5)調停の手続…………………………………………………………………………………332
(6)時効の完成猶予……………………………………………………………………………334
(7)訴訟手続きの中止…………………………………………………………………………334
(8)資料提供の要求等…………………………………………………………………………335
第11個人情報保護法の遵守等……………………………………………………………………336
1 概要……………………………………………………………………………………………336
2 個人情報保護法等の規定並びに派遣元事業主が講ずべき措置及びその主な
留意点等…………………………………………………………………………………………336
第12 違法行為の防止、摘発………………………………………………………………………338
1 概要……………………………………………………………………………………………338
2 労働者等の相談への対応……………………………………………………………………338
(1)概要…………………………………………………………………………………………338
(2)意義…………………………………………………………………………………………338
(3)不利益取扱いの禁止………………………………………………………………………338
3 派遣元事業主、派遣先への周知徹底………………………………………………………339
4 指導及び助言…………………………………………………………………………………339
(1)概要…………………………………………………………………………………………339
(2)意義…………………………………………………………………………………………339
(3)権限の委任…………………………………………………………………………………339
5 報告……………………………………………………………………………………………339
(1)概要…………………………………………………………………………………………339
(2)意義…………………………………………………………………………………………340
(3)報告の徴収の手続…………………………………………………………………………340
(4)権限の委任…………………………………………………………………………………340
6 立入検査………………………………………………………………………………………340
(1)立入検査の実施……………………………………………………………………………340
(2)証明書………………………………………………………………………………………341
(3)立入検査の権限……………………………………………………………………………341
(4)権限の委任…………………………………………………………………………………341
7 違反の場合の効果……………………………………………………………………………341
(1)適用除外業務等……………………………………………………………………………341
(2)労働者派遣事業の許可等…………………………………………………………………342
(3)事業報告等…………………………………………………………………………………343
-日12-
(4)労働者派遣契約……………………………………………………………………………344
(5)派遣元事業主の講ずべき措置等…………………………………………………………345
(6)派遣先の講ずべき措置等…………………………………………………………………348
(7)紛争の解決(第10参照)…………………………………………………………………348
(8)報告…………………………………………………………………………………………348
(9)立入検査……………………………………………………………………………………348
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表…………………………………………350
1 違法行為による罰則…………………………………………………………………………350
2 違法行為による行政処分……………………………………………………………………353
(1)概要…………………………………………………………………………………………353
(2)労働者派遣事業に係る行政処分…………………………………………………………353
(3)改善命令……………………………………………………………………………………355
(4)労働者派遣の停止命令……………………………………………………………………355
3 法第4条第3項、第24条の2、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、
第40条の3、若しくは第40条の6第1項の規定に違反している者に対する勧告、公表 …356
(1)概要…………………………………………………………………………………………356
(2)法第4条第3項、第24条の2、第40条の2第1項の規定、第4項若しくは第5項
若しくは第40条の9第1項の規定に違反している者に対する勧告……………………356
(3)法第4条第3項、第24条の2、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、
若第40条の3若しくは第40条の9第1項の規定に違反している者に対する公表……359
4 労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として
行われている場合の勧告………………………………………………………………………359
(1)概要…………………………………………………………………………………………359
(2)意義…………………………………………………………………………………………359
(3)「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」の判断基準等…360
(4)勧告の対象としない事由…………………………………………………………………360
(5)勧告の内容…………………………………………………………………………………361
(6)権限の委任…………………………………………………………………………………361
(7)勧告実施の手続等…………………………………………………………………………361
5 関係派遣先への派遣割合制限違反等に関する指示………………………………………361
(1)概要…………………………………………………………………………………………361
(2)指示の対象となる判断基準等……………………………………………………………361
(3)指示の内容…………………………………………………………………………………362
(4)指示の委任…………………………………………………………………………………363
(5)指示の手続等………………………………………………………………………………363
第14 無許可で労働者派遣事業を行った事業主の公表…………………………………………364
1 概要……………………………………………………………………………………………364
2 無許可派遣事業主への対応…………………………………………………………………364
-日13-
3 公表内容………………………………………………………………………………………364
第15 その他…………………………………………………………………………………………366
1 行政機関の連携体制の確立…………………………………………………………………366
(1)都道府県労働局間の連携…………………………………………………………………366
(2)他の労働行政との連携……………………………………………………………………366
2 派遣元責任者講習……………………………………………………………………………366
(1)概要…………………………………………………………………………………………366
(2)講習機関の要件等…………………………………………………………………………367
(3)講習の内容等………………………………………………………………………………367
(4)手続き関係…………………………………………………………………………………370
(5)講習の適正な実施等について……………………………………………………………371
3 派遣先責任者講習……………………………………………………………………………379
(1)概要………………………………………………………………………………………… 379
(2)講習の実施に係る手続…………………………………………………………………… 383
4 民間の協力体制の整備………………………………………………………………………384
(1)概要…………………………………………………………………………………………384
(2)労働者派遣事業適正運営協力員…………………………………………………………384
第16 様式集
① 労働者派遣事業許可申請書/許可有効期間更新申請書(様式第1号)………………387
② 労働者派遣事業計画書(様式第3号)……………………………………………………390
③ 労働者派遣事業許可証(様式第4号)……………………………………………………397
④ 許可証再交付申請書/労働者派遣事業変更届出書/労働者派遣事業
変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)…………………………………………398
⑤ 労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)………………………………………………402
⑥ 労働者派遣事業報告書(様式第11号)……………………………………………………403
⑦ 労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)………………………………………………417
⑧ 関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2)……………………………………………419
⑨ 海外派遣届出書(様式第13号)……………………………………………………………421
⑲ 労働者派遣事業立入検査証(様式第14号)………………………………………………422
⑪ 労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について
⑫⑬⑭⑮⑱⑰⑱
(様式第15号)………………………………………………………………………………423
財産的基礎に関する要件についての誓約書(様式第16号)……………………………426
常時雇用する派遣労働者数の報告(様式第17号)………………………………………428
派遣元責任者講習実施申出書
派遣元責任者講習実施日程書
派遣元責任者講習受講者名簿
派遣元責任者講習受講証明書
派遣先責任者講習実施申出書
(様式第18号)
(様式第19号)
(様式第20号)
(様式第21号)
(様式第22号)
……………………………………………429
……………………………………………430
……………………………………………431
……………………………………………432
……………………………………………433
-日14-
⑲ 派遣先責任者講習実施日程書(様式第23号)……………………………………………434
⑳ 派遣元責任者講習廃止申出書(様式第24号)……………………………………………435
㊧ 労働者派遣事業不許可/許可有効期間不更新通知書……………………………………436
⑳ 労働者派遣事業許可条件通知書……………………………………………………………437
⑳ 労働条件通知書(派遣労働者用;常用、有期雇用型)…………………………………438
⑳ 労働条件通知書(派遣労働者用;日雇型)………………………………………………442
⑮ モデル就業条件明示書………………………………………………………………………444
⑳ モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)……………………………………447
⑰ 労働者派遣受入適正実施勧告書……………………………………………………………450
⑳ 労働者派遣事業勧告書………………………………………………………………………451
⑳ 労働者派遣事業指示書………………………………………………………………………452
⑳ 労働者派遣事業適正運営協力員身分証明書………………………………………………453
⑪ 比較対象労働者の待遇等に関する情報提供(様式第25号)……………………………454
⑫ 労使協定書(イメージ)……………………………………………………………………479
-日15-
第1 労働者派遣事業の意義等
第1 労働者派遣事業の意義等
1 労働者派遣
(1)「労働者派遣」の意義
労働者派遣とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受
けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇
用させることを約してするものを含まない」ものをいう(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号)。
したがって、労働者派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間の関係は、(力派遣元と
派遣労働者との間に雇用関係があり、②派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この
契約に基づき、派遣元が派遣先に労働者を派遣し、③派遣先は派遣元から委託された指揮命令の権
限に基づき、派遣労働者を指揮命令するというものである。
(2)「労働者」及び「雇用関係」の意義
イ 「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から賃金を支払われる者をいう。
ロ 「雇用関係」とは、民法(明治29年法律第89号)第623条の規定による雇用関係のみではな
く、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に従属的地位において労働を提供し、その提
供した労働の対債として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関
係をいう。労働者派遣に該当するためには、派遣元との間において当該雇用関係が継続している
ことが必要である。
(3)「指揮命令」の意義
イ 労働者派遣は、労働者を「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」
であり、この有無により、労働者派遣を業として行う労働者派遣事業(3参照)と請負により行
われる事業とが区分される(第1-1図参照)。
第1-1図 労働者派遣事業と請負により行われる事業との差異
○ 労働者派遣事業
労働者派遣契約
[垂∃→一一一一→[垂司
雇用関係\言揮命令関係
[亘亘]
○ 請負により行われる事業
請負契約
請負業者 く >
雇用関
[亘亘∃
\
[亘亘]
ロ 「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる」ものではないとして、労働
者派遣事業に該当せず、請負により行われる事業に該当すると判断されるためには、
-1-
第1 労働者派遣事業の意義等
第1に、当該労働者の労働力を当該事業主が自ら直接利用すること、すなわち、当該労働者の
作業の遂行について、当該事業主が直接指揮監督のすべてを行うとともに、
第2に、当該業務を自己の業務として相手方から独立して処理すること、すなわち、当該業務
が当該事業主の業務として、その有する能力に基づき自己の責任の下に処理されることが必要で
あるが、具体的には、次のような基準に基づき判断を行う(昭和61年労働省告示第37号)。
なお、労働者派遣を受け、当該派遣労働者を用いて、請負により事業を行うことが可能である
のは当然であるので留意すること。
- 2 -
第1 労働者派遣事業の意義等
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
(昭和61年労働省告示第37号)
I この基準は、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業に該当するか否かの判断を的
確に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明ら
かにすることを目的とする。
Ⅱ 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行
う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の1及び2のいずれにも該当する場
合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
1 次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら
直接利用するものであること。
(1)次の①及び②のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自
ら行うものであること。
① 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
当該要件の判断は、当該労働者に対する仕事の割り付け、順序、緩急の調整等につき
当該事業主が自ら行うものであるか否かを総合的に勘案して行う。
「総合的に勘案して行う」とは、これらのうちいずれかの事項を事業主が自ら行わな
い場合であっても、これについて特段の合理的な理由が認められる場合は、直ちに当該
要件に該当しないとは判断しない(以下同様。)という趣旨である。
〔製造業務の場合〕
受託者は、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を注文主から受けるよ
うにし、当該業務を処理するのに必要な労働者数等を自ら決定し、必要な労働者を選定
し、請け負った内容に沿った業務を行っていること。
受託者は、作業遂行の速度を自らの判断で決定することができること。また、受託者
は、作業の割り付け、順序を自らの判断で決定することができること。
〔車両運行管理業務の場合〕
あらかじめ定められた様式により運行計画(時刻、目的地等)を注文主から提出させ
当該運行計画が安全運転の確保、人員体制等から不適切なものとなっている場合には、
受託者がその旨を注文主に申し入れ変更できるものとなっていること。
〔医療事務受託業務の場合〕
受託業務従事者が病院等の管理者又は病院職員等から、その都度業務の遂行方法に関
する指示を受けることがないよう、受託するすべての業務について、業務内容やその量
- 3 -
第1 労働者派遣事業の意義等
遂行手順、実施日時、就業場所、業務遂行に当たっての連絡体制、トラブル発生時の対:
応方法等の事項について、書面を作成し、管理責任者が受託業務従事者に対し具体的に!
指示を行うこと。
〔バンケットサービスの場合〕
受託者は、バンケットコンパニオンがホテル等から業務の遂行に関する指示を受ける:
ことのないよう、あらかじめホテル等と挨拶、乾杯、歓談、催し物等の進行順序並びに!
それぞれの時点におけるバンケットコンパニオンが実施するサービスの内容及びサービ!
スの実施に際しての注意事項を打ち合わせ、取り決めていること。
② 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
当該要件の判断は、当該労働者の業務の遂行に関する技術的な指導、勤惰点検、出来
高査定等につき、当該事業主が自ら行うものであるか否かを総合的に勘案して行う。
〔医療事務受託業務の場合〕
受託者は、管理責任者を通じた定期的な受託業務従事者や病院等の担当者からの聴取
又はこれらの者との打ち合わせの機会を活用し、受託業務従事者の業務の遂行について
の評価を自ら行っていること。
(2)次の①及び②のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自
ら行うものであること。
① 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(
これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
当該要件の判断は、受託業務の実施日時(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)
について、事前に事業主が注文主と打ち合わせているか、業務中は注文主から直接指示
を受けることのないよう書面が作成されているか、それに基づいて事業主側の責任者を
通じて具体的に指示が行われているか、事業主自らが業務時間の実績把握を行っている
か否かを総合的に勘案して行う。
〔製造業務の場合〕
受託業務の行う具体的な日時(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)については
事前に受託者と注文主とで打ち合わせ、業務中は注文主から直接指示を受けることのな
いよう書面を作成し、それに基づいて受託者側の現場責任者を通じて具体的に指示を行
っていること。
受託業務従事者が実際に業務を行った業務時間については、受託者自らが把握できる
- 4 -
第1 労働者派遣事業の意義等
ような方策を採っていること。
② 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示そ
の他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこ
と。
当該要件の判断は、労働者の時間外、休日労働は事業主側の責任者が業務の進捗状況
等をみて自ら決定しているか、業務量の増減がある場合には、事前に注文主から連絡を
受ける体制としているか否かを総合的に勘案して行う。
〔製造業務の場合〕
受託業務の業務量の増加に伴う受託業務従事者の時間外、休日労働は、受託者側の現
場責任者が業務の進捗状況等をみて決定し、指示を行っていること。
〔バンケットサービスの場合〕
宴席が予定した時間を超えた場合の請負契約に定められたサービス提供の終了時間の
延長についてのホテル等との交渉及び延長することとした場合のバンケットコンパニオ
ンへの指示については、現場に配置している責任者が行っていること。
(3)次の①及び②のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための
指示その他の管理を自ら行うものであること。
① 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
当該要件の判断は、当該労働者に係る事業所への入退場に関する規律、服装、職場秩
序の保持、風紀維持のための規律等の決定、管理につき、当該事業主が自ら行うもので
あるか否かを総合的に勘案して行う。
なお、安全衛生、機密の保持等を目的とする等の合理的な理由に基づいて相手方が労
働者の服務上の規律に関与することがあっても、直ちに当該要件に該当しないと判断さ
れるものではない。
〔医療事務受託業務の場合〕
職場秩序の保持、風紀維持のための規律等の決定、指示を受託者が自ら行う(衛生管
理上等別途の合理的理由に基づいて病院等が労働者の服務上の規律に関与する場合を除
く。)ほか、聴取及び打合せの際に、あるいは定期的な就業場所の巡回の際に、勤務場
所での規律、服装、勤務態度等の管理を受託者が自ら行っていること。また、あらかじ
め病院等の担当者に対して、この旨の説明を行っていること。
- 5 -
第1 労働者派遣事業の意義等
② 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
当該要件の判断は、当該労働者に係る勤務場所、直接指揮命令する者等の決定及び変
更につき、当該事業主が自ら行うものであるか否かを総合的に勘案して行う。
なお、勤務場所については、当該業務の性格上、実際に就業することとなる場所が移
動すること等により、個々具体的な現実の勤務場所を当該事業主が決定又は変更できな
い場合は当該業務の性格に応じて合理的な範囲でこれが特定されれば足りるものである
〔製造業務の場合〕
自らの労働者の注文主の工場内における配置も受託者が決定すること。
また、業務量の緊急の増減がある場合には、前もって注文主から連絡を受ける体制に
し、受託者が人員の増減を決定すること。
〔バンケットサービスの場合〕
業務に従事するバンケットコンパニオンの決定についてはホテル等による指名や面接
選考等を行わずバンケット業者自らが決定すること。また、同一の宴席におけるバンケ
ットサービスを複数のバンケット業者が請け負う場合には、異なるバンケット業者のバ
ンケットコンパニオンが共同して1つのサービスを実施することのないよう、あらかじ
め各バンケット業者が担当するテーブルやサービス内容を明確に区分していること。
2 次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己
の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
(1)業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
(2)業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任
を負うこと。
当該要件の判断に当たり、資金についての調達、支弁の方法は特に問わないが、事業
運転資金等はすべて自らの責任で調達し、かつ、支弁していることが必要である。
〔医療事務受託業務の場合〕
受託業務の処理により、病院等及び第三者に損害を与えたときは、受託者が損害賠償
の責任を負う旨の規定を請負契約に定めていること。
〔車両運行管理業務の場合〕
自動車事故等が発生し、注文主が損害を被った場合には、受託者が注文主に対して損
害賠償の責任を負う(又は求償権に応ずる)旨の規定を契約書に明記するとともに、当
該責任を負う意思及び履行能力を担保するため、受託者が自動車事故等に係る任意保険
- 6 -
第1 労働者派遣事業の意義等
に加入していること。
〔給食受託業務の場合〕
契約書等に食中毒等が発生し損害賠償が求められる等注文主側が損害を被った場合に!
は、受託者が注文主に対して損害賠償の責任を負う(又は求償権に応ずる)旨の規定を!
明記していること。
(3)次のイ又はロのいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するもので
ないこと。
イ 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工
具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
当該要件は、機械、設備、資材等の所有関係、購入経路等の如何を問うものではない
が、機械、資材等が相手方から借り入れ又は購入されたものについては、別個の双務契
約(契約当事者双方に相互に対価的関係をなす法的義務を課する契約)による正当なも
のであることが必要である。なお、機械、設備、器材等の提供の度合については、単に
名目的に軽微な部分のみを提供するにとどまるものでない限り、請負により行われる事
業における一般的な社会通念に照らし通常提供すべきものが業務処理の進捗状況に応じ
て随時提供使用されていればよいものである。
〔製造業務の場合〕
注文主からの原材料、部品等の受取りや受託者から注文主への製品の受渡しについて
伝票等による処理体制が確立されていること。また、注文主の所有する機械、設備等の
使用については、請負契約とは別個の双務契約を締結しており、保守及び修理を受託者
が行うか、ないしは保守及び修理に要する経費を受託者が負担していること。
〔車両運行管理業務の場合〕
運転者の提供のみならず、管理車両の整備(定期整備を含む。)及び修理全般、燃料
・油脂等の購入及び給油、備品及び消耗品の購入、車両管理のための事務手続、事故処
理全般等についても受託することで注文主の自動車の管理全体を行っているものであり
また、当該受託業務の範囲を契約書に明記していること。
ロ 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理する
こと。
当該要件は、事業主が企業体として有する技術、技能等に関するものであり、業務を
処理する個々の労働者が有する技術、技能等に関するものではない。
- 7 -
第1 労働者派遣事業の意義等
Ⅲ Ⅱの1及び2のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを免れ
るため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が法第2条第1号に規定する労働者
派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることが
できない。
- 8 -
第1 労働者派遣事業の意義等
ハ(イ)「他人のために労働に従事させる」とは、当該労働への従事に伴って生ずる利益が、当該指
揮命令を行う他人に直接に帰属するような形態で行われるものをいう。したがって、事業主が、
自己の雇用する労働者を指揮命令する方法の一つとして、当該事業主自身の事業所の作業の遂
行について専門的能力を有する「他人」に当該事業主自身のための指揮命令の実施を委任等の
形式により委託し、当該指揮命令の下に自己の雇用する労働者を労働に従事させるような場合
は、「他人のために労働に従事させる」とはいえず、労働者派遣には該当しない。
(ロ)「労働に従事させる」の前提として場所的な移動は前提ではなく、他人が派遣元の事業所に
出向いて指揮命令を実施する場合であっても、当該指揮命令に伴って生ずる利益が当該他人に
直接に帰属する限りは労働者派遣に該当する。
(ハ)なお、「労働に従事させる」とは、派遣元が雇用主としての資格に基づき、労働者について
自己の支配により、その規律の下に従属的地位において労働を提供させることをいうものであ
り、労働者に対する指揮命令に係る権限についても、派遣元から派遣先へ委託されてはいるが
本来的には、派遣元に留保され、労働についても観念的には派遣元に提供されているものであ
ることに留意する必要がある。
ニ ロに掲げる基準は労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準であるが、
労働者派遣契約に係る規制(第6参照)、派遣労働者に係る雇用制限の禁止に係る規定及び就
業条件の明示に係る規定の派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主についての準用(第12
の7(5)ホ(ロ)及び第12の7(5)へ(ニ)参照)、労働者派遣契約に関する措置に係る規定の派遣先
以外の労働者派遣の役務の提供を受ける者についての準用(第8の2の(4)参照)並びに労働基
準法(昭和22年法律第49号)等の適用に関する特例等の規定(第9参照)において必要とな
る「業として行わない労働者派遣」と請負の形態の区分においても、当該基準を準用するもの
とする。
(4)出向との関係
イ 労働者派遣には、「当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするもの
を含まない」が、これによりいわゆる在籍型出向が除外される(第1-2図参照)。
第1-2図 労働者派遣と在籍型出向との差異
○ 労働者派遣
労働者派遣契約
[垂∃→一一一一→
雇用
\
[車重]
[垂司
指揮命令関係
- 9 -
[亘∃
雇用
○ 在籍型出向
出向契約
→一一一一→[亘∃
\
[車重]
雇用関係
第1 労働者派遣事業の意義等
ロ いわゆる出向は、出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先事業主との間において新
たな雇用契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態であるが、出向元事業主との関係から、
次の二者に分類できる。
① 在籍型出向
出向元事業主及び出向先事業主双方との間に雇用契約関係がある(出向先事業主と労働者と
の間の雇用契約関係は通常の雇用契約関係とは異なる独特のものである)。
形態としては、出向中は休職となり、身分関係のみが出向元事業主との関係で残っていると
認められるもの、身分関係が残っているだけでなく、出向中も出向元事業主が賃金の一部につ
いて支払義務を負うもの等多様なものがある。
なお、労働者保護関係法規等における雇用主としての責任は、出向元事業主、出向先事業主
及び出向労働者三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元事業主又は
出向先事業主が負うこととなる。
② 移籍型出向
出向先事業主との間にのみ雇用契約関係がある。
なお、労働者保護関係法規等における雇用主としての責任は、出向先のみが負うこととなる。
ハ 移籍型出向については、出向元事業主との雇用契約関係は終了しており、労働者派遣には該当
しない。
ニ 在籍型出向については、出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけではなく、出向元事業
主と出向先事業主との間の出向契約により、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約し
て行われている(この判断は、出向、派遣という名称によることなく、出向先と労働者との間の
実態、具体的には、出向先における賃金支払、社会、労働保険への加入、懲戒権の保有、就業規
則の直接適用の有無、出向先が独自に労働条件を変更することの有無をみることにより行う。)
ことから、労働者派遣には該当しない。
ホ ニのとおり、在籍型出向は労働者派遣に該当するものではないが、その形態は、労働者供給
((5)参照)に該当するので、その在籍型出向が「業として行われる」(3の(2)参照)ことによ
り、職業安定法(昭和22年法律141号)第44条により禁止される労働者供給事業に該当するよ
うなケースが生ずることもあるので、注意が必要である。
ただし、在籍型出向と呼ばれているものは、通常、①労働者を離職させるのではなく、関係会
社において雇用機会を確保する、②経営指導、技術指導の実施、③職業能力開発の一環として行
う、④企業グループ内の人事交流の一環として行う等の目的を有しており、出向が行為として形
式的に繰り返し行われたとしても、社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ない
と考えられるので、その旨留意すること(3の(2)参照)。
へ 二重の雇用契約関係を生じさせるような形態のものであっても、それが短期間のものである場
合は、一般的には在籍型出向と呼ばれてはいないが、法律の適用関係は在籍型出向と異なるもの
-10 -
第1 労働者派遣事業の意義等
ではないこと(例えば、短期間の教育訓練の委託、販売の応援等においてこれに該当するものが
ある)。
ト なお、移籍型出向については、出向元事業主と労働者との間の雇用契約関係が終了しているた
め、出向元事業主と労働者との間の事実上の支配関係を認定し、労働者供給に該当すると判断し
得るケースは極めて少ないと考えられるので、その旨留意すること。
ただし、移籍型出向を「業として行う」(3の(2)参照)場合には、職業紹介事業に該当し、
職業安定法第30条、第33条等との関係で問題となる場合もあるので注意が必要である。
チ いわゆる出向は、法の規制対象外となるが、出向という名称が用いられたとしても、実質的に
労働者派遣とみられるケースがあるので注意が必要である。
(5)労働者供給との関係
イ 労働者供給とは「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること
をいい、労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないもの」をい
う(職業安定法第4条第6項)。
ロ 労働者供給を「業として行う」(3の(2)参照)ことは、職業安定法第44条による労働者供給
事業の禁止規定により禁止されることとなる。
ハ 労働者供給と労働者派遣の区分は次により行うこととする(第1-3図参照)。
(イ)供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させる場合のうち、供給元
と労働者との間に雇用契約関係がないものについては、全て労働者供給に該当する。当該判断
は、具体的には、労働保険・社会保険の適用、給与所得の確認等に基づき行う。
(ロ)(イ)の場合とは異なり、供給元と労働者との間に雇用契約関係がある場合であっても、供給
先に労働者を雇用させることを約して行われるものについては、労働者派遣には該当せず、労
働者供給となる(法第2条第1号)。
ただし、供給元と労働者との間に雇用契約関係があり、当該雇用関係の下に、他人の指揮命
令を受けて労働に従事させる場合において、労働者の自由な意思に基づいて結果として供給先
と直接雇用契約が締結されたとしても、これは前もって供給元が供給先に労働者を雇用させる
旨の契約があった訳ではないため、労働者派遣に該当することとなる。
○ 労働者派遣
第1-3図 労働者派遣と労働者供給との差異
○ 労働者供給
労働者派遣契約 供給契約 供給契約
=←lト= =←→ト= =←lト=
\/ \/・ \/
巨亘] く。)巨亘∃ 巨亘∃
-11-
第1 労働者派遣事業の意義等
(ハ)(ロ)における「派遣先に労働者を雇用させることを約して行われるもの」の判断については、
契約書等において派遣元、派遣先間で労働者を派遣先に雇用させる旨の意思の合致が客観的に
認められる場合はその旨判断するが、それ以外の場合は、次のような基準に従い判断するもの
とすること。
(力 労働者派遣が法の定める枠組に従って行われる場合は、原則として、派遣先に労働者を雇
用させることを約して行われるものとは判断しないこと。
② 派遣元が企業としての人的物的な実体(独立性)を有しない個人又はグループであり派遣
元自体も当該派遣元の労働者とともに派遣先の組織に組み込まれてその一部と化している場
合、派遣元は企業としての人的物的な実体を有するが当該労働者派遣の実態は派遣先の労働
者募集・賃金支払の代行となっている場合その他これに準ずるような場合については、例外
的に派遣先に労働者を雇用させることを約して行われるものと判断することがあること。
いわゆる「二重派遣」は、派遣先が派遣元事業主から労働者派遣を受けた労働者をさらに業と
して派遣することをいうが、この場合、当該派遣先は当該派遣労働者を雇用している訳ではない
ため、形態としては労働者供給を業として行うものに該当するものであり、職業安定法第44条
の規定により禁止される。
これについては、派遣労働者を雇用する者と、当該派遣労働者を直接指揮命令する者との間の
みにおいて労働者派遣契約(第6参照)が締結されている場合は、「二重派遣」に該当しない
ものである。したがって、労働者派遣契約を単に仲介する者が存する場合は、通常「二重派遣」
に該当するものとは判断できないものであること(詳しくは(6)のロ及びハ参照)。
(6)ジョイント・ベンチャー(J V)との関係
イ JVの請負契約の形式による業務の処理
(イ)JVは、数社が共同して業務を処理するために結成された民法上
の組合(民法第667条)の一種であり、JV自身がJV参加の各社
(以下「構成員」という。)の労働者を雇用するという評価はでき
ないが、JVが民法上の組合である以上、構成員が自己の雇用する
労働者をJV参加の他社の労働者等の指揮命令の下に従事させたと
しても、通常、それは自己のために行われるものとなり、当該法律
関係は、構成員の雇用する労働者を他人の指揮命令を受けて、「自
己のために」労働に従事させるものであり、法第2条第1号の「労
注文主
請負
J V
A B C
働者派遣」には該当しない。
しかしながら、このようなJVは構成員の労働者の就業が労働者派遣に該当することを免れ
るための偽装の手段に利用されるおそれがあり、その法的評価を厳格に行う必要がある。
(ロ)JVが民法上の組合に該当し、構成員が自己の雇用する労働者をJV参加の他社の労働者等
の指揮命令の下に労働に従事させることが労働者派遣に該当しないためには、次のいずれにも
-12 -
第1 労働者派遣事業の意義等
該当することが必要である。
a JVが注文主との間で締結した請負契約に基づく業務の処理について全ての構成員が連帯
して責任を負うこと。
b JVの業務処理に際し、不法行為により他人に損害を与えた場合の損害賠償義務について
全ての構成員が連帯して責任を負うこと。
C 全ての構成員が、JVの業務処理に関与する権利を有すること。
d 全ての構成員が、JVの業務処理につき利害関係を有し、利益分配を受けること。
e JVの結成は、全ての構成員の間において合同的に行わなければならず、その際、当該J
Vの目的及び全ての構成員による共同の業務処理の2点について合意が成立しなければなら
ないこと。
f 全ての構成員が、JVに対し出資義務を負うこと。
g 業務の遂行に当たり、各構成員の労働者間において行われる次に掲げる指示その他の管理
が常に特定の構成員の労働者等から特定の構成員の労働者に対し一方的に行われるものでは
なく、各構成員の労働者が、各構成員間において対等の資格に基づき共同で業務を遂行して
いる実態にあること。
(力 業務の遂行に関する指示その他の管理(業務の遂行方法に関する指示その他の管理、業
務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理)
② 労働時間等に関する指示その他の管理(出退勤、休憩時間、休日、休暇等に関する指示
その他の管理(これらの単なる把握を除く。)、時間外労働、休日労働における指示その
他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。))
③ 企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理(労働者の服務上の規律に
関する事項についての指示その他の管理、労働者の配置等の決定及び変更)
h 請負契約により請け負った業務を処理するJVに参加するものとして、a、b及びfに加
えて次のいずれにも該当する実態にあること。
(力 全ての構成員が、業務の処理に要する資金につき、調達、支弁すること。
② 全ての構成員が、業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主と
しての責任を負うこと。
③ 全ての構成員が次のいずれかに該当し、単に肉体的な労働力を提供するものではないこ
と。
i 業務の処理に要する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又
は材料若しくは資材を、自己の責任と負担で相互に準備し、調達すること。
辻 業務の処理に要する企画又は専門的な技術若しくは経験を、自ら相互に提供すること。
(ハ)JVが(ロ)のいずれの要件をも満たす場合については、JVと注文主との間で締結した請負
契約に基づき、構成員が業務を処理し、また、JVが代表者を決めて、当該代表者がJVを代
-13 -
第1 労働者派遣事業の意義等
表して、注文主に請負代金の請求、受領及び財産管理等を行っても、法において特段の問題は
生じないと考えられる。
ロ JVによる労働者派遣事業の実施
(イ)JVは、数社が共同して業務を処理するために結成された民法上の
組合(民法第667条)であるが、法人格を取得するものではなく、J
V自身が構成員の労働者を雇用するという評価はできないため(イの
(イ)参照)、JVの構成員の労働者を他人の指揮命令を受けて当該他
人のための労働に従事させ、これに伴い派遣労働者の就業条件の整備
等に関する措置を講ずるような労働者派遣事業を行う主体となること
派遣先
労働者派遣
/
A B C
は不可能である。
したがって、JVがイに述べた請負契約の当事者となることはあっても、法第26条に規定
する労働者派遣契約の当事者となることはない。
(ロ)このため、数社が共同で労働者派遣事業を行う場合にも、必ず個々の派遣元と派遣先との間
でそれぞれ別個の労働者派遣契約が締結される必要があるが、この場合であっても、派遣元が
その中から代表者を決めて、当該代表者が代表して派遣先に派遣料金の請求、受領及び財産管
理等を行うことは、法において特段の問題は生じないものと考えられる。
(ハ)この場合、派遣先において、派遣元の各社が自己の雇用する労働者を派遣元の他社の労働者
の指揮命令の下に労働に従事させる場合、例えば特定の派遣元(A)の労働者が特定の派遣元
(B、C)の労働者に対し一方的に指揮命令を行うものであっても、派遣元(A)の労働者は
派遣先のために派遣先の業務の遂行として派遣元(B、C)の労働者に対して指揮命令を行っ
ており、派遣元(B、C)の労働者は、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従
事するものとなるから、ともに法第2条第1号の「労働者派遣」に該当し、法において特段の
問題は生じない。
ハ その他
JVの行う労働者派遣事業に類するものとして、次の点に留意すること。
(イ)派遣元に対して派遣先を、派遣先に対して派遣元をそれぞれあっせんし、両者間での労働者
派遣契約の結成を促し、援助する行為は法上禁止されていないこと(5)のニ、第1-4図参
照)。
(ロ)また、派遣元のために、当該派遣元が締結した労働者派遣契約の履行について派遣先との間
で保証その他その履行を担保するための種々の契約の締結等を行うことも、同様に法上禁止さ
れていないこと(第1-4図参照)。
-14 -
第1 労働者派遣事業の意義等
第1-4図 労働者派遣に係るあっせんと保証
○ あっせん
労働者派遣
[車重∃→一一一一→[亘車∃
\ぁっせん/
[二重⊃
○ 保 証
労働者派遣
千一
[車重∃
(7)派遣店員との関係
イ デパートやスーパー・マーケットのケース貸し等に伴ってみられるいわゆる派遣店員は、派遣
元に雇用され、派遣元の業務命令により就業するが、就業の場所が派遣先事業所であるものであ
る。
ロ この場合において、就業に当たって、派遣元の指揮命令を受け、通常派遣先の指揮命令は受け
ないものは、請負等の事業と同様((3)参照)「他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働
に従事させる」ものではなく、労働者派遣には該当しないが、派遣先が当該派遣店員を自己の指
揮命令の下に労働に従事させる場合は労働者派遣に該当することとなる(第1-5図参照)。
第1-5図 労働者派遣と派遣店員との差異
○ 労働者派遣 ○ 派遣店員
労働者派遣契約 派遣店員に係る派遣契約
[垂∃→一一一一→[垂∃ [垂∃→一一一一→[垂∃
雇用関係\/指揮命令関係 雇用関係\ ∴業断の排
[亘亘] [亘亘]
ハ 現実にも、派遣店員に関する出退勤や休憩時間に係る時間の把握等については、派遣先の事業
主や従業者等に委任される場合があるが、このことを通じて、実質的に労働者派遣に該当するよ
うな行為(例えば、派遣先の事業主や従業者から派遣元の事業とは無関係の業務の応援を要請さ
れる等)が行われることのないよう、関係事業主に対し、派遣店員に係る法律関係についての周
知徹底等を行っていく必要がある。
(8)その他
老人、身体障害者等に対する家庭奉仕員派遣事業、母子家庭等介護人派遣事業、盲人ガイドヘル
パー派遣事業、手話奉仕員派遣事業、脳性マヒ者等ガイドヘルパー派遣事業その他これらに準ずる
社会福祉関係の個人を派遣先とする派遣事業については、法施行前は職業安定法第44条で禁止す
る労働者供給事業に該当しないものとして判断されてきたが、これらの事業が、今後従来と同様法
-15 -
第1 労働者派遣事業の意義等
第2条第1号の「労働者派遣」に該当しない態様により行われる限りにおいて、「派遣」という名
称とは関わりなく、(力派遣元が国、地方公共団体、民間のいずれであるかを問わず、また、②派遣
先が不特定多数の個人であるか、特定の会員等であるかを問わず、労働者派遣事業とはならないも
のであること。
2 派遣労働者
(1)「派遣労働者」の意義
派遣労働者とは、「事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるもの」をいう
(法第2条第2号)。
(2)「事業主が雇用する労働者」の意義
派遣労働者は、事業主が現に雇用している状態にある者である。したがって、いわゆる登録型の
労働者派遣事業(3の(4)参照)において登録されているだけで、当該事業主が雇用していない労
働者は派遣労働者に該当しない。
なお、当該登録中の労働者についても、法第30条、第30条の7、第31条の2及び第33条にお
いて「派遣労働者として雇用しようとする者」として派遣労働者とは異なる規制の対象となる(第
7の2の(1)、第7の8の(1)、第7の10の(1)及び第7の12の(1)参照)。
(3)「労働者派遣の対象」の意義
イ 派遣労働者は、事業主が雇用する労働者のうち、労働者派遣の対象となる者である。この労働
者派遣の対象とは、現に労働者派遣をされていると否とを問わず、労働者派遣をされる地位にあ
る者のことをいう。
ロ 労働者派遣の対象となるか否かの判断は、具体的には、労働協約、就業規則、労働契約等の定
めを確認することにより行う。
ハ なお、派遣労働者としての地位を取得させるためには、法第32条の定めに従った手続が必要
である(第7の11参照)。
(4)有期雇用派遣労働者と無期雇用派遣労働者
派遣労働者のうち、期間を定めて雇用される派遣労働者を有期雇用派遣労働者といい(法第30
条第1項)、期間を定めないで雇用される派遣労働者を無期雇用派遣労働者という(法第30条の
2第1項)。
3 労働者派遣事業
(1)「労働者派遣事業」の意義
労働者派遣事業とは、「労働者派遣を業として行うこと」をいう(法第2条第3号)。
(2)「業として行う」の意義
-16 -
第1 労働者派遣事業の意義等
イ 「業として行う」とは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、
1回限りの行為であったとしても反復継続の意思をもって行えば事業性があるが、形式的に繰り
返し行われていたとしても、全て受動的、偶発的行為が継続した結果であって反復継続の意思を
もって行われていなければ、事業性は認められない。
ロ 具体的には、一定の目的と計画に基づいて経営する経済的活動として行われるか否かによって
判断され、必ずしも営利を目的とする場合に限らず(例えば、社会事業団体や宗教団体が行う継
続的活動も「事業」に該当することがある。)、また、他の事業と兼業して行われるか否かを問
わない。
ハ しかしながら、この判断も一般的な社会通念に則して個別のケースごとに行われるものであり、
営利を目的とするか否か、事業としての独立性があるか否かが反復継続の意思の判定の上で重要
な要素となる。例えば、(力労働者の派遣を行う旨宣伝、広告をしている場合、②店を構え、労働
者派遣を行う旨看板を掲げている場合等については、原則として、事業性ありと判断されるもの
であること。
(3)適用除外業務との関係
労働者派遣事業は、労働者派遣を業として行うことをいうものであり、派遣労働者が従事する業
務に応じて労働者派遣に該当したり、該当しなかったりするものではなく、適用除外業務(第2の
1参照)について労働者派遣を業として行ったとしても労働者派遣事業に該当する。
(4)「登録型派遣」と「常用型派遣」
いわゆる「登録型派遣」とは、一般に、派遣労働を希望する者をあらかじめ登録しておき、労働
者派遣をするに際し、当該登録されている者と期間の定めのある労働契約を締結し、有期雇用派遣
労働者として労働者派遣を行うことを称される。
いわゆる「常用型派遣」とは、一般に、労働者派遣事業者が常時雇用している労働者の中から労
働者派遣を行うことを称される。なお、この「常時雇用される」労働者のみで労働者派遣事業を行
う特定労働者派遣事業は平成27年法改正により廃止された(第4参照)。
4 紹介予定派遣
(1)紹介予定派遣とは、法第5条第1項の許可を受けた派遣元事業主が、労働者派遣の役務の提供
の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先に対して、職業安定法その他
の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してす
るものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者
派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含む(法第2条
第4号)。
(2)紹介予定派遣については、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に係る
規定を適用しない(法第26条第6項)。
-17 -
第1 労働者派遣事業の意義等
(3)紹介予定派遣については、円滑かつ的確な労働力需給の結合を図るための手段として設けられ
たものであり、具体的には次の①から③までの措置を行うことができるものである。
(力 派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等
② 派遣就業開始前及び派遣就業期間中の求人条件の明示
③ 派遣就業期間中の求人・求職の意思等の確認及び採用内定
(4)紹介予定派遣を行う場合には、派遣元事業主及び派遣先は次の措置等を講じなければならない。
① 労働者派遣契約に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること(第6の2の(1)イ(ハ)の⑲
参照)
② 紹介予定派遣を受け入れる期間の遵守(第7の25の(1)及び第8の17の(1)参照)
③ 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示(第7の
25の(2)及び第8の17の(2)参照)
④ 派遣労働者の特定に当たっての年齢、性別等による差別防止に係る措置(第8の17の(3)参
照)
⑤ 派遣労働者であることの明示等(第7の11の参照)
⑥ 就業条件等の明示(第7の13の(3)のイの⑲参照)
⑦ 派遣元管理台帳に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること(第7の20の(1)のホの⑬
参照)
⑧ 派遣先管理台帳に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること(第8の12の(2)のハの⑬
参照)
5 法の適用範囲
(1)法の適用範囲の原則
法は、(3)によりその適用を除外される「船員」を除き、公務員も含めたあらゆる労働者、あら
ゆる事業に適用される。
(2)公務員等に対する法の適用
イ 国家公務員、地方公務員が派遣労働者となる場合にも、法の規制が適用される(国家公務員法
(昭和22年法律第120号)附則第16条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条)。
そのため、法第3章第4節の規定だけではなく、当該規定により適用される労働基準法等の規定
も適用されることとなる。特定独立行政法人及び国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務す
る職員や水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業、ガス事業等の地方公
営企業及び特定地方独立行政法人の職員についても同様である(特定独立行政法人等の労働関係
に関する法律(昭和23年法律第257号)第37条、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭
和27年法律第289号)第17条、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条、地方独立
行政法大法(平成15年法律第118号)第53条)。
-18 -
第1 労働者派遣事業の意義等
口 国、地方公共団体が派遣先である場合についても、法(第3章第4節の規定及び当該規定によ
り適用される労働基準法等の規定を含む。)は全面的に適用される。
(3)船員に対する法の適用除外
イ 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員については、法は適
用されない(法第3条)。
ロ 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員とは船員法による船員及び同法による船員でない
者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
(イ)船員法(昭和22年法律第100号)による船員とは「日本船舶又は日本船舶以外の国土交通
省令で定める船舶(船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第1条)に乗り組む船長及
び海員並びに予備船員」のことをいう(船員法第1条第1項)。
(ロ)「船舶」には、(力総トン数5トン未満の船舶、②湖、川又は港のみを航行する船舶、③政令
の定める総トン数30トン未満の漁船、④船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第
149号)第2条第4項に規定する小型船舶であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供
するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて、
船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令で定めるものは含まれない(船員法
第1条第2項)。
(ハ)「海員」とは、「船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対債として給料その他の報酬
を支払われる者」をいう(船員法第2条第1項)。したがって、船内における酒場、理髪店、
洗たく屋、売店、事務室内で働く労働者も、船舶内で使用される乗組員に該当する以上、直接
に運航業務に従事しなくても、この海員に含まれる。
(ニ)「予備船員」とは、「船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないもの」
をいう(船員法第2条第2項)。
ハ 船員について法が適用除外されるとは、船員である者を派遣労働者として船員の業務以外の業
務に就かせること及び船員以外の者を船員の業務に就かせることの双方について法の規定が適用
されないという意味である。例えば船員以外の者が派遣先であるロの(ロ)の「船舶」内で就業す
る限りにおいて(ロの(イ)に該当する必要がある。)、派遣労働者は船員に該当することとなり、
法の適用は受けない。
ニ なお、船員に係る労働者派遣事業に相当する事業については、船員職業安定法第55条第1項
により、国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができることとされている。
「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他
人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に
対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものをいう(船員職業安
定法第6条第1項)。その旨に留意するとともに、必要な場合には、地方運輸局等運輸関係行政
機関と相互に連携を保ちつつ、的確な行政運営を行うこと。
-19 -
第2 適用除外業務等
第2 適用除外業務等
1 適用除外業務に係る制限
何人も、次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない(法第4条第1
項)。
① 港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同
条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める
業務をいう。)
② 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又
はこれらの準備の作業に係る業務をいう。)
③ 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務
④ その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(第2から第5までにお
いて単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる
業務として2の(5)に掲げる業務
以上の業務(以下「適用除外業務」という。)については、労働者派遣事業を行ってはならない。
また、労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に
当該適用除外業務のいずれかに該当する業務に従事させてはならない(法第4条第3項)。
(参考)港湾運送事業を営んでいる事業主は、港湾労働法第12条により、厚生労働大臣の許可を受けた
場合は、港湾運送業務に労働者派遣を行うことができる。
2 適用除外業務の範囲
(1)港湾労働法第2条第1号に規定する港湾(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門)における同
条第2号に規定する港湾運送業務
イ 港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送業務の範囲
1の①に掲げる港湾運送業務のうち港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務とは、
次に掲げる行為であること。
(イ)港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第1項第2号から第5号までに規定する、船
内荷役、はしけ運送、沿岸荷役及びいかだ運送の各行為(港湾労働法第2条第2号イ)
(ロ)(イ)の行為と本質的機能を同じくするとともに、港湾運送の波動性の影響を受ける等労働の態
様が港湾運送と類似し、実際に港湾運送との間に労働者の相互の流動が見られる行為である次
に掲げる行為であって、他人の需要に応じて行うもの(港湾労働法第2条第2号ロ)
a 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若し
くは荷直し
b (イ)の行為に先行し、又は後続する船倉の清掃
- 20 -
第2 適用除外業務等
C 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の港湾の水域の沿岸か
らおおむね500メートル(東京及び大阪の港湾にあっては200メートル)の範囲内において厚
生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んです
る運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下「港湾倉庫」という。)
への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であって、港湾運送事業法第
2条第3項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第1号に掲げる行為に係るもの若しくは
同法第3条第1号から第4号までに掲げる事業又は倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条
第2項に規定する倉庫業のうち港湾倉庫に係るものを営む者(以下「港湾運送関係事業者」
という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組
んで運送されるべき貨物の港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物
の搬出であって、港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の港湾倉庫に
おける荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき
場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室にお
ける荷さばきを除く。
d 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両若しくは鉄
道(軌道を含む。)(以下「車両等」という。)により運送された貨物の港湾倉庫若しくは
上屋その他の荷さばき場への搬入(港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除
く。)又は車両等により運送されるべき貨物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場か
らの搬出(港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉
庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室
から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
ロ イの(ロ)のaの「船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画」とは、船舶に
積み込まれた貨物の移動又は荷くずれ等を防止するために行う支持または固縛の行為であって、
通常ラッシング又はショアリングと呼ばれているものをいい、「船積貨物の荷造り若しくは荷直
し」とは、船内、岸壁又は上屋等の荷さばき場において行われる船積貨物の梱包、袋詰め等の荷
造り若しくは荷の詰めかえ又は包装の修理等の荷直しの行為をいうものである。
ハ イの(ロ)のbの「(イ)の行為に先行し、又は後続する船倉の清掃」とは、船倉(タンクを含
む。)の清掃をいい、船員の居住区域、機関区域、燃料タンク、飲料水タンク等直接港湾運送事
業の業務と関連のない区域の清掃の行為は含まないものであること。
ニ イの(ロ)のC及びdにおける「港湾倉庫」については、昭和63年労働省告示第101号(港湾労働
法施行令第2条第3号の規定に基づいて厚生労働大臣が指定する区域)により厚生労働大臣が指
定する区域(具体的には別表1のとおり。)にある倉庫のうち、船舶若しくははしけにより又は
いかだに組んでする運送になる貨物以外の貨物のみを通常取り扱うもの以外のものであること。
ホ イの(ロ)のCのいわゆる海側倉庫荷役については、次のとおりとする。
(イ)「船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の港湾倉庫への搬入」
- 21-
第2 適用除外業務等
には、単に港湾倉庫に運び入れる作業だけでなく、港湾倉庫にはいっける作業まで含まれるも
のであること。
(ロ)「船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の港湾倉庫への搬出」
には、単に港湾倉庫から運び出す作業だけでなく、港湾倉庫にはいくずす作業まで含まれるも
のであること。
(ハ)「上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入」及び「上屋その他の荷さばき場へ搬
入すべき貨物の搬出」については、港湾運送関係事業者が行う場合に限り対象となるが、港湾
運送関係事業者であることの判断は、港湾労働法施行通達により判断された事業者をもって港
湾運送関係事業者とすること。
(ニ)「貨物の港湾倉庫における荷さばき」とは、はい替え、仕訳け、看貫及び庫移しの作業を指
すこと。
この場合において「貨物」とは、船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に
係る貨物だけではなく、当該倉庫にあるすべての貨物をいうものであること。
(ホ)冷蔵倉庫に係る海側倉庫荷役については、冷蔵倉庫に附属する荷さばき場(冷蔵倉庫にプラ
ットホーム等冷蔵室における作業に従事する労働者がその作業の一環として従事する場所をい
う。以下同じ。)と冷蔵室との間における荷役作業及び冷蔵室における荷さばきの作業に限
り、港湾運送の業務に入らないのであって、いわゆる水切りをした貨物をプラットホームに搬
入する作業、冷蔵室外における荷さばき等それ以外の作業については、港湾運送の業務となる
こと。
(へ)港湾倉庫以外の倉庫に係る寄託契約による貨物についてのはしけへの積込み又ははしけから
の取卸し(いわゆる水切り作業)については、当該倉庫に係る倉庫荷役として取り扱うもので
あること。
ヘ イの(ロ)のdのいわゆる山側倉庫荷役については、次のとおりとすること。
(イ)「貨物の港湾倉庫又は上屋その他の荷さばき場への搬入」には、単に港湾倉庫又は上屋その
他の荷さばき場に運び入れる作業だけでなく、はいっける作業まで含まれるものであること。
(ロ)「貨物の港湾倉庫又は上屋その他の荷さばき場への搬出」には、単に港湾倉庫又は上屋その
他の荷さばき場から運び出す作業だけでなく、はいくずす作業まで含まれるものであること。
(ハ)冷蔵倉庫に係る山側倉庫荷役については、ホの(ホ)と同様であること。
ト 港湾運送事業法第2条第1項に規定する港湾運送の中には、検数(第6号)、鑑定(第7号)
及び検量(第8号)の各行為が含まれているが、これらについては法第4条第1項に規定する港
湾運送の業務には含まれないので留意すること。また、元請(第1号)の行為のうち、港湾運送
事業法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為については、法第4条第1項に規定する
港湾運送業務に含まれるものであること。
(2)港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送業務
(1)以外の業務であって、港湾運送事業法施行令(昭和26年政令第215号)別表第1で指定する港
- 22 -
第2 適用除外業務等
湾(京浜港(東京港及び横浜港)、名古屋港、大阪港、神戸港及び関門港を除く。)において行わ
れる同様の業務を定めるものである。
イ 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送の業務に相当する業務の
範囲
1の①掲げる港湾運送業務のうち、港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾におけ
る港湾運送の業務とは、次に掲げる行為に係る業務とする。
(イ)港湾運送事業法第2条第1項第2号から第5号までに規定する、船内荷役、はしけ運送、沿
岸荷役及びいかだ運送の各行為
(ロ)(イ)の行為と本質的機能を同じくするとともに、港湾運送の波動性の影響を受ける等労働の態
様が港湾運送と類似し、実際に港湾運送との間に労働者の相互の流動が見られる行為である次
に掲げる行為であって、他人の需要に応じて行うもの
a 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若し
くは荷直し
b (イ)の行為に先行し、又は後続する船倉の清掃
C 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿
岸からおおむね500メートル(水島港にあっては1,000メートル、鹿児島港にあっては1,500メ
ートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域(別表2参照)内にある倉庫(船舶
若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱
うものを除く。以下「特定港湾倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬
出された貨物の搬入であって、港湾運送事業法第2条第3項に規定する港湾運送関連事業の
うち同項第1号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第3条第1号から第4号までに掲げる
事業又は倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者
(以下「特定港湾運送関係事業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しく
ははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出(上
屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であって、特定港湾運送関係事業者以外の者
が行うものを除く。)又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合
にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉
庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
d 道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以
下「車両等」という。)により運送された貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さば
き場への搬入(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両
等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出
(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の
場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から
当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
- 23 -
第2 適用除外業務等
口 各語の定義は(1)のロ以下と同様とすることとする。
(3)建設業務
イ1の②の建設業務は、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しく
は解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務」をいうが、この業務は建設工事の現場におい
て、直接にこれらの作業に従事するものに限られる。したがって、例えば、建設現場の事務職員
が行う業務は、これによって法律上当然に適用除外業務に該当するということにはならないので
留意すること。
ロ 土木建築等の工事についての施工計画を作成し、それに基づいて、工事の工程管理(スケジュ
ール、施工順序、施工手段等の管理)、品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっ
ているかの管理)、安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)等工事の施工の管理を行ういわ
ゆる施工管理業務は、建設業務に該当せず労働者派遣の対象となるものであるので留意するこ
と。
なお、工程管理、品質管理、安全管理等に遺漏が生ずることのないよう、請負業者が工事現場
ごとに設置しなければならない専任の主任技術者及び監理技術者については、建設業法(昭和24
年法律第100号)の趣旨に鑑み、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して専らその
職務に従事する者で、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置する
こととされていることから、労働者派遣の対象とはならないものとされていることに留意するこ
と。
ハ 林業の業務は、造林作業(①地ごしらえ、②植栽、③下刈り、④っる切り、⑤除伐、⑥枝打、
⑦間伐)及び素材(丸太)生産作業(①伐採(伐倒)、②枝払い、③集材、④玉切り(造材))
に分けることができるが、このうち造林作業の(力地ごしらえの業務については建設現場における
整地業務と作業内容が類似していること、②植栽の業務については土地の改変が行われることか
ら、いずれも労働者派遣法の解釈としては建設業務に該当するものである。一方、造林作業の③
下刈り、④っる切り、⑤除伐、⑥枝打及び⑦間伐の各業務及び素材(丸太)生産作業の各業務に
ついては、いずれも建設業務と類似する点は認められないため、建設業務に該当せず、労働者派
遣事業の対象となるものである。ただし、同一の派遣労働者が同時に、造林作業のうちの(力又は
②の業務と、造林作業のうちの③から⑦までの業務又は素材(丸太)生産作業の各業務のうちの
いずれかの業務を併せて行う場合のように、当該労働者派遣に適用除外業務が一部含まれている
ときは、全体として違法な労働者派遣となるものである。
また、造林作業のうちの③から⑦までの業務又は素材(丸太)生産作業の各業務を実施するに
当たっては、作業場・土場の整備、集材機の架設等建設業務に該当する業務を併せて行う場合が
あるが、同一の派遣労働者が同時に素材(丸太)生産作業の各業務のうちのいずれかの業務と作
業道・土場の整備、集材機の架設等建設業務に該当する業務を併せて行う場合のように、当該労
働者派遣に適用除外業務が一部含まれているときは、全体として違法な労働者派遣となるもので
ある。
- 24 -
第2 適用除外業務等
こ また、派遣労働者が従事する業務の一部に「建設業務」に該当する業務が含まれている場合も
違法な労働者派遣となるものである。
(4)警備業務
イ 1の③の警備業務に相当する業務は、次に掲げる業務をいう。
(イ)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における
盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等」とは、警備業務を行う対象となる施設を例
示的に列記しているものである。施設とは、建物その他の工作物等の物的設備のほか、事業
活動の全体を指す総合的な概念であるが、ある施設が警備業務対象施設に該当するかどうか
の判断は、その施設における事故の発生の警戒、防止の業務について、警備業法による規制
を行う社会的必要性が一般的に認められるかどうかという観点に基づいて行われるものであ
る。
「事故の発生を警戒し、防止する業務」とは、施設における異常の有無を確認し、不審者
を発見したときに警察へ通報したり、倒れている負傷者を救出するなどの活動を行う業務を
いう。「事故」とは、施設における事業活動の正常な運行を妨げ、又は施設の正常な状態を
損なうような出来事をいう。「警戒し、防止する」とは、事故の発生につながるあらゆる情
報を把握する目的を持って巡回、監視等の活動を行い、事故の発生につながる情報を把握し
た場合には、事故の発生を防止するために必要な措置を行い、又は事故が発生した場合には
被害の拡大を防止するために必要な措置を行う一連の活動を意味するが、この一部分を行う
業務であっても、「警戒し、防止する業務」に該当する。
(ロ)人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の
発生を警戒し、防止する業務
・ 祭礼、催し物等によって混雑する場所での雑踏整理、道路工事等現場周辺での人や車両の
誘導等を行う業務をいう。
(ハ)運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・ 現金、貴金属、美術品等の運搬に際し、その正常な運行を妨げるような事故の発生を警戒
し、防止する業務をいう。「現金、貴金属、美術品等」とは、運搬中の事故が及ぼす社会
的、経済的影響の大きい物品を例示的に列記しているものである。この業務としては、現金
等の運搬に際し警備員を運搬車両に添乗させる等して事故の発生を警戒し、防止する業務の
ほか、現金等を運搬すると同時に事故の発生を警戒、防止するという形態の業務が含まれ
る。
(ニ)人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
・ 人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒、防止するいわゆるボディーガード
等の業務をいう。
ロ また、派遣労働者が従事する業務の一部にイの(イ)から(ニ)までの業務のうちいずれかの業務が
- 25 -
第2 適用除外業務等
含まれているときは、全体として違法な労働者派遣となるものである。
ハ なお、警備業務に係る労働者派遣事業が行われることのないよう労働者派遣事業を行う事業主
に対する指導監督の強化を図るとともに、警備業務について労働者派遣事業を行っているおそれ
があることを認知した場合には、都道府県公安委員会に対し速やかに通報するなどの必要な措置
を講ずること。
(5)その他の業務
イ 1の④に該当する業務は、次に掲げる業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業
務が法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合(第8の5の(3)の⑤又は⑥参照。以下
同じ。)及び医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する医業(以下単に「医業」とい
う。)に係る派遣労働者の就業の場所がへき地(※1)にあり、又は地域における医療の確保のた
めには医業に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるもの
として厚生労働省令で定める場所(※2)(へき地にあるものを除く。)である場合を除く。)で
ある(令第2条)。
(イ)医業(病院等、助産所、介護老人保健施設、介護医療院又は医療を受ける者の居宅において行
われるものに限る。)
(ロ)歯科医師法(昭和23年法律202号)第17条に規定する歯科医業(病院等、介護老人保健施設、
介護医療院又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限る。)
(ハ)薬剤師法(昭和35年法律第146号)第19条に規定する調剤の業務(病院等又は介護医療院にお
いて行われるものに限る。)
(ニ)保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条、第3条、第5条、第6条及び第31条
第2項に規定する業務(※3)(他の法令の規定により、保健師助産師看護師法第31条第1項及
び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務(※
4)を含み、病院等、助産所、介護老人保健施設、介護医療院又は医療を受ける者の居宅におい
て行われるもの(訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)に限る。)
(ホ)栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する業務(傷病者に対する療養のため
必要な栄養の指導に係るものであって、病院等、介護老人保健施設、介護医療院又は医療を受け
る者の居宅において行われるものに限る。)
(へ)歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項に規定する業務(病院等、介護老人保健
施設、介護医療院又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限る。)
(ト)診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項に規定する業務(病院等、介護老人
保健施設、介護医療院又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限る。)
(チ)歯科技工士法(昭和30年法律168号)第2条第1項に規定する業務(病院等又は介護医療院に
おいて行われるものに限る。)
※1)へき地とは、以下の①から⑦の法律に規定された地域をその区域に含む市町村として、労働
者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第2条第2項の市
- 26 -
第2 適用除外業務等
町村を定める省令(平成18年厚生労働省令第70号)により指定された地域であること。
① 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として
指定された離島の区域
② 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域
③ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律
第88号)第2条第1項に規定する辺地
④ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域
⑤ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
の地域
⑥ 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
⑦ 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島の地域
※2)厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
① 都道府県が医療法(昭和23年法律第205号)第30条の23第1項の協議を経て同項の必要な施
策として地域における医療の確保のためには医業に業として行う労働者派遣により派遣労働者
を従事させる必要があると認めた病院又は診療所(以下「病院等」という。)であって、厚生
労働大臣が定めるもの
②(力の病院等に係る患者の居宅
※3)「保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条、第3条、第5条、第6条及び第
31条第2項に規定する業務」とは、具体的には、保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務
である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助をいう。
※4)「他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務とは、歯
科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学
技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士及び認定特定行為業務従事者の行う業務が含まれ
る。
ロ 労働者派遣事業(紹介予定派遣による場合、労働者派遣に係る業務が法第40条の2第1項第4号
又は第5号に該当する場合及び労働者派遣に係る業務が医業に該当する場合であって、当該業務に
係る派遣労働者の就業の場所がへき地にあり、又は地域における医療の確保のためには医業に業と
して行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働省
令で定める場所(※2)(へき地にあるものを除く。)である場合を除く。)を行うことができな
い医業等の医療関連業務は、イに掲げるとおり、(力病院、診療所(厚生労働省令で定めるものを除
く。※5)、助産所、②介護老人保健施設、③介護医療院又は④医療を受ける者の居宅において行
われるものに限られる。
このため、(力から④以外の施設等(社会福祉施設等)において行われる医業等の医療関連業務は
労働者派遣事業の対象となる。
- 27 -
第2 適用除外業務等
【労働者派遣事業の対象となる施設の例】
・ 養護老人ホーム
・ 特別養護老人ホーム
・ 軽費老人ホーム
・ 老人デイサービスセンター
・ 老人短期入所施設
・ 老人介護支援センター
障害者支援施設
・ 乳児院
・ 保育所
・ 福祉型障害児入所施設
・ 福祉型児童発達支援センター
等
注)これらの施設は例示であって、これらの施設以外の施設であっても、上記の(力~④以外の施設
等において行われる医業等の医療関連業務は、労働者派遣事業の対象となる。
※5)診療所において行われる医業等の医療関連業務については、原則として労働者派遣事業(紹介
予定派遣による場合、労働者派遣に係る業務が法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する
場合及び労働者派遣に係る業務が医業に該当する場合であって、当該業務に係る派遣労働者の就
業の場所がへき地にあり、又は地域における医療の確保のためには医業に業として行う労働者派
遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所
(※2)(へき地にあるものを除く。)である場合を除く。)の対象とならないが、以下の診療
所において行われる医業等の医療関連業務については、労働者派遣事業の対象となる。
(力 障害者支援施設の中に設けられた診療所
② 救護施設の中に設けられた診療所
③ 更生施設の中に設けられた診療所
④ 養護老人ホームの中に設けられた診療所
⑤ 特別養護老人ホームの中に設けられた診療所
⑥ 原子爆弾被爆者養護ホームの中に設けられた診療所
ハ なお、社会福祉施設であっても、以下の施設は医療法上の病院、診療所又は助産所である場合が
ほとんどであり、その場合は労働者派遣事業(紹介予定派遣による場合、労働者派遣に係る業務が
法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合及び労働者派遣に係る業務が医業に該当する
場合であって、当該業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にあり、又は地域における医療の
確保のためには医業に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めら
れるものとして厚生労働省令で定める場所(※2)(へき地にあるものを除く。)である場合を除
- 28 -
第2 適用除外業務等
く。)の対象とならないので留意すること。
(力 医療型障害児入所施設
② 医療型児童発達支援センター
③ 助産施設
④ 医療保護施設
ニ 「医療を受ける者の居宅」において行われる医療関連業務については、一般の住居において行わ
れるものに限らず、労働者派遣事業の対象となる社会福祉施設等において行われる往診・訪問看護
についても該当するので留意すること。
ホ 訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護において看護師又は准看護師が行うサービス利用者の
身体の状況の把握等の業務は、居宅において行われる療養上の世話及び診療の補助の業務に該当
するが、上記イのとおり労働者派遣事業の対象となる。
へ 病院等における看護補助の業務についてはイに掲げる業務には含まれず、労働者派遣を行うこ
とができるので留意すること。
ト また、ホームヘルパー等介護の業務についてはイに掲げる業務には含まれず、労働者派遣を行
うことができるので留意すること。
なお、介護業務の労働者派遣の形態としては個人家庭に対するもの、病院、福祉施設等に対す
るもの、介護業務の受託業者に対するものが想定される。
チ 医業に係る派遣労働者の就業場所がへき地にある場合(以下「へき地の場合」という。)又は地
域における医療の確保のためには医業に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必
要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所(※2)の場合(以下「地域医療の場
合」という。)に労働者派遣を行うにあたっては、派遣労働者である医師による適正な医療を確保
するため、派遣後に医業を円滑に行うために必要な研修(以下「事前研修」という。)をあらかじ
め受けた医師を派遣すべきであり、派遣先となる病院等が派遣労働者として医師を受け入れるに当
たっては、事前研修を受けた医師を受け入れるべきであること。(※6)
この点については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に
関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について」(平成18年3月31日医政発第0331022号
・職発第0331028号・老発第0331011号)及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について」(平成19年12月
14日医政発第1214004号・職発第1214001号)において、派遣先である病院等に対しても、派遣労働
者として医師を受け入れる場合には、事前研修を受けた医師であるか確認した上で受け入れるよう
求めていること。
なお、医師を派遣する派遣元事業主が、派遣労働者に事前研修を受けさせてから派遣しているか
否かの確認は、事前研修を修了した旨の証明書又はこれに準ずるものを確認することにより行うこ
ととし、事前研修を受けさせず医師の派遣を行っていることが判明した場合には、派遣元事業主及
び派遣先の双方に対し、事前研修を受けさせてから就業させるよう、指導及び助言を行うこと。
- 29 -
第2 適用除外業務等
※6)事前研修
事前研修の実施主体、内容等については、一般的には、以下のようなものが望ましいと考えられ
る。ただし、派遣先となる病院等の意向を十分に確認した上で、派遣される医師の個人的な属性
(専門分野、派遣勤務経験等)や労働者派遣契約の内容(勤務場所、派遣期間、業務内容の特約
等)等に応じた取扱いをしても差し支えないこと。
(力 事前研修の実施主体
へき地の場合は各都道府県のへき地医療支援機構が、地域医療の場合は各都道府県が設ける
医療対策協議会の協力の下で派遣元事業主が中心となって行うものであること。
② 事前研修の内容
・ 派遣先である病院等と医療機能の連携体制を図っている医療機関や消防・警察等の関係機
関との連携体制のあり方について
・ 派遣先である病院等に係る医療圏における医療提供体制や、救急医療・在宅医療等に関す
る知識及び手技等について
・ 派遣先である病院等の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、
ライフラインの整備状況等)について
③ 事前研修の期間について
最低6時間以上であることが望ましいこと。
④ 事前研修を修了した旨の証明について
当該医師が事前研修を修了したと認められる場合には、へき地の場合はへき地医療支援機
構、地域医療の場合は派遣元事業主において、その旨の証明書を発行又はこれに準ずる取扱い
をもって明らかにすること。
⑤ 事前研修を実施する必要のない者について
事前研修の実施については、上記のとおり、派遣先となる病院等の意向を十分に確認した上
で、一定の柔軟な取扱いをすることも可能であるが、へき地の場合又は地域医療の場合にそれ
ぞれ医師不足病院等へ派遣労働者として派遣され、1年以上勤務した経験を有する者又はそれ
と同等以上の経験を有すると認められる者に対しては、事前研修を実施する必要はないものと
して取り扱って差し支えないこと。
3 適用除外業務以外の業務に係る制限
以下の(力から⑧の業務については、次のような観点から労働者派遣事業を行ってはならず、また、
労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働
者派遣に係る派遣労働者をこれらの業務に従事させてはならないものであるので留意すること。
(重 大事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のため
の労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務(許可基準により、当該業務への労働者派
遣を行う場合は許可しないこととしており、また当該業務への労働者派遣を行わない旨を許可条件
- 30 -
第2 適用除外業務等
として付すこととしている)であること(第3の1の(12)参照)。
② 弁護士法(昭和24年法律第205号)、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61
年法律第66号)、司法書士法(昭和25年法律第197号)及び土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に
基づく弁護士、外国法事務弁護士、司法書士及び土地家屋調査士の業務については、資格者個人が
それぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う(当該業務については指揮命令を受けることがない)こ
ととされていることから、労働者派遣の対象とはならないものであること。
③ 公認会計士法(昭和23年法律第103号)に基づく公認会計士の業務については、資格者個人がそれ
ぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う(当該業務については指揮命令を受けることがない)こと
とされていることから、労働者派遣の対象とはならないものであること。ただし、派遣元が監査法
人(公認会計士を含む。)以外の者である場合であって、かつ、当該派遣の対象となる公認会計士
が公認会計士法第2条第1項に規定する業務を行わない場合には、労働者派遣は可能であること。
なお、公認会計士が、公認会計士法第2条第3項の規定により、監査証明に補助者として従事する
業務は、同条第1項に規定する業務に該当するものであること。
④ 税理士法(昭和26年法律第237号)に基づく税理士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務
の委託を受けて当該業務を行う(当該業務については指揮命令を受けることがない)こととされて
いることから、労働者派遣の対象とはならないものであること。ただし、派遣元が税理士及び税理
士法人以外の者である場合であって、かつ、当該派遣の対象となる税理士が派遣先の税理士又は税
理士法人の補助者(同法第2条第3項に規定する補助者をいう。)として同条第1項又は第2項に
規定する業務を行う場合には、税理士の労働者派遣は可能であること。なお、派遣される税理士
は、派遣先の補助税理士として登録しなければならないとされていること。
⑤ 弁理士法(平成12年法律第49号)に基づく弁理士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務の
委託を受けて当該業務を行う(当該業務については指揮命令を受けることがない)こととされてい
ることから、労働者派遣の対象とはならないものであること。ただし、弁理士法第4条第1項及び
第3項に規定する業務のうち同法第75条で規定する業務以外の業務となる、相談に応ずること(い
わゆるコンサルティング)に係るものに関し、特許業務法人以外を派遣元とする場合には、労働者
派遣は可能であること。
※ なお、当該弁理士の労働者派遣については、その業務が適正に実施されるよう、特許庁長官よ
り職業安定局長あてに参考のとおり留意事項が示されているので留意されたい。
⑥ 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく社会保険労務士の業務については、資格者個人
がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う(当該業務については指揮命令を受けることがない)
こととされていることから、労働者派遣の対象とはならないものであること。ただし、社会保険労務
士法第2条に規定する業務に関し、社会保険労務士法人が派遣元となり、社会保険労務士法人の使用
人である社会保険労務士を労働者派遣の対象とし、かつ、他の開業社会保険労務士又は社会保険労務
士法人(社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第17条の3第2号イ~ニの
いずれかに該当するものを除く。)を派遣先とする場合には、社会保険労務士の労働者派遣は可能で
- 31-
第2 適用除外業務等
あること。
⑦ 行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づく行政書士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務
の委託を受けて当該業務を行う(当該業務については指揮命令を受けることがない)こととされている
ことから、労働者派遣の対象とはならないものであること。ただし、行政書士法第1条の2及び第1
条の3に規定する業務に関し、行政書士又は行政書士法人が派遣元となり、他の行政書士又は行政書
士法人を派遣先とする場合には、行政書士の労働者派遣は可能であること。
⑧ 建築士法(昭和25年法律第202号)第24条第1項に規定する建築士事務所の管理建築士について
は、同法により「専任」でなければならないとされていることから、労働者派遣の対象とはならない
ものであること。
- 32 -
第2 適用除外業務等
(参考)
20060209特許002
平成18年2月20日
特許庁長官 中嶋 誠
厚生労働省職業安定局長 鈴木 直和 殿
弁理士が派遣労働者として業務に従事する場合に
留意すべき事項について
弁理士の業務については、その業務の特性からこれまで労働者派遣の対象とはなりえないと
してきたところである。しかし、平成17年10月21日付けで構造改革特別区域推進本部決
定において、弁理士法第4条第1項及び第3項に規定する業務のうち同法第75条で規定する
業務以外となる、相談に応ずること(いわゆるコンサルティング)に係るものに関し、特許業
務法人以外を派遣元とする場合には、労働者派遣の対象としても差し支えないこととしたとこ
ろである。
ついては、留意すべき事項を別添のとおり日本弁理士会会長に対し通知しましたので、貴局
におかれましては、弁理士の労働者派遣が適正に実施されるようご協力方お願いします。
(別添)
20060209特許002
平成18年2月20日
特許庁長官 中嶋 誠
日本弁理士会会長 佐藤 辰彦 殿
弁理士が派遣労働者として業務に従事する場合に
留意すべき事項について
弁理士法(平成12年法律第49号)に基づく弁理士の業務については、その業務の特性か
らこれまで労働者派遣の対象とはなりえないとしてきたところである。しかし、平成17年1
0月21日付けで構造改革特別区域推進本部決定(以下「本部決定」という。)において、弁
- 33 -
第2 適用除外業務等
理士法第4条第1項及び第3項に規定する業務のうち同法第75条で規定する業務以外となる
、相談に応ずること(いわゆるコンサルティング)に係るものに関し、特許業務法人以外を派
遣元とする場合には、労働者派遣の対象としても差し支えないこととしたところである。
ついては、弁理士の労働者派遣が適正に実施されるよう留意すべき事項を下記のとおり通知
しますので、御了知の上、貴会の会員である弁理士に対して、周知徹底を図られるようお願い
します。
記
1.業務範囲の明確化
弁理士が派遣労働者として行う業務は、コンサルティング業務の範囲内(個別事案に係る
ものを除く)とし、具体的かつ明確に業務内容を派遣契約(派遣元と派遣先の契約(以下同
じ。))、雇用契約(派遣元と派遣弁理士の契約(以下同じ。))に明記すること。
(理由)
弁理士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う(
当該業務については指揮命令を受けることがない)ことから、労働者派遣事業の対象とは
ならないとしてきたところである。しかし、上記の本部決定において、「弁理士法第4条
第1項及び第3項に規定する業務のうち同法第75条で規定する業務以外となる、相談に
応ずること(いわゆるコンサルティング)に係るものに関し、特許業務法人以外を派遣元
とする場合には、労働者派遣を認めること。」及び「当該弁理士の労働者派遣事業につい
ては適正に実施されるようコンサルティング業務の範囲の明確化(個別事案に係るものを
除外)、守秘及び利益相反行為防止の徹底の措置を講ずる。」として決定されたところで
ある。
コンサルティング業務のうち、個別事案に係るものを除外することとしたのは、弁理士
法第75条に規定する業務(以下「独占業務」という。)と密接な連続性を有することか
ら、これを派遣された弁理士が行えることとすると、実態上派遣先において独占業務が行
われるおそれが高くなるためである。
なお、派遣された弁理士が派遣先において独占業務を行った場合には、雇用主である派
遣元が実質的にその業務を行ったと判断されるおそれが高く、その場合には、派遣元に対
して弁理士法第79条(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の適用がありうる。
2.守秘及び利益相反行為防止
(1)雇用契約及び派遣契約に守秘義務規定を明記すること。
(2)雇用契約に、派遣労働者である弁理士が業務の委託を受けていた企業と競合関係にある
- 34 -
第2 適用除外業務等
企業及び派遣先企業と競合関係にある企業(以下単に「競合企業」という。)への派遣
を拒否できる規定を明記すること。
(理由)
派遣された弁理士は業務上派遣先の秘密を知得する機会があることから守秘を徹底する
とともに、競合企業への派遣がありうることから利益相反行為を防止する必要がある。守
秘及び利益相反行為防止については、上記の本部決定においても示されているところであ
る。
なお、派遣された弁理士に対しては、守秘義務違反につき弁理士法第80条(6月以下
の懲役又は50万円以下の罰金)の適用がありうる。さらに、派遣元及び派遣先に対して
は、秘密開示教唆につき刑法第61条(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)の適用
及び派遣された弁理士からの営業秘密取得につき不正競争防止法第21条(法人:1億5
千万円以下の罰金)の適用がありうる。
また、弁理士に対しては、利益相反行為(弁理士法第31条)につき弁理士法第32条
による懲戒処分(経済産業大臣による処分)がありうる。
- 35 -
第2 適用除外業務等
別表1
港湾労働法施行令第2条第3号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する区域
(昭和63年労働省告示第101号)
港湾労働法施行令(昭和63年政令第335号)第2条第3号の規定に基づき、厚生労働大臣が指
定する区域を次のように定める。
港湾労働法施行令(以下「令」という。)第2条第3号に規定する厚生労働大臣が指定する区域
は、次の表の上欄に掲げる令別表の上欄に掲げる港湾ごとに、それぞれ次の表の下欄に掲げる区域
とする。
令別表の上
欄に掲げる
港湾
区
域
東 京一 荒川口左岸突端から東日本旅客鉄道株式会社(以下「東日本旅客会社」という。)
総武本線荒川橋りように至る同川左岸の線、同橋りようから東日本旅客会社総武本線
に沿って同線都道上野月島線橋りように至る線、同橋りようから都道上野月島線、都
道本郷亀戸線、都道吾妻橋伊興町線、一般国道4号、都道言問橋南千住線、一般国道
6号、特別区道中日第3号路線、特別区道中日第6号路線、都道日本橋芝浦大森線、
一般国道15号、一般国道131号及び都道東京大師横浜線に沿って多摩川大師橋に至る
線、同橋から多摩川口左岸突端に至る同川左岸の線並びに陸岸により囲まれた区域
二 東京灯標(北緯35度33分58秒東経139度49分41秒)から25度30分9,280メートルの地
点から199度5,370メートルの地点まで引いた線、同地点から190度10,610メートルの地
点(以下「A地点」という。)まで引いた線、A地点から多摩川の河口における東京
都と神奈川県との境界に当たる地点(以下「B地点」という。)まで引いた線及び陸
岸により囲まれた区域内の埋立地
三 令別表の上欄に掲げる東京の港湾の水域のうち陸岸から200メートルの範囲内の海面
及び多摩川多摩川大橋下流の東京都の区域内の河川水面
横 浜一 多摩川口右岸突端から同川多摩川大橋に至る同川右岸の線、同橋から市道幸多摩線
及び県道川崎府中線に沿って東日本旅客会社東海道本線県道川崎府中線橋りように至
る線、同橋りようから東日本旅客会社東海道本線に沿って同線県道大師河原幸線橋り
ように至る線、同橋りようから県道大師河原幸線、県道東京大師横浜線、一般国道15
号及び一般国道1号に沿って派新田間川金港橋に至る線、同橋から新田間川新田間橋
に至る派新田間川及び新田間川左岸の線、同橋から県道横浜生田線及び一般国道16号
に沿って東日本旅客会社根岸線一般国道16号橋りように至る線、同橋りようから東日
本旅客会社根岸線に沿って同線中村川橋りように至る線、同橋りよう、同橋りようか
- 36 -
第2 適用除外業務等
ら堀川山下橋に至る中村川及び堀川右岸の線、同橋から市道山下本牧磯子線、一般国
道16号及び市道杉田方面389号線に沿って杉田川つくも橋に至る線、同橋、同橋から杉
田川神戸橋に至る同川右岸の線、同橋から一般国道357号に沿って横浜市金沢区福浦三
丁目の陸岸まで引いた線並びに陸岸により囲まれた区域
B地点からA地点まで引いた線、A地点から233度9,360メートルの地点まで引いた
線、同地点から219度6,000メートルの地点まで引いた線、同地点から204度7,230メー
トルの地点まで引いた線、同地点から226度30分1,450メートルの地点まで引いた線、
同地点から神奈川県横須賀市夏島町北端(北緯35度19分49秒東経139度38分27秒)まで
引いた線及び陸岸により囲まれた区域内の埋立地
令別表の上欄に掲げる横浜の港湾の水域のうち陸岸から500メートルの範囲内の海面
及び多摩川多摩川大橋下流の神奈川県の区域内の河川水面
名 古 屋一
矢田川口右岸突端から名古屋鉄道株式会社常滑線矢田川橋りように至る同川右岸の
線、同橋りようから名古屋鉄道株式会社常滑線に沿って同線東海旅客鉄道株式会社(
以下この号において「東海旅客会社」という。)東海道本線橋りように至る線、同橋
りようから東海旅客会社東海道本線に沿って同線一般国道19号橋りように至る線、同
橋りようから一般国道19号及び市道広小路線に沿って東海旅客会社関西本線市道広小
路線橋りように至る線、同橋りようから東海旅客会社関西本線に沿って市道名古屋環
状線東海旅客会社関西本線橋りように至る線、同橋りようから市道名古屋環状線及び
一般国道23号(名四道路)に沿って同国道が海部郡飛島村大字飛鳥新田字竹之郷ヨタ
レ南の割の位置に達する地点に至る線、同地点から村道新政成三福線及び県道104号に
沿って筏川樋門に至る線、同門、同門から名古屋港防潮堤及び名古屋港高潮防波堤に
沿って同防波堤屈曲部南西角(北緯35度1分6秒東経136度46分53秒。次号において「
C地点」という。)に至る線並びに陸岸により囲まれた区域(東海旅客会社東海道本
線市道江川線橋りようから東海旅客会社東海道本線及び日本貨物鉄道株式会社東臨港
貨物線に沿って同線市道東海橋線橋りように至る線並びに同橋りようから市道東海橋
線、一般国道154号、市道西町線及び市道江川線に沿って東海旅客会社東海道本線市道
江川線橋りように至る線により囲まれた区域を除く。)
大野港北防波堤灯台(北緯34度55分58秒東経136度49分19秒)から340度100メートル
の地点から伊勢湾灯標(北緯34度56分16秒東経136度47分33秒)まで引いた線、同灯標
から353度30分980メートルの地点まで引いた線、同地点から331度30分4,520メートル
の地点まで引いた線、同地点から38度2,420メートルの地点まで引いた線、同地点から
C地点まで引いた線、C地点から名古屋港高潮防波堤北西基点(北緯35度2分6秒東
経136度45分58秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内の埋立地
令別表の上欄に掲げる名古屋の港湾の水域のうち陸岸から500メートルの範囲内の海
面
- 37 -
第2 適用除外業務等
大 阪一 神崎川口右岸突端から左門殿川辰巳橋に至る神崎川及び左門殿川右岸の線、同橋か
ら一般国道43号、市道福町浜町線、一般国道2号、市道海老江九条線、市道安井町
線、市道川口西九条線、市道西野田線、市道曾根崎川北岸線、府道大阪伊丹線、市道
江戸堀線、府道大阪臨海線、市道玉造西九条線、市道南北線、市道難波境川線、府道
大阪臨海線、一般国道26号、府道堺狭山線及び府道堺阪南線に沿って大津川大津川橋
に至る線、同橋、同橋から大津川口左岸突端に至る同川左岸の線並びに陸岸により囲
まれた区域
二 大阪南港南防波堤灯台(北緯34度37分42秒東経135度23分22秒)から12度7,920メー
トルの地点から214度18,000メートルの地点まで引いた線、同地点から130度に引いた
線及び陸岸に囲まれた区域内の埋立地
三 令別表の上欄に掲げる大阪の港湾の水域のうち陸岸から200メートルの範囲内の海面
神 戸一 芦屋川口左岸突端から同川芦屋川橋に至る同川左岸の線、同橋から一般国道43号、
一般国道2号、市道中央幹線及び市道税関線に沿って西日本旅客鉄道株式会社(以下
この号において「西日本旅客会社」という。)東海道本線市道税関線橋りように至る
線、同橋りようから西日本旅客会社の東海道本線、山陽本線及び和田岬線に沿って一
般国道2号西日本旅客会社和田岬線橋りように至る線、同橋りようから一般国道2号
に沿って妙法寺川若宮橋に至る線、同橋、同橋から妙法寺川口右岸突端に至る同川右
岸の線並びに陸岸により囲まれた区域
二 神戸第七防波堤東灯台(北緯34度40分34秒東経135度17分45秒)から10度4,800メー
トルの地点から175度9,870メートルの地点まで引いた線、同地点から259度11,940メー
トルの地点まで引いた線、同地点から301度5,430メートルの地点まで引いた線、同地
点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた区域内の理立地
三 令別表上欄に掲げる神戸の港湾の水域のうち陸岸から500メートルの範囲内の海面
関 門 一 一般国道2号と市道長府才川19号線との交会点から同市道及び市道長府扇町1号線
に沿って陸岸に至る線、同交会点から一般国道2号、一般国道9号及び一般国道191号
に沿って同国道が下関市今浦町57番地の1の位置に達する地点に至る線、同地点から2
10度に引いた陸岸に至る線並びに陸岸により囲まれた区域
二 彦島関彦橋から県道南風泊港線、県道田の首下関線、県道福浦港金比羅線及び県道
南風泊港線に沿って竹ノ子島昭和橋に至る線並びに陸岸により囲まれた区域
三 響灘大橋から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた区域
四 令別表上欄に掲げる関門の港湾の、海上における南西側の境界線と交わる陸岸の地
点(北緯33度56分43秒東経130度45分09秒)から180度1,587メートルの地点まで引いた
線、同地点から202度38分に引いた響灘西1号道路に至る線、同道路、一般国道495
号、市道浜町19号線、市道本町20号線、市道本町33号線、一般国道199号、 県道本城
- 38 -
第2 適用除外業務等
熊手線、一般国道3号、県道八幡戸畑線及び一般国道199号に沿って一般国道199号
九州旅客鉄道株式会社鹿児島本線橋りように至る線、同橋りようから九州旅客鉄 道
株式会社鹿児島本線に沿って同線県道小倉港線橋りように至る線、同橋りようから
県道小倉港線、一般国道199号、一般国道3号、一般国道2号及び県道黒川白野江東本
町線に沿って同県道が北九州市門司区大字田野浦1,206番の1の位置に達する地点に至
る線、同地点から部埼灯台(北緯33度57分34秒東経131度1分23秒)まで引いた線、同
灯台から10度30分に引いた陸岸に至る線並びに陸岸により囲まれた区域
五 吉志橋から142度に引いた陸岸に至る線、同橋から県道門司苅田線に沿って北九州市
門司区大字畑847番の1の位置に達する地点に至る線、同地点から38度に引いた陸岸に
至る線及び陸岸により囲まれた区域
六 令別表の上欄に掲げる関門の港湾の水域のうち陸岸から500メートルの範囲内の海面
- 39 -
第2 適用除外業務等
別表2
令第1条第3号に規定する厚生労働大臣が指定する区域
[
平成11年11年17日
コ
労働省告示第139
令第1条第3号に規定する厚生労働大臣が指定する区域は、次の表の上欄に掲げる港湾ご
とに、それぞれ下欄に掲げる区域とする。
港 湾 区 域
牧
内萌樽館蘭小路森戸古石巻釜
稚留小函室苫釧青八宮釜 石塩
小名浜
秋田船川
酒田
新潟
直江津
日立
鹿島
木更津
千葉
田子の浦
清水
三河
衣浦
四日市
伏木富山
敦賀
舞鶴
和歌山下津
阪南
尼崎西宮芦屋
東播磨
姫路
稚内の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
留萌の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
小樽の港湾の水域の沿岸から200メートルの範囲内の区域
函館の港湾の水域の沿岸から200メートルの範囲内の区域
室蘭の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
苫小牧の港湾の水域の沿岸から300メートルの範囲内の区域
釧路の港湾の水域の沿岸から300メー
青森の港湾の水域の沿岸から200メー
八戸の港湾の水域の沿岸から500メー
宮古の港湾の水域の沿岸から200メー
釜石の港湾の水域の沿岸から100メー
石巻の港湾の水域の沿岸から200メー
塩釜の港湾の水域の沿岸から500メー
トルの範囲内の区域
トルの範囲内の区域
トルの範囲内の区域
トルの範囲内の区域
トルの範囲内の区域
トルの範囲内の区域
トルの範囲内の区域
小名浜の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
秋田船川の港湾の水域の沿岸から400メートルの範囲内の区域
酒田の港湾の水域の沿岸から500メートルの範囲内の区域
新潟の港湾の水域の沿岸から300メートルの範囲内の区域
直江津の港湾の水域の沿岸から500メートルの範囲内の区域
日立の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
鹿島の港湾の水域の沿岸から300メートルの範囲内の区域
木更津の港湾の水域の沿岸から500メートルの範囲内の区域
千葉の港湾の水域の沿岸から400メートルの範囲内の区域
田子の浦の港湾の水域の沿岸から200メートルの範囲内の区域
清水の港湾の水域の沿岸から300メートルの範囲内の区域
三河の港湾の水域の沿岸から300メートルの範囲内の区域
衣浦の港湾の水域の沿岸から200メートルの範囲内の区域
四日市の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
伏木富山の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
敦賀の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
舞鶴の港湾の水域の沿岸から200メートルの範囲内の区域
和歌山下津の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
阪南の港湾の水域の沿岸から500メートルの範囲内の区域
尼崎西宮芦屋の港湾の水域の沿岸から500メートルの範囲内の区域
東播磨の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
姫路の港湾の水域の沿岸から300メートルの範囲内の区域
- 40 -
第2 適用除外業務等
徳島小松島
高松
坂出
新居浜
今治
松山
高知
水島
笠岡
福山
尾道糸崎
呉
広島
境
岩国
徳山下松
三田尻中関
宇部
小野田
苅田
博多
三池
唐津
伊万里
三角
八代
水俣
大分
細島
油津
鹿児島
名瀬
那覇
石垣
徳島小松島の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
高松の港湾の水域の沿岸から300メートルの範囲内の区域
坂出の港湾の水域の沿岸から300メートルの範囲内の区域
新居浜の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
今治の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
松山の港湾の水域の沿岸から200メートルの範囲内の区域
高知の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
水島の港湾の水域の沿岸から1,000メートルの範囲内の区域
笠岡の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
福山の港湾の水域の沿岸から400メートルの範囲内の区域
尾道糸崎の港湾の水域の沿岸から500メートルの範囲内の区域
呉の港湾の水域の沿岸から200メートルの範囲内の区域
広島の港湾の水域の沿岸から500メートルの範囲内の区域
境の港湾の水域の沿岸から300メートルの範囲内の区域
岩国の港湾の水域の沿岸から300メートルの範囲内の区域
徳山下松の港湾の水域の沿岸から200メートルの範囲内の区域
三田尻中関の港湾の水域の沿岸から500メートルの範囲内の区域
宇部の港湾の水域の沿岸から300メートルの範囲内の区域
小野田の港湾の水域の沿岸から200メートルの範囲内の区域
苅田の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
博多の港湾の水域の沿岸から500メートルの範囲内の区域
三池の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
唐津の港湾の水域の沿岸から200メートルの範囲内の区域
伊万里の港湾の水域の沿岸から200メートルの範囲内の区域
三角の港湾の水域の沿岸から300メー
八代の港湾の水域の沿岸から200メー
水俣の港湾の水域の沿岸から100メー
大分の港湾の水域の沿岸から400メー
細島の港湾の水域の沿岸から200メー
油津の港湾の水域の沿岸から100メー
トルの範囲内の区域
トルの範囲内の区域
トルの範囲内の区域
トルの範囲内の区域
トルの範囲内の区域
トルの範囲内の区域
鹿児島の港湾の水域の沿岸から1,300メートルの範囲内の区域
名瀬の港湾の水域の沿岸から300メートルの範囲内の区域
那覇の港湾の水域の沿岸から400メートルの範囲内の区域
石垣の港湾の水域の沿岸から100メートルの範囲内の区域
- 41-
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
1事業主の行う許可手続について
(1)許可の概要
労働者派遣事業については、当該事業が法の趣旨に沿って適正に運営され、労働力需給の適正
な調整が図られるとともに、派遣労働者の保護及び雇用の安定が確保されることが必要である。
このような観点から、労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対して申請書を提
出し、その許可を受けなければならない(法第5条第1項)ところであり、厚生労働大臣が許可
を与えるにあたっての許可要件として、許可の欠格事由(法第6条(詳細は(7)参照))及び
許可基準(法第7条第1項(詳細は(8)参照))を定めているところである。したがって、許
可の申請に係る事業が、許可の欠格事由に該当せず、許可基準を全て満たすと認められる場合に
のみ許可されるものであり、労働者保護と雇用の安定のためのルールを遵守し、適正な事業運営
を行い得る資質を有する者に限り事業の実施を認めることとしているものである。
(2)許可の申請手続
イ 許可の申請書等の作成
事業主は、労働者派遣事業に係る許可にあたって、手数料(法第54条)(詳細は(3)参
照)及び登録免許税(登録免許税法(昭和42年法律第35号)第3条)(詳細は(4)参照)を
納付するとともに厚生労働大臣に提出する書類(申請書、事業計画書のほか、これらに添付すべ
きこととされている書類を含む。以下「許可申請関係書類」という。)を提出することにより申
請する(法第5条第2項から第4項まで)。また、上記の許可要件の審査の参考とするための
「自己チェックシート」等の資料(以下「参考資料」という。)も併せて提出することが求めら
れる(別表「労働者派遣事業関係手続提出書類一覧」参照)。
事業主は、労働者派遣事業を実施しようとする事業所についてそれぞれの許可を受けなければ
ならない。このため、主たる事務所の所在地以外の事業所でも労働者派遣事業を行おうとする場
合、その申請に際して労働者派遣事業を行おうとする全ての事業所の名称等を申請書の所定欄に
記載するとともに、各事業所の事業計画書等の書類について作成する必要がある。
なお、許可後に労働者派遣事業を実施する事業所を新設する場合については、3(1)を参照
のこと。
また、特定製造業務(物の製造の業務で、第8の5の(3)のイの⑤及び⑥以外のもの)を行
う事業主にあっては、その旨を申請書等の所定欄に記載しなければならない(法附則第4項)。
ロ 同一の事業主で行うことができる労働者派遣事業
事業主は、複数の事業所を有する場合において、労働者派遣事業を実施する事業所と(旧)特
定労働者派遣事業を実施する事業所(第4(旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置参照)の双
方の事業所を有することができる。ただし、同一の事業所において労働者派遣事業と(旧)特定
労働者派遣事業の双方を行うことはできない。また、(旧)特定労働者派遣事業は、経過措置期
- 42 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
間中のみ実施可能であることに併せて留意すること。
ハ 許可申請関係書類及び参考資料の提出等
許可申請関係書類及び参考資料(以下「許可申請関係書類等」という。)については、原則と
して事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「事業主管轄労働局」とい
う。)を経由して厚生労働大臣に提出するものとする(則第19条)。
事業主管轄労働局は、事業主から管轄以外の地域において派遣事業を実施する内容の許可申請
関係書類等の提出を受けた場合、労働者派遣事業を行おうとする各事業所の所在地を管轄する労
働局(以下「事業所管轄労働局」という。)に対して、申請書の複写及び各事業所に関する許可
申請関係書類等を送付しなければならない。
ただし、次に掲げる事項については、事業主は、事業所管轄労働局へ許可申請関係書類等を提
出することができる。
① 労働者派遣事業及び(旧)特定労働者派遣事業の変更の届出(3の(1)及び第4参照)
② 労働者派遣事業許可証(様式第4号)(以下「許可証」という。)再交付の申請(5の
(2)参照)
③ 許可証の返納(5の(3)参照)
また、当該許可申請関係書類等を受理した事業所管轄労働局は、内容を確認の上、その提出の
都度、当該許可申請関係書類等に連絡文を添えて速やかに事業主管轄労働局へ送付しなければな
らない。
許可及び許可の有効期間の更新等の権限は厚生労働大臣が有している。事業主管轄労働局及び
事業所管轄労働局は許可申請関係書類等の到達の確認を行い受理した後、到達した許可申請関係
書類等について、(力必要な書類が添付されていること、②書面に記載漏れがないこと及び記入事
項に誤りがないこと等を確認した上で、事業主管轄労働局を経由して本省に送付し、本省におい
て厚生労働大臣が「申請に対する処分(許可等)」を行うこととなる。
なお、許可申請関係書類等の提出期限が定められている場合は、期限内に、事業主管轄労働局
に提出されることが必要であること。
(3)手数料の納付
事業主は、(2)に掲げる労働者派遣事業に係る許可申請の手続を行うに際し、9の(1)表
に定める手数料に相当する額の収入印紙を申請書に貼って、手数料を納付しなければならない
(令第9条、則54条第1項)。
なお、手数料は、それぞれの申請書を受理(申請書に受理印を押印)し、当該収入印紙に消印
した後は返還しない(則第54条第2項)。
(4)登録免許税の納付等
イ 概要
許可については登録免許税を課せられる(登録免許税法第2条)ことから、(2)に掲げる労
働者派遣事業に係る許可申請を行おうとする者は登録免許税を納付しなければならない。ただ
- 43 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
し、国及び登録免許税法別表第2に掲げる者が自己のために受ける許可については、登録免許税
が課されない(登録免許税法第4条第1項)。
納税額として、許可一件当たり9万円が課される(登録免許税法別表第1第81号)。
ロ 登録免許税の納付方法
登録免許税については、登録免許税の納付に係る領収証書を申請書(様式第1号の第1面の裏
面)に貼って提出するものとすること(登録免許税法第21条)。納付方法は、現金納付が原則
であり、国税の収納機関である日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行等や郵便局)又は都道府県
労働局の所在地を管轄する税務署において、登録免許税の相当額を現金で納付するものであるこ
と(国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条)。
ハ 納期限について
登録免許税の納期限(許可日(登録免許税第27条))までに、領収証書の提出がなく、納付
の確認ができない場合には、許可を受けた者の当該登録免許税に係る同法第8条第2項の規定に
よる納税地の所轄税務署長に対し、その旨を9の(2)のイの様式例により通知すること。
ニ 還付について
登録免許税の納付をして許可の申請をした者につき当該申請が却下された場合及び当該申請の
取り下げがあった場合には、納付された登録免許税の額及び登録免許税法施行令第31条に規定
する事項を許可の申請をした者の当該登録免許税に係る同法第8条第2項の規定による納税地の
所轄税務署長に対し、その旨を9の(2)のロの様式例により通知すること。
(5)許可申請関係書類等の種類
イ 許可申請関係書類
許可申請関係書類は法人及び個人の区分に応じ次の(イ)及び(ロ)のとおりとする(法第5
条第2項から第4項まで、則第1条の2第1項から第3項まで)。
(イ)法人の場合
a 労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
b 労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書(様式第3号、様式第3号
-2及び様式第3号-3(ただし、様式第3号-3は、派遣労働者のうち、雇用保険又は健
康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合にのみ提出を要するものであること。))
C 定款又は寄附行為
d 登記事項証明書
e 役員の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第
2条の規定に基づく個人番号の記載のないものに限る。出入国管理及び難民認定法(昭和
26年政令第319号。以下「入管法」という。)第19条の3に規定する中長期在留者にあっ
ては、住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規
定する国籍等をいう。以下同じ。)及び在留資格(入管法第2条の2第1項に規定する在留
- 44 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
資格をいう。)を記載したもの並びに番号法第2条の規定に基づく個人番号の記載のないも
のに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に
関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者にあっては、住民票の写し(国
籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したもの及び番号法第2条の規定に基づく
個人番号の記載のないものに限る。)とし、入管法第19条の3第1号に掲げる者にあって
は、旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書(職歴、賞罰及
び役職員への就任解任状況等を明らかにしたものであることが必要。以下同じ。)
f 役員(以下このfにおいて「役員甲」とする。)が未成年者のため、労働者派遣事業に関
し法定代理人から営業の許可を受けていない場合は、(a)・(b)の区分に応じ、それぞ
れ(a)・(b)の書類(ただし、役員甲が法定代理人から営業の許可を受けている場合
は、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登記事項証明書))
(a)役員甲の法定代理人が個人である場合
役員甲の法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(b)役員甲の法定代理人が法人である場合
役員甲の法定代理人の定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及
び履歴書(ただし、役員甲の法定代理人の役員(以下このfにおいて「役員乙」とす
る。)が未成年者のため、労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていな
い場合は、(a)・(b)の区分に準じ、それぞれ(a)・(b)の書類(役員乙が法定
代理人から営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを証する
書面(未成年者に係る登記事項証明書))を含む。さらに、法定代理人の役員について、
同様の事例が続く限り、前記と同様に取り扱うこと。)
g 労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程(「派遣元事業主が講ずべき措
置に関する指針」第2の11の(2)のハの(イ)から(ニ)までの内容が含まれているこ
とが必要(第7の27参照)。)
h 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(持分会社に
あっては、社員資本等変動計算書。以下「株主資本等変動計算書等」という。)であって納
税地の所轄税務署長に提出したもの。
なお、損益計算書については、可能な限り事業区分(セグメント)単位で売上額が確認で
きるものであること。
(a)最近の事業年度における決算は終了しているものの株主総会の承認を得ていないため納
税地の所轄税務署長に提出していない場合は、当該決算に係る貸借対照表、損益計算書及
び株主資本等変動計算書等を確実に納税地の所轄税務署長に提出することが確認できる場
合に限り、当該貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等であれば差し支えな
い。なお、申請時においては、この場合iの(a)の(力及び②を提出させる必要はない。
(b)設立後最初の決算期を終了していない法人の申請に係る場合は、会社法(平成17年法
- 45 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
律第86号)第435条第1項に規定する会社成立時の貸借対照表、一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第123条第1項(同法第199条において
準用する場合を含む。)に規定する法人成立時の貸借対照表等のみでよい。
i 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
(a)納税関係書類
① 最近の事業年度における法人税の確定申告書の写し(納税地の所轄税務署の受付印の
あるもの(電子申請の場合にあっては、納税地の所轄税務署に受け付けられた旨が確認
できるもの。以下同じ。)に限る。法人税法施行規則別表1(1)及び4は、必ず提出
すること。)
なお、連結納税制度を採用している法人については次に掲げる書類
・ 最近の連結事業年度における連結法人税の確定申告書の写し(連結親法人の納税
地の所轄税務署の受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表1の2「各連結
事業年度分の連結所得に係る申告書」の写し及び同申告書添付書類「個別帰属額等
の一覧表」の写しのみでよい。ただし、別表7の2付表1「連結欠損金当期控除額
及び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書」が提出される場合には、その写
しを併せて提出すること。)
・ 最近の連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書(申請法人に係るものに
限る。)の写し(納税地の所轄税務署長に提出したもの。ただし当該届出書の別表
にあっては別表4の2付表「個別所得の金額の計算に関する明細書」の写しのみで
よい。))
② 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号
様式(その2)による法人の最近の事業年度における所得金額に関するもの)
(なお、連結納税制度を採用している法人については納税証明書(国税通則法施行令第
41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による最近の連結事
業年度における連結所得金額に関するもの))
(設立後最初の決算を終了していない法人の申請に係る場合は、①及び②は不要。)
(b)労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証
明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し(転貸借の場合にあっては、その所有者
の転貸借に係る同意書その他権利関係を証する書類を含む。以下同じ。))
j 労働者派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書(派
遣元責任者と役員が同一である場合においては、提出を要しない。)並びに厚生労働省告示
(平成27年厚生労働省告示第392号)に定められた講習機関が実施する派遣元責任者講習
(則第29条の2)を修了したことを証する「派遣元責任者講習受講証明書(許可の申請の
受理目前3年以内の受講日のものに限る)」(様式第21号)の写し
k 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程
- 46 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
(a)教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とするこ
とから、当該取扱いの記載された就業規則(労働基準法第89条第1項第2号。以下同
じ。)又は労働契約の該当箇所の写し等。
(b)派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル
等又はその概要の該当箇所の写し。
1 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書
類。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続してい
る派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する
書類。
・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について
規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。
m 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が
終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休
業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した就業規則又は
労働契約の該当箇所の写し等。
(ロ)個人の場合
a 労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
b 労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書(様式第3号、様式第3号
-2及び様式第3号-3(ただし、様式第3号-3は、派遣労働者のうち、雇用保険又は健
康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合にのみ提出を要するものであること。))
C 住民票の写し及び履歴書
d 申請者が未成年者のため、労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていな
い場合は、(a)・(b)の区分に応じ、それぞれ(a)・(b)の書類(ただし、申請者
が法定代理人から営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを証
する書面(未成年者に係る登記事項証明書))
(a)申請者の法定代理人が個人である場合
申請者の法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(b)申請者の法定代理人が法人である場合
申請者の法定代理人の定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及
び履歴書(ただし、申請者の法定代理人の役員(以下この(b)において「役員丙」とす
る。)が未成年者のため、労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていな
い場合は、(a)・(b)の区分に準じ、それぞれ(a)・(b)の書類(ただし、役員
丙が法定代理人から営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたこと
を証する書面(未成年者に係る登記事項証明書))を含む。さらに、法定代理人の役員に
ついて、同様の事例が続く限り、前記と同様に取り扱うこと。)
- 47 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
e 労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程(「派遣元事業主が講ずべき措
置に関する指針」第2の11の(2)のハの(イ)から(ニ)までの内容が含まれているこ
とが必要(第7の27参照)。)
f 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
(a)納税関係書類
① 最近の納税期における所得税の確定申告書の写し(納税地の所轄税務署の受付印のあ
るもの)
② 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号イに係る同施行規則別紙第8号
様式(その2)による最近の納税期における金額に関するもの)
③ 申告納税制度関係
・ 青色申告の場合(簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。)は、
最近の納税期における所得税法施行規則第65条第1項第1号の貸借対照表及び損
益計算書(所得税青色申告決算書(一般用)の写し(納税地の所轄税務署の受付印
のあるもの))
なお、損益計算書については、可能な限り事業区分(セグメント)単位で売上額
が確認できるものであること。
・ 白色申告又は青色申告で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合は、bの
労働者派遣事業計画書の「3 資産等の状況」欄に記載された土地・建物に係る不
動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書
④ 預金残高証明書(納税期末日のもの)
(事業開始後最初の納税を終了していない個人の申請に係る場合は、(力から④までの書
類に代えて、bの労働者派遣事業計画書の「3 資産等の状況」欄(近接する適当な日
の状況につき記載する。)に記載された土地・建物に係る不動産の登記事項証明書及び
固定資産税評価額証明書並びに現金・預金に係る預金残高証明書を提出する。)
(b)労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証
明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)
g 労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書(派遣元責任
者と申請者が同一である場合においては、提出を要しない。)並びに厚生労働省告示(平成
27年厚生労働省告示第392号)に定められた講習機関が実施する「派遣元責任者講習」を
修了したことを証する「派遣元責任者講習受講証明書(許可の申請の受理目前3年以内の受
講日のものに限る)」(様式第21号)の写し
h 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程
(a)教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とするこ
とから、当該取扱いの記載された就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。
(b)派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル
ー 48 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
等又はその概要の該当箇所の写し。
i 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書
類。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続してい
る派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する
書類。
・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について
規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。
j 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が
終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休
業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した就業規則又は
労働契約の該当箇所の写し等。
ロ 参考資料の作成と提出
許可要件の審査の参考とするため、法人及び個人の区分にかかわらず、事業主は以下の参考資
料を提出すること。
(イ)自己チェックシート
事業主は、許可申請にあたって「自己チェックシート」(様式第15号)を作成し、提出す
ること。
当該自己チェックシートは、事業主が許可申請に必要な要件等を理解、認識して提出するこ
とを目的とするものであって、これにより遵法意識の高まりとともに許可要件の審査も円滑に
進むことが期待されるものとして労働政策審議会の議論の中で導入が決められたものであるこ
とに留意すること。
なお、就業規則又は労働契約に、無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由と
して解雇できる規定がないか、また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時
に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解
雇できる規定がないかについては、申請事業主においても自己チェックシートによって申請内
容を確認するものである。
(ロ)企業パンフレット等事業内容が確認できるもの(設立直後等で作成していない場合を除
く。)
(ハ)労働者名簿(申請月の前月末現在(前月末で把握が困難な場合は前々月末現在)のもので、
派遣労働者を含む全労働者分)(ただし、(8)許可要件(許可の基準)のこの(イ)のbに
よる申請を行わない事業主は除く。)
(ニ)小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置により、許可基準のうち緩和された資産要件にて
申請する場合には別途定める次のa及びbを提出すること((8)のこの(イ)のb参照)
a 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第7条第1項第
4号の財産的基礎に関する要件についての誓約書(様式第16号)
- 49 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
b 労働者派遣事業許可申請の当分の間の措置に関する常時雇用する派遣労働者数の報告につ
いて又は労働者派遣事業許可申請の3年間の暫定措置に関する常時雇用する派遣労働者数の
報告について(様式第17号)
ハ イの(イ)及び(ロ)就業規則の該当箇所(写)を添付させる場合、事業主の主たる事務所の
所在地を管轄する労働基準監督署の受理印がある該当ページ(写)を併せて提出すること。
ニ 経過措置期間中の(旧)特定労働者派遣事業を行う事業主が、労働者派遣事業の許可を申請す
るに際しては、イの(イ)のCからeまでに掲げる書類及びイの(ロ)のCに掲げる書類を添付
することを要しない(改正規則附則第12条)。
(6)提出すべき書類の部数
イ 許可申請関係書類(許可証を除く。)の部数については、(5)のイの(イ)及び(ロ)の
a、bについては、正本1通及びその写し2通であり、原則として事業主管轄労働局に提出する
ものとする。
また、イの(イ)のCからm及び(ロ)のCからjまでの添付書類は、正本1通及びその写し
1通を同様に提出する(則第20条)。
ロ 参考資料の部数については、正本1通及びその写し1通を同様に提出するものとする。
ハ このうち、正本1通については本省に送付するとともに、写し1通は事業主管轄労働局が保管
するものとする。
(5)のイの(イ)及び(ロ)のa、bのうち残りの写し1通は、申請者に控えとして交付す
る。
(7)許可要件(許可の欠格事由)
労働者派遣事業の許可要件のうち、許可の欠格事由(法第6条)に該当する者は、労働者派遣
事業の許可を受けることができない。
労働者派遣事業の許可を受けた後、許可の欠格事由に該当するに至ったときは、許可が取り消
されることになる(法第14条第1項第1号。第13の2の(2)のイ(イ)①参照)。
申請者が法人か個人かの区分に応じて、次のイ及びロにより許可の欠格事由に該当するか否か
の判断を行う。
イ 法人の場合
次のいずれかに該当する法人は、労働者派遣事業の許可を受けることができない(法第6
条)。
(イ)当該法人が、次のaからCまで及びgから1までの規定に違反し又は、d、e及びfの罪を
犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
った日から起算して5年を経過していない場合(※1及び2)(法第6条第1号、第2号)
a 法の規定
b 労働に関する法律の規定であって政令で定める規定は、次のとおりとする(令第3条)。
(a)労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限
- 50 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分
に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る
部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が法第
44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
(b)職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこ
れらの規定に係る同法第67条の規定
(C)最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42
条の規定
(d)建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及
び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の
規定
(e)賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の
規定に係る同法第20条の規定
(り 港湾労働法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係
る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
(g)中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の
促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第3号を除
く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
(h)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法
律第76号)第62条から第65条までの規定
(i)林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び
第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
(j)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第
89号)第108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る。)、第
111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分
に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定
に係る同法第113条の規定
(k)法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条
の規定並びに法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第
57号)第119条及び第122条の規定
C 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(第50
条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)
d 刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条
又は第247条
e 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)
- 51-
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
f 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項
g 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2又は第214条第1項の規定
h 船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条の3又は第160条第1項の規定
i 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段又は第54条第1項(第51
条前段の規定に係る部分に限る。)
j 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2又は第104条第1項
(第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)
k 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段又は第48
条第1項(第46条前段の規定に係る部分に限る。)
1 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条又は第86条(第83条の規定に係る部分に
限る。)
※1 執行猶予等の取扱い
刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過し
た者は、刑の「執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過
していない場合」には該当せず、猶予期間を無事経過することによって直ちに欠格事由を離脱
する。大赦又は特赦により刑の言渡しの効力を失った者についても同様である。
なお、刑の時効の完成、仮出獄を許された者の刑の残余期間の満了その他の事由により、刑
の執行の免除を得たものは、「執行を受けることがなくなった」に該当し、当該欠格事由につ
き判断する必要がある。
※2 法人の両罰規定による処罰
法人が両罰規定により処罰された場合についても当該欠格事由についての判断を行う必要が
あるが、法人については、罰金刑しか存在しないので、処罰の根拠となる法規定は、上記a及
びb並びにfから1に掲げる規定のみである。
(ロ)当該法人が破産者で復権していない場合(法第6条第3号)
(ハ)当該法人が法第14条第1項(第1号を除く。)の規定により労働者派遣事業の許可を取り
消され、又は法附則第6条第4項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し
又は命令の日から起算して5年を経過しない場合(法第6条第4号)
(ニ)当該法人が、第14条第1項の規定による労働者派遣事業の許可の取消し又は法附則第6条
第4項の規定による労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法(平成5年法律第
88号)第15条の規定による通知(以下「聴聞の通知」という。))があった日から当該処分
をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第13条第1項の規定による労働者派
遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当
該届出の日から起算して5年を経過しない場合(図1参照)(法第6条第6号)
- 52 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
因
廃止の届出
囲
図1
この間に届出をした者が対象
[
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ト
廃止の届出をした者は、届出の目か
ら5年間、欠格事由に該当する。
(ホ)当該法人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力
団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)に
その事業活動を支配されている場合(法第6条第11号)
(へ)当該法人が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれ
のある場合(法第6条第12号)
(ト)当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談
役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、
取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含
む。以下このィ、ロ、第7の16の(2)のイ及び第13の2の(2)のイにおいて同じ。)の
うちに次のいずれかに該当する者がある場合(法第6条第10号)
(a)禁固以上の刑に処せられ、又は(イ)のaからCまで及びgから1までの規定に違反し
又はd、e及びfの罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者(法第6条第1
号、第2号)
(b)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権していない者(法第6条第3号)
(C)当該法人が法第14条第1項(第1号を除く。)の規定により個人事業主として行って
いた労働者派遣事業の許可を取り消され、又は法附則第6条第4項の規定により個人事業
主として行っていた労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算
して5年を経過しない場合(法第6条第4号)
(d)第14条第1項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合
(同項第1号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人がイの(イ)に
規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)又は法附則第6条第4項の
規定により労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人がイの
(イ)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取
消し又は命令の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員であっ
た者で、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しないもの(図2参照)(法第
6条第5号)
- 53 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
処分原因
の発生
派遣元
当時の役員
図2
取消し又は
廃止命令
処分の
決定
5年間
処分原因が発生した当時現に法人の
役員であった者は、処分の目から5
年間、欠格事由に該当する。
・ト
(e)当該法人が、第14条第1項の規定による個人事業主として行っていた労働者派遣事業
の許可の取消し又は法附則第6条第4項の規定による労働者派遣事業の廃止の命令の処分
に係る聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま
での間に法第13条第1項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業
の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過
しないもの(図1参照)(法第6条第6号)
(り (ニ)に規定する期間内に法第13条第1項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出
又は旧法第20条の規定による(旧)特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人で
ある場合において、(ニ)の聴聞の通知の目前60 日以内に当該法人(当該事業の廃止に
ついて相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して
5年を経過しないもの(図3参照)(法第6条第7号)
図3
60日
田
廃止の届出
因
この間に役員で
あった者が対象
派遣元
当時の役員
この間に届出をした
法人が対象
5年間
+
聴聞の通知の目前60日以内に法人の役
員であった者は、廃止の届出の目から
5年間、欠格事由に該当する。
(g)暴力団員等(法第6条第8号)
(h)労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、
その法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人の役員)が上記(a)から(g)
までのいずれかに該当する者又はその法定代理人(法人である場合に限る。)が上記
- 54 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する者(法第6条第9号)
※ 未成年者等についての取扱い
未成年者とは、満年齢が20歳に満たない者をいう(民法第4条)。なお、婚姻した未成年者
については、未成年者としては取り扱わない(同法第753条)。
未成年者の法定代理人は、通常その父母である(民法第818条)が、場合によっては、後見
人が選任されている場合がある(同法第838条)。
未成年者であっても、その法定代理人から労働者派遣事業につき民法第6条第1項の規定に
基づく営業の許可を受けている者については、この要件につき判断する必要がない。
ロ 個人の場合
次のいずれかに該当する者は、労働者派遣事業の許可を受けることができない(法第6条)。
(イ)禁固以上の刑に処せられ、又はイの(イ)のaからCまで及びgから1までの規定に違反し
又はd、e及びfの罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者(法第6条第1号、第2
号)
(ロ)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権していない者(法第6条第3号)
(ハ)法第14条第1項(第1号を除く。)の規定により、個人事業主として行っていた労働者派
遣事業の許可を取り消され、又は法附則第6条第4項の規定により個人事業主として行ってい
た労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しない
場合(法第6条第4号)
(ニ)法第14条第1項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合
(同項第1号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人がイの(イ)に規定
する者に該当することとなったことによる場合に限る。)又は法附則第6条第4項の規定によ
り労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人がイの(イ)に規定する
者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を
受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員であった者で、当該取消し又は命
令の日から起算して5年を経過しないもの(図2参照)(法第6条第5号)
(ホ)当該法人が、第14条第1項の規定による個人事業主として行っていた労働者派遣事業の許
可の取消し又は法附則第6条第4項の規定による個人事業主として行っていた労働者派遣事業
の廃止の命令の処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないこと
を決定する日までの間に法第13条第1項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者
(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年
を経過しないもの(図1参照)(法第6条第6号)
(へ)(ホ)に規定する期間内に法第13条第1項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出又は
- 55 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
法第20条の規定による(旧)特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合に
おいて、(ホ)の聴聞の通知の目前60 日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理
由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないも
の(図3参照)(法第6条第7号)
(ト)暴力団員等(法第6条第8号)
(チ)暴力団員等がその事業活動を支配する者(法第6条第11号)
(リ)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
(法第6条第12号)
(ヌ)労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その
法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人の役員)が上記(イ)から(ト)までのい
ずれかに該当する者又はその法定代理人(法人である場合に限る。)が上記イの(イ)から
(ニ)までのいずれかに該当する者(法第6条第9号)
欠格事由について(○は該当の可能性があるもの)
事業主
法人の場合
〇
〇
〇
〇
該当条文
第6条第1号
第6条第2号
第6条第3号
第6条第4号
第6条第5号
第6条第6号
第6条第7号
第6条第8号
合
場
の 〇 〇 〇 〇 〇
人
個
派遣元責任者
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇〇
〇
〇
第6条第9号(※) 〇
第6条第10号
○(第1号から第9号ま
でに該当する役員)
第6条第11号 ○ ○
第6条第12号 ○ ○
※ 未成年者の法定代理人が自然人の場合は第1号から第8号まで、未成年者の法定代理人が法人の
場合は第1号から第4号まで、第6号及び第9号のいずれかに該当している者が対象。
(8)許可要件(許可の基準)
労働者派遣事業の許可要件のうち、許可の基準に適合していると認めるときでなければ労働者
派遣事業の許可をしてはならない(法第7条第1項)。
許可の基準については、労働者派遣事業の健全化及び派遣労働者の実効性ある保護を図る観点
から、次に掲げるイから二までの全てに適合していると認められることとする。
イ 法第7条第1項第1号の要件(当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを
- 56 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
目的として行われるものでないこと。)
労働力需給の適正な調整を図るため、特定企業への労働者派遣に関して、次のとおり判断す
る。
(イ)当該要件を満たすためには、法第48条第2項の勧告の対象とならないものであること、す
なわち、当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるも
の(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要
であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)で
ないことが必要である(第13の4参照)。
(ロ)「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」とは、特定の者に対し
てのみ当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行っているものであって、それ以
外の者に対して労働者派遣を行うことを目的としていない場合である。
(ハ)「厚生労働省令で定める場合」とは、当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主が雇用する
派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の
定年により退職した後雇い入れられた者に限る。)である場合である。
(ニ)なお、「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこ
と」を、労働者派遣事業の許可条件として付することに留意すること。
ロ 法第7条第1項第2号の要件(申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに
足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。)
「厚生労働省令で定める基準に適合するもの」とは、
(力 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限
る。)を有すること(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
法律施行規則第1条の4第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」参照)
②(力のほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること
の2点である(則第1条の4)。
(イ)派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度の内容に関する判断
派遣元事業主は、派遣労働者のキャリア形成を行うために、次のa、b、C、d及びeを満
たすキャリア形成支援制度を有しなければならない。
a 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定め
ていること。当該訓練計画は、以下の要件を全て満たしていること。
(a)教育訓練計画の内容の判断
i 実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としたものであること。
ただし、実際の教育訓練の受講にあたり、以下の者については、当該教育訓練は受講
済みであるとして取り扱うことができる。
(i)過去に同内容の教育訓練を受けたことが確認できる者
(の 当該業務に関する資格を有している等、明らかに十分な能力を有している者
- 57 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
なお、受講済みとして取り扱うことができる派遣労働者であっても、当該派遣労働者
が当該教育訓練の受講を希望する場合は、受講させることが望ましい。
辻 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。
教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とす
る。ただし、派遣元事業主において時間を管理した訓練を実施することが困難であるこ
とに合理的な理由がある場合(例えば、派遣元事業所と派遣先の事業所との距離が非常
に遠く終業後に訓練を行うことが困難である場合であって、eラーニングの設備もない
場合)については、キャリアアップに係る自主教材を渡す等の措置を講ずることとして
も差し支えないが、その場合は、当該教材の学習に必要とされる時間数に見合った手当
を支払うものであること。
また、これらの取扱は就業規則又は労働契約等に規定することとする。
なお、派遣労働者が段階的かつ体系的な教育訓練を受講するためにかかる交通費につ
いては、派遣先との間の交通費より高くなる場合は派遣元事業主において負担すべきも
のであること。
嵐 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。
教育訓練の内容は、派遣元事業主が一義的に定めるものであるが、派遣労働者として
より高度な業務に従事すること、派遣としてのキャリアを通じて正社員として雇用され
ることを目的としている等、キャリアアップに資するものであること。具体的に資する
理由は、キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号-2)において記述するこ
と。
複数の訓練コースを設けることも可能であり、訓練内容によって対象者が異なっても
差し支えない。なお、ヨガ教室や趣味的な英会話教室、面接対策とは異なるメイクアッ
プ教室のような、派遣労働者の福利厚生を目的とした明らかにキャリア形成に無関係な
ものは含まれない。派遣元事業主は、当該教育訓練計画についてキャリアアップに資す
る内容であることを説明できなければならない。
k 派遣労働者として雇用するにあたり実施する教育訓練が含まれたものであること。
訓練内容に、入職時に行う訓練が含まれていること。短期雇用の者であっても当該訓
練を受講させることができるよう、派遣元事業主と派遣先とが互いに協力することが望
ましいこと。
Ⅴ 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置
いた内容のものであること。
派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者に対する教育訓練計画が長期的なキャリア形成
を念頭とする内容であることを説明できなければならない。
(b)教育訓練の実施形態に関する判断
教育訓練の実施形態は、通常の業務を一時的に離れて行う教育訓練(OFFJT:Off The
- 58 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
Job Training)のみならず、日常の業務につきながら行う教育訓練(OJT:On TheJob
Training)のうち計画的に行うものを含めていても差し支えない。
b キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること。
(a)相談窓口には、担当者が配置されていること。
担当者については、キャリアコンサルタント(有資格者)、キャリアコンサルティング
の知見を有する者(職業能力開発推進者、3年以上の人事担当の職務経験がある者等)、
又は派遣先との連絡調整を行う営業担当者を配置する必要がある。
(b)相談窓口は、雇用する全ての派遣労働者が利用できること。
相談窓口については、事務所内に定められた相談ブースを設置することのみならず、電
話による相談窓口の設置、e-mailでの相談の受付、専用WEBサイトの相談窓口の設置等
により雇用する派遣労働者がキャリアコンサルティングを申し込めるよう、その雇用する
派遣労働者に対して周知するとともに、適切な窓口を提供しなければならないこと。
(C)希望する全ての派遣労働者がキャリアコンサルティングを受けられること。
(d)キャリアコンサルティングは、実施にあたっての規程(事務手引、マニュアル等)に基
づいて実施されることが望ましいこと。
なお、キャリアコンサルティングは、必ずしも常時行わなければならないわけではな
く、例えば毎週2回定期的に実施することや派遣労働者の希望に応じ随時実施すること等
も可能である。また、キャリアコンサルティングを行う場所についても事務所の内外を画
一的に指定するものではない。
C キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規定されていること。
(a)派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル
等が整備されていること。
(b)派遣労働者への派遣先の提供は(a)に基づいて行われるものであること。
d 教育訓練の時期・頻度・時間数等
(a)派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であること。また、教育訓練は、少な
くとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要であり、その後も、キャリアの節
目などの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されていること。
(b)実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、
少なくとも最初の3年間は、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要であるこ
と。
(C)派遣元事業主は上記の教育訓練計画の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるよ
うに就業時間等に配慮しなければならない。
なお、派遣元事業主は、派遣先に対して、派遣労働者が教育訓練を受けられるように協
力を求めることが望ましいこと。
e 教育訓練計画の周知等
- 59 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
(a)教育訓練計画の策定に当たっては、派遣労働者との相談や派遣実績等に基づいて策定
し、可能な限り派遣労働者の意向に沿ったものとなることが望ましいこと。
(b)派遣元事業主は教育訓練計画について、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対
し、労働契約を締結する時までに周知するよう努めること。
(C)教育訓練計画は事業所に備え付ける等の方法により派遣労働者に周知するとともに、計
画に変更があった際にも派遣労働者に周知するよう努めること。
(d)派遣元事業主は、派遣労働者が良質な派遣元事業主を選択できるように、教育訓練に関
する事項等に関する情報として、段階的かつ体系的な教育訓練計画の内容についての情報
をインターネットの利用その他適切な方法により提供することが望ましいこと。
(e)派遣元事業主は、派遣労働者のキャリアアップ措置に関する実施状況等、教育訓練等の
情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること。労働契約が更新された
場合は、更新された労働契約終了後3年間は保存していること。
(り キャリア形成支援制度を適正に実施しようとしない者又は経過措置期間中の(旧)特定
労働者派遣事業を実施していた者であって、キャリア形成支援制度を有する義務を免れる
ことを目的とした行為を行っており、労働局から指導され、それを是正していない者では
ないこと。
(ロ)派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制整備に関する判断
派遣労働者を雇用する者と指揮命令する者が分離するという特性に鑑み、派遣労働者に対す
る適切な雇用管理能力を要求することにより、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るため、
次のような事項につき判断する。
a 派遣元責任者に関する判断
(a)派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って適切に
選任、配置されていること。
・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
① 法第36条の規定により、未成年者でなく、法第6条第1号から第8号までに掲げ
る欠格事由のいずれにも該当しないこと。
② 則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること
(第7の19の(2)参照)。
③ 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
④ 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
⑤ 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
⑥ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であるこ
と。
⑦ 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこ
と。
- 60 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
⑧ 次のいずれかに該当する者であること。
(i)成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主
(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41
条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できる
こと、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者で
あったことをいう。
(の 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
(の 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
(k)成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
⑨ 厚生労働省告示(平成27年厚生労働省告示第392号)に定められた講習機関が実
施する則第29条の2で規定する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の
目前3年以内の受講に限る。)した者であること。
⑲ 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の一及び二の表並びに別表第二の
表のいずれかの在留資格を有する者であること。
⑪ 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行う
ものであること。
(b)派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること。
b 派遣元事業主に関する判断
派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが
見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。
・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
(重 労働保険、社会保険の適用基準を満たす派遣労働者の適正な加入を行うものであるこ
と。
② 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
③ 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
④ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であるこ
と。
⑤ 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
⑥ 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「高度専門職第一号
ハ」、「高度専門職第二号ハ」及び「経営・管理」若しくは別表第二の表のいずれかの
在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う
者であること。
なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。
⑦ 派遣労働者に関する就業規則又は労働契約等の記載事項について
- 61-
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
・ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定
がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契
約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解
雇できる旨の規定がないこと。
・ 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣
契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に
帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う
旨の規定があること。
⑧ 既に事業を行っている者であって、雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行
為を行っており、労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと。
C 教育訓練(キャリア形成支援制度に関するものを除く。)に関する判断
(a)派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全
衛生教育の実施体制を整備していること。
(b)派遣労働者に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設、設備
等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)を整備していること。
・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
(力 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
② 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者
が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。
(C)法第30条の2に定める教育訓練以外に自主的に実施する教育訓練については、派遣労
働者が受講しやすいよう、当該教育訓練に係る派遣労働者の費用負担を実費程度とするこ
と。
ハ 法第7条第1項第3号の要件(個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必
要な措置が講じられていること。)
業務の過程で得た派遣労働者等の個人情報を管理する能力を要求することにより、派遣労働者
等の個人情報を適正に管理し、秘密を守るため、次のような事項につき判断する。
a 個人情報管理の事業運営に関する判断
(力 派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者(ハにおいて「派遣労働者等」という。)
の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。
(a)当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当し、これを内容に含む個人情報適正
管理規程を定めていることが必要である。
i 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされているこ
と。
辻 業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他
に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
- 62 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
嵐 派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同
じ。)の取扱いに関する事項についての規程があり、かつ当該規程について派遣労働
者等への周知がなされていること。なお、開示しないこととする個人情報としては、
当該個人に対する評価に関する情報が考えられる。
k 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関して、派遣元責任者等を苦情処理の担当
者等取扱責任者を定める等、事業所内の体制が明確にし、苦情を迅速かつ適切に処理
することとされていること。
(b)個人情報適正管理規程については、以下の点に留意するものとする。
i 派遣元事業主は、(a)のiからkまでに掲げる規定を含む個人情報適正管理規程
を作成するとともに、自らこれを遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなけれ
ばならないものとする。
辻 派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、
当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないものとする。ここでいう、「不利
益な取扱い」の例示としては本人が個人情報の開示又は訂正の求めをした以後、派遣
就業の機会を与えないこと等をいう。
(C)「個人情報の収集、保管及び使用」については、以下の点に留意するものとする。
i 派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者の登録をする際には当該労働者の希
望及び能力に応じた就業の機会の確保を図る範囲内で、派遣労働者として雇用し労働
者派遣を行う際には当該派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、派遣労
働者等の個人情報(以下ハにおいて単に「個人情幸勘 という。)を収集することと
し、次に掲げる個人情報を収集してはならないものとする。ただし、特別な業務上の
必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示
して本人から収集する場合はこの限りではない。
(i)人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるお
それのある事項
(の 思想及び信条
(の 労働組合への加入状況
(i)から(弟 については、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当す
る。
(i)関係
① 家族の職業、収入、本人の資産等の情報(税金、社会保険の取扱い等労務
管理を適切に実施するために必要なもの及び日雇派遣の禁止の例外として認
められる場合の収入要件を確認するために必要なものを除く。)
② 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報
(の 関係 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
- 63 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
(の 関係 労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
「業務の目的の達成に必要な範囲」については、雇用することを予定する者
を登録する段階と、現に雇用する段階では、異なることに留意する必要があ
る。前者においては、例えば労働者の希望職種、希望勤務地、希望賃金、有す
る能力・資格など適切な派遣先を選定する上で必要な情報がこれに当たり、後
者においては、給与事務や労働・社会保険の手続上必要な情報がこれに当たる
ものである。
・ なお、一部に労働者の銀行口座の暗証番号を派遣元事業主が確認する事例が
みられるが、これは通常、「業務の目的の達成に必要な範囲」に含まれるとは
解されない。
② 派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の
下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないものとす
る。
「等」には本人が不特定多数に公表している情報から収集する場合が含まれる。
③ 派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新
規卒業予定者である派遣労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職
業安定局長の定める書類(全国高等学校統一応募用紙又は職業相談票(乙))により提出
を求めるものとする。
・ 当該応募書類は、新規卒業予定者だけでなく、卒業後1年以内の者についてもこれを
利用することが望ましいこと。
④ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。なお、派遣労働者として雇用
し労働者派遣を行う際には、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣先に提供
することができる派遣労働者の個人情幸酎ま、法第35条第1項の規定により派遣先に通知
すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情幸酎こ限られるものであるも
のとする。ただし、他の保管又は使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律
に定めのある場合は、この限りではない。
b 個人情報管理の措置に関する判断
派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
(a)当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
1 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講
じられていること。
辻 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
嵐 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個
人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
k 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための括
- 64 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
置が講じられていること。なお、当該措置の対象としては、本人からの破棄や削除の要
望があった場合も含むものである。
(b)「適正管理」については以下の点に留意するものとする。
i 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情幸酎こ関し適切な措置((a)のiか
らkまで)を講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明
しなければならないものとする。
辻 派遣元事業主等が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当
該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなけれ
ばならないものとする。
「個人情幸田 とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」と
は、一般に知られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことにつき
本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実(要保護性)をいうものであ
る。具体的には、本籍地、出身地、支持・加入政党、政治運動歴、借入金額、保証人
となっている事実等が秘密に当たりうる。
法第7条第1項第4号の要件(ロ及びハの他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能
力を有するものであること。)
労働者派遣事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎、組織的基礎や当該事業に適し
た事業所の確保等一定以上の事業遂行能力を要求することにより、労働者派遣事業を労働力需給
調整システムの一つとして適正かつ有効に機能させ、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るた
め、次のような事項につき判断する。
(イ)財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)
a 許可申請事業主に関する財産的基礎
許可申請事業主についての財産的基礎の要件については以下のとおりとする。
(a)資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準
資産額」という。)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定す
る)事業所の数を乗じた額以上であること。
厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書(様
式第3号)の「3 資産等の状況」欄により確認する。
「繰延資産」とは、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第74条第3項第5
号に規定する繰延資産をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計算規
則第2編第2章第2節の「のれん」をいう。
(b)(a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
(C)事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業
を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
・厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書(様式
- 65 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
第3号)の「3 資産等の状況」欄により確認する。
(d)基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあったときは、公
認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算による場合に限り、
基準資産額、負債の総額及び自己名義の現金・預金の額のいずれについても当該中間決算
又は月次決算により確認するものとする。
ただし、個人の場合に限り、基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨の
申し立てがあったときは、(力市場性のある資産の再販売価格の評価額が、基礎価額を上回
る旨の証明があった場合(例えば、固定資産税の評価額証明書等による。)、②提出され
た預金残高証明書により普通預金、定期預金等の残高を確認できた場合(複数の預金残高
証明書を用いる場合は、同一日付のものに限る。)に限り、当該増加後の額を基準資産額
又は自己名義の現金・預金の額とする。
(e)職業安定法第45条に規定する厚生労働大臣の許可を受け、労働者供給事業を行う労働
組合等から供給される労働者を対象として、労働者派遣事業を行うことを予定する場合に
ついては、(a)において「2,000万円」を「1,000万円」と、(C)において「1,500
万円」を「750万円」と読み替えて適用する。
(り 地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派遣労働者
に対する賃金支払いが担保されている場合は、(a)、(b)及び(C)の要件を満たし
ていなくても差し支えないこととする。
b 小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置
小規模派遣元事業主であってaの(a)、(b)又は(C)の要件を満たさない者に係る
財産的基礎に関する判断については以下のとおりとする。
ただし、平成28年9月30日以降は、改正法附則第6条第1項の規定により引き続き行う
ことができることとされた労働者派遣事業を行っている者からの申請に限るものとする(当
該申請について、平成30年9月29日までに事業主管轄労働局に対して新規許可の申請を行
い、当該申請が受理されている者も含む。)。
(a)常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主の財産的基礎(当分の
間の措置)
平成27年9月30日から当分の間の措置として、1つの事業所(労働者派遣事業を実施
する事業所のみではなく、当該事業主の労働者の勤務する場所又は施設を含む。)のみを
有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主に対しては、財産
的基礎に関する判断基準について以下のとおりとする。
i 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基
準資産額」という。)について1,000万円以上であることとする。
・厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書(様
式第3号)の「3 資産等の状況」欄により確認する。
- 66 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
「繰延資産」とは、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第74条第3項第
5号に規定する繰延資産をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計
算規則第2編第2章第2節の「のれん」をいう。
辻 iの基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
嵐 事業資金として自己名義の現金・預金の額が800万円以上であることとする。
・厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書(様
式第3号)の「3 資産等の状況」欄により確認する。
k 事業所数については、定款及び登記事項証明書、又は企業パンフレット等により確認
する。
Ⅴ 常時雇用している派遣労働者の人数については、過去1年間の月末における派遣労働
者(日雇派遣労働者を含む。)の平均人数とし(常用換算数ではない。)、「労働者派
遣事業許可申請の当分の間の措置に関する常時雇用する派遣労働者数の報告について」
(様式第17号)により確認する。
(b)常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主の財産的基礎(3年間の
暫定措置)
平成27年9月30日~平成30年9月29日の3年間の暫定措置として、1つの事業所
(労働者派遣事業を実施する事業所のみではなく、当該事業主の労働者の勤務する場所又
は施設を含む。)のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事
業主に対しては、財産的基礎に関する判断基準について以下のとおりとする。
i 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基
準資産額」という。)について500万円以上であることとする。
・厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書(様
式第3号)の「3 資産等の状況」欄により確認する。
「繰延資産」とは、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第74条第3項第
5号に規定する繰延資産をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計
算規則第2編第2章第2節の「のれん」をいう。
辻 iの基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
嵐 事業資金として自己名義の現金・預金の額が400万円以上であることとする。
・ 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書
(様式第3号)の「3 資産等の状況」欄により確認する。
k 事業所数については、定款及び登記事項証明書、又は企業パンフレット等により確認
する。
Ⅴ 常時雇用している派遣労働者の人数については、過去1年間の月末における派遣労働
者(日雇派遣労働者を含む。)の平均人数とし(常用換算数ではない。)、「労働者派
遣事業許可申請の3年間の暫定措置に関する常時雇用する派遣労働者数の報告につい
- 67 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
て」(様式第17号)により確認する。
C 産業分類に関する判断
派遣元事業主の産業分類については、日本標準産業分類によるものであり、原則として、
当該事業主において実施している主たる事業とする。この主たる事業の確認については、定
款、登記事項証明書、及び参考資料として提出のあったパンフレット等によって確認するこ
と。
なお、複数の事業を実施している事業主については原則として損益計算書のセグメントご
との売上額について最大を占めるものを、当該事業主の主たる産業分類と判断すること。
d 企業規模の判断
派遣元事業主が、中小企業に該当するかについては、次の定義によって判断する。
なお、大企業は中小企業に該当しない事業主をいう。
○中小企業に該当する企業
産業分類
製造業その他
中小企業の定義
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時雇用する労
働者の数が300人以下の会社及び個人
卸 売 業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時雇用する労
働者の数が100人以下の会社及び個人
サービス業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用する
労働者の数が100人以下の会社及び個人
小 売 業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用する
労働者の数が50人以下の会社及び個人
(a)確認方法等について
・産業分類に関する確認
上記Cによって確認すること。
(b)資本金に関する確認
貸借対照表によって確認すること。なお、基準資産額、負債の総額及び自己名義の現金
・預金の額について、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次
決算により確認を行った場合、資本金についても、当該監査法人による監査証明を受けた
中間決算又は月次決算によって確認すること。
ただし、個人の場合については会計科目として資本金がないことから常時雇用する労働
者数で判断すること。
(C)常時雇用する労働者に関する確認
- 68 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
労働者名簿によって許可申請日の直近の月末(直近の月末が確認できない場合は前々月
の末)現在における労働者数を確認すること。
(d)雇用保険との整合性について
雇用保険での産業分類と異なる場合、雇用保険部門にその旨連絡し、同一の行政機関が
行う産業分類に関する判断に矛盾が生じないよう整理を行うこと。
(ロ)組織的基礎に関する判断
派遣労働者数に応じた派遣元責任者が配置される等組織体制が整備されるとともに、労働者
派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこ
と。
(ハ)事業所に関する判断
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20I撼以上あるほか、その位置、設備等
からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。
・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当すること。
a 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制
する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこ
と。
b 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20I撼以上あること。
(ニ)適正な事業運営に関する判断
労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利
用しないこと、登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等
法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うものであり、次のいずれにも該当すること。
a 労働者派遣事業において事業停止命令を受けた者が、当該停止期間中に、許可を受けよう
とするものではないこと。
b 法人にあっては、その役員が、個人事業主として労働者派遣事業について事業停止命令を
受け、当該停止期間を経過しない者ではないこと。
C 労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として
利用するものではないこと。
許可申請関係書類として提出された定款又は寄附行為及び登記事項証明書については、そ
の目的の中に「労働者派遣事業を行う」旨の記載があることが望ましいが、当該事業主の行
う事業の目的中の他の項目において労働者派遣事業を行うと解釈される場合においては、労
働者派遣事業を行う旨の明示的な記載は要しないものであること。
なお、定款又は寄附行為及び登記事項証明書の目的の中に適用除外業務について労働者派
遣事業を行う旨の記載がある場合については、そのままでは許可ができないものであるので
留意すること。
d 登録制度を採用している場合において、登録に際し、いかなる名義であっても手数料に相
- 69 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
当するものを徴収するものではないこと。
e 自己の名義をもって、他人に労働者派遣事業を行わせるために、許可を得ようとするもの
ではないこと。
f 法第25条の規定の趣旨に鑑み、人事労務管理業務のうち、派遣先における団体交渉又は
労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行
う業務について労働者派遣を行おうとするものではないこと。
なお、当該業務について労働者派遣を行おうとするものではないことを労働者派遣事業の
許可条件として付するものであることに留意すること。
ホ 民営職業紹介事業と兼業する場合の許可の要件
労働者派遣事業と民営職業紹介事業の許可の要件をともに満たす限りにおいて兼業が認められ
るものであるが、同一の事業所内において兼業を行おうとする場合は、更に次の事項のとおりと
する。
(イ)事業運営の区分
派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情幸酎こついて、労働者派遣事業又は職業紹介
事業の業務の目的の達成に必要な範囲でこれを収集し、当該収集の目的の範囲内でこれを保管およ
び使用するよう管理されること等事業運営につき明確な区分がなされていること。
・ 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
a 労働者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、同一の者について労働者派遣に
係る登録と求職の申込みの受付を重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。
b 派遣の依頼者又は求人者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、派遣の依頼と
求人の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。
C 派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情幸酎こついて、職業紹介事業又は労働者
派遣事業のいずれの業務に使用することを目的として収集されたものであるかを明確にして
管理されること。
d 派遣の依頼者に係る情報と求人者に係る情幸酎こついて、職業紹介事業又は労働者派遣事
業のいずれの業務に使用することを目的として収集されたものであるかを明確にして管理さ
れること。
e 労働者派遣の登録のみをしている派遣労働者に対して職業紹介を行わないこと、かつ、
求職申込みのみをしている求職者について労働者派遣を行わないこと。
f 派遣の依頼のみを行っている者に対して職業紹介を行わないこと、かつ、求人申込みの
みをしている求人者について労働者派遣を行わないこと。
g 紹介予定派遣を行う場合を除き、求職者に対して職業紹介する手段として労働者派遣を
するものではないこと。
(ロ)民営職業紹介事業と兼業する場合の許可申請関係書類等
既に労働者派遣事業の許可を取得している者又は労働者派遣事業の許可の有効期間の更新を
- 70 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
行った者が、職業紹介事業の許可の申請を行う場合、もしくは、労働者派遣事業の許可の申請
と同時に職業紹介事業の許可の申請を行う場合において、職業安定法施行規則第18条第7項
の規定に基づき、職業紹介事業の許可の申請に係る添付書類を省略することができる。
民営職業紹介事業と兼業する場合の許可申請に関する詳細は、「職業紹介事業業務運営要
領」を参照すること。
へ 海外派遣を予定する場合の許可の要件
イから二までに掲げる要件の他、更に次の事項につき併せて判断すること(これは法第7条第
1項各号の要件に基づくものである。)。
① 派遣元責任者が派遣先国の言語及び労働事情に精通するものであること。
・ 派遣先国の言語とは、派遣先国で一般的に通用する言語(例、英語、仏語等)を含み、必
ずしも派遣先の現地語に限られない。
② 海外派遣に際し派遣労働者に対してガイダンスを実施すること、海外の事業所との連絡体制
が整備されていること等派遣労働者の海外における適正な就業のための体制が整備されている
こと。
海外の事業所とは派遣先の事業所をいう。
ト 労働安全衛生に関する許可の要件
派遣労働者への労働安全衛生の徹底を図るため、以下の措置等が講じられているか判断するこ
と。
(力 労働者派遣契約に安全及び衛生に関する事項を記載すること。
② 物の製造の業務に労働者派遣を行う場合には、製造業務専門派遣元責任者及び製造業務専門
派遣先責任者を選任すること。
③ 派遣元責任者及び派遣先責任者は、派遣労働者の安全及び衛生に関し、必要な連絡調整を行
うこと。
④ 派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や
配慮を行うこと。
なお、林業における労働災害の発生頻度は、他産業に比べ高い水準にあることに鑑み、労働者
派遣の受け入れに当たっては、労働安全衛生法等に十分に留意する必要があること。
(9)申請内容の確認
申請を受けた事業主管轄労働局及び事業所管轄労働局においては、速やかに当該事業主に係る
欠格事由及び許可基準の各事項について、許可申請関係書類の審査、実地調査等により確認す
る。
提出された許可申請関係書類については、事業主管轄労働局及び事業所管轄労働局で、①必要
な書類が添付されていること、②書面に記入もれがないこと及び記入事項に誤りがないこと等の
許可要件に関する確認を行い、その結果を関係書類と共に本省に送付・報告する。
(10)労働政策審議会への諮問等
- 71-
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
イ 労働政策審議会への諮問
厚生労働大臣は、労働者派遣事業の許可をするにあたって労働政策審議会(労働力需給制度部
会)の意見を聴くこととなっており(法第5条第5項)、その意見を聴いた後に許可又は不許可
の処分を行うこととなる。
労働政策審議会(労働力需給制度部会)は原則として毎月1回開催している。
原則として、前月末までに本省に到達した許可申請は、当月の労働政策審議会(労働力需給制
度部会)に諮問する。
なお、労働政策審議会(労働力需給制度部会)においては、その適切な審議に資するよう確認
事項を求める場合があるが、この確認事項については申請事業主もできる限り協力するよう求め
ること。
ロ 労働政策審議会への報告
(イ)許可の有効期間更新時の許可基準の報告
許可の有効期間の更新については労働政策審議会(労働力需給制度部会)への諮問は要しな
いが、許可の取得後最初の許可更新の際に、当該更新を受けようとする派遣元事業主が引き続
き許可基準を満たしていることを当該審議会へ報告する。
(ロ)初めての許可より2年後における資産等の状況の報告
初めて労働者派遣事業の許可の取得を受けた派遣元事業主の許可取得2年後の資産等の状況
については労働政策審議会(労働力需給制度部会)へ報告する。
(11)許可及び不許可処分
イ 許可申請の許可を行ったときは、許可証を作成し事業主管轄労働局を経由して、労働者派遣事
業を行う事業所の数に応じ申請者に交付する(法第8条第1項、則第2条)。
ロ 許可申請につき、不許可とした時は、遅滞なく、労働者派遣事業不許可通知書を作成し、事業
主管轄労働局を経由して申請者に交付する(法第7条第2項)。
ハ イ又はロに際しては、併せて労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)の写し及び労働者派遣
事業計画書(様式第3号)の写しそれぞれ1通を申請者に控えとして交付する((6)参照)。
ニ 事業所台帳の整備
労働者派遣事業の許可をしたときは、労働者派遣事業所台帳又は派遣元事業主台帳(第3にお
いて「事業所台帳等」という。)の作成、記載を行う(6参照)。
(12)許可の条件
イ 許可の条件の範囲
労働者派遣事業の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる(法第9条第1
項)が、当該条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図る
ために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けようとする者に不当な義務を課すこ
ととなってはならない(同条第2項)。
ロ 許可の条件を付す場合
- 72 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
労働者派遣事業の運営に当たり、労働力需給の適正な調整を図り、派遣労働者に係る雇用管理
を適正に行わせる等の観点から、許可をした後においても一定の条件の下に当該事業を行わせる
ことが必要であると考えられる場合に付されるものであり、具体的には、例えば専ら労働者派遣
の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこと、派遣先における団体交渉
又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行
う業務について労働者派遣を行うものではないこと、労働保険・社会保険の適用基準を満たす派
遣労働者の適正な加入を行うものであること、労働者派遣契約の終了のみを理由として派遣労働
者を解雇しないことといった条件が付されるものである。
また、許可後に届出により新設される労働者派遣事業所においても、適正な事業運営がなされ
るよう、(8)の「許可基準」の所定の要件を満たすことが許可条件として付されるものであ
る。
この他にも、例えば、①同一事業所において労働者派遣事業と民営職業紹介事業を兼業して行
おうとする場合において、当該許可の後においても、(8)の「許可基準」のホの事項を遵守す
ること、②特定企業に対する労働者派遣事業の許可をする場合において、当該許可の後において
も、同「許可基準」のイに掲げる厚生労働省令で定める条件を維持し続けること、③登録型で事
業を行う場合において、当該許可の後においても、同「許可基準」のこの(ニ)のdの事項を遵
守することを条件に付すことが考えられる。
ハ 許可の条件を付す場合は、(11)のイに定める許可証とは別に、次の様式による労働者派遣事
業許可条件通知書を作成し、事業主管轄労働局を経由して、申請者に交付する。
- 73 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
年 月 日
労働者派遣事業許可条件通知書
厚生労働大臣 印
年 月 目付け許可番号 の許可は下記の理由により次の許可条件を付して行う。
なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、処分のあった
ことを知った目の翌日から起算して3箇月以内(ただし、処分のあった目の翌日から起算して1年以内)に厚生労
働大臣に対し、審査請求をすることができる。
また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この処分のあった
ことを知った目の翌日から起算して6箇月以内(ただし、処分のあった目の翌日から起算して1年以内)に、国を
被告(代表者は法務大臣)として提起することができる。ただし、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴え
は、その審査請求に対する裁決があったことを知った目の翌日から6箇月以内(ただし、裁決のあった目の翌日か
ら起算して1年以内)に提起することができる。
(許可条件)
① 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこと。
② 派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事
者として行う業務について労働者派遣を行うものではないこと。
③ 労働保険・社会保険の適用基準を満たす派遣労働者の適正な加入を行うものであること。
④ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと。また、有期雇用派遣労働者に
ついても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみ
を理由として解雇しないこと。
⑤ 労働者派遣事業を行う事業所を新設する場合においても、「許可基準」の所定の要件を満たすこと。
⑥ また、労働者派遣事業を行う事業所を新設する場合にあっては、届出を行うに先立って、事業主管轄労働局又
は事業所管轄労働局に事業計画の概要及び派遣元責任者となる予定の者等について説明を行うこと。
記
(①、②、③及び④の理由)
労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行
を考慮する必要があるため。
(⑤及び⑥の理由)
許可後に届出により新設される労働者派遣事業を行う事業所においても、適正な事業運営を確保する必要があ
るため。
- 74 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
(13)許可番号の付与
イ 許可事業主については、許可申請関係書類として完全なものと判断したときには、ニに基づく
当該事業主固有の許可番号(以下「許可番号」という。)及び各申請事業所の事業所枝番号(以
下「事業所枝番号」という。)を付与する。
ロ 許可番号及び事業所枝番号は付与後、住所の変更等により事業主管轄労働局が変更される場合
を除き、変更されることはない。
ハ 許可証には、当該許可番号及び事業所枝番号を所定の欄に必ず記載すること。
ニ 許可番号等の設定について
(イ)労働者派遣事業である旨の表示
「派」の文字をもって表す。
(ロ)都道府県番号
労働保険機械事務手引の「都道府県コード表」に定める2桁の数字で表す。例えば、北海道
は「01」と表す。
(ハ)事業主の一連番号
管轄労働局ごとに6桁の数字をもって表すものとし、原則として許可時期の早い事業主から
起番する。なお、(旧)一般労働者派遣事業の事業主については、平成27年9月30日以降は
「般」を「派」に切り替え、番号そのものは変更しない。
(ニ)事業所枝番号
事業所枝番号は、事業所ごとに3桁の数字をもって表す。この際、派遣元事業主の主たる事
務所を「001」として、許可申請書に記載された順に起番する。
(ホ)平成27年9月29日以前に許可及び許可の有効期間の更新を受けた派遣元事業主の取扱い
平成27年9月29日以前に許可及び許可の有効期間の更新を受けた(旧)一般労働者派遣事
業主については、平成27年9月30日以降、厚生労働省のハローワークシステム労働力需給調
整事業機能群の管理上は許可番号の「般」が「派」に自動的に変更されるが、当該許可の有効
期間内は、許可証の許可番号の「般」を「派」に変更する必要はない。
また、派遣元事業主が締結する労働者派遣契約等に記載している許可番号については、平成
27年9月29日以前に締結した労働者派遣契約等に記載している許可番号を「般」から「派」
に変更する必要はないが、平成27年9月30日以降に締結する労働者派遣契約等については、
許可番号を「般」から「派」に変更しなければならないことに留意すること。
(経過措置)
経過措置期間(平成27年9月 30 日~平成30年9月 29 日、詳細について第4参照)の
(旧)特定労働者派遣事業の事業所は、現行の届出受理番号である「特」を引き続き使用す
る。ただし、経過措置期間以降、当該番号及び事業所枝番号は使用できなくなるので留意する
こと。
- 75 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
(具体例)
派 01-500037 - 事業主の一連番号(000001~999999)
Lt
都道府県番号(01~47)
力働者派遣事業であることの表示
(14)労働者派遣事業制度に係る周知
事業主管轄労働局においては、(11)イにより許可証を交付する際、当該事業主に対して以下
の内容により適正な労働者派遣事業の運営に係る講習を実施するものとする。
イ 労働者派遣事業制度の適正な運営について
ロ 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分について
ハ その他労働者派遣事業の適正な運営の確保を図るために必要な事項
なお、当該講習の実施に当たっては、必要に応じ、労働基準行政、雇用均等行政、職業安定行
政の需給調整事業担当部門以外の部門との連携を図ること。
2 許可の有効期間の更新手続について
(1)許可の有効期間
労働者派遣事業の許可の有効期間は、初めて許可を受けた場合、許可の日から起算して3年で
ある(法第10条第1項)。
また、一度許可の更新を受けた場合における有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する
日の翌日から起算して5年とする。以後の有効期間については、それを繰り返す(法第10条第
2項及び第4項、則第19条)。
許可の有効期間が満了したとき、当該許可は失効する。
(2)労働者派遣事業の許可の有効期間の更新の手続
イ 事業主は、許可の有効期間の満了後においても引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合に
は、厚生労働大臣に対して、許可の有効期間の更新を申請しなければならない。
許可の有効期間の更新申請については、事業主は、(3)に掲げる厚生労働大臣に提出する書
類(申請書、事業計画書のほか、これらに添付すべきこととされている書類を含む。以下、「許
可有効期間更新申請関係書類」という。)を事業主管轄労働局に提出することにより行う(法第
10条第5項において準用する法第5条第2項から第4項まで、則第19条)。また、上記許可の
有効期間の更新の審査の参考とするための参考資料も併せて提出することが求められる(以下、
「許可有効期間更新申請関係書類等」という。)。
許可有効期間更新申請関係書類等については、原則として事業主管轄労働局を経て厚生労働大
臣に提出される(則第19条)。
ロ 許可有効期間更新申請関係書類等は、当該許可の有効期間が満了する日の3箇月前までに、事
業主管轄労働局に提出しなければならない(則第5条第1項)こととなっており、申請日の超過
- 76 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
は認められない。
事業主管轄労働局は、事業主から管轄以外の地域において派遣事業を実施する内容の許可有効
期間更新申請関係書類等の提出を受けた場合、労働者派遣事業を行おうとする各事業所の事業所
管轄労働局に対して、申請書の写し及び各事業所に関する書類を送付しなければならない。
ハ 申請を受けた事業主管轄労働局及び事業所管轄労働局においては、速やかに(4)の当該事業
主に係る許可有効期間更新要件の各事項について実地調査等による確認を行い、許可有効期間更
新申請関係書類等の審査を行う。
提出された許可有効期間更新申請関係書類等については、事業主管轄労働局及び事業所管轄労
働局で、(力必要な書類が添付されていること、②書面に記入もれがないこと及び記入事項に誤り
がないこと等の許可有効期間更新要件に関する確認を行い、その結果を関係書類と共に本省に送
付・報告すること。
ニ 本省は、許可の取得後最初の許可更新を受けようとする派遣元事業主における許可の更新状況
について、労働政策審議会(労働力需給制度部会)へ報告しなければならない(1の(10)参
照)。
ホ 許可の有効期間の更新とは、更新時前と許可内容の同一性を存続させつつ、その有効期間のみ
を延長するものである。
したがって、許可の有効期間の更新に際し、併せて、更新前から変更する事項(変更の届出を
行う必要がある事項のみ)がある場合は、許可の有効期間の更新の手続きと併せて、変更の届出
の手続(3参照)を行う必要がある。
(3)許可有効期間更新申請関係書類
労働者派遣事業の許可有効期間更新申請関係書類は法人及び個人の区分に応じ次のイ及びロの
とおりとする(法第10条第5項において準用する法第5条第2項から第4項まで、則第5条第
1項から第3項まで)。
イ 法人の場合
(イ)労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)
(ロ)労働者派遣事業を行う事業所(許可後に届出により新設した事業所を含む。以下同じ。)ご
との当該事業に係る事業計画書(様式第3号、様式第3号-2及び様式第3号-3(ただし、
様式第3号-3は、派遣労働者のうち、雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がい
る場合にのみ提出を要するものであること。))
(ハ)定款又は寄附行為(ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。)
(ニ)登記事項証明書(ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。)
(ホ)役員(以下この(ホ)において「役員甲」とする。)が未成年者のため、労働者派遣事業に
関し法定代理人から営業の許可を受けていない場合は、a・bの区分に応じ、それぞれa・b
の書類(ただし、役員甲が法定代理人から営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の
許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登記事項証明書))(ただし、法定代理人の
- 77 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
変更があった場合に限る。)
a 役員甲の法定代理人が個人である場合
役員甲の法定代理人の住民票の写し及び履歴書
b 役員甲の法定代理人が法人である場合
役員甲の法定代理人の定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び
履歴書(ただし、役員甲の法定代理人の役員(以下この(ホ)において「役員乙」とす
る。)が未成年者のため、労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていない
場合は、a・bの区分に準じ、それぞれa・bの書類(役員乙が法定代理人から営業の許可
を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登
記事項証明書))を含む。さらに、法定代理人の役員について、同様の事例が続く限り、前
記と同様に取り扱うこと。)
(へ)労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程(「派遣元事業主が講ずべき措置
に関する指針」第2の11の(2)のハの(イ)から(ニ)までの内容が含まれていることが
必要(第7の27参照)。)(ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限
る。)
(ト)最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等であって納税
地の所轄税務署長に提出したもの。
なお、損益計算書については、可能な限り事業区分(セグメント)単位で売上額が確認でき
るものであること。
最近の事業年度における決算は終了しているものの株主総会の承認を得ていないため納税地
の所轄税務署長に提出していない場合は、当該決算に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資
本等変動計算書等を確実に納税地の所轄税務署長に提出することが確認できる場合に限り、当
該貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等であれば差し支えない。なお、申請時
においては、この場合(チ)のa及びbを提出させる必要はない。
(チ)労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
a 最近の事業年度における法人税の確定申告書の写し(納税地の所轄税務署の受付印のある
もの(電子申請の場合にあっては、納税地の所轄税務署に受け付けられた旨が確認できるも
の。以下同じ。)に限る。法人税法施行規則別表1(1)及び4は、必ず提出すること。)
なお、連結納税制度を採用している法人については次に掲げる書類
・ 最近の連結事業年度における連結法人税の確定申告書の写し(連結親法人の納税地の所
轄税務署の受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表1の2「各連結事業年度分の
連結所得に係る申告書」の写し及び同申告書添付書類「個別帰属額等の一覧表」の写しの
みでよい。ただし、別表7の2付表1「連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額
の計算に関する明細書」が提出される場合には、その写しを併せて提出すること。)
・ 最近の連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書(申請法人に係るものに限
- 78 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
る。)の写し(納税地の所轄税務署長に提出したもの。ただし当該届出書の別表にあって
は別表4の2付表「個別所得の金額の計算に関する明細書」の写しのみでよい。))
b 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式
(その2)による法人の最近の事業年度における所得金額に関するもの)
(なお、連結納税制度を採用している法人については納税証明書(国税通則法施行令第41
条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による最近の連結事業年度に
おける連結所得金額に関するもの))
(リ)労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣元責任者に係る厚生労働省告示(平成27年厚生労
働省告示第392号)に定められた講習機関が実施する「派遣元責任者講習」の「派遣元責任者
講習受講証明書(許可の有効期間が満了する目前3年以内の受講日のものに限る)」(様式第
21号)の写し
(ヌ)派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程(ただし、既に提出されているものに変更
があった場合に限る。)
a 教育訓練受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とすることか
ら、当該取扱の記載された就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等
b 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等
又はその概要等の該当箇所
(ル)無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書
類。また、有期雇用派遣労働者についても、派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労
働者については、派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類(ただし、既
に提出されているものに変更があった場合に限る。)
・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規
定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等
(ヲ)無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終
了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業さ
せた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した就業規則又は労働契
約の該当箇所の写し等(ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。)
ロ 個人の場合
(イ)労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)
(ロ)労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書(様式第3号、様式第3号-
2及び様式第3号-3(ただし、様式第3号-3は、派遣労働者のうち、雇用保険又は健康保
険・厚生年金保険の未加入者がいる場合にのみ提出を要するものであること。))
(ハ)申請者が未成年者のため、労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていない
場合は、a・bの区分に応じ、それぞれa・bの書類(ただし、申請者が法定代理人から営業
の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係
- 79 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
る登記事項証明書))(既に提出されているものに変更があった場合に限る。)
a 申請者の法定代理人が個人である場合
申請者の法定代理人の住民票の写し及び履歴書
b 申請者の法定代理人が法人である場合
申請者の法定代理人の定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び
履歴書(ただし、申請者の法定代理人の役員(以下この(ハ)において「役員丙」とす
る。)が未成年者のため、労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていない
場合は、a・bの区分に準じ、それぞれa・bの書類(ただし、役員丙が法定代理人から営
業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者
に係る登記事項証明書))を含む。さらに、法定代理人の役員について、同様の事例が続く
限り、前記と同様に取り扱うこと。)
(ニ)労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程(「派遣元事業主が講ずべき措置
に関する指針」第2の11の(2)のハの(イ)から(ニ)までの内容が含まれていることが
必要(第7の27参照)。)(ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限
る。)
(ホ)労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
① 最近の納税期における所得税の確定申告書の写し(納税地の所轄税務署の受付印のあるも
の)
② 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号イに係る同施行規則別紙第8号様式
(その2)による最近の納税期における金額に関するもの)
③ 申告納税制度関係
・ 青色申告の場合(簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。)は、最近の
納税期における所得税法施行規則第65条第1項第1号の貸借対照表及び損益計算書(所
得税青色申告決算書(一般用)の写し(納税地の所轄税務署の受付印のあるもの))
なお、損益計算書については、可能な限り事業区分(セグメント)単位で売上額が確認
できるものであること。
・ 白色申告又は青色申告で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合は、(ロ)の労
働者派遣事業計画書の「3 資産等の状況」欄に記載された土地・建物に係る不動産の登
記事項証明書及び固定資産税評価額証明書
④ 預金残高証明書(納税期末日のもの)
(へ)労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣元責任者に係る厚生労働省告示(平成27年厚生労
働省告示第392号)に定められた講習機関が実施する「派遣元責任者講習」の「派遣元責任者
講習受講証明書(許可の有効期間が満了する目前3年以内の受講日のものに限る)」(様式第
21号)の写し
(ト)派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程(ただし、既に提出されているものに変更
- 80 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
があった場合に限る。)
a 教育訓練受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とすることか
ら、当該取扱の記載された就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等
b 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等
又はその概要等の該当箇所の写し
(チ)無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書
類。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している
派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書
類。(ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。)
・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規
定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等
(リ)無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終
了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業さ
せた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した就業規則又は労働契
約の該当箇所の写し等(ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。)
ハ 参考資料の作成と提出
許可の有効期間更新の審査を行うにあたっての参考とするため、法人及び個人に対して以下の
参考資料を提出するよう求めること。
(イ)自己チェックシート
事業主には、許可申請時と同様に「自己チェックシート」の提出を求めること。
(ロ)企業パンフレット等事業内容が確認できるもの(既に提出されているものに変更があった場
合に限る。)
(ハ)労働者名簿(申請月の前月末現在(前月末で把握が困難な場合は前々月末現在)のもので、
派遣労働者を含む全労働者分)
(ニ)小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置により、許可基準のうち緩和された財産的基礎に
関する要件にて申請する場合には別途定める次のa及びbの提出を求めること。((4)のロ
の(イ)のb参照)
a 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第7条第1項第
4号の財産的基礎に関する要件についての誓約書(様式第16号)
b 労働者派遣事業許可申請の当分の間の措置に関する常時雇用する派遣労働者数の報告につ
いて又は労働者派遣事業許可申請の3年間の暫定措置に関する常時雇用する派遣労働者数の
報告について(様式第17号)
ニ 就業規則の該当箇所の写しを添付させる場合、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する労働
基準監督署の受理印がある該当ページの写しを併せて提出すること(既に提出されている就業規
則の該当ページの写しに変更があった場合に限る。)。
- 81-
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
(4)許可の有効期間の更新要件等
イ 許可の有効期間の更新については、許可申請時においては「許可の基準に適合していると認め
るときでなければ、許可をしてはならない」(法第7条第1項)とされているのとは異なり、
「許可の基準に適合していないと認めるときは、許可の更新をしてはならない」(法第10条第
3項)としている。
このため、許可の欠格事由及び許可条件違反に該当しない等、許可申請時及び許可の有効期間
更新時において適合していると認めた許可要件について、特段の事情変更がないことを確認しな
ければならない。
ロ イの「特段の事情変更がないこと」の確認に当たって、財産的基礎に関する判断に係る許可基
準の取扱い(事業主(法人又は個人)単位で判断)は、次のとおりとする。
(イ)財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)
a 許可申請事業主に関する財産的基礎
許可申請事業主についての財産的基礎の要件については以下のとおりとする。
(a)資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準
資産額」という。)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定す
る)事業所の数を乗じた額以上であること。
・厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書(様式
第3号)の「3 資産等の状況」欄により確認する。
「繰延資産」とは、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第74条第3項第5
号に規定する繰延資産をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計算規
則第2編第2章第2節の「のれん」をいう。
(b)(a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
(C)事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業
を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
・厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書(様式
第3号)の「3 資産等の状況」欄により確認する。
(d)基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあったときは、公
認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算による場合に限り、
基準資産額、負債の総額及び自己名義の現金・預金の額のいずれについても当該中間決算
又は月次決算により確認するものとする。
ただし、個人の場合に限り、基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨の
申し立てがあったときは、(力市場性のある資産の再販売価格の評価額が、基礎価額を上回
る旨の証明があった場合(例えば、固定資産税の評価額証明書等による。)、②提出され
た預金残高証明書により普通預金、定期預金等の残高を確認できた場合(複数の預金残高
証明書を用いる場合は、同一日付のものに限る。)に限り、当該増加後の額を基準資産額
- 82 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
又は自己名義の現金・預金の額とする。
(e)職業安定法第45条に規定する厚生労働大臣の許可を受け、労働者供給事業を行う労働
組合等から供給される労働者を対象として、労働者派遣事業を行うことを予定する場合に
ついては、(a)において「2,000万円」を「1,000万円」と、(C)において「1,500
万円」を「750万円」と読み替えて適用する。
(り 地方公共団体による債務保証契約又は損失補填契約が存在することによって派遣労働者
に対する賃金支払いが担保されている場合は、(a)、(b)及び(C)の要件を満たし
ていなくても差し支えないこととする。
b 小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置
小規模派遣元事業主であってaの(a)、(b)又は(C)の要件を満たさない者に係る
財産的基礎に関する判断については以下のとおりとする。
ただし、平成28年9月30日以降は、①改正法附則第6条第1項の規定により引き続き行
うことができることとされ、平成27年9月30日以降、暫定的な配慮措置により許可を受け
て労働者派遣事業を行っている者、及び②(力以外の者で平成27年9月30日から平成28年
9月 29 日までの間に、暫定的な配慮措置により新規許可又は許可の更新を受けて労働者派
遣事業を行っている者(平成28年9月29日までに事業主管轄労働局に対して許可の有効期
間の更新に係る申請を行い、当該申請が受理されている者も含む。)からの申請に限るもの
とする。
(a)1つの事業所(労働者派遣事業を実施する事業所のみではなく、当該事業主の労働者の
勤務する場所又は施設を含む。)のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下
である中小企業事業主の財産的基礎(当分の間の措置)に関する判断については以下のと
おりとする。
i 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基
準資産額」という。)について1,000万円以上であることとする。
・厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書(様
式第3号)の「3 資産等の状況」欄により確認する。
「繰延資産」とは、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第74条第3項第
5号に規定する繰延資産をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計
算規則第2編第2章第2節の「のれん」をいう。
辻 iの基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
嵐 事業資金として自己名義の現金・預金の額が800万円以上であることとする。
・厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書(様
式第3号)の「3 資産等の状況」欄により確認する。
k 事業所数については、定款及び登記事項証明書、又は企業パンフレット等により確認
する。
- 83 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
Ⅴ 常時雇用している派遣労働者の人数については、過去1年間の月末における派遣労働
者(日雇派遣労働者を含む。)の平均人数とし(常用換算数ではない。)、「労働者派
遣事業許可申請の当分の間の措置に関する常時雇用する派遣労働者数の報告について」
(様式第17号)により確認する。
C 産業分類に関する判断
派遣元事業主の産業分類については、日本標準産業分類によるものであり、原則として、
当該企業において実施している主たる事業とする。この主たる事業の確認については、定
款、登記事項証明書、及び参考資料として提出のあったパンフレット等によって確認するこ
と。
なお、複数の事業を実施している事業主については原則として損益計算書のセグメントご
との売上額について最大を占めるものを、当該事業主の主たる産業分類と判断すること。
d 企業規模の判断
派遣元事業主が、中小企業に該当するかについては、次の定義によって判断する。
なお、大企業は中小企業に該当しない事業主をいう。
○中小企業に該当する企業
産業分類
製造業その他
卸 売 業
サービス業
小 売 業
中小企業の定義
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時雇用する
労働者の数が300人以下の会社及び個人
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時雇用する
労働者の数が100人以下の会社及び個人
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用す
る労働者の数が100人以下の会社及び個人
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用す
る労働者の数が50人以下の会社及び個人
(a)確認方法等について
・産業分類に関する確認
上記Cによって確認すること。
・資本金に関する確認
貸借対照表によって確認すること。
なお、基準資産額、負債の総額及び自己名義の現金・預金の額について、公認会計士
又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算により確認を行った場合、
資本金についても、当該監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算によっ
- 84 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
て確認すること。
ただし、個人の場合については会計科目として資本金がないことから常時雇用する労
働者の数で判断すること。
・常時雇用する労働者に関する確認
労働者名簿によって許可申請日の直近の月末(直近の月末が確認できない場合は前々
月の末)現在における労働者数を確認すること。
(b)雇用保険との整合性について
雇用保険での産業分類と異なる場合、雇用保険部門にその旨連絡し、同一の行政機関が
行う産業分類に関する判断に矛盾が生じないよう整理を行うこと。
ハ 関係法令の準用
許可の有効期間の更新については、法第5条第2項から第4項まで、法第6条(第4号から第
7号を除く。)及び第7条第2項を準用する(法第10条第5項)。
ニ 許可有効期間更新申請関係書類等のうち、(3)イの(イ)及び(ロ)並びにロの(イ)及び
(ロ)に掲げる書類は、正本1通及びその写し2通を提出することを要するが、それ以外の書類
については、正本1通及びその写し1通で足りる。
(5)更新前後の許可内容の同一性の判断
許可の欠格事由及び許可条件違反に該当しない等、許可申請時及び許可の有効期間更新時にお
いて適合していると認めた許可要件について、特段の事情変更がないことの確認にあたって以下
のとおり判断する。
イ 教育訓練のために既に利用されているか1年以内に利用することが確実であると認められる施
設、機器等に教育訓練の機会の確保の観点から投資を行った結果、1の(8)の「許可基準」
中、ニの(イ)のaの(b)、bの(a)のii及びbの(b)のiiの要件を満たさなくなった場
合は、負債の総額から当該施設、機器等に要した金額を控除して算定して差し支えない。
(イ)この際、「当該施設、機器等に要した金額」に該当するのは、派遣元事業主が自ら雇用する
派遣労働者を主たる対象として行う教育訓練に必要な土地の購入又は教室、実習場等の建物の
新設若しくは増改築に要した金額及び当該教育訓練に必要な機器・備品等の購入に要した金額
であって、当該満了する許可の有効期間中に購入又は新設若しくは増改築した土地、建物及び
機器・備品等に係る金額のうち(3)のイの(ト)又は(3)のロの(ホ)の③の貸借対照表
の有形固定資産として記載されている金額に限る。
ただし、白色申告又は青色申告で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合は、当該満
了する許可の有効期間中に購入又は新設若しくは増改築した土地、建物及び機器・備品等に係
る金額とする。
(ロ)「当該施設、機器等に要した金額」の確認は、次の書類を添付することにより行う。
a 土地又は建物の購入にあっては売買契約書の写し及び領収証の写し、建物の新設又は増改
築にあっては請負契約書の写し及び領収証の写し、機器・備品等の購入にあっては領収証の
- 85 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
写し
b 法人又は個人の別について
法人にあっては、(力「固定資産の取得及び処分並びに原価償却費の明細書」又は固定資
産台帳の写し及び②法人税法施行規則別表16(定額法又は定率法による原価償却資産の
償却額の計算に関する明細書)の写し
・ 青色申告(簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。)を行った個人にあ
っては、「固定資産の取得及び処分並びに原価償却費の明細書」又は固定資産台帳の写し
ロ 許可の有効期間の更新における「許可要件(許可の基準)」の(8)のこの(イ)のaの
(d)の取扱いについては、日本公認会計士協会が平成30年12月20日付けで公表した「労働
者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指
針」に基づいて公認会計士又は監査法人が実施した「合意された手続業務」による中間決算又は
月次決算でも可能とする。
ハ 許可の有効期間の更新の判断を行うに際しては、法第9条第1項の規定に基づき付した条件の
(力専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこと、②派遣
先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の
直接当事者として行う業務について労働者派遣を行うものではないこと等に違反していないこと
について審査し、更新申請の直近有効期間内において違反の事実がみられた場合は、許可を更新
しないこととする。
ニ キャリア形成支援制度を有することについては、その許可の基準の判断においてキャリアアッ
プに資する教育訓練の内容となっていることや、希望する全ての派遣労働者に対するキャリアコ
ンサルティングの相談窓口の設置を要することとなっている。このため、更新申請の直前の有効
期間内において、これら「キャリア形成支援制度を有すること」について許可の基準を満たす実
施状況であったかを確認するとともに必要な指導を行い、例えば、計画はあっても実施されてお
らず、指導しても是正されないような義務違反がみられた場合は、許可基準を満たしていないと
して、許可を更新しないこととする。
ホ 個別の派遣労働者ごとに派遣元事業主の事業所でのキャリアアップに資する教育訓練の実績等
を保存することはその実施を把握する上で重要なことから、キャリア形成支援制度に関連する情
報(計画・実績等)を労働契約終了から3年間管理する体制を整備することを求めることとし、
当該整備にあたっては、人事記録等でも構わないが、原則として派遣元管理台帳等を活用するこ
と。なお、派遣元管理台帳や人事記録等に記載されていない場合には、必要な指導を行うこと。
へ 雇用安定措置について、更新申請の直前の有効期間内において、許可基準を満たす実施状況で
あったかを確認するとともに必要な指導を行い、それでも実施されないような義務違反がみられ
た場合は、許可を更新しないこととする。
ト 労働安全衛生教育及びその他の教育訓練の実績については、更新申請までに実績がない場合に
は、必要な指導を行うこと。
- 86 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
なお、労働安全衛生教育の未実施等を確認した場合、その状況を都道府県労働局労働基準部担
当部門に連絡すること。
チ 1の(8)の「許可基準」中ロの(ロ)のaの(a)の⑨については、「許可の申請の受理の
日」を「許可の有効期間が満了する日」に読み替えること。
リ 1の(8)の「許可基準」中ロの(イ)のeの(O については、「経過措置期間中の(旧)
特定労働者派遣事業を実施していた者」を「許可の有効期間が満了する日以前より5年以内に労
働者派遣事業の許可の有効期間の更新を受け事業を実施していた者」に読み替えること。
(6)更新及び不更新処分
イ 許可有効期間更新申請の更新を行ったときは、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じた許可
証を新たに作成し、事業主管轄労働局を経由して、申請者に、当該申請者が所持していた許可証
と引き換えに、交付する(則第5条第4項)(1の(11)のイ参照)。
ロ 許可の条件が変更される場合は、許可証とは別に、1の(12)のハに掲げた様式による労働者
派遣事業許可条件通知書を作成し、事業主管轄労働局を経由して申請者に交付する。
なお、平成27年9月29日以前に許可を受けた派遣元事業主について、平成27年9月30日以
降の最初の更新時にすべての派遣元事業主の許可の条件が変更になることに留意すること。
ハ 許可有効期間更新申請につき不更新としたときは、遅滞なく、1の(11)のロに掲げた様式に
よる労働者派遣事業許可有効期間不更新通知書を作成し、事業主管轄労働局を経由して申請者に
交付する(法第10条第5項において準用する法第7条第2項)。
ニ イ又はハに際しては、併せて、労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)の写し
及び労働者派遣事業計画書(様式第3号)の写しそれぞれ1通を申請者に控えとして交付する。
ホ 許可有効の更新及び不更新をしたときは、事業所台帳等の作成、記載を行う(6参照)。
(7)労働者派遣事業制度に係る周知
事業主管轄労働局においては、(6)イにより許可証を交付する際、当該事業主に対して許可
時に準じて、適正な労働者派遣事業の運営に係る講習を実施するものとする。
3 事業主の行う変更の届出手続
(1)変更の届出
派遣元事業主が次に掲げる事項を変更したときは、事業主管轄労働局を経て、厚生労働大臣に
対して、変更の届出をしなければならない。ただし、事業所における次の⑥から⑫までに掲げる
事項の変更のみを届け出るときは、当該変更に係る事業所管轄労働局へ届出を行っても差し支え
ない(法第11条第1項、則第19条)。
なお、届出については、届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付され
ていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合に、都道府県労働
局において受理が行われた段階で効力を発揮するものである。
事業所の変更の届出等の手続に際し、事業主管轄労働局に対し、届出書及び関係書類が提出さ
- 87 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
れた場合においては、当該提出を受けた事業主管轄労働局は、必要に応じ、当該届出書の複写を
作成し、添付書類とともに連絡文を添えて当該事業所管轄労働局に送付する。
なお、事業所の所在地が変更になった場合については、当該事業所管轄労働局において管理し
ていた関係書類に連絡文を添えて新たな事業所の所在地を管轄する労働局に引き継ぐこと。
イ 変更事項
(力 氏名又は名称
② 住所
③ 代表者の氏名
④ 役員(代表者を除く。)の氏名
⑤ 役員の住所
⑥ 労働者派遣事業を行う事業所の名称
⑦ 労働者派遣事業を行う事業所の所在地
⑧ 労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了
⑨ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名
⑲ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所
⑪ 労働者派遣事業を行う事業所の新設(事業所における労働者派遣事業の開始)
⑫ 労働者派遣事業を行う事業所の廃止(事業所における労働者派遣事業の終了)
ロ 届出期日
イの①から⑫まで(⑨及び⑲並びに変更に伴い変更届出関係書類として登記事項証明書を添付
する場合を除く。)の変更の届出は、当該変更に係る事項のあった日の翌日から起算して10 日
以内に、派遣元責任者を選任した場合におけるイの⑨及び⑲並びに変更に伴い変更届出関係書類
として登記事項証明書を添付する場合の変更の届出については当該変更に係る事項のあった日の
翌日から起算して30 日以内に、(2)に掲げるイの①から⑫までの区分に応じた変更届出関係
書類を事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に提出することにより行う(法第11条第2項、
則第8条第1項)。なお、イの②及び⑦の変更(同一労働局の管轄区域内の変更を除く。)の場
合の事業主管轄又は事業所管轄労働局とは、変更後のものをいう。
なお、イの⑪の届出に関しては、届出に不備のないよう、当該事業所において労働者派遣事業
を開始する前に事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局へ、事業計画(キャリア形成支援制度に
関する計画を含む)(既に雇用する派遣労働者に雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入
者がいる場合には、雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書が必要であること。)の概要、
派遣元責任者となる予定の者等についてあらかじめ説明するよう指導するものとすること(当該
説明については、事前に届け出ようとする変更届出関係書類を提出することで足りる。)。
ハ 変更の届出については、イの①から⑫までの事項のうち複数の事項の変更を1枚の届出書によ
り行うことができる(この場合(2)に掲げる変更届出関係書類のうち重複するものにつき省略
することができる。)。
- 88 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
ニ イの②、⑤、⑦及び⑲の事項について、単に市町村合併や住居番号の変更により住所又は所在
地に変更が生じた場合には、当該変更に係る変更届出書又は変更届出書及び許可証書換申請書を
提出することを要しない。なお、単に市町村合併や住居番号の変更による許可証書換申請が行わ
れた場合には、当該申請に係る手数料を徴収しないこととするので、申請に当たっては各自治体
から無料で交付される住所(所在地)表示変更証明書を添付するよう指導すること。
(2)変更届出関係書類
労働者派遣事業の変更届出関係書類は、(1)のイの(力から⑫までに掲げる変更された事項の
区分に応じ、当該事項に係る次のイからヲまでに掲げる書類とする(則第8条第2項から第4
項)。
イ 氏名又は名称の変更
(イ)法人の場合(名称の変更)
a 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 定款又は寄附行為
C 登記事項証明書
(ロ)個人の場合(氏名の変更)
a 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 住民票の写し及び履歴書
口 住所
(イ)法人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 定款又は寄附行為(ただし、法人の所在地に変更が加えられた場合に限る。)
C 登記事項証明書
(ロ)個人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 住民票の写し及び履歴書
ハ 代表者の氏名(法人の場合のみ)
(イ)労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)登記事項証明書
(ハ)代表者の住民票の写し及び履歴書(氏名又は役職のみの変更の場合、不要。)
(ニ)代表者が未成年者の場合は、1の(5)のイの(イ)のfに定める書類
二 役員(代表者を除く。)の氏名(法人の場合のみ)
(イ)労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)登記事項証明書
(ハ)役員の住民票の写し及び履歴書(氏名又は役職のみの変更の場合、不要。)
(ニ)役員が未成年者の場合は、1の(5)のイの(イ)のfに定める書類
- 89 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
ホ 役員の住所(法人の場合のみ)
(イ)労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)登記事項証明書(代表者を除く役員の変更の場合、不要)
(ハ)役員の住民票の写し
へ 労働者派遣事業を行う事業所の名称
(イ)法人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 定款又は寄附行為(事業所の名称の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。)
C 登記事項証明書(事業所の名称の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。)
(ロ)個人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
ト 労働者派遣事業を行う事業所の所在地
(イ)法人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 定款又は寄附行為(事業所の所在地の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。)
C 登記事項証明書(事業所の所在地の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。)
d 事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契
約書の写し)
(ロ)個人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契
約書の写し)
チ 労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了(法人・個人
の場合共通)
(イ)労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
リ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名(法人・個人の場合共通)
(イ)労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書(氏名のみの変更の場合、不要。派遣元事業主が複
数の事業所において労働者派遣事業を行っている場合において、他の労働者派遣事業を行う事
業所の派遣元責任者を異動させ、変更の届出に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任
するときは、履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履
歴書)を添付することを要しない。)
(ハ)派遣元責任者講習受講証明書(様式第21号)(受講日が届出目前3年以内のもの)の写し
(派遣元事業主が複数の事業所において労働者派遣事業を行っている場合において、他の労働
者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者を異動させ、変更の届出に係る事業所の派遣元責任者
- 90 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
として引き続き選任するときは、派遣元責任者講習受講証明書を添付することを要しない。)
ヌ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所(法人・個人の場合共通)
(イ)労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)派遣元責任者の住民票の写し
ル 労働者派遣事業を行う事業所の新設(事業所における労働者派遣事業の開始)
(イ)法人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
b 新設する事業所ごとの労働者派遣事業計画書(様式第3号、様式第3号-2及び様式第3
号-3)(ただし、様式第3号-3は、派遣労働者のうち、雇用保険又は健康保険・厚生年
金保険の未加入者がいる場合にのみ提出を要するものであること。)
C 新設する事業所ごとの個人情報適正管理規程(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指
針」第2の11の(2)のハの(イ)から(ニ)までの内容が含まれていることが必要(第7
の27参照)。)
d 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等(納税地の
所轄税務署長に提出したもの。)
なお、損益計算書については、可能な限り事業区分(セグメント)単位で売上額が確認で
きるものであること。
最近の事業年度における決算は終了しているものの株主総会の承認を得ていないため納税
地の所轄税務署長に提出していない場合は、当該決算に係る貸借対照表、損益計算書及び株
主資本等変動計算書等を確実に納税地の所轄税務署長に提出することが確認できる場合に限
り、当該貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等であれば差し支えない。な
お、届出時においては、この場合eの(a)の(力及び②を提出させる必要はない。
e 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
(a)納税関係書類
① 最近の事業年度における法人税の確定申告書の写し(納税地の所轄税務署の受付印の
あるものに限る。法人税法施行規則別表1(1)及び4は、必ず提出すること。)
なお、連結納税制度を採用している法人については次に掲げる書類
・ 最近の連結事業年度における連結法人税の確定申告書の写し(連結親法人の納税地
の所轄税務署の受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表1の2「各連結事業
年度分の連結所得に係る申告書」の写し及び同申告書添付書類「個別帰属額等の一覧
表」の写しのみでよい。ただし、別表7の2付表1「連結欠損金当期控除額及び連結
欠損金個別帰属額の計算に関する明細書」が提出される場合には、その写しを併せて
提出させること。)
・ 最近の連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書(申請法人に係るものに限
る。)の写し(納税地の所轄税務署長に提出したもの。ただし当該届出書の別表にあ
ー 91-
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
っては別表4の2付表「個別所得の金額の計算に関する明細書」の写しのみでよ
い。))
② 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号
様式(その2)による法人の最近の事業年度における所得金額に関するもの。
なお、連結納税制度を採用している法人については納税証明書(国税通則法施行令第
41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による最近の連結事
業年度における連結所得金額に関するもの))
(b)新設する事業所ごとの事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動
産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)
f 新設する事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書(派遣元責任者と役員が同
一である場合においては提出を要しない。)(他の労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責
任者を異動させ、新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、履歴書
(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書)を添付する
ことを要しない。)
g 派遣元責任者講習受講証明書(様式第21号)(受講日が届出目前3年以内のもの)の写
し(他の労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者を異動させ、新設する事業所の派遣元
責任者として引き続き選任するときは、派遣元責任者講習受講証明書を添付することを要し
ない。)
h 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程
(a)教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とするこ
とから、当該取扱の記載された就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。
(b)派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル
等又はその概要の該当箇所の写し。
i 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書
類。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続してい
る派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する
書類。
・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について
規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。
j 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が
終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休
業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した就業規則又は
労働契約の該当箇所の写し等。
(ロ)個人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
- 92 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
b 新設する事業所ごとの労働者派遣事業計画書(様式第3号、様式第3号-2及び様式第3
号-3)(ただし、様式第3号-3は、派遣労働者のうち、雇用保険又は健康保険・厚生年
金保険の未加入者がいる場合にのみ提出を要するものであること。)
C 新設する事業所ごとの個人情報適正管理規程(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指
針」第2の11の(2)のハの(イ)から(ニ)までの内容が含まれていることが必要(第
7の27参照)。)
d 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
(a)納税関係書類
① 最近の納税期における所得税の確定申告書の写し(所轄税務署の受付印のあるも
の。)
② 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号イに係る同施行規則別紙第8号
様式(その2)による最近の納税期における金額に関するもの。)
③ 申告納税制度関係
・ 青色申告の場合(簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。)は、最
近の納税期における所得税法施行規則第65条第1項第1号の貸借対照表及び損益計
算書(所得税青色申告決算書(一般用)の写し(納税地の所轄税務署の受付印のある
もの。)
・ 白色申告又は青色申告で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合は、備考欄
に記載された資産等の状況のうち、土地・建物に係る不動産の登記事項証明書及び固
定資産税評価額証明書
④ 預金残高証明書(納税期末日のもの。)
(b)新設する事業所ごとの事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動
産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)
e 新設する事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書(派遣元責任者と申請者が
同一である場合においては提出を要しない。)(他の労働者派遣事業を行う事業所の派遣元
責任者を異動させ、新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、履歴書
(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書)を添付する
ことを要しない。)
f 派遣元責任者講習受講証明書(様式第21号)(受講日が届出目前3年以内のもの)の写
し(他の労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者を異動させ、新設する事業所の派遣元
責任者として引き続き選任するときは、派遣元責任者講習受講証明書を添付することを要し
ない。)
g 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程
(a)教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とするこ
とから、当該取扱の記載された就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。
- 93 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
(b)派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル
等又はその概要の該当箇所の写し。
h 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書
類。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続してい
る派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する
書類。
・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について
規定した就業規則又は労働契約の該当箇所の写し等。
i 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が
終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休
業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した就業規則又は
労働契約の該当箇所の写し等。
(ハ)参考資料の作成と提出
事業所の新設に係る届出の受理を行うにあたっての参考とするため、法人及び個人に対して
以下の参考資料を提出するよう求めること。
a 自己チェックシート
事業主には、許可申請時と同様に「自己チェックシート」の提出を求めること。
b 企業パンフレット等事業内容が確認できるもの(既に提出されているものに変更があった
場合に限る。)
C 就業規則の該当箇所の写しを添付させる場合、事業主の主たる事務所の所在地を管轄す
る労働基準監督署の受理印がある該当ページの写しを併せて提出すること(既に提出され
ている就業規則の該当ページの写しに変更があった場合に限る。)。
ヲ 労働者派遣事業を行う事業所の廃止(事業所における労働者派遣事業の終了)
(法人・個人の場合共通)
(イ)労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)廃止する事業所ごとの許可証
ワ イからヲまでに掲げる書類のうち労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)及び労働者派遣事
業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)については、正本1通及びその写し2通を提
出することを要するが、それ以外の書類については、正本1通及びその写し1通を提出すること
で足りる(則第20条)。
(3)変更の届出の受理
イ 労働者派遣事業の変更の届出を受理したときは、当該変更の届出を受理した事業主管轄労働局
又は事業所管轄労働局において、労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)又は労働者派遣事業
変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)の写し1通を届出者に控えとして交付する。
ロ 労働者派遣事業の変更の届出と併せて許可証の書換申請が行われたときは、許可証を新たに作
- 94 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
成し、当該変更の届出を受理した労働局を経由して、申請者に、当該申請者が所持していた許可
証と引き換えに交付する。
ハ なお、(1)のイの(力及び②に掲げる事項の変更の届出と併せて許可証の書換申請が行われた
ときは、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じた許可証を新たに作成し、当該事業主が所持し
ていた許可証と引き換えに交付する。
ニ 労働者派遣事業の変更の届出を受理したときは、事業所台帳等につき、所要の補正又は整備を
行う(6参照)。
ホ 事業所の新設に係る届出の受理について
(イ)(1)のイの⑪に掲げる事項の変更の届出を受理したときは、事業主管轄労働局は、事業所
台帳等を補正又は整備するとともに、労働者派遣事業変更届出書の複写及び当該事業所属性に
係る書類に、連絡文を添えて当該変更に係る事業所管轄労働局に送付する。この場合におい
て、当該連絡を受けた事業所管轄労働局は、関係事業所の事業所台帳を補正又は整備するもの
とする。
なお、(1)のイの⑪に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る事業所管轄労
働局に提出される場合もあるが、この場合、当該事業所管轄労働局は、届出書の写し1通及び
事業主属性に係る書類に連絡文を添えて、事業主管轄労働局へ送付する。
(ロ)イの⑪に係る変更の届出を受けた事業主管轄労働局及び事業主管轄労働局より連絡を受けた
事業所管轄労働局(又は届出を受けた事業所管轄労働局と、当該事業所管轄労働局より連絡を
受けた事業主管轄労働局)においては、速やかに法第9条第1項の規定に基づき付した許可条
件(1の(12)参照)に違反していないことについて、イの届出関係書類、実地調査等により
確認し、その結果をイの⑪に掲げる変更の届出を受理した事業主管轄労働局又は事業所管轄労
働局でとりまとめて本省に報告する。
(ハ)また、届出関係書類によって、法第9条第1項の規定に基づき付した条件の⑤労働者派遣事
業を行う事業所を新設する場合においても、「許可基準」の所定の要件を満たすこと、を確認
するとともに、イの⑪に掲げる変更の届出を受理した事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局
でとりまとめて本省に報告する。
この場合、本省において当該新設に係る事業所ごとに許可証を作成するとともに、1の
(12)のハと同様に、労働者派遣事業許可条件通知書を新たに作成し、イの⑫に掲げる変更の
届出を受理した事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局を経由して、当該届出者に交付する。
(ニ)(ハ)の「「許可基準」の所定の要件を満たすこと」の確認に当たって、財産的基礎に関す
る判断に係る許可基準の取扱いは、以下のとおりとする。
a 基準資産額が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所
の数を乗じた額以上であること。
・厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書(様式第
3号)の「3 資産等の状況」欄により確認する。
- 95 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
「繰延資産」とは、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第74条第3項第5号
に規定する繰延資産をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである会社計算規則第
2編第2章第2節の「のれん」をいう。
b aの基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
C 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を
行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
・厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は労働者派遣事業計画書(様式第
3号及び様式第3号-2)の「3 資産等の状況」欄により確認する。
(ホ)職業安定法第45条に規定する厚生労働大臣の許可を受け、労働者供給事業を行う労働組合
等から供給される労働者を対象として、労働者派遣事業を行う派遣元事業主に係る上記(ニ)
の適用については、1の(8)の「許可基準」中二の(イ)のaの(e)のⅤに準じて取り扱
う。
(へ)また、「許可基準」の財産的基礎に関する判断に当たって、基準資産額又は自己名義の現金
・預金の額が増加する旨の申し立てがあった場合の確認書類の取扱いについては、許可の有効
期間の更新手続の公認会計士又は監査法人による「合意された手続業務」を実施した中間決算
又は月次決算による場合でも可能とする。
(ト)なお、1の(12)により付された許可の条件に違反した場合には、法第14条の規定に該当
し、許可の取消し、事業停止命令の対象となる。
4 事業廃止届出手続
(1)労働者派遣事業の廃止の届出
イ 派遣元事業主は、労働者派遣事業を廃止したときは、当該廃止の日の翌日から起算して10 日
以内に、労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて事業主管轄労働局を経て、労
働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)を厚生労働大臣に提出しなければならない(法第13条
第1項、則第10条)。
ロ 労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)は、正本1通及びその写し2通を提出しなければな
らない(則第20条)。
ハ なお、「廃止」とは「休止」とは異なる概念であり、今後事業を行わないことを派遣元事業主
が決定し、現実に行わないこととなったことが必要である。
(2)事業廃止の届出の受理
労働者派遣事業の廃止の届出を受理したときは、労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)の
写し1通を届出者に控えとして交付する。
(3)許可の効力
(1)の届出により、労働者派遣事業の許可はその効力を失う(法第13条第2項)ので、た
とえ許可の有効期間が残っていたとしても、当該廃止の届出の後、再び労働者派遣事業を行おう
- 96 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
とするときは、新たに許可を受け直す必要がある。
5 許可証の取扱い
(1)許可証の備付け及び提示
イ 労働者派遣事業の許可を受けた者は、交付を受けた許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ご
とに備え付けるとともに、関係者(※)から請求があったときは、これを提示しなければならな
い(法第8条第2項)。
当該許可証の備付け及び提示は、労働者派遣契約締結時の許可を受けている旨の明示(法第
26条第3項)とともに、適法に事業活動を行っていることを関係者に知らせるための措置とし
て重要な機能を有するものである。
:※「関係者」の範囲について
「関係者」には、当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けている者若しくは受
!けようとする者、又は当該事業主に雇用されている者若しくは雇用されようとする者等、当該
:事業主が適法に事業活動を行っているか否かにつき利害関係を有すると認められる者の全てを
:含む。
ロ 許可証再交付申請書を受理した事業主管轄労働局及び事業所管轄労働局は、受理した許可申
請関係書類等について、書面に記載漏れがないこと及び記入事項に誤りがないこと等を確認す
ること。
また、事業所管轄労働局は、その提出の都度、当該書類に連絡文を添えて速やかに事業主管轄
労働局へ送付しなければならない。
事業主管轄労働局は、書面に記載漏れがないこと及び記入事項に誤りがないこと等を確認後、
本省に提出すること。
(2)許可証の再交付手続
イ 許可証の交付を受けた者が、許可証を亡失し、又は許可証を滅失したときは、速やかに許可証
再交付申請書(様式第5号)を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けなければならない
(法第8条第3項、則第3条)。
なお、一事業所において許可証を亡失又は滅失した場合には、当該事業所に係る事業所管轄労
働局へ申請を行っても差し支えない(則第19条)。
ロ 「亡失」とは許可証を無くすことであり、「滅失」とは許可証が物理的存在を失うことであ
る。
なお、「毀損」した場合も、その程度が重大なものについては「滅失」したものとして取り扱
うこととして差し支えない。
ハ 当該許可証の再交付手続は、(1)の許可証の備付け及び提示を確実に行うための措置として
機能するものである。
(3)許可証の返納手続
- 97 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
イ 許可証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった
日の翌日から起算して10 日以内に許可証(③の場合には、発見し、又は回復した許可証)を事
業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に返納しなければならない(則第4条第1項、則第8条第3
項、則第10条、則第19条)。ただし、③又は④の場合であって、一事業所に係る許可証を返納
する場合には、当該事実のあった事業所管轄労働局を経て返納することとしても差し支えない
(則第19条)。
① 許可が取り消されたとき(法第14条第1項の規定による。)
② 許可の有効期間が満了したとき(2により許可の有効期間の更新が行われず許可の有効期間
が満了し、許可が失効した場合である。)
③ 許可証の再交付を受けた場合((2)による)において、亡失した許可証を発見し、又は回
復したとき)
④ 労働者派遣事業を行う事業所を廃止したとき(事業所における労働者派遣事業を終了したと
き)
ロ 許可証の交付を受けた者が次のいずれかに該当することとなったときは、それぞれに掲げる者
は当該事実のあった日の翌日から起算して10 日以内に許可証を事業主管轄労働局を経て厚生労
働大臣に返納しなければならない(則第4条第2項、則第19条)。
(力 死亡した場合にあっては、同居の親族又は法定代理人
② 法人が合併により消滅した場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人
の代表者
ハ イ及びロのいずれの場合においても、事業主管轄労働局において当該返納すべきこととなった
事由及び当該事由の発生年月日を確認するとともに、イの(力、②及び④並びにロの場合にあって
は当該事業主の全ての事業所管轄労働局へ、イの③の場合にあっては当該事実のあった事業所を
管轄する労働局へ、届出書の複写を送付する等により連絡するものとする。なお、イの③及び④
に係る届出については、届出に係る事実のあった事業所管轄労働局に提出される場合もあるが、
この場合、当該事業所管轄労働局は、届出書の複写を1部作成して保管するほか、届出書の写し
に連絡文を添えて事業主管轄労働局へ送付する。イ及びロのいずれの場合においても事業所台帳
等については、その旨を記載するとともに労働者派遣事業の廃止の届出があった場合と同様に当
該台帳の保管を行う(6の(4)のロ参照)。
ただし、
(力 死亡した者の同居の親族又は法定代理人が、引き続き事業を実施することを希望する場合
② 合併により消滅する法人が有していた労働者派遣事業を実施する事業所において、合併後存
続し、又は合併により設置された法人が、引き続き労働者派遣事業を実施しようとする場合
等については、8により取扱うこととする。
- 98 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
6 労働者派遣事業所台帳及び労働者派遣事業主台帳の整備等
(1)許可時の対応
労働者派遣事業の許可をしたときは、事業主管轄労働局において各事業所について労働者派遣
事業所台帳及び労働者派遣事業主台帳(以下「事業所台帳等」という。)を作成し、所要の事項
を記載する。
(2)更新時の対応
労働者派遣事業の許可の有効期間の更新をしたときは、事業主管轄労働局は事業所台帳等の作
成、記載を行う。
また、労働者派遣事業の許可の有効期間が更新されなかったときは、事業主管轄労働局は、当
該事業主の事業所台帳等に不更新となった旨の記載を行う。
(3)変更時の対応
イ 労働者派遣事業変更届出書を受理し、1の(11)の二により作成された事業所台帳等の記載事
項に変更が加えられたときは、事業主管轄労働局は、利用の便を考慮して、原則として新たに事
業所台帳等を作成することなく、従来使用した事業所台帳等の関係事項の記載を、その都度、補
正するものとする。
労働者派遣事業の変更の届出を受理したときは、事業所台帳等につき所要の補正又は整備を行
う。
ロ 3の(1)のイの②及び⑦の変更(同一労働局の管轄区域内の変更を除く。)については、当
該変更後の事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局において届出を受理することとなるため、当
該変更届出関係書類が提出されたときは、当該変更前の事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局
に連絡し、管理されていた当該事業主又は事業所に関係する全ての書類を引き継ぐものとする。
ハ 3の(1)のイの⑥から⑲及び⑫に掲げる事項の変更の届出を受理したときは、事業主管轄労
働局は当該変更に係る変更の届出については、当該変更後の事業所管轄労働局へ、事業所属性に
係る書類が添付されている場合においては、あわせて当該事業所管轄労働局へ、当該変更事項を
労働者派遣事業変更届出書の複写を送付する等により連絡するものとする。
なお、3の(1)のイの⑥から⑲及び⑫に係る変更の届出については、当該変更に係る事業所
管轄労働局に提出される場合もあるが、この場合、当該事業所管轄労働局は、届出書の写し1通
及び事業主属性に係る書類に連絡文を添えて、事業主管轄労働局へ送付し、事業主管轄労働局に
おいて事業所台帳等の補正又は整備を行う。
(4)廃止時の対応
イ 労働者派遣事業廃止届を受理したときは、事業主管轄労働局は、当該事業主に係る全ての事業
所管轄労働局へ、届出書の複写を送付する等により連絡するものとする。事業所台帳等について
は当該廃止を行った旨の記載を行う。
ロ 労働者派遣事業の廃止後においても、労働者の権利関係、労働関係に関する紛争の解決、監督
上の必要から当該台帳を別途保存しておくこと((5)参照)。
- 99 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
(5)事業所台帳等の保管
イ 事業所台帳等は、事業主管轄労働局において保管するものとし、利用の便を考慮して労働者派
遣事業、(旧)一般労働者派遣事業、(旧)特定労働者派遣事業別等に適宜分類し、編綴するも
のとする。
ロ 労働者派遣事業、(旧)一般労働者派遣事業の事業所台帳等であって許可の有効期間内のもの
又は経過措置期間中の(旧)特定労働者派遣事業の事業所台帳等については、イにより保管す
る。(旧)一般労働者派遣事業であって許可の有効期間の更新が行われなかったもの又は経過措
置期間以降に労働者派遣事業の許可を申請しなかったもの、若しくは労働者派遣事業、(旧)一
般労働者派遣事業又は(旧)特定労働者派遣事業を廃止した場合の事業所台帳等は別途保管する
ものとする。
ハ 事業所台帳等の保存期限は原則として永年とする。
7 名義貸しの禁止
労働者派遣事業は、欠格事由に該当せず、事業遂行能力、雇用管理能力等について許可基準に照ら
して審査を受けた事業主が自ら行うものでなければ許可制度自体の維持が困難となるため、派遣元事
業主について許可を受けた自分の名義を他人に貸して労働者派遣事業を行わせることが禁止される
(法第15条)。
8 その他
(1)個人事業主が死亡した場合の取扱い
個人事業主が死亡した場合であって、その同居の親族又は法定代理人からその旨が届け出られ
た場合には、当該届出者の責任において、当該事実のあった日現在有効な労働者派遣契約に基づ
く労働者派遣に限り、当該事実のあった日から 30 日間継続しても差し支えないものとする。ま
た、当該期間内に当該事業を継続しようとする者から労働者派遣事業の許可申請がなされた場合
には、その時点で明らかに当該許可申請を許可できないと判断される場合を除き、許可が決定さ
れるまでの間も当該労働者派遣契約に係る労働者派遣を継続実施することを認めて差し支えない
ものとする。なお、この場合、5の(3)のロ、ハの取扱いは行わないものとする。
(2)法人の合併等に際しての取扱い
法人の合併等に際し、消滅する法人(以下「消滅法人」という。)が労働者派遣事業の許可
(以下(2)において単に「許可」という。)を有しており、当該消滅法人の事業所において、
合併後存続する法人(以下「存続法人」という。)又は合併により新たに設立される法人(以下
「新設法人」という。)が引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合等には、通常の許可又は
変更の手続では当該事業の継続的な実施に支障が生じ、派遣労働者の保護に欠けるおそれがある
こと等から、次のとおり取り扱うこととし、許可申請等必要な手続を行うよう指導するものとす
る。
-100 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
イ 吸収合併の場合の取扱い
(イ)合併前に存続法人が許可を受けておらず、かつ、消滅法人が許可を受けている場合であっ
て、合併後に存続法人が労働者派遣事業を行うときは、新規許可申請が必要となる。
この場合、労働者派遣事業の許可の期間に空白が生じることを避けるため、許可申請に当た
っては、例えば合併を議決した株主総会議事録等により合併が確実に行われることを確認する
ことにより、合併の日付と同日付けで許可することが可能となるよう、存続法人において事前
に許可申請を行わせることとする。
その際、合併により、事業開始予定日まで又は事業開始予定日付けで、法人の名称、住所、
代表者、役員、派遣元責任者が変更するときであって、これらについて、許可申請時に合併を
議決した株主総会議事録等により当該変更が確認できるときは、労働者派遣事業許可申請書
(様式第1号)においては、変更後のものを記載させ、変更後直ちに、その内容に違いがなか
った旨を報告させるものとする。
(ロ)合併前に存続法人が許可を受けている場合であって、合併後に存続法人が労働者派遣事業を
行うときは、新規許可申請を行う必要はないが、合併により法人の名称等に変更がある場合に
は、変更の届出を行わせることが必要である。この場合において、合併後の存続法人の事業所
数が、合併前の存続法人の事業所数を超えることとなるときは、事業所の新設に係る届出を行
わせることが必要である。
(ハ)(ロ)の場合において、存続法人及び消滅法人が合併前に許可を受けており、かつ、当該消
滅法人の事業所において、合併後に存続法人が引き続き労働者派遣事業を行うときは、次のと
おりとする。
a 当該合併により、合併後の存続法人の事業所数が、合併前の存続法人及び消滅法人の事業
所数を合算した数以下であるときは、許可基準の特例として、3の(3)のホの(ニ)にか
かわらず、当該事業所の新設をすることができるものとする。
b 当該合併により、合併後の存続法人の事業所数が、合併前の存続法人及び消滅法人の事業
所数を合算した数を超えることとなるときは、3の(3)のホの(ニ)のとおり取り扱う。
ロ 新設合併の場合の取扱い
(イ)新設合併の場合(合併する法人が全て解散し、それと同時に新設法人が成立する場合)に
は、合併後に新設法人が労働者派遣事業を行うときは、新規許可申請が必要となる。
この場合、イの(イ)と同様の手続により事前に許可申請を行わせることとするが、申請時
には新設法人の主体はないため、特例的に合併後の予定に基づいて申請書等を記載させるもの
とし、新設法人の成立後直ちに、その内容に違いがなかった旨を報告させるものとする。
(ロ)なお、全ての消滅法人が合併前に許可を受けており、かつ、当該消滅法人の事業所におい
て、合併後に新設法人が引き続き労働者派遣事業を行うときであっても、財産的基礎に関する
判断に係る許可基準については、通常どおり取り扱うこととする。
ハ 吸収分割の場合の取扱い
-101-
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
既に存在する他の法人に、分割する法人の営業を継承させる吸収分割の場合には、イに準じて
取り扱うものとする。
なお、分割する法人について事業所数等が変更したときは、変更の届出又は事業の廃止の届出
を行わせることが必要である。
ニ 新設分割の場合
分割により新たに創設した法人(以下「分割新設法人」という。)に、分割する法人の営業を
承継させる新設分割(会社法第2条第30号)の場合には、分割する法人が労働者派遣事業の許
可を有している場合であっても、分割新設法人が労働者派遣事業を行う場合は新規許可申請が必
要となり、ロの(イ)及び(ロ)に準じて取り扱うものとする。
なお、分割する法人について事業所数等が変更したときは、変更の届出又は事業の廃止の届出
を行わせることが必要である。
ホ 事業譲渡、譲受の場合の取扱い
ハに準じて取り扱うものとする。
へ 民営職業紹介事業を行う法人と合併する場合の取扱い
労働者派遣事業の許可を有する法人と民営職業紹介事業の許可を有する法人が合併するときで
あって、労働者派遣事業の許可を有する法人が消滅する場合は、合併後、当該法人において労働
者派遣事業の新規許可申請が必要となる。労働者派遣事業の許可を有する法人が存続する場合
は、合併後、当該事業所において新規許可申請を行う必要はないが、合併により法人の名称等が
変更したときは、変更の届出を行わせることが必要である。
ト 許可の有効期間に関する経過措置
平成27年9月29日以前に受けた(旧)一般労働者派遣事業の許可の有効期間は、許可の日か
ら起算して初回の更新については3年、2回目以降の更新については5年である。ただし、
(旧)一般労働者派遣事業は、法施行後は労働者派遣事業として取り扱われる。
-102 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
9 参考一覧表
(1)手数料の納付手続き一覧表
労働者派遣事業の許可申請を行おうとする者に係る手数料の種類は次に掲げるとおりである。
② 手続 ② 手数料 ③ 申請書様式
労働者派遣事業の許可申請
許可手数料
120,000円+55,000円×(労働者派遣事業を行う事 様式第1号
業所の数から一を減じた数)
労働者派遣事業の許可の有効期間の更新 許可有効期間更新手数料
申請 55,000円×(労働者派遣事業を行う事業所の数)
様式第1号
許可証の亡失または滅失の際の許可証の 許可証再交付手数料
再交付申請 許可証1枚につき1,500円
様式第5号
許可証の書換申請 許可証書換手数料
(労働者派遣事業において氏名若しくは 許可証1枚につき 3,000円
名称、所在地、事業所の名称又は事業所
の所在地を変更する場合。)
様式第5号
(2)登録免許税の課税手続き一覧表
登録免許税の通知に係る様式例は次のとおりである。
イ 登録免許税の納付不足額の通知について
年 月 日
○○労働局需給調整事業担当部長
○○税務署長 殿
登録免許税の納付不足額の通知について
登録免許税法第28条第1項の規定により、下記のとおり通知します。
記
1 区 分 労働者派遣事業の許可
2 登録免許税の額
3 未 納 額
4 納 期 限
5 申請者の氏名又は名称
9万円
〇〇円
年 月 日
-103 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
ロ 還付について
年 月 日
○○労働局需給調整事業担当部長
○○税務署長 殿
登録免許税の過誤綿の通知について
登録免許税法第31条第1項の規定により、下記のとおり通知します。
記
1 納 付 額 〇〇円
2 過 誤 綿 の 理 由 登録免許税法第31条第〇項に該当
及び該当することとなった日 年 月 日
3 申請者の氏名又は名称
(3)用語の整理
○ 事業所
「事業所」とは、労働者の勤務する場所又は施設のうち、事業活動が行われる場所のことであ
り、相当の独立性を有するものである。
具体的には雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的には同一であり、次の要件に該当す
るか否かを勘案することによって判断する。
(力 場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。
② 経営(又は業務)単位としてある程度の独立性を有すること。すなわち、人事、経理、経営
(又は業務)上の指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること。
③ 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。
労働者の勤務する場所又は施設が(力、②及び③の全てに該当する場合並びに事業主が法人で
ある場合であってその登記簿上の本店又は支店に該当するときは、もとより、一の事業所とし
て取り扱うものであるが、それ以外の場合であっても、他の社会保険の取扱い等によっては、
一の事業所と認められる場合があるから、実態を把握の上慎重に事業所か否かの判断を行うも
のである。
○ 労働者派遣事業を行う派遣元事業所の判断
事業主が許可を受け、及び届け出る必要があるのは、「事業所」のうち「労働者派遣事業を行
う派遣元事業所」であるが、これについては、次のように判断する。
(イ)実質的に労働者派遣事業の内容となる業務処理の一部又は全部を行っている事業所であるこ
と。
すなわち、派遣労働者に対し派遣就業の指示を行い労働に従事させていると評価できる事業
所であって、具体的には、法第34条の就業条件の明示、派遣労働者に係る労働契約の締結若
-104 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
しくは派遣労働者となろうとする者の登録、派遣労働者に係る雇用管理の実施等の事務の処理
機能を有しているいわば、派遣労働者が帰属する事業所である(場所的に他の(主たる)事業
所から独立している事業所(特に異なった都道府県に所在する事業所)については、このよう
に判断される蓋然性が極めて高くなるので留意すること。)。
労働者派遣事業を行う事業所の事業主が法人である場合の登記簿上の本店又は支店であって
も同様の基準により判断する。
(ロ)なお、(イ)の基準により労働者派遣事業の内容となる業務処理を行っている場所又は施設
が「事業所」に該当しないと認められる場合(そのようなことは通常考えられない。)は、当
該施設が他の労働者派遣事業を行う事業所に附属し労働者派遣事業を行っているものとして取
り扱う。この場合において、事業主が許可を受け及び届け出る必要があるのは、当該「他の労
働者派遣事業を行う事業所」である。
(ハ)派遣労働者の教育訓練のみを行う事業所、派遣労働者の募集のみを行う事業所、派遣先の開
拓のみを行う事業所、労働者派遣事業に係る会計、財務の処理のみを行っている事業所等につ
いては、労働者派遣事業を行う事業所ではないと判断されるものである。
(ニ)(イ)の派遣労働者となろうとする者の登録申込みについて、真に偶発的にこれを受理する
に過ぎない場合には労働者派遣事業の許可を要するものではないが、(ハ)のような業務を行
う事業所については、その事業内容からも、登録申込みの受理を行う場合には業として労働者
派遣事業(の一部)を行っていると解される蓋然性が高く、労働者派遣事業を行う事業所とし
て許可を受け、及び届け出ることが適当である。
また、当該事業所において、登録の申込みの受理が繰り返し行われる場合には、業として労
働者派遣事業(の一部)を行っていると解されるものであることから、労働者派遣事業を行う
事業所としての許可及び届出が必要である。
(ホ)(イ)により、労働者派遣事業を行う事業所と判断した事業所が現実の雇用保険の取扱いに
おいては、事業所非該当施設とされている場合にあっては、雇用保険部門にその旨連絡し、同
一の行政機関が行う「事業所」に関する判断に矛盾が生じない整理を行うこと。
○ 製造の業務
「製造の業務」とは、具体的には、物を溶融、鋳造、加工、又は組み立て、塗装する業務、製
造用機械の操作の業務及びこれらと密接不可分の付随業務として複数の加工・組立て業務を結ぶ
場合の運搬、選別、洗浄等の業務をいう。
したがって、例えば、製品の設計、製図の業務、物を直接加工し、又は組み立てる業務等の工
程に原料、半製品等を搬入する業務、加工、組立て等の完了した製品を運搬、保管、包装する業
務、製造用機械の点検の業務、製品の修理の業務はこれに含まれない。
○ 林業の業務
「林業の業務」とは、造林作業(①地ごしらえ、②植栽、③下刈り、④っる切り、⑤除伐、⑥
枝打、⑦間伐)及び素材(丸太)生産作業(①伐採(伐倒)、②枝払い、③集材、④玉切り(造
材))に分けることができるが、このうち素材(丸太)生産作業については、立木を伐採し、最
終的に丸太という人工物に「加工」するものであり、製造業務に該当するものであること、(力か
ら④までの業務が時間的にも空間的にも連続的・一体的に営まれる業務であることから、素材
(丸太)生産作業の全ての業務が製造業務に該当するもの。
-105 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
また、造林作業の③から⑦までの業務は労働者派遣の対象となるものである(第2の2の
(3)のハ参照)が、これらの業務と素材(丸太)生産作業の業務を同一の派遣労働者が同時に
併せて行う場合は、当該労働者派遣に製造業務が含まれているため、全体として製造業務に該当
するものである。
○ 法人の「役員」
イ 法人の役員とは、おおむね次に掲げる者をいう。
① 株式会社については、代表取締役、取締役(会計参与設置会社である場合は会計参与、監
査役設置会社である場合は監査役、委員会設置会社である場合は執行役)
② 合名会社及び合同会社については、総社員(定款をもって業務を執行する社員を定めた場
合は、当該社員)
③ 合資会社については、総無限責任社員(定款をもって業務を執行する無限責任社員を定め
た場合は、当該無限責任社員)
④ 特例有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87
号)第3条第2項に規定する特例有限会社をいう。)については、取締役、監査役を置いた
場合には監査役
⑤ 一般社団法人及び一般財団法人については、理事及び監事
⑥ 特殊法人、独立行政法人及び地方独立行政法人については、総裁、理事長、副総裁、副理
事長、専務理事、理事、監事等法令により役員として定められている者
口 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協
同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合や組合等登記令(昭和39年政令第29
号)第1条に規定する組合等(以下単に「組合等」という。)のように法律上法人格を与えられ
ているものは、組合等を構成する法人とは独立した別個の法人であり、当該組合等が許可を受け
労働者派遣事業を行う主体となる(JVとの関係については第1の1の(6)参照)。
○ キャリアアップとは
キャリアアップとは、関連した職務経験の連鎖や職業訓練等の能力開発機会を通じ、職業能力
の向上が図られること、また、その先の職業上の地位や賃金等の処遇の向上が図られることをい
う(「非正規雇用労働者の能力開発抜本強化に関する検討会」報告書(平成24年12月 21
日))。
法令上のキャリアアップ措置の義務付けについては、派遣労働者がキャリアアップした成果ま
でを求めるものではないことに留意が必要である。
○ キャリアコンサルティングとは
労働者派遣事業の許可要件における「キャリアコンサルティング」とは、「職業能力開発促進
法(昭和44年法律第64号)第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングのうち労働者の
職業生活の設計に関する相談その他の援助を行うこと」をいう(労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大
臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第391号))。
-106 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
(4)事業主の行う手続の種類
労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る事業主により行われる手続は、次に掲
げるとおりである。
事項 参照箇所 許芸よ票田 条項
許可 1 許可 法第5条第1項
許可証の亡失、滅失による再交付(許可証再交付申
請)
5の(2) 事後申請 法第8条第3項
許可有効期間の更新
2
許可有効期
間の更新
法第10条第2項
事業を行う者の氏名若しくは名称
又は住所、法人の場合その代表者
の氏名
法人の場合その役員の氏名又は住所
労働者派遣事業を行う
事業所の名称又は所在地
派遣元責任者の氏名又は住所
に係る変
更(許可
証書換申
請 を 含
む。)
特定製造業務への労働者派遣の開始・終了
労働者派遣事業を行う事業所の新設(事業所におけ
る事業の開始)
労働者派遣事業を行う事業所の廃止(事業所におけ
る事業の終了)
3事後届出、 法第11条第1項
申請 及び第2項
事業の廃止 4 事後届出 法第13条第1項
許可証の返納 5の(3) 返納 則第4条
事業報告
収支決算書
第5の1 書面提出 法第23条第1項
関係派遣先派遣割合報告書 第5の2 書面提出 法第23条第3項
海外派遣 第5の3 事前届出 法第23条第4項
-107 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
(5)労働者派遣事業関係手続提出書類一覧
労働者派遣事業関係手機提出書類一覧(巾
ロ 司書漁期■¢夏着
ロロ和された土産要件にて申■する
A当分の同曲絶■)
ロ和された資産要件にて錮こ■する
{3年蘭鉛管定檜t U
ロ一可
嚢更の■出
兼帯叩廃止
彙所離散
遭元責僅薯の膣厨
遭元責任著の氏名釘み
.遭元責僅奮
定蝶造婁i誓〓聖頴遭
簑新曲所在地
t一閃の女一種
歪
■ 八代生者を陰く】血氏名Ⅹ膿
のみ
■爪代凛書を脆く〕
表書の氏名翼は投後のみ
表書
一m
名凸■人〕又は名楓 (■Å】
-翻された責産事件ヒ〓上申洩する
凸当分の問の掛t〕
ロ 可旺の遮■
t良止■出
口薗旺■交付
桐別提出後…釧 貼肝mmmm制制
==回書SSSS書け旧旧88回回■■■車■回回書車■■■■車車車
=ニ l北Ⅲ0冊甘lm日日l日日
餃■0■腰書 I Cl0101 1 1 1 101 10
疇人情報蒼正管理規程 ⑳・⑳ ⑳ ▲ ▲ 密
書憬対照表及び■益断l書 l010101010111111111111110
主賓本尊蜜散計算書等 0 0 0 0 0 0
法人勤址定申告■の事し 0 0 0 0 0 0
法人税の納報復蘭書 0 0 0 0 0 0
不■長巾tt書1旺明●(●書削 l¢l el el l l l l l l l l l l⑳l l l l l母
語 銑彙朋又は甜隻脚以下の駄当鶴凱軋芦
番
長I l 円田Ⅷ辞の至緋晴間書労■■問として恥㌧相当する1合音支
払うことを靡刑とする取扱いを規定した悠分
●
考
贅
料
個」 ◎l「砂 ▲ ▲ ⑳
■期1月地勢齢書を労■看瀬遭整地ぬ釣了血み委理由として
解題しないこと喜駁する■軋。また、有期■用瀬遭労働膚濫つい
てもh労機番訳鷹架釣終了抑=労■経勤が存欄しても㍗慮止弁
■書について臥労t毒瀕遭粟釣由終了のみを理由として解11個= 感l⑳ ▲ ▲
しないことを狂する書類。
労後者瀬遭粟的血終了に配する事乱文更l=罰する事項及び濃
法 び解1に闘する事項について散乱.た節分
人
⑳
無期1用瀬遭労畿書叉は有期1馬瀬捌普醐恩掴用膿
属契約期間内に労嶺を漏脚が終了した肴について.次の瀬
遭免を見つけら拙い獣使用書町動こ錆すべき事由品川値l噌診巨⑳l⑳ ▲ ▲
彙させた■会には.労輸基準法第光義に基刊手当車支払う=上
を規定した節分
匂
派遣労畿書のキャリアお戌を含凱こおいた瀕遣先の攫供のための
務手引.マニュアル等又はそ鵬の髄当首断の零し
⑪l唱日日診l▲ ▲ ◎
皿皿…旧…:皿…:
派遣元責任毒血住展鷹府零し
軋遭元貴餐肴の且丘書
派遣元量優甜晋受講E睨書の写し
自己チエ甘ケシ案卜 ⑳ ◎l項目日払l⑳
窃
企粛パンフレット尊書彙内容が確認できるもの膿宜薗後場で作成し
てい机ヽ場合を陰もI
OI C日日コl ▲ ▲
0
労■著名難く申■月由前月末現在〔前月末で檻姓が田酸な1台壮
齢々月末現在)のもので、瀦遭静■著書食む全労嶺書分)
61⑳l l e
法第7集第1項第4号の財産的基譲に闘する要件について缶誓約t O O O
労■薔瀕遭尊貴爵可申掬の当分の問の柵tに肺する甘鴫1用する
拾遺労甘薯致瓜柵こついて
Ol 10
労■薔薦遭真庭許可申■の3年間の℡定槽tに許す引即日開け
る派遣労鼻毛■の報告について
0
蜘…州酬脚脚瑚u l中中小国日日日日日日日日l=∥日日回目∥日日
【1 確、 についてr.正1 し2. 由 ロlについてはへ正1J引J濃覇掛説
亡注2〕0郎仕様也が必蔓なも軌⑳射ますぺて曲事彙断ごとに橿触桐囲瞳も吼血蹄は当膝雷粗に蜜更が加えられた■創このみ提出を翳す与も吼▲酎ままに提出されているものに変更があゥた場合のみ提出妻嘉するも
の。
亡謹3)様式第3号一別ま.濾遭州書のうち.量用昆験叉l娼膿課■虻生年会荏験の未加入書机ヽる亀倉にのみ攫組を蜃す軸であること,
-108 -
第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続
労七着派遣雷果開鮪手鍾提出書類一覧(2)
ロ 可有効期■の蔓f
D和された資産馨l件にて申■する
.A当分の間の緻量】
和された資産要鉢にて申■する
A3年間缶暫定檜t U
n一可
重要の■出
兼帯廃止
ロ 彙H所鰊殴
遭元王優毒の蛙斯
遭元責任書中氏名缶み
辻元一貫饉奮
定饗一定彙露への淳…丑
果断の所轄地
t。的の虫一輝
._一昭佐一臍
■<代表者を除く】の氏名叉臆
のみ
t A代轟書を膝く)
表書の氏名翼は設題のみ
表書
ー閥
名二〓■人∴〓半はi崇敬 A_T人
ロ和された董産一靂縫Hにて申■”すl患
こ更軍の問の籍i二
ロ 可旺の遮■
t良止■出
口可旺薫交什
事1別壕也書濃l榛東書朝
闇抑日
間〓]
圃〓]
圃〓]
圃=㈲目刺田
圃〓]
圃日日]
問
圃〓]
圃日日]
圃〓]
圃日日]
≡Ⅷ 皿.l.仕
断絶咄中軸軋 回中車回日日
==脾 l出拙=l
描出日日
不動産の登能書胡虻欄■旧朗引
国定資産税闊薗慮旺覇●
不動童心豊監事覆K明t樽震断〉 ⑳l匂l⑳
鑑t規照又は静■粟粒の以下由駿当箇諾t零し)
至 芸畏謂票豊謂㌫濫・相射る量鯖重◎窃⑳…
農期1用瀬遭労畿書を労■肴瀕■酎蜘織丁軌童糧由として
解ⅡU軋1ことを旺する書駄また、有期■用瀬鮒後者につい
ても、労■馨瀧並製釣帳了晴に労脚欄していも瀬遭労
嶋書について瞳、労舶巌遭奥釣の終了のみ垂壇由として解題 ⑳l窃l⑳ ▲ ▲
しないことを狂する書類。
鮒肴規遭螢鞄の格了に関する事軋蜜王に闘する事項及び及
び解■に嗣する事項について儒定した節分
t
属
●
肴
貰
科
人 無期量用瀬遭労蜘又は有期1用瀬遭労■書であるが卦齢1
用契約期間内に労■書漏遭契約が終了した書につLlて.攻の瀬
遭先を見つけられ釦ヽ獣使用書の鄭=網すべき事由によ明に 日払l◎l⑳l ▲ ▲
無弛蛙丑朗こ臥労■基準法鴬2白鳥に基づ梓彗童支払う=上
を規定した醜分
濱遺労銀薯憫キャリ7形成婁念頭に翻.1た瀬遣先の提供のための
事務手引.マニユ7ル竃又はその軋罫の駄当笛新の零し
⑳l項目=診l▲ ▲
派遭元■色香切磋題意由暮し ・⑳l噛l⑳
漏遭元暮著者血履歴書 ⑳llのI.⑳
液遭元量饉書講習受講旺曝書の零し ⑧l窃l⑳l⑳l⑳
日加ウトト 回中車何日目
二二
企食パンフレツ尊書稟内容が確毘できももの服立薗後場で作成し
てしない場合 隆.〉
労■書名簿亡申■月の前月末老荘【前月末で杷■が田■な■鋸は
々月末現在畑もめで、駕遭労像香を含む全労貴著分〉
歳第7粂第1環欝4号の財産的基礎に現すも要件についての誓約後
日日日日日日日
労■看瀬遭事ま餅可申釣の当分ぬ問の播tに随する常疇1用する
濱遭労■暑教職について
労■書乱封は鼎可申h心8年閑の暫定静tに嗣する粛鴫1用す
源遭粛然毒■硝昔について
t規劇l労儀基準監t事の受遷印があ囲零し1
回回回回回書書
目川日日日間日
日l=∥日日回目日日日
日川∥日日廿日日日
日用∥日日廿日日日
⑳l l l l l Q
旬
窃
㊨
窃
el l⑰l命
el l l O
elll命
∥l=∥日日回目日日日
日日日日日0日目日日
R[RRRRRRRR
∥l=∥日日回目∥日日
1 f. についてl、正1、 についてl、正1、 1で 。
注2 0印瞳提出が腰なもめ、◎印はすべて缶書共新ごとに擾出が庭草な 仇A印吐当俵書類に餐更が加えられた壌部この舟場出を璽するも軌▲卸はEに棲出されているも曲に変更があゥた■奮のみ攫出重要するも
の.
腫3〕様式第3号-3臥減量測軸うち、量用搬又吐農事保険・■生年会保険血未加入書がいも場合にのみ攫也を蜃するも缶であること。
-109 -
第4 (旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置
第4 (旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置
1 経過措置に関する概要
(1)(旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置
イ 平成27年9月 30 日から(旧)一般労働者派遣事業及び(旧)特定労働者派遣事業は廃止と
なり、労働者派遣事業の実施を希望するすべての事業主は、厚生労働大臣に「労働者派遣事
業」の許可を受けなければならないこととされたところである。
当該改正の経過措置として、(旧)特定労働者派遣事業を行うため平成27年9月 29 日まで
に厚生労働大臣に対して届出書(以下「(旧)特定労働者派遣事業届出書」という。)を提出
した者は、平成27年9月30 日から平成30年9月29 日までの3年間(当該期間内に改正法附
則第6条第4項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられたとき、又は法第13条第1項の
規定により労働者派遣事業を廃止した旨の届出をしたときは、当該廃止を命じられた日又は当
該届出をした日までの間)(以下「経過措置期間」という。)、(旧)特定労働者派遣事業を
行っていた事業主は引き続き「その事業が「常時雇用される労働者」(※)のみである労働者
派遣事業」を行うことができる(改正法附則第6条第1項)とされたところである。
※ 常時雇用される労働者とは
「常時雇用される労働者」とは、労働契約の形式の如何を問わず、事実上期間の定め
なく雇用されている労働者のことをいう。
具体的には、次のいずれかに該当する場合に限り「常時雇用される労働者」に該当す
る。
(イ)期間の定めなく雇用されている者
(ロ)一定の期間(例えば、2箇月、6箇月等)を定めて雇用されている者であって、
その雇用期間が反復継続されて事実上(イ)と同等と認められる者。すなわち、過
去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用の時から1年を超
えて引き続き雇用されると見込まれる者
(ハ)日日雇用される者であって、雇用契約が日日更新されて事実上(イ)と同等と認
められる者。すなわち、(ロ)の場合と同じく、過去1年を超える期間について引
き続き雇用されている者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込
まれる者
なお、雇用保険の被保険者とは判断されないパートタイム労働者であっても、(イ)
から(ハ)までのいずれかに該当すれば「常時雇用される」と判断するものであるので
留意すること。
-110 -
第4 (旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置
ロ 経過措置期間中は、(旧)特定労働者派遣事業に係る変更の届出については労働者派遣事業
を行う事業所の新設の届出を除く事項の変更の届出を行うことができる。
(旧)特定労働者派遣事業を事業主の主たる事業所以外の事業所で労働者派遣事業を行うた
め事業所の新設を希望する場合については、厚生労働大臣から当該事業所での労働者派遣事業
の許可を受けなければならない。(改正法附則第6条第2項)
ハ 経過措置期間の経過後は、厚生労働大臣から労働者派遣事業の許可を受けなければ労働者派
遣事業を行うことはできない。
なお、平成30年9月 29 日までに厚生労働大臣に労働者派遣事業の許可の申請をした場合に
おいて、平成30年9月 30 日を過ぎてもその申請について許可又は不許可の処分がある日まで
の間は、引き続き常時雇用される労働者のみを派遣する労働者派遣事業を行うことができる。
(改正法附則第6条第1項)
(旧)特定労働者派遣事業を行う事業主は、経過措置期間においても、施行日前に締結した
労働者派遣契約に基づく期間制限に関する規定といった経過措置が置かれたもの以外の事項
(法第30条の2第1項の段階的かつ体系的な教育訓練の実施等)については、労働者派遣事業
を実施する事業主と同様に改正法による改正後の法の規定が適用される。
他方、許可基準である、無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇
できる旨の規定がないこと、また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に
労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇
できる旨の規定がないことや派遣元責任者が許可の受理の目前3年以内に派遣元責任者講習を
受講していること等については、経過措置期間の経過後に労働者派遣事業を実施する意思がな
い事業主であっても、経過措置期間中は労働者派遣事業を実施するのであれば、法に規定され
る義務ではないものの、遅滞なくこれらの体制を整えることが望ましい。
ホ (旧)特定労働者派遣事業を行う事業主は、変更の届出として義務付けられた内容を除き、
ニの内容を追加、変更した事業計画書を再提出する必要はない。
しかし、法第30条の2第1項の規定に基づき派遣元事業主が実施する教育訓練及び同条第2
項の規定に基づき派遣元事業主が実施する相談の機会の確保その他の援助(以下「キャリアア
ップ措置」という。)については、キャリアコンサルティングの担当者の配置状況、キャリア
コンサルティングの実施状況、キャリアアップに資する教育訓練の実施状況等について、労働
者派遣事業の事業主と同様に法の規定に基づき実施していることを、労働者派遣事業報告によ
って報告しなければならない。
労働者派遣事業報告によって、キャリアアップに資する教育訓練等が実施されていない等の
状況を確認した場合、都道府県労働局等による指導等が行われることもあること。
ヘ ロの届出については、届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付され
ていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合、都道府県労働
-111-
第4 (旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置
局において受理が行われる。
(2)(旧)特定労働者派遣事業の欠格事由
(旧)特定労働者派遣事業の欠格事由は、労働者派遣事業の許可の欠格事由と同様である(第
3の1の(7)の「許可の欠格事由」参照)。
(旧)特定労働者派遣事業の欠格事由に該当しないこととして(旧)特定労働者派遣事業の届
出を行い事業を開始した者が、経過措置期間中に(旧)特定労働者派遣事業の欠格事由に該当す
ると判明したときは、当該労働者派遣事業の廃止を命ずることとなる(法第6条各項(第4号か
ら第7号までを除く。)、改正法附則第4条、改正法附則第6条第4項。)。
(3)書類の備付け等
イ 概要
(旧)特定労働者派遣事業を行う事業主は、(旧)特定労働者派遣事業届出書を提出した旨
その他の事項を記載した書類を、(旧)特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けると
ともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない(改正法附則第6条第3
項)。
当該事業主は、労働者派遣事業を実施する事業主とは異なり「許可証」が交付されていない
ことから、当該書類の備付け及び提示によって適法に事業活動を行っていることを関係者に知
らせるための措置である。
※「関係者」の範囲について
「関係者」には、当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けている者若し
くは受けようとする者、又は当該事業主に雇用されている者若しくは雇用されようとす
る者等、当該事業主が適法に事業活動を行っているか否かにつき利害関係を有すると認
められる者の全てを含む。
ロ (旧)特定労働者派遣事業届出書を提出した旨その他の事項を記載した書類
(イ)「その他の事項」は次に掲げるものとする。
(力 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
② 事業所の名称及び所在地
(ロ)当該書類については新たに所定の事項を記載、作成したものであることを要件としている
わけではなく、所定の事項が記載されていればいかなる様式によっても、また複数の書類に
よってもその要件を満たすものであれば足りるものである。このため、当該書類の備付け及
び提示について、(旧)特定労働者派遣事業届出書の写し及び法第11条第1項前段の規定
による変更の届出を行った場合には、当該届出により交付される書類の複写によって行って
も差し支えない。
(ハ) 書面によらず電磁的記録により当該書類の作成を行う場合は、電子計算機に備えられたフ
ー112 -
第4 (旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置
アイルに記録する方法又は磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法によ
り一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)を
もって調製する方法により作成を行わなければならない。
また、書面によらず電磁的記録により当該書類の備付けを行う場合は、次のいずれかの方
法によって行った上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直
ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作
成できるようにしなければならない。
a 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調
製するファイルにより保存する方法
b 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み
取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調
製するファイルにより保存する方法
さらに、電磁的記録により当該書類の備付けをしている場合において、当該書類の提示を
行うときは、当該事業所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該電磁的記録に
記録された事項を出力した書類により行わなければならない。
2 経過措置に関する変更の届出手続
(1)(旧)特定労働者派遣事業の変更の届出
イ (旧)特定労働者派遣事業を行う事業主が次に掲げる事項を変更したときは、事業主管轄労
働局を経て、厚生労働大臣に対して、変更の届出をしなければならない。
なお、事業所の新設を除き、取扱いは労働者派遣事業における変更の届出と同様の取扱いで
ある。
ただし、事業所における次の⑥から⑪までに掲げる事項の変更のみを届け出るときは、当該
変更後の事業所管轄労働局へ届出を行うことも差し支えない(改正法附則第6条第2項)。
なお、事業所の所在地が変更になった場合については、当該事業所管轄労働局において管理
していた書類に連絡文を添えて新たな事業所の所在地を管轄する労働局に引き継ぐこと。
(力 氏名又は名称
② 住所
③ 代表者の氏名
④ 役員(代表者を除く。)の氏名
⑤ 役員の住所
⑥ (旧)特定労働者派遣事業を行う事業所の名称
⑦ (旧)特定労働者派遣事業を行う事業所の所在地
⑧ (旧)特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名
⑨ (旧)特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所
-113 -
第4 (旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置
⑲ (旧)特定労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務(第3の1の(2)のイ参
照)への労働者派遣の開始・終了
⑪ (旧)特定労働者派遣事業を行う事業所の廃止(事業所における特定労働者派遣事業の終
了)
ロ 届出期日
イの①から⑪まで(⑧及び⑨並びに変更に伴い届出関係書類として登記事項証明書を添付す
る場合を除く。)の変更の届出は、当該変更に係る事項のあった日の翌日から起算して10 日
以内に、派遣元責任者を選任した場合におけるイの⑧及び⑨並びに変更に伴い届出関係書類と
して登記事項証明書を添付する場合の変更の届出については当該変更に係る事項のあった日の
翌日から起算して30 日以内に、(2)に掲げるイからルまでの区分に応じた変更届出関係書
類を事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に提出することにより行う(法第11条第2項、
則第8条第1項)。なお、イの②及び⑦の変更(同一労働局の管轄区域内の変更を除く。)の
場合は、事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局とは、変更後のものをいうものである。
また、イの②、⑤、⑦及び⑨の事項について、単に市町村合併や住居番号の変更により住所
又は所在地に変更が生じた場合には、当該変更に係る変更届出書を提出することを要しない。
なお、単に市町村合併や住居番号の変更による変更届出が行われた場合、届出に当たっては各
自治体から無料で交付される住所(所在地)表示変更証明書を添付するよう指導すること。
(2)変更届出関係書類
労働者派遣事業の変更届出関係書類は、(1)のイの(力から⑪までに掲げる変更された事項の区
分に応じ、当該事項に係る次のイからルまでに掲げる書類とする(則第8条第2項から第4項)。
イ 氏名又は名称の変更
(イ)法人の場合(名称の変更)
a 労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
b 定款又は寄附行為
C 登記事項証明書
(ロ)個人の場合(氏名の変更)
a 労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
b 住民票の写し及び履歴書
口 住所
(イ)法人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
b 定款又は寄附行為(ただし、法人の所在地に変更が加えられた場合に限る。)
C 登記事項証明書
(ロ)個人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
-114 -
第4 (旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置
b 住民票の写し及び履歴書
ハ 代表者の氏名(法人の場合のみ)
(イ)労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)登記事項証明書
(ハ)代表者の住民票の写し及び履歴書(氏名又は役職のみの変更の場合、不要。)
(ニ)代表者が未成年者の場合は、第3の1の(5)のイの(イ)のfに定める書類
二 役員(代表者を除く。)の氏名(法人の場合のみ)
(イ)労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)登記事項証明書
(ハ)役員の住民票の写し及び履歴書(氏名又は役職のみの変更の場合、不要。)
(ニ)役員が未成年者の場合は、第3の1の(5)のイの(イ)のfに定める書類
ホ 役員の住所(法人の場合のみ)
(イ)労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)登記事項証明書(代表者を除く役員の変更の場合、不要)
(ハ)役員の住民票の写し
へ 労働者派遣事業を行う事業所の名称
(イ)法人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
b 定款又は寄附行為(事業所の名称の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。)
C 登記事項証明書(事業所の名称の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。)
(ロ)個人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
ト 労働者派遣事業を行う事業所の所在地
(イ)法人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
b 定款又は寄附行為(事業所の所在地の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。)
C 登記事項証明書(事業所の所在地の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。)
d 事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契
約書の写し)
(ロ)個人の場合
a 労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
b 事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契
約書の写し)
チ 労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了(法人・個人
の場合共通)
-115 -
第4 (旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置
(イ)労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
リ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名(法人・個人の場合共通)
(イ)労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書(氏名のみの変更の場合、不要。派遣元事業主が
複数の事業所において労働者派遣事業を行っている場合において、他の労働者派遣事業を行
う事業所の派遣元責任者を異動させ、変更の届出に係る事業所の派遣元責任者として引き続
き選任するときは、履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写
し及び履歴書)を添付することを要しない。)
ヌ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所(法人・個人の場合共通)
(イ)労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)派遣元責任者の住民票の写し
ル (旧)特定労働者派遣事業を行う事業所の廃止(様式第5号)(事業所における(旧)特定労
働者派遣事業の終了)(個人・法人の場合共通)
(3)他局に移管した場合の受理番号関係
イ 経過措置期間中においては、既に付与された事業主固有の届出受理番号を引き続き使用するこ
と。この場合、当該届出受理番号はその後、事業主の住所の変更等により事業主管轄労働局が変
更される場合を除き、新規に付与又は変更されることはないこと。
ロ 経過措置期間中において、事業主の住所の変更等により事業主管轄労働局が変更される場合、
届出者への通知書には、当該届出受理番号を必ず記載すること。
ハ 届出受理番号は、経過措置期間の経過後は使用できない。
(4)(旧)特定労働者派遣事業届出受理番号の設定について
イ (旧)特定労働者派遣事業である旨の表示
「特」の文字をもって表す。
ロ 都道府県番号
労働保険機械事務手引の「都道府県コード表」に定める2桁の数字で表す。例えば、鹿児島は
「46」と表す。
ハ 事業主の一連番号
管轄労働局ごとに6桁の数字をもって表すものとし、原則として届出時期の早い事業主から起
番する。
(具体例)
特 01-500037 - 事業主の一連番号(000001~999999)
」」
都道府県番号(01~47)
(旧)特定労働者派遣事業であることの表示
-116 -
第4 (旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置
(5)労働者派遣事業変更届出書の受理
イ 労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)の備考欄に届出受理番号及び届出受理年月日を記載
するとともに、当該写しに次の記載例により労働者派遣事業変更届出書が受理された旨を記載し、
当該写しそれぞれ1通を届出者に対して控えとして交付する。
〔記 載 例〕
年 月
る法律等
行う労働
理年月日
一派よ
の者に
閥獅凋
藤
間
に
包
の確保及び派遣労働者の保護等に関す
号)附則第6条第1項の規定に基づき
ヽl
ては、上記、届出受理番号、届出受
ロ 1の(2)の欠格事由に該当していることにより、届出者に係る届出書を受理できない場合は
次の様式により、(旧)特定労働者派遣事業の変更の届出が受理できない旨の書面を作成し、当
該届出者に対して交付する。
(日本工業規格A列4)
年 月 日
厚 生 労 働 大 臣 印
殿
年 月 日付けの「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第1項の規
定に基づき行う労働者派遣事業に係る事業主」に係る届出者については、事業開始の欠格
事由(法第6条第 号)に該当し、かつ、当該届出書の内容が法第61条第1号の虚偽の記
載に該当することが、明らかであるため受理できない。
このため、労働者派遣事業を行うためには、当該欠格事由が解消された後、改めて、法
第5条に基づく労働者派遣事業の許可を受けることが必要である。
3 事業主の行う事業廃止の届出手続
(1)(旧)特定労働者派遣事業の廃止の届出
イ (旧)特定派遣元事業主は、(旧)特定労働者派遣事業を廃止したときは、当該廃止の日の
翌日から起算して10 日以内に、事業主管轄労働局を経て、労働者派遣事業廃止届出書(様式第
8号)を厚生労働大臣に提出しなければならない(法第13条、則第19条)。
-117 -
第4 (旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置
口 労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)は、正本1通及びその写し2通を提出しなければ
ならない(則第20条)。
ハ なお、「廃止」とは「休止」とは異なる概念であり、今後事業を行わないことを派遣元事業
主が決定し、現実に行わないこととなったことが必要である。
(2)事業廃止の届出の受理
(旧)特定労働者派遣事業の廃止の届出を受理したときは、労働者派遣事業廃止届出書(様式第
8号)の写し1通を届出者に控えとして交付する(第3の4の(2)参照)。
(3)届出の効力
(1)の届出により、(旧)特定労働者派遣事業は行うことができなくなる。
4 (l日)特定労働者派遣事業所台帳等の整備等
(旧)特定労働者派遣事業については、既に作成している(旧)特定労働者派遣事業所台帳又は
(旧)特定派遣元事業主台帳(第4において「(旧)特定労働者事業所台帳等」という。)によって
管理すること。なお、(旧)特定労働者事業所台帳等の保存期間は永年とする。
イ 2(1)の(旧)特定労働者派遣事業の変更の届出を受理したときは、(旧)特定労働者派遣
事業所台帳等につき所要の補正又は整備を行う(第3の5参照)。
ロ 2(1)のイの②及び⑦の変更(同一労働局の管轄区域内の変更を除く。)については、当該
変更後の管轄労働局において届出を受理することとなるため、当該変更届出関係書類が提出され
たときは、当該変更前の管轄労働局に連絡し、管理されていた当該事業主又は事業所に関係する
全ての書類を引き継ぐものとする。
ハ 2(1)のイの⑥から⑪に掲げる事項の変更の届出を受理したときは、事業主管轄労働局は当
該変更に係る事業所管轄労働局へ、当該変更事項を(旧)特定労働者派遣事業変更届出書の複写
及び事業所属性に係る書類に通知文を添えて当該事業所管轄労働局に送付する。
なお、2(1)のイの⑥から⑪に係る変更の届出については、当該変更に係る事業所管轄労働
局に提出される場合もあるが、この場合、当該事業所管轄労働局は、届出書の写し1通及び事業
主属性に係る書類(①(旧)特定労働者派遣事業計画書、②個人情報適正管理規程、③事業所の
使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)④
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書、⑤ ①~④に付随する書類)に連絡文を添えて、事業
主管轄労働局へ送付し、事業主管轄労働局において事業所台帳等の補正又は整備を行う。
ニ 本届出に係る事業所台帳の整備については、労働者派遣事業所台帳又は派遣元事業主台帳と同
様である。
5 名義貸しの禁止
経過措置期間中の(旧)特定労働者派遣事業につき、名義貸しが行われることとなれば欠格事由に
該当する者が労働者派遣事業を行う等、適法な労働者派遣事業の制度の維持が困難となる。
-118 -
第4 (旧)特定労働者派遣事業に係る経過措置
このため、自分の名義を他人に貸して、当該他人に経過措置期間中の(旧)特定労働者派遣事業を
行わせることが禁止される(法第15条、第13の1参照)。
6 その他
個人事業主が死亡した場合の取扱い、法人の合併等に際しての取扱いについては、第3の8に準じ
て行うものとする。
-119 -
第5 事業報告等
第5 事業報告等
1 事業報告書、収支決算書
労働者派遣事業を労働力需給調整システムとして適正に機能させていくためには労働者派遣事業
の労働力需給調整機能や当該事業の派遣労働者の就業実態等、事業運営の状況を的確に把握し、派
遣労働者の保護及び雇用の安定を図り、必要な行政措置を講じていく必要がある。
派遣元事業主は、毎事業年度における労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る労働者
派遣事業報告書(様式第11号)(以下「事業報告書」という。)及び労働者派遣事業収支決算書
(様式第12号)(以下「収支決算書」という。)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならな
い(法第23条第1項及び第2項、則第17条、則第19条)こととしている。
(1)事業報告書
事業報告書は、各派遣元事業主の事業所ごとの毎事業年度における業務の運営状況(以下
「年度報告」という。)及び毎年6月1日現在の業務の運営状況(以下「6月1日現在の状況
報告」という。)の2つの内容について、厚生労働大臣に報告を求めているものである。
報告内容としては、以下のとおりとしている。また、法第30条の4第1項の労使協定を締結
した派遣元事業主は、事業報告書に当該協定を添付しなければならない。
イ 年度報告については、派遣元事業主における事業年度(事業主ごとに定められた決算期に
基づく。)の事業報告であって、派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の
数、労働者派遣に関する料金・賃金の額、労働者派遣事業の売上高、キャリアアップに資す
る教育訓練の実施状況等としている。
ロ 6月1日現在の状況報告については、毎年の6月1日現在の派遣労働者が従事する業務別
の派遣労働者の数等の状況としている。
ハ 記載方法
事業報告書は、様式第11号の「記載要領」に基づき記載すること。
ニ 提出部数等
派遣元事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとに事業報告書を作成し、とりまとめの
上、正本1通及びその写し2通について、事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出しな
ければならない(則第20条)。
事業主管轄労働局は、派遣元事業主から提出された事業報告書について記載事項に不備が
ないことを確認の上受理し、正本1通を本省に送達すると共に、そのうち1通を提出者に控
えとして交付する。
ホ 提出期限
事業報告書の提出期限は、派遣元事業主の事業年度の終了の日の属する月の翌月以後最初
の毎年6月30日とする(則第17条第3項第1号)。したがって、例えば、事業年度が6月に
終了する派遣元事業主については、α年6月30日までに提出すべき事業報告書は、α-1年
-120 -
第5 事業報告等
6月に終了した事業年度についての事業報告を提出することになる。
(2)収支決算書
収支決算書は、派遣元事業主の報告対象事業年度における資産等の状況及び労働者派遣事業
に係る売り上げ等の状況について厚生労働大臣に報告を求めているものである。
報告内容としては、報告対象事業年度末における資産等の状況及び労働者派遣事業に係る売
上高等としており、以下に留意すること。
イ 派遣元事業主が法人である場合
収支決算書の記載に代えて、報告対象事業年度における確定した決算の貸借対照表及び損
益計算書を添付することとしても差し支えない。
なお、損益計算書については、可能な限り事業区分単位(セグメント)による記載となっ
ており、労働者派遣事業に係る売上額が確認できる状況が望ましいこと。
ロ 派遣元事業主が個人事業主である場合
個人事業主で青色申告をしている場合(記載事項の簡易な損益計算書を作成する場合を除
く。)には、収支決算書の記載に代えて、報告対象事業年度に係る貸借対照表及び損益計算
書(税務署に提出したもの。所得税青色申告決算書(一般用)中に貸借対照表及び損益計算
書が記載されている。)を添付することとしても差し支えない。
なお、損益計算書については、可能な限り事業区分単位(セグメント)による記載となっ
ており、労働者派遣事業に係る売上額が確認できる状況が望ましいこと。
ハ 派遣元事業主が労働者派遣事業以外の事業と兼業する場合等において、収支決算書につい
ては、事業区分単位(セグメント)による記載となっており、労働者派遣事業に係る内容の
確認をできる状況が望ましいこと。ただし、事業区分単位(セグメント)の決算としていな
い場合やその把握が困難な場合等については事業全体の収支の状況を記載することとして差
し支えない。
なお、記載に代えて、貸借対照表及び損益計算書を提出することとした場合も同様とす
る。
ニ 記載方法
収支決算書は、様式第12号の「記載要領」に基づき記載すること。
ホ 提出部数等
派遣元事業主は、作成した収支決算書について、正本1通及びその写し2通について、事
業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。(則第20条)。
なお、記載に代えて、貸借対照表及び損益計算書を提出することとした場合も同様とす
る。
事業主管轄労働局は、派遣元事業主から提出された収支決算書について記載事項に不備が
ないことを確認の上受理し、正本1通を本省に送達すると共に、そのうち1通を提出者に控
えとして交付する。
-121-
第5 事業報告等
へ 提出期限
収支決算書の提出期限は、派遣元事業主の事業年度経過後3箇月以内とする(則第17条第
3項第1号)。
2 関係派遣先に対する労働者派遣の制限等
グループ企業内での派遣は、これが全て否定されるものではないが、グループ企業内の派遣会社
がグループ企業内派遣ばかりを行うとすれば、派遣会社がグループ企業内の第二人事部的なものと
して位置付けられていると評価され、労働力需給調整システムとして位置付けられた労働者派遣事
業制度の趣旨に鑑みて適切ではない。
そのため、派遣元事業主が労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下と
なるようにしなければならない(法第23条の2)。
(1)「関係派遣先」の範国
関係派遣先の範囲は、次のとおりである(則第18条の3第1項から第3項まで)。
イ 派遣元事業主が連結財務諸表を作成しているグループ企業に属している場合
(力 派遣元事業主を連結子会社とする者(いわゆる親会社)
② 派遣元事業主を連結子会社とする者の連結子会社(いわゆる親会社の連結子会社)
(イ)連結子会社とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大
蔵省令第28号)第2条第4号に規定する連結子会社をいうこと。
(ロ)連結子会社の範囲は、当該派遣元事業主が属しているグループ企業が選択している会
計基準により判断されるものであり、例えば、連結財務諸表に関する会計基準(企業会
計基準委員会が作成している企業会計基準第22号)を選択している場合において、親会
社と子会社が一体となって他の会社を支配している場合、子会社一社で他の会社を支配
している場合等(連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用
指針(企業会計基準適用指針第22号)を参照)には、当該他の会社は親会社の子会社と
みなされること。
ロ 派遣元事業主が連結財務諸表を作成していないグループ企業に属している場合
(力 派遣元事業主の親会社等
(イ)「親会社等」とは、派遣元事業主(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数
を所有している者、派遣元事業主(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定
する持分会社(以下「持分会社」という。)である場合に限る。)の資本金の過半数を
出資している者又は派遣元事業主の事業の方針の決定に関してこれらと同等以上の支配
力を有すると認められる者をいうこと。
(ロ)「派遣元事業主の事業の方針の決定に関してこれらと同等以上の支配力を有すると認
められる者」とは、一般社団法人や事業協同組合等のように、議決権や出資金という概
念では支配関係の有無を判断できない者のことを指しており、連結範囲の決定に用いる
-122 -
第5 事業報告等
実質支配力基準を指しているものではないこと。例えば、派遣元事業主が一般社団法人
であり、当該一般社団法人の社員が各1個の議決権を有する場合であって、当該社員の
過半数の議決権の行使に関する意思決定を実質的に支配している者が存在する場合、当
該支配している者が「派遣元事業主の事業の方針の決定に関してこれらと同等以上の支
配力を有すると認められる者」に該当すること。
② 派遣元事業主の親会社等の子会社等
(イ)「子会社等」とは、派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者(株
式会社である場合に限る。)、派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資してい
る者(持分会社である場合に限る。)又は事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親
会社等の支配力がこれらと同等以上と認められる者をいうこと。
(ロ)「事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力がこれらと同等以上と
認められる者」の考え方は、(力の(ロ)と同様であること。
(2)「派遣割合」の算出方法
イ 関係派遣先への派遣割合は、一の事業年度における派遣元事業主が雇用する派遣労働者
(60歳以上の定年退職者を除く。)の関係派遣先での派遣就業に係る総労働時間を、当該事
業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の全ての派遣就業に係る総労働時間
で除すことにより算出すること。なお、百分率(%)表記にした場合に、小数点以下一位未
満の端数が生じた場合には、これを切り捨てること(則第18条の3第4項)。
ロ 「60歳以上の定年退職者」とは、60歳以上の定年年齢に達した者のことをいい、継続雇用
(勤務延長・再雇用)の終了の後に離職した者(再雇用による労働契約期間満了前に離職し
た者等を含む。)や、継続雇用中の者のような60歳以上の定年退職者と同等の者も含まれる
こと。また、グループ企業内の退職者に限られるものではないこと。
ハ 「60歳以上の定年退職者」であることの確認は、労働基準法第22条第1項の退職証明、雇
用保険法施行規則第16条の離職証明書等により行うが、書類による確認が困難である場合に
は労働者本人からの申告によることでも差し支えない。ただし、申告を受ける際には、本人
からの誓約書等の書面によることが望ましい。
ニ 事業年度中に関係派遣先の範囲に変更があった場合には、当該変更があった時点から起算
して関係派遣先への派遣割合を計算することを基本とするが、決算書類に基づき前々事業年
度末(前事業年度開始時点)又は前事業年度末(当事業年度開始時点)におけるグループ企
業の範囲を前事業年度における関係派遣先の範囲とした上で、関係派遣先への派遣割合を計
算することも可能とすること。ただし、その場合には、関係派遣先派遣割合報告書(様式第
12号-2)(表面)の余白に、「前々事業年度末(又は前事業年度末)のグループ企業の範囲
を前事業年度における関係派遣先の範囲とした」旨を記載すること。
(3)報告の方法等
イ 派遣元事業主は、関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2)については、上記
-123 -
第5 事業報告等
(1)、(2)及び様式第12-2の「記載要領」に基づき記載すること。
ロ 提出期限
関係派遣先割合報告書の提出期限は、派遣元事業主の事業年度経過後3箇月以内とする
(則第17条の2)。
ハ 提出部数等
派遣元事業主は、作成した関係派遣先派遣割合報告書について、正本1通及びその写し2
通について、事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。(則第20
条)。
事業主管轄労働局は、派遣元事業主から提出された関係派遣先派遣割合報告書について記
載事項に不備がないことを確認の上受理し、正本1通を本省に送達すると共に、そのうち1
通を提出者に控えとして交付する。
3 海外派遣の届出
海外派遣については、派遣先に対しては国内法が適用されず、法の規定のみによっては、派遣労
働者の適正な就業の確保が困難であるため、派遣元事業主には事前に届出を行わせ(法第23条第4
項)、労働者派遣契約の締結時において講ずべき措置(法第26条第3項)の規定と相まって海外派
遣に係る派遣労働者の保護を図ることとしている。
(1)法第23条第4項に規定する「海外派遣」の概要
法第23条第4項に規定する海外派遣は「この法律の施行地外の地域に所在する事業所その他
の施設において就業させるための労働者派遣」をいうものである。
したがって海外の事業所その他の施設において指揮命令を受け派遣労働者を就業させること
を目的とする限り、海外に所在する法人又は個人である場合はもとより、派遣先が国内に所在
する法人又は個人である場合において、当該派遣先の海外支店等において就業させるときもこ
れに該当する。
なお、派遣就業の場所が一時的に国外となる場合であったとしても出張等の形態により業務
が遂行される場合、すなわち、主として指揮命令を行う者が日本国内におり、その業務が国内
に所在する事業所の責任により当該事業所に帰属して行われている場合は、法の派遣先の講ず
べき措置等の規定が直接当該派遣先に適用され、ここにおける「海外派遣」には該当しないも
のであるので特に留意すること。
また、派遣先が国内に所在する法人又は個人である場合における当該派遣先の海外の事業所
その他の施設において就業する労働者派遣であって、当該労働者派遣の期間がおおむね1箇月
を超えないものについては、「海外派遣」には該当せず、当該届出を要しないものとして取り
扱って差し支えない。
(2)届出の方法
イ 海外派遣の届出は、海外派遣をしようとするときに、あらかじめ、海外派遣届出書(様式
-124 -
第5 事業報告等
第13号)を厚生労働大臣に提出することにより行う。
また、提出に当たっては、法第41条の派遣先責任者等の規定について、その書面の写しを
添付しなければならない(法26条第2項、法第41条、法第42条第1項及び第3項、則第18
条、則第19条、則第23条、則第24条)。
ロ 海外派遣届出書については正本1通及びその写し2通を、添付書類については正本1通及び
その写し1通を提出しなければならない(則第20条)。
(3)海外派遣の届出の受理
事業主管轄労働局は、海外派遣届出書(様式第13号)及び添付書類について、記載事項等に
不備がないことを確認の上受理し、正本及び添付書類1通を本省に送達すると共に、海外派遣
届出書の写しについては、そのうち1通を提出者に控えとして交付する。
また、海外派遣の届出を受理した事業主管轄労働局は、当該事業所に係る事業所管轄労働局
へ海外派遣届出書の複写及び関係書類を送付するものとする。
4 事業所ごとの情報提供
(1)概要
派遣元事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣労働者の数、労働者派遣の役務の
提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均
額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合、教育訓練に関
する事項など、あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である事項について情報の提供
を行わなければならない(法第23条第5項)。
これによって、派遣元事業主の透明性を確保し、派遣労働者による派遣元事業主の適切な選
択や派遣労働者の待遇改善等に資することが期待される。
(2)情報提供すべき事項
派遣元事業主が事業所ごとに情報提供すべき事項は、次のとおりである(法第23条第5項、
則第18条の2第3項)。
イ 派遣労働者の数
(イ)直近の数が望ましいが、直近の「6月1日現在の状況報告」で報告した事業所ごとの派
遣労働者の数でも差し支えない。
(ロ)情報提供にあたっては、「α年6月1日付け派遣労働者数 β人」と記載する等、時点
及び単位がわかるようにすること。
ロ 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数
(イ)直近の数が望ましいが、直近の「事業報告書」の派遣先事業所数でも差し支えない。
(ロ)情報提供にあたっては、「α年度 派遣先事業所数(実数) β件」と記載する等、時
点及び単位等がわかるようにすること。
ハ 労働者派遣に関する料金の額の平均額
-125 -
第5 事業報告等
(イ)直近の労働者派遣に関する料金の額の平均額(当該事業所における派遣労働者1人1日
(8時間)当たりの労働者派遣に関する料金の平均額。また、小数点以下の端数が生じた
場合には、四捨五入のうえ表記すること。)が望ましいが、直近の「事業報告書」に記載
した派遣料金とすることでも差し支えない。
(ロ)情報提供にあたっては、「α年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額 β円」と記
載する等、時点がわかるようにするとともに、事業報告で報告したすべての業務について
も記載する等、単位等についてもわかるようにすること。
- 派遣労働者の賃金の額の平均額
(イ)派遣労働者の賃金の平均額(当該事業所における派遣労働者の1人1日(8時間)当た
りの賃金の額の平均額。また、小数点以下の端数が生じた場合には、四捨五入のうえ表記
すること。)が望ましい。ただし、個別に算出する代わりに直近の「事業報告書」に記載
した派遣労働者の賃金の額とすることでも差し支えない。
(ロ)情報提供にあたっては、「α年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 β円」と記載する
等、時点がわかるようにするとともに、事業報告で報告したすべての業務についても記載
する等、単位等についてもわかるようにすること。
ホ 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を
当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(以下「マージン率」とい
う。)
(イ)マージン率の算出方法
前事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣に関する料金の額の平
均額(当該事業年度における派遣労働者1人1日(8時間)当たりの労働者派遣に関する
料金の平均額。)から派遣労働者の賃金の額の平均額(当該事業年度における派遣労働者
1人1日(8時間)当たりの派遣労働者の賃金の額の平均額。)を控除した額を当該労働
者派遣に関する料金の平均額で除すことにより算出すること。
なお、百分率(%)表記にした場合に、小数点以下一位未満の端数が生じた場合には、
これを四捨五入すること(則第18条の2第2項)。
(ロ)労働者派遣に関する料金の額の平均額及び派遣労働者の賃金の額の平均額については、
加重平均による。例えば、3名の派遣労働者を雇用している場合であって、労働者派遣に
関する料金の額が1万円・1万円・3万円であるときは、1万円と3万円の単純平均とす
るのではなく、1万円の派遣労働者が2名いることを加味した加重平均の計算の考えによ
ること。
(ハ)ただし、直近の「事業報告書」の「派遣料金」及び「派遣労働者の賃金」を元に算出す
る場合は上記(ロ)の限りではない。
(ニ)情報提供にあたっては、(ハ)によって算出した場合は「α-1年度 マージン率の平
均 8%」と事業報告で報告したすべての業務についても記載することが望ましい。ま
-126 -
第5 事業報告等
た、時点及び単位、マージン率に含めている教育訓練に要する経費、福利厚生費、社会保
険料等の事項についても示す、派遣労働者が自社のいわゆるマージン率について理解しや
すくすることが望ましい。
(ホ)なお、マージン率の算定は事業所単位が基本であるが、当該事業所が労働者派遣事業を
行う他の事業所と一体的な経営を行っている場合には、その範囲内で算定することも妨げ
′°°°°°°°°°.こ.▼.
ないこと(則第18条の2第2項)。
※「一体的な経営」とは
e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼▼
「一体的な経営」とは、例えば、一定の地域に所在する複数の事業所で共通経費の処理を行
;っており、事業所ごとに経費が按分されていないような場合などが該当すること
°e▼e▼e▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽeヽ°ヽ°ヽ°ヽ°ヽ°ヽ°ヽ°ヽ°ヽ°ヽ°°0°0°0°e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼e▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽ▼ヽe▼°▼°▼°▼°▼°▼°▼°▼°▼°▼
へ 法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
(イ)法第30条の4第1項の労使協定を締結している場合には、当該協定の対象となる派遣労
働者の範囲及び当該協定の有効期間の終期、当該協定を締結していない場合には、当該協
定を締結していない旨を情報提供すること。
(ロ)また、法第30条の4第1項の労使協定を締結している否かの別等の情幸田ま、比較対象労
働者の待遇等に関する情報提供等の派遣先の義務の履行に重要な情報であることを踏ま
え、派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結や更新等の機会を捉え、当該情報を派遣先に
積極的に提供することが望ましい。
ト 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
(イ)派遣元事業主には、希望者全員へのキャリアコンサルティングの実施及びキャリア形成
に資する教育訓練の実施等が義務づけられている。
このため、キャリアコンサルティングの相談窓口の連絡先やキャリアアップに資する教
育訓練に関する計画内容(その概要を含む)を示すことが求められる。
(ロ)公表する内容としては、入職時等の教育訓練や職能別訓練等の訓練種別、対象となる派
遣労働者、賃金支給の有無、派遣労働者の費用負担の有無等の労働者派遣計画で計画し記
載すべき事項と同様の事項を公表することが考えられるが、それ以外の事項についても、
公表すべき事項があれば、積極的に公表することが望ましい。
(ハ)派遣労働者が良質な派遣元事業主を選択できるように、教育訓練に関する事項等に関す
る情報として、キャリア形成支援制度の内容についての情報をインターネットの利用その
他適切な方法により提供することが許可要件(第3の1の(8)のロの(イ))となって
いる点に留意すること。
(ニ)その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項
積極的な情報提供を行うことで実態をより正確に表すことが可能となり、派遣労働者に
よる派遣元事業主の適切な選択等に資すると考えられる事項をいう。その内容は、各派遣
元事業主において判断すべきものであるが、例えば、福利厚生に関する事項や派遣労働者
の希望や適性等に応じた派遣先とのマッチング状況等が考えられる。
-127 -
第5 事業報告等
(3)情報提供の方法等
イ 情報提供の方法は、事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法
により行うこととする(則第18条の2第1項)。なお、派遣元指針により、マージン率及び
(2)のへの事項の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、
とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすることとされているので留意す
ること。
「その他の適切な方法」としては、例えば、パンフレットの作成や人材サービス総合サイ
トの活用等が考えられるが、情報提供の趣旨に鑑みて適切な方法によることが必要である。
なお、人材サービス総合サイトについては、上記のインターネットの利用が原則とされてい
ることにかんがみ、自社でホームページを有していない場合等については積極的に活用する
ことが望ましい。
ロ 情報提供((2)のへに係るものを除く。)は、少なくとも、毎事業年度終了後可能な限
り速やかに前年度分の実績を公表することが必要であるが、情報公開を積極的に進める観点
から、派遣元事業主の判断により、当年度分の実績を追加的に情報提供することとしても差
し支えない。(2)のへの事項の情報提供について、法第30条の4第1項の労使協定を締結
していない派遣元事業主が当該協定を締結したとき、当該協定の対象となる派遣労働者の範
囲又は有効期間が変更されたときなど、当該事項に変更があったときは、速やかに情報提供
することが必要である。
ハ マージン率は、当該事業所が行っている労働者派遣の全業務・全派遣労働者の平均値を計
算すればよいが、情報公開を積極的に進める観点から、派遣元事業主の判断により、詳細な
計算結果を追加的に情報提供することとしても差し支えない。
ニ 情報提供は、派遣労働者による派遣元事業主の適切な選択等に資するよう、マージン率だ
けではなく、教育訓練に関する事項やその他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認め
られる事項等も含めて総合的に判断できるような形で行うことが重要である。
ホ 派遣元事業主は、関係者からの情報提供の求めがあった場合には、これに応じる義務があ
るのは当然である。
5 労働争議に対する不介入
(1)概要
イ 派遣元事業主は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は事業所閉鎖
の行われている事業所に関し、労働者派遣(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に
当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあっては、当該労働者派遣及びこれに相当す
るものを除く。)をしてはならない(法第24条、職業安定法第20条第1項)。
ロ イのほか、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉
鎖に至るおそれの多い争議が発生していること及び無制限に労働者派遣が行われることによ
-128 -
第5 事業報告等
って、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は都道
府県労働局に連絡し、都道府県労働局はその旨を派遣元事業主に通報するものとし、当該通
報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報の際現に当該事業所
に関し労働者派遣をしている場合にあっては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除
く。)をしてはならない。ただし、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者(労働者
派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)の員数を維持するため必要な限度まで労働
者派遣をする場合はこの限りでない(法第24条、職業安定法第20条第2項)。
(2)労働争議に対する不介入の趣旨
労働争議は、労使対等の立場で行われその解決も自主的に行われるべきものである。ところ
が労働者派遣事業等の労働力需給調整システムが争議が行われている事業所に対し労働力の提
供を行うことは、争議の自主的解決を妨げることとなり、適当ではない。
そのための民営職業紹介事業、労働者募集及び労働組合の行う労働者供給事業について準用
されている職業安定法第20条をこれらと同様に準用することにより労働者派遣事業も労働争議
に対して中立的立場に立ち、労働争議の自主的な解決を妨げないこととしたものである。
(3)現に同盟罷業又は作業所閉鎖の行われているときの規制
イ 労働争議のうち同盟罷業(ストライキ)又は作業所閉鎖(ロックアウト)の行われている
事業所に労働者派遣をすることが禁止される。
ロ 「同盟罷業」とは、労働者が団結して労働力の提供を拒否し、労働力を使用者に利用させ
ない行為をいい、一部スト、部分スト、波状スト等ストライキ一般が含まれる。また、「作
業所閉鎖」とは、労働者に対して作業所を閉鎖して労働者を就業不能の状態におき、労働者
の提供する労務の受領を拒否することをいい、いわゆるロックアウトがこれに当たる。
ハ イの趣旨は、公正な労働関係を維持するためであるから、法律により争議行為が禁止され
た国、地方公共団体又は公共企業体において、争議行為が行われる等違法な争議行為が行わ
れている場合に、労働者派遣をすることはイの趣旨に反するものではない。
ニ 禁止されるのは、同盟罷業又は作業所閉鎖が行われて以後、新たに労働者派遣をすること
であり、その際現に、労働者派遣をしている場合には、その範囲内で引き続き労働者派遣を
することまで禁止するものではない(同盟罷業又は作業所閉鎖中に同一内容の契約の更新、
更改を行うことも許容される)。ただし、従来から労働者派遣はしていても派遣労働者を増
加させるような行為は許されない。
同盟罷業又は作業所閉鎖が予定されている場合に、その直前に、新たに労働者派遣をする
ことは法の趣旨に反するものであり、同様に許されないものと考えられる。
(4)争議行為が発生しており、同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多いときの規制
イ 労働委員会から公共職業安定所に対し、無制限に労働者派遣をすることによって、当該争
議の解決が妨げられることが通報された場合、公共職業安定所は都道府県労働局に連絡し、
都道府県労働局は派遣元事業主に対しその旨を通報する。
-129 -
第5 事業報告等
この場合、当該派遣元事業主が労働者派遣をすることが一定の範囲において禁止される。
ロ 禁止される労働者派遣の範囲は、(3)と同様新たに労働者派遣をすることであり、通報
の際に、現に労働者派遣をしている場合に、引き続き労働者派遣をすることまで禁止する趣
旨ではない。
ハ また、当該労働争議の発生前に、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な
限度まで新たに労働者派遣をし、又は派遣労働者を増加させることは禁止されない。ここに
いう通常使用されていた労働者の員数とは、派遣労働者を含めた数であり、一応労働争議発
生前3箇月の平均をもって判断するが、季節や時期によって事情が異なる場合もあり、この
ような場合には、例年のその時期の労働者数を考慮して判断する。
6 個人情報等の保護
(1)概要
派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介
を含む。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使用し(法第24
条の3第1項)、当該個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない
(法第24条の3第2項)。また、派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正
当な理由がある場合でなければ、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない(法第24
条の4)。
なお、紹介予定派遣をする場合において職業紹介を行う段階では、職業紹介事業者として、
個人情報の保護等について職業安定法その他の法律の規定が適用となることに留意し、紹介予
定派遣の各段階に応じ、派遣元事業所及び職業紹介事業所としてそれぞれ必要な個人情報保護
措置を講じること(職業紹介事業関係業務取扱要領第11の3参照)。
(2)個人情報の収集、保管及び使用
派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人
情報を収集、保管及び使用するに際し、以下の点に留意しなければならない。
イ 派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者を登録する際には当該労働者の希望及び能
力に応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣を
行う際には当該派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、派遣労働者となろうと
する者及び派遣労働者(以下「派遣労働者等」という。)の個人情報((2)及び(3)に
おいて単に「個人情幸勘 という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集しては
ならない。ただし、特別な業務上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不
可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではない。
(イ)人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれの
ある事項
(ロ)思想及び信条
-130 -
第5 事業報告等
(ハ)労働組合への加入状況
(イ)からハ)については、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当する。
(イ)関係
① 家族の職業、収入、本人の資産等の情報(税金、社会保険の取扱い等労務管理を
適切に実施するために必要なもの及び日雇派遣の禁止の例外として認められる場合
の収入要件を確認するために必要なものを除く。)
② 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報
(ロ)関係 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
(ハ)関係 労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
「業務の目的の達成に必要な範囲」については、雇用することを予定する者を登録する
段階と、現に雇用する段階では、異なることに留意する必要がある。前者においては、例
えば労働者の希望職種、希望勤務地、希望賃金、有する能力・資格など適切な派遣先を選
定する上で必要な情報がこれに当たり、後者においては、給与事務や労働・社会保険の手
続上必要な情報がこれに当たるものである。
・ なお、一部に労働者の銀行口座の暗証番号を派遣元事業主が確認する事例がみられる
が、これは通常、「業務の目的の達成に必要な範囲」に含まれるとは解されない。
ロ 派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下
で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならない。
「等」には本人が不特定多数に公表している情報から収集する場合が含まれる。
なお、これ以外の場合で、問題が生じた場合には、本省あて相談すること。
ハ 派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新規
卒業予定者であって派遣労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職業
安定局長の定める書類(全国高等学校統一応募用紙又は職業相談票(乙))により提出を求
めることが必要であること。
なお、当該応募書類は、新規卒業予定者だけでなく、卒業後1年以内の者についてもこれ
を利用することが望ましいこと。
ニ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。
なお、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、労働者派遣事業制度の性質上、
派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情幸酎ま、法第35条第1項の
規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情幸酎こ
限られるものである。ただし、他の保管又は使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は
他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある
場合を除き、労働者派遣事業の実施に伴い収集等される派遣労働者等の個人情幸酎こついて
は、「労働者派遣業務(自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指
-131-
第5 事業報告等
揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる業務をいい、当該他人に対し当該労
働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。)」又は、紹介予定派遣
も行う場合にあっては「労働者派遣業務(自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下
に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる業務をいい、当
該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。)及
び紹介予定派遣をする場合における職業紹介業務(求人及び求職の申込みを受け、求人者
と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんする業務)」として利用目的を特定す
べきものであり、その変更も基本的に想定されないものであること。
なお、法及び派遣元指針においては、法第24条の3第1項ただし書及び派遣元指針第2
の11の(1)のこのただし書に該当する場合は、労働者派遣事業の実施に伴い収集等され
る派遣労働者等の個人情報の労働者派遣業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介
を含む。)以外の目的での利用も可能となっているが、この場合にあっても、その利用日
的をできる限り特定する必要があること。
「派遣労働者登録申込書」等により直接当該本人から個人情報を取得する場合について
は、当該個人情報が労働者派遣業務に利用されることが明らかであることから、個人情報
の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第18条第4
項に規定する「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当す
るものとして、同条第1項及び第2項による利用目的の通知等の対象となるものではない
こと。一方、アンケート調査票等に記載された個人情報を労働者派遣業務に利用する場合
にあっては、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当す
るものではなく、利用目的の通知等が必要となるものであること。
ただし、トラブル防止等の観点からは、派遣労働者登録申込書、アンケート調査票等、
本人から直接個人情報を取得する書面には、当該書面により取得される個人情報の利用目
的を併せて記載する等により、当該利用目的が明示されるようにしておくことが望ましい
ものであること。
個人情報保護法第23条において、個人データを第三者に提供することについて定めてい
るものであるが、労働者派遣業務においては、例えば、派遣労働者登録申込書に、派遣先
に提供されることとなる個人データの範囲を明らかにしつつ、労働者派遣に必要な範囲
(派遣元指針第2の11の(1)の二に定める範囲)で個人データが派遣先に提供されるこ
とに関する同意欄を設けること等により、派遣労働者となろうとする者から同意をあらか
じめ得るようにすることが必要となるものであること。なお、この「同意」の取得の方法
は、特段の要式行為とされているものではないが、トラブル防止等の観点からも、書面に
よる取得など事後に「同意」の事実を確認できるような形で行うことが望ましいものであ
ること。
派遣先に対して派遣労働者等の個人データを示す行為は、個人情報保護法第23条第1項の
-132 -
第5 事業報告等
「第三者提供」に該当するものであるが、派遣元事業主が法第35条第1項各号に掲げる事項
を派遣先に通知する場合は、個人情報保護法第23条第1号の「法令に基づく場合」に該当
し、派遣元事業主は、あらかじめ本人の同意を得る必要がないものであること。
(3)個人情報の適正管理
イ 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情幸酎こ関し、次に掲げる措置を適切に講ず
るとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならない。
(イ)個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
(ロ)個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
(ハ)正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
(ニ)収集目的に照らして保管する必要がなくなった(本人からの破棄や削除の要望があった場
合を含む。)個人情報を破棄又は削除するための措置
口 派遣元事業主等が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個
人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならな
い。
「個人情幸田 とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」とは、一
般に知られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことにつき本人が相当の
利益を有すると客観的に認められる事実(要保護性)をいうものである。具体的には、本籍
地、出身地、支持・加入政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実等が秘密に
当たりうる。
ハ 派遣元事業主は、次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規程を作成するとともに、自ら
これを遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければならない。
(イ)個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項
(ロ)個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項
(ハ)本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ)の取扱い
に関する事項
「個人情報の開示又は訂正」については、「利用の停止等」及び「第三者への提供の
停止」が明示的に規定されているものではないが、概念上、「利用の停止」及び「第三
者への提供の停止」が排除されているものではないこと。
・ 派遣元事業主は、個人情報適正管理規程について、個人情報保護法第32条を踏まえた
内容として所要の改正等を行うことが望ましいこと。
(ニ)個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項
なお、(ハ)において開示しないこととする個人情報とは、当該個人に対する評価に関
する情報が考えられる。
また、(ニ)に関して苦情処理の担当者等取扱責任者を定めることが必要である。
-133 -
第5 事業報告等
(参考) 個人情報適正管理規程の例
1 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、営業課派遣事業係及び総務課総務係とする
こととする。個人情報取扱責任者は派遣事業係長〇〇〇〇とすることとする。
2 派遣元責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取
扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、派遣元責任者は少なくとも3
年に1回は派遣元責任者講習を受講し、個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得る
よう努めることとする。
3 1の個人情報取扱責任者は、派遣労働者等から本人の個人情幸酎こついて開示の請求があっ
た場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示
を遅滞なく行うこととする。更にこれに基づく訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があ
った場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととす
る。
また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、派遣元責任者は派遣労働者等への
周知に努めることとする。
4 派遣労働者等の個人情幸酎こ関して、当該情幸酎こ係る本人からの苦情の申出があった場合に
ついては、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
なお、個人情幸酎こ係る苦情処理担当者は派遣元責任者◇◇◇◇とすることとする。
年 月 日
ニ 派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本
人に対して不利益な取扱いをしてはならない。
「不利益な取扱い」とは、具体的には、例えば、以後、派遣就業の機会を与えないこと等
をいう。
(4)個人情報の保護に関する法律の遵守等
(1)から(3)までに定めるもののほか、派遣元事業主は、個人情報保護法に規定する個
人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)に該当する場合には、個人情報保
護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならない。また、個人情報取扱事業者に該
当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努
めなければならない(第7の27及び第11参照)。
(5)秘密を守る義務
派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなけれ
ば、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、派遣
元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
なお、「正当な理由がある場合」とは、本人の同意がある場合、他の法益との均衡上許され
-134 -
第5 事業報告等
る場合等をいう。
また、「秘密」には、個々の派遣労働者(雇用することを予定する者を含む。)及び派遣先
に関する個人情報が含まれるものであり、私生活に関するものに限られない。職務を執行する
機会に知り得た個人情報を含むものである。この他、例えば、法第26条第7項及び第10項並び
に第40条第5項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする者又は派遣先から提供
を受けた情幸酎こついても、この「秘密」に含まれる(派遣元指針第2の12)。
さらに、「他に」とは、当該秘密を知り得た事業所内の使用人その他の従業員以外の者をい
うものである。
-135 -
第6 労働者派遣契約
第6 労働者派遣契約
1 意義
(1)法第26条にいう「労働者派遣契約」は、「契約の当事者の一方が、相手方に対し労働者派遣する
ことを約する契約」であり、当事者の一方が労働者派遣を行う旨の意思表示を行いそれに対しても
う一方の当事者が同意をすること又は当事者の一方が労働者派遣を受ける旨の意思表示を行いそれ
に対してもう一方の当事者が同意をすることにより成立する契約であり、その形式については、文
書であるか否か、又有償であるか無償であるかを問うものではない。
(2)労働者派遣に関する契約については、恒常的に取引先との間に労働者派遣をする旨の基本契約を
締結し、個々具体的に労働者派遣をする場合に個別に就業条件をその内容に含む個別契約を締結す
るという場合があるが、この場合、法第26条の意味における労働者派遣契約とは、後者の個別契約
をいうものである。
(3)「労働者派遣契約の当事者」とは、業として行うものであるか否かを問わず、当事者の一方が労
働者派遣を行い、相手方がその役務の提供を受ける場合を全て含むものであり、労働者派遣をする
者及び労働者派遣の役務の提供を受ける者の全てを指すものである。
2 契約の内容等
(1)契約内容
イ 契約事項の定め
(イ)概要
労働者派遣契約の締結に当たっては、(ハ)の事項を定めるとともに、その内容の差異に応じ
て派遣労働者の人数を定めなければならない(法第26条第1項、則第22条)。
(ロ)意義
法で定める契約事項の定めは、労働者派遣を行うに当たっての必要最低限のものであり、そ
れ以外の派遣料金、債務不履行の場合の賠償責任等の定めについては当事者の自由に委ねられ
る。
(ハ)契約事項
労働者派遣契約には、次の事項を定めなければならない。
(力 派遣労働者が従事する業務の内容
・ 業務の内容は、その業務に必要とされる能力、行う業務等が具体的に記述され、当該記
載により当該労働者派遣に適格な派遣労働者を派遣元事業主が決定できる程度のものであ
ることが必要であり、できる限り詳細であることが適当である。
・ 適用除外業務(第2の1参照)以外の業務に限られること。
・ 従事する業務の内容については可能な限り詳細に記載すること。
-136 -
第6 労働者派遣契約
(例 環境関連機器の顧客への販売、折衝、相談及び新規顧客の開拓並びにそれらに付帯
する業務)
・ 同一の派遣労働者が複数の業務に従事する場合については、それぞれの業務の内容につ
いて記載すること。
・ 業務の内容に令第4条第1項各号に掲げる業務が含まれるときは、日雇労働者に係る労
働者派遣が可能な業務であることを労働者派遣契約当事者間で認識を共有するため、当該
号番号を付すること。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかで
ある場合は、この限りではない。
「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、
(i)無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合
(の 契約期間が31日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合
(の(a)又は(b)の労働者派遣に限る場合
のいずれかであり、かつその旨が労働者派遣契約において明記されている場合である。
② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度(則第22条第1号)
・ 派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程
度等をいうこと。
・ チームリーダー、副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職を、
役職を有さない派遣労働者であればその旨を記載することで足りるが、派遣元事業主と派
遣先との間で、派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度について共通認識を持つこと
ができるよう、より具体的に記載することが望ましい。
③ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の
場所並びに組織単位
・ 派遣労働者が実際に派遣就業する事業所その他の施設の名称、所在地だけではなく具体
的な派遣就業の場所及び組織単位(組織の名称)も含むものであり、原則として、派遣労
働者の所属する部署、電話番号等必要な場合に派遣元事業主が当該派遣労働者と連絡がと
れる内容であること。加えて、組織単位を特定するために必要な事項(組織の長の職名)
を明記することが望ましい。
事業所等における組織単位については、課、グループ等の業務としての類似性や関連性
がある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮命令監督権限を
有するものであって、派遣先における組織の最小単位よりも一般に大きな単位を想定して
いるが、名称にとらわれることなく実態により判断すべきものである。ただし、小規模の
事業所等においては、組織単位と組織の最小単位が一致する場合もあること。また、実際
上の取扱いとしては、派遣先における組織が指定されることから、派遣先がこの基準に従
って指定することが通常であると考えられること。
④ 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者
-137 -
第6 労働者派遣契約
に関する事項
・ 派遣労働者を具体的に指揮命令する者の部署、役職及び氏名である。
⑤ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
・ 当該労働者派遣契約に基づき、派遣労働者が労働者派遣される期間及び派遣労働者が具
体的に派遣就業をする日であり、期間については、具体的な労働者派遣の開始の年月日及
び終了の年月日、就業する目については、具体的な曜日又は日を指定しているものである
こと。
・ 第8の5の(3)のイの①から⑥までに掲げる場合以外の労働者派遣を行うときは、事業
所その他派遣就業の場所(以下「派遣先事業所等」という。)ごとの業務における派遣可
能期間は3年であること。ただし、派遣可能期間の起算点は当該派遣先事業所等で最初に
労働者派遣の受入れを行った日とする。なお、派遣先事業所等における組織単位ごとの業
務について、派遣元事業主は3年を超える期間継続して同一の有期雇用の派遣労働者に係
る労働者派遣を行うことはできない。
⑥ 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
・ 派遣就業すべき日の派遣労働者の日々の始業、終業の時刻並びに休憩時間(法律上は時
間数のみであるが、一般的には休憩の開始及び終了の時刻を特定して記載することが適当)
である。
この定めの内容は、労働基準法で定める労働時間、休憩時間に関する規定に反しておら
ず、かつ、派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約の枠内でなければならない。
⑦ 安全及び衛生に関する事項
次に掲げる事項のうち、派遣労働者が派遣先において(力の業務を遂行するに当たって、
当該派遣労働者の安全、衛生を確保するために必要な事項に関し就業条件を記載する必要
がある。
(i)派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項
(例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務によ
る危険又は健康障害を防止する措置の内容等)
(の 健康診断の実施等健康管理に関する事項
(例えば、有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務に就かせる場合には、当
該健康診断の実施に関する事項等)
(の 換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項
(k)安全衛生教育に関する事項
(例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容等)
(Ⅴ)免許の取得、技能講習の修了の有無等就業制限に関する事項
(例えば、就業制限業務を行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種
類等)
-138 -
第6 労働者派遣契約
(d)安全衛生管理体制に関する事項
(壷)その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項
⑧ 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事
項
・ 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主及び派
遣先において苦情処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携のための体制等を記載
すること(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の3(第7の27参照)及び
「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の7(第8の19参照))。
・ 派遣労働者の苦情の申出を受ける者については、その者の氏名の他、部署、役職、電話
番号についても記載すること。
⑨ 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法第26条
の規定により使用者が支払うべき手当をいう。以下同じ。)等の支払に要する費用を確保す
るための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣
労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
・ 労働者派遣契約の解除に際して、派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、当該労働者
派遣契約の当事者である派遣元事業主及び派遣先が協議して次の事項等に係る必要な措置
を具体的に定めること(法第29条の2、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第
2の2の(2)(第7の27参照)及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の6の(1)
(第8の19参照))。
(i)労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する
前の解除を行おうとする場合には、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらか
じめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うものとすること。
(の 派遣先における就業機会の確保
派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の
責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該
派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労
働者の新たな就業機会の確保を図るものとすること。
(の 損害賠償等に係る適切な措置
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前
に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保
を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴
い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なく
されたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないものとすること。例えば、
当該派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額
-139 -
第6 労働者派遣契約
について、当該派遣元事業主がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合
は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより当
該派遣元事業主が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の
日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日まで
の日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害賠償を行わなければならない
ものとすること。その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方
策を講ずるものとすること。また、派遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由
がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合につい
ても十分に考慮するものとすること。
(k)労働者派遣契約の解除の理由の明示
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おう
とする場合であって、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を
行った理由を当該派遣元事業主に対し明らかにするものとすること。
⑲ 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従
事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合は、次に掲げる当該紹介予定派遣に
関する事項を記載すること(第1の4参照)。
・ 紹介予定派遣である旨
・ 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される従事すべき業務の内容及び労働
条件等
【例】
I 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
Ⅱ 労働契約の期間に関する事項
Ⅲ 試みの使用期間(以下「試用期間」という。)に関する事項
※ ただし、紹介予定派遣により雇い入れた労働者について試用期間を設けることは望
ましくない。
Ⅳ 就業の場所に関する事項
Ⅴ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時聞及び休日に関する
事項
Ⅵ 賃金の額に関する事項
Ⅶ 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法
による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項
Ⅷ 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業
-140 -
第6 労働者派遣契約
紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれのその
理由を、書面の交付、ファクシミリを利用してする送信、又は電子メールその他のその受
信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和
59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」とい
う。)の送信の方法(当該電子メール等の受信をする者が当該電子メール等の記録を出力
することにより書面を作成できるものに限る。以下同じ。)により、派遣元事業主に対し
て明示する旨
・ 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについ
て、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨
・ 労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨
⑪ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項(則第22条第2号)
・ 派遣元責任者及び派遣先責任者の役職、氏名及び連絡方法である。また、①(派遣労働
者が従事する業務の内容)が製造業務である場合には、当該派遣元責任者及び派遣先責任
者が、それぞれ製造業務専門派遣元責任者(則第29条第3号)又は製造業務専門派遣先責
任者(則第34条第3号)である旨を記載すること。
・ 派遣先責任者の選任義務規定の適用を受けない場合(則第34条第2号ただし書)は、当
該事項の記載は要しない。ただし、派遣先責任者を選任している場合には、記載を要する
ものである。
⑫ 労働者派遣の役務の提供を受ける者が⑤の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせる
ことができ、又は⑥の派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することが
できる旨の定めをした場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長すること
ができる時間数(則第22条第3号)
この定めをする場合には、当該定めの内容が派遣元事業主と派遣労働者との間の労働
契約又は派遣元事業場における36協定により定められている内容の範囲内でなければな
らない。
⑬ 派遣元事業主及び派遣先との間で、派遣先が当該派遣労働者に対し、派遣先が設置及び
運営する物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運
動場、体育館、保養施設等の施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用して
いるもの(給食施設、休憩室及び更衣室を除く。)の利用、レクリエーション等に関する
施設又は設備の利用、制服の貸与、教育訓練その他の派遣労働者の福祉の増進のための便
宜を供与する旨の定めをした場合には、当該便宜の供与に関する事項についても記載する
こと(法第40条第4項、則第22条第4号、派遣先指針第2の9(1))。
なお、派遣先の給食施設、休憩室及び更衣室の利用については、法律上の労働者派遣契
約の記載事項ではないが、法第40条第3項の規定に基づき利用機会を付与しなければなら
ないものとされていることに留意すること。
-141-
第6 労働者派遣契約
⑭ 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る
派遣労働者を雇用する場合に、その雇用意思を事前に労働者派遣をする者に対し示すこと、
当該者が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払うことその
他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置
(則第22条第5号)。
なお、派遣先が派遣元事業主に紹介手数料を払うのは、派遣元事業主が職業安定法その
他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合に
おいて、派遣先がその職業紹介により当該派遣労働者を雇用したときに限られる。(「派
遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の2(2)ロ)。
紹介手数料のことを定める場合については、可能な限り記載例のように詳細に記載する
ことが望ましいが、紹介手数料の額までを記載することまでは要しない(紹介手数料につ
いては別途定めるといった記載でも差し支えない。)。
⑮ 派遣労働者を協定対象派遣労働者(法第30条の4第1項の協定で定めるところによる待遇
とされる派遣労働者をいう。以下同じ。)に限定するか否かの別(則第22条第6号)
⑱ 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別(則第22条第7
号)
⑰ 派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する事項
・ 第8の5の(3)のイの③に掲げる有期プロジェクトの業務について労働者派遣を行うと
きは、法第40条の2第1項第3号イに該当する旨を記載すること(則第22条の2第2号)。
・ 第8の5の(3)のイの④に掲げる業務(日数限定業務)について労働者派遣を行うとき
は、i)法第40条の2第1項第3号ロに該当する旨、の 当該派遣先において、同号ロに
該当する業務が1箇月間に行われる日数、の 当該派遣先の通常の労働者の1箇月間の所
定労働日数を記載すること(則第22条の2第3号)。
・ 第8の5の(3)のイの⑤に掲げる育児休業等の代替要員としての業務について労働者派
遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及
び終了予定の日を記載すること(則第22条の2第4号)。
・ 第8の5の(3)のイの⑥に掲げる介護休業等の代替要員としての業務について労働者派
遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及
び終了予定の日を記載すること(則第22条の2第5号)。
(ニ)派遣労働者の人数の定め
a 派遣労働者の人数の定めは次により行わなければならない(則第21条第1項)。
(力(ハ)の(力から⑱に掲げる就業条件の組合せが1つの場合は、当該労働者派遣に係る派遣
労働者の人数
②(ハ)の(力から⑱に掲げる就業条件の組合せが複数の場合は、当該組合せごとの派遣労働
者の人数
-142 -
第6 労働者派遣契約
b 派遣労働者の人数とは、当該就業条件の組合せで常時居ることとなる人数であり、複数
の者が交替して行うこととなる場合であってもその複数の者分の人数を定めるものではな
い。例えば、午前と午後で1人ずつ就業することとなる場合は1人となる。
(ホ)労働者派遣契約の定めに関する留意事項
a(ハ)の(力から⑱の契約事項の内容を一部変更し、再度労働者派遣契約を締結するに際して
は、一部変更することとなる以前に締結した契約を指定し、当該一部変更事項を定めるこ
とで足りるものとし、再度すべての契約内容の定めを行うことは要しないものとする(⑤
の労働者派遣の期間については、一部変更した内容で改めて派遣期間を決定することとな
るため、必ず変更を伴うものである)。また、(ニ)における派遣労働者の人数についても変
更する場合は、併せて、人数を定める(就業条件の組合せが複数であるときには、組合せ
ごとに人数を定める。)ことで足りるものとする。
b 派遣労働者が複数の業務を兼任して行う旨の労働者派遣契約を定めることができること。
C 就業条件の組合せについては、次のような就業条件は複数とはならないものであり、当
該就業条件をもって、就業条件の組合せが複数あることとはならないこと。
・ 派遣労働者が法第40条の2第1項第3号ないし第5号の業務のうち2つ以上の業務を
兼任する場合
・ 派遣労働者を直接指揮命令する者が時間制により交替する場合
・ 派遣元責任者及び派遣先責任者が時間制により交替する場合
d 第8の5の(3)のイの④に掲げる業務(日数限定業務)について労働者派遣を行う場合は、
当該派遣先において、(ハ)の⑰の辻(当該派遣先において、法第40条の2第1項第3号ロに
該当する業務が1箇月間に行われる日数)に記載した日数に係る日以外には当該業務が行
われないものであることを、労働者派遣契約の当事者において十分確認すること。
(参考) 労働者派遣契約の定めの例(有期雇用派遣労働者を派遣する場合)
〇〇〇〇株式会社(派遣先)と□□□□株式会社(派遣元事業主)(派**-******)とは、次の
とおり労働者派遣契約を締結する。
1 業務内容 パーソナルコンピュータの操作によるプレゼンテーション用資料、業績管理資料、
会議用資料等の作成業務
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第
4条第1項第3号の事務用機器操作に該当。)
2 責任の程度 副リーダー(部下2名、リーダー不在の間における緊急対応が過1回程度有)
3 就業場所 〇〇〇〇株式会社本社 国内マーケテイング部営業課販売促進係
(〒110-0010千代田区霞が関1-2-20ビル2階
TEL 3593-****)
-143 -
第6 労働者派遣契約
4 組織単位 国内マーケテイング営業課(国内マーケテイング営業課長)
5 指揮命令者 国内マーケテイング部営業課販売促進係長★★★★★
6 派遣期間 2020年4月1日か2021年3月31日まで
(※紹介予定派遣の場合は、6箇月以内の期間とする。)
7 就業 日 月~金(ただし、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、夏季休業(8月13日から
8月16日)を除く。)
8 就業時間 9時から18時まで
9 休憩時間12時から13時まで
10 安全及び衛生
派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条から第47条の3までの規定により課された各法令を遵
守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣
先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する
規定を適用する。
11派遣労働者からの苦情の処理
(1)苦情の申出を受ける者
派遣先 営業課総務係主任 ☆☆☆☆☆ TEL3597-**** 内線101
派遣元事業主 派遣事業運営係主任 ※※※※※ TEL3593-**** 内線5721
(2)苦情処理方法、連携体制等
① 派遣元事業主における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者の
◎◎◎◎◎へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞な
く、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知す
ることとする。
② 派遣先における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者の●●●
●●へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当
該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知する
こととする。
③ 派遣先及び派遣元事業主は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、
相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いっつ、その解決を図ることとする。
12 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
(1)労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解
除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間
をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。
(2)就業機会の確保
派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰
すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先の関連会社での就業を
-144 -
第6 労働者派遣契約
あっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る
こととする。
(3)損害賠償等に係る適切な措置
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働
者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることと
し、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元事業主が当
該労働者派遣に係る派遣労者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠
償を行わなければならないこととする。例えば、派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる
場合は休業手当に相当する額以上の額について、派遣元事業主がやむを得ない事由により当該
派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われな
かったことにより派遣元事業主が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日か
ら解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日ま
での日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこ
ととする。その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずるこ
ととする。また、派遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元
事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする
(4)労働者派遣契約の解除の理由の明示
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする
場合であって、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を
派遣元事業主に対し明らかにすることとする。
13 派遣元責任者 派遣元事業主の派遣事業運営係長◎◎◎◎◎TEL3597-****内線100
14 派遣先責任者 派遣先の総務部秘書課人事係長=…TEL3593-****内線5720
15 就業日外労働 6の就業日以外の就労は、1箇月に2日の範囲で命ずることができるものとす
る。
16 時間外労働 7の就業時間外の労働は1日4時間、1箇月45時間、1年360時間の範囲で命ずる
ことができるものとする。
17 派遣人員 2人
18 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与
派遣先は、派遣先の労働者に対して利用の機会を与える診療所については、本契約に基づく労
働者派遣に係る派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならないこと
とする。
19 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、その雇用意
思を事前に派遣元事業主に対して示すこと。
また、職業紹介を経由して行うこととし、紹介手数料として、派遣先は派遣元事業主に対して
-145 -
第6 労働者派遣契約
、支払われた賃金額の●●分の●●に相当する額を支払うものとする。ただし、引き続き6箇月
を超えて雇用された場合にあっては、6箇月間の雇用に係る賃金として支払われた賃金額の●分
の●に相当する額とする
20 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別
協定対象派遣労働者に限定しない。
21派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別
無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。
(紹介予定派遣に係る契約である場合は下記の項目例を記載)
22 紹介予定派遣に関する事項
(1)派遣先が雇用する場合に予定される労働条件等
契約期間 期間の定めなし
業務内容 プレゼンテーション用資料、業績管理資料、会議用資料等の作成業務及び来
客対応
試用期間に関する事項 なし
就業場所
始業・終業
休憩時閉
所定時間外労働
休 日
休 暇
’:
〇〇〇〇株式会社本社 国内マーケテイング部営業課販売促進係
(〒110-0010千代田区霞が関1-2-20ビル2階 TEL 3593-****)
始業:9時 終業:18時
60分
有(1日4時間、1箇月45時間、1年360時間の範囲内)
毎週土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、
夏季休業(8月13日から8月16日)
年次有給休暇:10日(6箇月継続勤務後)
その他:有給(慶弔休暇)
基本賃金 月給180,000~240,000円(毎月15日締切、毎月20日支払)
通勤手当:通勤定期券代の実費相当(上限月額35,000円)
所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
・所定時間外:法定超 25%、休日:法定休日 35%、深夜:25%
昇給:有(0~3,000円/月) 賞与:有(年2回、計1箇月分)
社会保険の加入状況 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険 有
労働者を雇用しようとする者の名称 □□□□株式会社
(2)その他
・ 派遣先は、職業紹介を受けることを希望しなかった又は職業紹介を受けた者を雇用しなか
った場合には、その理由を、派遣元事業主に対して書面により明示する。
・ 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合には、年次有給休暇及び退職金の取扱いについ
て、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入することとする。
-146 -
第6 労働者派遣契約
ロ 労働者派遣契約の締結に際しての手続
(イ)労働者派遣契約締結の際の手続
a 契約の当事者は、契約の締結に際し上記イの(ハ)の契約の内容を上記イの(ハ)の組み合わせ
ごとに書面に記載しておかなければならない(則第21条第3項)。
b 派遣先は、当該労働者派遣契約の締結に当たり、法第26条第3項の規定により派遣元事業
主からなされる、許可を受けている旨の明示の内容(具体的には許可番号。なお、経過措置
期間中の特定労働者派遣事業については届出受理番号。)を上記aの書面に記載しておかな
ければならない(則第21条第4項)。
(ロ)労働者派遣契約の締結の際の手続に関する留意点
a イの(ホ)のaにより、以前締結した契約の一部を変更した契約を締結する際に行う書面への
記載は、当該以前締結した契約の内容により労働者派遣を行い、又は受ける旨の記載並びに
変更される契約事項について、その契約事項及びその変更内容を記載すれば足りるものとす
る。
例えば、「平成〇年〇月〇日付け労働者派遣契約と同内容で〇〇〇〇株式会社は、□□□
□株式会社に対し、労働者派遣を行うものとする。ただし、派遣期間については平成〇年〇
月〇日から平成〇年〇月〇日まで、派遣人員は3人とする。」という記載となる。
なお、ここでいう労働者派遣契約とは、基本契約書や個別契約書等の名称にかかわらず、
当該契約事項が定められていれば足りるものである。よって、例えば、必要な契約事項が個
別契約書に定められていなくても、基本契約書に定められていれば差し支えないものである。
b 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに際しては、派遣先が求める
業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該業務を遂行するために必要とされる知識、
技術又は経験の水準、労働者派遣の期間その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業
条件を事前にきめ細かに把握すること(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2
の1(第7の27参照))。
特に、労働者派遣の期間について、派遣先は派遣可能期間を延長する場合において、当該
派遣先の事業所等ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日から事業所単位
の期間制限の抵触日の1箇月前の日までの間(以下「意見聴取期間」という。)に派遣先の
労働者の過半数で組織する労働組合等に対して意見聴取を行う必要がある(法第40条の2第
4項)ことから、派遣元事業主は派遣先に対し、当該意見聴取が実施されているか確認して
から労働者派遣契約を締結すること。
C 派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就業中の派遣労働者を直接
指揮命令することが見込まれる者から、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該業
務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準その他労働者派遣契約の締結に
際し定めるべき就業条件の内容を十分に確認すること(「派遣先が講ずべき措置に関する指
-147 -
第6 労働者派遣契約
針」第2の1(第8の19参照))。
(2)派遣可能期間の制限に抵触する日の通知
イ 概要
新たな労働者派遣契約に基づき、第8の5の(3)のイの①から⑥までに該当する労働者派遣以
外の労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あら
かじめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の開始の日以後、第8の5の派遣可能期間の制限
に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない(法第26条第4項)。
また、派遣元事業主は当該通知がないときは、当該者との間で、労働者派遣契約を締結しては
ならない(法第26条第5項)。
なお、当該抵触する日の判断は第8の5の(4)により行う。
ロ 通知の趣旨
新たな労働者派遣契約を締結する派遣元事業主に対し、自らの行う第8の5の(3)のイの①か
ら⑥までに該当する労働者派遣以外の労働者派遣について事業所単位の派遣可能期間の制限に抵
触することとなる最初の日を把握させ、派遣元事業主及び派遣先の双方に派遣可能期間の制限の
規定を遵守させることを目的とする。
ハ 通知の方法等
(イ)派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知については、労働者派遣契約の締
結に際し、あらかじめ、労働者派遣(第8の5の(3)のイの①から⑥までに該当する労働者派
遣を除く)の役務の提供を受けようとする者から派遣元事業主に対して、通知すべき事項に係
る書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信をすることに
より行わなければならない(則第24条の2)。
(ロ)通知すべき事項は、締結しようとする労働者派遣契約に係る労働者派遣(第8の5の(3)の
イの(力から⑥までに該当する労働者派遣を除く)の役務の提供が、当該労働者派遣の開始の日
以後、派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日とする。
(ハ)派遣元事業主は、当該通知がないときは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者
との間で、労働者派遣契約を締結してはならない。
ニ 派遣労働者への明示
(イ)派遣元事業主は、第8の5の(3)のイの①から⑥までに掲げる労働者派遣以外の労働者派遣
をしようとするときは、あらかじめ、派遣労働者に対して、当該派遣労働者が労働者派遣に係
る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主
が期間制限に抵触することとなる最初の日及び当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事
する事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が期間制限に抵触することとなる最初
の日を明示しなければならない(法第34条第1項第3号、第4号)。なお、派遣可能期間の制
限に抵触することとなる最初の日の明示は、派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の
日を書面、ファクシミリ又は電子メール等(ファクシミリ又は電子メール等による場合にあっ
-148 -
第6 労働者派遣契約
ては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)を交付することにより行わなければならない
(則第26条、第7の13の(4)及び(5)参照)。
また、派遣労働者への明示については、個人単位の期間制限(第8の6参照)と事業所単位
の期間制限(第8の5参照)の2種類を示す必要がある点に留意すること(第7の13の(4)参
照)。
(ロ) 当該明示については、派遣労働者が派遣先における派遣就業に係る期間の制限を認識でき
ることが派遣労働者のために望ましく、また、派遣先に対して派遣可能期間の制限の規定を遵
守させるためにも有用であることから、行われるものである。
(ハ)派遣元事業主は、上記の個人単位と事業所単位の期間制限の抵触日の明示を行うに当たっ
ては、当該個人単位の期間制限の抵触日以降同一の組織単位に派遣された場合、又は、派遣先
において過半数労働組合等の意見聴取がされずに当該事業所単位の期間制限の抵触日以降派遣
された場合には、法第40条の6の労働契約申込みみなし制度の適用があり、派遣先は当該派遣
労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を明示すること。これ
は、労働契約申込みみなし制度が適用される場合が必ずしも派遣労働者にとって明らかでない
ことがあるので、明示することによって派遣労働者が労働契約申込みみなし制度の適用がある
場合を認識することを容易にしようとするものである。
ホ その他
派遣先は、事業所における派遣可能期間を延長した時は、速やかに、当該労働者派遣をする派
遣元事業主に対し、当該業務について派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知
しなければならない(法第40条の2第7項)。
なお、当該通知については、派遣先から派遣元事業主に対して、通知すべき事項に係る書面の
交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信をすることにより行わな
ければならない(則第33条の6、第8の5の(5)参照)。
(3)比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供
イ 概要
労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらか
じめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象
労働者の賃金その他の待遇等に関する情報を提供しなければならない(法第26条第7項)。
また、派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から、当該情報提供がな
いときは、当該者との間で、労働者派遣契約を締結してはならない(法第26条第9項)。
ロ 意義
派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について、派遣先に雇用される通常の労働者との間で均等
・均衡待遇(法第30条の3第1項又は第2項の規定に基づき、派遣先に雇用される通常の労働者
との間で不合理な待遇の禁止等に係る措置を講ずることをいう。以下同じ。)を確保しなければ
ならない(法第30条の3)。派遣元事業主は、派遣労働者の均等・均衡待遇を確保するため、派
-149 -
第6 労働者派遣契約
遣先の労働者の待遇等に関する情報が必要となることから、労働者派遣の役務の提供を受けよう
とする者に対し、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、比較対象労働者の待遇等に
関する情報を派遣元事業主に提供する義務を課すこととしたものである。
ハ 比較対象労働者の内容
(イ) 比較対象労働者とは、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労
働者であって、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)
並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であ
ると見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者であり、具体的には、
次に掲げる労働者である(法第26条第8項、則第24条の5)。
なお、比較対象労働者の選定に際しては、派遣労働者が就業する場所にとどまらず、労働者
派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所全体の労働者が対象となることに留意が必要で
ある。
① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込
まれる通常の労働者
②(力に該当する労働者がいない場合にあっては、職務の内容が派遣労働者と同一であると見
込まれる通常の労働者
③ ①及び②に該当する労働者がいない場合にあっては、業務の内容又は責任の程度のいずれ
かが派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
④ ①~③に該当する労働者がいない場合にあっては、職務の内容及び配置の変更の範囲が派
遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
⑤(力~④に該当する労働者がいない場合にあっては、(力から④までに相当する短時間・有期
雇用労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年
法律第76号。以下「短時間・有期雇用労働法」という。)第2条第3項に規定する「短時間
・有期雇用労働者」をいう。)
当該短時間・有期雇用労働者の待遇については、労働者派遣の役務の提供を受けようとす
る者が雇用する通常の労働者の待遇との間で、短時間・有期雇用労働法第8条に基づき、不
合理と認められる相違を設けてはならない(なお、中小企業事業主(※)においては、短時
間・有期雇用労働法が2021年4月1日より適用されるため、同年3月31日までの間は、短時
間労働者にあっては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年
法律第71号)による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律
第76号)第8条に基づき、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の
労働者との間の待遇の相違は不合理と認められるものであってはならず、有期雇用労働者に
あっては、労働契約法(平成19年法律第128号)第20条に基づき、労働者派遣の役務の提供
を受けようとする者に雇用される無期雇用労働者との間の労働条件の相違は不合理と認めら
れるものであってはならない。)。
-150 -
第6 労働者派遣契約
(※)資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業
主について5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事
業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主につい
ては50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下であ
る事業主
⑥(力~⑤に該当する労働者がいない場合にあっては、派遣労働者と同一の職務の内容で業務
に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該通常の労
働者(以下「仮想の通常の労働者」という。)
仮想の通常の労働者の待遇は、実際に雇い入れた場合の待遇であることを証する一定の根
拠に基づき決定されていることが必要である。「一定の根拠」とは、例えば、これまで適用
実績はないが、仮に雇い入れるとすれば適用される待遇が示されている就業規則であって、
労働基準監督署に届け出ている就業規則、労働基準監督署には届け出ていないがモデル就業
規則に基づき作成している就業規則等が考えられ、労働者派遣の役務の提供を受けようとす
る者が明示的に説明できることが必要である。
また、仮想の通常の労働者は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される
通常の労働者との間で適切な待遇が確保されている必要がある。「適切な待遇が確保されて
いる」とは、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者が、仮想の通常の労働者の待遇に
ついて、実際に雇用する通常の労働者との間で「職務の内容」、「職務の内容及び配置の変
更の範囲」等も考慮しつつ、客観的・具体的な実態に照らして不合理でないことについて派
遣元事業主に説明できる状態であることをいう。
なお、仮想の通常の労働者については、その時点では実在しない労働者を指すが、例えば、
過去1年以内に雇用していた者や現存する就業規則等に基づき設定され、適用実績のある労
働者の標準的なモデルがある場合は、当該者が(力から⑤までに該当する可能性があることに
留意すること。
(ロ)比較対象労働者が(イ)の(力から⑤までの同じ分類に複数の労働者が該当する場合には、労働
者派遣の役務の提供を受けようとする者は、例えば、次の観点から、派遣労働者と最も近いと
考える者を選定すること。
・ 基本給の決定等において重要な要素(職能給であれば能力・経験、成果給であれば成果な
ど)における実態
・ 派遣労働者と同一の事業所に雇用されているかどうか
(ハ)(イ)の(力から⑤までの比較対象労働者に関しては、例えば、次に掲げる者又は区分等を比較
対象として選定することが考えられる。
・ 一人の労働者
・ 複数人の労働者又は雇用管理区分
・ 過去1年以内に雇用していた一人又は複数人の労働者
-151-
第6 労働者派遣契約
・ 労働者の標準的なモデル(新入社員、勤続〇年目の一般職など)
比較対象労働者の選定手順
労働者派遣の役務の提供を受けようとする者が比較対象労働者を選定するに当たっては、その
雇用する労働者と受け入れようとする派遣労働者との間で「職務の内容」及び「職務の内容及び
配置の変更の範囲」が同一であるかどうかを以下の(イ)から(ハ)までに基づき判断すること。
(イ)「通常の労働者」の定義
「通常の労働者」とは、いわゆる正規型の労働者及び期間の定めのない労働契約を締結して
いるフルタイム労働者(以下「無期雇用フルタイム労働者」という。)をいう。「いわゆる正
規型の労働者」とは、労働契約の期間の定めがないことを前提として、社会通念に従い、当該
労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、
賃金の主たる部分の支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇給の有無)を総合的に勘案
して判断するものであること。また、「無期雇用フルタイム労働者」とは、その業務に従事す
る無期雇用労働者のうち、1週間の所定労働時間が最長の労働者をいうこと。
(ロ)「職務の内容」が同一であると見込まれることの判断
a 「職務の内容」の定義
「職務の内容」とは、「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」をいう。
「業務の内容」とは、職業上継続して行う仕事の内容をいう。
「責任の程度」とは、業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度
等をいうこと。具体的には、授権されている権限の範囲(単独で契約締結可能な金額の範囲、
管理する部下の数、決裁権限の範囲等)、業務の成果について求められる役割、トラブル発
生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度、ノルマ等の成果への期待の程度等を指す。
b 「職務の内容」が同一であると見込まれることの判断手順
「職務の内容が同一である」とは、個々の作業まで完全に一致していることを求めるもの
ではなく、それぞれの労働者の職務の内容が「実質的に同一」であることを意味するもので
あり、「業務の内容」が「実質的に同一」であるかどうかを判断し、次いで「責任の程度」
が「著しく異なって」いないかを判断するものであること。また、これらの判断に当たって
は、将来にわたる可能性についても勘案した上で、「同一であると見込まれる」かどうかを
判断すること。
まず、「業務の内容」が「実質的に同一」であることの判断に先だって、「業務の種類」
が同一であるかどうかを確認する。これは、『厚生労働省編職業分類』の細分類を目安とし
て比較し、この時点で異なっていれば、「職務の内容が同一でない」と判断することとなる。
他方、「業務の種類」が同一であると判断された場合には、次に労働者派遣の役務の提供
を受けようとする者に雇用される労働者及び派遣労働者の職務を業務分担表、職務記述書等
により個々の業務に分割し、その中から「中核的業務」をそれぞれ抽出する。
なお、「中核的業務」とは、ある労働者に与えられた職務に伴う個々の業務のうち、当該
-152 -
第6 労働者派遣契約
職務を代表する中核的なものを指し、以下の基準に従って総合的に判断する。
(力 与えられた職務に本質的又は不可欠な要素である業務
② その成果が事業に対して大きな影響を与える業務
③ 労働者本人の職務全体に占める時間的割合・頻度が大きい業務
労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される労働者と派遣労働者について、
抽出した「中核的業務」を比較し、同じであれば、「業務の内容」は「実質的に同一」と判
断し、明らかに異なっていれば、業務の内容は「異なる」と判断する。なお、抽出した「中
核的業務」が一見すると異なっている場合には、当該業務に必要とされる知識や技能の水準
等を含めて比較した上で、「実質的に同一」と言えるかどうかを判断する。
ここまで比較した上で「業務の内容」が「実質的に同一である」と判断された場合には、
最後に、両者の業務に伴う「責任の程度」が「著しく異なって」いないかどうかを確認する
こと。その確認に当たっては、「責任の程度」の内容に当たる以下のような事項について比
較を行う。
① 授権されている権限の範囲(単独で契約締結可能な金額の範囲、管理する部下の数、決
裁権限の範囲等)
② 業務の成果について求められる役割
③ トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度
④ ノルマ等の成果への期待の程度
⑤ 上記の事項の補助的指標として所定外労働の有無及び頻度
この比較においては、例えば、管理する部下の数が一人でも違えば、「責任の程度」が異
なる、といった判断をするのではなく、「責任の程度」の差異が「著しい」といえるもので
あるかどうかを見るものであること。なお、いずれも役職名等外見的なものだけで判断せず、
実態を見て比較することが必要である。
以上の判断手順を経て、「業務の内容」及び「責任の程度」の双方について、労働者派遣
の役務の提供を受けようとする者に雇用される労働者と派遣労働者が同一であると判断され
た場合が、「職務の内容が同一である」こととなる。
(ハ)「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であると見込まれることの判断
a 「職務の内容及び配置の変更の範囲」の定義
現在の我が国の雇用システムにおいては、長期的な人材育成を前提として待遇に係る制度
が構築されていることが多く、このような人材活用の仕組み、運用等に応じて待遇の違いが
生じることも合理的であると考えられている。
人材活用の仕組み、運用等については、ある労働者が、ある事業主に雇用されている間又
はある派遣先に派遣されている間にどのような職務経験を積むこととなっているかを見るも
のであり、転勤、昇進を含むいわゆる人事異動や本人の役割の変化等(以下「人事異動等」
という。)の有無や範囲を総合判断するものであるが、これを法律上「職務の内容及び配置
-153 -
第6 労働者派遣契約
の変更の範囲」と規定したものである。
「職務の内容の変更」と「配置の変更」は、現実にそれらが生じる際には重複が生じ得る
ものである。つまり、「職務の内容の変更」とは、配置の変更によるものであるか、そうで
なく業務命令によるものであるかを問わず、職務の内容が変更される場合を指すこと。他方、
「配置の変更」とは、人事異動等によるポスト間の移動を指し、結果として職務の内容の変
更を伴う場合もあれば、伴わない場合もあるものであること。
それらの変更の「範囲」とは、変更により経験する職務の内容又は配置の広がりを指すも
のである。
b 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であると見込まれることの判断における留意
点
「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であるかどうかの判断にあたっては、一つ一
つの「職務の内容及び配置の変更」の態様が同様であることを求めるものではなく、それら
の変更が及び得ると予定されている範囲を画した上で、これが同一であるかどうかを判断す
る。例えば、ある会社において、一部の部門に限っての人事異動等の可能性がある者と、全
部門にわたっての人事異動等の可能性がある者とでは、「配置の変更の範囲」が異なること
となり、「職務の内容及び配置の変更の範囲」(人材活用の仕組み、運用等)が同一である
とは言えない。
ただし、「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であるかどうかの判断に当たっては、
その「範囲」が完全に一致することまでを求めるものではなく、実質的に同一と考えられる
かどうかという観点から判断するものである。
また、「職務の内容及び配置の変更の範囲」(人材活用の仕組み、運用等)が同一である
かどうかを判断するに当たっては、将来にわたる可能性についても勘案するものである。た
だし、この「将来にわたる可能性」(見込み)については、労働者派遣の役務の提供を受け
ようとする者の主観によるものではなく、文書や慣行によって確立されているものなど客観
的な事情によって判断されるものであること。また、例えば、労働者派遣の役務の提供を受
けようとする者に雇用される通常の労働者の集団は定期的に転勤等があることが予定されて
いるが、ある職務に従事する派遣労働者については転勤等がないという場合にも、そのよう
な形式的な判断だけでなく、例えば、同じ職務に従事している他の派遣労働者には転勤等が
あるといった「可能性」についての実態を考慮して具体的な見込みがあるかどうかで判断す
るものである。
なお、育児又は家族介護などの家族的責任を有する労働者については、その事情を配慮し
た結果として、その労働者の人事異動等の有無や範囲が他と異なることがあるが、「職務の
内容及び配置の変更の範囲」を比較するに当たっては、そのような事情を考慮することが必
要となる。例えば、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者
のうち、人事異動等があり得る人材活用の仕組み、運用等である者が、育児又は家族介護に
-154 -
第6 労働者派遣契約
関する一定の事由で配慮がなされ、その配慮によって異なる取扱いを受けた場合、「職務の
内容及び配置の変更の範囲」を比較するに際しては、その取扱いについては除いて比較する
ことが考えられる。
C 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であると見込まれることの判断手順
まず、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者と派遣労働
者について、配置の変更に関して、転勤の有無が同じかどうかを比較すること。この時点で
異なっていれば、「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であると見込まれないと判断
することとなる。
次に、転勤が双方ともあると判断された場合には、全国転勤の可能性があるのか、エリア
限定なのかといった転勤により移動が予定されている範囲を比較する。この時点で異なって
いれば、「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であると見込まれないと判断すること
となる。
転勤が双方ともない場合、及び双方ともあってその範囲が実質的に同一であると判断され
た場合には、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者における「職務の内容」の変更の
態様について比較する。まずは、「職務の内容」の変更(労働者派遣の役務の提供を受けよ
うとする者における「配置」の変更の有無を問わない。)の有無を比較し、この時点で異な
っていれば、「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同一であると見込まれないと判断する
こととなる。同一であれば、「職務の内容」の変更により経験する可能性のある範囲も比較
し、同一であるかどうかを判断する。
ニ 情報提供の方法
比較対象労働者の待遇に関する情報提供については、労働者派遣契約の締結に際し、あらかじ
め、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から派遣元事業主に対して、情報提供すべき事
項に係る書面の交付若しくはファクシミリをしてする送信又は電子メール等の送信をすることに
より行わなければならない(則第24条の3第1項)。
ホ 情報提供に係る書面等の保存
派遣元事業主は、比較対象労働者の待遇に関する情報提供に係る書面等を、派遣先は、当該書
面等の写しを、労働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から起算して3年を経過する日
まで保存しなければならない(則第24条の3第2項)。
へ 情報提供すべき事項
(イ) 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象
派遣労働者に限定しないことを定める場合
次のaからeまでに掲げる情報を提供しなければならない。
a 比較対象労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
(a)職務の内容
「職務の内容」とは、業務の内容及び当該業務の内容に伴う責任の程度をいう。
-155 -
第6 労働者派遣契約
「業務の内容」とは、職業上継続して行う仕事の内容をいう。『厚生労働省編職業分類』
等を参考として、具体的な内容を提供すること。
「責任の程度」とは、業務に伴って行使するものとして付与されている授権の範囲・程度
等をいう。具体的には、授権されている権限の範囲(単独で契約締結可能な金額の範囲、管
理する部下の数、決裁権限の範囲等)、業務の成果について求められる役割、トラブル発生
時や臨時・緊急時に求められる対応の程度、ノルマ等の成果への期待の程度等を指すもので
あり、それぞれについて具体的な内容を提供すること。
(b)職務の内容及び配置の変更の範囲
「職務の内容及び配置の変更の範囲」とは、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者
に雇用される労働者が、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用されている間に
どのような職務経験を積むこととなっているかを見るものであり、転勤、昇進を含むいわゆ
る人事異動や本人の役割の変化等の有無や範囲を総合判断するものであるが、これらの具体
的な内容を提供すること。
(C)雇用形態
ここでいう「雇用形態」とは、通常の労働者、短時間労働者、有期雇用労働者又は仮想の
通常の労働者をいう。比較対象労働者がこれらのどの雇用形態に該当するか、これとあわせ
て雇用期間(期間の定めのある労働契約を更新している有期雇用労働者にあっては、当初の
労働契約の開始時からの通算雇用期間をいう。)を提供することが必要であることに留意す
ること。
b 比較対象労働者を選定した理由
次に掲げる事項を情報提供することが必要。
・ ハの(イ)の(力から⑥までのうち選択した比較対象労働者の分類とその理由。例えば、ハ
の(イ)の③の比較対象労働者を選定した場合の理由は、「派遣労働者と職務の内容が同一
である通常の労働者はいないが、業務の内容が同一である通常の労働者がいるため」と記
載すること等が考えられる。
・ 比較対象労働者としてどういう者又は区分等を情報提供するか(一人の労働者、複数人
の労働者、雇用管理区分、過去1年以内に雇用していた一人又は複数人の労働者、労働者
の標準的なモデル(新入社員、勤続〇年目の一般職など))
C 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、
その旨を含む。)
次に掲げるいずれかの内容を情報提供することが必要。なお、待遇ごとに(a)~(C)のいずれ
の方法によることとしても差し支えない。ただし、例えば、扶養家族の人数に応じて支給され
る家族手当等、機械的に計算・適用がなされる待遇であって、扶養家族の人数などの比較対象
労働者と派遣労働者のとの間で計算・適用の前提となる実態が異なり得るものについては、
(C)の内容が提供されることが必要であることに留意すること。また、基本給等が時給単位で
-156 -
第6 労働者派遣契約
確認できるよう、年間の所定労働時間をあわせて提供することが必要であることに留意するこ
と。
(a)比較対象労働者が一人である場合に、当該者に対する個別具体の待遇の内容。例えば、
賃金であればその額、教育訓練であればその実施状況。
(b)比較対象労働者が複数人である場合に、これらの者に対する個別具体の待遇の内容。数
量的な待遇については平均額又は上限・下限額、数量的でない待遇については標準的な内容
又は最も高い水準・最も低い水準の内容。
(C)比較対象労働者が一人又は複数人である場合に、それぞれの適用している待遇の実施基
準(比較対象労働者の賃金水準等を把握できるものに限る。)。例えば、賃金であれば、賃
金テーブル及び等級表等の支給基準並びに比較対象労働者が当該賃金テーブル及び等級表等
の賃金水準のいずれに該当するかがわかるもの。
d 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
待遇の具体的な性質や待遇を行う具体的な目的をいうこと。例えば、通勤手当であれば
「通勤に要する交通費を補填する目的」、精皆勤手当であれば「一定数の業務を行う人数を
確保するため、皆勤を奨励する目的」等が考えられること。
e 比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更
の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たって考慮したもの
考慮した具体的な職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情をいう
こと。
(ロ) 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象
派遣労働者に限定することを定める場合
次のa及びbに掲げる情報を提供すること。
a 法第40条第2項の教育訓練(派遣先が派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先に雇用さ
れる労働者に対して行う業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練をいう。このa
において単に「教育訓練」という。)の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨)
教育訓練の実施の有無及び具体的な内容をいうこと。
b 則第32条の3各号に掲げる福利厚生施設(派遣先が派遣先に雇用される労働者に対して利
用の機会を与える給食施設、休憩室及び更衣室をいう。このbにおいて単に「福利厚生施設」
という。)の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨)
福利厚生施設それぞれの利用の機会の付与の有無及び利用時間等の具体的な内容をいうこ
と。
ト 比較対象労働者の待遇に関する情報の取扱い
(イ) 比較対象労働者の待遇等に関する情報のうち個人情幸酎こ該当するものの保管又は使用は、
法第30条の3等の規定による待遇の確保等の目的に限られるものである(派遣元指針第2の11
の(1)のニ)。
-157 -
第6 労働者派遣契約
(ロ)比較対象労働者の待遇に関する情報のうち個人情幸酎こ該当しないものの保管及び使用につ
いては、個人情報保護法の適用はないが、派遣元事業主は、当該情報の保管又は使用を法第30
条の3等の規定による待遇の確保等の目的の範囲に限定する等適切に対応することが必要であ
る(派遣元指針第2の11の(4))。この「等」には、例えば、当該情報の保存義務経過後に利
用することがなくなった情幸酎こついて、当該情報を速やかに消去すること等が含まれる。
(ハ) 比較対象労働者の待遇等に関する情幸田ま、法第24条の4の秘密を守る義務の対象となるた
め、派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなけれ
ば、その業務上取り扱ったことについて知り得た比較対象労働者の待遇等に関する情報を他に
漏らしてはならない。
(ニ) この他、例えば、派遣先に雇用される通常の労働者が1名である場合等、比較対象労働者
が一定の個人に特定されるおそれがある場合には、労働者派遣の役務の提供を受けようとする
者は、当該比較対象労働者の意向を掛酌し、比較対象労働者の待遇等の情報を提供する際、個
人が特定されないよう、標準的なモデルとしての待遇情報を提供すること等の配慮を行うこと
が考えられる。
チ 派遣先に雇用される通常の労働者がいない場合の取扱い
派遣先に雇用される通常の労働者がいない場合、法第30条の3の規定は適用されない。比較対
象労働者の待遇に関する情報提供は、同条の適正な履行のために行うものであり、当該場合には、
当該情報提供を行う必要はないものであること。
リ 変更時の情報提供
(イ) 概要
派遣先は、比較対象労働者の待遇等に関する情幸酎こ変更があったときは、遅滞なく、派遣元
事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない(法第26条第10項)。
(ロ) 意義
労働者派遣契約を締結するに当たって提供された比較対象労働者の待遇等に関する情幸酎こ変
更があった場合には、その変更の内容によっては、派遣労働者の待遇と派遣先に雇用される通
常の労働者の待遇との間で不合理な待遇差が生じることとなりかねない。このため、派遣元事
業主は、変更された比較対象労働者の待遇等に関する情報をもとに、派遣労働者の待遇を変更
することについて検討し、必要な対応を行うことができるよう、派遣先に対し、労働者派遣契
約の締結に当たっての比較対象労働者の待遇等に関する情報提供と同様の義務を課すこととし
たものである。
(ハ) 変更時の情報提供の内容
への情報提供すべき事項のうち変更があった内容を提供すること。あわせて、当該変更が生
じた時点を提供することが必要であることに留意すること。
(ニ) 変更の内容に関する情報提供の方法
比較対象労働者の待遇等に関する情報の変更時の情報提供については、当該情報の変更があ
ー158 -
第6 労働者派遣契約
ったときは、遅滞なく、派遣先から派遣元事業主に対して、情報提供すべき事項に係る書面の
交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信をすることにより行わ
なければならない(則第24条の6第1項)。
「遅滞なく」とは、1か月以内に派遣労働者の待遇に適正に反映されるよう、可能な限り速
やかに情報提供を行うことをいうこと。なお、派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について、
情報提供を受けた時点からではなく、比較対象労働者の待遇が変更された時点から、法第30条
の3に基づき、派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保しなければならないこと
に留意すること。
(ホ) 変更時の情報提供が不要である場合
a 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定めた労働者派遣契約に基づき現に
行われている労働者派遣契約に係る派遣労働者の中に協定対象派遣労働者以外の者がいない
場合には、法第40条第2項の教育訓練(派遣先が派遣先に雇用される労働者に対して行う業
務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練)及び則第32条の3各号に掲げる福利厚生
施設(派遣先が派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える給食施設、休憩室及
び更衣室)を除き、比較対象労働者の待遇等に関する情報の変更時の派遣先から派遣元事業
主に対する当該変更の内容に関する情報の提供を要しない(則第24条の6第2項)。
b 労働者派遣契約が終了する目前一週間以内における変更であって、当該変更を踏まえて派
遣労働者の待遇を変更しなくても法第30条の3の規定に違反しないものであり、かつ、当該
変更の内容に関する情報の提供を要しないものとして労働者派遣契約で定めた範囲を超えな
いものが生じた場合には、比較対象労働者の待遇等に関する情報の変更時の派遣先から派遣
元事業主に対する当該変更の内容に関する情報の提供を要しない(則第24条の6第3項)。
(へ) 変更時の情報提供に係る書面等の保存
派遣元事業主は、比較対象労働者の待遇等に関する変更時の情報提供に係る書面等を、派遣
先は、当該書面等の写しを、労働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から起算して3
年を経過する日まで保存しなければならない(則第24条の6第4項)。
ヌ 比較対象労働者の待遇等に関する情報を捏供せず、又は虚偽の情報を提供した場合の取扱い
厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者が比較対象労働者の待遇等に関
する情報を捏供せず、若しくは虚偽の情報を提供した場合又は派遣先が比較対象労働者の待遇等
に関する情幸酎こ変更があったときに当該変更の内容に関する情報を捏供せず、若しくは虚偽の情
報を提供した場合又はこれらの場合に派遣先等に法第48条第1項の規定による指導又は助言をし
たにもかかわらず、当該派遣先等がその指導等に従わなかった場合等には、当該派遣先等に対し、
当該派遣就業を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる(法第49条の
2第1項)。
また、厚生労働大臣は、当該勧告を行った場合において、その勧告を受けた者がこれに従わな
かった場合には、その旨を公表することができる(法第49条の2第2項)。
-159 -
第6 労働者派遣契約
(4)派遣料金の配慮
イ 概要
労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額
(以下「派遣料金」という。)について、派遣元事業主が派遣先に雇用される通常の労働者との
間の均等・均衡待遇の確保のための措置及び一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保の
ための措置を遵守することができるように配慮しなければならない(法第26条第11項)。
ロ 意義
派遣元事業主が、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働者
との間の均等・均衡待遇の確保のための措置及び一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確
保のための措置を行う場合には、これらの措置を行うための原資を確保することが必要となるた
め、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先に対し、派遣料金に関する配慮義務
を課すこととしたものである。
ハ 派遣料金の配慮に関する留意点
(イ) この派遣料金の配慮義務は、労働者派遣契約の締結又は更新の時だけではなく、当該締結
又は更新がなされた後にも求められる(派遣先指針第2の9の(2)のイ)。
(ロ)また、派遣先は、派遣料金の決定に当たっては、派遣労働者の就業の実態、労働市場の状
況、当該派遣労働者が従事する業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度並びに当該派遣労働
者に要求する技術水準の変化等を勘案するよう努めなければならない(派遣先指針第2の9の
(2)のロ)。
(ハ)例えば、派遣元事業主から要請があるにもかかわらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応
じない場合や、派遣元事業主が法第30条の3又は法第30条の4第1項に基づく賃金を確保する
ために必要な額を派遣先に提示した上で派遣料金の交渉を行ったにもかかわらず、派遣料金が
当該額を下回る場合には、配慮義務を尽くしたとは解されず、指導の対象となり得るものであ
ること。
(5)海外派遣の場合の労働者派遣契約
イ 概要
派遣元事業主は海外派遣(第5の3の(2)参照)に係る労働者派遣契約の締結に際しては、上
記(1)及び(2)で定めるもののほか、ハの派遣先が講ずべき措置等を定めた事項を書面に記載して、
当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に対し、当該定めた事項に係る書面の交付若しくはフ
ァクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信をすることにより通知しなければならな
い(法第26条第2項、則第23条、則第24条)。
ロ 意義
海外派遣の場合の労働者派遣契約の定めに関する措置は、当該海外派遣が行われる場合、法が
派遣先に適用されないことから、特に労働者派遣契約において派遣先の講ずべき措置を定めさせ
-160 -
第6 労働者派遣契約
ることにより、民事的にその履行を確保させようとするものである。
ハ 派遣先の講ずべき措置の定め
海外派遣の場合には、特に派遣先の講ずべき措置として次に掲げる事項を定めなくてはならな
い(則第24条)。
① 派遣先責任者を選任すること。
法第41条の規定による派遣先責任者の選任と同様の方法とすること(第8の11参照)
② 派遣先管理台帳の作成、記載及び通知を行うこと。
法第42条第1項及び第3項の規定による派遣先管理台帳の作成、記載及び通知と同様の
方法とすること(第8の12参照)。
③ 派遣労働者に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講ずるこ
と。
法第39条の規定による措置と同様のものとすること(第8の2参照)。
④ 派遣労働者の派遣先における就業に伴って生ずる苦情等について、派遣元事業主に通知し、
その適切かつ迅速な処理を図ること。
法第40条第1項と同様のものとすること(第8の3参照)。
⑤ 法第40条第2項に規定する教育訓練の実施等必要な措置と同様の規定
⑥ 法第40条第3項に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与と同様の規定
⑦ 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助を
行うこと。
海外への派遣であるために、特に求められる派遣労働者の福祉の増進のための援助であ
る。
「その他派遣労働者の福祉の増進のための援助」とは、例えば、派遣労働者の帰国に対
する援助である。
⑧ 事業所単位の期間制限に係る派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知を行
うこと。
法第26条第4項と同様のものとすること((2)、第8の5及び⑪参照)。
⑨ 第8の5の(3)のイの①から⑥までに掲げる労働者派遣以外の労働者派遣を行う場合におい
て、当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所におけ
る組織単位の業務について継続して1年以上、同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者
派遣の役務の提供を受けた場合であって、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるた
め、労働者を雇い入れようとするときの、当該特定有期雇用派遣労働者の雇用に関する措置
法第40条の4と同様のものとすること(第8の8参照)。
⑲ 同一の事業所等において、派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者に
係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、当該場所において通常の労働者の募集
を行う時は、当該募集情報の提供に関する措置。また、特定有期雇用派遣労働者が、事業所
-161-
第6 労働者派遣契約
等における同一の組織単位の業務について3年間継続して従事する見込みがある場合におい
て、当該場所において労働者の募集をし、かつ、派遣元事業主から派遣先に対して労働契約
の申込みが求められた時は、当該募集情報の提供に関する措置。
法第40条の5と同様のものとすること(第8の8、第8の9参照)。
⑪ 法第40条の9第2項の離職後1年以内の派遣労働者の受入れ禁止について、派遣先が派遣元
事業主より派遣する労働者名等の通知を受けたときに、その者を受け入れたときに当該離職後
1年以内の受け入れ禁止規定に抵触する場合は、速やかにその旨を通知する旨(第8の10参
照)。
⑫ その他派遣就業が適正に行われるため必要な措置を行うこと。
(参考) 海外派遣に係る労働者派遣契約における派遣先が講ずべき措置の定めの例(特定有期雇
用派遣労働者の場合)
〇〇〇〇株式会社東京支店(甲)と、□□□□株式会社(乙)は甲の労働者2人を乙のアメ
リカ支局における秘書業務に従事させるための労働者派遣について次の事項を約するものとする
1 乙は甲の労働者に係る次の業務を行う派遣先責任者を1人選任すること。
(1)次に掲げる事項の内容を、当該甲の労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にあ
る者その他の関係者に周知すること。
a 当該甲の労働者に係る労働者派遣契約の定め
b 当該甲の労働者に係る甲からの通知
(2)当該契約に基づく労働者派遣に係る業務について、契約締結後に労働者派遣の役務の提供
を受ける期間を定めた場合又はこれを変更した場合の甲への通知及び派遣先管理台帳の作
成、記録、保存及び通知に関すること。
(3)当該甲の労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
(4)当該甲の労働者の安全及び衛生に関し、乙の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管
理する者及び甲との連絡調整を行うこと。
(5)(1)~(4)に掲げるもののほか、甲との連絡調整に関すること。
2 乙は甲の労働者の就業に関し、派遣先管理台帳を作成するものとし、当該派遣先管理台帳に
次の事項について甲の労働者ごとに記載し、このうち(1)、(6)、(7)、(8)及び(9)につき
甲に通知すること。
(1)甲の労働者の氏名
(2)有期雇用派遣労働者(無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者の別)
(3)60歳未満(60歳以上の者か否かの別)
(4)甲の事業主の名称
(5)甲の事業所の名称及び所在地
-162 -
第6 労働者派遣契約
(6)派遣就業をした日
(7)派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
(8)従事した業務の種類
(9)派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業を
した場所
(10)教育訓練を行った日時及び内容
(11)派遣労働者からの苦情の申出を受けた苦情の処理に関する事項
(12)派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
3 乙は本契約に定める甲の労働者の就業条件の定めに反することのないように適切な措置を講
ずること。
4 乙は甲の労働者の派遣就業に伴って生じる苦情等について、甲に通知するとともに、甲との
密接な連携の下に誠意をもって、遅滞なく、その適切かつ迅速な処理を図ること。
5 乙は甲の労働者の疾病、負傷等に際し療養の実施を行うほか、甲の労働者の福祉の増進のた
めに必要な援助を行うこと。
6 乙は甲の労働者の派遣期間終了後等の帰国について責任をもって行うこと。
7 乙が甲から本契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けることにより、当該業務について
派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日は〇年〇月〇日であること。
8 乙は甲から本契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者の氏名の通知を受けた場合に、当該
労働者が乙を離職して1年を経過していない者である場合はその旨を甲に通知すること。ただ
し、当該者が60歳以上の定年退職者である場合は除く。
9 乙は、甲からの求めに応じ、本契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者について、当該派
遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する乙の労働者が従事する業務の遂行に必要な能
力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者に対しても実施するなど必要な措置
を講じなければならないこと。
10 乙は、乙に雇用される労働者に対して利用の機会を与える給食施設、休憩室、及び更衣室に
ついては、本契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者に対しても、利用の機会を与えなけれ
ばならないこと。
11乙は、甲からの求めに応じ、乙に雇用される労働者に関する情報、本契約に基づく労働者派
遣に係る派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報を提供する等必要な協力をするよう配慮
しなければならないこと。
12 乙は1年以上の期間甲の同一の労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において
、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため労働者を雇い入れようとするときは、当
該同一の業務に派遣実施期間中継続して従事した甲の当該同一の労働者を遅滞なく雇い入れる
よう努めなければならないこと。ただし、当該同一の労働者が継続就業を希望する旨を乙に申
し出ない場合、又は希望する旨を乙に申し出た場合でも、甲が乙に対し当該同一の労働者に対
-163 -
第6 労働者派遣契約
する労働契約の申込みを依頼しない場合はこの限りではないこと。
13 乙は、乙の同一の事業所その他派遣就業の場所において甲から1年以上の期間継続して同一
の労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事業所その他派遣就
業の場所において通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の
場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、業務の内容、賃金、労働時間その他の
当該募集に係る事項を当該同一の労働者に周知しなければならないこと。
14 乙は、乙の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して3
年間従事する見込みがある有期雇用派遣労働者に対しては、当該事業所その他派遣就業の場所
において労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示する
ことその他の措置を講ずることにより、業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る
事項を当該有期雇用派遣労働者に周知しなければならないこと。
15 乙は、乙に雇用される通常の労働者であって、その職務の内容並びに当該職務の内容及び配
置の変更の範囲が、本契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるも
の等の当該派遣労働者と比較すべき労働者の待遇等に関する情報を甲に提供するとともに、当
該情幸酎こ変更があったときは、遅滞なく、当該変更の内容に関する情報を甲に提供しなければ
ならないこと。
16 乙は、甲が派遣労働者の不合理な待遇の禁止等に関する措置を遵守できるよう、労働者派遣
に関する料金の額について配慮しなければならないこと。
ニ 海外派遣に係る労働者派遣契約の締結の際の手続等
派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、上記ハの契約内容を当該海外
派遣に係る派遣先に対して、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メー
ル等の送信をすることにより通知しなければならない(則第23条)。
ホ 派遣先が当該労働者派遣契約の定めに反した場合
(イ)派遣先が当該海外派遣に係る労働者派遣契約の定めに反した場合、当該契約について債務
不履行となり、派遣元事業主は、その履行を派遣先に求めることができ、また、それを理由
に労働者派遣契約を解除することができる。
(ロ)したがって、海外派遣については、派遣元事業主を通じて、派遣先における一定の措置の
履行を確保するものである。
(6)派遣元事業主であることの明示
イ 概要
派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、当該契約の相手方
に対し、当該事業所について労働者派遣事業の許可を受けている旨を明示しなければならない
(法第26条第3項)。なお、経過措置期間中の特定労働者派遣事業の派遣元事業主においては、
特定労働者派遣事業の届出書を提出している旨を明示しなければならない。
-164 -
第6 労働者派遣契約
口 具体的な明示の方法
具体的な明示の方法は次により行うこと。
(力 労働者派遣事業を行う事業主は、許可証に記載される許可番号により明示すること。
② 経過措置期間中の特定労働者派遣事業を行う事業主は、届出受理通知書に記載される届出
受理番号により明示すること。
3 労働者派遣契約の解除の制限
(1)概要
労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労
働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない
(法第27条)。
(2)意義
イ 禁止されるのは、労働者派遣契約について、業として行われる労働者派遣であると否とを問
わず、また、当該労働者派遣契約の一部であるか全部であるかを問わず、これを解除する行為
である。
なお、労働者派遣の役務の提供を受ける者が労働者派遣をする者と合意の上、労働者派遣契
約を解除する場合であっても、(3)の事由を理由とする限り、当該解除は、労働者派遣の役務の
提供を受ける者について禁止されるものである。
ロ 法第27条に違反して、労働者派遣契約を解除した場合には、当該解除は公序良俗に反するも
のとして無効となる。したがって、労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該解除を主張した
としても、労働者派遣をする者は解除の無効を主張して契約の履行を求めることができ、さら
に、損害を被った場合には、損害賠償の請求をすることができる。
(3)労働者派遣契約の解除が禁止される事由
イ 「国籍」とは、国民たる資格で、「信条」とは特定の宗教的又は政治的信念を、「社会的身
分」とは生来的な地位をそれぞれいうものである。
ロ 「労働組合の正当な行為」とは、労働組合法上の労働組合員が行う行為であって、労働組合
の社会的相当行為として許容されるものであるが、具体的には、団体交渉、正当な争議行為は
もちろん、労働組合の会議に出席し、決議に参加し、又は組合用務のために出張する等の行為
も含まれるものである。
これに該当しない行為としては、例えば、いわゆる政治ストや山猫ストがある。
なお、「労働組合の正当な行為」に該当するか否かは、主として派遣労働者が組合員となっ
ている組合と労働者派遣をする事業主との間の問題として決定することとなると考えられる。
ハ 労働者派遣契約の解除が禁止される不当な事由は、労働関係において形成されている公序に
反するものであり、その他には人種、門地、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産したこと、心
身障害者であること、労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、又はこれを結成しよ
-165 -
第6 労働者派遣契約
うとしたこと、法第40条第1項の規定により派遣先へ苦情を申し出たこと、労働者派遣の役務
の提供を受ける者が法に違反したことを関係行政機関に申告したこと等も含まれるものである。
「理由として」とは、国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為
をしたこと等の事由が労働者派遣契約の解除の決定的原因となっていると判断される場合をい
う。この場合、当該事由が決定的原因であるものか否かについては、個々具体的事実に即して
判断する。
4 派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等
(1)概要
労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、
法又は法第3章第4節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を
含む。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除
することができる(法第28条)。
(2)意義
イ 法第31条の規定による派遣元事業主の適正な派遣就業の確保を実質的に担保するためのもの
である。
ロ 解除を行うことができるのは、業として行われると否とを問わず、労働者派遣をする事業主
であり、派遣元事業主以外の事業主であっても労働者派遣をする場合には、当該解除を行える。
ハ 当該労働者派遣の停止又は労働者派遣契約の解除は、直ちに行うことができるものであり、
当該労働者派遣契約において解除制限事由又は解除予告期間が定められていたとしても当該定
めは無効となるものである。
ニ 一般に、契約は、解除事由につき別段の定めがあり、また、契約の当事者の合意がある場合
を除き、法定の解除事由である債務不履行がある場合以外一方的に解除することはできず、一
方的に解除した場合には、債務不履行で損害賠償の責を負うこととなるが、法第28条の規定に
より、当該労働者派遣の停止又は労働者派遣契約の解除により当該労働者派遣の役務の提供を
受ける者が損害を被っても、解除又は停止を行った労働者派遣を行う事業主は債務不履行によ
る損害賠償の責を負うことはない。
(3)労働者派遣契約の解除等を行える具体的事由
労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の規定に違反した場合である。
① 法第39条から第42条まで、第45条第10項及び第14項並びに第46条第7項
② 労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法、雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律の規定であって法第3章第4節の規定により労働者派遣の役務の提供を
受ける者に適用される規定(第9参照)
-166 -
第6 労働者派遣契約
5 労働者派遣契約の解除の非遡及
(1)概要
労働者派遣契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる(法第29条)。
(2)意義
イ 労働者派遣契約は、労働契約と同様に継続的給付の実施を内容とするものであるため、契約
の解除がなされた場合にその効果を遡及すると当該契約の当事者間に著しい不均衡が生じ、給
付の返還を行うことが不可能となる等適当ではないことから、当該労働者派遣契約の解除の意
思表示がなされたとき以後についてのみ解除の効果が生ずることとされたものである。
ロ 法第29条は、強行規定であり、当事者間において、労働者派遣契約においてこれに反する定
めをしても無効となる。
6 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(1)概要
短期間の労働者派遣契約の反復更新に伴い、短期間の労働契約を反復更新することは、派遣労
働者の雇用が不安定になる面があり、望ましくないため、派遣労働者の雇用の安定が図られるよ
うに、派遣元事業主及び派遣先は、労働契約及び労働者派遣契約の締結に当たり必要な配慮をす
るよう努めるとともに、労働者派遣契約の解除に際して、当該労働者派遣契約の当事者である派
遣元事業主及び派遣先が協議して必要な措置を具体的に定めることとしている。
また、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当
たっては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業
主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負
担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならないことと
している(法第26条第1項第8号、法第29条の2、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」
第2の2の(2)(第7の27参照)及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の6の(1)(第
8の19参照))。
(2)派遣先の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
イ 労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置
派遣先は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契
約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣先は派遣労働
者の新たな就業機会の確保を図ること及びこれができないときには少なくとも当該労働者派遣契
約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀
なくされることにより生ずる損害である休業手当、解雇予告手当等に相当する額以上の額につい
て損害の賠償を行うことを定めなければならないこと。また、労働者派遣の期間を定めるに当た
っては、派遣元事業主と協力しつつ、当該派遣先において労働者派遣の役務の提供を受けようと
する期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮
-167 -
第6 労働者派遣契約
をするよう努めること。
ロ 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解
除を行おうとする場合には、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶
予期間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うこと。
ハ 派遣先における就業機会の確保
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の
事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあ
っせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るこ
と。
ニ 損害賠償等に係る適切な措置
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働
者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることと
し、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主
が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損
害の賠償を行わなければならないこと。例えば、当該派遣元事業主が当該派遣労働者を休業さ
せる場合は休業手当に相当する額以上の額について、当該派遣元事業主がやむを得ない事由に
より当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって
行われなかったことにより当該派遣元事業主が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予
告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当
該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害賠償を行わなければ
ならない。その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずるこ
と。また、派遣元事業主及び派遣先の双方に責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主
及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。また、当該
派遣労働者に対しても、派遣元等の責めに帰すべき事由によって、派遣労働者の労働義務が履
行不能となった場合は、民法第536条第2項の規定による反対給付や労働基準法第26条の規定に
よる休業手当を求めることができることを周知すること。
なお、派遣元事業主が派遣労働者を休業させる場合における休業手当に相当する額、又は派
遣元事業主がやむを得ない事由により派遣労働者を解雇する場合における解雇予告手当に相当
する額(=派遣先による労働者派遣契約の解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなか
ったことにより当該派遣元事業主が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日
から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日
までの日数分以上の賃金に相当する額)については、派遣元事業主に生ずる損害の例示であり、
休業手当及び解雇予告手当以外のものについても、それが派遣先の責に帰すべき事由により派
遣元事業主に実際に生じた損害であれば、賠償を行わなければならない。
-168 -
第6 労働者派遣契約
ホ 労働者派遣契約の解除の理由の明示
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする
場合であって、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を
当該派遣元事業主に対し明らかにすること。
(3)派遣元事業主の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
イ 労働契約の締結に際して配慮すべき事項
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該労働者の希望及
び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、労働契約の期間を、当該労働者派遣契
約における労働者派遣の期間と合わせる等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮を
するよう努めること。
ロ 労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置
派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由により労働者
派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除が行われる場合には、派遣先は派遣労
働者の新たな就業機会の確保を図ること及びこれができないときには少なくとも当該労働者派遣
契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余
儀なくされることにより生ずる損害である休業手当、解雇予告手当等に相当する額以上の額につ
いて損害の賠償を行うことを定めるよう求めること。
ハ 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置
派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以
外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先
と連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受けること、当該派遣元事業主
において他の派遣先を確保すること等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就
業機会の確保を図ること。また、当該派遣元事業主は、当該労働者派遣契約の解除に当たって、
新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図
るようにするとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすこと。さらに、
やむを得ない事由によりこれができない場合において、当該派遣労働者を解雇しようとするとき
であっても、労働契約法の規定を遵守することはもとより、当該派遣労働者に対する解雇予告、
解雇予告手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすこと。
(4)その他
イ 労働者派遣契約の契約期間が満了する前に当該労働者派遣契約に基づく派遣就業をしている
派遣労働者を交替させる場合は、当該派遣労働者について6(2)のロ、ハ及びホ並びに(3)のロ
に準じた取扱いをすること。
ロ 労働者派遣契約の解除があった場合に、派遣元事業主が、当該労働者派遣をしていた派遣労
働者との労働契約を変更するよう派遣労働者に強要することは適切ではない旨指導すること。
-169 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
1 概要
労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて
労働に従事するという複雑な形態で事業が行われる。
このため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る観点から、派遣元事業主に対し、適正な雇用管
理のための措置を講じさせる必要がある。
以上の観点から、派遣元事業主は、次の措置等を講じなければならない。
① 特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置(法第30条)
② 段階的かつ体系的な教育訓練等(法第30条の2)
③ 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置(法第30条の3)
④ 一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保のための措置(法第30条の4)
⑤ 職務の内容等を勘案した賃金の決定(法第30条の5)
⑥ 就業規則の作成等における派遣労働者の過半数を代表する者への意見聴取(法第30条の6)
⑦ 派遣労働者等の福祉の増進のための措置(法第30条の7)
⑧ 適正な派遣就業の確保のための措置(法第31条)
⑨ 待遇に関する事項等の説明(法第31条の2)
⑲ 派遣労働者であることの明示等(法第32条)
⑪ 派遣労働者に係る雇用制限の禁止(法第33条)
⑫ 就業条件等の明示(法第34条)
⑬ 労働者派遣に関する料金の額の明示(法第34条の2)
⑭ 派遣先への通知(法第35条)
⑮ 派遣可能期間の適切な運用(法第35条の2、法第35条の3)
⑮ 日雇労働者についての労働者派遣の原則禁止(法第35条の4)
⑰ 離職した労働者についての労働者派遣の禁止(法第35条の5)
⑱ 派遣元責任者の選任(法第36条)
⑲ 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存(法第37条)
2 特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置
(1)概要
派遣元事業主は、後述の個人単位の期間制限(同じ組織単位で3年)(第7の16参照)に達す
る見込みの派遣労働者に対し、派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、以下のいず
れかの措置を講じなければならない。(法第30条第2項)
① 派遣先への直接雇用の依頼
-170 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
② 新たな就業機会(派遣先)の提供
③ 派遣元事業主において無期雇用
④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置
このうち、(力を講じた場合に、直接雇用に至らなかった場合は、その後②から④のいずれかを講
ずるものとする。(則第25条の2第2項)
1年以上継続して派遣先の同一の組織単位に派遣された派遣労働者が、個人単位の期間制限に達
する前に当該組織単位での派遣就業を終了する場合であって、派遣労働者が引き続き就業すること
を希望するときには、派遣元事業主は、上記(力から④までのいずれかを講ずるよう努めるものとす
る。
上記に加え、当該派遣元事業主に通算して1年以上雇用された有期雇用派遣労働者(雇用しよう
とする者を含む)に対しては、②から④のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。
(2)意義
派遣労働者については、派遣労働への固定化防止の観点から派遣先の同一の組織単位において3
年の期間制限が課せられているが、この期間制限に達した後に次の就業先がなければ職を失うこと
になる可能性がある。このため、雇用主である派遣元事業主に派遣期間終了後に派遣労働者の雇用
が継続されるようにするための措置を講ずべき責務を課すことにより派遣労働者の雇用の安定を図
ることとしたものである。
また、3年未満の期間においても、派遣契約の終了により職を失うことがないようにすることは
重要であることから、1年以上同一の組織単位に派遣されている労働者については雇用安定を図る
努力義務を課すこととしている。
(3)具体的な措置の内容
派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者であって派遣先の事業所その他派遣就業の場
所(以下「派遣先の事業所等」という。)における同一の組織単位の業務について継続して1年以
上の期間派遣労働に従事する見込みがある者等の一定の者(以下「特定有期雇用派遣労働者等」と
いう。)に対して、次のイからホまでのいずれかの措置を講ずるように努めなければならない(法
第30条第1項、則25条の2)。
また、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労
働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)のう
ち、3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者については、次のイからホまでの
いずれかの措置を講じなければならず、イの措置を講じた場合であって、その後派遣先が当該派遣
労働者に対し労働契約の申込みをしなかった場合には、ロからホまでのいずれかの措置をさらに講
じなければならない(法第30条第2項、則第25条の2第2項)。
この「特定有期雇用派遣労働者等」とは、次の①~③に掲げる者をいう(則第25条)。
① 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について、継続して1
年以上の期間派遣労働者として就業する見込みがある有期雇用派遣労働者であって、予定されて
-171-
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
いる派遣期間終了後も引き続き就業することを希望している者(特定有期雇用派遣労働者)
② 当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である有期雇用派遣労働者(特定有期
雇用派遣労働者を除く。)
③ 当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である、今後派遣労働者として期間を
定めて雇用しようとする労働者(いわゆる「登録状態」の者)
(派遣元事業主が講ずべき措置)
イ 特定有期雇用派遣労働者に係る派遣先に対し、当該特定有期雇用派遣労働者に対して雇用契約
の申込みをすることを求めること。
ロ 派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者
等の能力、経験、派遣労働者の居住地、就業場所、通勤時間、賃金等の以前の派遣契約により派
遣されていた際の待遇等に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保するとともに、その機
会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
ハ 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確
保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
ニ 派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介
を行うことができる場合にあっては、特定有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又
は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
ホ イから二までに掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等に対する教育訓練であって、新
たな就業機会を提供するまでの間に報酬を与えて受けさせる教育訓練を実施することその他雇用
の安定を図るために必要な措置を講じること。
なお、この措置に関連して、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(第7の27参照)にお
いて、次のような内容が盛り込まれているので十分留意すること。
(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(抄))
第2 派遣元事業主が講ずべき措置
8 派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等
(1)無期雇用派遣労働者について留意すべき事項
派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者の募集に当たっては、「無期雇用派遣」という文言を使
用すること等により、無期雇用派遣労働者の募集であることを明示しなければならないこと。
(2)特定有期雇用派遣労働者等について留意すべき事項
イ 派遣元事業主が、労働者派遣法第30条第2項の規定の適用を避けるために、業務上の必要
性等なく同一の派遣労働者に係る派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」
という。)における同一の組織単位(労働者派遣法第26条第1項第2号に規定する組織単位
をいう。以下同じ。)の業務について継続して労働者派遣に係る労働に従事する期間を三年
未満とすることは、労働者派遣法第30条第2項の規定の趣旨に反する脱法的な運用であって
、義務違反と同視できるものであり、厳に避けるべきものであること。
-172 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
ロ 派遣元事業主は、労働者派遣法第30条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用す
る場合を含む。以下同じ。)の規定により同条第一項の措置(以下「雇用安定措置」という
。)を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定有期雇用派遣労働者等(同
条第1項に規定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。)(近い将来に該当する
見込みのある者を含む。)に対し、キャリアコンサルティング(職業能力開発促進法(昭和
44年法律第64号)第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングのうち労働者の職業生
活の設計に関する相談その他の援助を行うことをいう。)や労働契約の更新の際の面談等の
機会を利用し、又は電子メールを活用すること等により、労働者派遣の終了後に継続して就
業することの希望の有無及び希望する雇用安定措置の内容を把握すること。
ハ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定
有期雇用派遣労働者等の希望する雇用安定措置を講ずるよう努めること。また、派遣元事業
主は、特定有期雇用派遣労働者(労働者派遣法第30条第1項に規定する特定有期雇用派遣労
働者をいう。)が同項第1号の措置を希望する場合には、派遣先での直接雇用が実現するよ
う努めること。
ニ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定
有期雇用派遣労働者等の労働者派遣の終了の直前ではなく、早期に当該特定有期雇用派遣労
働者等の希望する雇用安定措置の内容について聴取した上で、十分な時間的余裕をもって当
該措置に着手すること。
(4)対象者についての留意点
イ 義務の対象となるのは、事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について
継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者であ
って、派遣先の当該組織単位での派遣就業が終了した後も働き続けることを希望する者(以下「
義務対象者」という。)である。3年間従事する見込みがあるとは、個人単位の期間制限の上限
まで就業することが予定されていることを指し、例えば、1年単位で契約期間が更新されている
労働者派遣契約について、2回目の更新をして通算契約期間が3年になった時点において、当該
派遣労働者が最初の派遣契約に基づく派遣就業の開始時点から同一の組織単位で継続して就業し
ている場合には、3年間派遣就業に従事する見込みがあると判断すること。つまり、派遣元事業
主の主観的な意思ではなく、契約期間という客観的な指標により判断すること。
ロ 法第30条第1項及び第2項の「特定有期雇用派遣労働者」に該当するか否かの判断に当たり、
同一有期雇用派遣労働者が、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について、派遣の
終了と次の派遣開始の間の期間が3箇月を超えないときは、派遣労働者に係る労働に「継続して
」従事しているものとみなす。
ハ 「派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上」とは、派遣元事業主に最初に雇用され
てからその時点までの雇用期間が通算して1年以上であるかどうかで判断すること(派遣労働者
-173 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
が複数の事業所に所属していた場合であっても、労働契約の相手方である派遣元事業主が同一で
ある場合には、その期間を通算する。)。
ただし、労働基準法等の規定により関係書類の保存が義務付けられている期間を超える部分に
ついては、派遣元事業主の人事記録等により雇用関係の有無が実際に確認できる範囲で判断する
こととして差し支えない。
なお、労働者が当該派遣元事業主から給与が支払われた事実が確認できる書類(給与明細等)
を持参してきた場合には、当該給与の支払対象となった期間については、雇用関係があったもの
として取り扱う。
ニ(3)②に該当する者は、主に、同一の派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上であ
る有期雇用派遣労働者のうち、派遣先の同一の組織単位で継続して就業している期間が1年未満
の者である。
ホ 「派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者」とは、労働者派遣の対象となるも
のとして将来期間を定めて雇用しようとする労働者をいう。具体的には、いわゆる登録型で労働
者派遣事業が行われる場合における登録状態にある労働者であって、今後派遣労働者として実際
に雇用しようとするものが該当する。
へ ことホの、派遣元事業主と通算して1年以上の労働契約を結んでいた派遣労働者は、派遣契約
の期間に関わらず雇用安定措置の対象となることに留意すること。特に、派遣契約が終了したと
しても、派遣元との雇用が継続しており通算雇用期間が1年以上であれば努力義務の対象となる
ことに留意すること。
(5)講ずべき措置の内容についての留意点
イ (3)イについて、義務対象者においては、当該派遣先で直接雇用されなかった場合には別の措置
を講じなければならないことに留意し、時間的な余裕をもって行うことが望ましい。なお、どの
雇用安定措置を講ずるかは派遣元事業主の裁量に委ねられているが、派遣労働者に継続就業の希
望を聴取した際に直接雇用の依頼を希望していることを把握した場合は、(3)イの直接雇用の依頼
により直接雇用が実現するよう努めること。
さらに、(3)イの直接雇用の申込みを依頼するにあたっては、派遣元事業主は派遣先に対して書
面の交付等により行うことが望ましいこと。
ロ (3)ロについて、「派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保」とは
、当該派遣労働者の能力、経験、居住地、就業場所、通勤時間、賃金等の以前の派遣契約により
派遣されていた際の待遇等を踏まえ、合理的な範囲のものでなければならない。この待遇につい
ては、賃金のみならず福利厚生等幅広いものが含まれること。
なお、派遣労働者を無期雇用派遣労働者にすると、期間制限の対象外となることから、従前と
同一の組織単位での就業の機会を確保することも可能となることに留意すること。
また、その際には以前の派遣契約により派遣されていた際の待遇について当然考慮されるべき
である。例えば、システムエンジニアの業務に従事していた派遣労働者に対して本人が希望して
-174 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
いないにも関わらず清掃業務に従事することを提示すること、現在の居住地の通勤圏内に派遣先
があるにも関わらず、転居を伴う遠方の派遣先を提示すること(本人が希望していた場合は除く
。)は合理的な範囲のものとは言えない。「合理的な範囲」か否かは個別具体的に判断されるこ
とになるが、当該派遣労働者の能力、経験、居住地、就業場所、通勤時間、賃金等の以前の派遣
契約により派遣されていた際の待遇等の客観的な要件のみならず、本人の希望についても事前に
把握しておくことが望ましい。
なお、これらの条件に合致した派遣先を派遣労働者に対して提示した場合には、派遣労働者の
事情によって当該派遣先で就業しなかったとしても、派遣元事業主は義務違反とはならないが、
派遣労働者の希望を全く考慮せず義務を履行する形を示すだけの形式的な提示とならないように
することは当然である。
ハ(3)ハの措置は、当該派遣元事業主における直接雇用のポストを提示することであり、具体的
には、当該派遣元における営業や派遣労働者を管理する仕事等を指す。
二(3)ホの措置は、派遣労働者の雇用の継続が確実に図られる措置であれば教育訓練に限定され
るわけではなく、例えば、派遣元事業主が職業紹介をできる場合にあっては当該派遣労働者を職
業紹介の対象とすること(ただし雇用に結びついた場合に限る)等も含まれる。
ホ 派遣労働者に対して実施した雇用安定措置の日時及び内容については、派遣元管理台帳に記載
すること(法第37条第1項第8号)。特に、派遣先に対して行った直接雇用の依頼については、
派遣先からの受入れの可否についても併せて記載すること。この台帳に記載することで、派遣労
働者に対するキャリアコンサルティングや雇用安定措置に係る派遣労働者の意向の確認等にも積
極的に活用することが望ましいこと。
(6)その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置に関する留意点
イ「同一の組織単位の業務」とは、課や室その他名称の如何を問わず、業務の関連性に基づいて派
遣先が設定した労働者の配置の区分であって、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する者
が当該労働者の業務の配分及び労務管理に関して直接の権限を有するものとする(則第21条の2
)(第6の2参照)。
ロ 雇用安定措置を円滑に実施する観点から、以下のように労働契約書において定めることが望ま
しい。
雇用安定措置について
派遣労働者が派遣先の同一の組織単位の業務について継続して3年間就業する見込みがあ
り、当該派遣就業の終了後も継続した就業の希望がある場合は、派遣元事業主は派遣労働
者に対し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30
条の規定に基づき、派遣先への直接雇用の依頼等(※)の措置を講ずる。
(※)雇用安定措置の具体的な措置の項目を列挙することや、特定の措置のみを規定することも
可能。
ハ 派遣労働者を義務対象者としないよう、同一の組織単位への派遣期間を故意に3年未満とする
-175 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
ことは、法の規定の趣旨に反する脱法的な運用であって、義務違反と同視できるものであり、厳
に避けるべきものであること。このような行為を行い、繰り返し行政により指導があったにも関
わらず是正しない派遣元事業主は許可基準を満たさず許可の更新を行わないこととなることに留
意すること。
本人が希望していないにもかかわらず、有期の労働契約を締結している派遣労働者については
、その希望に応じできる限り無期の労働契約で雇用されるようにしていくことが、派遣労働者の
雇用の安定を図るうえで重要である。そのため派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等の希
望に応じ、無期雇用契約での雇用も念頭に置きながら、雇用安定措置を講ずるよう留意すること
ホ 雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該措置の対象となる特定有期雇用派遣労働者等(近い
将来該当する見込みのある者を含む。)に対し、キャリアコンサルティングや労働契約の締結及
び更新、賃金の支払等の機会を利用し、又は電子メールを活用すること等により、継続して就業
する希望の有無及び希望する措置の内容を把握するよう努めること。なお、特定有期雇用派遣労
働者になる可能性のある者について、継続して就業することの希望の有無は、当該派遣労働者に
係る派遣就業が終了する日の前日までに聴取しなければならないが、可能な限り早期に把握する
ことが望ましいこと。
へ また、雇用安定措置のうちいずれの措置を講ずるかについては派遣労働者の意向を尊重するこ
とが重要であることから、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる
派遣労働者等の希望する雇用安定措置を講ずるよう努めること。また、当該派遣労働者等の労働
者派遣の終了の直前ではなく、早期に希望する雇用安定措置の内容について聴取を行い、十分な
時間的余裕をもって当該雇用安定措置に着手すること。
ト (4)イの雇用安定措置の義務化の対象となる派遣労働者については、派遣元事業主によって当
該義務が適切に履行されるか、当該派遣労働者が就業することを希望しなくなるまでその効力が
失われることがないため、労働契約の終期が到来した後であっても、(3)ニ又はホにより、派遣
元事業主は、労働契約を継続して有給で雇用の安定を図るために必要な措置を講ずること等を通
じて、その義務を履行しなければならないことに留意すること。
チ 派遣元が(3)イからホまでのいずれかの雇用安定措置を実施できることが明確であるにもかか
わらず実施しない場合には、厚生労働大臣は新たな就業機会の確保等雇用安定措置に係る指示を
行い、その指示に従わない場合には許可の取消を行うことができる。
リ 雇用安定措置のうち、派遣先への直接雇用の依頼については、直接雇用の依頼を受けた件数に
対して派遣先が直接雇用した人数が著しく少ない場合は、派遣先に対してその理由を聴取し直接
雇用化の推進に向けた助言・指導を行うものとすること。
(7)労働契約法の適用について留意すべき事項
雇用安定措置の真に実効性ある実施により労働契約法第18条の無期転換申込権を得ることのでき
-176 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
る派遣労働者を拡大することが、派遣労働の中では比較的安定的な無期雇用派遣労働者への転換を
望む派遣労働者の希望をかなえることにつながることから、同法第18条の立法趣旨(16(3)ホ参照
)を周知徹底すること。また、派遣元事業主が、その雇用する有期雇用派遣労働者について、当
該有期雇用派遣労働者からの労働契約法第18条第1項の規定による期間の定めのない労働契約の締
結の申込みを妨げるために、当該有期雇用派遣労働者に係る期間の定めのある労働契約の更新を拒
否し、または、空白期間を設けることは、同条の規定の趣旨に反する脱法的な運用であることに留
意すること。
3 派遣労働者に対するキャリアアップ措置
(1)概要
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知
識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。この場合において、当該
派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期
間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない(法第30条の2第
1項)。
また、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の
設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない(法第30条の2第2項)。
(2)意義
派遣労働者の中には、正規雇用の労働者として働きたい、あるいは派遣労働者としてスキルアッ
プしたいというニーズもあるが、派遣労働者は一般に、正規雇用労働者に比べ、教育訓練の受講機
会確保等の職業能力形成の機会が乏しい状況にある。そこで、派遣労働者のキャリアアップを図る
ことの重要性に鑑み、派遣元事業主に派遣労働者に対する教育訓練を義務づけるものである。
また、派遣労働者が正規雇用労働者になったり派遣労働者のままステップアップしていくために
は、派遣労働者がどのようなキャリアパス(ある職位や職務等に就任するために必要な一連の業務
経験とその順序、配置、異動のルートやスキルの積み重ね等をいう。)を歩んでいくのか、当該派
遣労働者の希望を聴取しながら、適切な派遣先の選択や必要な資格取得等についての知識を付与す
る等の支援を行うことが重要である。このため、希望者に対してキャリアコンサルティング(労働
者の職業生活の設計に関する相談その他の援助を行うことをいう。)を実施することを求めること
としたものである。
(3)段階的かつ体系的な教育訓練について
どのような教育訓練を行うかについては、一義的には派遣元事業主の裁量に委ねられるが、教育
訓練を段階的かつ体系的に行うために、次に掲げる要件を満たす教育訓練計画を作成し、それに沿
って行う必要がある。
労働者派遣事業の許可又は更新を行った年については、都道府県労働局に提出した教育訓練計
-177 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
画に基づいた教育訓練を実施することが求められる。なお、教育訓練計画については年度変わり
等の時期に随時見直すことは可能であり、その都度、都道府県労働局に提出する必要はないが、
以下の要件は満たしている必要があることに留意すること。
イ 派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員を対象とするものであること。
雇用期間が1年以上見込みの常用的な労働者のみならず、登録型の有期雇用派遣労働者や日雇
派遣労働者も対象となること。登録型の者については、労働契約が締結された状態で教育訓練が
実施されること。そのため、労働契約の締結・延長等の措置を講ずる必要があり得ること。
ただし、過去に同じ派遣元事業主の下で同じ内容の訓練を受けた者、訓練内容に係る能力を十
分に有していることが明確な者については、訓練の対象者ではあるが、実際の訓練の受講に際し
ては受講済みとして扱って差し支えない。
なお、「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」とは、例えば資格取得のた
めの訓練については既に当該資格を有する者、初めて就労する者を対象とした社会人用マナー研
修については、正社員等の経験がある者が考えられる。
ロ 有給、無償で実施されるものであること
当該訓練の実施時間は、労働基準法上の労働時間と同様の扱いをすることを原則とし、当該取
扱いを就業規則又は労働契約に規定する必要がある。その場合の賃金の額は、原則として通常の
労働の場合と同額とすべきである(例外としては、複数の派遣先・派遣業務に就いていた場合に
その平均額を用いること、業務に関する特殊な手当は不支給とすることを想定。)。
ただし、派遣先が派遣元事業主の事業所から通常の交通手段では半日(概ね4時間)以上を必
要とする等の遠隔地に散らばっており集合研修をするための日程調整等が困難であることに加え
、e ラーニングの施設も有していない等については、キャリアアップに資する自主教材を派遣労働
者に提供した上で、当該教材の学習に必要とされる時間数に見合った手当の支給を行うこととし
ても差し支えない。
また、派遣労働者が教育訓練を受講するためにかかる交通費については、派遣先との間の交通
費より高くなる場合は派遣元事業主において負担すべきものであること。
さらに、登録型派遣の派遣労働者や日雇派遣の派遣労働者にも実施するにあたっては、労働契
約が締結された状況で行われなければならない。そのため必要に応じて労働契約の締結・延長等
の措置を講ずる必要があること。
なお、教育訓練を有給無償で行うために、当該費用をマージン率の引上げによる派遣労働者の
賃金の削減で補うことは望ましくないこと。
ハ 派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること
教育訓練の内容については派遣元事業主の裁量に委ねられるが、一般的にヨガ教室のような趣
味的要素が強いキャリア形成と無関係であることが明確な場合は本措置に基づく訓練とは認めら
れない。具体的な教育訓練項目がキャリアアップに資する理由については教育訓練計画に記載す
る必要がある。
-178 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
また、教育訓練の内容としては、OFF-JTのみならず計画的に実施される OJT も含めても差し支
えないが、教育訓練計画に記載しておく必要があるほか、派遣先に協力を求める場合は、労働者
派遣契約等において具体的な時間数や必要とする知識の付与や訓練方法等について記載しておく
ことが必要である。
二 人職時の訓練が含まれたものであること
短期雇用の者であっても当該訓練を受講させることができるよう、派遣元事業主と派遣先が協
力することが望ましい。
また、その後もキャリアの節目等の一定の期間ごとにキャリアパスに応じた訓練が準備されて
いる必要がある。
なお、派遣労働者一人あたり、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必要で
あり、最初の3年間を過ぎた後の提供の時期については、事業主の裁量に委ねられる。
1年以上の雇用見込みのある者について、フルタイム勤務の者に対しては、毎年概ね8時間以上
の訓練機会の提供が必要であり、短時間勤務の者に対しては、フルタイム勤務の者の勤務時間に
比した時間の訓練機会を提供しなければならない。1年以上の雇用の見込みがない者については
、少なくとも入職時の訓練は実施しなければならない。
ホ 無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること
無期雇用派遣労働者については、派遣労働者以外の期間の定めなく雇用されている労働者と同
様に、長期的なキャリア形成を念頭において教育訓練を行う必要がある。例えば同一の派遣先に
長期間勤務した者については、職場のリーダーとして役割が期待されるので、コミュニケーショ
ン能力やマネージメントスキルに係る研修を行うことが考えられる。
(4)段階的かつ体系的な教育訓練に関する留意点(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第
2の8(5)、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の9(3)参照)
イ 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約締結時までに、
教育訓練計画を明示するとともに、事務所に備え付ける等の方法で周知することが望ましい。ま
た、当該教育訓練計画に変更があった場合にも、その雇用する派遣労働者に対し、これを周知す
ることが望ましい。
ロ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が教育訓練計画に基づく教育訓練を受けられるよう
配慮しなければならない。特に、教育訓練計画の策定に当たっては、複数の受講機会を設け、又
は開催日時や時間に配慮する等により、可能な限り派遣労働者が受講しやすいものとすることが
望ましい。
ハ 派遣元事業主は、派遣労働者が良質な派遣元事業主を選択できるよう、教育訓練に関する事項
等に関する情報として、段階的かつ体系的な教育訓練計画の内容がわかる情報をインターネット
の利用その他適切な方法により提供する必要がある。
ニ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るため、(3)の要件を満たした
教育訓練計画に基づく教育訓練を実施するのみならず、さらなる教育訓練を実施することが望ま
-179 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
しい。なお、さらなる教育訓練については、必ずしも(3)の要件を満たしている必要はないが、当
該教育訓練に係る派遣労働者の費用負担を実費程度とすることで、派遣労働者が教育訓練を受講
しやすいようにすることが望ましい。なお、この場合であっても、派遣労働者の参加が強制され
る場合、派遣労働者が当該教育訓練に参加した時間は労働時間であり有給とする必要があること
ホ 派遣元事業主は、個々の派遣労働者の適切なキャリアアップについて、個人単位のキャリアア
ップ計画を当該派遣労働者との(5)のキャリアコンサルティング等に基づいて策定し、派遣労働者
の意向に沿った実効性ある教育訓練等が実施されることが望ましい。
へ 段階的かつ体系的な教育訓練を実施するために、派遣料金の引き上げ等ではなく、マージン率
を引き上げ、派遣労働者の賃金削減で対応することは望ましくない。
ト 段階的かつ体系的な教育訓練を受けるためにかかる交通費については、派遣先との間の交通費
よりも高くなる場合は派遣元事業主において負担すべきものである。
(5)希望者に対するキャリアコンサルティング等の実施について
イ キャリアコンサルティングを実施するため、キャリアコンサルティングの知見を有する相談員
又は派遣先と連絡調整を行う担当者を相談窓口に配置しなければならない。この「キャリアコン
サルティングの知見」とは必ずしも国家資格の取得を必要とするものではなくキャリアコンサル
ティングの経験でも可とする。また、「派遣先と連絡調整を行う担当者」は派遣先の事情など労
働市場の状況等を考慮した相談を行うことが求められる。なお、外部のキャリアコンサルタント
に委嘱して対応することとしても差し支えない。また、相談窓口はその雇用するすべての派遣労
働者が利用できるものである必要がある。
ロ キャリアコンサルティングは、希望に応じて行うものであることから、希望があるにもかかわ
らず実施しないことは認められない。実施方法については派遣元事業主の裁量に委ねられるため
、対面のみならず電話等で行うことも差し支えない。
ハ 雇用安定措置の実施に当たっては、キャリアコンサルティングの結果を踏まえて行うことが望
ましい。また、キャリアコンサルティングを受けることにより、今後の自身のキャリアを見つめ
直すきっかけになることや、教育訓練当該訓練を受けることにより習得できる知識・技能と希望
する職務の関連性を理解することにつながることが考えられること等から、キャリアコンサルテ
ィングを受けることが望ましい旨を派遣労働者に対して周知することが望ましい。
(6)その他の留意事項
イ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るとともに、その適正な雇用
管理に資するため、当該派遣労働者に係る労働者派遣の期間及び派遣就業をした日、従事した業
務の種類、法第30条の2による段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時及び内容等を記載した
書類を中長期的に管理・保存するように努めること。これは、人事記録等の書類でも構わないが
、派遣元管理台帳の一部として管理・保存すること。
ロ キャリアアップ支援については、派遣労働者の正社員化や賃金等の待遇改善という成果につな
-180 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
がることを目的とするべきであり、派遣労働者の賃金表に反映させることが望ましい。
4 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置
(1)概要
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当
該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通
常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の
性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相
違を設けてはならない(法第30条の3第1項)。
また、派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であ
って、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先におけ
る派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係
が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範
囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇
のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはな
らない(法第30条の3第2項)。
さらに、この措置に関連して、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(第7の27参照)
において、次のような内容が盛り込まれているので十分留意すること。
(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(抄))
第2 派遣元事業主が講ずべき措置
8 派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等
(6)労働者派遣に関する料金の額に係る交渉等
イ 労働者派遣法第30条の3の規定による措置を講じた結果のみをもって、派遣労働者の賃金
を従前より引き下げるような取扱いは、同条の規定の趣旨を踏まえた対応とはいえないこと
ロ 派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額に係る派遣先との交渉が当該労働者派遣に
係る派遣労働者の待遇の改善にとって極めて重要であることを踏まえっっ、当該交渉に当た
るよう努めること。
ハ 派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額が引き上げられた場合には、可能な限り、
当該労働者派遣に係る派遣労働者の賃金を引き上げるよう努めること。
(2)意義
派遣労働者の待遇については、実態として正社員との間で格差が存在すること等が指摘されてい
-181-
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
る。同一就業先における通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消することにより
、派遣労働という働き方を選択しても納得が得られる待遇が受けられ、多様な働き方を自由に選択
できるようにするため、派遣元事業主に対し、派遣労働者の待遇について、派遣先の通常の労働者
との間で均等・均衡を確保する措置を講ずることを義務付けたものである。
(3)均衡を考慮した待遇の確保のための措置の考え方
イ 派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間の不合理な待遇差の解消を図るため、
派遣先の通常の労働者との均衡(バランス)をとることを目指すものである。「均衡」とは、
派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先の通常の労働者の待遇との
間で、「職務の内容」、「職務の内容及び配置の変更の範囲」及び「その他の事情」のうち、
当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理
と認められる相違を設けてはならないことをいう。
ロ 派遣労働者の待遇については、派遣労働者と同一の事業所で就業する派遣先に雇用される通
常の労働者や職務の内容が同一の通常の労働者との間だけではなく、派遣先に雇用される全て
の通常の労働者との間で、不合理と認められる待遇の相違を設けることが禁止されるものであ
ること。
ハ 「待遇」には、基本的に、全ての賃金、教育訓練、福利厚生施設、休憩、休日、休暇、安全衛
生、災害補償等の全ての待遇が含まれる。一方、例えば、労働時間及び労働契約の期間について
は、個々の待遇を決定する要素であり、ここにいう「待遇」には含まれない。なお、派遣先では
なく、派遣先の労使が運営する共済会、派遣先に雇用される労働者が被保険者として加入する健
康保険組合等が実施しているものは、均等・均衡待遇の確保の措置の対象となる「待遇」には含
まれない。
ニ 「通常の労働者」については、第6の2の(3)のこの(イ)を参照のこと。
ホ 「職務の内容」及び「職務の内容及び配置の変更の範囲」については、第6の2の(3)のこの
(ロ)及び同(3)のこの(ハ)を参照のこと。
へ 「その他の事情」
「職務の内容」及び「職務の内容及び配置の変更の範囲」に関連する事情に限定されるもので
はなく、具体的には、職務の成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、事業主と労働組合との間
の交渉といった労使交渉の経緯などの諸事情が想定されるものであり、考慮すべきその他の事情
があるときに考慮すべきものである。
また、法第31条の2第4項に基づく待遇の相違の内容及びその理由等に関する説明については
労使交渉の前提となりうるものであり、派遣元事業主が十分な説明をせず、その後の労使交渉に
おいても十分な話し合いがなされず、労使間で紛争となる場合があると考えられる。「その他の
事情」に労使交渉の経緯が含まれると解されることを考えると、このように待遇の相違の内容及
びその理由等について十分な説明をしなかったと認められる場合には、その事実も「その他の事
情」に含まれ、不合理性を基礎付ける事情として考慮されうると考えられるものである。
-182 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
ト 法第30条の3第1項については、私法上の効力を有する規定であり、派遣労働者に係る労働
契約のうち、同条に違反する待遇の相違を設ける部分は無効となり、故意・過失による権利侵
害、すなわち不法行為として損害賠償が認められ得ると解されるものである。また、派遣労働
者と派遣先に雇用される通常の労働者との待遇の相違が法第30条の3第1項に違反する場合で
あっても、同項の効力により、当該派遣労働者の待遇が比較の対象である派遣先に雇用される
通常の労働者の待遇と同一となるものではないと解されるものである。
チ 法第30条の3第1項に基づき民事訴訟が捏起された場合の裁判上の主張立証については、待
遇の相違が不合理であるとの評価を基礎付ける事実については派遣労働者が、当該相違が不合
理であるとの評価を妨げる事実については派遣元事業主が主張立証責任を負うものと解され、
同項の司法上の判断は、派遣労働者及び派遣元事業主双方が主張立証を尽くした結果が総体と
してなされるものであり、立証の負担が派遣労働者側に一方的に負わされることにはならない
と解されるものである。
(4)均衡を考慮した待遇の確保のための措置の実施
イ 派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について、次に掲げる情報等に基づき、派遣先に雇用さ
れる通常の労働者との均衡を考慮した待遇を確保するための措置を講ずることとなる。
(力 労働者派遣契約の締結に当たってあらかじめ派遣先から提供される比較対象労働者の待遇等
に関する情報
② 比較対象労働者の待遇等に関する情幸酎こ変更があった場合に派遣先から提供される比較対象
労働者の待遇等に関する情報
③ 派遣元事業主の求めに応じて派遣先から提供される派遣先に雇用される労働者に関する情報
、派遣労働者の業務の遂行の状況等
(5)均等待遇の確保のための措置の考え方
イ 均等待遇の確保のための措置(法第30条の3第2項)の要件を満たした場合については、派遣
元事業主は、派遣労働者であることを理由として、賃金、教育訓練、福利厚生施設、休憩、休日
、休暇、安全衛生、災害補償等の全ての待遇について、当該待遇に対応する派遣先の通常の労働
者の待遇に比して不利なものとしてはならない。
この場合、待遇の取扱いが同じであっても、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者に
ついて査定や業績評価等を行うに当たり、意欲、能力、経験、成果等を勘案することにより、そ
れぞれの賃金水準が異なることは、通常の労働者の間であっても生じうることであって問題とは
ならないが、当然、当該査定や業績評価等は客観的かつ公正に行われるべきである。また、労働
時間が短いことに比例した取扱いの差異として、査定や業績評価等が同じである場合であっても
、賃金が時間比例分少ないといった合理的な差異は許容される。
ロ 「待遇」、「通常の労働者」、「職務の内容」及び「職務の内容及び配置の変更の範囲」に
ついては、(3)の場合と同じ解釈となる。
ハ 「当該派遣先における慣行」とは、当該派遣先において繰り返し行われることによって定着
-183 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
している人事異動等の態様をいう。
ニ 「その他の事情」とは、例えば、人事規程等により明文化されたもの等が含まれるものであ
ること。なお、ここでいう「その他の事情」とは、職務の内容及び配置の変更の範囲(人材活
用の仕組み、運用等)を判断するに当たって、当該派遣先における「慣行」と同等と考えられ
るべきものを指すものであり、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者の待遇の相違の
不合理性を判断する考慮要素としての法第30条の3第1項の「その他の事情」とは異なる。
ホ 「当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間」とは、当該派遣労働者が派遣先に雇用
される通常の労働者と「職務の内容」が同一となり、かつ、「職務の内容及び配置の変更の範
囲」(人材活用の仕組み、運用等)が派遣先に雇用される通常の労働者と同一となってから雇
用関係が終了するまでの間であること。すなわち、派遣先に派遣された後、上記要件を満たす
までの間に派遣先に雇用される通常の労働者と「職務の内容」が異なり、また、「職務の内容
及び配置の変更の範囲」(人材活用の仕組み、運用等)が派遣先に雇用される通常の労働者と
異なっていた期間があっても、その期間まで「全期間」に含めるものではなく、同一となった
時点から将来に向かって判断するものである。
へ 「見込まれる」とは将来の見込みも含めて判断されるものであること。したがって、労働者
派遣契約が更新されることが未定の段階であっても、更新をした場合には、どのような扱いが
されるかということを含めて判断されるものであること。
(6)均等待遇の確保のための措置の実施
イ 次に掲げる要件に該当するときは、均等待遇の確保のための措置(法第30条の3第2項)の
適用対象となる。
(力 職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一であること
② 職務の内容及び配置の変更の範囲(人材活用の仕組み、運用等)が、当該派遣先における派
遣就業が終了するまでの全期間において、派遣先に雇用される通常の労働者と同一であること
ロ 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から法第26条第7項に基づき提供された比較対
象労働者の待遇等に関する情幸酎こおける当該比較対象労働者が第6の2の(3)のハの(イ)の①で
ある場合は、均等待遇の確保のための措置を講ずることが基本となるものである。ただし、同
①以外の場合であっても、実態として法第30条の3第2項の要件を満たす場合には、同項の適
用対象となることに留意が必要である。
ハ なお、均等待遇を確保するための措置として、短時間・有期雇用労働法第9条においては、
通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者について「短時間・有期雇用労働者である
ことを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはな
らない」と規定しており、法第30条の3第2項とは規定ぶりが異なる。これは、派遣元事業主
は、派遣先に雇用される通常の労働者の待遇を決定する立場にないため、法第30条の3第2項
では「差別的取扱い」という文言を用いなかったことによるものであるが、同項は短時間・有
期雇用労働法第9条と同様の趣旨であり、これらの規定の内容が異なるものではない。
-184 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
(7)同一労働同一賃金ガイドライン
イ 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(以下
「ガイドライン」という。)は、法第30条の3及び第30条の4等に定める事項に関し、雇用形
態又は就業形態に関わらない公正な待遇を確保し、我が国が目指す同一労働同一賃金の実現に
向けて定めるものである。我が国が目指す同一労働同一賃金は、協定対象派遣労働者以外の派
遣労働者にあっては、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理と認めら
れる待遇の相違及び差別的取扱いの解消、協定対象派遣労働者にあっては、当該協定対象派遣
労働者の待遇が法第30条の4第1項の協定により決定された事項に沿った運用がなされている
ことを目指すものである。
ロ 派遣労働者については、雇用関係にある派遣元事業主と指揮命令関係にある派遣先とが併存
するという特殊性があり、これらの関係者が不合理と認められる待遇の相違の解消等に向けて
認識を共有することが求められることに留意すること。
ハ また、ガイドラインは、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間に待遇の相違
が存在する場合に、いかなる待遇の相違が不合理と認められるか、いかなる待遇の相違が不合
理と認められるものでないのか等の原則となる考え方及び具体例を示したものである。派遣元
事業主が、この原則となる考え方等に反した場合、当該待遇の相違が不合理と認められる等の
可能性がある。なお、ガイドラインに原則となる考え方が示されていない退職手当、住宅手当
、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合理と認められる待遇の相違
の解消等が求められる。このため、各派遣元事業主において、労使により、個別具体の事情に
応じて待遇の体系について議論していくことが望まれる。
ニ なお、ガイドラインの第4の1(注)において、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労
働者との間に賃金の決定基準・ルールの相違がある場合の考え方を記載しており、この考え方
は基本給に限られたものではないが、賃金の決定基準・ルールが異なるのは、基本的に、基本
給に関する場合が多いと考えられることから、ガイドライン第4の1において規定しているも
のである。
(8)短時間・有期雇用労働者である派遣労働者についての短時間・有期雇用労働法の適用
イ 短時間・有期雇用労働者である派遣労働者については、労働者派遣法及び短時間・有期雇用
労働法の両方が適用されるものであること。このため、基本的に、労働者派遣法において、派
遣先に雇用される通常の労働者との間の待遇の相違(協定対象派遣労働者にあっては、労働者
派遣法第30条の4第1項の協定が同項に定められた要件を満たすものであること及び当該協定
に沿った運用がなされていることの有無をいう。以下同じ。)が問題になるとともに、短時間
・有期雇用労働法において、派遣元事業主に雇用される通常の労働者との間の待遇の相違が問
題になるものである。
ロ このことから、短時間・有期雇用労働者である派遣労働者の待遇のうち、職務の内容に密接
に関連するものに当たらない待遇については、派遣先に雇用される通常の労働者との間の待遇
-185 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
の相違に加えて、短時間・有期雇用労働者である派遣労働者と派遣元事業主に雇用される通常
の労働者との間の待遇の相違が問題になると考えられるものであること。
一般に、ガイドライン第3の3(7)及び第4の3(7)の通勤手当及び出張旅費、ガイドラ
イン第3の3(8)及び第4の3(8)の食事手当、ガイドライン第3の3(9)及び第4の3
(9)の単身赴任手当、ガイドライン第3の4及び第4の4並びに第5の2の福利厚生(ガイド
ライン第3の4(1)及び第4の4(1)並びに第5の2(1)の福利厚生施設を除く。)につ
いては、職務の内容に密接に関連するものに当たらないと考えられるものであること。
ハ 他方で、職務の内容に密接に関連する待遇については、派遣労働者が派遣先の指揮命令の下
において派遣先の業務に従事するという労働者派遣の性質から、特段の事情がない限り(ニ参
照)、派遣元事業主に雇用される通常の労働者との待遇の相違は、実質的に問題にならないと
考えられるものであること。
職務の内容に密接に関連する待遇に当たるか否かは、個々の待遇の実態に応じて判断されるも
のであるが、例えば、ガイドライン第3の1及び第4の1の基本給、ガイドライン第3の2及び
第4の2の賞与、ガイドライン第3の3(1)及び第4の3(1)の役職手当、ガイドライン第
3の3(2)及び第4の3(2)の特殊作業手当、ガイドライン第3の3(4)及び第4の3(
4)の精皆勤手当、ガイドライン第3の3(5)及び第4の3(5)の時間外労働手当、ガイド
ライン第3の3(6)及び第4の3(6)の深夜労働手当及び休日労働手当、ガイドライン第3
の5(1)、第4の5(1)及び第5の3(1)の教育訓練、ガイドライン第3の5(2)、第
4の5(2)及び第5の3(2)の安全管理に関する措置及び給付については、一般に、職務の
内容に密接に関連するものと考えられるものであること。
なお、これらの点については、協定対象派遣労働者であるか否かによって異なるものではない
と考えられるものであること。
ニ ただし、職務の内容に密接に関連する待遇であっても、派遣先に雇用される通常の労働者と
の均等・均衡とは異なる観点から、短時間・有期雇用労働者ではない派遣労働者に対して、短
時間・有期雇用労働者である派遣労働者よりも高い水準の待遇としている場合には、短時間・
有期雇用労働者ではない派遣労働者と短時間・有期雇用労働者である派遣労働者との間の待遇
の相違について、短時間・有期雇用労働法において問題となることがあると考えられるもので
あること。
ホ また、職務の内容に密接に関連するものに当たらない待遇であっても、短時間・有期雇用労
働者である派遣労働者と短時間・有期雇用労働者でない派遣労働者が異なる派遣先に派遣され
ている場合において、待遇を比較すべき派遣先に雇用される通常の労働者が異なることにより
待遇に相違がある場合には、当該待遇の相違は、短時間・有期雇用労働法において問題になる
ものではないと考えられるものであること。
(9)留意点
イ 派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から提供される比較対象労働
-186 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
者の待遇等に関する情幸酎こついて、比較対象労働者が適切に選出されているかどうかを確認す
ることが重要である。
このため、例えば、比較対象労働者が第6の2の(3)のハの(イ)の⑤又は⑥である場合には、
第6の2の(3)のハの(イ)の⑤の比較対象労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で均
衡待遇が確保されている根拠又は第6の2の(3)のハの(イ)の⑥の比較対象労働者と派遣先に雇
用される通常の労働者との間で適切な待遇が確保されている根拠を確認するため、派遣労働者
からの求めも踏まえながら、法第40条第5項に基づき派遣先に追加の情報提供を求めるなど、
適切に対応することが求められること。
ロ 派遣元事業主の派遣料金交渉が、派遣労働者の賃金も含めた待遇改善にとって重要であるこ
とに留意することを踏まえっっ、当該交渉に当たること。また、派遣料金が引き上げられたと
きは、できる限りそれを派遣労働者の賃金の引上げに反映するよう努めること。
ハ 派遣先に雇用される通常の労働者との均等・均衡を考慮した結果のみをもって、当該派遣労
働者の賃金を従前より引き下げるような取扱いは、法第30条の3の趣旨を踏まえた対応とはい
えず、労働契約の一方的な不利益変更との関係でも問題が生じうる。
ニ また、特に通勤手当に関し、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(第7の27参照
)において、次のような内容が盛り込まれているので十分留意すること。通勤手当はあくまで
例示であり、有期雇用派遣労働者のその他の待遇についても同様に、短時間・有期雇用労働法
第8条及び第9条の対象となる旨、注意すること。
(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(抄))
第2 派遣元事業主が講ずべき措置
8 派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等
(3)労働契約法等の適用について留意すべき事項
イ・ロ (略)
ハ 派遣元事業主は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平
成5年法律第76号)第8条の規定により、その雇用する有期雇用派遣労働者の通勤手当につ
いて、その雇用する通常の労働者の通勤手当との間において、当該有期雇用派遣労働者及び
通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当
該通勤手当の性質及び当該通勤手当を支給する目的に照らして適切と認められるものを考慮
して、不合理と認められる相違を設けてはならないこと。また、派遣元事業主は、同法第9
条の規定により、職務の内容が通常の労働者と同一の有期雇用派遣労働者であって、当該事
業所における慣行その他の事情からみて、当該派遣元事業主との雇用関係が終了するまでの
全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び範囲と同一
の範囲で変更されることが見込まれるものについては、有期雇用労働者であることを理由と
して、通勤手当について、差別的取扱いをしてはならないこと。なお、有期雇用派遣労働者
-187 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
の通勤手当については、当然に労働者派遣法第30条の3又は第30条の4第1項の規定の適
用があることに留意すること。
5 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保のための措置
(1)概要
派遣元事業主は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合(5に
おいて「過半数労働組合」という。)、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者(5において「過半数代表者」という。)との書面による協定(以下
単に「労使協定」という。)により、その雇用する派遣労働者の待遇(法第40条第2項の教育訓練
及び同条第3項の福利厚生施設に係るものを除く。)について、一定の事項を定めたときは、派遣
先に雇用される通常の労働者との均等・均衡を確保するための措置(法第30条の3の規定に基づく
措置)は適用しない(法第30条の4第1項)。ただし、労使協定で定めた事項を遵守していない場
合又は労使協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない(法第30条の
4第1項ただし書)。
また、労使協定を締結した派遣元事業主は、労使協定をその雇用する労働者に周知しなければな
らない(法第30条の4第2項)。
(2)意義
派遣労働者については、その就業場所は派遣先であり、待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮
するためには、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を確保するための措置を講ずることは重要な
観点である。一方、この場合には、派遣先が変わるたびに派遣労働者の賃金水準が変わり、派遣労
働者の所得が不安定になることが想定され、また、一般に賃金水準は大企業であるほど高く、小規
模の企業であるほど低い傾向にあるが、派遣労働者が担う職務の難易度は、同様の業務であっても
、大企業であるほど高度で、小規模の企業であるほど容易とは必ずしも言えず、結果として、派遣
労働者個人の段階的かつ体系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くことがあり得る。
このため、派遣元事業主が、労使協定を締結した場合には、労使協定に基づき派遣労働者の待遇
を決定することで、計画的な教育訓練や職務経験による人材育成を経て、段階的に待遇を改善する
など、派遣労働者の長期的なキャリア形成に配慮した雇用管理を行うことができるようにしたもの
である。
(3)労使協定の締結方法
イ 労使協定は、派遣元事業主単位又は労働者派遣事業を行う事業所単位で締結することが可能で
ある。ただし、待遇を引き下げることを目的として、悉意的に締結単位を分けることは、労使協
定方式の趣旨に反するものであり、適当ではないことに留意すること。
ロ 派遣元事業主は、労使協定により派遣労働者の待遇を決定することとする場合には、過半数労
働組合又は過半数代表者との間で書面による協定を締結しなければならない。書面によらず協定
した場合には、法第30条の4第1項の協定とは認められず、派遣先に雇用される通常の労働者と
-188 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
の間の均等・均衡待遇を確保しなければならない。
ハ 過半数労働組合との間で労使協定を締結する場合における過半数労働組合は、派遣元事業主に
おける労働者又は派遣元事業主の各事業所における労働者の過半数で組織する労働組合である。
「労働組合」とは、労働組合法第2条に規定する要件を満たすものに限る。
ニ 過半数代表者との間で労使協定を締結する場合には、過半数代表者は、以下の(力及び②のいず
れにも該当する者とすること(則第25条の6第1項)。また、過半数代表者は、派遣労働者を含
む全ての労働者から選出されることとなる。過半数代表者が適切に選出されなかった場合には、
法第30条の4第1項の協定とは認められず、派遣先の通常の労働者との均等・均衡による待遇を
確保しなければならない。なお、労働者の過半数の信任を得ていない労働者個人は、過半数代表
者とは認められないことから、派遣元事業主は当該労働者個人との間で労使協定を締結すること
は認められないことに留意すること。
① 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者ではないこと。
② 労使協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法に
よる手続により選出された者であって、派遣元事業主の意向に基づき選出されたものでないこ
と。
なお、「投票、挙手等」の方法としては、「投票、挙手」のほか、労働者の話合い、持ち回
り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当
する。
ただし、①に該当する者がいない派遣元事業主(労使協定を派遣元事業主単位で締結する場
合)又は①に該当する者がいない事業所(労使協定を事業所単位で締結する場合)にあっては
、②に該当する者とすること(則第25条の6第1項)。
また、派遣元事業主は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうと
したこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、解雇、賃金の減額、降
格等労働条件について不利益な取扱いをしないようにしなければならない(則第25条の6第2
項)。「過半数代表者として正当な行為」には、労使協定の締結の拒否等も含まれる。
ホ 派遣元事業主は、過半数代表者が労使協定の事務を円滑に遂行することができるよう必要な
配慮を行わなければならない(則第25条の6第3項)。この「必要な配慮」には、例えば、過
半数代表者が労働者の意見集約等を行うに当たって必要となる事務機器(イントラネットや社
内メールを含む。)や事務スペースの提供を行うことが含まれるものである。
へ なお、派遣中の派遣労働者が異なる派遣先に派遣されているため意見交換の機会が少ない場
合があるが、その場合には、過半数代表者を選任するための投票等に併せて意見、希望等を提
出させ、これを過半数代表者が集約するなどにより、派遣労働者の意思が反映されることが望
ましいことに留意すること。
(4)労使協定の保存
派遣元事業主は、労使協定を締結したときは、労使協定に係る書面を、その有効期間が終了した
-189 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない(則第25条の12)。
(5)労使協定の対象とならない待遇
労使協定の対象とならない待遇は、派遣先に実施が義務付けられている法第40条第2項の教育訓
練及び利用の機会の付与が義務付けられている法第40条第3項の福利厚生施設(給食施設、休憩室
、更衣室)である(則第25条の7)。これらの待遇については、派遣先に雇用される通常の労働者
との間の均等・均衡待遇を確保しなければ実質的な意義を果たすことができないため、労使協定の
対象となる待遇から除いている。
(6)労使協定の記載事項
労使協定には、次のイからへまでに掲げる事項を記載しなければならない(法第30条の4第1項
各号)。
イ その待遇が労使協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
全ての派遣労働者を一律に労使協定の対象とするのではなく、派遣労働者の職種、雇用期間の
有無等の特性に応じて、労使協定の対象とするか否かを判断すべきものであることから、労使協
定の対象となる派遣労働者の範囲を労使協定に定めることとしたもの。一つの派遣元事業主にお
いて、派遣先に雇用される通常の労働者との均等・均衡によりその待遇を決定する者と労使協定
によりその待遇を決定する者が併存することはあり得る。
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を定めるに当たっては、職種(一般事務、エンジニア
等)や労働契約期間(有期、無期)などといった客観的な基準によらなければならない。また、
客観的な基準であったとしても、性別、国籍等、他の法令に照らして不適切な基準によることは
認められない。この他、例えば、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を「賃金水準が高い企
業に派遣する労働者」とすることは、労使協定方式を設けた趣旨に照らして適当ではない。
これらの事項が遵守されている場合には、実際にどのような範囲を定めるかは基本的に労使に
委ねられるが、当該範囲の設定については、労使協定制度の趣旨に沿って労使協定の対象となる
範囲を定めることが望ましい。
ロ 派遣労働者の賃金の決定方法
(イ)「賃金」の範囲は、労働基準法の賃金に含まれるかどうかにより判断し、基本給のみならず
諸手当も含まれることに留意すること。
(ロ)労使協定に定める賃金の決定方法は、次の(力及び②を満たさなければならない。ただし、職
務の内容に密接に関連しない賃金(例えば、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教
育手当が考えられるが、名称の如何を問わない。)については、職務の内容、職務の成果等に応
じて決定することになじまないものであることから、②の要件を満たす必要はない。
(力 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(以下「一
般賃金」という。)の額と同等以上の賃金の額となるものであること
② 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事
項の向上があった場合に賃金が改善されるものであること
-190 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
これは、派遣労働者の待遇について、派遣先に雇用される通常の労働者との比較ではなく、様
々な派遣先に雇用される通常の労働者一般との比較において一定の水準を確保しようとするもの
である。
①については、具体的には、派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域におい
て派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者であって、当該派遣労働者と
同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額と同等以上であることが必要である(則第
25条の9)。この比較対象となる一般賃金の具体的な額、同等以上の確認方法等については、別
途通知により示す。
②については、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事
項のうちどの事項を勘案するか、その事項をどのように勘案するかは、基本的には労使に委ねら
れるものであるが、手当を追加支給すること、新たな派遣就業の機会を提示することなど、就業
の実態に関する事項の向上があった場合の具体的な措置の内容を労使協定に記載することが求め
られる。
なお、常時10人以上の労働者を使用する派遣元事業主は、労働基準法第89条に基づき、賃金の
決定等に関する事項を就業規則に記載し、労働基準監督署に届け出なければならないこととされ
ていることに留意すること。
ハ 公正な評価に基づく賃金の決定
派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項
を公正に評価され、賃金の改善に反映されるよう、適切な評価方法を定めることが必要である。
評価の具体的な方法としては様々なものが考えられるが、例えば、
・ キャリア(スキル)マップを整備し、一定期間ごとに能力評価、派遣就業の状況の確認等
により、派遣労働者の就業の実態の当てはめを行うこと
・ 派遣労働者と面談して成果目標を設定し、一定期間後に達成状況について改めて面談を行
って評価を決めること
など、公正さを担保する工夫がなされていることが必要である。なお、正社員の評価方法と同様
の方法により派遣労働者の評価を行うことも考えられる。
ニ 賃金を除く待遇の決定の方法
派遣労働者の待遇(賃金を除く。ニにおいて同じ。)のそれぞれについて、派遣元事業主に雇
用される通常の労働者(派遣労働者を除く。ニにおいて同じ。)の待遇との間において、当該派
遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情の
うち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不
合理と認められる相違が生じることのないものでなければならない。
なお、この「待遇」には、法第40条第2項の教育訓練及び同条第3項の福利厚生施設は含まれ
ないことに留意すること。
ホ 段階的かつ体系的な教育訓練
-191-
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
教育訓練計画に基づき、段階的かつ体系的に実施されるものでなければならない。
へ その他の事項
(イ)有効期間(則第25条の10第1号)
労使協定は、その対象となる派遣労働者の待遇の根拠となるものであり、労働者の入れ替わ
りがあるため、労使協定で明らかにしておくこととするものである。具体的には、労使協定の
始期と終期を記載すること。
有効期間の長さについては、その対象となる派遣労働者の待遇の安定性や予見可能性、実務
上の対応を考慮すれば長くすることが考えられる一方で、労働者の意思を適正に反映すること
を考慮すれば短くすることが考えられるため、画一的な基準を設けることとはしていないが、
目安として2年以内とすることが望ましい。
なお、労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても
、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認す
ること。派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額でない場合には、労使協定に定め
る賃金の決定方法を変更するために労使協定を締結し直す必要があること。一方、派遣労働者
の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主は、同等以上の額であ
ることを確認した旨の書面を労使協定に添付すること。
(ロ)労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合には、その理
由(則第25条の10第2号)
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲が、労使合意のもとで適正に定められるようにする
ことを担保するためのものである。具体的な理由としては、例えば、「派遣先が変更される頻
度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐため」と記載するこ
とが考えられる。
(ハ)特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、当該労働契約に係る派遣労働者に
ついて、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更しないこと(則
第25条の10第3号)
派遣労働者の待遇決定方式(派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式)が、派遣先の変更を
理由として、一の労働契約期間中に変更されることは、所得の不安定化を防ぎ、中長期的なキ
ャリア形成を可能とする労使協定制度の趣旨に反するおそれがあることから、特段の事情がな
い限り、認められないことを記載するものである。
「特段の事情」とは、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲が職種によって定められてい
る場合であって派遣労働者の職種の転換によって待遇決定方式が変更される場合、待遇決定方
式を変更しなければ派遣労働者が希望する就業機会を提供できない場合であって当該派遣労働
者から合意を得た場合等のやむを得ないと認められる事情がある場合が考えられる。
(7)労使協定の周知
イ 労使協定を締結した派遣元事業主は、次のいずれかの方法により、労使協定をその雇用する労
-192 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
働者に周知しなければならない(法第30条の4第2項)。当該方法については、派遣元事業主が
派遣労働者の待遇に関する重要な事項を定めた労使協定を周知するに当たっては、周知対象であ
る派遣労働者の就業場所が派遣元事業主の事業所ではなく、派遣先の様々な場所であり、派遣元
事業主の事業所内における掲示等では不十分であることを踏まえたものである。なお、周知対象
となる労働者は、派遣労働者に限らず、派遣元事業主が雇用する全ての労働者である。
(力 書面の交付の方法
② 次のいずれかによることを労働者が希望した場合における当該方法
・ ファクシミリを利用してする送信の方法
・ 電子メール等の送信の方法
③ 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ労
働者が当該記録の内容を常時確認できる方法
具体的には、例えば、派遣労働者にログイン・パスワードを発行し、イントラネット等で常
時確認できる方法等をいうこと。
④ 常時派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける方法(労使協定の概
要について、(力又は②の方法によりあわせて周知する場合に限る。)
概要については、少なくとも、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲、派遣労働者の賃金
(基本給、賞与、通勤手当、退職手当等)の決定方法及び有効期間を盛り込み、派遣労働者が
容易に理解できるようにすることが望ましい。
労使協定の概要(例)
く)対象となる派遣労働着の範直Iこプログラマーの叢預に従事する従茶昌
C)賞金の構成二基本給、賞与、時間外労l動手当、深夜・休日労働手当、通勤手当及び退職手当
○ 賃金の決定方法
く基本給+賞与>
‥・ ・甥だ1〇〇〇〇〇〇〇〇し諷㌫ -、逼T _・
I 坤潤■ 。AI関係等高度去覧鍔三品をかた関劾 I L6可I 可 用Ol
l 各章お夢l ㈲アブ。温㌫
l 電一寿城l恥lのマク。等、票認諾㍍
難易度の倒捗り
ム言語を用いた閉捗り
[ 日中l 叫
l・UUL 「
巨星
※1 半期ごとの勤脚価の靂各署、より熟、等緑の職務を運行する能力があると認められた場合には、その掛こ応じた派遣就茶の機会を提示す
るよう努めるものとする。
※2 半期ごとの勤務評価の鑑真、繹顆の蓄積や能力の向上があると認められた場合には、基本給鞘の1・〉3%の紺で能力手当を加算する。
※3 半期ごとの勤脚価の結果、Å評価(標準より優秀)であれば基本給書貞の25%相当、B評価く標準)であれば基本給書貞の20%相当、C評価
(標準より物足りなヽ、)であれは基本給鞘の15%紺碧を支給するe
<嘲外学帽か手当、深掛休日ラ欄序当> 法律の矧こ鮎で支給
く通勤手当> 通勤に要する毒嘲こ相当する醇を支給
・く退凝手当>
・亘野替 圏l憲澄菓旺盛封猥漂=監禁
自己都合退職l l・O ll 3』l 7・O ll l…ll15・O l
会社都合退職l 2・O ll 5・O ll g・O ll12・O ll17・O l
※1 退職手当の受給に必要な相続年数は3年とし、退職時の動統年数が3年未満の場合はま冶しない。
y2 退聯寺の基本鯛覿こ退職手当の支給月数を乗じて得た報を支給する。
○ 有効期間二平成●年●月●日から平成◆年◆月◆日までの●年間
ュ 2
※ 宍
1∫1「」
平成●年●月●首
●●人材サービス株式会社+取締役人事苦長 ●●●●
●●人・柑サービス矧艶且合覇憫貼●●●●
※ 労使協定の概要には、派遣労働者の賃金の決定方法に加えて、比較対象である一般賃金の
額を記載することが望ましい。
-193 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
ロ 労使協定の周知の趣旨を踏まえると、派遣労働者が求める場合には、労使協定を常時閲覧でき
るようにすることが必要であるため、派遣労働者が希望する場合には、労使協定本体を書面の交
付等により周知することが望ましい。
(8)行政機関への報告
労使協定を締結した派遣元事業主は、事業報告書に労使協定を添付するとともに、協定対象派
遣労働者の職種ごとの人数及び職種ごとの賃金額の平均額を報告しなければならない。
(9)協定対象派遣労働者に対する安全管理に関する措置及び給付
派遣元事業主がその雇用する協定対象派遣労働者に対して行う安全管理に関する措置及び給付
のうち、当該協定対象派遣労働者の職務の内容に密接に関連するものについては、派遣先に雇用
される通常の労働者との間で不合理と認められる相違等が生じないようにすることが望ましい(
派遣元指針第2の8の(8))。
6 職務の内容等を勘案した賃金の決定
(1)概要
派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労
働者(均等待遇の対象となる派遣労働者及び協定対象派遣労働者を除く。)の職務の内容、職務の
成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(職務の内容に密
接に関連して支払われる賃金以外の賃金を除く。)を決定するように努めなければならない(法第
30条の5)。
(2)意義
イ 均衡待遇を確保する対象となる派遣労働者の賃金については、派遣先に雇用される通常の労働
者との間において、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該賃
金の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設け
てはならないこととされている。不合理と認められない相違がある中で、派遣労働者の納得感の
向上、就業の促進等を図るためには、働き又は貢献に関する事情を考慮して賃金を決定するよう
に努めることが望ましいことから、均衡待遇の確保の上乗せの措置として、職務の内容等を勘案
して派遣労働者の賃金を決定する努力義務を課すこととしたものである。
ロ なお、均等待遇の対象となる派遣労働者については、派遣先に雇用される通常の労働者と同様
の賃金が担保されることから、職務の内容等を勘案した賃金の決定の対象とはしていない。また
、協定対象派遣労働者については、職務の内容等の向上があった場合に賃金が改善されるもの等
の要件を満たす賃金の決定方法を労使で合意して労使協定に定めて遵守することとされているこ
とから、職務の内容等を勘案した賃金の決定の対象とはしていない。
(3)職務の内容等を勘案した賃金の決定の対象外となる賃金
-194 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる
賃金(職務の内容に密接に関連して支払われるものを除く。)については、職務の内容等を勘案し
た賃金の決定の対象外となる(則第25条の13)。
賃金が職務の内容に密接に関連して支払われるものに該当するかを判断するに当たっては、名称
のみならず、支払い方法、支払いの基準等の実態を見て判断する必要があるものであること。例え
ば、通勤手当について、現実に通勤に要する交通費等の費用の有無や金額如何にかかわらず、一律
の賃金が支払われている場合など、名称は「通勤手当」であるが、実態として基本給などの一部と
して支払われているものや、家族手当について、名称は「家族手当」であるが、家族の有無にかか
わらず、一律に支払われているものについては、職務の内容に密接に関連して支払われるものに該
当する可能性があること。
(4)具体的な措置の内容
イ 派遣労働者の「職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事
項を勘案し」とは、派遣労働者の働きや貢献に見合った賃金決定がなされるよう、働きや貢献を
評価する要素である職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験を勘案要素の例示として挙げて
いるものであること。勘案要素のうち、その要素によることとするかは、各派遣元事業主の判断
に委ねられるものであるが、その勘案については、法第31条の2第4項による説明(第7の10参
照)を求められることを念頭に、どの要素によることとしたのか、またその要素をどのように勘
案しているのかについて客観的かつ具体的な説明ができるものとされるべきであること。
ロ 「職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項」を勘案し
た措置の例としては、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関す
る事項を踏まえた①賃金水準の見直し、②昇給・昇格制度や成績等の考課制度の整備、③職務手
当、役職手当、成果手当の支給等が考えられること。例えば、職務の内容を勘案する場合、責任
の重さや業務の困難度で賃金等級に差を設けることなどが考えられるが、職務の内容等を勘案し
た賃金の決定の趣旨は、この措置の結果として、派遣労働者の中で賃金の差を生じさせることに
あるのではなく、職務の内容等を適切に賃金に反映させることにより、結果として通常の労働者
の待遇との均衡を図っていくことにある点に留意すべきであること。
なお、「その他の就業の実態に関する事項」としては、例えば、派遣先における就業期間が考
えられること。
ハ 「派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ」とは、派遣労働者の職務の内容が
同一である派遣先に雇用される通常の労働者だけではなく、職務の内容が異なる派遣先に雇用さ
れる通常の労働者との均衡も考慮することを指しているものであること。具体的には、派遣先に
雇用される通常の労働者の賃金決定に当たっての勘案要素を踏まえ、例えば、職務の内容が同一
の派遣先に雇用される通常の労働者の賃金が経験に応じて上昇する決定方法となっているならば
、派遣労働者についても経験を考慮して賃金決定を行うこととする等、「職務の内容、職務の成
果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項」に応じた待遇に係る措置等を講ずる
-195 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
ことが望まれる。
この措置を講ずる時期については、派遣元に雇用される通常の労働者の定期昇給や賃金表の改
定に合わせて実施すること等が考えられるが、例えば、労働者派遣契約を更新する際に、あわせ
て賃金の決定方法について均衡を考慮したものとなるよう見直すことも考えられる。
7 就業規則の作成等における派遣労働者の過半数を代表する者への意見聴取
(1)概要
派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするとき
は、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表するものの意見を聴くよ
うに努めなければならない(法第30条の6)。
(2)意義
イ 派遣労働者を含む常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働基準法第89条の定めるとこ
ろにより、就業規則を作成する義務があるが、その作成又は変更に当たっては、同法第90条にお
いて、使用者は事業場の過半数労働組合等の意見を聴かなければならないこととされている。派
遣労働者に適用される就業規則についてもこの手続がとられなければならないことは当然である
が、派遣労働者に適用される就業規則の作成又は変更に当たっては、これに加えて、就業規則の
適用を受ける派遣労働者の意見が反映されることが望ましい。
このため、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、
当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くよう
に努めるものとしたものである。
(3)具体的な措置の内容
イ 「派遣労働者の過半数を代表すると認められるもの」は、事業所の派遣労働者の過半数で組織
する労働組合がある場合はその労働組合、派遣労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は
派遣労働者の過半数を代表する者(この(3)において「派遣労働者の過半数代表者」という。)
が考えられる。
ロ 派遣労働者の過半数代表者については、以下のいずれにも該当する者とすることが考えられる
こと。また、(力に該当する者がいない事業所にあっては、②に該当する者とすることが考えられ
ること。
① 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者ではないこと。
② 就業規則の作成又は変更に係る意見を事業主から聴取される者を選出することを明らかにし
て実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であって、派遣元事
業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
ハ なお、これは、派遣労働者の過半数を代表すると認められる者の意見の聴取を要請するもので
あって、就業規則を労働基準監督署に届け出る際に意見書の添付を義務付けるものではない。
-196 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
8 派遣労働者等の福祉の増進
(1)概要
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者につい
て、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会(派遣労働者以外の労働者としての就業の機会
を含む。)及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置
を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない(法第30条の7
)。なお、ここでの就業の機会の中には、派遣労働以外の就業の機会も含まれることから、直接雇
用を希望する者については、派遣元事業主は正社員等の直接雇用の機会を確保して提供するよう努
めなければならない。
この措置に関連して、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(第7の27参照)において
、派遣労働者等の福祉の増進に関し次のような内容が盛り込まれているので十分留意すること。
(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(抄))
第2 派遣元事業主が講ずべき措置
8 派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等
(4)派遣労働者等の適性、能力、経験、希望等に適合する就業機会の確保等
派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者(以下「派遣労働者等」と
いう。)について、当該派遣労働者等の適性、能力、経験等を勘案して、最も適した就業の
機会の確保を図るとともに、就業する期間及び日、就業時間、就業場所、派遣先における就
業環境等について当該派遣労働者等の希望と適合するような就業機会を確保するよう努めな
ければならないこと。また、派遣労働者等はその有する知識、技術、経験等を活かして就業
機会を得ていることに鑑み、派遣元事業主は、労働者派遣法第30条の2の規定による教育訓
練等の措置を講じなければならないほか、就業機会と密接に関連する教育訓練の機会を確保
するよう努めなければならないこと。
(2)直接雇用の推進
派遣労働者の中には直接雇用を希望する者も相当程度存在することから、派遣元事業主は、一般
的な責務として、雇用する派遣労働者の希望に応じ、直接雇用の労働者として雇用されることがで
きるように雇用の機会を確保し、その機会を提供するよう努めることが求められる。
法第30条の7では就業機会の中に含まれる事項として「派遣労働者以外の労働者としての就業
の機会を含む」と記述しているだけであるが、このような趣旨にかんがみ直接雇用の機会の提供に
ついては雇用安定措置やキャリアアップ措置とあいまって積極的に行うことが求められる。
(3)派遣労働者等の福祉の増進に関する留意点
イ 「派遣労働者として雇用しようとする労働者」とは、労働者派遣の対象となるものとして将
来雇用しようとする労働者をいう。具体的には、いわゆる登録型で労働者派遣事業が行われる
場合における登録状態にある労働者が主に想定される。
したがって、派遣元事業主は、現に雇用している労働者だけではなく、登録中の労働者等、
-197 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
派遣労働者として雇用しようとする労働者についても、以下ロから二までの福祉の増進を図る
よう努めなければならない。
ロ 「各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会の確保」とは、個々の労働者の適性、能力
及び経験を勘案してこれに最も適合し、かつ、直接雇用を望むのか派遣労働者としての就業を
望むのかといった当該労働者の就業ニーズ、就業する期間、日、1日における就業時間、就業
場所、派遣先の職場環境についてその希望に適合するような就業機会の確保のことである。
ハ 「教育訓練の機会の確保」とは、派遣元事業主に最低限義務付けられているもの(3参照)
の他に教育訓練を実施することである。
ニ 「労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置」とは、賃金、労働時間、安全
衛生、災害補償等労働者の職場における待遇である労働条件について、よりよい条件の下にお
ける労働者の就業機会の確保、社会保険、労働保険の適用の促進、福利厚生施設の充実等に努
めることである。
(4) 育児休業から復帰する際の就業機会の確保
派遣元事業主は、派遣労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業から復帰する際には、当該派遣労
働者が就業を継続できるよう、当該派遣労働者の派遣先に係る希望も勘案しつつ、就業機会の確保に
努めるべきであることに留意することが求められる(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」
第2の8(9)(第7の27参照))。
(5)障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るため
の措置
派遣元事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用
促進法」という。)第2条第1号に規定する障害者(以下単に「障害者」という。)である派遣労働
者から派遣先の職場において障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている
事情の申出があった場合又は派遣先から当該事情に関する苦情があった旨の通知を受けた場合等にお
いて、同法第36条の3の規定による措置を講ずるに当たって、当該障害者である派遣労働者と話合い
を行い、派遣元事業主において実施可能な措置を検討するとともに、必要に応じ、派遣先と協議等を
行い、協力を要請することが求められる(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の8(
10)(第7の27参照))。
9 適正な派遣就業の確保
(1)概要
派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者を労働
させるに当たって、当該派遣就業に関し法又は法第3章第4節の規定により適用される法律の規
定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反することがないよう、その他当該派遣就
業が適正に行われるように、必要な措置を講じる等適切な配慮をしなければならない(法第31条
-198 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
)。
なお、この措置に関連して、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(第7の27参照)
において、(力派遣先との連絡体制の確立、②関係法令の関係者への周知に関し次のような内容が
盛り込まれているので十分留意すること。
(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(抄))
第2 派遣元事業主が講ずべき措置
5 派遣先との連絡体制の確立
派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、派遣労働者の就業の状況が労働
者派遣契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、派遣労働者の適正な派遣就業
の確保のために、きめ細かな情報提供を行う等により、派遣先との連絡調整を的確に行うこと
。特に、労働基準法第36条第1項の時間外及び休日の労働に関する協定の内容等派遣労働者の
労働時間の枠組みについては、情報提供を行う等により、派遣先との連絡調整を的確に行うこ
と。なお、同項の協定の締結に当たり、労働者の過半数を代表する者の選出を行う場合には、
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第6条の2の規定に基づき、適正に行うこ
と。
また、派遣元事業主は、割増賃金等の計算に当たり、その雇用する派遣労働者の実際の労働
時間等について、派遣先に情報提供を求めること。
「派遣先との連絡調整」には、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のために必要となる連絡調整
が広く含まれるものであり、例えば、派遣労働者に対する年次有給休暇、産前産後休業、育児休業
又は介護休業の付与は、派遣元事業主の義務となっているところであるが、派遣労働者が派遣先に
おける業務遂行に気兼ねして休業の申出を行いにくいことがないよう、これらの休業の取得に関し
て十分な連絡調整を行うこと等、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のために必要となる連絡調整
が広く含まれるものである。
「関係者」とは、派遣労働者(登録中のものを含む。)、派遣先等がこれに該当するものである
(2)意義
「法又は法第3章第4節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規
定を含む。)」は、第6の4の(3)と同じ規定である。
(3)具体的配慮の内容
「適切な配慮」の内容は、具体的には、例えば、次のようなものである。
(力 法違反の是正を派遣先に要請すること。
② 法違反を行う派遣先に対する労働者派遣を停止し、又はその派遣先との間の労働者派遣契約
を解除すること(第6の4参照)。
③ 派遣先に適用される法令の規定を習得すること。
④ 派遣元責任者に派遣先の事業所を巡回させ、法違反がないよう事前にチェックすること。
-199 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
⑤ 派遣先との密接な連携の下に、派遣先において発生した派遣就業に関する問題について迅速
かつ的確に解決を図ること。
(4)法第44条第3項及び第4項並びに法第45条第6項及び第7項との関係
この配慮に加えて、派遣先が労働者派遣契約に定める就業条件に従って派遣労働者を労働させれ
ば、労働基準法の労働時間、休憩、休日、深夜業、危険有害業務の就業制限等の規定又は労働安全
衛生法上の就業制限、病者の就業禁止等の規定に抵触することとなる場合に、労働者派遣を行い、
現実に派遣先が当該規定に抵触した場合には、派遣元事業主も派遣先と同様に罰せられることとな
るので留意しておくこと(第9の2の(3)及び第9の3の(6)参照)。
(5)安全衛生に係る措置
派遣元事業者は、派遣労働者に対する雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を適切に行え
るよう、当該派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣先から入手すること、健康診断等の結果
に基づく就業上の措置を講ずるに当たって、派遣先の協力が必要な場合には、派遣先に対して、当
該措置の実施に協力するよう要請すること等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するため、
派遣先と必要な連絡調整等を行うこと(「派遣元が講ずべき措置に関する指針」第2の14(第7の
27参照))。派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な連絡調整等として、具体的
には、以下に掲げるものがあること。
イ 安全衛生教育に係る連絡調整等
(イ)派遣元事業主は、派遣労働者に対する雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を適切に行
えるよう、当該派遣労働者が従事する具体的な業務に係る情報を派遣先から事前に入手するとと
もに、教育カリキュラムの作成支援等の必要な協力を派遣先に対して求めること。
(ロ)派遣元事業主は、派遣先に対し、雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育の実施を委託し
た場合は、その実施結果について確認すること。また、派遣元事業主は、派遣労働者が、危険有
害業務に従事する場合には、派遣先が行った労働安全衛生法第59条第3項に規定する危険有害
業務就業時の安全衛生教育の実施結果を確認すること。
(ハ)派遣元事業主は、派遣先において派遣労働者の作業内容が変更されたことを把握した場合には
、派遣先が行った作業内容変更時の安全衛生教育の実施結果を確認すること。
ロ 危険有害業務に係る連絡調整等
派遣元事業主は、派遣労働者が従事することが予定されている労働安全衛生法第59条第3項又は
第61条第1項に規定する業務及びこれらの業務に係る当該派遣労働者の資格等の有無を確認し、必
要な資格等がない者がこれらの業務に従事することがないよう、派遣先と連絡調整を行うこと。
ハ健康診断の実施後の就業上の措置等に係る連絡調整等
(イ)派遣元事業主は、面接指導の実施又は健康診断の結果についての医師からの意見の聴取を適切
に行えるよう、派遣先から通知された当該派遣労働者の労働時間に加え、必要に応じ、その他の
勤務の状況又は職場環境に関する情報の提供を派遣先に対して求めること。
(ロ)派遣元事業主は、派遣労働者に対し、健康診断又は面接指導の結果に基づく就業上の措置を講
- 200 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
ずるに当たって、派遣先の協力が必要な場合には、派遣先に対して、当該措置の実施に協力する
よう要請すること。この場合において、派遣元事業主は、あらかじめ、就業上の措置の内容につ
いて当該派遣労働者の意見を聴くよう努めるとともに、派遣先への要請について当該派遣労働者
の同意を得ること。
(ハ)派遣元事業主は、派遣先が行った特殊健康診断の結果に基づく就業上の措置の内容に関する情
報の提供を派遣先に対して求めること。
ニ労働災害の再発防止対策に係る連絡調整等について
派遣元事業主は、派遣先に対し、派遣労働者に係る労働災害について、所轄労働基準監督署に提
出した労働者死傷病報告の写しの送付を受け、送付された写しを踏まえた労働者死傷病報告を所轄
労働基準監督署に提出すること。この場合において、派遣元事業主は、派遣先に対し、当該労働災
害の原因、再発防止のための対策等について必要な情報の提供を求め、これらの情報を雇入れ時及
び作業内容変更時の安全衛生教育に活用するとともに、当該労働災害に係る業務と同種の業務に従
事する派遣労働者にこれらの情報を提供すること。
ホ派遣労働者の安全衛生に係る措置について
イから二までのほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項に係る措
置その他の派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。
10 待遇に関する事項等の説明
(1)派遣労働者として雇用しようとするときの説明
イ 概要
派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、当該労働者を派遣労働者
として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する
事項等を説明しなければならない(法第31条の2第1項)。
ロ 意義
派遣労働者として就労しようとする労働者が、実際の就労時の賃金の額の見込み等を事前に把
握し、安心・納得して働くことができるよう、派遣元事業主に対し、待遇に関する事項等の説明
義務を課すものである。
ハ説明すべき待遇に関する事項等
説明すべき事項は、次のとおりである(則第25条の6第2項)。
(イ)労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の
当該労働者の待遇に関する事項
「賃金の額の見込み」とは、当該労働者の能力・経験・職歴・保有資格等を考慮し、当該
労働者を派遣労働者として雇用した場合の現時点における賃金額の見込みであり、一定の
幅があっても差し支えないこと。
「健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各労働・社会保険の被保険者となることに関する
- 201-
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
事項」については、社会保険等の制度に関する一般的な加入条件の説明で足りるが、予定さ
れている派遣就業がある場合には、当該派遣就業に就いた場合の社会保険等の被保険者資格
の取得の有無を明示すること。
「その他の当該労働者の待遇に関する事項」とは、想定される就業時間や就業日・就業場
所・派遣期間、教育訓練、福利厚生等が該当するが、当該時点において説明可能な事項につ
いて労働者に説明することで差し支えないこと。
(ロ) 事業運営に関する事項
具体的には、派遣元事業主の会社の概要(事業内容、事業規模等)を指しており、例えば、
既存のパンフレット等がある場合には、それを活用して説明することで差し支えないこと。
(ハ) 労働者派遣に関する制度の概要
「労働者派遣に関する概要」の説明については、労働者派遣制度の概要が分かれば足りる
ものであるが、特に派遣労働者の保護に関する規定については十分な説明が求められること
・ 労働者派遣法に改正があった場合は、改正法の内容についても説明することが求められる
こと。なお、既に派遣労働者として雇用している者については、派遣元責任者の責務として
、同様に改正の内容について説明すること(16(3)ホ参照)。
説明の際、例えば、厚生労働省で作成している派遣労働者向けのパンフレット又はそれと
同等以上の内容が盛り込まれた派遣元事業主で作成している資料を活用して説明することで
も差し支えないこと。
(ニ) 均衡待遇確保のために配慮した内容
均衡を考慮した待遇の確保を図るために配慮した内容の説明とは、例えば、派遣労働者の賃
金の決定にあたって派遣先から提供のあった派遣先の同種の労働者に係る賃金水準を参考にし
た等の説明をいう。
二説明の方法
(イ) 待遇に関する事項等の説明は、書面の交付、ファクシミリを利用してする送信又は電子
メールの送信その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、賃金の額の見込みを
説明する場合には、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送
信により行わなければならない。(則第25条の6第1項)。
(ロ) 「その他の適切な方法」としては、例えば、口頭やインターネットによる説明が考えら
れること。なお、インターネットにより説明する場合には、派遣元事業主のホームページのリ
ンク先を明示するなど、労働者が確認すべき画面が分かるようにする必要があること。なお、
(3)ハの「労働者派遣に関する制度」については、口頭のみにより説明することはできないと
考えられることから、派遣労働者に直接パンフレット等を配布することや、ファクシミリ又は
電子メールを利用して資料を送付することとし、インターネットにより説明する際も、厚生労
働省や派遣元事業主が作成した資料が掲載されたホームページのリンク先を電子メール等に明
- 202 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
示することにより、労働者が確認すべき画面が分かるようにする必要があること。
(ハ) 賃金の額の見込みを電子メールの送信により説明する場合には、電子メールの本文の中
で賃金の額の見込みを明示する必要があり、派遣元事業主のホームページのリンク先を明示す
ることによって説明に代えることは原則として認められない。
(ニ) 「派遣労働者として雇用しようとする労働者」とは、例えば、いわゆる登録型で労働者
派遣事業が行われる場合における登録状態にある労働者の他、いわゆる常用型で労働者派遣事
業が行われる場合で、新たに労働者を派遣労働者として雇用しようとする者(雇い入れ後に一
定期間研修を受講したり、派遣による就業以外の業務を行ったりした後に派遣される者を含む
。)等も該当すること。
(2)派遣労働者として雇い入れようとするときの明示及び説明
イ 概要
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該
労働者に対し、文書の交付等により、労働条件に関する事項を明示するとともに、第30条の3
(均等・均衡待遇の確保)、第30条の4第1項(一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の
確保)、第30条の5(職務の内容等を勘案した賃金の決定)の規定により措置を講ずべきこと
とされている事項に関し講ずることとしている措置の内容を説明しなければならない(法第31
条の2第2項)。
ロ 意義
派遣労働者の労働条件は、営業や派遣労働者を管理する仕事等に従事する労働者に比べて、
個々の事情に応じて多様に設定されることが多く、派遣労働者の雇入れ後に労働条件に関する
疑義が生じることも少なくない。また、そもそも派遣元事業主が派遣労働者についてどのよう
な雇用管理の改善等の措置を講じているのかについて、派遣労働者が認識していない場合も多
いと考えられ、こうしたことが派遣労働者の不安や不満につながっていると考えられる。
このため、派遣労働者の待遇に関する納得性を高め、紛争の防止を図れるよう、派遣元事業
主に対し、労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のもののうち、
特に派遣労働者にとって重要である労働条件に関する事項の明示義務を課すとともに、派遣労
働者の待遇について措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしている措置の
内容の説明義務を課すものである。
ハ 明示すべき労働条件に関する事項
明示すべき労働条件に関する事項は、次の(力~⑤の事項であり、これらは事実と異なるもの
としてはならない(則第25条の16、則第25条の17)。
(力 昇給の有無
「昇給」とは、一つの労働契約の中での賃金の増額をいう。したがって、有期労働契約の契
約更新時の賃金改定は、「昇給」に当たらない。
「昇給」が業績等に基づき実施されない可能性がある場合には、制度としては「有」と明示
- 203 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
しつつ、あわせて「昇給」が業績等に基づき実施されない可能性がある旨を明示することが必
要である。また、「賃金改定(増額):有」等の「昇給」の有無が明らかである表示をしてい
る場合には義務の履行といえるが、「賃金改定:有」と表示し、「賃金改定」が「昇給」のみ
であるか明らかでない場合等の「昇給」の有無が明らかでない表示をしている場合には義務の
履行とはいえない。
② 退職手当の有無
「退職手当」とは、労使間において、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確になっ
ており、退職により支給されるものであればよく、その支給形態が退職一時金であるか、退職
年金であるかを問わない。「退職手当」が勤続年数等に基づき支給されない可能性がある場合
には、制度としては「有」と明示しつつ、あわせて「退職手当」が勤続年数等に基づき支給さ
れない可能性がある旨について明示することが必要である。
③ 賞与の有無
「賞与」とは、定期又は臨時に支給されるものであって、その支給額が予め確定されていな
いものをいう。「賞与」が業績等に基づき支給されない可能性がある場合には、制度としては
「有」と明示しつつ、あわせて「賞与」が業績等に基づき支給されない可能性がある旨を明示
することが必要である。
④ 協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期
間の終期)
⑤ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
「派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項」とは、派遣労働者の苦情の申出を受
ける者、派遣元事業主及び派遣先において苦情処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携
のための体制等をいう。
- 明示の方法
明示は、文書の交付、ファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信により行わな
ければならない(法第31条の2第2項、則第25条の16)。
ホ 説明すべき措置の内容
説明の内容は、次の(力~③に掲げる内容である。
① 法第30条の3の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしてい
る措置の内容
派遣労働者の待遇のうち均衡待遇の対象となるものについては、派遣先に雇用される通常の
労働者との間で不合理な相違を設けない旨をいうこと。派遣労働者の待遇のうち均等待遇の対
象となるものについては、派遣先に雇用される通常の労働者との間で差別的な取扱いをしない
旨をいうこと。
② 法第30条の4第1項の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることと
している措置の内容
- 204 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
派遣労働者の賃金及び賃金以外の待遇(法第40条第2項の教育訓練及び同条第3項の福利厚
生施設を除く。)が法第30条の4第1項の労使協定に基づき決定される旨をいうこと。
③ 法第30条の5の規定により措置を講ずべきこととされている事項
均衡待遇の対象となる派遣労働者の賃金について、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又
は経験その他の就業の実態に関する事項のうちどの要素を勘案するかをいうこと。
へ 説明の方法
説明は、書面の活用その他の適切な方法により行わなければならない(則第25条の18)。
派遣労働者が、派遣元事業主が講ずる措置の内容を理解できるよう、書面を活用し、口頭によ
り行うことが基本である。当該書面としては、就業規則、賃金規程、派遣先に雇用される通常の
労働者の待遇のみを記載した書面が考えられる。また、派遣労働者が措置の内容を的確に理解す
ることができるようにするという観点から、説明に活用した書面を交付することが望ましい。
一方、説明すべき事項を全て記載した派遣労働者が容易に理解できる内容の書面を用いる場合
には、当該書面を交付する等の方法でも差し支えない。なお、待遇の内容の説明に関しては、就
業規則の条項を書面に記載し、その詳細は、別途就業規則を閲覧させるという方法も考えられる
が、派遣元事業主は、就業規則を閲覧する者からの質問に、誠実に対応する必要がある。
ト 明示及び説明に関する留意点
(イ)有期雇用派遣労働者については、労働契約の更新をもって雇い入れることとなるため、労
働契約の更新の都度、法第31条の2第2項に基づく明示及び説明が必要となる。
(ロ)明示及び説明に当たっては、個々の派遣労働者ごとに行うほか、雇い入れ時の説明会等に
おいて複数の派遣労働者に同時に説明を行う等の方法によっても差し支えない。
(ハ)労働者を無期雇用派遣労働者として雇い入れる場合、その時点では派遣先が決まっていな
い場合がある。
この場合の明示に当たっては、その時点で締結しようとしている労働契約に基づく昇給の
有無等を明示すること。また、この場合の説明に当たっては、派遣先が決定されていない場
合には、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から派遣元事業主への比較対象労働者
の待遇等に関する情報が提供されておらず、具体的な説明は困難であることから、待遇決定
方法に関する制度の説明で足りることとする。
(3)労働者派遣をしようとするときの明示及び説明
イ 概要
派遣元事業主は、労働者派遣(労使協定に係るものを除く。)をしようとするときは、あらか
じめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、労働条件に関する事項を
明示するとともに、法第30条の3(均等・均衡待遇の確保)、第30条の4第1項(一定の要件を
満たす労使協定に基づく待遇の確保)、第30条の5(職務の内容等を勘案した賃金の決定)の規
定により措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしている措置の内容を説明し
なければならない(法第31条の2第3項)。
- 205 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
口 意義
法第30条の3(均等・均衡待遇の確保)が適用される場合、一つの労働契約を継続している場
合でも、派遣先が変わるごとに待遇の内容が変わることがあり得る。一方、労働者派遣をしよう
とするときには、労働基準法第15条第1項に基づく労働条件の明示は義務付けられていない。
このため、派遣元事業主に対し、均等・均衡待遇の確保により大きく変更されることがあり得
る労働条件に関する事項について、労働者派遣の都度明示する義務を課したものである。また、
待遇の内容に加えて、派遣元事業主が講ずる措置も大きく変更されることがあり得ることから、
労働条件に関する事項とあわせて説明することを義務付けたものである。
ハ明示すべき労働条件に関する事項
明示すべき労働条件は、労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び
雇い入れようとするときに明示しなければならない事項から厚生労働省令で定める事項を除いた
ものであり、具体的には、次の①~⑥に掲げる事項である(法第31条の2第3項第1号、則第
25条の20)。協定対象派遣労働者以外の派遣労働者にあっては(力~⑥に掲げる事項、協定対象
派遣労働者にあっては⑥に掲げる事項を明示しなければならない。
(力 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。)の決定等に関する事項
② 休暇に関する事項
③ 昇給の有無
④ 退職手当の有無
⑤ 賞与の有無
⑥ 協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期
間の終期)
ニ 明示の方法
(イ)明示は、文書の交付、ファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信により行
わなければならない(法第31条の2第3項)。
(ロ)ただし、当該労働者派遣の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ、(イ)のい
ずれかの方法によることができない場合は、明示すべき事項を、あらかじめ、(イ)のいず
れかの方法以外の方法で明示すればよい(則第25条の19第1項)。
この「緊急の必要があるため、あらかじめ、(イ)のいずれかの方法によることができな
い場合」とは、社会通念上(イ)のいずれかの方法によるための時間的余裕がないことを意
味するものであり、この取扱いはあくまで例外的な取扱いであることに十分留意すること。
(ハ)(ロ)の場合でも、派遣労働者から労働者派遣の開始よりも前に個別の請求(その方法は
問わない。)があったとき、又は当該請求がなくても当該労働者派遣の期間が一週間を超え
るときは、当該労働者派遣の開始後、遅滞なく、当該明示すべき事項を(イ)のいずれかの
方法により個々の派遣労働者に明示しなければならない(則第25条の19第2項)
ホ 説明すべき措置の内容
- 206 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
措置の内容は、(2)のホの①~③に掲げる内容である。ただし、法第30条の4第1項の規定に
より措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしている措置の内容については、
説明を要しない。
へ 説明の方法
当該説明は、(2)のへと同様の方法により行わなければならない。
(4)待遇の相違の内容及び理由等の説明
イ 概要
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、当該派遣労働者に対し、
当該派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第30条の3から第30
条の6までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考
慮した事項を説明しなければならない(法第31条の2第4項)。
ロ 意義
派遣労働者の待遇に関する納得性を高めるとともに、派遣労働者が自らの待遇に納得できない
場合に、まずは、労使間での対話を行い、不合理な待遇差の是正につなげていくとともに、事業
主しか持っていない情報のために、派遣労働者が訴えを起こすことができないことを防止する等
のため、派遣元事業主に対し、派遣労働者の求めに応じ、派遣労働者と比較対象労働者との間の
待遇の相違の内容及び理由等の説明義務を課すこととしたものである。
ハ 説明すべき内容
説明の内容は、次のとおりである(派遣元指針第2の9の(1)及び(2))。
(イ)派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第30条の3及び第
30条の4の規定より講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した
事項
a 協定対象派遣労働者以外の派遣労働者の場合
派遣元事業主は、法第26条第7項及び第10項並びに第40条第5項の規定により提供を受け
た情幸酎こ基づき、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由を説明し
なければならない。
「派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容」とは、次に掲げる事項をいい
、あわせて、比較対象労働者が第6の2の(3)のハの(イ)の①~⑥のいずれに該当するか、ど
のような区分等であるか(一人の労働者、複数人の労働者、雇用管理区分、過去1年以内に
雇用していた一人の労働者、標準的なモデル等)及び派遣先による比較対象労働者の選定理
由についても、説明を求めた派遣労働者に説明する必要がある。なお、個人情報保護の観点
から、説明を受けた派遣労働者において、比較対象労働者が特定されることのないよう配慮
する必要があることに留意すること。
(a)派遣労働者及び比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項
(b)次の(力又は②に掲げる事項
- 207 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
(力 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇の個別具体的な内容
例えば、賃金であれば、比較対象労働者が一人である場合にはその金額、比較対象労
働者が複数人である場合にはその平均額又は上限額・下限額をいうこと。
② 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇に関する基準
説明を求めた派遣労働者が比較対象労働者の待遇の水準を把握できるものであること
が必要である。例えば、賃金であれば、賃金規程や等級表等の支給基準をいうが、あわ
せて比較対象労働者がどの賃金水準となるかを含む内容であることが必要である。
また、「派遣労働者と比較対象労働者の待遇の相違の理由」については、派遣元事業主は
、派遣労働者及び比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の
事情のうち、待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるものに基づき、説
明しなければならない。
具体的には、派遣先から提供を受けた比較対象労働者の待遇に関する情報等を踏まえっっ
、派遣労働者と比較対象労働者の待遇に関する基準が同一である場合には、同一の基準のも
とで違いが生じている理由(職務の成果、能力、経験の違い等)を、派遣労働者と比較対象
労働者の待遇に関する基準が異なる場合には、待遇の性質・目的を踏まえ、待遇に関する基
準に違いを設けている理由(職務の内容、職務の内容及び配置の変更範囲、労使交渉の経緯
等)並びにそれぞれの基準を派遣労働者及び比較対象労働者にどのように適用しているかを
説明しなければならない。
b 協定対象派遣労働者の場合
協定対象派遣労働者の賃金について、派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の賃金が労使
協定で定めた事項及び労使協定の定めによる公正な評価に基づき決定されていることについ
て説明しなければならない。また、労使協定に定められた待遇の決定方法をどのように適用
したか、例えば、能力をどのような方法でどのように評価して賃金を決定したか、を説明し
なければならない。
加えて、派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の待遇(賃金、法第40条第2項の教育訓練
及び同条第3項の福利厚生施設を除く。)について、当該待遇が労使協定で定めた決定方法
に基づき決定されていること、法第40条第2項の教育訓練及び同条第3項の福利厚生施設に
ついて、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で均等・均衡が確保されてい
ることについて、(イ)の説明に準じて説明しなければならない。
(ロ)法第30条の5(職務の内容等を勘案した賃金の決定)の規定より講ずべきこととされてい
る事項に関する決定をするに当たって考慮した事項
賃金の決定に当たって勘案する職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験等のうちどれ
を勘案しているか、どのように勘案しているかをいう。
(ハ)法第30条の6(就業規則の作成の手続)の規定より講ずべきこととされている事項に関す
る決定をするに当たって考慮した事項
- 208 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
就業規則の作成又は変更しようとするときの意見聴取の対象となった派遣労働者がどのよ
うに選出され、どのような事項に関して意見聴取したのかをいう。
ニ 説明の方法
当該説明は、(2)のへと同様の方法により行わなければならない(派遣元指針第2の9の(3)
)。
ホ 不利益な取扱いの禁止
派遣元事業主は、派遣労働者が法第31条の2第4項の規定により説明を求めたことを理由とし
て、当該派遣労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(法第31条の2第5
項)。
へ 比較対象労働者が短時間・有期雇用労働者又は仮想の通常の労働者である場合の説明
比較対象労働者が第6の2の(3)のハの(イ)の⑤の短時間・有期雇用労働者である場合には、派
遣労働者の求めに応じ、比較対象労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で、短時間・
有期雇用労働法第8条等の規定に基づく均衡が確保されている根拠を説明しなければならない。
また、比較対象労働者が第6の2の(3)のハの(イ)の⑥の仮想の通常の労働者である場合には、
派遣労働者の求めに応じ、比較対象労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で、適切な
待遇が確保されている根拠を説明しなければならない。
これらの場合において、法第26条第7項に基づき派遣先から提供されている比較対象労働者の
待遇等に関する情幸酎こよる説明が困難な場合は、派遣元事業主は、法第40条第5項により派遣先
に雇用される労働者に関する情報の提供を求めることができ、派遣先はその求めに応じ的確に対
応することが求められる。
ト 派遣労働者からの求めがない場合の対応
派遣元事業主は、派遣労働者から求めがない場合でも、当該派遣労働者に対し、比較対象労働
者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに法第30条の3から第30条の6までの規定により措置
を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項に変更があったと
きは、その内容を情報提供することが望ましい(派遣元指針第2の9の(4))。
11派遣労働者であることの明示等
(1)雇入れの際の明示
イ 概要
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労
働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む
。)を明示しなければならない(法第32条第1項)。
また、派遣労働者の労働条件の明確化を図るため、モデル労働条件通知書により労働契約内容
が明示されるようにする。
- 209 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
口 雇入れの際の明示の意義
(イ)雇入れの際の明示は、労働者が派遣労働者という地位(第1の2参照)を取得して雇用さ
れること(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む
。)を個々に明確にするために行うものである。このため、派遣労働者となるのかどうか(
紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、紹介予定派遣に係る派遣
労働者となるのかどうか)が不明確なものであってはならない。
(ロ)明示は、労働契約の締結に際し、事前に行われなければならない。
(ハ)労働者を派遣労働者として雇い入れようとする際に、あらかじめ、その旨(紹介予定派遣
に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、それを承
知で当該労働者が雇い入れられた場合は、派遣労働者となることについて同意が得られたも
のと解され、それが労働契約の内容となっていると解される。
ハ モデル労働条件通知書の普及
派遣労働者の労働条件の明確化を図るため、許可の機会等をとらえて、派遣労働者の雇入れ
の際にモデル労働条件通知書(第16 様式集参照)により当該派遣労働者との労働契約内容を
明示するよう、様式の利用を勧奨すること。
ニ 登録型については、労働条件の通知と就業条件等の明示(第7の13参照)が同時に行われ、
また、短期の雇用契約を繰り返し行う派遣労働者については、その都度行われるものであるが
、労働条件通知書の雇用・社会保険の加入状況は派遣労働者と新たな労働契約を締結して雇い
入れ、労働条件通知書を明示する際に加入又は適用されていなくても、繰り返し労働契約を締
結し、被保険者資格を取得した際に加入又は適用とすればよく、その旨の徹底を図ることによ
り、この加入又は適用状況の明示ができないことを理由に通知、明示が遅れることのないよう
努めること。
(2)雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意
イ 概要
派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外の
ものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新
たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)明示し、その同意
を得なければならない(法第32条第2項)。
ロ 意義
(イ)「新たに労働者派遣の対象としようとする」とは、派遣労働者としての地位を取得してい
ない労働者に対し新たに当該地位を取得させようとすることをいい、既に当該地位を取得し
ている派遣労働者については労働者派遣を行うごとに同意を要するものではない。
ただし、派遣労働者として雇い入れた労働者を、新たに紹介予定派遣の対象としようとする
場合には、明示及び同意を要するものである。
(ロ)明示及び同意は、労働者派遣の実施に際し、事前に行われなければならない。
- 210 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
(3)派遣労働者であることの明示等に関する留意点
イ 雇入れの際の明示に当たって、労働協約又は就業規則に「労働者派遣の対象となる」旨(紹
介予定派遣の対象となる場合にはその旨)の定めがある場合に当該労働協約等を明示し当該労
働者が当該労働協約又は就業規則の適用対象であることが明確である場合は、当該労働協約等
の明示をすれば雇入れの際の明示と解し得るものであること。
ロ 雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意については、当該労働者を採用した後に、
新たに労働協約又は就業規則に「労働者派遣の対象となる」旨の定めを設けた場合であっても
、それだけでは、明示及び同意があったとは解されず新たに労働者派遣の対象とする際に個々
の労働者について、あらかじめ、行わなければならないものである。
ハ 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止
派遣元事業主は、労働者を新たに派遣労働者としようとする場合であって、当該労働者がその
旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)同意をしない
ときにおいて、当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(「派遣元事業主
が講ずべき措置に関する指針」第2の7(第7の27参照))。
ニ 労働者を派遣労働者として転籍させる場合の取扱い
事業主が自ら雇用する労働者を転籍させる場合における一般的な取扱いと同じく、事業主は
雇用する労働者を当該事業主以外の派遣元事業主に雇用される派遣労働者として転籍させよう
とするときについても、あらかじめ労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとす
る場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならないものであり、
その旨の周知、指導の徹底を図る。
ホ 紹介予定派遣の対象者として登録を行う場合の取扱い
派遣元事業主は紹介予定派遣の対象として登録しようとするときは、あらかじめその旨を当該
労働者に明示しなければならないものであり、その旨の周知、指導の徹底を図ること(既に労働
者派遣の登録を行い、又は求職の申込みをしている者を紹介予定派遣の対象とする場合も同様の
取扱いとする。)。
12派遣労働者に係る雇用制限の禁止
(1)概要
イ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者(
第7の8の(3)のイ参照)との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先若しくは派遣先で
あった者又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用される
ことを禁ずる旨の契約を締結してはならない(法第33条第1項)。
例えば、「退職後6箇月間は派遣先に雇用されないこと」等を定める契約は原則として締結
できない。
ロ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする
- 211-
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の
終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない(法第33条第2項)。
例えば、「派遣先が労働者派遣を受けた派遣労働者について、当該労働者派遣の終了後、1
年間は雇用しないこと」等を定める契約は原則として締結できない。
(2)派遣労働者に係る雇用制限の禁止の意義
イ 派遣労働者に係る雇用を制限する契約の定めは、憲法第22条により保障されている労働者の
職業選択の自由を実質的に制約し、労働者の就業機会を制限し、労働権を侵害するものであり
、派遣元事業主と派遣労働者間における派遣先に雇用されない旨の定め、あるいは、派遣元事
業主と派遣先間における派遣先が派遣労働者を雇用しない旨の定めをすることは禁止される。
ロ このような契約の定めは、一般の雇用関係の下にある労働者についても、公序に反し、民法
第90条により無効とされており、仮に契約上そのような定めがあっても、契約の相手方である
派遣労働者又は派遣先はこれに従う必要はない。
ハ なお、禁止されるのは雇用関係の終了後、雇用し、又は雇用されることを禁ずる旨の契約で
あって、雇用契約の終了以前(特に期間の定めのある雇用契約においては当該期間内)につい
て、派遣労働者を雇用し、又は雇用されることを禁ずる旨の契約を締結すること自体は、許容
することができるものである。
(3)「正当な理由」の意義
「正当な理由」は、競業避止義務との関係で問題となるが、雇用契約の終了後特定の職業に就
くことを禁ずる定めについては、次のように考えられる。
イ 労働者が雇用関係継続中に習得した知識、技術、経験が普遍的なものではなく、特珠なもの
であり、他の使用者の下にあっては、習得できないものである場合には、当該知識、技術、経
験は使用者の客体的財産となり、これを保護するために、当該使用者の客体的財産について知
り得る立場にある者(例えば、技術の中枢部に接する職員)に秘密保持義務を負わせ、かつ、
当該秘密保持義務を実質的に担保するため雇用契約終了後の競業避止義務を負わせることが必
要である場合については、正当な理由が存在するといえる。
ロ 具体的には、制限の時間、場所的範囲、制限の対象となる機種の範囲、代償の有無について
、使用者の利益(企業秘密の保護)、労働者の不利益(職業選択の自由の制限)、社会的利害
(独占集中のおそれ等)を総合的に勘案して正当な理由の存否を決定する。
ハ しかしながら、派遣労働者が、もともと他社に派遣され就業するという性格を有することか
らすると、このような正当な理由が存在すると認められる場合は非常に少ないと解される。
13 就業条件等の明示
(1)概要
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労
働者に対し、労働者派遣をする旨、当該派遣労働者に係る就業条件並びに派遣先の事業所単位の期
- 212 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
間制限に抵触することとなる最初の日及び派遣労働者個人単位の期間制限に抵触することとなる最
初の日を明示しなければならない(法第34条)。
(2)意義
派遣労働者に対する就業条件等の明示は、労働者派遣契約の締結に際しての手続等(第6の2の
(1)参照)及び派遣先への通知(第7の15参照)と相まって派遣元事業主、派遣先、派遣労働者の
三者間において就業条件等を明確化し、トラブルの発生を防止するとともに、派遣労働者が当該労
働者派遣に係る期間制限を認識できるようにすることは派遣労働者のためにも望ましく、また、派
遣先の事業所単位の期間制限及び派遣労働者個人単位の期間制限の規定を遵守させるためにも有用
であると考えられるためのものである。
(3)明示すべき就業条件等
イ 明示すべき具体的就業条件等
具体的には、労働者派遣契約で定めた次に掲げる事項のうち当該契約により労働者派遣され
る個々の派遣労働者に係るものを明示しなければならない(法第34条)。
(力 派遣労働者が従事する業務の内容
・ 令第4条第1項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げ
る業務の号番号を付すこと。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明ら
かである場合は、この限りではない。
・「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、
(i)無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合
(の 契約期間が31日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合
(の(a)又は(b)の労働者派遣に限る場合
のいずれかであり、かつその旨が就業条件等の明示の際に派遣労働者に明示されている場
合である。
② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
・ 派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程
度等をいうこと。
・ チームリーダー、副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職
を、役職を有さない派遣労働者であればその旨を明示することで足りるが、派遣労働者が
自ら従事する業務に伴う責任の程度について正確に認識できるよう、より具体的に明示す
ることが望ましい。
③ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称、所在地その他派遣就業の場
所及び組織単位
④ 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
⑤ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
⑥ 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
- 213 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
⑦ 安全及び衛生に関する事項
・ 派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項(危険有害業務の内
容)等の労働者派遣契約において定めた安全及び衛生に関する事項(第6の2の(1)のイの
(ハ)の⑦参照)
⑧ 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事
項
⑨ 派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用
を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講
ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
⑲ 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従事
すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項として以下の事項
・ 紹介予定派遣である旨
・ 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される労働条件
【例】
I 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
Ⅱ 労働契約の期間に関する事項
Ⅲ 試用期間に関する事項
※ ただし、紹介予定派遣により雇い入れた労働者について試用期間を設けることは望ま
しくない。
Ⅳ 就業の場所に関する事項
Ⅴ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時聞及び休日に関する事項
Ⅵ 賃金の額に関する事項
Ⅶ 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法によ
る労働者災害保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項
Ⅷ 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹
介を受けた者を雇用しなかった場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ
、書面、ファクシミリ又は電子メール等(ファクシミリ又は電子メール等による場合にあっ
ては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)により、派遣労働者に対して明示する旨
紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて
、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨
労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨
⑪ 派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日(期間制限のない労働者派遣に該当す
- 214 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
る場合はその旨)((4)のイ参照)
⑫ 派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日(期間制限のない労働者派遣に該当す
る場合はその旨)((4)のロ参照)
⑬ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
⑭ 派遣先が⑤の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は⑥の派遣就
業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契
約において行った場合には、当該派遣就業させることができる日又は当該延長することがで
きる時間数
⑮ 派遣元事業主及び派遣先との間で、派遣先が当該派遣労働者に対し、派遣先が設置及び運
営する物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、
体育館、保養施設等の施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(
給食施設、休憩室及び更衣室を除く。)の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の
利用、制服の貸与、教育訓練その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定
めをした場合には、当該便宜の供与に関する事項についても記載すること。
なお、派遣先の給食施設、休憩室及び更衣室の利用については、法律上の就業条件の明示事
項ではないが、法第40条第3項の規定に基づき利用機会を付与しなければならないものとされ
ていることに留意すること。
⑱ 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派
遣労働者を雇用する場合に、その雇用意思を事前に労働者派遣をする者に対し示すこと、当
該者が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の
労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置
なお、派遣労働者に対する就業条件等の明示の際には、紛争防止措置を簡潔に示すことでも
差し支えない。
⑰ 則第27条の2第1項各号に掲げる健康保険被保険者資格取得届等の書類が行政機関に提出さ
れていない場合は、その理由(則第26条の2)
⑱ 期間制限のない労働者派遣に関する事項
・ 有期プロジェクトの業務について労働者派遣を行うときは、法第40条の2第1項第3号イ
に該当する旨を記載すること。
日数限定業務について労働者派遣を行うときは、①法第40条の2第1項第3号ロに該当す
る旨、②当該派遣先において、同号ロに該当する業務が1箇月間に行われる日数、③当該派
遣先の通常の労働者の1箇月間の所定労働日数を記載すること。
法第40条の2第1項第5号に掲げる育児休業等の代替要員としての業務について労働者派
遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び
終了予定の日を記載すること。
法第40条の2第1項第5号に掲げる介護休業等の代替要員としての業務について労働者派
- 215 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び
終了予定の日を記載すること。
ロ 就業条件の明示に関する留意点
(イ)労働者派遣契約においては、(力から⑱までの内容の組合せごとに派遣労働者の人数を定め
ることとされているが、この就業条件の明示は個々の派遣労働者に係るこれらの事項である
ため、労働者派遣契約に定めた派遣期間内等において派遣労働者を入れ替える等の場合には
、労働者派遣契約に定めるこれらの事項の内容とこの就業条件の明示の内容が相違するもの
である。
(ロ)個々の派遣労働者に明示される就業条件は、労働者派遣契約の定めた就業条件の範囲内で
なければならない。
(4)期間制限に抵触することとなる最初の日の明示
イ 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、当該労働者派遣が期間制限の適用を受け
ないものである場合を除き、あらかじめ、派遣労働者に対して、
(力 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組
織単位の業務について派遣元事業主が期間制限に抵触することとなる最初の日(個人単位の期
間制限の抵触日。法第34条第1項第3号)
② 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所等の業務について、派遣先が期間
制限に抵触することとなる最初の日(派遣先の事業所単位の期間制限の抵触日。法第34条第1
項第4号)
を明示しなければならない。
派遣労働者の個人単位の期間制限に抵触する日は、当該派遣労働者が当該派遣先の同一の組織
単位で就業することを超える日であるため、当該抵触日をあらかじめ通知しておくことによって
、個人単位の期間制限の到来により労働者派遣が終了したことによる雇用契約の更新をめぐるト
ラブルを未然に防ぐことができる。また、派遣先の事業所単位の期間制限については、派遣労働
者の個人単位の期間制限の日が到来する前に当該派遣先の事業所単位の期間制限の抵触日が到来
し派遣可能期間が延長されない場合は、その時点において当該派遣先で就業できる上限となる。
こうしたことから、派遣元事業主に対し、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、派遣
労働者個人単位と派遣先の事業所単位の双方の期間制限抵触日を派遣労働者に明示する義務を課
すものである。
ロ 派遣先は、派遣先の事業所単位の派遣可能期間が延長された場合には、速やかに、当該労働者
派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣先の事業所単位の期間制限に抵触することとなる最初
の日を通知しなければならないこととされている。(第8の5の(5)参照)派遣元事業主は派遣
先から当該通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事業所等における派遣労働に従事す
る派遣労働者に対し、当該日を明示しなければならない(法第34条第2項)。
ハ 派遣元事業主は、派遣労働者に対し就業条件等の明示をするに当たっては、派遣先が派遣先の
- 216 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
事業所ごとの派遣期間の制限又は同一の派遣労働者に係る組織単位ごとの派遣期間の制限に違反
して労働者派遣の役務の提供を受けた場合には労働契約の申込みをしたものとみなされることと
なる旨を併せて明示しなければならない。
さらに、派遣元事業主は、労働契約申込みみなし制度が適用される場合については、期間制限
以外の事由によるものもあることについて厚生労働省が公表しているリーフレット等により明示
することが望ましいこと。
(参考)就業条件等の明示の例
次の条件で労働者派遣を行います。
1 従事する業務の内容 営業課内における事務の補助、電話応対、郵便物の仕分・発送の
業務
2 業務の内容に伴う責任の程度 副リーダー(部下2名、リーダー不在の間における緊急対
応が過1回程度有)
3 就業の場所 □□□□株式会社本社 国内マーケテイング部営業課総務係
(〒110-8988 千代田区霞が関1-2-20ビル14階TEL3593-****内線5745)
4 組織単位 国内マーケテイング部営業課
5 指揮命令者 国内マーケテイング部営業課総務係長 △△△△△
6 派遣期間 平成27年10月1日から平成28年9月30日まで
(派遣先の事業所における期間制限に抵触する最初の日 平成30年10月1日)
(組織単位における期間制限に抵触する最初の日 平成30年10月1日)
※派遣先の事業所における期間制限の抵触日は延長されることがあるが、組織単位における
期間制限の抵触日は延長されることはない。
なお、派遣先の事業所における派遣可能期間の延長について、当該手続を適正に行って
いない場合や派遣労働者個人単位の期間制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場
合は、派遣先は労働契約申込みみなし制度の対象となる。
7 就業日 土、日を除く毎日
8 就業時間 9時から18時まで
9 休憩時間12時から13時まで
10 安全及び衛生
次の事項のうち、派遣労働者が派遣先において業務を遂行するに当たって、当該派遣労働
者の安全、衛生を確保するために必要な事項に関し、就業条件を記載する
○危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項
○健康診断の実施等健康管理に関する事項
○換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項
○安全衛生教育に関する事項
○免許の取得、技能講習の終了の有無等就業制限に関する事項
- 217 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
〔
○安全衛生管理体制に関する事項
○その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項
〕
11派遣労働者からの苦情の処理
(1)苦情の申出を受ける者
派遣元においては、派遣事業運営係主任 ☆☆☆☆☆ TEL3597-**** 内線101
派遣先においては、総務部秘書課人事係主任 ※※※※※ 内線5721
(2)苦情処理方法、連携体制等
① 派遣元における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者の
◎◎◎◎◎へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意をもって、遅
滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労
働者に通知することとする。
② 派遣先における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者の
MHへ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意をもって、遅
滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労
働者に通知することとする。
③ 派遣元事業主及び派遣先は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他
は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いっつ、その解決を図るこ
ととする。
12 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事
由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係
る派遣先と連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受けること、当該
派遣元事業主において他の派遣先を確保すること等により、当該労働者派遣契約に係る派遣
労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。また、当該派遣元事業主は、当該労働者
派遣契約の解除に当たって、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、
当該派遣労働者の雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払の労働基準法等に
基づく責任を果たすこととする。さらに、やむを得ない事由によりこれができない場合にお
いて、当該派遣労働者を解雇しようとするときであっても、労働契約法の規定を遵守するこ
とはもとより、少なくとも30日前に予告することとし、30日前に予告しないときは労働基準
法第20条第1項に基づく解雇予告手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条
に基づく休業手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。
13 派遣元責任者
〇〇〇〇株式会社 派遣事業運営係長 ◎◎◎◎◎ TEL3597-**** 内線100
14 派遣先責任者
- 218 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
総務部秘書課人事係長 MH 内線5720
15 就業日外労働
6の就業日以外の日の労働は1箇月に2日の範囲で命ずることができるものとする。
16 時間外労働
7の就業時間外の労働は1日4時間、1箇月45時間、1年360時間の範囲で命ぜられるこ
とがある。
17 □□□□株式会社内の診療所の利用可。制服の貸与あり。
18 労働者派遣に関する料金
日額 *****円(労働契約時に明示しており、変更がない場合は不要)
19 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、その雇用
意思を事前に派遣元事業主に対して示すこと。
また、職業紹介を経由して行うこととし、紹介手数料として、派遣先は派遣元事業主に対し
て、支払われた賃金額の●●分の●●に相当する額を支払うものとする。ただし、引き続き
6箇月を超えて雇用された場合にあっては、6箇月間の雇用に係る賃金として支払われた賃
金額の●分の●に相当する額とする。
(紹介予定派遣に係る契約である場合は下記の項目例を記載)
20 紹介予定派遣に関する事項
(1)派遣先が雇用する場合に予定される労働条件等
契約期間 期間の定めなし
業務内容 営業課内における事務の補助、電話応対、郵便物の仕分・発送の
業務
試用期間に関する事項 なし
就業場所 □□□□株式会社本社 国内マーケテイング部営業課総務係
(〒110-8988 千代田区霞が関1-2-20ビル14階TEL3593-****内線5745)
始業・終業 始業:9時 終業:18時
休憩時間 12時から13時まで
所定時間外労働 有(1日4時間、1箇月45時間、1年360時間の範囲内)
休日
休暇
賃金
毎週土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、
夏季休業(8月13日から8月16日)
年次有給休暇:10日(6箇月継続勤務後)その他:有給(慶弔休暇)
基本賃金月給180,000~240,000円(毎月15日締切、毎月20日支払)
通勤手当:通勤定期券代の実費相当(上限月額35,000円)
所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
- 219 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
・所定時間外:法定超 25%、休日:法定休日 35%、深夜:25%
昇給:有(0~3,000円/月) 賞与:有(年2回、計1箇月分)
社会保険の加入状況 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険 有
労働者を雇用しようとする者の名称 □□□□株式会社
(2)その他
・ 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職
業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求
めに応じ、書面、ファクシミリ又は電子メール等により明示する。
・ 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いにつ
いて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する。
(5)明示の方法
就業条件等の明示は次により行うこととする(則第26条)。
イ 就業条件等の明示は、労働者派遣に際し、あらかじめ、明示すべき事項を書面、ファクシミ
リ又は電子メール等(※)(ファクシミリ又は電子メール等による場合にあっては、当該派遣
労働者が希望した場合に限る。)により個々の派遣労働者に明示することにより行わなければ
ならない。また、(4)のロの明示については、派遣先から当該通知を受けた後、遅滞なく、明示
すべき事項を書面、ファクシミリ又は電子メール等(ファクシミリ又は電子メール等による場
合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)により個々の派遣労働者に明示する
ことにより行わなければならない。
!※ 「電子メール等」とは
「電子メール等」とは、「電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達する
!ために用いられる電気通信」をいう。
この「その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」と
Hj:、具体的には、LINEやFacebook等のSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)メッセ
トジ機能等を利用した電気通信が該当すること。
また、電子メール等により行う就業条件等の明示等の派遣労働者への明示又は説明について
:は、当該明示又は説明された事項を派遣労働者がいっでも確認することができるよう、当該派
;遣労働者が保管することのできる方法により明示する必要がある。このため、電子メール等に
巨いては、当該派遣労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成できる
;ものに限ることとしている。この場合において、「出力することにより書面を作成することが
;できる」とは、当該電子メール等の本文又は当該電子メール等に添付されたファイルについ
:て、紙による出力が可能であることをいうが、就業条件等の明示等を巡る紛争の未然防止及び
;書類管理の徹底の観点から、モデル就業条件明示書等に記入し、電子メール等に添付し送信す
;る等、可能な限り紛争を防止しつつ、書類の管理がしやすい方法とすることが望ましい。
- 220 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
なお、これらのサービスによっては、情報の保存期間が一定期間に限られている場合がある
ことから、派遣労働者が内容を確認しようと考えた際に情報の閲覧ができない可能性があるた
め、派遣元事業主は、当該明示又は説明を行うにあたっては、派遣労働者に対し、当該明示又
は説明の内容を確認した上でその内容を適切に保管するよう伝えることが望ましい。また、仮
に保存期間が経過するなど、派遣労働者が内容を確認することなく必要な情報が削除されてし
まった場合には、派遣元事業主は、派遣労働者の求めに応じて、再度その情報を送信するなど
適切に対応することが望ましい。
ロ ただし、就業条件等の明示については、当該労働者派遣の実施について緊急の必要があるた
め、あらかじめ、イのいずれかの方法によることができない場合は、明示すべき事項を、あら
かじめ、イのいずれかの方法以外の方法で明示すればよいこととする。「緊急の必要があるた
め、あらかじめ、イのいずれかの方法によることができない」とは、社会通念上、イのいずれ
かの方法によるための時間的余裕がないことを意味するものであり、この取扱いはあくまで例
外的な取扱いであることに十分留意すること。
ハ ロの場合でも、派遣労働者から労働者派遣の開始より前に個別の請求(その方法は問わない
。)があったとき、又は当該請求がなくても当該労働者派遣の期間が一週間を超えるときは、当
該労働者派遣の開始後、遅滞なく、当該明示すべき事項をイのいずれかの方法により個々の派
遣労働者に明示しなければならない。
(6)明示に関する留意点
イ 就業条件等の明示及び(4)の明示をファクシミリ又は電子メール等により行うことについては
、当該派遣労働者が当該方法によることを希望することが条件となっている。派遣元事業主によ
る派遣労働者の希望の確認は、事後のトラブルを防止する観点から、口頭により行うのではなく
、派遣労働者が希望したことを事後的に確認できる方法(例えば、労働契約書等に記載欄を設け
、ファクシミリ又は電子メール等による明示を希望する派遣労働者はその旨を同欄に記載するこ
ととする等)により行うことが望ましい。また、派遣元事業主がファクシミリ又は電子メール等
による明示を希望するよう派遣労働者に強いてはならないことは、当然である。
ロ また、就業条件等の明示及び(4)の明示をファクシミリ又は電子メール等により行う場合にあ
っては、到達の有無に関して事後のトラブルが起きることを防止する観点から、派遣元事業主は
ファクシミリ又は電子メール等の到達の有無について確認を行う(例えば、到達した旨の返信を
派遣労働者に求め、当該返信がない場合は、再送することとする等)ことが望ましい。
ハ さらに、派遣元事業主は、派遣労働者のメールアドレスを取得した場合は、法第24条の3によ
り、労働者の個人情報の適正な取扱いが求められていることに留意する必要がある。
ニ 就業条件及び(4)の明示は個々の派遣労働者に就業条件等を明確にするためのものであり、就
業条件の一部を変更して(例えば、派遣期間のみを変更して)再度労働者派遣をしようとする
場合は、就業条件等のうち当該変更される事項及び変更内容が明確にされ、他の就業条件等は
- 221-
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
同一であることが明確にされていれば足りるものである。
ホ(5)のハの「当該労働者派遣の期間」とは、実際に派遣される期間であり、労働者派遣契約の
派遣期間が一週間以内とされているものであっても、契約の更新等により、実質的に一週間を
超えることとなる場合には(5)のイのいずれかの方法による明示が必要である。
へ 派遣労働者の請求がなく、かつ、労働者派遣の期間が一週間以内の場合であっても、派遣労
働者の就業条件等の明確化のためには、可能な限り労働者派遣の開始の後、遅滞なく、(5)のイ
のいずれかの方法により就業条件等を明らかにすることが適当であり、その旨周知徹底、指導
を図ること。特に、個々の派遣期間が一週間以内の就業であってもそれが継続的に続く場合は
必ず(5)のイのいずれかの方法により就業条件等の明示を行わせるよう指導することとする。
ト 労働基準法第15条では、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労
働条件を明示しなければならないこととされているが、労働契約の締結の際と労働者派遣を行
おうとする際が一致するような場合(いわゆる、登録型の場合に発生しやすい。)において、
就業条件等の明示を書面、ファクシミリ又は電子メール等により行うときは、明示する事項が
一致する範囲内で両方の明示を兼ねて行って差し支えないものである。
チ 派遣労働者の就業条件等の明確化を図るため、許可の機会等をとらえて、労働者派遣を行う
際にモデル就業条件明示書の様式(第16 様式集参照)により当該派遣労働者に係る就業条件
の内容を明示するよう(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の6(第7の27)
参照)、様式の利用を勧奨すること。
14 労働者派遣に関する料金の額の明示
(1)概要
派遣元事業主は、イ及びロに掲げる場合には、当該イ及びロに定める労働者に対し、当該労働者
に係る労働者派遣に関する料金の額を明示しなければならない(法第34条の2)。
イ 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合 当該労働者
口 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合 当該労働
者派遣に係る派遣労働者
(2)意義
派遣労働者による派遣元事業主の選択に資するよう、派遣元事業主に対し、派遣労働者の雇入れ
時(労働契約を締結する場合)、派遣開始時(実際に派遣する場合)及び労働者派遣に関する料金
の額の変更時に、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額の明示義務を課すものである。
(3)明示すべき労働者派遣に関する料金の額
イ 明示すべき労働者派遣に関する料金の額は、次のいずれかとする(則第26条の3第3項)。
(力 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
② 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の平均額
具体的には、事業所ごとの情報提供を行う場合に用いる前事業年度における派遣労働者一
一 222 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
人一日当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額をいう(第5の4の(2)参照)。なお
、料金の額の単位についてはロを参照のこと。
また、事業年度期間中に派遣料金の平均額が大きく変わる見込みがある場合には、再度
明示することが望ましい。
・ なお、法第23条第5項の規定による情報の提供を行うに当たり、当該事業所が労働者派遣
事業を行う他の事業所と一体的な経営を行っている場合において、その範囲内で労働者派遣
に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派
遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(いわゆるマージン率)を算出している場合
には、当該マージン率の算定に用いた労働者派遣に関する料金の額の平均額を明示すること
として差し支えない(第5の4参照)。
ロ 明示すべき労働者派遣に関する料金の額について、時間額・日額・月額・年額等は問わないが
、その料金額の単位(時間額・日額・月額・年額等)がわかるように明示する必要がある。
(4) 明示の方法
イ 労働者派遣に関する料金の明示は、書面の交付、ファクシミリを利用してする送信、又は電子
メール等の送信の方法により行わなければならない(則第26条の3第1項)。
ロ 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における当該労働者に係る労働者派遣に関する
料金が、労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合に明示した額(法第34条の2第1号
)と同一である場合には、再度の明示は要しない(則第26条の3第2項)
15 派遣先への通知
(1)概要
派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名、当該労
働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別、当該労働者派遣に係る派遣
労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別、当該労働者派遣に係る
派遣労働者が60歳以上の者であるかの別、当該派遣労働者の労働・社会保険への加入状況等を派
遣先に通知しなければならない(法第35条第1項)。
また、通知した後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者について協定対象派遣労働者であるか
否かの別、無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別、60歳以上の者である
かの別又は労働・社会保険への加入状況等について変更があったときは、遅滞なく、その旨を当
該派遣先に通知しなければならない(法第35条第2項)。
(2)通知の趣旨
イ 派遣労働者を派遣先にいっ、どのように派遣するかは派遣元事業主が決定し、派遣先は、当
該派遣元事業主が定めた派遣労働者を当該派遣労働者に係る派遣就業の条件に従って就業させ
ることとなる。
しかしながら、派遣元事業主と派遣先との間で締結された労働者派遣契約においては、当該
- 223 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
労働者派遣に係る全体としての就業条件と派遣労働者の人数は定められるものの、実際の派遣
就業に当たって、どのような派遣労働者が労働者派遣され、かつ、どのような就業条件で当該
派遣労働者を就業させることができるのかは定められていない。
このため、労働者派遣契約の適正な履行を確保する観点から、派遣元事業主から派遣先に対
して、労働者派遣する派遣労働者の氏名のほか、当該派遣労働者の派遣就業に係る就業条件と
当該労働者派遣契約に定めた就業条件の関係を明確にする等派遣先における適正な派遣労働者
の雇用管理を確保するために必要な情報を通知させるものである。
また、協定対象派遣労働者であるか否かについては、法第26条第7項及び第10項による情報
提供の内容、派遣料金に係る配慮の内容に関わる情報であり、派遣先の義務の履行に当たって
重要な情報であることから、当該情報を派遣元事業主から派遣先に対して通知させるものであ
る。
ロ さらに、法第40条の2第1項第1号の規定により、無期雇用派遣労働者は期間制限の対象外
となるとともに、法第40条の5第2項の規定により、派遣先は、直接雇用の依頼があった特定
有期雇用派遣労働者に対しては当該派遣先における労働者等の募集情報を提供しなければなら
ないが、無期雇用派遣労働者は対象にならない。
そのため、派遣先が、無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者の別を事前に把握できるよ
う、当該情報を派遣元事業主から派遣先に対して通知させるとともに、通知後に当該事項に変
更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知させるものである。
ハ また、労働者派遣に係る期間制限の遵守及び労働・社会保険の適正な加入を担保するため、
派遣労働者が期間制限の例外の対象者になるか否かに関係する事項や労働・社会保険の加入状
況、またその変更について、その旨を派遣先に通知させるものである。
(3)通知すべき事項
派遣先に通知しなければならない事項は、次に掲げるものである(法第35条、則第27条の2、
則第28条)。
(力 派遣労働者の氏名及び性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨並びに当該
派遣労働者の氏名及び性別、派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年
齢並びに氏名及び性別)
労働者派遣をする際に、性別等を派遣先に通知する趣旨は、派遣先における労働関係法令の
遵守を担保することにあることに留意すること。
② 協定対象派遣労働者であるか否かの別
通知をした後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければ
ならない(法第35条第2項)。
③ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者であるかの別
通知をした後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければ
ならない(法第35条第2項)。
- 224 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
④ 派遣労働者が法第40条の2第1項第2号による60歳以上の者であるか否かの別
通知をした後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければ
ならない(法第35条第2項)。
⑤ 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
(「無」の場合は、当該書類が提出されていない具体的な理由を付して派遣先及び派遣労働者
へ通知しなければならない(則第27条の2第2項))。
具体的な理由としては、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の適用基準を満たしていない場
合にあっては、単に「適用基準を満たしていないため」、「被保険者に該当しないため」等と記
載するのでは足りず、「1週間の所定労働時間が15時間であるため」等、適用基準を満たしてい
ないことが具体的にわかるものであることが必要である。
また、被保険者資格の取得届の手続中である場合にあっては、単に「手続中であるため」等と
記載するのでは足らず、「現在、必要書類の準備中であり、今月の〇日には届出予定」等と、手
続の具体的な状況を記載することが必要である。
なお、当該通知により、派遣先は当該労働者派遣に係る派遣労働者が派遣元において労働・社
会保険に加入するか否かについての明確な認識を持った上で、当該労働者派遣の受入れを行う効
果が期待できるものであることに留意すること。
さらに、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況について変更があった場合にも通知
を行わなければならないので留意する。(法第35条第2項)
⑥ 当該派遣労働者の派遣就業の就業条件の内容が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約の就業
条件(第6の2の(1)のイの(ハ)の⑤、⑥、⑪、⑫、⑬に係る就業条件に限られる。)の内容と
異なる場合における当該派遣労働者の就業条件の内容
(参 考) 派遣元事業主から派遣先への通知の例
(力 労働者派遣契約に基づき次の者を派遣します。
(例A)
〇〇〇〇〇 女 45歳以上60歳未満
××××× 男 60歳未満
(例B)
〇〇〇〇 女【a18歳未満(歳)⑥45歳以上60歳未満 C60歳以上 d aからCまでの
いずれにも該当せず】
×××× 男【a18歳未満(歳)b45歳以上60歳未満 C60歳以上 ④aからCまでの
いずれにも該当せず】
② 社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無は次のとおりです。
健康保険 厚生年金保険 雇用保険
〇〇〇〇〇 有 有 有
- 225 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
××××× 無(加入手続中)無(加入手続中)無(加入手続中)
(理由:現在、必要書類の準備中であり、今月の〇日には届出予定)
③ 派遣労働者の雇用期間は次のとおりです。
〇〇〇〇〇 無期雇用
××××× 有期雇用(6箇月契約)
④ 派遣労働者の協定対象派遣労働者であるか否かの別(待遇決定方式)は次のとおりです。
〇〇〇〇〇 協定対象派遣労働者(労使協定方式)
××××× 協定対象派遣労働者ではない(派遣先均等・均衡方式)
(4)通知の方法
通知は次の方法により行わなければならない(則第27条第1項)。
イ 労働者派遣契約に定める派遣労働者の就業条件の内容の組合せが一つである場合は、当該組
合せに係る(3)の事項を通知すること。
ロ 労働者派遣契約に定める派遣労働者の就業条件の内容の組合せが複数である場合には、当該
組合せごとに当該組合せに係る(3)の事項を通知すること。
(5)通知の手続
通知は、次の手続により行わなければならない(則第27条第2項及び第3項)。
イ 通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ、(3)の通知すべき事項に係る書面の交付若しくはフ
ァクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信をすることにより行うこと。
ロ ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるため、書面の交付若しくはファクシミ
リを利用してする送信又は電子メール等の送信ができない場合は、通知すべき事項を、あらか
じめ、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信以外の方
法で通知すればよいこととする。
ハ この場合、労働者派遣契約に係る就業条件の組合せが複数ある場合であって当該労働者派遣
の期間が2週間を超えるときは、当該労働者派遣の開始後、遅滞なく、当該事項に係る書面の
交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信をしなければならない
(3)の④の事項については、派遣労働者に係る次の各書類が関係行政機関に提出されているこ
と(労働者派遣に当たって派遣労働者を新たに雇用する場合には、当該労働者派遣の開始の後
速やかに提出すること)の有無とする(則第27条の2第1項)。ただし、「無」の場合は、そ
の理由を具体的に記載することとする(則第27条の2第2項)。
(イ)健康保険法施行規則第24条第1項に規定する健康保険被保険者資格取得届
(ロ)厚生年金保険法施行規則第15条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届
(ハ)雇用保険法施行規則第6条に規定する雇用保険被保険者資格取得届
「無」の場合の具体的理由としては、(3)の④のとおり、「一週間の所定労働時間が15時間
- 226 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
であるため」「現在、必要書類の準備中であり、今月の〇日には届出予定」等、適用基準を満た
していない具体的理由又は手続の具体的状況が明らかであることが必要である。また、具体的理
由が適正でない場合には、派遣元事業主に対し、労働・社会保険に加入するよう所要の指導を行
うこと。
また、派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対
して通知した当該派遣労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、当該派遣労働
者に対しても通知することが必要である(法第34条第1項第2号、則第26条の2)。
また、派遣先は第8の13の考え方に従い対処する必要があり、適正でないと考えられる理由の
通知を受けた場合には、派遣元事業主に対して、労働・社会保険に加入させてから派遣するよう
求めることとされていることに留意すること。
なお、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させた上で労働者を派遣するとき又は労働
者派遣の開始の後、加入手続中の派遣労働者について被保険者資格取得届が提出されたときは、
派遣元事業主は被保険者証の写し等の加入させていることがわかる資料を派遣先に提示又は送付
すること。
さらに、この被保険者証等の写し等を提示する場合は、原則として労働者本人の同意を得るこ
ととするが、この同意が得られなかった場合には、生年月日、年齢等を黒塗りするとともに、派
遣先に確認後には派遣元に返送することを依頼する等個人情報の保護に配慮すること。
ホ 派遣元事業主は、第35条第1項第2号から第5号までの事項(協定対象派遣労働者であるか否
かの別、期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別、60歳以上の者であるか否かの別、
各種保険の加入状況に係る事項)の通知をした後に当該事項に変更があり、同条第2項の通知を
するときには、遅滞なくその旨を書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子
メール等の送信により派遣先に通知する必要がある(則第27条第5項)。
(6)通知に際しての留意点
イ 労働者派遣契約において就業条件の内容の組合せごとに派遣労働者の人数を定めなければな
らないため、同一の組合せの範囲内で派遣労働者が交代する場合を除き、派遣労働者の就業条
件は、当該派遣労働者の属する組合せと同一となる。このため、同一の組合せの範囲内で派遣
労働者が交代しない場合は、それぞれの組合せごとに(3)の(力から⑤までを通知し、派遣労働者
が交代する場合は、それぞれの組合せごとの(3)の(力から⑤並びに当該交代することとなる派遣
労働者の氏名及び当該交代により労働者派遣契約と異なることとなる就業条件の内容を明確に
して通知すれば足りるものであり、全ての派遣労働者ごとにその就業条件を併せて通知する必
要はない。
ロ 当該派遣先で就業することとなる業務の遂行について当該業務を行う労働者に免許、資格等
を有することが法令により義務付けられている場合には、派遣元事業主は当該免許、資格等を
有する者を派遣する必要があるので留意すること。
- 227 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
16 労働者派遣期間の制限の適切な運用
(1)概要
派遣元事業主は、派遣先の事業所等ごとの業務について、派遣可能期間を超えて継続して労働者
派遣を行ってはならない。(法第35条の2、第8の5参照)。また、派遣先の事業所等における組
織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40
条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行ってはならない(法第35条の3)。
(2)意義
派遣労働については、その雇用の安定やキャリア形成が図られにくい面があることから、派遣労
働を臨時的・一時的な働き方として位置づけることを原則とするともに、派遣先の常用労働者(い
わゆる「正社員」)との代替が生じないよう、派遣労働の利用を臨時的・一時的なものに限ること
を原則とし、その旨は厚生労働大臣が行う運用上の配慮について規定した法第25条にも明記して
いる。
具体的には、常用代替防止の観点から派遣先の事業所等ごとの業務に係る派遣について原則3年
までとする事業所単位の期間制限(以下「事業所単位の期間制限」という)が設けられ、また、派
遣労働への固定化防止の観点からは、派遣先の事業所その他就業の場所における組織単位ごとの業
務についての同一の派遣労働者の派遣を3年までとする個人単位の期間制限(以下「個人単位の期
間制限」という)が設けられている。なお、この常用代替防止は、派遣労働者が現に派遣先で就労
している常用労働者を代替することを防止するだけでなく、派遣先の常用労働者の雇用の機会が不
当に狭められることを防止することも含むことに留意すること。
派遣元事業主は、この趣旨を踏まえ、事業所単位の期間制限と個人単位の期間制限が守られるよ
うにする必要がある。
(3)派遣期間の制限の適切な運用のための留意点
イ 派遣先は、事業所等において、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者
派遣の役務の提供を受けることはできず、また、事業所等における組織単位ごとの業務につい
て、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはな
らないため、派遣元事業主がこれらの期間制限に違反する労働者派遣を行うことを禁止してい
るものである。
ロ なお、新たな労働者派遣を行うに際し、当該派遣先の事業所等においてすでに労働者派遣の
役務の提供が行われていたか否かについて、当該派遣元事業主は把握することができず、事業
所単位の派遣可能期間を超えて労働者派遣の提供を行ってしまうおそれがある。したがって、
第8の5の(3)のイの①から⑥までに該当する以外の場合について派遣元事業主から新たな労働
者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第6の労働者派遣契約の
締結に当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始さ
れる日以後当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所において期間制限に抵触することとなる
- 228 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
最初の日を通知しなければならず、また、派遣元事業主は、当該通知がないときは、当該者と
の間で、労働者派遣契約を締結してはならないこととされていることに留意すること(第6の
2の(2)参照)。
ハ 「継続して労働者派遣の役務の提供を行う」の「継続して」とは、労働者派遣の役務の提供
を行っていない期間があったとしても、それが3箇月以内であれば継続しているとみなされる
ので注意すること。
なお、3箇月を超える空白期間を設定した後に再度同一の組織単位で就業させることは、当
該派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくないものであるので留意すること。
ニ 派遣元事業主は、ロにより通知された派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する日以降継続
して労働者派遣を行ってはならない。また、派遣先の事業所単位の派遣可能期間が延長された
場合であっても、派遣労働者個人単位の期間制限を超えて同一の組織単位に同一の派遣労働者
を派遣してはならない。
ホ なお、期間制限の対象となる派遣労働者については、労働契約法の各規定の趣旨にも留意す
ること。
① 労働契約法第18条の趣旨
有期労働契約の現状を踏まえ、法第18条において、有期労働契約が5年を超えて更新された
場合は、有期契約労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」と
いう。)に転換させる仕組み(以下「無期転換ルール」という。)を設けることにより、有期
労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることとしたものであること。
② 労働契約法第19条の趣旨
有期労働契約は契約期間の満了によって終了するものであるが、契約が反復更新された後に
雇止めされることによる紛争がみられるところであり、有期労働契約の更新等に関するルール
をあらかじめ明らかにすることにより、雇止めに際して発生する紛争を防止し、その解決を図
る必要がある。
このため、法第19条において、最高裁判所判決で確立している雇止めに関する判例法理(い
わゆる雇止め法理)を規定し、一定の場合に雇止めを認めず、有期労働契約が締結又は更新さ
れたものとみなすこととしたものであること。
17 日雇労働者についての労働者派遣の禁止
(1)概要
派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要
とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働
者をいう。以下同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれが
ないと認められる業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認
められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合等を除き、その雇用する
- 229 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない(法第35条の4第1項)。
(2)意義
日雇派遣(日雇労働者についての労働者派遣をいう。以下同じ。)については、必要な雇用管理
がなされず、労働者保護が果たされない等といった課題が指摘されている。そのため、適正な雇用
管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会
の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる
場合等を除き、日雇派遣を原則禁止するものである。
(3)禁止の範囲
禁止される日雇派遣の範囲は、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣である。
そのため、労働契約の期間が31日以上であれば、労働者派遣契約の期間が30日以内であったとして
も、日雇派遣の禁止に違反するものではない。
ただし、例えば、労働者派遣の期間が1日しかないにもかかわらず31日以上の労働契約を締結す
る、労働契約の初日と最終日しか労働者派遣の予定がないにもかかわらず当該期間を通じて労働契
約を締結するなど、社会通念上明らかに適当とはいえない労働契約については、日雇派遣の禁止の
適用を免れることを目的とした行為であると解される。
(4)禁止の例外
日雇派遣の禁止の例外として認められるものは、次のとおりである。
イ 労働者派遣の対象となる日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められ
る業務
令第4条第1項各号に掲げる業務(17.5業務)が該当する。
ロ 雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であ
ると認められる場合等
労働者派遣の対象となる日雇労働者が次の(力から④までのいずれかに該当する場合
(令第4条第2項、則第28条の2、則第28条の3)。
(力 労働者派遣の対象となる日雇労働者が60歳以上である場合
② 労働者派遣の対象となる日雇労働者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条
又は第134条第1項の学校の学生又は生徒である場合
雇用保険の適用を受けない昼間学生の範囲と同一であるが、次のいずれかに該当する場合に
は、日雇派遣の例外となる学生又は生徒に含まれない。
・ 定時制の課程に在学する者(大学の夜間学部、高等学校の夜間等)
・ 通信制の課程に在学する者
・ 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に雇用保険法第5条第1項に規定する適用事
業に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの
・ 休学中の者
- 230 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
・ 事業主の命により(雇用関係を存続したまま)、大学院等に在学する者(社会人大学生等
)
・ その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業に
おいて同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの
③ 労働者派遣の対象となる日雇労働者の生業収入の額が500万円以上である場合(副業として
日雇派遣に従事させる場合)
「生業収入」とは、主たる業務の収入のことをいい、例えば、労働者派遣の対象となる日
雇労働者が複数の業務を兼務している場合には、その収入額が最も高い業務が主たる業務と
なること。また、使用者から労働の対価として支払われるものに限られるものではなく、例
えば、不動産の運用収入やトレーディング収入(株式売買、投資信託、外国為替及び先物取
引等による収入)等も「生業収入」に含まれること。
④ 労働者派遣の対象となる日雇労働者が主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしてい
ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族(以下「配偶者等」と
いう。)の収入により生計を維持している場合であって、世帯収入が500万円以上である場合
(主たる生計者以外の者を日雇派遣に従事させる場合)
「主として生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持している」とは、世帯全体の
収入に占める労働者派遣の対象となる日雇労働者の収入の割合が50%未満であることをいう
こと。
「生計を一にする」か否かの判断は、実態として、労働者派遣の対象となる日雇労働者が
配偶者等の収入により生計を維持しているかどうかにより確認するものとし、必ずしも配偶
者等と同居している必要はないこと。したがって、例えば、両親の収入により生計を維持し
ている子供が単身で生活をしている場合であっても、世帯収入が500万円以上であれば対象
となること。
「世帯収入」には、労働者派遣の対象となる日雇労働者の収入も含まれること。また、「
収入」とは、使用者から労働の対価として支払われるものに限られるものではなく、例えば
、不動産の運用収入やトレーディング収入(株式売買、投資信託、外国為替及び先物取引等
による収入)等も含まれること。
(5)要件の確認方法
イ (4)のロの(力、②又は④に該当するか否かの確認は、年齢が確認できる公的書類(住民票、健
康保険証、運転免許証等)、学生証、配偶者等と生計を一にしているかどうかを確認できる公的
書類(住民票、健康保険証)等によることを基本とする。ただし、合理的な理由によりこれらの
書類等が用意できない場合、これらの書類等のみでは判断できない場合(昼間学生に該当するか
否か等)等には、やむを得ない措置として日雇労働者本人からの申告(誓約書の提出)によるこ
ととしても差し支えない。
ロ (4)のロの③又は④の収入要件を満たしているか否かの確認は、労働者派遣の対象となる日雇
- 231-
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
労働者本人やその配偶者等の所得証明書、源泉徴収票の写し等によることを基本とする。ただし
、合理的な理由によりこれらの書類等が用意できない場合等には、やむを得ない措置として労働
者派遣の対象となる日雇労働者本人からの申告(誓約書の提出)によることとしても差し支えない。
ハ(4)のロの③又は④の収入要件は前年の収入により確認することとするが、前年の収入が500万
円以上である場合であっても、当年の収入が500万円を下回ることが明らかとなった場合には、
日雇派遣の禁止の例外として認められない。
ニ 労働者派遣の対象となる日雇労働者の従事する業務が(4)のイに該当するかどうか、又は労働
者派遣の対象となる日雇労働者が(4)のロに該当するかどうかの確認は、労働契約の締結ごとに
行う必要がある。また、(4)のロに該当するかどうかについて、労働契約の締結時には書類等に
よる確認ができなかったが、その後、書類等による確認ができるようになった場合には、事後的
であっても書類等により確認することを基本とする。
ホ 派遣元事業主は、要件の確認に用いた書類等を保存しておく必要はないが、例えば、派遣元管
理台帳に記録を残しておくなど、どのような種類の書類等により要件の確認を行ったかが分かる
ようにしておく必要がある。ただし、要件の確認を誓約書の提出により行った場合には、事後の
トラブル等を未然に防止するためにも、当該誓約書を派遣元管理台帳と合わせて管理しておくこ
とが望ましい。その際、書類等による確認ではなく誓約書によることとなった理由についても分
かるようにしておくことが望ましい。
- 232 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
令第4条の業務
(日雇派遣の原則禁止の例外として認められる業務(第7の14の(4)のイ参照))
(1)情報処理システム開発関係(令第4条第1項第1号)
電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続
し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であっ
て、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。(17)及び(18)において同
じ。)の設計、作成若しくは保守の業務
イ 情報処理システムの開発に係る次の業務をいう。
① 情報処理システム開発の可否を決定するための、又は既存のシステムのメンテナンスのため
の調査、分析、システム化計画書の作成
② 情報処理システムの設計(システム基本設計、システム詳細設計)
③ プログラムの設計、作成又は保守
④(力から③までに付随して行われるプログラムテスト又はシステムテスト
⑤ 情報処理システム又はプログラムの使用マニュアルの作成の業務
⑥ 本稼働と同じ、又はそれに近い環境で、ユーザーの用いる条件下において運用できるか否か
を検証、評価する運用テスト
ロ この場合において、電子計算機とは「演算、判別、照合などのデータ処理を高速で行う電子機
器でプログラムの実行に最低限必要な機能を有しているもの」であり、データ入力機を含むもの
である((3)、(10)及び(17)において同じ。)。
(2)機械設計関係(令第4条第1項第2号)
機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この(2)及び(18)において「機械等」とい
う。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務
イ 建築又は土木に係る設計・製図の分野以外の次のような機械等の設計又は製図(現図製作を含
む。)の業務をいう。
① 電気、電子機器、加工機械、輸送用機械(車両、船舶)、クレーン、ボイラー、労働安全衛
生法施行令上の急停止措置、安全装置、タンク、タワー、ベッセル(槽)、玩具、家具等の機
械、装置、器具又はこれらの部品(IC、LSI、電線、プリント基板等を含む。)
② 原子力発電配管プラント、化学プラント等各種プラント
③ ①、②に係る配管、配線
ロ 「設計」とは、機械等の製作に当たり、その目的に即して費用、材料及び構造上の諸点につい
ての計画を立て、図面その他の方式で明示することをいい、必ずしも図面を用いるものに限ら
ず、数表等を用いるものあるいはコンピュータを用いるもの(いわゆるCAD)も含む。
- 233 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
また、自らの設計に基づき製作された機械等の機能、構造等が製作の目的に適合しない場合に
その原因を検討し必要な設計の変更を行う等の作業を的確に遂行するために、当該機械等の①仕
様、構造、能力等の検査、②据え着け、及び③他の装置、部品等との組立、に立合う業務は設計
の業務に含まれるものである。
ハ 「製図」とは、設計に基づき、製図機器(コンピュータを含む。)を使って機械等を図面を用
いて紙面等に書き表すことをいう。
ニ 建築設計・製図とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定される「建築
物」(建築設備そのものを除く。)に係る設計・製図である。このため、建築士法の一級、二級
建築士はこの業務に含まれない。また、原子力プラント等における建屋の設計は含まれない。
ホ 土木設計・製図とは、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一「土木工事業」に係るもの
で、道路、河川、鉄道、橋りょう、港湾、空港、都市計画等の設計、製図をいう。
(3)機器操作関係(令第4条第1項第3号)
電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器((17)において「事務用機器」とい
う。)の操作の業務
イ (1)のロに掲げる電子計算機、タイプライターほか、これらに準ずるワードプロセッサー、テレ
タイプ等の事務用機器についての操作の業務及びその過程において一体的に行われる準備及び整
理の業務をいう。
ロ 当該機器は、迅速かつ的確な操作に習熟を必要とするものに限られるものであり、ファクシミ
リ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取器等迅速かつ的確な操作に習熟を必要とし
ない機器は含まれない。
ハ 機器の保守管理、中継車の運転等は、当該機器の操作でもなく機器の操作の「過程において一
体的に行われる準備及び整理」とも解することができないので留意すること。
ニ 電子計算機の操作を行う者が行う処理結果が印字された連続紙の切離し、仕分けの業務は、機
器の操作の「過程において一体的に行われる準備及び整理」の業務に含まれる。ただし、当該連
続紙を梱包し又は発送する業務はこれに含まれない。
(4)通訳、翻訳、速記関係(令第4条第1項第4号)
通訳、翻訳又は速記の業務
次のいずれかの業務をいう。
イ 通訳 一の言語を他の言語に訳して相手方に伝達する業務又は通訳案内士法(昭和24年法律第
210号)第2条の通訳案内業務
口 翻訳 一の言語を他の言語に訳す業務
ハ ロの翻訳業務の一環として行われる次の業務で主として、外国語の文書について行われるも
し/一
一 234 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
(力 高度な技術により製作された機器の使用、操作、保守のためのマニュアル等の文書を使用目
的に応じて的確かつ理解しやすく作成する業務(テクニカルライター業務)
② 翻訳文書を使用目的に応じて編集、修正する業務(ェディター業務)
③ 翻訳文書を使用目的に応じて翻訳言語の発想に従って書き直す業務(リライター業務)
④ 翻訳文書の文法、表記上等の誤りを訂正する業務(チェッカー業務)
速記 人の話を速記符号で書き取り、一般の人々に読めるよう書き直す業務
(5)秘書関係(令第4条第1項第5号)
法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にあ
る者の秘書の業務
イ 取締役又はこれに準ずる者の秘書として文書の作成、受発信管理、資料・情報の整理及び管
理、関係部門との連絡調整、スケジュール表の作成、来客の応対等を行う業務をいう。
ロ 単に来客に対するお茶の接待、会議室の準備、文書の受発信等のみを行う庶務的な補助業務は
含まれない。
(6)ファイリング関係(令第4条第1項第6号)
文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に
従ってする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この(6)において同じ。)に係
る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)
の業務
イ 文書、図書、新聞、雑誌、帳簿、伝票、カード、ディスク、カタログ、地図、図面、フイル
ム、磁気テープ、写真、カルテ等についてファイリングの分類の作成又はファイリングを行う業
務をいう。
この場合において、「ファイリング」とは、事務の能率化を図るために、文書等の分類基準を
作成した上で当該分類基準に従って文書等の整理保管を行う、文書等の整理、保管の組織化、能
率化の意であり、例えば、全社的に統一された文書整理規定を作成し、キャビネット等の整理用
の器具を配置し、この文書整理規定に基づいて文書等の整理、保管を行うことをいう。
また、「高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。」とは、文書等の整理
のために当該文書等の内容又は整理の方法等について相当程度の知識、技術又は経験を必要とす
るものに限られ、単に機械的な仕分けを行うものではないことをいう。
ロ 個人の机の周囲の片付けや文書等の番号順の並べ換えの業務はもとより、郵便物を発信元ある
いは受信先別に仕分けする業務や売上、経理伝票等を取引先別に仕分けする業務等文書等の内容
や整理の方法等について専門的な知識等を用いることのない業務は含まれない。
- 235 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
(7)調査関係(令第4条第1項第7号)
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当
該調査の結果の整理若しくは分析の業務
市場調査等の調査を企画若しくは実施し(電話又は面接による聴き取り調査を含む。)、又はそ
の結果を集計若しくは分析し、最終的に統計表の作成を行う業務をいう(特定個人を対象として行
われるものは含まれない。)。
(8)財務関係(令第4条第1項第8号)
貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務
イ 次のような財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務をいう。
① 仕訳、仕入帳・売上帳・勘定科目別台帳等の会計帳簿の作成
② 保険証券の作成
③ 社会保険料・税金の計算及び納付手続
④ 医療保険の事務のうち財務の処理の業務
⑤ 原価計算
⑥ 試算表、棚卸表、貸借対照表、損益計算書等の決算書類の作成
⑦ 資産管理、予算編成のための資料の作成
⑧ 株式事務
口 当該財務の処理、特に(力から④まで及び⑧については、専門的な業務、すなわち、その迅速か
つ的確な実施に習熟を必要とする業務に限られるものであり、単なる現金、手形等の授受、計算
や書き写しのみを行うようなその業務の処理について特に習熟していなくても、平均的な処理を
し得るような業務は含まれないものである。
ハ なお、店頭における商品(有価証券を含む。)売買に伴う現金又はこれに準ずるものの授受の
行為及びセールスマンの行う商品の勧誘の行為は財務の処理には当たらず、これらの行為を伴う
業務は含まれない。
また、銀行の貸金庫、セーフティケースの管理や社会保険の得喪手続も財務の処理とは解すこ
とができないので留意すること。
(9)貿易関係(令第4条第1項第9号)
外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引
換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第2条第1
項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法(昭和42年法律第122号)第2条第1号に規
定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務
イ 次の書類の作成及びそのために必要な資料の収集、電話照会等の業務をいう。
(力 貿易、海外調達等対外取引に際しての商品又はサービスの受発注契約書又はインボイス、パ
ー 236 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
ッキング・リスト、船積指図書等船積・通関業務に必要な書類
② 国内取引に際しての商品又はサービスの受発注契約書又は船積等輸送に必要な書類
ロ なお、取引とは関係のない官庁等への申請、届出をするための書類の作成は含まれない。ま
た、商品(有価証券を含む。)売買に伴う現金又はこれに準ずるものの授受の行為及びセールス
マンの行う商品の勧誘の行為は、文書の作成には該当せず、これらの行為を伴う業務は含まれな
い。
ハ 「港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの」とは、同法上の一般
港湾運送事業を行う者が行うイの文書の作成のことであり、一般港湾運送事業を行う者に労働者
を派遣し、当該文書を作成する業務は、令第4条第1項第9号の業務には含まれないものである
ので留意すること。
「通関業法第2条第1号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作
成」とは、関税法等の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関業法第2条第1
号イの(1)に規定する通関手続又は同号イの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服
申立書等の通関業法第2条第1号ロに規定する通関書類の作成をいい、通関業者に通関業務の従
事者として労働者を派遣し、通関書類を作成する業務は、令第4条第1項第9号の業務には含ま
れないものであるので留意すること。
(10)デモンストレーション関係(令第4条第1項第10号)
電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技
術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務
イ 電子計算機、各種産業用機械(ワードプロセッサー、タイプライター等の事務用機器を含
む。)又は自動車について紹介及び説明を行う業務(実演を含む。)をいう。これらは、通常は
商品の販売促進のためのキャンペーン等におけるいわゆるデモンストレーション業務に対応す
る。
ロ 当該機械は、用途に応じた的確な操作をするためには、高度の専門的知識、技術又は経験を必
要とするものであり、ファクシミリ等の機器は、当然これには含まれず、また、民生用商品につ
いて紹介及び説明を行う業務は、パーソナルコンピューター等の例外を除き通常これには含まれ
ない((2)参照)。
また、家具、衣料品、食料品等機械に該当しないものは当然含まれるものではない。
(11)添乗関係(令第4条第1項第11号)
旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して
行うものに限る。)若しくは同法第4条第1項第4号に規定する企画旅行(参加する旅行者の募集
をすることにより実施するものに限る。)以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当
する業務(以下(11)において「旅程管理業務等」という。)、旅程管理業務等に付随して行う旅行
- 237 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除
く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待
合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務
イ 次のいずれかの業務をいう。
① 添乗員の行う旅行業法第12条の11第1項に規定される旅程管理業務若しくは同法第4条第1
項第4号に規定する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限
る。)以外の旅行における旅程管理業務に相当する業務又はそれらに付随する旅行者のパスポ
ートの紛失等の事故処理、旅行者の苦情処理等の業務
この場合において、「旅程管理業務」とは、旅行者に対する運送又は宿泊のサービスの確実
な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配
その他の企画旅行を円滑に実施するための次の措置を講ずるために必要な業務を意味する(旅
行業法施行規則第32条)。
i 旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始
前に必要な予約その他の措置
辻 旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実
施その他の措置(本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じな
い旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示し
た書面を交付した場合を除く。)
嵐 旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における
代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置
(本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、
かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付し
た場合を除く。)
k 旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区
間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関
する指示
② 空港、港湾、鉄道駅、バスターミナルに設けられた旅客の乗降又は待合いの用に供する建築
物内(ロビー、待合室等)における送迎並びに送迎に付随する案内及び接遇の業務
空港等の施設内において行う旅行者の集合の確認、乗車券等必要な書類の手渡し、海外渡航
事務手続等必要な手続の実施、旅行日程及び注意事項についての説明、利用する交通機関の確
認及び当該交通機関への案内、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合におけ
る代替サービスの手配等の業務を含む。
ロ なお、バスガイド、スチュワーデス等が業務として行う車両、船舶又は航空機内における案内
の業務、旅行者に同行するのではない海外渡航事務手続、空港、港湾等とそれ以外の施設との間
の送迎はイの業務の一部として行われる場合を除き含まれない。
- 238 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
(12)受付・案内関係(令第4条第1項第12号)
建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務
イ 次のいずれかの業務をいう。
(力 建築物の入り口又は建築物内の事業所の入り口等における受付又は案内
② 博覧会場の入退場口又は博覧会場内に設けられた案内所における受付又は案内
この場合において「博覧会場」とは、国、地方公共団体又はそれらの設立した公益法人等が
主催する博覧会のために設けられた展示等のための建築物、施設又は広場等からなる会場をい
い、具体的には国際博覧会又は地方博覧会の会場をいう。
ロ イの①には、中高層分譲住宅等の建築物の管理業務は含まれない。
(13)研究開発関係(令第4条第1項第13号)
科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若
しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開
発の業務((1)及び(2)に掲げる業務を除く。)
イ 研究又は開発に係る次のような業務をいう。
(力 研究課題の探索及び設定
② 文献、資料、類例、研究動向等関連情報の収集、解析、分析、処理等
③ 開発すべき新製品又は製品の新たな製造方法の考案
④ 実験、計測、解析及び分析、実験等に使用する機器、装置及び対象物の製作又は作成、標本
の 製作等
⑤ 新製品又は製品の新たな製造方法の開発に必要な設計及び試作品の製作等
⑥ 研究課題に関する考察、研究結果のとりまとめ、試作品等の評価、研究報告書の作成
⑦ 前記の業務に関して必要なデータベースの構築及び運用
口 次の業務は含まれない。
(力 専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務でないものを専ら行うもの
② 製品の製造工程に携わる業務を専ら行うもの
ハ 科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品の開発又は科学に関す
る知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発を目的とした
試作品の製作の業務はロの②に該当しない。
(14)事業の実施体制の企画、立案関係(令第4条第1項第14号)
企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は
立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)
イ 企業等における事業の実施体制又は運営方法の整備に関する次の業務をいう。
- 239 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
(力 自企業・ユーザー企業に対するアンケート、ヒアリング等、自企業・他の企業の現場視察及
び事業内容の分析等を通じての実態把握並びに改善が必要と思料される事項に関する問題意識
の提起
② 各種統計データ、他社の事例等資料の収集
③ 統計的手法を用いての調査結果の分析並びに自企業における事業の実施上の問題点の分析及
び摘出
④ 事業の実施体制の改善策の策定
⑤ 実施すべき内容のとりまとめ及び提案
ロ 「労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務」とは、(力賃金、
労働時間、福利厚生、安全衛生等の労働条件管理、②募集、採用、配置、昇進、能力開発等の人
事管理、③人事相談その他の人間管理、④団体交渉、苦情処理等の労使関係管理等のいわゆる人
事労務管理に係わる業務をいい、例えば、就業規則の作成又は変更に関する検討、個別の労働者
に係わる具体的な配置の提案、労働組合及び個々の労働者に対する説明・説得等をいう。
一方、例えば、新規事業等を開始するに当たり、業務量及びそれに必要な人員数についての試
算を行う業務等は「労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務」
には含まれない。
ハ なお、アンケート、ヒアリングの実施又はその結果を集計する業務、統計データ、事例等の資
料収集を専ら行う等の補助的な業務は含まれない。
(15)書籍等の制作・編集関係(令第4条第1項第15号)
書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務
イ 書籍等の制作における編集に係わる次の業務をいう。
① 書籍等の内容、読者層、価格、発売時期、発行部数等の企画及び決定
② 企画に沿った執筆者等の選定並びに執筆者等に対する執筆等の依頼及び交渉
③ 執筆者等(執筆者、写真家、画家、イラストレーター等のうち、編集者と交渉を行い、編集
者から業務委託を受ける者)の補助(資料収集及び取材並びにそれらの補助)
④ 編集者自身が行う取材、資料収集及び執筆
⑤ 原稿等の点検及び原稿等の内容の調整並びに執筆者等との交渉及び調整
⑥ 書籍等の用紙、装丁、割付け等の考案及び決定
⑦ 上記に付随する校正及び校閲
ロ この場合において、「書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品」とは、
文章、写真、図表等により構成され、紙等(CD-ROM、マイクロフィルム等を含む。)に記
録されるものをいう。
ハ なお、校正等を専ら行うような補助的な業務は含まれない。
- 240 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
(16)広告デザイン関係(令第4条第1項第16号)
商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用する
ことを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(2の(6)に掲げる業務を除く。)
イ 商品若しくはその包装のデザイン又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的
とするデザインについての考案、設計、試作品の作成又はデザイン自体の作成の業務、ショール
ーム等における商品の陳列を考案し、設計し又は実施する業務をいう。
ロ 「企業等」には、私企業、公企業の他、企業団体、一般社団法人又は一般財団法人、個人事業
主が含まれる。
ハ この場合において、「広告」の媒体としては、テレビ、新聞、雑誌、パンフレット、カタロ
グ、ポスター、看板等が想定される。
ニ また、この場合において、「設計」とは、あくまでデザインの設計及び作図のことをいい、(2)
における設計とは異なる((2)のロ参照)。
ホ なお、次の業務は含まれない。
(力 2の(6)に該当する業務
② デザイン作成に当たって、印刷又は決定されたデザインのとおりに彩色等を専ら行う業務
③ 決定された方法のとおりに商品の陳列を専ら行う業務
(17)oAインストラクション関係(令第4条第1項第17号)
事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプロ
グラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務
イ (3)のイの事務用機器の操作方法の教授又は指導の業務又は(1)のロに掲げる電子計算機を使用
することにより機能するシステム又はプログラムの使用方法の教授又は指導の業務並びにそれら
に付随して行う指導方針等に係るユーザー企業との打合せ及びこれに基づくテキストの作成の業
務をいう。
ロ この場合において、「事務用機器」は(3)における「事務用機器」と同一であり、ファクシミ
リ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取機等迅速かつ的確な操作に習熟を必要とし
ない機器は含まない((3)参照)。
ハ なお、事務用機器の操作方法等に関するテキスト等の作成を専ら行う業務及びVTR、OHP
その他教授のための教材の操作を専ら行う業務は含まれない。
(18)セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係(令第4条第1項第18号)
顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構
成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要であ
る金融商品(金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)第2条第1項に規定する金融
商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契
- 241-
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同
じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧
誘の業務
イ 次のいずれかの業務をいう。
① 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等によ
り構成される設備若しくはプログラムに係る次の業務
i 顧客の要求の把握並びに顧客に対する説明又は相談及びそれらに必要な説明資料の作成
辻 顧客との交渉又は見積書作成
嵐 売買契約の締結等売買契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契
約の申込み若しくは締結の勧誘
k 上記に付随する納入(運送業務を含む。)及びその管理
② 顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品に係る次の業務
i 金融商品の特性、リスク等に関する説明(情報提供)又は相談及びそれらに必要な説明資
料の作成
辻 顧客との交渉又は見積書作成
嵐 ニーズの的確な把握等を踏まえ選定された金融商品についての売買契約の締結等売買契約
についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧
誘
ロ イの①には、既製品や既製品に既成の付属物を付加するものの営業に係わる業務は含まれない
ことに留意すること。
ハ イの(力において、「機械等若しくは機械等により構成される設備」には、電気・電子機器、加
工機器、輸送用機器、産業用機器(クレーン、ボイラー、タンク、タワー等)、原子力プラン
ト、化学プラント等が該当する。
ニ イの(力において、「プログラム」には、I T関連商品としてのシステム、ソフトウェア、ネッ
トワーク等が該当する。
ホ イの②のiには、①企業調査、産業調査に基づき行う個別証券の分析、評価、②顧客のライフ
プラン等を踏まえたポートフォリオ(運用資産のもっとも有利な分散投資の選択)の作成等も含
む。
ヘ イの②とは、具体的には、次のような資格を有する者(これに相当すると認められる者を含
む。)の行う専門的知識を要する業務をいう。
① デリバティブに係る業務まで行い得る一種外務員資格を有する証券外務員
② 損害保険のほぼ全種目につき必要な知識を持ち、十分に自立して取り扱う能力があると認め
られていた従前の特級又は上級資格を有する損害保険外務員
③ ファイナンシャル・プランニング・サービスに必要な知識の習得を目的とする応用課程試験
合格者である生命保険外務員
- 242 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
④ 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のAFP(Amliated Financial Planner)資格審査
試験に合格し同協会に個人正会員として入会している者(AFP認定者。)
⑤ (社)日本証券アナリスト協会の試験に合格し同協会の会員として登録している証券アナリ
スト
ト なお、次の業務は含まれない。
(重 機械等の設計若しくは製造又はその管理の業務及びプログラムの設計若しくは作成又はその
管理の業務
② 建築設計の業務((2)のこ参照)
③ 機械等又はプログラムの納入及びそれに付随する輸送を専ら行う業務
④ 機械等又はプログラムの保守及びアフターサービスの業務
- 243 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
18 離職した労働者についての労働者派遣の禁止
(1)概要
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提
供を受けたならば法第40条の9第1項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行っ
てはならない(法第35条の5)(第8の10参照)。
(2)意義
労働者派遣事業は、常用雇用の代替防止を前提として制度化されているものであり、ある企業を
離職した労働者を当該企業において派遣労働者として受け入れ、当該企業の業務に従事させること
は、法の趣旨に鑑みても適当ではない。そのため、派遣元事業主に対し、派遣先を離職した後1年
を経過しない労働者(60歳以上の定年退職者を除く。)を派遣労働者として当該派遣先へ労働者派
遣することを禁止するものである。
(3)離職した労働者についての労働者派遣の禁止の留意点
イ 離職した労働者についての労働者派遣の禁止の例外となる「60歳以上の定年退職者」の取扱い
は、第5の2の(2)のロ及びハと同様である。
ロ 「派遣先」とは、事業者単位で捉えられるものであり、例えば、ある会社のA事業所を離職し
た労働者を同じ会社のB事業所へ派遣することは、離職後1年を経過しない場合は認められない
こと。なお、グループ企業への派遣に関しては、同一の事業者には該当しないため、離職した労
働者についての労働者派遣の禁止対象になるものではないこと。
ハ 「労働者」とは、正社員に限定されるものではなく、非正規労働者も含まれる。
19 派遣元責任者の選任
(1)概要
派遣元事業主は、(3)に掲げる事項を行わせるため、派遣先で就業することとなる派遣労働者に
係る派遣元事業主の雇用管理上の責任を一元的に負う「派遣元責任者」を選任し、派遣元事業主
による適正な雇用管理を確保しなければならない(法第36条)。
(2)派遣元責任者の選任の方法等
イ 派遣元責任者となる者の要件
(イ)派遣元責任者は、次のaからhまでのいずれにも該当しない者のうちから選任しなくてはなら
ない(法第36条、則第29条の2)。
a 禁銅以上の刑に処せられ、又は第3の1の(7)「許可要件(許可の欠格事由)」のイの(イ)
のaからCまで及びgから1までの規定に違反し、又はd、e及びfの罪を犯したことにより、罰金
の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5
年を経過しない者
b 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
C 労働者派遣事業若しくは、平成27年9月29日以前に(旧)一般労働者派遣事業の許可を取り
- 244 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
消され、又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起
算して5年を経過しない者
d 労働者派遣事業若しくは、平成27年9月29日以前に(旧)一般労働者派遣事業の許可を取り
消され、又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合において、
当該取消し又は命令の処分を受ける原因となった事項が発生した当時に当該法人の役員であ
った者で、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しないもの
e 労働者派遣事業若しくは、平成27年9月29日以前に(旧)一般労働者派遣事業の許可の取消
し又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る聴聞の通知があった日から当該
処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に労働者派遣事業及び平成27年9
月29日以前に(旧)一般労働者派遣事業又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止の届出をした
者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
f eの期間内に廃止の届出をした者が法人である場合において、聴聞の通知の目前60日以内に
当該法人の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
g 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力
団員でなくなった日から5年を経過しない者
h 未成年者
(ロ)労働者派遣事業の許可において、派遣元責任者は雇用管理能力に係る一定の基準を満たすこ
と及び過去3年以内に厚生労働大臣に開催を申し出た者が実施する派遣元責任者講習を受講し
ていること(則第29条の2)を選任の要件としている(第3の1の(8)参照)。
なお、経過措置期間中の(旧)特定労働者派遣事業については、法令上一定の資格能力は
要求されていないが、同様に派遣元責任者が労働関係法令に関する知識を有し、雇用管理に
関し専門的知識又は相当期間の経験を有する者を選任することが適当で、派遣元責任者講習
を受講していることが望ましいことから、その旨周知徹底を図ること。
ロ 派遣元責任者の選任方法
派遣元責任者は、次の方法により選任しなければならない(則第29条)。
(イ)派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属(※)の派遣元責任者として自己の雇用す
る労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人の場合は、その役員)を派遣
元責任者とすることを妨げない。
;※ 専属とは
この場合において、専属とは当該派遣元責任者に係る業務のみを行うということではな
く、他の事業所の派遣元責任者と兼任しないという意味。
なお、会社法等の規定により、法人の会計参与は同一の法人又はその子会社の取締役、監
査役、執行役又は従業員を兼ねることはできず、監査役は同一の法人又はその子会社の取締
役若しくは従業員又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行
うべき社員)若しくは執行役を兼ねることはできないため、これらの者については派遣元責
- 245 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
任者として選任できないので、留意すること。
(ロ)当該事業所の労働に従事する派遣労働者の数について1人以上100人以下を1単位とし、1
単位につき1人以上ずつ選任しなければならない。
ハ 派遣元責任者講習の受講
派遣元責任者として選任された後においても、労働者派遣事業に関する知識、理解を一定の
水準に保つため、労働者派遣事業において選任された派遣元責任者については、派遣元責任者
として在任中は3年ごとに「派遣元責任者講習」を受講するよう指導を行うこと。なお、経過
期間中の(旧)特定労働者派遣事業において選任された派遣元責任者についても、可能な限り
受講するよう指導を行うこと。
ニ 製造業務専門派遣元責任者の選任
(イ)物の製造の業務に労働者派遣をする事業所等にあっては、物の製造の業務に従事させる派
遣労働者の数について1人以上100人以下を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ、物の製
造の業務に従事させる派遣労働者を専門に担当する者(以下、「製造業務専門派遣元責任
者」という。)を、選任しなければならない(則第29条第3号)。
(ロ)ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、物の製造の業務に労働者派遣をしない
派遣労働者(それ以外の業務へ労働者派遣された派遣労働者)を併せて担当することができ
る。
(ハ)物の製造業務に労働者派遣をする場合には、製造現場での就業の実情を考慮し、派遣労働
者の適正な就業を確保するため、派遣労働者の雇用管理体制の一層の充実を図る必要がある
ことから、物の製造業務へ派遣された派遣労働者を担当する派遣元責任者と、それ以外の業
務へ派遣された派遣労働者を担当する派遣元責任者とを区分して選任するものである。
例えば、以下のようなケースが考えられる。
a 労働者派遣事業を行う事業所における全派遣労働者300人のうち、物の製造の業務へ派遣さ
れている派遣労働者が150人、物の製造の業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者が150
人である場合、製造業務専門派遣元責任者を2人(うち1人は物の製造の業務以外の業務へ
派遣されている派遣労働者を併せて担当することができる。)を選任することが必要であ
る。
b 労働者派遣事業を行う事業所における全派遣労働者50人のうち、物の製造の業務へ派遣さ
れている派遣労働者が20人、物の製造の業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者が30人
である場合、製造業務専門派遣元責任者を1人(この1人については物の製造の業務以外の
業務へ派遣されている派遣労働者を併せて担当することができる。)を選任する必要があ
る。
(3)派遣元責任者の職務
派遣元責任者は、次に掲げる職務を行わなければならない。
イ 派遣労働者であることの明示等(11参照)
- 246 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
口 就業条件等の明示(13参照)
ハ 派遣先への通知(15参照)
ニ 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存(20参照)
ホ 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
具体的には、例えば、法に沿って、労働者派遣事業制度の趣旨、内容、労働者派遣契約の趣
旨、派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置、労働基準法等の適用に関すること、苦情等の申
出方法等につき必要な助言及び指導を行うことである。
・ 特に労働者派遣法に改正があった場合は、改正の内容について説明会等の実施、文書の配布
等により、派遣労働者に周知すること(10、22及び「派遣元が講ずべき措置に関する指針」指
針第2の10(第7の27参照)参照)。説明の際には、例えば、厚生労働省で作成している派遣
労働者向けのパンフレットのほか、それと同等以上の内容が盛り込まれた派遣元事業主で作成
している資料等を配布することや、ファクシミリ又は電子メール等を利用して資料を送付する
こと、厚生労働省や派遣元事業主が作成した資料が掲載されたホームページのリンク先を電子
メール等に明示することなどにより、派遣労働者が確認すべき画面を分かるようにする必要が
あること。
へ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
具体的には、例えば、派遣労働者から直接申出を受けた苦情及び法第40条第1項の規定により
派遣先から通知のあった苦情に、適切な処理を行うことである。
なお、派遣元責任者が苦情処理を適切に処理し得るためには、本人が派遣先に直接出向いて処
理する必要性も高いことから、派遣先の対象地域については派遣元責任者が日帰りで苦情処理を
行い得る地域とされていることが必要であることに留意すること。
ト 派遣先との連絡・調整
具体的には、例えば、派遣先の連絡調整の当事者となる派遣先責任者との間においてへのほか
派遣就業に伴い生じた問題の解決を図っていくことである。
チ 派遣労働者の個人情報の管理に関すること
具体的には、例えば、派遣労働者等の個人情報が目的に応じ正確かつ最新のものに保たれてい
るか、個人情報が紛失、破壊、改ざんされていないか、個人情報を取り扱う事業所内の職員以外
の者が当該個人情幸酎こアクセスしていないかについての管理を行うこと、また、目的に照らして
必要がなくなった個人情報の破棄又は削除を行うこと等である。
リ 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活設計に関する相談の機会の確保に関す
ること
(a)段階的かつ体系的な教育訓練の実施に関すること
派遣元事業主において作成した教育訓練が実施されるよう管理を行うことが必要である。
(b)キャリアコンサルティングの機会の確保に関すること
キャリアコンサルティングに関して、キャリアコンサルティングを希望する派遣労働者との相
- 247 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
談窓口としての連絡及び調整及び派遣先との連絡、調整等に関する業務を行うこと。
ただし、別途キャリアコンサルティング等についての窓口担当者が選任された場合、派遣元責
任者がキャリアコンサルティングの窓口担当である必要はないこと。
ヌ 安全衛生に関すること
派遣労働者の安全衛生に関し、当該派遣元事業所において労働者の安全衛生に関する業務を統
括する者(※)及び派遣先と必要な連絡調整を行うこと。
具体的には、派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、例えば、以下の内容に係る連絡
調整を行うことである。
(イ) 健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実施に関
する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)
(ロ) 安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、
職長等教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)
(ハ) 労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認
(ニ) 事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認
;※ 労働者の安全・衛生に関する業務を統括する者とは
労働者の安全・衛生に関する業務を統括する者とは、労働安全衛生法における安全管理:
;者、衛生管理者等が選任されているときは、その者をいい、統括安全衛生管理者が選任さi
iれているときは、その者をいう。
また、小規模事業場で、これらの者が選任されていないときは、事業主自身をいう。
20 派遣元管理台帳
(1)派遣元管理台帳の作成、記載
イ 概要
派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに
ホに掲げる事項を記載しなければならない(法第37条第1項)。
ロ 意義
派遣元管理台帳は、派遣元事業主が派遣先において派遣就業する派遣労働者の雇用主として
適正な雇用管理を行うためのものである。
ハ 派遣元管理台帳の作成の方法
(イ)派遣元管理台帳は、派遣元事業主の事業所(第3の6参照)ごとに作成しなければならな
い(則第30条第1項)。
(ロ)派遣元事業主は、派遣労働者の雇用管理が円滑に行われるよう派遣労働者を有期雇用労働
者と無期雇用労働者に分けて作成しなければならない。
(ハ)派遣元事業主は、労働基準法第107条第1項の労働者名簿や同法第108条の賃金台帳と派遣
元管理台帳とをあわせて調製することができる。
- 248 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
一 派遣元管理台帳の記載方法
(イ)派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行われなければならない(則第30条
第2項)。これは、ホの事項の確定する都度記載していくという意味であり、事項の内容に
より記載時期は、異なるものである(ホの⑫、⑱及び⑲を除くすべての事項は、労働者派遣
をする際には、あらかじめ記載されている必要があるが、⑫、⑱及び⑲の事項については、
苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度及び教育訓練やキャリアコンサルティン
グを行った都度記載することとなる)。また、派遣先からの派遣就業の実績に関する通知
(第8の12の(4)参照)を受けた場合に当該派遣就業の実績があらかじめ予定していた就業の
時間等と異なるときは、当該通知を受けた都度当該異なった派遣就業の実績内容を記載しな
ければならない(則第30条第3項)。
(ロ)記載については、所要の事項が記載されておれば足りるものである。
なお、書面によらず電磁的記録により派遣元管理台帳の作成を行う場合は、電子計算機に備
えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わ
なければならない。
また、書面によらず電磁的記録により派遣元管理台帳の保存を行う場合は、次のいずれかの
方法によって行った上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直
ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成
できるようにしなければならない。
a 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって
調製するファイルにより保存する方法
b 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読
み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもっ
て調製するファイルにより保存する方法
ホ 派遣元管理台帳の記載事項
派遣元管理台帳には、次の事項を記載しなければならない(法第37条第1項、則第31条)
(第6の2の(1)のイの(ハ)参照)。
(力 派遣労働者の氏名
② 協定対象派遣労働者であるか否かの別
③ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別、有期雇用派遣労働者の場合は労働契約
の期間
④ 法40条の2第1項第2号による60歳以上の者であるか否かの別
⑤ 派遣先の氏名又は名称
・ 個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載する。
⑥ 派遣先の事業所の名称
⑦ 派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
- 249 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
派遣先の事業所において当該派遣労働者が就業する組織単位(第8の6の(3)参照)を記載す
ること。
⑧ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
⑨ 始業及び終業の時刻
⑲ 従事する業務の種類
・ 従事する業務については可能な限り詳細に記載すること。
・ 令第4条第1項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、当該号番号を付すこ
と。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限り
ではない。
・「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、
(i)無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合
(の 契約期間が31日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合
(の(a)又は(b)の労働者派遣に限る場合
のいずれかであり、かつその旨が派遣元管理台帳に明記されている場合である。
⑪ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
・ 派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程
度等をいうこと。
・ チームリーダー、副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職
を、役職を有さない派遣労働者であればその旨を記載することで足りるが、派遣労働者の
適正な雇用管理を行うため、より具体的に記載することが望ましい。
⑫ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
・ 苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受
け、及び苦情の処理に当たった都度、記載すること(「派遣元事業主が講ずべき措置に関す
る指針」第2の3(第7の27参照))。
・ 派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な
取扱いをしてはならない(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の3(第7の
27参照)。
・ なお、苦情の処理に関する事項を派遣労働者ごとに管理している趣旨は、派遣元事業主が
派遣労働者の過去の苦情に応じた的確な対応を行うためのものであることに留意すること。
⑬ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
・ 紹介予定派遣である旨
・ 求人・求職の意思確認等の職業紹介の時期及び内容
・ 採否結果
・ 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹
介を受けた者を雇用しなかった場合に、派遣先から明示された理由
- 250 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
⑭ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
⑮ 労働者派遣契約において、派遣先が法第37条第1項第6号に掲げる派遣就業をする日以外の
日に派遣就業をさせることができ、又は同項第7号に掲げる始業の時刻から終業の時刻までの
時間を延長することができる旨の定めをした場合には、当該派遣就業させることができる日ま
たは延長することのできる時間数
⑱ 期間制限のない労働者派遣に関する事項
・ 有期プロジェクトの業務について労働者派遣を行うときは、法第40条の2第1項第3号イ
に該当する業務である旨
日数限定業務について労働者派遣を行うときは、①法第40条の2第1項第3号ロに該当す
る旨、②当該派遣先において、同号ロに該当する業務が1箇月間に行われる日数、③当該派
遣先の通常の労働者の1箇月間の所定労働日教
法第40条の2第1項第4号に掲げる育児休業等の代替要員としての業務について労働者派
遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び
終了予定の日
法第40条の2第1項第5号に掲げる介護休業等の代替要員としての業務について労働者派
遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び
終了予定の日
⑰ 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
(「無」の場合はその理由を具体的に付すこと。また、手続終了後は「有」に書き換えるこ
と。)
⑱ 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容に関する事項
法第30条の2第1項に規定する教育訓練(OFF-JT及び計画的なOJT)について記述する。
⑲ キャリアコンサルティングを行った日とその内容に関する事項
法第30条の2第2項に規定するキャリアコンサルティングについて記述する。
⑳ 雇用安定措置の内容
派遣労働者に対して実施した措置の日付、内容とその結果について記載すること。派遣先に
対して直接雇用の依頼を行った場合については、派遣先の受入れの可否についても記載するこ
と。
(参 考) 派遣元管理台帳の例
1 派遣労働者氏名 〇〇〇〇〇(60歳未満)
2 協定対象派遣労働者ではない(派遣先均等・均衡方式)
3 有期雇用派遣労働者(労働契約期間 平成〇年〇月〇日~平成〇年〇月〇日)
4 派遣先の名称 □□□□株式会社
5 派遣先の事業所の名称 □□□□株式会社××支店
6 就業の場所及び組織単位 経理課
- 251-
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
(〒100-1234 千代田区大手町1-2-30ビル4階
TEL3593-**** 内線571)
7 業務の種類 営業課内における事務の補助、電話応対、郵便物の仕分・発送の業務。
8 副リーダー(部下2名、リーダー不在の間における緊急対応が過1回程度有)
9 派遣元責任者 派遣事業運営係長 ◎◎◎◎◎ 内線100
10 派遣先責任者 □□□□株式会社 ××支店人事課人事係長 =… 内線5720
11派遣就業の期間 平成××年×月×日から平成××年×月×日まで
12 就業する日 土曜、日曜を除く毎日
13 就業時間 9時から18時までとし、休憩時間は12時から13時まで
1411の就業時間外の労働 1日4時間、1箇月45時間、1年360時間の範囲で命ずることがで
きる。
15 就業状況
〇月〇日(月) 2時間の就業時間外の労働
×月×日(水) カゼにより欠勤
16 派遣労働者からの苦情処理状況
(申出を受けた日) (苦情内容、処理状況)
△月△日(木) 派遣先において社員食堂の利用に関して便宜が図られていないとの苦情。
法の趣旨を説明し、以後、派遣先の他の労働者と同様に、派遣先の施設を
利用できるよう申入れ。
17 労働・社会保険の被保険者資格取得届の提出の有無
雇用保険 有
健康保険 無(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の〇
日に届出予定)・・・〇月〇日手続完了、有
厚生年金保険 無(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の〇
日に届出予定)・・・〇月〇日手続完了、有
18 教育訓練の日時及び内容 〇年〇月〇日~〇月〇日 各日15:00~17:00
人職時の基本業務の研修(ェクセル、パワーポイントによるデモ資料作成等)
19 キャリアコンサルティングの日及び内容
〇年〇月〇日 キャリアコンサルタントによる能力の棚卸しの実施
〇年〇月〇日 前回の能力の棚卸しに基づく今後のキャリアパスについて相談
20 雇用安定措置の内容
1 派遣先への直接雇用の依頼
依頼日時、方法 〇年〇月〇日文書により依頼。
派遣先の回答日時、内容 〇年〇月〇日 受入可(雇用形態:正社員)
2 他の派遣先の紹介 省略
- 252 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
3 期間を定めない雇用の機会の確保 省略
4 その他 省略
(2)派遣元管理台帳の保存
イ 概要
派遣元事業主は、派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない(法第37条第2項)。
ロ 意義
(イ)派遣元管理台帳の保存は、派遣労働者の派遣就業に関する紛争の解決を図り、行政による
監督の用に供するために行うためのものである。
(ロ)派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算の起算日は、労働者派遣の終了の日とする(則第
32条)。
(ハ)「労働者派遣の終了」とは、労働者派遣に際し定められた当該派遣労働者に係る派遣期間
の終了であり、労働者派遣契約が更新された場合には、当該更新に伴い定められた当該派遣
労働者に係る派遣期間の終了とする。ただし、同一の派遣労働者を、同一の就業の場所及び
組織単位で就業させる労働者派遣(法第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除
く。)については、当該労働者派遣契約が更新されていない場合であっても当該派遣就業の
終了の日から次の同一の派遣就業の開始の日までの期間が3箇月以下のときは労働者派遣の
終了とは取り扱わない。
(ニ)保存は、当該事業所ごとに行わなければならない。
(ホ)紹介予定派遣とそれ以外の派遣については、派遣元管理台帳は別々に管理することが適当
である。
21労働・社会保険の適用の促進
(1)労働・社会保険への適切な加入
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続
を適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働
者派遣を行うこと(新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働
者派遣の開始後速やかに労働・社会保険の加入の手続を行うときを含む。)(「派遣元事業主が講
ずべき措置に関する指針」第2の4(第7の15の(5)のニ、27参照))。
(2)被保険者証等の写し等の提示
派遣元事業主は、健康保険法施行規則第24条第1項に規定する健康保険被保険者資格取得届、
厚生年金保険法施行規則第15条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届、雇用保険法施行規則
第6条に規定する雇用保険被保険者資格取得届の提出がなされている派遣労働者に係る労働者派遣
をする場合には、派遣先に対し、当該派遣労働者に係る被保険者証等の写しを郵送する又は持参す
る等により、提示しなければならない。(則第27条第4項)これにより、派遣先も派遣労働者が社
- 253 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
会保険等に適切に加入していることを確認することが可能となる。
また、派遣就業開始後に上記資格取得届が提出された場合も同様に取り扱う(則第27条第6
項)。
なお、派遣元が派遣先に被保険者証等を送付する場合には、原則として当該派遣労働者の同意を
得た上で行うこととするが、当該同意が得られない場合には、生年月日、年齢を黒塗りする等の個
人情幸酎こ配慮することが適当である。
(3)派遣労働者に対する未加入の理由の通知
派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対して通知
した当該派遣労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、当該派遣労働者に対して
も通知すること(第7の15の(5)のこ参照)。
22 関係法令の関係者への周知
派遣元事業主は、法の規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容や法第3章第4節
に規定する労働基準法等の適用に関する特例等の関係者への周知を図るために、説明会等の実施、文
書の配布等の措置を講ずること(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の10(第7の
27参照))。
23 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等
派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者の特定を目的とする行為に
協力してはならない(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の13の(1)(第7の27参
照))。
「特定を目的とする行為」への「協力」とは、派遣先からの派遣労働者の指名行為に応じることだ
けでなく、例えば、派遣先への履歴書の送付、派遣先による派遣労働者の事前面接への協力等特定を
目的とする行為(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の3(第8の15、18参照))に対する
協力は全て含まれる。
ただし、本取扱いは、あくまでも個々の派遣労働者の特定につながる行為を禁止する趣旨であるた
め、一定の技術や技能の水準を特定することをもって、当該禁止対象の行為とするものではない。
したがって、派遣先において必要とされる技術・技能の水準が明確な場合であって、派遣元が派遣
先に対して候補となる派遣労働者(派遣労働者となろうとする者も含む。)に係るいわゆるスキルシ
ートの提供を行う場合は、当該派遣労働者の現時点における技術・技能レベル(取得資格等)と当該
技術・技能に係る経験年数のみを記載したものを提供することとし、特定日的行為に該当することが
ないよう十分に配慮する必要がある。
なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として適当であるか
どうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は
派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とす
- 254 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
る行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働
者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目
的とする行為への協力の禁止に触れないよう十分留意すること。(「派遣元事業主が講ずべき措置に
関する指針」第2の13の(1)(第7の27参照))。
また、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、事業所訪問等を行わないことを理由とする
不利益取扱いを行ってはならないものであること。
24 性・障害の有無・年齢による差別的な取扱いの禁止等
(1)派遣労働者の性別の労働者派遣契約への記載の禁止等
職業安定法第3条の規定は労働者派遣事業にも適用があるものであること(職業紹介事業者、労
働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等
の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するた
めの指針(平成11年労働省告示第141号)第2条の1参照)。
このため、派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、職業安定
法第3条の規定を遵守し、派遣労働者の性別を労働者派遣契約に記載し、これに基づき当該派遣労
働者を当該派遣先に派遣してはならず、また、性別による不合理な差別的労働者派遣を行ってはな
らないので、その旨の周知、指導に努めること(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第
2の13の(2)(第7の27参照))。
(2)障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いの禁止等
派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣元事業主が当該
派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、障害者であることを理由として、障
害者を排除し、又はその条件を障害者に対してのみ不利なものとしてはならず、かつ、これに基づ
き障害者でない派遣労働者を当該派遣先に派遣してはならないので、その旨の周知、指導に努める
こと(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の13の(3)(第7の27参照))。
なお、職業安定法第3条による差別的取扱いの禁止の対象には、障害者であることも含まれるも
のであり、障害者であることを理由として差別的労働者派遣を行ってはならないものであることに
留意すること。
(3)年齢による不合理な差別的派遣に対する指導等
派遣元事業主は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す
る法律(昭和41年法律第132号。以下「労働施策総合推進法」という。)第9条及び職業安定法第
3条の趣旨に鑑み、年齢による不合理な差別的労働者派遣を行うことは不適当である旨、周知、指
導に努めること。
(4)派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の禁止に向けた取組
- 255 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
法に規定する労働者派遣に関し、派遣元事業主が行う派遣労働者の募集及び採用についても、原
則として労働施策総合推進法第9条及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職
業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号。以下「労働施策総合推進法施行
規則」という。)第1条の3の規定は適用されること。なお、以下の点について留意すること。
イ いわゆる登録型派遣の場合における募集及び採用について
派遣元事業主が登録された者の中から派遣労働者の募集及び採用を行うに当たっても、労働施
策総合推進法第9条及び労働施策総合推進法施行規則第1条の3の規定は当然に適用されるこ
と。
ロ いわゆる登録型派遣の場合における「登録」の取扱い
(力 具体的な雇用契約の締結を前提とした「登録」の場合
具体的な雇用契約の締結を前提とし、派遣労働者になろうとする者に「登録」を呼びかける
行為は、労働者の募集に該当するものであり、労働施策総合推進法第9条及び労働施策総合推
進法施行規則第1条の3の規定が適用され、年齢の制限を行うことができるのは労働施策総合
推進法施行規則第1条の3第1項各号に掲げる例外事由(以下「例外事由」という。)に該当
するときに限られるものであること。
② 具体的な雇用契約の締結を前提としない「登録」の場合
具体的な雇用契約の締結を前提とせず派遣労働者になろうとする者に呼びかけて「登録」を
させる場合において、当該「登録」をした者から派遣労働者を募集又は採用するときには、労
働施策総合推進法第9条及び労働施策総合推進法施行規則第1条の3の規定が適用され、年齢
の制限を行うことができるのは例外事由に該当するときに限られるものであること。
したがって、上記(力及び②のいずれの「登録」であっても、例外事由に該当する条件の下で
派遣労働者を募集又は採用することを最終的な目的とする「登録」でなければ、個人の年齢に
関する情報を収集し、保管し、又は使用することは法第24条の3に基づき許容される「業務の
目的の達成に必要な範囲内」を超えて個人情報を収集することに該当して同条の規定に違反す
ることとなり、例外事由に該当する条件の下で派遣労働者を募集又は採用することを最終的な
目的とするものでなければ派遣労働者の雇用に結びつけることはできないものであること。ま
た、例外事由に該当することとなる条件の下で年齢制限をして派遣労働者を募集又は採用する
ことを最終的な目的とする「登録」を行うときには、年齢情報を含む登録者の情報を収集し、
保管し、又は使用するに当たり、当該年齢制限をした事由ごとに明確に区分して登録情報を取
り扱わなければならないものであること。
(5)紹介予定派遣における派遣労働者の特定に当たっての年齢、性別、障害の有無等による差別防止
に係る措置
上記の措置と関連して、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の18の(3)、(4)及び(5)に
おいて、派遣先は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為又は派遣労働
者の特定(以下「特定等」という。)を行うに当たっては、直接採用する場合と同様に、労働施策
- 256 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
総合推進法第9条及び労働施策総合推進法施行規則第1条の3、男女雇用機会均等法に基づく「労
働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対
処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)」並びに障害者雇用促進法に基づく「障害
者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平
成27年厚生労働省告示第116号)」の内容と同旨の内容の措置を適切に講ずるものとすることとさ
れている(第8の17の(3)参照)ことに十分に留意すること。
(6)「派遣労働者を特定することを目的とする行為への協力の禁止等」との関係
性別、障害(障害者雇用促進法第2条第1項に規定する障害)の有無、年齢等による差別的な
取扱いの禁止の観点と特定日的行為の禁止の観点から提供が望ましくない情幸田ま別のものである
ので、留意する必要がある。
25 紹介予定派遣
紹介予定派遣を行う場合の取扱いについては、第1の4及び第6の2の(1)によるほか、派遣元事
業主は次の(1)から(6)に留意すること。
(1)紹介予定派遣の期間
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行うに当たっては、6箇月を超えて、同一の派遣労働者の労働
者派遣を行わないものとすること(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の15の
(1)、第7の27参照)。
(2)派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
イ 派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合
又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先
に対して、それぞれその理由について、書面、ファクシミリ又は電子メール等により明示するよ
う求めるものとすること。また、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面、ファ
クシミリ又は電子メール等(ファクシミリ又は電子メール等による場合にあっては、当該派遣労
働者が希望した場合に限る。)により明示するものとすること(「派遣元事業主が講ずべき措置
に関する指針」第2の15の(2)、第7の27参照)。なお、この場合の派遣労働者に対するファク
シミリ又は電子メール等による明示に関しては、10の(6)のイからハまでに掲げる留意点に十分
留意する必要があること。
ロ イに関連して、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の18の(2)において、派遣先は、
紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業
紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれのそ
の理由を、派遣元事業主に対して書面、ファクシミリ又は電子メール等により明示することとさ
れているので、十分留意すること。
(3)派遣就業期間の短縮
イ 当初予定していた紹介予定派遣の派遣期間については、三者(派遣労働者、派遣先、派遣元幸
一 257 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
業主)の合意の下これを短縮し、派遣先と派遣労働者との間で雇用契約を締結することが、可能
であること。
ロ 早期の職業紹介による派遣先の直接雇用を実現できるようにする観点から、三者の合意に基づ
き、当初の契約において、派遣就業期間の短縮(派遣契約の終了)がある旨及びその短縮される
期間に対応する形で紹介手数料の設定を行うことが認められる旨を定めることは可能であり、こ
の場合において派遣就業期間が短縮されたときには、当該契約に基づき派遣元事業主(職業紹介
事業者)がこれに対応した手数料を徴収しても差し支えないこと。
ハ イ及びロの特約による派遣就業期間の短縮(派遣契約の終了)は、あくまで職業紹介による派
遣先の直接雇用の早期実現を可能とするために認められるものであり、派遣先の責に帰すべき事
由により派遣契約の中途解除が行われるような目的で行ってはならない旨派遣先に周知するこ
と。
(4)求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化
イ 当初予定していた紹介予定派遣の求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期
については、三者(派遣労働者、派遣先及び派遣元事業主)の合意の下、これを早期化すること
が可能であること。
ロ 早期の派遣先の直接雇用を実現できるようにする観点から、三者の合意に基づき、当初の契約
において、求人・求職の意思確認及び職業紹介の早期化がある旨を定めることは可能であるこ
と。
ハ イ及びロの特約による求人・求職の意思確認及び職業紹介の早期化は、あくまで派遣先の直接
雇用の早期実現を可能とするために認められるものであり、派遣先の責に帰すべき事由により派
遣契約の中途解除が行われるような目的で行ってはならない旨派遣先に周知すること。
(5)紹介予定派遣における派遣労働者を特定することを目的とする行為
イ 年齢・性別・障害の有無による差別の禁止
紹介予定派遣については、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が可能である
が、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の18の(3)、(4)及び(5)において、派遣先
は、紹介予定派遣に係る特定等を行うに当たっては、直接採用する場合と同様に、労働施策総合
推進法第9条及び労働施策総合推進法施行規則第1条の3、男女雇用機会均等法に基づく「労働
者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対
処するための指針」並びに障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定
に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第116
号)」の内容と同旨の内容の措置を適切に講ずるものとすることとされている(第8の17参照)
ことに派遣元事業主としても十分に留意すること。
ロ 派遣労働者の特定
紹介予定派遣について派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が認められるの
は、あくまで円滑な直接雇用を図るためであることに鑑み、派遣先が、試験、面接、履歴書の送
- 258 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
付等により派遣労働者を特定する場合は、業務遂行能力に係る試験の実施や資格の有無等、社会
通念上、公正と認められる客観的な基準によって行われることが必要であることに、派遣元事業
主としても十分に留意すること。
ハ 派遣先が障害者に対して特定することを目的とする行為を行う場合の措置
事業主は、派遣先が障害者に対し、面接その他紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定すること
を目的とする行為を行う場合に、障害者雇用促進法第36条の2又は第36条の3の規定による措置
を講ずるに当たっては、障害者と話合いを行い、派遣元事業主において実施可能な措置を検討す
るとともに、必要に応じ、派遣先と協議等を行い、協力を要請すること。(「派遣元事業主が講
ずべき措置に関する指針」第2の15の(3)(第7の27参照))。
(6)その他
イ 紹介予定派遣においては、派遣先及び派遣労働者の求人・求職の意思等を確認して職業紹介が
行われるものであり、当該意思等のいかんによっては職業紹介が行われないこともあることを派
遣労働者及び派遣先に明示すること。
ロ 派遣受入期間の制限を免れる目的で紹介予定派遣を行うものではないこと。
ハ 紹介予定派遣の場合に派遣元事業主が行う職業紹介についても、当然に職業安定法第3条(均
等待遇)、第5条の3(労働条件等の明示)、第5条の4(求職者等の個人情報の取扱い)等の
職業紹介に係る関係法令が適用されるものであり、その旨派遣元事業主に対して十分周知するこ
と。
26 紹介予定派遣以外の派遣として派遣就業を開始した場合における求人条件の
明示等
当初より紹介予定派遣として派遣就業が開始された場合でなくとも、派遣就業期間中に、(力職業紹
介事業者でもある派遣元事業主が、派遣労働者又は派遣先の希望に応じて、求人条件の明示、求人・
求職の意思等の確認を行うこと、及び、②派遣先が派遣労働者に対して採用内定を行うことは可能で
ある。
なお、(力の求人条件の明示等の結果、派遣労働者及び派遣先が職業紹介を受けることに合意した場
合には、その時点で当該労働者派遣は紹介予定派遣に該当することとなることから、速やかに、従前
の労働者派遣契約の変更を行い、紹介予定派遣に係る事項を定める等(第6の2の(1)のイの(ハ)の⑲
参照)、紹介予定派遣に必要とされる措置を行うことが必要である。
27 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(1)概要
厚生労働大臣は、法に規定される派遣元事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実
施を図るため必要な指針を公表するものとする(法第47条の4)。
- 259 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
(2)指針の公表
指針は、平成11年労働省告示第137号「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」及び平成20
年厚生労働省告示第36号「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が
講ずべき措置に関する指針」による。
(3)無期雇用派遣労働者の募集
派遣元指針において、派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者の募集に当たっては、「無期雇用派
遣」という文言を使用すること等により、無期雇用派遣労働者の募集であることを明示しなけれ
ばならないこととしている。
これは、平成27年の派遣法改正において無期雇用派遣が期間制限の例外とされたこと等を契機
として、無期雇用派遣を「正社員」と誤解されかねない募集広告により求職者を集めようとした
ビジネスモデルが国会において問題視されたこと等から、このような誤解を招かないようにする
趣旨である。
したがって、現在、既に定着している派遣形態として見られる、派遣元の「正社員」として採
用しており、待遇面も「正社員」に相応しいものとなっている技術者派遣まで直ちに規制しよう
とするものではなく、当分の間、現在の取扱いを認めること。ただし、この場合も、可能な限り
早期に「無期雇用派遣」という標記に移行することが望ましいこと。
なお、このような、既に「正社員派遣」として行っている事業についてであっても、以下に該
当するケースについては「正社員」として募集することは指針の規制の対象となること
(力採用時点が明確になっていないこと(派遣先が見つかるまで無給で待機となっていること)
②事業所内の正社員に係る就業規則又は同等の内容の就業規則の適用がないこと
28 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が
講ずべき措置に関する指針
「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指
針」(以下第7において、「日雇派遣指針」という。)の取扱い等については、以下のとおりとす
る。
(1)労働者派遣契約の期間の長期化(日雇派遣指針第2の2)
労働者派遣契約の期間の長期化については、「派遣先において労働者派遣の役務の提供を受けよ
うとする期間を勘案して」行うものであり、長期にすることが可能と考えられる労働者派遣契約を
短期の細切れのものとすることを防止しようとするものであること。
(2)労働契約の期間の長期化(日雇派遣指針第2の4)
労働契約の期間の長期化については、労働者派遣契約の期間の長期化と同様、「労働者派遣契約
における労働者派遣の期間を勘案して」行うものであり、長期にすることが可能と考えられる労働
契約を短期の細切れのものとすることを防止しようとするものであること。「派遣元事業主が講ず
べき措置に関する指針」(以下この第8において「派遣元指針」という。)では、労働契約の期間
- 260 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
を「労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等」としているが、日雇派遣の場合に
は、この労働者派遣の期間が短期であるために労働契約の期間も短期にしかならないため、日雇派
遣指針においては、労働契約を「できるだけ長期にする」ということを定めているものであるこ
と。その方法としては、複数の労働者派遣契約について、同一の派遣労働者を派遣することによ
り、当該派遣労働者との労働契約を長期にすることが考えられること。
(3)労働者派遣契約に定める就業条件の確保(日雇派遣指針第3)
イ 派遣先による就業場所の巡回等については、「1の労働者派遣契約について少なくとも1回以
上の頻度で定期的に」行うこととしており、例えば、日々の労働者派遣契約であれば、毎日行わ
なければならず、また、1週間の労働者派遣契約であれば、1週間に1回以上行わなければなら
ないものであること。
ロ 日雇派遣指針第3の2(1)において派遣先は「日雇派遣労働者の就業場所を巡回」することと
しているが、「日雇派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に反していないことを確認する」
ために行うものであり、巡回する者については、労働者派遣契約の内容を把握していることはも
ちろん、当該内容を確保することに責任を有する者でなければ、派遣先が適切に行ったことには
ならないものであること。したがって、就業の現場に派遣先の労働者がいることをもって、派遣
先が就業場所の巡回をしたこととはならないことに留意すること。
(4)労働・社会保険の適用の促進(日雇派遣指針第4)
日雇派遣指針第4の3の日雇手続を「行えないとき」とは、労働保険の保険料の徴収等に関する
法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第39条の規定に反して日雇労働被保険者である日雇派遣
労働者が日雇労働被保険者手帳を提出しない場合や、健康保険法第169条第4項の規定に反して日
雇特例被保険者である日雇派遣労働者が日雇特例被保険者手帳を提出しない場合等、例外的なもの
であること。
(5)関係法令等の関係者への周知(日雇派遣指針第7)
日雇派遣指針第7の「関係法令」には労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律、職業安定法、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、健康保険法及びこれら
に基づく政省令等が含まれるものであること。
(6)日雇派遣労働者の安全衛生の確保(日雇派遣指針第8)
安全衛生教育又は危険有害業務の特別教育の実施の有無を確認する時点については、雇入時の安
全衛生教育であれば、派遣初日に、派遣先から派遣元事業主に電話等により確認する、派遣先が派
遣労働者本人に口頭で確認すること等により対応すること。また、危険有害業務の特別教育であれ
ば、派遣初日に、派遣元事業主から派遣先に電話等により確認すること等により対応すること。
(7)派遣先への説明(日雇派遣指針第12)
派遣元事業主による派遣先への説明については、派遣労働者との雇用契約の当事者である派遣元
事業主が派遣先に対して、派遣労働者が日雇派遣労働者であるか否かを説明しない場合、派遣先が
この指針を適用し、労働者派遣事業の適正な運営を確保することができないことから、求めている
- 261-
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
ものであること。
29短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する
指針
ガイドラインは、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、い
かなる待遇の相違が不合理と認められるものであり、いかなる待遇の相違が不合理と認められるも
のでないのか等の原則となる考え方及び具体例を示したものである。派遣元事業主は、派遣労働者
の待遇について、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を確保し、及び一定の要件を満たす労
使協定に基づく待遇を確保するに当たっては、ガイドラインも踏まえて適切に対応すること。詳細
は4の(7)を参照のこと。
- 262 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(平成11年労働省告示第137号)
(最終改正 平成30年厚生労働省告示第427号)
第1 趣旨
この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働
者派遣法」という。)第24条の3並びに第3章第1節及び第2節の規定により派遣元事業主が講ずべき
措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。
また、労働者派遣法第24条の3の規定により派遣元事業主が講ずべき措置に関する必要な事項と併
せ、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の遵守等についても定めたものである。
第2 派遣元事業主が講ずべき措置
1 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認
派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに際しては、派遣先が求める業務の内
容及び当該業務に伴う責任の程度(8及び9において「職務の内容」という。)、当該業務を遂行す
るために必要とされる知識、技術又は経験の水準、労働者派遣の期間その他労働者派遣契約の締結に
際し定めるべき就業条件を事前にきめ細かに把握すること。
2 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(1) 労働契約の締結に際して配慮すべき事項
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該労働者の希望及
び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、労働契約の期間について、当該期間を当
該労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、派遣労働者の雇用の安定を図るために
必要な配慮をするよう努めること。
(2) 労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置
イ 派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由により労働者
派遣契約の契約期間が満了する前に当該労働者派遣契約の解除が行われる場合には、派遣先は当
該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること及びこれができないときには
少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働
者を休業させること等を余儀なくされることにより生ずる損害である休業手当、解雇予告手当等
に相当する額以上の額について損害の賠償を行うことを定めるよう求めること。
ロ 派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に当たって、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に
係る派遣労働者を派遣先が雇用する場合に、当該雇用が円滑に行われるよう、派遣先が当該労働
者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する意思がある場合には、当該意思を事前に派遣元事業
主に示すこと、派遣元事業主が職業安定法(昭和22年法律第141号)その他の法律の規定による
許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合には、派遣先は職業紹介により
当該派遣労働者を雇用し、派遣元事業主に当該職業紹介に係る手数料を支払うこと等を定めるよ
う求めること。
(3) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置
派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以
外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と
連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受けること、当該派遣元事業主にお
いて他の派遣先を確保すること等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会
の確保を図ること。また、当該派遣元事業主は、当該労働者派遣契約の解除に当たって、新たな就
業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図るようにす
るとともに、休業手当の支払等の労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づく責任を果たすこ
と。さらに、やむを得ない事由によりこれができない場合において、当該派遣労働者を解雇しよう
とするときであっても、労働契約法(平成19年法律第128号)の規定を遵守することはもとより、
当該派遣労働者に対する解雇予告、解雇予告手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすこ
と。
(4) 労働者派遣契約の終了に当たって講ずべき事項
イ 派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者(労働者派遣法第30条の2第1項に規定する無期雇用派
遣労働者をいう。以下同じ。)の雇用の安定に留意し、労働者派遣が終了した場合において、当
該労働者派遣の終了のみを理由として当該労働者派遣に係る無期雇用派遣労働者を解雇してはな
らないこと。
ロ 派遣元事業主は、有期雇用派遣労働者(労働者派遣法第30条第1項に規定する有期雇用派遣労
働者をいう。以下同じ。)の雇用の安定に留意し、労働者派遣が終了した場合であって、当該労
働者派遣に係る有期雇用派遣労働者との労働契約が継続しているときは、当該労働者派遣の終了
のみを理由として当該有期雇用派遣労働者を解雇してはならないこと。
3 適切な苦情の処理
派遣元事業主は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主において苦情の処理を行う方
法、派遣元事業主と派遣先との連携のための体制等を労働者派遣契約において定めること。また、派
遣元管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を
受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載すること。また、派遣労働者から苦情の申出を受けたこ
とを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。
- 263 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
4 労働・社会保険の適用の促進
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続を
適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派
遣を行うこと。ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労
働者派遣の開始後速やかに労働・社会保険の加入手続を行うときは、この限りでないこと。
5 派遣先との連絡体制の確立
派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣
契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のため
に、きめ細かな情報提供を行う等により、派遣先との連絡調整を的確に行うこと。特に、労働基準法
第 36 条第1項の時間外及び休日の労働に関する協定の内容等派遣労働者の労働時間の枠組みについ
ては、情報提供を行う等により、派遣先との連絡調整を的確に行うこと。なお、同項の協定の締結に
当たり、労働者の過半数を代表する者の選出を行う場合には、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生
省令第23号)第6条の2の規定に基づき、適正に行うこと。
また、派遣元事業主は、割増賃金等の計算に当たり、その雇用する派遣労働者の実際の労働時間等
について、派遣先に情報提供を求めること。
6 派遣労働者に対する就業条件の明示
派遣元事業主は、モデル就業条件明示書の活用等により、派遣労働者に対し就業条件を明示するこ
と。
7 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止
派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを
新たに労働者派遣の対象としようとする場合であって、当該労働者が同意をしないことを理由とし
て、当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
8 派遣労働者の雇用の安定及び福祉の増進等
(1) 無期雇用派遣労働者について留意すべき事項
派遣元事業主は、無期雇用派遣労働者の募集に当たっては、「無期雇用派遣」という文言を使用
すること等により、無期雇用派遣労働者の募集であることを明示しなければならないこと。
(2) 特定有期雇用派遣労働者等について留意すべき事項
イ 派遣元事業主が、労働者派遣法第30条第2項の規定の適用を避けるために、業務上の必要性等
なく同一の派遣労働者に係る派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」とい
う。)における同一の組織単位(労働者派遣法第26条第1項第2号に規定する組織単位をいう。
以下同じ。)の業務について継続して労働者派遣に係る労働に従事する期間を3年末満とするこ
とは、労働者派遣法第30条第2項の規定の趣旨に反する脱法的な運用であって、義務違反と同視
できるものであり、厳に避けるべきものであること。
ロ 派遣元事業主は、労働者派遣法第30条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場
合を含む。以下同じ。)の規定により同条第1項の措置(以下「雇用安定措置」という。)を講
ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定有期雇用派遣労働者等(同条第1項に規
定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。)(近い将来に該当する見込みのある者を
含む。)に対し、キャリアコンサルティング(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第
2条第5項に規定するキャリアコンサルティングのうち労働者の職業生活の設計に関する相談そ
の他の援助を行うことをいう。)や労働契約の更新の際の面談等の機会を利用し、又は電子メー
ルを活用すること等により、労働者派遣の終了後に継続して就業することの希望の有無及び希望
する雇用安定措置の内容を把握すること。
ハ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定有
期雇用派遣労働者等の希望する雇用安定措置を講ずるよう努めること。また、派遣元事業主は、
特定有期雇用派遣労働者(労働者派遣法第 30 条第1項に規定する特定有期雇用派遣労働者をい
う。)が同項第1号の措置を希望する場合には、派遣先での直接雇用が実現するよう努めるこ
と。
ニ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、当該雇用安定措置の対象となる特定有
期雇用派遣労働者等の労働者派遣の終了の直前ではなく、早期に当該特定有期雇用派遣労働者等
の希望する雇用安定措置の内容について聴取した上で、十分な時間的余裕をもって当該措置に着
手すること。
(3) 労働契約法等の適用について留意すべき事項
イ 派遣元事業主は、派遣労働者についても労働契約法の適用があることに留意すること。
ロ 派遣元事業主が、その雇用する有期雇用派遣労働者について、当該有期雇用派遣労働者からの労
働契約法第18条第1項の規定による期間の定めのない労働契約の締結の申込みを妨げるために、当
該有期雇用派遣労働者に係る期間の定めのある労働契約の更新を拒否し、また、空白期間(同条第
2項に規定する空白期間をいう。)を設けることは、同条の規定の趣旨に反する脱法的な運用であ
ること。
ハ 派遣元事業主は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年
法律第76号)第8条の規定により、その雇用する有期雇用派遣労働者の通勤手当について、その雇
用する通常の労働者の通勤手当との間において、当該有期雇用派遣労働者及び通常の労働者の職務
の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該通勤手当の性質及び当該
通勤手当を支給する目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を
- 264 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
設けてはならないこと。また、派遣元事業主は、同法第9条の規定により、職務の内容が通常の労
働者と同一の有期雇用派遣労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該
派遣元事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常
の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものにつ
いては、有期雇用労働者であることを理由として、通勤手当について差別的取扱いをしてはならな
いこと。なお、有期雇用派遣労働者の通勤手当については、当然に労働者派遣法第30条の3又は第
30条の4第1項の規定の適用があることに留意すること。
(4) 派遣労働者等の適性、能力、経験、希望等に適合する就業機会の確保等
派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者(以下「派遣労働者等」という。)
について、当該派遣労働者等の適性、能力、経験等を勘案して、最も適した就業の機会の確保を図る
とともに、就業する期間及び目、就業時間、就業場所、派遣先における就業環境等について当該派遣
労働者等の希望と適合するような就業機会を確保するよう努めなければならないこと。また、派遣労
働者等はその有する知識、技術、経験等を活かして就業機会を得ていることに鑑み、派遣元事業主
は、労働者派遣法第 30 条の2の規定による教育訓練等の措置を講じなければならないほか、就業機
会と密接に関連する教育訓練の機会を確保するよう努めなければならないこと。
(5) 派遣労働者に対するキャリアアップ措置
イ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に対し、労働者派遣法第30条の2第1項の規定による
教育訓練を実施するに当たっては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律施行規則第1条の4第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労
働省告示第 391号)第4号に規定する教育訓練の実施計画(以下「教育訓練計画」という。)に基
づく教育訓練を行わなければならないこと。
ロ 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約の締結時までに教
育訓練計画を周知するよう努めること。また、派遣元事業主は、当該教育訓練計画に変更があった
場合は、その雇用する派遣労働者に対し、速やかにこれを周知するよう努めること。
ハ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が教育訓練計画に基づく教育訓練を受講できるよう配
慮しなければならないこと。特に、教育訓練計画の策定に当たっては、派遣元事業主は、教育訓練
の複数の受講機会を設け、又は開催目時や時間の設定について配慮すること等により、可能な限り
派遣労働者が教育訓練を受講しやすくすることが望ましいこと。
ニ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るため、教育訓練計画に基づく
教育訓練を実施するほか、更なる教育訓練を自主的に実施するとともに、当該教育訓練に係る派遣
労働者の費用負担を実費程度とすることで、派遣労働者が教育訓練を受講しやすくすることが望ま
しいこと。
ホ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るとともに、その適正な雇用管
理に資するため、当該派遣労働者に係る労働者派遣の期間及び派遣就業をした目、従事した業務の
種類、労働者派遣法第37条第1項第10号に規定する教育訓練を行った目時及びその内容等を記載
した書類を保存するよう努めること。
(6) 労働者派遣に関する料金の額に係る交渉等
イ 労働者派遣法第30条の3の規定による措置を講じた結果のみをもって、当該派遣労働者の賃金を
従前より引き下げるような取扱いは、同条の規定の趣旨を踏まえた対応とはいえないこと。
ロ 派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額に係る派遣先との交渉が当該労働者派遣に係る派
遣労働者の待遇の改善にとって極めて重要であることを踏まえつつ、当該交渉に当たるよう努める
こと。
ハ 派遣元事業主は、労働者派遣に関する料金の額が引き上げられた場合には、可能な限り、当該労
働者派遣に係る派遣労働者の賃金を引き上げるよう努めること。
(7) 同一の組織単位の業務への労働者派遣
派遣元事業主が、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して3年間同一の
派遣労働者に係る労働者派遣を行った場合において、当該派遣労働者が希望していないにもかかわら
ず、当該労働者派遣の終了後3月が経過した後に、当該同一の組織単位の業務について再度当該派遣
労働者を派遣することは、派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくないこと。
(8) 派遣元事業主がその雇用する協定対象派遣労働者(労働者派遣法第 30条の5に規定する協定対象
派遣労働者をいう。以下同じ。)に対して行う安全管理に関する措置及び給付のうち、当該協定対象
派遣労働者の職務の内容に密接に関連するものについては、派遣先に雇用される通常の労働者との間
で不合理と認められる相違等が生じないようにすることが望ましいこと。
(9) 派遣元事業主は、派遣労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律(平成3年法律第 76号)第2条第1号に規定する育児休業から復帰する際には、当該派遣
労働者が就業を継続できるよう、当該派遣労働者の派遣先に係る希望も勘案しつつ、就業機会の確
保に努めるべきであることに留意すること。
(10) 障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための
措置
派遣元事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用
- 265 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
促進法」という。)第2条第1号に規定する障害者(以下単に「障害者」という。)である派遣労働
者から派遣先の職場において障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている
事情の申出があった場合又は派遣先から当該事情に関する苦情があった旨の通知を受けた場合等にお
いて、同法第36条の3の規定による措置を講ずるに当たって、当該障害者である派遣労働者と話合い
を行い、派遣元事業主において実施可能な措置を検討するとともに、必要に応じ、派遣先と協議等を
行い、協力を要請すること。
9 派遣労働者の待遇に関する説明等
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に対し、労働者派遣法第31条の2第4項の規定による説
明を行うに当たっては、次の事項に留意すること。
(1)派遣労働者(協定対象派遣労働者を除く。以下この(1)及び(2)において同じ。)に対する説明の
内容
イ 派遣元事業主は、労働者派遣法第26条第7項及び第10項並びに第40条第5項の規定により提
供を受けた情報(11及び12 において「待遇等に関する情報」という。)に基づき、派遣労働者
と比較対象労働者(労働者派遣法第26条第8項に規定する比較対象労働者をいう。以下この9に
おいて同じ。)との間の待遇の相違の内容及び理由について説明すること。
ロ 派遣元事業主は、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容として、次の(イ)及
び(ロ)に掲げる事項を説明すること。
(イ) 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項の相
違の有無
・l H〓
) ( (
ロ
次の(i)又は(のに掲げる事項
) 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇の個別具体的な内容
派遣労働者及び比較対象労働者の待遇に関する基準
ハ 派遣元事業主は、派遣労働者及び比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の
範囲その他の事情のうち、待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるものに基
づき、待遇の相違の理由を説明すること。
(2)協定対象派遣労働者に対する説明の内容
イ 派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の賃金が労働者派遣法第30条の4第1項第2号に掲げる
事項であって同項の協定で定めたもの及び同項第3号に関する当該協定の定めによる公正な評価
に基づき決定されていることについて説明すること。
ロ 派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の待遇(賃金、労働者派遣法第40条第2項の教育訓練及
び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年
労働省令第20号)第32条の3各号に掲げる福利厚生施設を除く。)が労働者派遣法第30条の4
第1項第4号に基づき決定されていること等について、派遣労働者に対する説明の内容に準じて
説明すること。
(3)派遣労働者に対する説明の方法
派遣元事業主は、派遣労働者が説明の内容を理解することができるよう、資料を活用し、口頭に
より説明することを基本とすること。ただし、説明すべき事項を全て記載した派遣労働者が容易に
理解できる内容の資料を用いる場合には、当該資料を交付する等の方法でも差し支えないこと。
(4)比較対象労働者との間の待遇の相違の内容等に変更があったときの情報提供
派遣元事業主は、派遣労働者から求めがない場合でも、当該派遣労働者に対し、比較対象労働者
との間の待遇の相違の内容及び理由並びに労働者派遣法第30条の3から第30条の6までの規定
により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項に変更が
あったときは、その内容を情報提供することが望ましいこと。
10 関係法令の関係者への周知
派遣元事業主は、労働者派遣法の規定による派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容並びに
労働者派遣法第3章第4節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等関係法令の関係者への周知
の徹底を図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずること。
11個人情報等の保護
(1)個人情報の収集、保管及び使用
イ 派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者を登録する際には当該労働者の希望、能力及び
経験に応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣を
行う際には当該派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、派遣労働者等の個人情報
(以下この(1)、(2)及び(4)において単に「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲
げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な業務上の必要性が存在することその
他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限
りでないこと。
(イ)人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのあ
る事項
(ロ)思想及び信条
(ハ)労働組合への加入状況
口 派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本
人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。
- 266 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
ハ 派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新規卒業
予定者であって派遣労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局
長の定める書類によりその提出を求めること。
ニ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。このため、例えば、待遇等に関
する情報のうち個人情報に該当するものの保管又は使用は、労働者派遣法第30条の2、第30条
の3、第30条の4第1項、第30条の5及び第31条の2第4項の規定による待遇の確保等という
目的((4)において「待遇の確保等の目的」という。)の範囲に限られること。なお、派遣労働
者として雇用し労働者派遣を行う際には、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣
先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条第1項各号に掲げる
派遣先に通知しなければならない事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に
限られるものであること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場
合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでないこと。
(2)適正管理
イ 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を適切に講ずると
ともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。
(イ)個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
(ロ)個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
(ハ)正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
(ニ)収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置
口 派遣元事業主が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報
が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。
ハ 派遣元事業主は、次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規程を作成し、これを遵守しなけれ
ばならないこと。
(イ)個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項
(ロ)個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項
(ハ)本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取扱い
に関する事項
(ニ)個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項
二 派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に
対して不利益な取扱いをしてはならないこと。
(3)個人情報の保護に関する法律の遵守等
(1)及び(2)に定めるもののほか、派遣元事業主は、個人情報の保護に関する法律第2条第5項に
規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)に該当する場合には、同法
第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならないこと。また、個人情報取扱事業者に該当し
ない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めるこ
と。
(4)待遇等に関する情報のうち個人情報に該当しないものの保管及び使用
派遣元事業主は、待遇等に関する情報のうち個人情報に該当しないものの保管又は使用を待遇の
確保等の目的の範囲に限定する等適切に対応すること。
12 秘密の保持
待遇等に関する情報は、労働者派遣法第24条の4の秘密を守る義務の対象となるもの
であるこ と。
13 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等
(1)派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者を特定することを目的と
する行為に協力してはならないこと。なお、派遣労働者等が、自らの判断の下に派遣就業開始前の
事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは、派遣先によっ
て派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、
派遣元事業主は、派遣労働者等に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定
することを目的とする行為への協力の禁止に触れないよう十分留意すること。
(2)派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、職業安定法第3条の
規定を遵守するとともに、派遣労働者の性別を労働者派遣契約に記載し、かつ、これに基づき当該
派遣労働者を当該派遣先に派遣してはならないこと。
(3)派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣元事業主が当該
派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、障害者であることを理由として、障
害者を排除し、又はその条件を障害者に対してのみ不利なものとしてはならず、かつ、これに基づ
き障害者でない派遣労働者を当該派遣先に派遣してはならないこと。
14 安全衛生に係る措置
派遣元事業主は、派遣労働者に対する雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を適切に行える
よう、当該派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣先から入手すること、健康診断等の結果に基
づく就業上の措置を講ずるに当たって、派遣先の協力が必要な場合には、派遣先に対して、当該措置
の実施に協力するよう要請すること等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するため、派遣先と
必要な連絡調整等を行うこと。
15 紹介予定派遣
- 267 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
(1)紹介予定派遣を受け入れる期間
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行うに当たっては、6箇月を超えて、同一の派遣労働者の労働
者派遣を行わないこと。
(2)派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又
は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対
し、それぞれその理由を書面、ファクシミリ又は電子メールその他のその受信をする者を特定して
情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号
に規定する電気通信をいう。以下この(2)において「電子メール等」という。)(当該派遣元事業
主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)に
より明示するよう求めること。また、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面、フ
ァクシミリ又は電子メール等(当該派遣労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書
面を作成することができるものに限る。)(ファクシミリ又は電子メール等による場合にあって
は、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)により明示すること。
(3)派遣元事業主は、派遣先が障害者に対し、面接その他紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定する
ことを目的とする行為を行う場合に、障害者雇用促進法第36条の2又は第36条の3の規定による措
置を講ずるに当たっては、障害者と話合いを行い、派遣元事業主において実施可能な措置を検討す
るとともに、必要に応じ、派遣先と協議等を行い、協力を要請すること。
16 情報の提供
派遣元事業主は、派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者派
遣の実績、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を
当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(以下この16において「マージン率」と
いう。)、教育訓練に関する事項、労働者派遣法第30条の4第1項の協定を締結しているか否かの別
並びに当該協定を締結している場合における協定対象派遣労働者の範囲及び当該協定の有効期間の終
期(以下この16において「協定の締結の有無等」という。)等に関する情報を事業所への書類の備付
け、インターネットの利用その他の適切な方法により提供すること。特に、マージン率及び協定の締
結の有無等の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者とりわけ派遣労働
者に必要な情報を提供することを原則とすること。また、労働者派遣の期間の区分ごとの雇用安定措
置を講じた人数等の実績及び教育訓練計画については、インターネットの利用その他の適切な方法に
より関係者に対し情報提供することが望ましいこと。
- 268 -
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために
派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針
(平成20年厚生労働省告示第36号)
(最終改正 平成27年厚生労働省告示第395号)
第1 趣旨
この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法
律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第3章第1節から第3節までの規定により、派遣元事業主
が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示137号。以下「派遣元指針」という。)及び派遣先
が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号。以下「派遣先指針」という。)に加え
て、日雇労働者(労働者派遣法第35条の4第1項に規定する日雇労働者をいう。以下単に「日雇労働
者」という。)について労働者派遣を行う派遣元事業主及び当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の
提供を受ける派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定め
たものである。
第2 日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
1 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認
(1) 派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就業中の日雇派遣労働者(労働
者派遣の対象となる日雇労働者をいう。以下同じ。)を直接指揮命令することが見込まれる者か
ら、業務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準その他労働
者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件の内容を十分に確認すること。
(2) 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに際しては、派遣先が求める業務
の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準、労働者派遣の期間
その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件を事前にきめ細かに把握すること。
2 労働者派遣契約の期間の長期化
派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の期間を定めるに当たって
は、相互に協力しつつ、当該派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して可能
な限り長く定める等、日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をすること。
3 労働契約の締結に際して講ずべき措置
派遣元事業主は、労働者を日雇派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該日雇派遣労働者
が従事する業務が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令
(昭和61年政令第95号)第4条第1項各号に掲げる業務に該当するかどうか、又は当該日雇派遣労働
者が同条第2項各号に掲げる場合に該当するかどうかを確認すること。
4 労働契約の期間の長期化
派遣元事業主は、労働者を日雇派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該労働者の希望及
び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、労働契約の期間について、できるだけ長期
にする、当該期間を当該労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、日雇派遣労働者の
雇用の安定を図るために必要な配慮をすること。
5 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置
(1) 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除
を行おうとする場合には、派遣元事業主の合意を得ること。
(2) 派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に日雇派遣労働者の責に
帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、互いに連携して、
当該派遣先の関連会社での就業のあっせん等により、当該労働者派遣契約に係る日雇派遣労働者
の新たな就業機会の確保を図ること。
(3) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者
派遣契約の解除を行おうとする場合には、日雇派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることと
し、これができないときには、速やかに、損害の賠償を行わなければならないこと。その他派遣
先は、派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、派遣元事業
主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの
責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。
(4) 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行う場合であっ
て、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を当該派遣元事業
主に対し明らかにすること。
第3 労働者派遣契約に定める就業条件の確保
1 派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、日雇派遣労働者の就業の状況が労働者
派遣契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、日雇派遣労働者の適正な派遣就業の確
保のためにきめ細かな情報提供を行う等により派遣先との連絡調整を的確に行うこと。また、派遣元
事業主は、日雇派遣労働者からも就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していなかったことを確認
すること。
2 派遣先は、労働者派遣契約を円滑かつ的確に履行するため、次に掲げる措置その他派遣先の実態に
即した適切な措置を講ずること。
(1) 就業条件の周知徹底
労働者派遣契約で定められた就業条件について、当該日雇派遣労働者の業務の遂行を指揮命令
する職務上の地位にある者その他の関係者に当該就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場
- 269 -
第4
1
2
3
4
5
第5
1
2
第6
1
2
3
4
5
6
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
所に掲示する等により、周知の徹底を図ること。
(2) 就業場所の巡回
1の労働者派遣契約について少なくとも1回以上の頻度で定期的に日雇派遣労働者の就業場所
を巡回し、当該日雇派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していないことを確認
すること。
(3) 就業状況の報告
日雇派遣労働者を直接指揮命令する者から、1の労働者派遣契約について少なくとも1回以上
の頻度で定期的に当該日雇派遣労働者の就業の状況について報告を求めること。
(4) 労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導
日雇派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業
務上の指示を行わないようにすること等の指導を徹底すること。
労働・社会保険の適用の促進
日雇労働被保険者及び日雇特例被保険者に係る適切な手続
派遣元事業主は、日雇派遣労働者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第43条第1項に規定する
日雇労働被保険者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者
に該当し、日雇労働被保険者手帳又は日雇特例被保険者手帳の交付を受けている者(以下「手帳所持
者」という。)である場合には、印紙の貼付等の手続(以下「日雇手続」という。)を適切に行うこ
と。
労働・社会保険に係る適切な手続
派遣元事業主は、その雇用する日雇派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険に係る手
続を適切に進め、被保険者である旨の行政機関への届出(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第27条の2第1項各号に掲げる
書類の届出をいう。以下単に「届出」という。)が必要とされている場合には、当該届出を行ってか
ら労働者派遣を行うこと。ただし、当該届出が必要となる日雇派遣労働者について労働者派遣を行う
場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに当該届出を行うときは、この限りでないこと。
派遣先に対する通知
派遣元事業主は、労働者派遣法第35条第1項に基づき、派遣先に対し、日雇派遣労働者について届
出を行っているか否かを通知すること。さらに、派遣元事業主は、日雇派遣労働者が手帳所持者であ
る場合においては、派遣先に対し、日雇手続を行うか行えないかを通知すること。
届出又は日雇手続を行わない理由に関する派遣先及び日雇派遣労働者への通知
派遣元事業主は、日雇派遣労働者について届出を行っていない場合には、その具体的な理由を派遣
先及び当該日雇派遣労働者に対し、通知すること。さらに、派遣元事業主は、日雇派遣労働者が手帳
所持者である場合であって、日雇手続を行えないときには、その具体的な理由を派遣先及び当該日雇
派遣労働者に対し、通知すること。
派遣先による届出又は日雇手続の確認
派遣先は、派遣元事業主が届出又は日雇手続を行う必要がある日雇派遣労働者については、当該届
出を行った又は日雇手続を行う日雇派遣労働者(当該派遣先への労働者派遣の開始後速やかに当該届
出が行われるものを含む。)を受け入れるべきであり、派遣元事業主から日雇派遣労働者について当
該届出又は当該日雇手続を行わない理由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でないと考え
られる場合には、派遣元事業主に対し、当該日雇派遣労働者について当該届出を行ってから派遣する
よう又は当該日雇手続を行うよう求めること。
日雇派遣労働者に対する就業条件等の明示
派遣元事業主は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条に基づき、日雇派遣労働者との労働契
約の締結に際し、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、労働
時間に関する事項、賃金に関する事項(労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いを含む。)及び退
職に関する事項について、書面の交付による明示を確実に行うこと。また、その他の労働条件につい
ても、書面の交付により明示を行うよう努めること。
派遣元事業主は、モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)の活用等により、日雇派遣労
働者に対し労働者派遣法第34条に規定する就業条件等の明示を確実に行うこと。
教育訓練の機会の確保等
派遣元事業主は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)及び労働者派遣法第30条の4に基づ
き、日雇派遣労働者の職業能力の開発及び向上を図ること。
派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練に
ついては、派遣就業前に実施しなければならないこと。
派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務を効率的に遂行するために必要な能力を付与する
ための教育訓練を実施するよう努めること。
派遣元事業主は、2及び3に掲げる教育訓練以外の教育訓練については、日雇派遣労働者の職務の
内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、実施することが望ましいこと。
派遣元事業主は、日雇派遣労働者又は日雇派遣労働者として雇用しようとする労働者について、当
該労働者の適性、能力等を勘案して、最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、就業する期間
及び目、就業時間、就業場所、派遣先における就業環境等について当該労働者の希望と適合するよう
な就業機会を確保するよう努めること。
派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や日雇派遣労働者の自主的な能力開発等の日雇派遣労働者
- 270 -
第7
1
2
3 第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図る
よう努めること。
関係法令等の関係者への周知
派遣元事業主は、日雇派遣労働者を登録するためのホームページを設けている場合には、関係法令
等に関するコーナーを設けるなど、日雇派遣労働者となろうとする者に対する関係法令等の周知を徹
底すること。また、派遣元事業主は、登録説明会等を活用して、日雇派遣労働者となろうとする者に
対する関係法令等の周知を徹底すること。
派遣元事業主は、労働者派遣法の規定による派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容並びに
労働者派遣法第3章第4節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等関係法令について、派遣
先、日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書の配布等の措置を講ずること。
派遣先は、労働者派遣法の規定による派遣先が講ずべき措置の内容及び労働者派遣法第3章第4節
に規定する労働基準法等の適用に関する特例等関係法令について、日雇派遣労働者を直接指揮命令す
る者、日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書の配布等の措置を講ずること。
4 派遣先は、日雇派遣労働者の受入れに際し、日雇派遣労働者が利用できる派遣先の各種の福利厚生
に関する措置の内容についての説明、日雇派遣労働者が円滑かつ的確に就業するために必要な、日雇
派遣労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関係についての説明及び職場生
活上留意を要する事項についての助言等を行うこと。
第8 安全衛生に係る措置
1 派遣元事業主が講ずべき事項
(1) 派遣元事業主は、日雇派遣労働者に対して、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第
1項に規定する雇入れ時の安全衛生教育を確実に行わなければならないこと。その際、日雇派遣労
働者が従事する具体的な業務の内容について、派遣先から確実に聴取した上で、当該業務の内容に
即した安全衛生教育を行うこと。
(2) 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が労働安全衛生法第59条第3項に規定する危険有害業務に従
事する場合には、派遣先が同項に規定する危険有害業務就業時の安全衛生教育を確実に行ったかど
うか確認すること。
2 派遣先が講ずべき事項
(1) 派遣先は、派遣元事業主が日雇派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育を適切に行えるよ
う、日雇派遣労働者が従事する具体的な業務に係る情報を派遣元事業主に対し積極的に提供すると
ともに、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には可能な限りこ
れに応じるよう努める等、日雇派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配
慮を行うこと。
(2) 派遣先は、派遣元事業主が日雇派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育を確実に行ったか
どうか確認すること。
(3) 派遣先は、日雇派遣労働者の安全と健康の確保に責務を有することを十分に認識し、労働安全
衛生法第59条第3項に規定する危険有害業務就業時の安全衛生教育の適切な実施等必要な措置を確
実に行わなければならないこと。
第9 労働条件確保に係る措置
1 派遣元事業主は、日雇派遣労働者の労働条件の確保に当たっては、第5の1に掲げる労働条件の明
示のほか、特に次に掲げる事項に留意すること。
(1) 賃金の一部控除
派遣元事業主は、日雇派遣労働者の賃金について、その一部を控除する場合には、購買代金、
福利厚生施設の費用等事理明白なものについて適正な労使協定を締結した場合に限り認められる
ことに留意し、不適正な控除が行われないようにすること。
(2) 労働時間
派遣元事業主は、集合場所から就業場所への移動時間等であっても、日雇派遣労働者がその指
揮監督の下にあり、当該時間の自由利用が当該日雇派遣労働者に保障されていないため労働時間
に該当する場合には、労働時間を適正に把握し、賃金を支払うこと。
2 1に掲げる事項のほか、派遣元事業主及び派遣先は、日雇派遣労働者に関して、労働基準法等関係
法令を遵守すること。
第10 情報の提供
派遣元事業主は、日雇派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者
派遣の実績、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額
を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合、教育訓練に関する事項等に関する情
報を事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により提供すること。
第11 派遣元責任者及び派遣先責任者の連絡調整等
1 派遣元責任者は、日雇派遣労働者の就業に関し、労働者派遣法第36条に規定する派遣労働者に対す
る必要な助言及び指導等を十分に行うこと。
2 派遣元責任者及び派遣先責任者は、日雇派遣労働者の就業に関し、労働者派遣法第36条及び第41条
に規定する派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、派遣労働者の安全、衛生等に関する相互の連絡
調整等を十分に行うこと。
第12 派遣先への説明
派遣元事業主は、派遣先が日雇派遣労働者についてこの指針に定める必要な措置を講ずることができ
- 271-
第7 派遣元事業主の講ずべき措置等
るようにするため、派遣先に対し、労働者派遣契約の締結に際し、日雇派遣労働者を派遣することが
予定されている場合には、その旨を説明すること。また、派遣元事業主は、派遣先に対し、労働者派
遣をするに際し、日雇派遣労働者を派遣する場合には、その旨を説明すること。
第13 その他
日雇派遣労働者について労働者派遣を行う派遣元事業主及び当該派遣元事業主から労働者派遣の役務
の提供を受ける派遣先に対しても、派遣元指針及び派遣先指針は当然に適用されるものであることに
留意すること
- 272 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
第8 派遣先の講ずべき措置等
1 概要
労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令
を受けて労働に従事するという形態で事業が行われる。
このため、派遣労働者の保護を図るためには、現実の就業場所である派遣先において派遣労働者の
適正な就業が確保され、派遣労働者が派遣先で指揮命令を受けることに伴い生じた苦情等が適切かつ
迅速に処理されることが必要である。
また、このような雇用と使用が分離した形態であることに伴い、派遣先の正社員との常用代替が生
じやすいことから、有期雇用を中心とした不安定な雇用形態である派遣労働者との常用代替の防止を
図ることが求められる。
以上の観点から、派遣元事業主から労働者派遣を受けた派遣先は、次のような措置等を講じなけれ
ばならない。
① 労働者派遣契約に関する措置(法第39条)
② 適正な派遣就業の確保等のための措置(法第40条第1項)
③ 派遣先による均衡待遇の確保(法第40条第2項~第5項)
④ 派遣先の事業所単位の派遣期間の制限の適切な運用(法第40条の2)
⑤ 派遣労働者個人単位の期間制限の適切な運用(法第40条の3)
⑥ 派遣労働者の雇用の努力義務(法第40条の4)
⑦ 派遣先での常用労働者(いわゆる「正社員」)化の推進(法第40条の5)
⑧ 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止(法第40条の9)
⑨ 派遣先責任者の選任(法第41条)
⑲ 派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知(法第42条)
2 労働者派遣契約に関する措置
(1)概要
派遣先は、労働者派遣契約の定め(第6の2の(1)のイにおける定め)に反することのないよう
に適切な措置を講じなければならない(法第39条)。
(2)労働者派遣契約に定める就業条件の確保
派遣先は、労働者派遣契約を円滑かつ的確に履行するため、次に掲げる措置その他派遣先の実態
に即した適切な措置を講ずるものとする(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の2(第8
の19参照))。
イ 就業条件の周知徹底
労働者派遣契約で定められた就業条件について、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する
- 273 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
職務上の地位にある者その他の関係者に当該就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場所に
掲示する等により、周知の徹底を図ること。
ロ 就業場所の巡回
定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、当該派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に反
していないことを確認すること。
ハ 就業状況の報告
派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に当該派遣労働者の就業の状況について報告を
求めること。
ニ 労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導
派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上
の指示を行わないようにすること等の指導を徹底すること。
(3)労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等
派遣先は、労働者派遣契約の定めに反する事実を知った場合には、これを早急に是正するととも
に、労働者派遣契約の定めに反する行為を行った者及び派遣先責任者に対し労働者派遣契約を遵守
させるために必要な措置を講ずること、派遣元事業主と十分に協議した上で損害賠償等の善後処理
方策を講ずること等の適切な措置を講ずるものとする(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第
2の5(第8の19参照))。
(4)法第43条による準用
労働者派遣契約に関する措置は、派遣元事業主以外の事業主から労働者派遣の役務の提供を受け
る場合も適用される。
3 適正な派遣就業の確保
(1)概要
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受
けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接
な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない
(法第40条第1項)。
(2)苦情の適切な処理
イ 苦情の申出
派遣労働者から出される派遣先における苦情の申出(例えば、指揮命令の方法の改善、セクシ
ュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラスメント、育児休業、介護休業等に関するハラ
スメント、パワーハラスメント、障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障とな
っている事情に関するもの等)は、派遣先事業主、派遣労働者を直接指揮命令する者、派遣先責
任者に限らず派遣先や派遣先に代わって派遣労働者を管理する職務上の地位にある者が認識し得
るものであれば申出としての効果を持つものであり、その方法は、書面によると口頭によるとを
- 274 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
問うものではない。
ロ 苦情の内容の派遣元事業主への通知
苦情の申出を受けた場合は、当該苦情の内容を、遅滞なく、派遣元事業主に通知しなければな
らない。ただし、派遣先において、申出を受けた苦情の解決が容易であり、現実的にその苦情を
即時に処理してしまったような場合は、あえて派遣元事業主に通知するまでの必要はない。
ハ 苦情の処理の方法
(イ)派遣先が適切かつ迅速な処理を図るべきである苦情には、セクシュアルハラスメント、妊娠、
出産等に関するハラスメント、育児休業、介護休業等に関するハラスメント、パワーハラスメ
ント、障害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情に関するも
の等が含まれていることに留意しなければならない(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」
第2の7(1)(第8の19参照)、なお、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確
保等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律に関する適用の特例により派遣先の事業主が責任を負う規定については第9参照。)。
(ロ)派遣労働者の苦情が、派遣先の派遣労働者への対処方法のみに起因する場合は派遣先のみ
で解決が可能であるが、その原因が派遣元事業主にもある場合は、単独では解決を図ること
が困難であり、派遣元事業主と密接に連絡調整を行いっつ、その解決を図っていくことが必
要である。いずれの場合においても、中心となってその処理を行うのは派遣先責任者であり、
後者の場合にあっては、派遣先責任者が派遣元責任者と連絡調整を行いっつ、その解決を図
らなければならない。
(ハ)派遣先は、派遣労働者の苦情の処理を行うに当たっては、派遣先の労働組合法上の使用者
性に関する代表的な裁判例や中央労働委員会の命令の内容に留意する必要がある。
(ニ)派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施して、派遣労働者の苦情の申出を
受ける者、派遣先において苦情の処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携を図るた
めの体制等労働者派遣契約の内容について派遣労働者に説明するものとする(「派遣先の講
ずべき措置に関する指針」第2の7(第8の19参照))。
- 苦情の申出を理由とする不利益取扱いの禁止
派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱
いをすることは禁じられている(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の7(第8の19
参照))。この禁止される「不利益な取扱い」には、苦情の申出を理由として当該派遣労働者が
処理すべき業務量を増加させる等のような派遣労働者に対して直接行う不利益取扱いのほか、苦
情の申出を理由として派遣元事業主に対して派遣労働者の交代を求めたり、労働者派遣契約の更
新を行わない等の間接的に派遣労働者の不利益につながる行為も含まれるものである。
また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由とする労働者派遣契約の解除は、法第
27条に違反するものでもある(第6の3の(3)のハ参照)ので、これらについて十分に周知指導
を行うこと。
- 275 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
(3)適正な就業環境の確保
イ 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑
に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、(中略)等必要な措置を講ずるように配慮
しなければならない(法第40条第4項)。
ロ 適正な就業環境の確保
派遣先は、その指揮命令の下に労働させている派遣労働者について、派遣就業が適正かつ円滑
に行われるようにするため、セクシュアルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持の措置を
講ずるように配慮しなければならない(「派遣先の講ずべき措置に関する指針」第2の9の(1)
(第8の19参照))。
なお、配慮義務というのは、何らかの具体的な措置を講ずることを求めるものであるが、セク
シュアルハラスメントの防止については、派遣元事業主のほか、派遣先においても、男女雇用機
会均等法に基づく雇用管理上の配慮に関する義務を負っていることに留意が必要である。
ハ 派遣労働者に対する説明会等の実施
派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施し、派遣労働者が円滑かつ的確に就業
するために必要な派遣労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関係につ
いての説明及び職場生活上留意を要する事項についての助言等を行うこと(「派遣先が講ずべき
措置に関する指針」第2の12(第8の19参照))。
ニ 派遣元事業主との連絡体制の確立
派遣先は、派遣元事業主の事業場で締結される労働基準法第36条第1項の時間外及び休日の
労働に関する協定の内容等派遣労働者の労働時間の枠組みについて派遣元事業主に情報提供を求
める等により、派遣元事業主との連絡調整を的確に行うこと(「派遣先が講ずべき措置に関する
指針」第2の11(第8の19参照))。
(4)障害者である派遣労働者の適正な就業の確保
イ 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対する教育訓練及び福利厚生の実施に
ついて、派遣労働者が障害者であることを理由として、障害者でない派遣労働者と不当な差別的
取扱いをしてはならない(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の9の(4)①(第8の
19参照))。
ロ 派遣先は、労働者派遣契約に基づき派遣された労働者について、派遣元事業主が障害者雇用促
進法第36条の3の規定による措置を講ずるため、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣
元事業主と協議等を行い、可能な限り協力するよう努めなければならない(「派遣先が講ずべき
措置に関する指針」第2の9の(4)②(第8の19参照))。
(5)雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの労働者派遣の受け入れ
派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、当該解雇後3箇月以内に派遣
労働者を受け入れる場合には、必要最小限度の労働者派遣の期間を定めるとともに、当該派遣先に
雇用される労働者に対し労働者派遣の役務の提供を受ける理由を説明する等、適切な措置を講じ、
- 276 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
派遣先の労働者の理解が得られるよう努めること(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の
16(第8の19参照))。
この趣旨は、安易な雇用調整の結果、派遣を受け入れるということは許されるものでなく、雇用
調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣の受入れについては、特に慎重に判断すべ
きことにある。なお、労働者派遣の「臨時的・一時的」な労働力の適正・迅速な需給調整としての
位置づけを踏まえると、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣の受入れにつ
いては、解雇後3箇月以内かどうかにかかわりなく、慎重に対応することが適当であること。
また、派遣先が派遣労働者を受け入れたことによりその雇用する労働者を解雇することは、常用
代替そのものであり、派遣労働の利用の在り方として適当ではない。
(6)安全衛生に係る措置
派遣先は、派遣元事業主が雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を適切に行えるよう、派
遣労働者が従事する業務に係る情報提供を派遣元事業主に対し積極的に提供するとともに、派遣元
事業主から雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には可能な限
りこれに応じるよう努めること、派遣元事業主が健康診断等の結果に基づく就業上の措置を講ずる
に当たって、当該措置に協力するよう要請があった場合には、これに応じ、必要な協力を行うこと
等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと(「派遣先が
講ずべき措置に関する指針」第2の17(第8の19参照))。
派遣先が行うべき派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮として、
具体的には、以下に掲げるものがあること。
イ 安全衛生教育に係る協力や配慮
(イ)派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者に対する雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育
を適切に行えるよう、当該派遣労働者が従事する具体的な業務に係る情報を派遣元事業主に対
し積極的に提供するとともに、派遣元事業主から教育カリキュラムの作成支援等の依頼があっ
た場合には、可能な限りこれに応じるよう努めること。また、派遣先は、派遣労働者の受入れ
に当たり、派遣元事業主が行った雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育の実施結果を確
認すること。
なお、「派遣労働者が従事する業務に係る情報提供」の内容としては、例えば、派遣労働
者が派遣先で使用する機械・設備の種類・型式の詳細、作業内容の詳細、派遣先の事業場に
おける労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育を行う際に使用している教材、資料等が考え
られる。
(ロ)派遣先は、派遣元事業主から雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育の委託の申入れがあ
った場合には、可能な限りこれに応じるよう努めるとともに、当該申入れに応じ、安全衛生教育
を実施した場合には、その実施結果を派遣元事業主に報告すること。
(ハ)派遣先は、派遣労働者の作業内容を変更した場合における作業内容変更時の安全衛生教育を実
施したときは、その実施結果を派遣元事業主に報告すること。
- 277 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
口 危険有害業務に係る連絡調整等
派遣先は、派遣労働者が従事することが予定されている労働安全衛生法第59条第3項又は第61
条第1項に規定する業務に係る当該派遣労働者の資格等の有無を確認し、必要な資格等がない者が
これらの業務に従事することがないよう、派遣元事業主と連絡調整を行うこと。
ハ健康診断の実施後の就業上の措置等に係る連絡調整等
(イ)派遣先は、派遣元事業主が面接指導の実施又は健康診断の結果についての医師からの意見の聴
取を適切に行えるよう、派遣元事業主に当該派遣労働者の労働時間を通知するほか、派遣元事業
主から当該派遣労働者のその他の勤務の状況又は職場環境に関する情幸酎こついて提供の依頼があ
った場合には、必要な情報を提供すること。
(ロ)派遣先は、派遣元事業主が健康診断や面接指導、心理的な負担の程度を把握するための検査の
結果に基づく就業上の措置を講ずるに当たって、当該措置に協力するよう要請があった場合には、
これに応じ、必要な協力を行うこと。この場合において、派遣先は、派遣元事業主から就業上の
措置に関する協力の要請があったことを理由として、派遣労働者の変更を求めることその他の当
該派遣労働者に対する不利益な取扱いをしてはならないこと。
(ハ)派遣先は、特殊健康診断の結果に基づく就業上の措置を講ずるに当たっては、あらかじめ、就
業上の措置の内容について当該派遣労働者の意見を聴くよう努めるとともに、派遣元事業主と連
絡調整を行った上でこれを実施すること。また、派遣先は、就業上の措置を講じたときは、派遣
元事業主に対し、当該措置の内容に関する情報を提供すること。
ニ労働災害の再発防止対策に係る連絡調整等
派遣先は、派遣労働者に係る労働災害について労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署に提出し
た場合には、派遣元事業者に対し、遅滞なく、その写しを送付するとともに、当該労働災害の原因、
再発防止のための対策等について必要な情報を提供すること。
ホ派遣労働者の安全衛生に係る措置について
イから二までのほか、派遣先は、労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項に係る措置その
他の派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。
4 派遣先による均衡待遇の確保
(1)概要
派遣労働者と派遣先の労働者との均衡待遇を推進し、派遣労働者の処遇改善を図るのは一義的
には雇用主たる派遣元事業主であるが、実際は派遣先による対応がないと処遇の改善が進まない
ため、派遣先においても、教育訓練、福利厚生等に関し、必要な措置を講じるものとしている。
(2)教育訓練・能力開発
派遣先は、派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付すための教育訓練を行ってい
る場合は、これらの者と同種の業務に従事する派遣労働者に対しても、当該派遣労働者を雇用す
る派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場
- 278 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
合や派遣元事業主で同様の訓練を実施することが可能である場合を除き、当該訓練を実施する等
必要な措置を講じなければならない(法第40条第2項)。
本来、派遣労働者に対しては、雇用主である派遣元事業主が必要な教育訓練を行うべきである
が、派遣先の業務に密接に関連した教育訓練については、実際の就業場所である派遣先が実施す
ることが適当であり、また、実施可能な訓練も想定されるところである。実際、派遣労働者に対
する教育訓練が少なくなりがちという実情にもかんがみ、派遣先は、派遣元事業主からの求めに
応じて、派遣先の労働者と同様の訓練を実施する等必要な措置を講ずる義務を課したものである。
なお、派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者に対し段階的かつ体系的な教育訓練を実施するに
当たって、求めがあったときは、派遣元事業主と協議等を行い、当該派遣労働者が当該教育訓練
を受けられるよう可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めな
ければならない。派遣元事業主が行うその他の教育訓練や派遣労働者の自主的な能力開発等につ
いても同様である(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の9(3))。
(3)福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)
派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設のうち、給
食施設、休憩室、更衣室については、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用
の機会を与えなければならない(法第40条第3項)。
食堂、休憩室、更衣室は、業務の円滑な遂行に資する施設であり、派遣労働者と派遣先の労働者
で別の取扱いをすることは適当でないことから、同様の取扱いをする義務を派遣先に課すこととし
たものである。
(4)福利厚生((3)の施設を除く。)
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に
行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所等の施設であって現に当該派遣先に雇用
される労働者が通常利用しているもの(4(3)の施設を除く。)の利用に関する便宜の供与等必要
な措置を講ずるように配慮しなければならない(法第40条第4項)。
「診療所等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの」とは、
派遣先が設置及び運営し、その雇用する労働者が通常利用している物品販売所、病院、診療所、浴
場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設をいうこと
(「派遣先の講ずべき措置に関する指針」第2の9の(1)(第8の19参照))。なお、配慮義務
というのは、何らかの具体的な措置を講ずることを求めるものであるが、派遣先の労働者と同様の
取扱いをすることが困難な場合まで当該取扱いを求めるものではなく、例えば、定員の関係で派遣
先の労働者と同じ時間帯に診療所の利用を行わせることが困難であれば別の時間帯に設定する等の
措置を行うことにより配慮義務を尽くしたと解される。
(5)派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の職務遂行状況等の情報について提供する配慮義務
イ 派遣先は、派遣元事業主において段階的かつ体系的な教育訓練やキャリアコンサルティング、
派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保のための措置、一定の要件を満たす労使協
- 279 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
定に基づく待遇の確保のための措置、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及
び理由等の説明が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、派遣先の労働
者に関する情報や、派遣先の指揮命令の下に労働させる派遣労働者の業務の遂行の状況等の情報
を派遣元事業主に提供する等必要な協力をするように配慮しなければならない。「業務の遂行の
状況」とは、仕事の処理速度や目標の達成度合いに関する情報を指し、派遣先の能力評価の基準
や様式により示されたもので足りる。
ロ 特に、派遣先の労働者に関する情報のうち、派遣先の通常の労働者と第6の2の(3)のハの(イ)
の⑤の比較対象労働者との間で均衡待遇が確保されている根拠又は派遣先の通常の労働者と第6
の2の(3)のハの(イ)の⑥の比較対象労働者との間で適切な待遇が確保されている根拠について、
派遣元事業主から求めがあった場合には、派遣先は、派遣元事業主による派遣労働者の均等・均
衡待遇の確保や比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等の説明が適切になされるよ
うにするため、それぞれの根拠について情報提供することが求められることに留意すること。
ハ 派遣元事業主が派遣労働者の職務能力の評価を行う場合には、当該情報のみならず、派遣元事
業主が自ら収集した情幸酎こ基づき評価を行うことが必要である。
(6)派遣先が業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施せず、又は福利厚生施設(給
食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会を付与しない場合の取扱い
厚生労働大臣は、派遣先が派遣元事業主の求めに応じて業務の遂行に必要な能力を付与するため
の教育訓練を実施しない場合若しくは福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会を
付与しない場合又はこれらの場合に当該派遣先に対して法第48条第1項の規定による指導若しく
は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がその指導等に従わなかった場合等には、当該派遣先に
対し、当該派遣就業を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる(法第
49条の2第1項)。
また、厚生労働大臣は、当該勧告を行った場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなか
った場合には、その旨を公表することができる(法第49条の2第2項)。
5 派遣先の事業所単位の期間制限の適切な運用
(1)概要
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「派遣先の事業所等」という。)ご
との業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して有期雇用の者に係る労働
者派遣の役務の提供を受けてはならない(法第40条の2)。
(2)意義
派遣労働者については、その雇用の安定やキャリア形成が図られにくい面があることから、派遣
就業を臨時的・一時的な働き方として位置づけることを原則とするとともに、派遣先の常用労働者
(いわゆる「正社員」)との代替が生じないよう、労働者派遣の利用を臨時的・一時的なものに限
ることを原則としている。
- 280 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
このうち常用労働者との代替を防止する観点及び派遣労働者の派遣就業への望まない固定化の防
止の観点から、派遣先の事業所等ごとの業務における有期雇用派遣の受入れについて原則3年まで
とする事業所単位の期間制限が設けられている。
なお、この常用代替防止は、派遣労働者が現に派遣先で就労している常用労働者を代替すること
を防止するだけでなく、派遣先の常用労働者の雇用の機会が不当に狭められることを防止すること
も含むものである。また、特に、派遣先が派遣労働者を受け入れたことによりその雇用する労働者
を解雇することは常用代替そのものであり、派遣労働者の利用の在り方として適当でないことに留
意すること。
(3)派遣可能期間の考え方
イ 派遣先は、次の(力から⑥までの場合を除いて、当該派遣先の事業所等ごとの業務について、派
遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
(力 労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用労働者の場合
② 労働者派遣に係る派遣労働者が60歳以上の者である場合
③ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了すること
が予定されているもの(「有期プロジェクト業務」第40条の2第1項第3号イ)について労
働者派遣の役務の提供を受ける場合
なお、「一定の期間内」とは、特に年数を定めるものではないが、終期が明確でなければな
らない。
④ 派遣労働者の従事する業務が1箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用
される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、月10 日以下で
ある業務(「日数限定業務」第40条の2第1項第3号ロ)について労働者派遣の役務の提供
を受ける場合
(i)「通常の労働者」の所定労働日数とは、原則として、派遣先のいわゆる正規の従業員(常
用雇用的な長期勤続を前提として雇用される者)の所定労働日数が該当する。
ただし、当該派遣先の正規の従業員の方が少数である場合には、派遣先の事業所等に、主
として従事する労働者の所定労働日数を、「通常の労働者」の所定労働日数とする。
したがって、例えば、正規の従業員が約2割の場外馬券売場の事業場で、所定労働日数が
月8日の有期雇用の労働者が主として従事する馬券販売の担当部門において、日数限定業務
として派遣可能期間の制限なしに労働者派遣を受けようとする場合には、「通常の労働者」
の所定労働日数は、月8日となる。
(の「相当程度少なく」とは半分以下である場合をいう。したがって、例えば、通常の労働者
の所定労働日数が月20日の場合には、月10日以下しか行われない場合が対象となる。
(の日数限定業務に該当するためには、その業務が、通常の労働者の1箇月間の所定労働日数
の半分以下、かつ、月10日以下しか行われない業務であることが必要である。
したがって、「通常の労働者の1箇月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10 日以下」
- 281-
第8 派遣先の講ずべき措置等
を超える日数行われている業務を分割又は集約し、その一部を「通常の労働者の1箇月間の
所定労働日数の半分以下、かつ、月10 日以下」となる範囲において派遣労働者に従事させ、
他の日は派遣先に雇用されている従業員のみで対応するような場合は、日数限定業務には該
当せず、期間制限の適用を受けることとなる。(例えば月15 日発生する業務について分割
し、月10 日間を派遣労働者に従事させ、残りの月5日間を派遣先に雇用されている従業員
に行わせるような場合は、その業務は月15 日間行われていることから、日数限定業務に当
たらない。)また、「通常の労働者の1箇月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10 日
以下」を超える日数行われている業務について、繁忙対策として、業務量の多い日のみ派遣
先に雇用されている従業員に加え派遣労働者にも従事させるような場合も、日数限定業務に
は該当せず、期間制限の適用を受けることとなる。
(k)なお、日数限定業務に該当する業務としては、例えば、書店の棚卸し業務や、土日のみに
行われる住宅展示場のコンパニオンの業務が想定される。
⑤ 産前産後休業及び育児休業、並びに産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後
続する休業であって、母性保護又は子の養育をするための休業をする場合における当該労働者
の業務(法第40条の2第1項第4号)について労働者派遣の役務の提供を受ける場合
⑥ 介護休業及び介護休業に後続する休業であって、育児・介護休業法第2条第4号に規定する
対象家族を介護するためにする休業をする場合における当該労働者の業務(法第40条の2第
1項第5号)について労働者派遣の役務の提供を受ける場合
なお、⑤及び⑥の業務については、休業に入る労働者が従事していた業務を、休業に入る前
に派遣労働者に対して引継ぎを行う場合及び当該業務に従事していた派遣労働者が、休業を終
えて当該業務に復帰する労働者に対して引継ぎを行う場合は、当該時間が必要最小限のもので
ある限り、⑤及び⑥の場合に含めて差し支えない。
ロ 「事業所等」については、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立
していること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立
性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して
判断する。
ハ 事業所とは、雇用保険法等雇用関係法令における概念と同様のものであり、出張所、支所等で、
規模が小さく、その上部機関等との組織的関連ないし事務能力からみて一の事業所という程度の
独立性がないものについては、直近上位の組織に包括して全体を一の事業所として取り扱う。そ
の他派遣就業の場所とは、事業を行っていない者が派遣先となる場合に当該労働者派遣の役務の
提供を受ける場所を指し、例えば、個人宅が派遣先になる場合は当該家庭(居宅)を、大学の研
究室が派遣先になる場合は、当該研究室を指す。
ニ 労働者派遣の役務((3)のイの(力から⑥までの場合を除く。以下において同じ。)の提供を受
けていた派遣先の事業所等が新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合に、当該新たな労働者
派遣と当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣との間の期間が
- 282 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
3箇月を超えないときは、当該派遣先の事業所等は、当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直
前に受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなす。
派遣先において継続して労働者派遣の役務の提供を受けている期間の判断は、継続していると
判断される最初の労働者派遣契約の始期から最後の労働者派遣契約の終期までの期間により行う。
(4)派遣可能期間の延長等
イ 派遣可能期間は、3年とする(法第40条の2第2項)。
ロ 派遣先は当該派遣先の事業所等ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続
して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所等ごとの業務に係る
労働者派遣の役務の提供が開始された日から事業所単位の期間制限の抵触日の1箇月前の日まで
の間(意見聴取期間)に、以下の手続を行うことにより、3年以内の期間であれば派遣可能期間
を延長することができる。また、延長した期間が経過した場合にこれを更に延長しようとすると
きも、同様の手続による(法第40条の2第3項)。
なお、派遣労働の利用は臨時的・一時的なものが原則であることから、その利用は3年以内が
原則であることに留意すること。
特に、派遣先が派遣可能期間の延長の是非を判断するに当たっては、必ずハに定める過半数労
働組合等からの意見聴取を実施し、この原則を尊重するべきであることを周知徹底すること。
ハ 派遣先は派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、当該派遣先の事業所に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合(以下「過半数労働組合」
という。)、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表す
る者(以下「過半数代表者」という。)の意見を聴かなければならない(法第40条の2第4
項)。
派遣先が過半数労働組合又は過半数代表者(以下「過半数労働組合等」という。)の意見を聴
くことで派遣可能期間を延長できるとする趣旨は、派遣労働者の受入を一律に制限するのではな
く、現場の実状等をよく把握している労使の判断に委ねることにする点にあることから、派遣先
の使用者と過半数労働組合等はお互いの意見を尊重し、実質的な話合いが行われることが期待さ
れる。また、使用者が行うべき説明等の内容は、労使のコミュニケーションを通じて明確化され
るべきものであり、意見聴取の際の説明は法律上の義務ではないが、過半数労働組合等から質問
があれば説明を行うことが期待される。さらに、最初の派遣労働者の受入れに当たっては、過半
数労働組合等にその受入れの考え方を説明することが望ましい。
このような趣旨や以下に掲げる内容を十分に踏まえ、意見聴取が確実に行われるよう、また意
見が尊重されるよう、関係者に対する十分な周知及び指導を行うこと。
ニ 意見聴取は、次の手続によらなければならない。
(イ)意見聴取の際に、過半数労働組合等に次に掲げる事項を書面により通知すること(則第33
条の3第1項)。
(力 労働者派遣の役務の提供を受けようとする事業所その他派遣就業の場所
- 283 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
② 延長しようとする派遣期間
また、派遣先は、過半数労働組合等に対し、派遣可能期間を延長しようとする際に意見を聴
くに当たっては、派遣先の事業所等の業務について、当該業務に係る労働者派遣の役務の提供
の開始時(派遣可能期間を延長した場合は、当該延長時)から当該業務に従事した派遣労働者
の数及び期間を定めないで雇用する労働者(正社員)の数の推移に関する資料等、意見聴取の
参考となる資料も過半数労働組合等に提供すること。また、派遣先は、意見聴取の実効性を高
める観点から、過半数労働組合等からの求めに応じ、部署ごとの派遣労働者の数、各々の派遣
労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた期間等に係る情報を提供することが望ましい。
(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の15(1))
(ロ)過半数代表者は、以下のいずれにも該当する者とすること(則第33条の3第2項)。
① 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
② 派遣可能期間の延長に係る意見を聴取される者を選出する目的であることを明らかにして
実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、派遣先の意向に基
づき選出されたものでないこと。
なお、「投票、挙手等」の方法としては、「投票、挙手」のほか、労働者の話合い、持ち
回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該
当する。
ただし、①に該当する者がいない事業所にあっては、②に該当する者とすること(則第33
条の3第2項)。
また、派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこ
と又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないように
しなければならない(則第33条の5)。
意見を聴取した過半数代表者が、使用者の指名等の民主的な方法により選出されたものでは
ない場合、派遣先の意向に基づき選出された場合、派遣可能期間の延長手続のための代表者選
出であることを明らかにせずに選出された場合、管理監督者である場合については、事実意見
聴取が行われていないものと同視できることから、労働契約申込みみなし制度(平成27年10
月1日より施行)の適用があることに留意すること。
また、派遣先は、過半数代表者が意見の聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよ
う必要な配慮を行わなければならない(則第33条の3第5項)。この「必要な配慮」には、
例えば、過半数代表者が労働者の意見集約等を行うに当たって必要となる事務機器(イントラ
ネットや社内メールを含む。)や事務スペースの提供を行うことが含まれるものである。
(ハ)派遣先は、派遣可能期間を延長するに当たっては、次に掲げる事項を書面に記載し、事業
所単位の期間制限の抵触日から3年間保存しなければならない(則第33条の3第3項)。
(力(イ)により、意見を聴取した過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名
※過半数代表者の場合は選出方法についても併せて記載することが望ましい。
- 284 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
②(イ)により過半数労働組合等に通知した事項及び通知した日
③ 過半数労働組合等から意見を聴いた日及び当該意見の内容
④ 意見を聴いて、(イ)の②の延長しようとする派遣可能期間を変更したときは、その変更し
た派遣可能期間
なお、電磁的記録により当該書面の作成を行う場合は、電子計算機に備えられたファイル
に記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
また、電磁的記録により当該書面の保存を行う場合は、次のいずれかの方法によって行った
上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然と
した形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなけ
ればならない。
a 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって
調製するファイルにより保存する方法
b 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読
み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもっ
て調製するファイルにより保存する方法
派遣先が意見聴取の過程及び結果並びに対応方針等の説明の内容について故意に記録を記録
せず又は記録を破棄した場合、意見聴取に当たり合理的な意見表明が可能となるような資料が
派遣先から捏供されない場合等については、延長手続を困難にすることから、厳正な対処が行
われるべきであること。
(ニ)派遣可能期間を延長するに当たっては、(ハ)(力~④の事項を次に掲げるいずれかの方法に
よって、当該事業所の労働者に周知しなければならない。(則第33条の3第4項)
(力 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
② 書面を労働者に交付すること。
③ 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準じる物に記録し、かつ、
各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
ホ 派遣先は、派遣可能期間の延長について意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたとき
は、事業所単位の期間制限の抵触日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、
(イ)延長しようとする期間及びその理由
(ロ)過半数労働組合等の異議(常用代替に関する意見に限る。)への対応に関する方針を説明
しなければならない(法第40条の2第5項、則第33条の4第1項)。
また、派遣先は、過半数労働組合等に説明した日及び説明した内容を書面に記載し、事業所
単位の期間制限の抵触日から3年間保存しなければならず、書面に記載した事項を(4)のこの
(ニ)の①~③の方法によって、当該事業所等の労働者に周知しなければならない(則第33条
の4第2項及び第3項)。
なお、過半数労働組合等の異議への対応に関する方針等の説明は、労使自治の考え方に基づ
- 285 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
く実質的な話合いができる仕組みの構築が目的であることに留意すること。
異議とは、派遣可能期間を延長することに反対する旨の意見のみならず、延長する期間を短
縮する旨の意見や、例えば今回限り延長を認めるといった意見や、受入派遣労働者数を減らす
ことを前提に延長を認めるといった条件付き賛成の旨の意見も含まれる。
派遣先は、過半数労働組合等から、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が適当で
ない旨の意見を受けた場合には、当該意見に対する派遣先の考え方を過半数労働組合等に説明
すること、当該意見を勘案して労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間について再検討
を加えること等により、過半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めるものとすること。
異議への対応に関する方針とは、例えば、派遣可能期間を延長しないことや、提示した延長す
る期間を短縮すること等を指す。
また、派遣先は、派遣可能期間を延長する際に過半数労働組合等から異議があった場合にお
いて、当該延長に係る期間が経過した場合にこれを更に延長しようとするに当たり、再度、過
半数労働組合等から異議があったときには、当該意見を十分に尊重し、派遣可能期間の延長の
中止又は延長する期間の短縮、延長しようとする派遣労働者の数の減少等の対応を採ることに
ついて検討した上で、その結論をより一層丁寧に過半数労働組合等に説明しなければならない。
なお、派遣先は派遣可能期間を延長しようとする場合の過半数労働組合等からの意見の聴取
及び過半数労働組合等が異議を述べた場合の当該過半数労働組合等に対する派遣可能期間の延
長の理由等の説明を行うにあたっては、誠実にこれらを行うよう努めなければならない。
へ その他
(イ)意見聴取は、派遣を受け入れようとする者の事業所等ごとに行う必要がある。
(ロ)派遣先は過半数労働組合等から(イ)の意見を聴くに当たっては、実際に意見の取りまとめに要
する期間を過半数労働組合等に確認する等十分な考慮期間を設けること。意見聴取を行う時期
については、意見聴取期間内であれば問題はないが、意見聴取の趣旨が常用代替が生じていな
いかの判断を現場の労使が行うことにある点にかんがみると、労働者派遣の役務の提供の受入
開始に接近した時点よりも、ある程度の期間経過した後の方が望ましい。
(ハ)なお、意見聴取に当たっては、派遣先は、意見聴取期間内であれば、過半数労働組合等の意
見の提出に際して期限を付することが可能である。また、当該期限までに意見がない場合には
意見がないものとみなす旨を過半数労働組合等に事前に通知した場合には、そのように取り扱
って差し支えない。ただし、この場合であっても、過半数労働組合等に十分な考慮期間を設け
ること。
(ニ)派遣を受け入れる前に意見聴取をすることや、複数回分の意見聴取をまとめて一度の意見聴
取で3年を超える期間延長することはできない。
(ホ)派遣期間を延長する際には、意見聴取が必要であることから、新たな業務において派遣労働
者を受け入れる際に、派遣期間を延長する可能性がある場合は、その受入の考え方について
過半数労働組合等に説明することが望ましい。
- 286 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
(5)派遣先の事業所単位の期間制限の適切な運用のための留意点
イ 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、(3)のイの(力から⑥までに掲げる場合以外に
ついて派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとす
るときは、第6の労働者派遣契約の締結に当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該
労働者派遣に係る事業所単位の期間制限の抵触日を通知しなければならない。また、派遣元事業
主は、当該通知がないときは、当該者との間で、労働者派遣契約を締結してはならない(第6の
2の(2)参照)。
ロ また、派遣先は、派遣可能期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事
業主に対し、延長後の事業所単位の期間制限に抵触する日を通知しなければならない(法第40
条の2第7項)。
ハ なお、イ及びロの通知については、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から派遣元事
業主に対して、通知すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は
電子メール等の送信をすることにより行わなければならない(則第24条の2)が、イ又はロの
通知である旨が明確になっていれば、他の連絡等と併せて一葉の書面等で通知することとしても
差し支えない。
ニ これらの規定は、労働者派遣契約に基づき労働者派遣を行う派遣元事業主及び当該労働者派遣
の役務の提供を受ける者の双方が、派遣可能期間の制限の規定を遵守できるようにすることを目
的としているものである。
ホ 派遣先は、派遣可能期間の延長に係る意見聴取の手続を回避することを目的として、当該労働
者派遣の終了後3箇月が経過した後に再度当該労働者派遣の役務の提供を受けるような、実質的
に派遣労働者の役務の受入れを継続する行為は、法の趣旨に反するものである。
6 派遣労働者個人単位の期間制限の適切な運用
(1)概要
派遣先は、派遣先の事業所等における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して
同一の有期雇用の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない(法第40条の
3)。
(2)意義
前述のとおり、派遣労働については、その雇用の安定やキャリア形成が図られにくい面があるこ
とから、派遣労働の利用を臨時的・一時的なものに限ることを原則とするとともに、派遣労働を臨
時的・一時的な働き方として位置づけることを原則としている。
このような観点及び派遣労働者の派遣就業への望まない固定化の防止の確保を図る観点から、
特に雇用安定等の観点で課題がある有期雇用の派遣労働者については、課などの同一の組織単位
における継続的な受入れを3年までとする個人単位の期間制限を設けることとしたものである。
つまり、有期雇用派遣労働者について、節目節目でキャリアを見つめ直し、キャリアアップの契
- 287 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
機とすることで派遣労働への固定化の防止を図るものである。
(3)期間制限の考え方
5(3)イの場合を除き、派遣先の事業所単位の期間制限が延長された場合であっても、事業所
等における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣
労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
事業所等における組織単位については、法第40条の3の期間制限の目的が、派遣労働者がその
組織単位の業務に長期にわたって従事することによって派遣就業に望まずに固定化されることを防
止することであることに留意しつつ判断することになる。具体的には、課、グループ等の業務とし
ての類似性や関連性がある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督
権限を有するものであって、派遣先における組織の最小単位よりも一般に大きな単位を想定してい
るが、名称にとらわれることなく実態により判断すべきものである。
ただし、小規模の事業所等においては、組織単位と組織の最小単位が一致する場合もあることに
留意する必要がある。
(4)その他
イ 労働者派遣期間の継続性の考え方
(イ)同一の派遣労働者について、派遣先の同一の組織単位における就業の日と次回の就業の日
との間の期間が3箇月以下であれば、派遣先は、事業所等における組織単位ごとの業務につ
いて、継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなす。
この場合、同一の派遣労働者について、派遣元事業主が異なる場合であっても同一の派遣労
働者と評価されることに留意すること。派遣先は、派遣労働者個人単位の期間制限に違反す
ることをもって、派遣元事業主に対し、派遣労働者の交代を要求することができる。
(ロ)派遣先は、派遣先の事業所等における業務について派遣元事業主から3年間を超える期間
継続して労働者派遣(5(3)イ(力から⑥までのいずれかに該当する場合を除く。)の役務の提
供を受けようとする場合において、派遣可能期間の延長に係る手続を回避することを目的とし
て、当該労働者派遣の終了後3箇月が経過した後に、再度当該派遣労働者の役務の提供を受け
ることは、趣旨に反するものであること。
ロ 派遣労働者個人単位の期間制限の延長はできない。
7 期問制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い
(1)概要
厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、過半数労働組合等からの意見聴取を
せずに事業所単位の期間制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けている場合、意見聴取をし
た際に過半数労働組合等が異議を述べたにもかかわらず説明義務を果たさなかった場合、派遣労
働者個人単位の期間制限を超えて同一の組織単位において同一の派遣労働者から労働者派遣の役
務の提供を受けている場合、法第48条第1項の規定による指導又は助言をしたにもかかわらず、
- 288 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
その者がその指導等に従わなかった場合等には、当該者に対し、当該派遣就業を是正するために
必要な措置をとるべきことを勧告することができる(法第49条の2第1項)。
厚生労働大臣はこれらの勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかった
ときは、その旨を公表することができる(法第49条の2第2項、第13の3参照)。
(2)勧告、公表の内容
勧告に従わなかったときの公表の際には、企業名及び所在地、事業所名及び所在地並びに指導、
助言、勧告及び公表の経緯について公表する。
(3)権限の委任
勧告に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働
大臣が自らその権限を行うことは妨げられない。
(4)勧告、公表の手続
(イ)勧告の決定は厚生労働大臣又は都道府県労働局長が行う。公表の決定は厚生労働大臣が行う。
なお、最終的に勧告については、文書により期限を設けて行う。
また、当該勧告に従わない場合は、その旨を公表することがある旨を記載する。また、併せ
て公表方法を示すものとする。
(ロ)また、勧告から原則として1箇月以内に公表すべく手続をとる。公表の方法は、(2)の内容
からなる資料を作成し、新聞発表することによる。
(ハ)なお、上記の目的はあくまで派遣労働者の雇用の安定を図ることであることに鑑み、個別
の事案に即して弾力的な対応を図ること。
(5)労働契約申込みみなし制度
労働者派遣の役務の提供を受ける者が、過半数労働組合等からの意見聴取をせずに事業所単位
の期間制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けている場合(5(4)二(イ)、(ハ)及び(ニ)の場
合を除く。)及び派遣労働者個人単位の期間制限を超えて同一の組織単位において同一の派遣労
働者から労働者派遣の役務の提供を受けている場合には、当該労働者派遣の役務の提供を受ける
者から当該派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条
件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる(法第40条の6)。
なお、派遣先は、労働契約申込みみなし制度の下で、有期の労働契約が成立した後に当該契約
を更新することについては、当該労働者の意向を踏まえっっ、派遣元事業主と締結されていた労
働契約の状況等を考慮し真撃に検討すべきものである。
8 特定有期雇用派遣労働者の雇用
(1)概要
派遣先は、派遣元事業主から雇用安定措置として特定有期雇用派遣労働者への直接雇用の依頼を
受けた場合において、引き続き当該特定有期雇用派遣労働者が従事していた業務に労働者を従事さ
せるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間が経過した日以後労働者を雇い入れようとす
- 289 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
るときは、当該直接雇用の依頼の対象となった特定有期派遣労働者であって、継続して就業するこ
とを希望している者を遅滞なく雇い入れるよう努めなければならない(法第40条の4)。
また、当該直接雇用の依頼の対象となった特定有期雇用派遣労働者であって、継続して就業する
ことを希望している者のうち、派遣先の同一の組織単位において継続して3年間就業する見込みが
ある者に対しては、当該派遣先における求人情報を提供しなければならない(法第40条の5第2
項)。
(2)意義
派遣労働への固定化防止の観点から派遣労働者個人単位の期間制限を設けているが、これにより
派遣期間の上限等に達した派遣労働者については派遣先を失うことにより失職するおそれがある。
このため雇用安定措置を設けているが、派遣労働者の中には、正社員等での直接雇用を希望しつつ
も、やむを得ず派遣就労に従事している者も存在していることから、雇用安定措置として派遣元事
業主から直接雇用の依頼があったときは、派遣先も可能な限り雇用する等の責務を課すこととした
ものである。
また、同一の組織単位において3年間継続就労した派遣労働者については、直接雇用の希望がよ
りかなえられるよう、上記の措置に加えて派遣先における直接雇用に係る募集情報を提供すること
としたものである。
(3)優先雇用の努力義務
派遣先は、以下の(力から③までをすべて満たす場合、受け入れている特定有期雇用派遣労働者を
遅滞なく、雇い入れるよう努めなければならない。(法第40条の4)
① 派遣先の事業所等の組織単位ごとの同一の業務について1年以上継続して有期雇用派遣労働者
(特定有期雇用派遣労働者)が派遣労働に従事したこと
② 引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため当該派遣の受入れ期間以後労働者を雇い入
れようとすること
③ 当該特定有期雇用派遣労働者について派遣元事業主から法に定める雇用安定措置の一つとして
直接雇用の依頼があったこと
(4)労働者募集情報の提供
派遣先は、一定の要件を満たした特定有期雇用派遣労働者について当該事業所における募集情報
を提供する義務が課せられるがその具体的な要件は以下のとおり。(第40条の5第2項)
イ 対象となる特定有期雇用派遣労働者
以下の(力及び②を満たす者である。
① 派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して3年間派遣就労する見込み
のある特定有期雇用派遣労働者
② 当該特定有期雇用派遣労働者について派遣元事業主から法に定める雇用安定措置の一つとして
直接雇用の依頼があったこと
ロ 派遣先が講ずる措置
- 290 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
当該特定有期雇用派遣労働者が就労している事業所等において労働者の募集を行うときは、当該募
集を行う事業所等にその者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を
掲示すること等により当該派遣労働者に周知すること
この募集情幸田ま、正規雇用労働者に関するもののみならずパートタイム労働者、契約社員など当該
事業所等において労働に従事する直接雇用の労働者に関するものである。ただし、特殊な資格を必要
とするなど当該有期雇用派遣労働者が募集条件に該当しないことが明らかな場合まで周知が必要とな
るものではない。
周知の方法としては、事業所の掲示板に求人票を貼り出すこと、直接メール等で通知すること等の
ほか、派遣先から派遣元事業主に募集情報を提供し、当該派遣元事業主を通じて当該特定有期雇用派
遣労働者に周知することとしても差し支えない。また、派遣元を通じずに募集情報を提供した際には、
提供したことを派遣元にも情報提供することが望ましい。
周知した事項の内容については、派遣先において記録及び保存をすることが望ましい。
9 派遣先での正社員化の推進
(1)概要
派遣先は、当該派遣先の事業所等において1年以上就業している派遣労働者について、当該事
業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集
に係る事業所等に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従事すべき業務の内
容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない
(法第40条の5第1項)。
(2)意義
派遣労働者の中には、いわゆる正社員での直接雇用を希望しつつも、やむを得ず派遣就労に
従事している者も存在していることから、これらの者について正社員として雇用される可能性
の機会をできるだけ提供しようとするものである。
(3)具体的な措置の内容
派遣先は、受け入れている一定の派遣労働者について通常の労働者の募集情報を提供しなけれ
ばならないこととされているが、その対象者と措置の内容は以下のとおり。
イ 対象となる派遣労働者
(イ)派遣先の同一の事業所等において1年以上の期間継続して就労している派遣労働者
(ロ) この派遣労働者は、有期雇用派遣労働者に限らず、無期雇用派遣労働者も含まれる。
(ハ) 同一の事業所等において1年以上の継続勤務があれば対象となり、これには途中で事業所内
の組織単位を異動した場合も含まれる。
ロ 講ずべき措置
(イ)当該事業所等において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときに、当該募集に係る情
報を当該派遣労働者に周知すること。
- 291-
第8 派遣先の講ずべき措置等
(ロ)「通常の労働者」とは、派遣先のいわゆる正規雇用労働者(常用雇用的な長期勤続を前提と
して雇用される者)を言う。
※ 有期雇用は含まない。
(ハ)当該募集に係る情幸田ま、新卒の学生を対象とした全国転勤の総合職の求人情報など当該派遣
労働者に応募資格がないことが明白である場合は周知する必要はない。
(ニ) 周知の方法としては、事業所の掲示板に求人票を貼り出すこと、直接メール等で通知する
こと等のほか、派遣先から派遣元事業主に募集情報を提供し、当該派遣元事業主を通じて当
該派遣労働者に周知することとしても差し支えない。また、派遣元を通じずに募集情報を提
供した際には、提供したことを派遣元にも情報提供することが望ましい。
(ホ) 周知した事項の内容については、派遣先において記録及び保存をすることが望ましい。
10 離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止
(1)概要
イ 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派
遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日
までの間は、当該派遣労働者(60歳以上の定年退職者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提
供を受け入れてはならない(法第40条の9第1項、則第33条の10第1項)。
ロ 派遣先は、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば、イに抵触することとなるときは、速
やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない(法第
40条の9第2項)。
(2)意義
第7の18を参照のこと。
(3)通知の方法
通知は、書面の交付、ファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信により行わなけ
ればならない(則第33条の10第2項)。
(4)離職して1年を経過していない労働者を派遣労働者として受け入れた場合の取扱い
厚生労働大臣は、離職して1年を経過していない労働者を派遣労働者として受け入れた場合及び
法第48条第1項の規定による指導又は助言をしたにもかかわらず、なお当該規定に違反している
場合には、当該派遣先に対し、当該派遣就業を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告す
ることができる(法第49条の2第1項)。
また、厚生労働大臣は、当該勧告を行った場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなか
った場合には、その旨を公表することができる(法第49条の2第2項)。
11派遣先責任者の選任
(1)概要
- 292 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
派遣先は、派遣就業に関し(4)に掲げる事項を行わせるために、労働者派遣された派遣労働者に
関する就業の管理を一元的に行う「派遣先責任者」を選任し、派遣労働者の適正な就業を確保しな
ければならない(法第41条)。
(2)派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行
派遣先は、派遣先責任者の選任に当たっては、労働関係法令に関する知識を有する者であること、
人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること、派遣労働者の
就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等派遣先責任者の
職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めること(「派遣先が講ずべき措置に関す
る指針」第2の13(第8の19参照))。
(3)派遣先責任者の選任の方法
派遣先責任者は次の方法により選任しなければならない(則第34条)。
イ 事業所その他派遣就業の場所(11及び12において「事業所等」という。)ごとに専属(※)
の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人であ
る場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。
※ 専属とは
この場合において、専属とは当該派遣先責任者に係る業務のみを行うということではなく、
他の事業所の派遣先責任者と兼任しないという意味。
また、派遣先責任者についても、派遣元責任者と同様、株式会社及び有限会社の監査役は選任
できないものであるので留意すること。
ロ 事業所等における派遣労働者の数について1人以上100人以下を1単位とし、1単位につき1
人以上ずつ選任しなければならない。
ハ 事業所等における派遣労働者の数と当該派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人以下の
ときについては選任することを要しない。
ニ 製造業務専門派遣先責任者の選任
(イ)製造業務に派遣労働者を従事させる事業所等にあっては、製造業務に従事させる派遣労働者
の数について1人以上100人以下を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ、製造業務に従事
させる派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)を、選
任しなければならない。
なお、事業所等における製造業務に従事させる派遣労働者の数が50人以下の事業所等につ
いては、製造業務専門派遣先責任者を選任することを要しない(この場合、通常の派遣先責任
者が製造業務に従事させる派遣労働者を含めて担当することとなる。)。
この趣旨は、派遣先における派遣労働者の就業管理体制の一層の充実を図る必要があること
から、製造業務に派遣された派遣労働者が一定数以上いる場合、当該派遣労働者を担当する派
遣先責任者と、それ以外の業務に派遣された派遣労働者を担当する派遣先責任者とを区分して
- 293 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
選任するものである。
(ロ)ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち1人は、製造業務に従事させない派遣労働者(そ
れ以外の業務へ労働者派遣された派遣労働者)を併せて担当することができる。また、製造業
務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」
という。)に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随
業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、製造業務に従
事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が100人を超えない範囲
内で、製造業務専門派遣先責任者に、製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させ
ることができる。
例えば、以下のようなケースが考えられる。
a 派遣先における全派遣労働者300人のうち、製造業務へ派遣されている派遣労働者が40
人、製造業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者が260人である場合、製造業務専門派
遣先責任者については選任することを要しない(通常の派遣先責任者3名で足りる。)
b 一方で、派遣先における全派遣労働者300人のうち、製造業務へ派遣されている派遣労働
者が150人、製造業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者が150人である場合には、製
造業務専門派遣先責任者を2人(うち1人は製造業務以外の業務へ派遣されている派遣労働
者を併せて担当することができる。)、製造業務以外の業務に従事する派遣労働者を担当す
る派遣先責任者を2人(製造業務専門派遣先責任者のうち1人が、製造業務以外の業務に従
事する派遣労働者を併せて担当する場合は、1人)を選任する必要がある。
(4)派遣先責任者の職務
派遣先責任者は、次に掲げる職務を行わなければならない。
イ 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者
その他の関係者に周知すること。
この場合において、「派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者」とは、
派遣労働者を直接指揮命令する者だけではなく、派遣労働者の就業の在り方を左右する地位に立
つ者は全て含む。また、「その他の関係者」とは、派遣労働者の就業に関わりのある者全てをい
う。
① 法及び法第3章第4節の労働基準法等の適用に関する特例等により適用される法律の規定
(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)
② 当該派遣労働者に係る法第39条に規定する労働者派遣契約の定め(2の(1)及び第6の2の
(1)のイ参照)
③ 当該派遣労働者に係る派遣元事業主からの通知(第7の15参照)。
ロ 派遣可能期間の延長通知に関すること(5の(5)参照)。
ハ 派遣先における均衡待遇の確保に関すること
(力 派遣先における教育訓練の実施状況の把握
- 294 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
② 利用できる福利厚生施設の把握
③ 派遣元に提供した派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行状況等の情報の把
握
二 派遣先管理台帳の作成、記録、保存及び記載事項の通知に関すること(12参照)。
ホ 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること(3参照)。
へ 安全衛生に関すること。
派遣労働者の安全衛生に関し、当該派遣先において労働者の安全衛生に関する業務を統括する
者及び派遣元事業主と必要な連絡調整を行うこと。
具体的には、派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、例えば、以下の内容に係る連絡
調整を行うことである。
(イ) 健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実施に関
する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)
(ロ) 安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、
職長等教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)
(ハ) 労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認
(ニ) 事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認
なお、労働者の安全衛生に関する業務を統括する者とは、労働安全衛生法における安全管理者、
衛生管理者等が選任されているときは、その者をいい、総括安全衛生管理者が選任されていると
きは、その者をいうものである。また、小規模事業場で、これらの者が選任されていないときは、
事業主自身をいうものである。
ト 上記に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。
具体的には、例えば、派遣元の連絡調整の中心となる派遣元責任者との間において、ホ及びへ
のほか、派遣就業に伴い生じた問題の解決を図っていくことである。
(5)派遣先責任者講習の受講
派遣先は、選任した派遣先責任者について、派遣就業に関する労働者派遣法や労働基準法等の趣
旨、派遣先責任者の職務、必要な事務手続等に関する適切な知識を取得できるよう、派遣先責任者
を新たに選任したとき、労働関係法令の改正が行われたとき等の機会を捉え、「派遣先責任者講習」
を受講させることが望ましい。
12 派遣先管理台帳
(1)意義
派遣先管理台帳は、派遣先が、労働日、労働時間等の派遣労働者の就業実態を的確に把握する
とともに、当該台帳の記載内容を派遣元事業主に通知することにより、派遣元事業主の適正な雇
用管理の実施に資するためのものである。
(2)派遣先管理台帳の作成、記載
- 295 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
イ 概要
派遣先は、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに、ハに掲
げる事項を記載しなければならない(法第42条)。
ロ 派遣先管理台帳の作成及び記載方法
(イ)派遣先管理台帳は、当該派遣労働者の就業する事業所等ごとに作成しなければならない(則
第35条第1項)。
(ロ)派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない
(則第35条第2項)。これは、ハの事項の確定する都度記載していくという意味であり、事
項の内容により記載時期は、異なるものである(例えば、派遣労働者の氏名や派遣元事業主の
氏名又は名称等については労働者派遣を受ける際には、既に記載されている必要があるが、就
業した日ごとのその始業及び終業の時刻については、一般的には当該就業の日の就業が終了し
た段階で遅滞なく記載することで足りる。)。また、ハの⑫の事項の派遣先管理台帳への記載
は、派遣労働者から苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、行わなければならな
い。
(ハ)事業所等における派遣労働者の数と当該派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人以下
のときについては派遣先管理台帳を作成及び記載することを要しない(則第35条第3項)。
(ニ)記載については、所要の事項が記載されておれば足りるものである。
なお、書面によらず電磁的記録により派遣先管理台帳の作成を行う場合は、電子計算機に備
えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わ
なければならない。
また、書面によらず電磁的記録により派遣先管理台帳の保存を行う場合は、次のいずれかの
方法によって行った上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直
ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成
できるようにしなければならない。
a 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調
製するファイルにより保存する方法
b 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み
取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調
製するファイルにより保存する方法
ハ 派遣先管理台帳の記載事項
派遣先管理台帳には、次の事項(第6の2の(1)のイの(ハ)参照)について派遣労働者ごとに記
載しなければならない(法第42条第1項、則第36条)。
(力 派遣労働者の氏名
② 派遣元事業主の氏名又は名称
・ 個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載する。
- 296 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
③ 派遣元事業主の事業所の名称
④ 派遣元事業主の事業所の所在地
・ 派遣先が必要な場合に派遣元事業主を直接訪れて連絡がとれる程度の内容であることが
必要である。
⑤ 協定対象派遣労働者か否かの別
⑥ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別
⑦ 派遣就業をした日
・ 実際に就業した日の実績を記載する。
⑧ 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
・ 実際の始業及び終業の時刻並びに休憩時間の実績を記載する。
⑨ 従事した業務の種類
・ 従事した業務の内容については可能な限り詳細に記載すること。
・ 令第4条第1項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、当該号番号を付すこ
と。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限り
ではない。
・「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、
(i)無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合
(の 契約期間が31日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合
(の(a)又は(b)の労働者派遣に限る場合
のいずれかであり、かつその旨が派遣先管理台帳に明記されている場合である。
⑲ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
・ 派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度
等をいうこと。
・ チームリーダー、副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職を、
役職を有さない派遣労働者であればその旨を記載することで足りるが、派遣労働者の適正な
雇用管理を行うため、より具体的に記載することが望ましい。
⑪ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をし
た場所並びに組織単位
⑫ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
・ 苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受
け、及び苦情の処理に当たった都度記載するとともに、その内容を派遣元事業主に通知す
ること。
・ また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して
不利益な取扱いをしてはならない。(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の7
(第8の3の(2)のニ、第8の19参照))。
- 297 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
・ なお、苦情の処理に関する事項を労働者ごとに管理している趣旨は、派遣先が労働者の
過去の苦情に応じた的確な対応を行うためであることに留意すること。
⑬ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
・ 紹介予定派遣である旨
・ 派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った場合には、当該行為の内容及び複
数人から派遣労働者の特定を行った場合には当該特定の基準
・ 採否結果
・ 職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった
場合には、その理由
⑭ 教育訓練を行った日時及び内容
・業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係
る教育訓練(OJT)であって計画的に行われるもの及び業務の遂行の過程外において行わ
れる教育訓練(off-JT)をいう。(則第35条の2第1号、第2号)
⑮ 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
⑱ 期間制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
法第40条の2第1項第2号による60歳以上の者か否か
法第40条の2第1項第3号イに掲げる有期プロジェクトの業務について労働者派遣を行
うときは、法第40条の2第1項第3号イに該当する業務である旨
法第40条の2第1項第3号ロに掲げる日数限定業務について労働者派遣を行うときは、
①法第40条の2第1項第3号ロに該当する旨、②当該派遣先において、同号ロに該当する
業務が1箇月間に行われる日数、③当該派遣先の通常の労働者の1箇月間の所定労働日教
法第40条の2第1項第4号に掲げる育児休業等の代替要員としての業務について労働者
派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及
び終了予定の日
法第40条の2第1項第5号に掲げる介護休業等の代替要員としての業務について労働者
派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及
び終了予定の日
⑰ 派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被
保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、その具体的な理由を付すこと。)
なお、派遣元事業主は、当該派遣労働者について被保険者資格の取得届の提出がなされてい
ない場合には、その「具体的な」理由を派遣先に通知しなければならないこととされており、
「雇用契約の期間が6週間であり、引き続き雇用されることが見込まれないため」「現在、必
要書類の準備中であり、今月の〇日には届出予定」等、適用基準を満たしていない具体的理由
又は手続の具体的状況が明らかとなるようなものでなければならないこととされている。
- 298 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
(参考) 派遣先管理台帳の例
1 派遣労働者の氏名 □□□□□(60歳未満)
2 派遣元事業主の名称 〇〇〇〇株式会社
3 派遣元事業主の事業所の名称 〇〇〇〇株式会社霞が関支店
4 派遣元事業主の事業所の所在地 〒100-8988千代田区霞が関1-2-2△ビル12階
TEL 3597-****
5 業務の種類 パーソナルコンピュータの操作によるプレゼンテーション用資料、
業績管理資料、会議用資料等の作成業務。
6 業務に伴う責任の程度 副リーダー(部下2名、リーダー不在の間における緊急対応が過
1回程度有)
7 協定対象派遣労働者かの別 協定対象派遣労働者ではない
8 無期雇用か有期雇用かの別 有期雇用
9 派遣就業した事業所の名称、就業場所及び組織単位 △△△△株式会社霞が関支店 経理課
10 派遣就業した事業所の所在地
〒100-8916 千代田区霞が関〇一〇一〇 TEL 3593-****(内線571)
11派遣元責任者 派遣事業運営係長 ◎◎◎◎◎ 内線100
12 派遣先責任者 総務部秘書課人事係長 =… 内線5720
13 就業状況
(就業日) (就業時間) (休憩時間)
◎月1日(月) 9:00~19:00 12:00~13:00
(事務用機器操作業務:9時間(時間外労働1時間を含む。))
◇月2日(火) 9:00~18:00 12:00~13:00
(事務用機器操作業務:8時間)
●月3日(水) 9:00~18:00 12:00~13:00
(事務用機器操作業務:8時間)
14 派遣労働者からの苦情処理状況
(申出を受けた日)(苦情内容、処理状況)
☆月〇日(金) 同一の部署内の男性労働者が、顔を合わせると必ず容姿や身体に関して
言及するとの苦情。当該部署内にセクシュアルハラスメント防止に関する
啓発用資料を配布するとともに、説明を行ったところ、以後、そのような
不適切な発言はなくなった。
15 教育訓練の日時及び内容
〇月〇日(水)15:00~17:00
人職時に社内で通常使用するPC等を利用しての基礎的訓練の実施
16 雇用保険・社会保険の被保険者資格取得届の提出の有無
- 299 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
雇用保険 有
健康保険 無(ただし、現在、必要書類の準備中であり、今月の〇日には届出予定)
……〇月〇日手続完了を確認、有
厚生年金保険 無(ただし、現在、必要書類の準備中であり、今月の〇日には届出予定)
……〇月〇日手続完了を確認、有
(3)派遣先管理台帳の保存
イ 概要
派遣先は、派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない(法第42条第2項)。
ロ 意義
(イ)派遣先管理台帳の保存は、派遣労働者の派遣就業に関する紛争の解決を図り、行政による監
督の用に供するために行わせるものである。
(ロ)派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする
(則第37条)。
(ハ)「労働者派遣の終了の日」とは、労働者派遣の役務の提供を受ける際に、派遣元事業主から
通知(第7の12参照)を受けた当該派遣労働者に係る労働者派遣の期間の終了の日であり、
労働者派遣契約が更新された場合は、当該更新に当たって通知された当該派遣労働者に係る派
遣期間の終了の日である。
(4)派遣元事業主への通知
イ 概要
派遣先は、(2)のハの(力、⑦、⑧、⑨、⑲及び⑪の事項を派遣元事業主に通知しなければなら
ない(法第42条第3項、則第38条)。
ロ 通知の方法
(力 派遣元事業主への通知は、1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて派遣労働者ごとに通
知すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送
信をすることにより行わなければならない(則第38条第1項)。
② 派遣元事業主から請求があった場合は、遅滞なく、派遣労働者ごとに書面の交付若しくはフ
ァクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信をすることにより通知しなければなら
ない(則第38条第2項)。
13 労働・社会保険の適用の促進
派遣先は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、労働・社会保険に加入し
ている派遣労働者(派遣元事業主が新規に雇用した派遣労働者であって、当該派遣先への労働者派遣
の開始後、速やかに労働・社会保険への加入手続が行われているものを含む。)を受け入れるべきも
のであり、派遣元事業主から労働・社会保険に加入していない具体的な理由の通知を受けた場合にお
- 300 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
いて、当該理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元事業主に対し当該派遣労働者を労働・社
会保険に加入させてから派遣するよう求めること(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の8
(第8の18参照)、第7の15の(5)のこ参照)。また、労働・社会保険に加入している派遣労働者
については、派遣元事業主から送付されてくる被保険者証の写し等を確認すること。
「理由が適正でないと考えられる場合」の例は、「派遣労働者が労働・社会保険への加入を希望し
ていないため」等のように加入の有無を派遣労働者の希望にかからしめている場合や、社会保険につ
いて「雇用期間が6箇月であるため」等のように適用基準を満たしているにもかかわらず、加入させ
ていない場合等が考えられる。
14 関係法令の関係者への周知
派遣先は、法の規定により派遣先が講ずべき措置の内容や法第3章第4節に規定する労働基準法等
の適用に関する特例等の関係者への周知を図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ず
ること(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の10(第8の19参照))。
15 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止
(1)概要
労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締
結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする
行為をしないよう努めなければならない(法第26条第6項)。
(2)意義
イ 派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させ
ようとする労働者について、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に
係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等の派遣労働者を特定するこ
とを目的とする行為を行わないこと(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の3(第8の
19参照))。
ロ 短期間の労働者派遣契約を締結し派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けた後に、更に労働
者派遣の役務の提供を受ける段階で、派遣先が当該派遣労働者を指名する場合についても、当該
規定に違反するものである。
ハ ただし、本取扱いは、あくまでも個々の派遣労働者の特定につながる行為をしないようにする
ことを目的とするものであり、業務に必要な技術や技能の水準を指定するため、技術・技能レベ
ル(取得資格等)と当該技術・技能に係る経験年数などを記載するいわゆるスキルシートを送付
することをもってこの規定に違反しているということにはならないこと。
なお、スキルシートに「当社に就労経験を有すること」のような記述を行うことは、必要とす
る技術を明確にしていないほか、具体的な派遣労働者が特定される可能性が高いことから適当で
はないこと。
- 301-
第8 派遣先の講ずべき措置等
16 性別・障害の有無・年齢による差別的取扱いの禁止等
(1)性別による差別的取扱いの禁止等
派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、当該労働者派遣契約
に派遣労働者の性別を記載してはならないので、その旨の周知、指導に努めること(「派遣先が講
ずべき措置に関する指針」第2の4(第8の19参照))。
また、職業安定法第3条、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(昭和47年法律第113号)の趣旨からも、性別を理由とする差別的取扱を行ってはならない。
(2)障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いの禁止等
派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣元事業主が当該
派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、障害者であることを理由として、障
害者を排除し、又はその条件を障害者に対してのみ不利なものとしてはならないので、その旨の周
知、指導に努めること(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の4(第8の19参照))。
また、職業安定法第3条、障害者雇用促進法の趣旨からも、障害の有無を理由とする差別的取り
扱を行ってはならない。
(3)年齢による差別的取扱いに対する指導等
派遣先が派遣労働者を雇用しているわけではなく、労働施策総合推進法第9条及び職業安定法第
3条の趣旨からも年齢による差別的な受入れ拒否等を行うことは不適当である旨周知、指導に努め
ること。また、職業安定法第3条による差別的取扱いの禁止の対象には、障害者であることも含ま
れるものであることから、同様に障害者であることを理由として差別的な受入れ拒否等を行うこと
は不適当である旨周知、指導に努めること。
(4)派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の禁止に向けた取組
派遣先は、派遣労働者を雇用する立場とならないことから、従来から一般的な募集、採用に関す
る考え方は適用できないが、労働施策総合推進法第9条の趣旨を踏まえ、また、派遣元事業主が労
働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項各号に掲げる例外事由を除き、募集、採用に係る年齢
制限の禁止が義務化されたことに鑑み、派遣先が派遣元事業主に対し、例外事由を除く年齢制限を
した募集、採用を求めることは認められないこと。
(5)15の「派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止等」との関係
性別、年齢等による差別的な取扱いの禁止の観点と特定日的行為の禁止の観点から提供が望まし
くない情幸田ま別のものであるので、留意する必要がある。
17 紹介予定派遣
紹介予定派遣を行う場合の取扱いについては、第1の4及び第6の2の(1)のイの(ハ)⑲によるほ
か、派遣先は次の(1)から(7)までに留意すること。
(1)紹介予定派遣を受け入れる期間
- 302 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、6箇月を超えて、同一の派遣労働者を受け
入れないこと(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の18の(1)(第8の19参照))。
(2)職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
イ 派遣先は、紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹介を受けることを希望しなかった
場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、
それぞれのその理由を派遣元事業主に対して書面、ファクシミリ又は電子メール等により明示す
ること(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の18の(2)(第8の19参照))。
ロ イに関連して、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の13の(2)において、派遣
元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職
業紹介を受けた労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、それぞれその理由
について、派遣先に対して書面、電子メール等又はファクシミリにより明示するよう求めるもの
とし、また派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面、ファクシミリ又は電子メー
ル等(ファクシミリ又は電子メール等による場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に
限る。)で明示するものとすることとされているので十分留意すること。
(3)派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別・障害の有無による差別防止に係る措置
紹介予定派遣については、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が可能であるが、
「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の18の(3)、(4)及び(5)において、派遣先は、紹介予
定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為又は派遣労働者の特定(以下「特定等」
という。)を行うに当たっては、直接採用する場合と同様に、労働施策総合推進法第9条及び労働
施策総合推進法施行規則第1条の3、男女雇用機会均等法に基づく「労働者に対する性別を理由と
する差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」並びに
障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主
が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第116号)」の内容と同旨の内容の措置
を適切に講ずるものとすることとされている。したがって、派遣労働者の特定等を行うに当たって
は、これらの指針に従って年齢・性別・障害の有無による差別を行ってはならない。
また、派遣先は、障害者に対し、面接その他特定することを目的とする行為を行う場合に、派遣
元事業主が障害者雇用促進法第36条の2又は第36条の3の規定による措置を講ずるため、派遣元
事業主から求めがあったときは、派遣元事業主と協議等を行い、可能な限り協力するよう努めなけ
ればならない(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の18の(1)(第8の19参照))。
(派遣先が講ずべき措置に関する指針(抄))
第2 派遣先が講ずべき措置
18 紹介予定派遣
(3)派遣先が特定等に当たり労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の
充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第9条の趣旨に照らし講ずべき措置
(力 派遣先は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為又は派遣労働
- 303 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
者の特定(以下「特定等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる措置を講ずること。
ア ②に該当するときを除き、派遣労働者の年齢を理由として、特定等の対象から当該派遣
労働者を排除しないこと。
イ 派遣先が職務に適合する派遣労働者を受け入れ又は雇い入れ、かつ、派遣労働者がその
年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択すること
を容易にするため、特定等に係る職務の内容当該職務を遂行するために必要とされる派遣
労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の派遣労働者が紹介予定派遣を希望するに
当たり求められる事項をできる限り明示すること。
② 年齢制限が認められるとき(派遣労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要で
あると認められるとき以外のとき)
派遣先が行う特定等が次のアからウまでのいずれかに該当するときには、年齢制限をする
ことが認められるものとする。
ア 派遣先が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている
場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として派遣労働者の特定等を行うとき
(当該派遣労働者について期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限
る。)。
イ 派遣先が、労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就
業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する派遣労働者以外の派
遣労働者の特定等を行うとき。
ウ 派遣先の特定等における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的
な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
i 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、
青少年その他特定の年齢を下回る派遣労働者の特定等を行うとき(当該派遣労働者につ
いて期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限り、かつ、当該派遣
労働者が職業に従事した経験があることを特定等の条件としない場合であって学校(小
学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力
開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設又は同法第27条
第1項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者として又は当該
者と同等の処遇で採用する予定で特定等を行うときに限る。)。
辻 当該派遣先が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(当該派遣先の
人事管理制度に照らし必要と認められるときは、当該派遣先がその一部の事業所におい
て雇用する特定の職種に従事する労働者。以下「特定労働者」という。)の数が相当程
度少ない場合(特定労働者の年齢について、30歳から49歳までの範囲内において、派遣
先が特定等を行おうとする任意の労働者の年齢の範囲(当該範囲内の年齢のうち最も高
いもの(以下「範囲内最高年齢」という。)と最も低いもの(以下「範囲内最低年齢」
- 304 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
という。)との差(以下「特定数」という。)が4から9までの場合に限る。)に属す
る労働者数が、範囲内最高年齢に1を加えた年齢から当該年齢に特定数を加えた年齢ま
での範囲に属する労働者数の2分の1以下であり、かつ、範囲内最低年齢から1に特定
数を加えた年齢を減じた年齢から範囲内最低年齢から1を減じた年齢までの範囲に属す
る労働者数の2分の1以下である場合をいう。)において、当該職種の業務の遂行に必
要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者である派遣
労働者の特定等を行うとき(当該派遣労働者について期間の定めのない労働契約を締結
することを予定する場合に限る。)。
嵐 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属
する派遣労働者の特定等を行うとき。
k 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(60歳以上の者に限
る。)である派遣労働者の特定等を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の
雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する派遣労働者の特定等を行うとき(
当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする
場合に限る。)。
(4)派遣先が特定等に当たり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法
律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第5条及び第7条の趣旨に照らし行って
はならない措置等
① 派遣先は、特定等を行うに当たっては、例えば次に掲げる措置を行わないこと。
ア 特定等に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
イ 特定等に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
ウ 特定に係る選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準に
ついて男女で異なる取扱いをすること。
エ 特定等に当たって男女のいずれかを優先すること。
オ 派遣就業又は雇用の際に予定される求人の内容の説明等特定等に係る情報の提供につい
て、男女で異なる取扱いをすること又は派遣元事業主にその旨要請すること。
② 派遣先は、特定等に関する措置であって派遣労働者の性別以外の事由を要件とするものの
うち、次に掲げる措置については、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の
実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施
が派遣就業又は雇用の際に予定される雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由
がある場合でなければ、これを講じてはならない。
ア 派遣労働者の特定等に当たって、派遣労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。
イ 派遣労働者の特定等に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とす
ること。
③ 紹介予定派遣に係る特定等に当たっては、将来、当該派遣労働者を採用することが予定さ
- 305 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
れている雇用管理区分において、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない場合に
おいては、特定等の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して特定することその他男
性と比較して女性に有利な取扱いをすることは、均等法第8条に定める雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする措置
(ポジティブ・アクション)として、(力にかかわらず、行って差し支えない。
④ 次に掲げる場合において①において掲げる措置を講ずることは、性別にかかわりなく均等
な機会を与えていない、又は性別を理由とする差別的取扱いをしているとは解されず、①に
かかわらず、行って差し支えない。
ア 次に掲げる職務に従事する派遣労働者に係る場合
i 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させ
ることが必要である職務
辻 守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務(労働者派
遣事業を行ってはならない警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる
業務を内容とするものを除く。)
嵐 i及び辻に掲げるもののほか、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上その
他の業務の性質上男女のいずれかのみに従事させることについてこれらと同程度の必要
性があると認められる職務
イ 労働基準法第61条第1項、第64条の2若しくは第64条の3第2項の規定により女性を就業
させることができず、又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条の規定に
より男性を就業させることができないことから、通常の業務を遂行するために、派遣労働
者の性別にかかわりなく均等な機会を与え又は均等な取扱いをすることが困難であると認
められる場合
ウ 風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場
合その他特別の事情により派遣労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え又は均等な
取扱いをすることが困難であると認められる場合
(5) 派遣先が特定等に当たり障害者雇用促進法第34条の趣旨に照らし行ってはならない措置等
① 派遣先は、特定等を行うに当たっては、例えば次に掲げる措置を行わないこと。
ア 特定等に当たって、障害者であることを理由として、障害者をその対象から排除するこ
と。
イ 特定等に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
ウ 特定等に当たって、障害者でない者を優先すること。
エ 派遣就業又は雇用の際に予定される求人の内容の説明等の特定等に係る情報の提供につ
いて、障害者であることを理由として障害者でない者と異なる取扱いをすること又は派遣
元事業主にその旨要請すること。
②(力に関し、特定等に際して一定の能力を有することを条件とすることについては、当該条
- 306 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
件が当該派遣先において業務遂行上特に必要なものと認められる場合には、行って差し支え
ないこと。一方、特定等に当たって、業務遂行上特に必要でないにもかかわらず、障害者を
排除するために条件を付すことは、行ってはならないこと。
③ ①及び②に関し、積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に
取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当しないこと。
④ 派遣先は、障害者に対し、面接その他特定することを目的とする行為を行う場合に、派遣
元事業主が障害者雇用促進法第36条の2又は第36条の3の規定による措置を講ずるため、派
遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主と協議等を行い、可能な限り協力するよ
う努めなければならないこと。
(4)派遣労働者の特定
紹介予定派遣について派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が認められるのは、
あくまで円滑な直接雇用を図るためであることに鑑み、派遣先が、試験、面接、履歴書の送付等に
より派遣労働者を特定する場合は、業務遂行能力に係る試験の実施や資格の有無等、社会通念上、
公正と認められる客観的な基準によって行われることが必要であることに十分に留意して行うこと。
(5)派遣就業期間の短縮
派遣就業期間の短縮については、第7の25の(3)に同じ。
(6)求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化
求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化については、第7の25の
(4)に同じ。
(7)その他
紹介予定派遣が行われる場合については、派遣先に対し、次のような指導を行うこととするので
配慮の上、的確な指導の実施を図ること。
(力 派遣先は、紹介予定派遣により雇い入れた労働者については試用期間を設けないよう必要な指
導を行うものとすること。
② 派遣就業終了後に派遣先が職業紹介を受けることを希望せず、又は職業紹介の結果派遣労働者
を採用することとならなかった場合であって、当該派遣先が当該派遣労働者を特定して労働者派
遣を受けることを希望した場合には、当該派遣先に対し、当該派遣労働者の雇入れについて必要
な指導を行うものとすること。
③ 派遣就業期間中に派遣先が派遣労働者に対して採用内定を行うことは可能であるが、紹介予定
派遣における採用内定についても、紹介予定派遣によらない通常の採用内定の取扱い(解約権を
留保した労働契約が成立したものとする判例がある。)と同様と考えられ、また、採用内定の取
消しの取扱いについても同様(解約権留保の趣旨・目的に照らし社会通念上相当として是認する
ことができなければ、解約権の濫用に当たり無効とする判例がある。)と考えられることから、
必要な指導を行うものとすること。
- 307 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
18 派遣労働者の判断で行う派遣就業開始前の事業所訪問等
イ 派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として適当であるかど
うかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又
は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは派遣先による派遣労働者を特定することを目的と
する行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、派遣先は、派遣元事業主又は派遣労
働者若しくは派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣
労働者を特定することを目的とする行為の禁止に触れないよう、十分留意すること(「派遣先が
講ずべき措置に関する指針」第2の3(第8の19参照))。
ロ 紹介予定派遣以外の派遣として派遣就業を開始した場合における求人条件の明示等
当初より紹介予定派遣として派遣就業が開始された場合でなくとも、派遣就業期間中に、(力職
業紹介事業者でもある派遣元事業主が、派遣労働者又は派遣先の希望に応じて、求人条件の明示、
求人・求職の意思等の確認を行うこと、又は、②派遣先が派遣労働者に対して採用内定を行うこ
とは可能である。
なお、(力の求人条件の明示等の結果、派遣労働者及び派遣先が職業紹介を受けることに合意し
た場合(労働者派遣をその時点で中止する場合を除く。)には、その時点で当該労働者派遣は紹
介予定派遣に該当することとなることから、速やかに、従前の労働者派遣契約の変更を行い、紹
介予定派遣に係る事項を定める等(第6の2の(1)のイの(ハ)の⑲参照)、紹介予定派遣に必要と
される措置を行うことが必要である。
19 派遣先が講ずべき措置に関する指針
(1)概要
厚生労働大臣は、法に規定される派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図
るため必要な指針を公表するものとする(法第47条の3)。
(2)指針の公表
指針は、平成11年労働省告示第138号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、平成20年厚生
労働省告示第36号「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ず
べき措置に関する指針」及び平成30年厚生労働省告示第430号「短時間・有期雇用労働者及び派
遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」による。
20 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべ
き措置に関する指針
日雇派遣については、必要な雇用管理がなされず、労働者保護が果たされない等といった課題が
指摘されている。そのため、適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められている業務に
- 308 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
ついて労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の
継続等を図るために必要であると認められる場合等を除き、原則禁止とされている(第7の17参
照)。
なお、日雇派遣の禁止の例外として認められる場合であっても、日雇派遣労働者の安全衛生確保
は重要な課題であり、日雇派遣の禁止の例外として日雇派遣労働者を受け入れる場合には、派遣先
においても、派遣元事業主における雇入時の安全衛生教育の実施状況の確認を確実に実施するとと
もに、派遣先の義務とされている危険有害業務の特別教育や日雇派遣労働者が従事する具体的な業
務内容の派遣元事業主への積極的な情報提供等を確実に実施すること。
「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する
指針」の取扱い等については、第7の28を参照のこと。
21短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する
指針
ガイドラインは、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、い
かなる待遇の相違が不合理と認められるものであり、いかなる待遇の相違が不合理と認められるも
のでないのか等の原則となる考え方及び具体例を示したものである。この「待遇」のうち、法第
40条第2項の教育訓練(業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練)及び法第40条第3
項の福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、派遣先が実施し、又は利用の機会を
付与することが必要であることから、ガイドラインも踏まえて適切に対応すること。詳細は第7の
4の(7)を参照のこと。
- 309 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
派遣先が講ずべき措置に関する指針
(平成11年労働省告示第138号)
(最終改正 平成30年厚生労働省告示第428号)
第1 趣旨
この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労
働者派遣法」という。)第3章第1節及び第3節の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その
適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。
第2 派遣先が講ずべき措置
1 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認
派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就業中の派遣労働者を直接指揮命
令することが見込まれる者から、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該業務を遂行するた
めに必要とされる知識、技術又は経験の水準その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件
の内容を十分に確認すること。
2 労働者派遣契約に定める就業条件の確保
派遣先は、労働者派遣契約を円滑かつ的確に履行するため、次に掲げる措置その他派遣先の実態
に即した適切な措置を講ずること。
(1)就業条件の周知徹底
労働者派遣契約で定められた就業条件について、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する
職務上の地位にある者その他の関係者に当該就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場所に
掲示する等により、周知の徹底を図ること。
(2)就業場所の巡回
定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、当該派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に反
していないことを確認すること。
(3)就業状況の報告
派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に当該派遣労働者の就業の状況について報告を
求めること。
(4)労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導
派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上
の指示を行わないようにすること等の指導を徹底すること。
3 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止
派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当
にせわ始にあれ
者さ行開先でこ
働付を業遣能て
労送為就派可し
るを行遣、施対
す苦る派は実に
と歴すにと、者
う履と下こずる
ついて、労働者派遣に先立って面接する
ここ働は勺労労
・∥
㌶椒紺栂栂
と派送
とはの
るな前よるら
ことのほか 若年者に限るこ
いのっがの
こと。なお、派遣労働者又
事て、行
業所訪問若しくは履歴
…鵠附
派派為
の禁止に触れないよう十分
書
と
こ
る
す
定
特
を
者
ま
又等
主る
業す
事と
元と
遣こと
派いこ
、なる
令て特者履れ労と
命Lをるのわ遣こ
蓋
の下に就業させよ
当定が歴た働を
該労働者に係る
することを目的
、自らの判断の
書こ者目
のと
送付を行う
には該当せ
となろうとす
的
とする行為
4 性別による差別及び障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いの禁止
(1)性別による差別の禁止
派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、当該労働者派遣契
約に派遣労働者の性別を記載してはならないこと。
(2)障害者であることを理由とする不当な差別的取扱いの禁止
派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣元事業主が当
該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、障害者の雇用の促進等に関する
法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第1号に規定する障害
者(以下単に「障害者」という。)であることを理由として、障害者を排除し、又はその条件を
障害者に対してのみ不利なものとしてはならないこと。
5 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等
派遣先は、労働者派遣契約の定めに反する事実を知った場合には、これを早急に是正するととも
に、労働者派遣契約の定めに反する行為を行った者及び派遣先責任者に対し労働者派遣契約を遵守
させるために必要な措置を講ずること、派遣元事業主と十分に協議した上で損害賠償等の善後処理
方策を講ずること等適切な措置を講ずること。
6 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(1) 労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置
イ 派遣先は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契
約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣先は派遣労働
者の新たな就業機会の確保を図ること及びこれができないときには少なくとも当該労働者派遣契
約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀
なくされることにより生ずる損害である休業手当、解雇予告手当等に相当する額以上の額につい
て損害の賠償を行うことを定めなければならないこと。また、労働者派遣の期間を定めるに当た
っては、派遣元事業主と協力しつつ、当該派遣先において労働者派遣の役務の提供を受けようと
する期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮
をするよう努めること。
ロ 派遣先は、労働者派遣契約の締結に当たって、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派
- 310 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
遣労働者を雇用する場合に、当該雇用が円滑に行われるよう、派遣元事業主の求めに応じ、派遣
先が当該労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する意思がある場合には、当該意思を事前
に派遣元事業主に示すこと、派遣元事業主が職業安定法(昭和22年法律第141号)その他の法律
の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合には、派遣先は職
業紹介により当該派遣労働者を雇用し、派遣元事業主に当該職業紹介に係る手数料を支払うこと
等を定め、これらの措置を適切に講ずること。
(2)労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除
を行おうとする場合には、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期
間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うこと。
(3)派遣先における就業機会の確保
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事
由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせ
んする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
(4)損害賠償等に係る適切な措置
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者
派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、
これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該
労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償
を行わなければならないこと。例えば、当該派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は
休業手当に相当する額以上の額について、当該派遣元事業主がやむを得ない事由により当該派遣
労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかった
ことにより当該派遣元事業主が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした目から解
雇の目までの期間が30日に満たないときは当該解雇の目の30日前の目から当該予告の目までの日
数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこと。その
他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、派遣元
事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞ
れの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。
(5)労働者派遣契約の解除の理由の明示
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行う場合であっ
て、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を当該派遣元事業主
に対し明らかにすること。
7 適切な苦情の処理
(1) 適切かつ迅速な処理を図るべき苦情
派遣先が適切かつ迅速な処理を図るべき苦情には、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産等
に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント、障害者である
派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情に関するもの等が含まれることに
留意すること。
(2) 苦情の処理を行う際の留意点等
派遣先は、派遣労働者の苦情の処理を行うに際しては、派遣先の労働組合法(昭和24年法律第
174号)上の使用者性に関する代表的な裁判例や中央労働委員会の命令に留意すること。また、派
遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣先において苦情の処理を行う方法、派遣元事
業主と派遣先との連携のための体制等を労働者派遣契約において定めるとともに、派遣労働者の
受入れに際し、説明会等を実施して、その内容を派遣労働者に説明すること。さらに、派遣先管
理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受
け、及び苦情の処理に当たった都度、記載するとともに、その内容を派遣元事業主に通知するこ
と。また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利
益な取扱いをしてはならないこと。
8 労働・社会保険の適用の促進
派遣先は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、労働・社会保険に加入
している派遣労働者(派遣元事業主が新規に雇用した派遣労働者であって、当該派遣先への労働者
派遣の開始後速やかに労働・社会保険への加入手続が行われるものを含む。)を受け入れるべきで
あり、派遣元事業主から派遣労働者が労働・社会保険に加入していない理由の通知を受けた場合に
おいて、当該理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元事業主に対し、当該派遣労働者を労
働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めること。
9 適正な派遣就業の確保
(1) 適切な就業環境の維持、福利厚生等
派遣先は、その指揮命令の下に労働させている派遣労働者について、派遣就業が適正かつ円滑
に行われるようにするため、労働者派遣法第40条第1項から第3項までに定めるもののほか、セ
クシュアルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持並びに派遣先が設置及び運営し、その雇
用する労働者が通常利用している物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、
講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるよ
うに配慮しなければならないこと。また、派遣先は、労働者派遣法第40条第5項の規定に基づ
き、派遣元事業主の求めに応じ、当該派遣先に雇用される労働者の賃金、教育訓練、福利厚生等
の実状をより的確に把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供するとともに、派遣元事業
主が当該派遣労働者の職務の成果等に応じた適切な賃金を決定できるよう、派遣元事業主からの
- 311-
第8 派遣先の講ずべき措置等
求めに応じ、当該派遣労働者の職務の評価等に協力をするように配慮しなければならないこと。
(2) 労働者派遣に関する料金の額
イ 派遣先は、労働者派遣法第26条第11項の規定により、労働者派遣に関する料金の額について、
派遣元事業主が、労働者派遣法第30条の4第1項の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあ
っては労働者派遣法第30条の3の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあっては同項第2号から
第5号までに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものとなるように配慮しな
ければならないこととされているが、当該配慮は、労働者派遣契約の締結又は更新の時だけでは
なく、当該締結又は更新がなされた後にも求められるものであること。
ロ 派遣先は、労働者派遣に関する料金の額の決定に当たっては、その指揮命令の下に労働させる
派遣労働者の就業の実態、労働市場の状況、当該派遣労働者が従事する業務の内容及び当該業務
に伴う責任の程度並びに当該派遣労働者に要求する技術水準の変化等を勘案するよう努めなけれ
ばならないこと。
(3) 教育訓練・能力開発
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対して労働者派遣法第40条第2項の規
定による教育訓練を実施する等必要な措置を講ずるほか、派遣元事業主が労働者派遣法第30条の
2第1項の規定による教育訓練を実施するに当たり、派遣元事業主から求めがあったときは、派
遣元事業主と協議等を行い、派遣労働者が当該教育訓練を受講できるよう可能な限り協力すると
ともに、必要に応じた当該教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならないこと。派遣元事
業主が行うその他の教育訓練、派遣労働者の自主的な能力開発等についても同様とすること。
(4) 障害者である派遣労働者の適正な就業の確保
① 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対する教育訓練及び福利厚生の実施
について、派遣労働者が障害者であることを理由として、障害者でない派遣労働者と不当な差
別的取扱いをしてはならないこと。
② 派遣先は、労働者派遣契約に基づき派遣された労働者について、派遣元事業主が障害者雇
用促進法第36条の3の規定による措置を講ずるため、派遣元事業主から求めがあったときは、
派遣元事業主と協議等を行い、可能な限り協力するよう努めなければならないこと。
10 関係法令の関係者への周知
派遣先は、労働者派遣法の規定により派遣先が講ずべき措置の内容及び労働者派遣法第3章第4
節に規定する労働基準法(昭和22年法律第49号)等の適用に関する特例等関係法令の関係者への周
知の徹底を図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずること。
11 派遣元事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立
派遣先は、派遣元事業主の事業場で締結される労働基準法第36条第1項の時間外及び休日の労働
に関する協定の内容等派遣労働者の労働時間の枠組みについて派遣元事業主に情報提供を求める等
により、派遣元事業主との連絡調整を的確に行うこと。
また、労働者派遣法第42条第1項及び第3項において、派遣先は派遣先管理台帳に派遣就業をし
た日ごとの始業及び終業時刻並びに休憩時間等を記載し、これを派遣元事業主に通知しなければな
らないとされており、派遣先は、適正に把握した実際の労働時間等について、派遣元事業主に正確
に情報提供すること。
12 派遣労働者に対する説明会等の実施
派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施し、派遣労働者が利用できる派遣先の各
種の福利厚生に関する措置の内容についての説明、派遣労働者が円滑かつ的確に就業するために必
要な、派遣労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関係についての説明及
び職場生活上留意を要する事項についての助言等を行うこと。
13 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行
派遣先は、派遣先責任者の選任に当たっては、労働関係法令に関する知識を有する者であるこ
と、人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること、派遣労働
者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等派遣先責任
者の職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めること。
14 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用
派遣先は、労働者派遣法第40条の2及び第40条の3の規定に基づき派遣労働者による常用労働者の代
替及び派遣就業を望まない派遣労働者が派遣就業に固定化されることの防止を図るため、次に掲げる
基準に従い、事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)ごとの業務について、派遣
元事業主から労働者派遣法第40条の2第2項の派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣(同条
第1項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この14において同じ。)の役務の提供を受けては
ならず、また、事業所等における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間
継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならないこと。
(1)事業所等については、工場、事
いること、経営の単位として人
有すること、一定期間継続し、
すること
(2)事業所等における組織
受ける期間の制限の目的
によって派遣就業を望ま
とに留意しつつ判断す
組織であり、かつ、
そ
るの
事施
、理し
所経と
務、設
店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立して
指導監督
て
tV
お
に
等
様
態
の
働
労
ヽj
力
点
観
の
等
と
こ
る
す
有
を
性
続
特
の
て
ある程度の独立性を
ら実態に即して判断
をとこる つ
供こるああ
握るあがで
のすに性の
務事と連も
役従こ関る
のてるやす
遣つす性有
派た止似を
者わ防類限
働にをの権
労間とて督
の期こし監
3長ると揮
のにれ務指
条務さ業の
40業化の上
第の定等理
法位固プ管
遣単に一務
派織業ル労
者組就グや
働の遣、分
労そ派課配
、がが、の
は者者ち務
て働働わ業
い労労なが
つ遣遣す長
に派派。の
位、いと織
単がなこ組
- 312 -
おに小労派務当続労て者とのな当提当質
に態最、者役、継、い働了れみ、の、実
先実のは働のはらはつ労終人とは務て、
遣く織先労遣にか先になの受の先役しな
派な組遣に派合遣遣務た遣のも遣のとうと
、とと派た者場派派業新派務る派遣的よこ
てこ位)新働い者)の該者役い)派目るる
3 4 5
川漂捌票測嘲捌…禁錮
.
肺腑蕉蕉鼎潤一
最べす役提直、派役遣とが入
のす致のののは者の派始聞け
織断一遣務れ先働遣の開期受
組判が派役人遣労派一ののに
るり位者の受派て者同遣間前
けよ単働遣の該し働、派の直
第8 派遣先の講ずべき措置等
般に大きな単位を想定しており、名称にとらわれる
ただし、小規模の事業所等においては、組織単
留意すること。
、た当該派遣先の事業所等ごとの業務について
。こしはた
ととてにい
労当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労
働者派遣の終了との間の期間が3月を超えな
者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働
を受けているものとみなすこと
た労遣にか
いな派合遣
てた者場派
当該派遣先の事業所等における組織単位ごと
働者派遣の役務の提供を受ける場合には、当
直、派
のは者
れ先働
入遣労
受派て
の該し
務当続
役、継
のはら
前に受け入れていた労働
当該新たな労働者派遣の
の
遣
役務の提供を受けて
年続の旨
3手遣趣
らる派の
か係者定
主に働規
業長労の
事延当項
元の度同
遣間再、
派期には
て能後為
い可た行
つ遣しる
に派過す
務、経続
業てが継
のい月を
とお3れ
ごに後入
等合了受
所場終の
業るの者
事い遣働
のて派労
。先け者遣
と遣受働派
こ派を労に
す該供該的
15 派遣可能期間の延長に係る意見聴取の適切かつ
施
実
な
実
確
間継続して労働者
を役こ
回避することを
務反
の提供を受け
するものであ
(1) 意見聴取に当たっての情報提供
派遣先は、労働者派遣法第40条の2第4項の規定に基づき、過半数労働組合等(同項に規定す
る過半数労働組合等をいう。以下同じ。)に対し、派遣可能期間を延長しようとする際に意見を
聴くに当たっては、当該派遣先の事業所等ごとの業務について、当該業務に係る労働者派遣の役
務の提供の開始時(派遣可能期間を延長した場合には、当該延長時)から当該業務に従事した派
遣労働者の数及び当該派遣先に期間を定めないで雇用される労働者の数の推移に関する資料等、
意見聴取の際に過半数労働組合等が意見を述べるに当たり参考となる資料を過半数労働組合等に
提供するものとすること。また、派遣先は、意見聴取の実効性を高める観点から、過半数労働組
合等からの求めに応じ、当該派遣先の部署ごとの派遣労働者の数、各々の派遣労働者に係る労働
者派遣の役務の提供を受けた期間等に係る情報を提供することが望ましいこと。
(2) 十分な考慮期間の設定
派遣先は、過半数労働組合等に対し意見を聴くに当たっては、十分な考慮期間を設けること。
(3) 異議への対処
イ 派遣先は、派遣可能期間を延長することに対して過半数労働組合等から異議があった場合
に、労働者派遣法第40条の2第5項の規定により当該意見への対応に関する方針等を説明する
に当たっては、当該意見を勘案して当該延長について再検討を加えること等により、当該過半
数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めること。
ロ 派遣先は、派遣可能期間を延長する際に過半数労働組合等から異議があった場合において、
当該延長に係る期間が経過した場合にこれを更に延長しようとするに当たり、再度、過半数労
働組合等から異議があったときは、当該意見を十分に尊重し、派遣可能期間の延長の中止又は
延長する期間の短縮、派遣可能期間の延長に係る派遣労働者の数の削減等の対応を採ることに
ついて検討した上で、その結論をより一層丁寧に当該過半数労働組合等に説明しなければなら
ないこと。
(4) 誠実な実施
派遣先は、労働者派遣法第40条の2第6項の規定に基づき、(1)から(3)までの内容を含め、派
遣可能期間を延長しようとする場合における過半数労働組合等からの意見の聴取及び過半数労働
組合等が異議を述べた場合における当該過半数労働組合等に対する派遣可能期間の延長の理由等
の説明を行うに当たっては、誠実にこれらを行うよう努めなければならないものとすること。
16 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労働者の受け入れ
派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、当該解雇後3箇月以内に派遣
労働者を受け入れる場合には、必要最小限度の労働者派遣の期間を定めるとともに、当該派遣先に
雇用される労働者に対し労働者派遣の役務の提供を受ける理由を説明する等、適切な措置を講じ、
派遣先の労働者の理解が得られるよう努めること。
17 安全衛生に係る措置
派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者に対する雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を適
切に行えるよう、当該派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣元事業主に対し積極的に提供す
るとともに、派遣元事業主から雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育の委託の申入れがあっ
た場合には可能な限りこれに応じるよう努めること、派遣元事業主が健康診断等の結果に基づく就
業上の措置を講ずるに当たって、当該措置に協力するよう要請があった場合には、これに応じ、必
要な協力を行うこと等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行
うこと。
18 紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣を受け入れる期間
派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、6箇月を超えて、同一の派遣労働者を受
け入れないこと。
(2) 職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
- 313 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
派遣先は、紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹介を受けることを希望しなかった
場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、
それぞれその理由を派遣元事業主に対して書面、ファクシミリ又は電子メールその他のその受信
をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律
第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この(2)において「電子メール等」とい
う。)(当該派遣元事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成すること
ができるものに限る。)により明示すること。
(3) 派遣先が特定等に当たり労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充
実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第9条の趣旨に照らし講ずべき措置
① 派遣先は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為又は派遣労働者
の特定(以下「特定等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる措置を講ずること。
ア ②に該当するときを除き、派遣労働者の年齢を理由として、特定等の対象から当該派遣労
働者を排除しないこと。
イ 派遣先が職務に適合する派遣労働者を受け入れ又は雇い入れ、かつ、派遣労働者がその年
齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易
にするため、特定等に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる派遣労働者の
適性、能力、経験、技能の程度その他の派遣労働者が紹介予定派遣を希望するに当たり求めら
れる事項をできる限り明示すること。
② 年齢制限が認められるとき(派遣労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であ
ると認められるとき以外のとき)
派遣先が行う特定等が次のアからウまでのいずれかに該当するときには、年齢制限をするこ
とが認められるものとする。
ア 派遣先が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場
合において当該定年の年齢を下回ることを条件として派遣労働者の特定等を行うとき(当該
派遣労働者について期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限る。)。
イ 派遣先が、労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業
等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する派遣労働者以外の派遣労
働者の特定等を行うとき。
ウ 派遣先の特定等における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な
制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
i 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青
少年その他特定の年齢を下回る派遣労働者の特定等を行うとき(当該派遣労働者について
期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限り、かつ、当該派遣労働者
が職業に従事した経験があることを特定等の条件としない場合であって学校(小学校(義
務教育学校の前期課程を含む。)及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法
(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設又は同法第27条第1項に規定
する職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇
で採用する予定で特定等を行うときに限る。)。
正 当該派遣先が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(当該派遣先の人
事管理制度に照らし必要と認められるときは、当該派遣先がその一部の事業所において雇
用する特定の職種に従事する労働者。以下「特定労働者」という。)の数が相当程度少な
い場合(特定労働者の年齢について、30歳から49歳までの範囲内において、派遣先が特定
等を行おうとする任意の労働者の年齢の範囲(当該範囲内の年齢のうち最も高いもの(以
下「範囲内最高年齢」という。)と最も低いもの(以下「範囲内最低年齢」という。)と
の差(以下「特定数」という。)が4から9までの場合に限る。)に属する労働者数が、
範囲内最高年齢に1を加えた年齢から当該年齢に特定数を加えた年齢までの範囲に属する
労働者数の2分の1以下であり、かつ、範囲内最低年齢から1に特定数を加えた年齢を減
じた年齢から範囲内最低年齢から1を減じた年齢までの範囲に属する労働者数の2分の1
以下である場合をいう。)において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関す
る知識の継承を図ることを目的として、特定労働者である派遣労働者の特定等を行うとき
(当該派遣労働者について期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限
る。)。
嵐 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属す
る派遣労働者の特定等を行うとき。
k 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(60歳以上の者に限
る。)である派遣労働者の特定等を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇
用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する派遣労働者の特定等を行うとき(当該
特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に
限る )
(4) 派遣先が特定等に
律(昭和47年法律第1
男う
るい
けと
お」
に法
野等
分均
の「
用下
雇以
nノ
た号
当13
はならない措置等
① 派遣先は、特定等を行うに当た
女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法
)第5条及び第7条の趣旨に照らし行って
に
次
ば
え
例
は
て
つ
ア 特定等に当たって、その対象か
れ
ず
tV
の
女
男
ら
掲げる措置を行わないこと
かを排除すること
イ 特定等に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
ウ 特定に係る選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準につ
- 314 -
第8 派遣先の講ずべき措置等
いて男女で異なる取扱いをすること。
エ 特定等に当たって男女のいずれかを優先すること。
オ 派遣就業又は雇用の際に予定される求人の内容の説明等特定等に係る情報の提供につい
て、男女で異なる取扱いをすること又は派遣元事業主にその旨要請すること。
② 派遣先は、特定等に関する措置であって派遣労働者の性別以外の事由を要件とするもののう
ち、次に掲げる措置については、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施
が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が派遣
就業又は雇用の際に予定される雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場
合でなければ、これを講じてはならない。
ア 派遣労働者の特定等に当たって、派遣労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。
イ 将来、コース別雇用管理における総合職の労働者として当該派遣労働者を採用することが
予定されている場合に、派遣労働者の特定等に当たって、転居を伴う転勤に応じることがで
きることを要件とすること。
③ 紹介予定派遣に係る特定等に当たっては、将来、当該派遣労働者を採用することが予定され
ている雇用管理区分において、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない場合におい
ては、特定等の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して特定することその他男性と比
較して女性に有利な取扱いをすることは、均等法第8条に定める雇用の分野における男女の均
等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする措置(ポジティ
ブ・アクション)として、①にかかわらず、行って差し支えない。
④ 次に掲げる場合において①において掲げる措置を講ずることは、性別にかかわりなく均等な
機会を与えていない、又は性別を理由とする差別的取扱いをしているとは解されず、①にかか
わらず、行って差し支えない。
ア 次に掲げる職務に従事する派遣労働者に係る場合
i 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させる
ことが必要である職務
正 守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務(労働者派遣
事業を行ってはならない警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業
務を内容とするものを除く )
嵐 i及び正に掲げるもののほか、宗教上、風紀上、スポーツにおけ
の業務の性質上男女のいずれかのみに従事させることについて
あると認められる職務
れ
こ
他が
の性
そ要
上必
質の
性度
の程
技同
競と
るら
イ 労働基準法第61条第1項、第64条の2若しくは第64条の3第2項の規定に
を
性
女
nノ
よ
させることができず、又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第
規
の
条
3
就業
定に
より男性を就業させることができないことから、通常の業務を遂行するために、派遣労働者
の性別にかかわりなく均等な機会を与え又は均等な取扱いをすることが困難であると認めら
れる場合
ウ 風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合
その他特別の事情により派遣労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え又は均等な取扱
いをすることが困難であると認められる場合
(5) 派遣先が特定等に当たり障害者雇用促進法第34条の趣旨に照らし行ってはならない措置等
① 派遣先は、特定等を行うに当たっては、例えば次に掲げる措置を行わないこと。
ア 特定等に当たって、障害者であることを理由として、障害者をその対象から排除するこ
と。
イ 特定等に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
ウ 特定等に当たって、障害者でない者を優先すること。
エ 派遣就業又は雇用の際に予定される求人の内容の説明等の特定等に係る情報の提供につい
て、障害者であることを理由として障害者でない者と異なる取扱いをすること又は派遣元事
業主にその旨要請すること。
② ①に関し、特定等に際して一定の能力を有することを条件とすることについては、当該条件
が当該派遣先において業務遂行上特に必要なものと認められる場合には、行って差し支えない
こと。一方、特定等に当たって、業務遂行上特に必要でないにもかかわらず、障害者を排除す
るために条件を付すことは、行ってはならないこと。
③ ①及び②に関し、積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取
り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当しないこと。
④ 派遣先は、障害者に対し、面接その他特定することを目的とする行為を行う場合に、派遣元
事業主が障害者雇用促進法第36条の2又は第36条の3の規定による措置を講ずるため、派遣元
事業主から求めがあったときは、派遣元事業主と協議等を行い、可能な限り協力するよう努め
なければならないこと
- 315 -
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
1 概要
(1)労働基準法等の労働者保護法規の労働者派遣事業に対する適用については、原則として派遣中の労
働者と労働契約関係にある派遣元の事業主が責任を負う立場にある。しかしながら、派遣中の労働者
に関しては、その者と労働契約関係にない派遣先の事業主が業務遂行上の具体的指揮命令を行い、ま
た実際の労働の提供の場における設備、機械等の設置・管理も行っているため、派遣中の労働者につ
いて、その保護に欠けることのないようにする観点から、派遣先における具体的な就業に伴う事項で
あって、労働者派遣の実態から派遣元の事業主に責任を問うことの困難な事項、派遣労働者保護の実
効を期すうえから派遣先の事業主に責任を負わせることが適当な事項については、派遣先の事業主に
責任を負わせることとし、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、作業環境測定法、雇用の分野に
おける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護
を行う労働者の福祉に関する法律につき適用の特例等に関する規定を設けている(法第44条から第47
条の3まで)。
(2)適用の特例等に関する規定の基本原則は次のとおりである。
イ 労働基準法等の適用の特例に関する規定は、当該特例規定がなければ派遣元の事業主が負担しな
ければならない責任を、特定のものについて派遣先の事業主に負わせるものであり、このような特
例規定が存しない労働基準法等の規定については、すべて派遣元の事業主が責任を負担することに
なる。
ロ 労働基準法等の適用の特例に関する規定は、派遣元事業主が雇用し、派遣先は指揮命令は行うが
雇用はしていないという就業形態に着目して現に労働者派遣されている派遣中の労働者について適
用されるものであり(第10-1図参照)、派遣労働者であっても、労働者派遣されていない状態の
者についてはこれらの規定が及ばず、派遣元の事業主が労働基準法等の規定の適用をすべて受ける
ことになる。
また、これらの規定は労働者派遣という就業形態に着目して、労働基準法等に関する特例を定め
るものであり、労働者派遣事業の実施につき許可を受けた者である派遣元事業主が行う労働者派遣
だけではなく、それ以外の事業主が行う労働者派遣についても適用され、また業として行われる労
働者派遣だけでなく業として行われるのではない労働者派遣についても適用されることになるので
注意すること。
さらに、派遣中の労働者が派遣先の事業主と雇用契約関係にあると評価し得る状態にある場合に
ついては、労働者派遣されている状態とはいえず、派遣先と派遣労働者間についてはこの特例規定
の適用はない(この意味では、法第2条第1号の「労働者派遣」の観念とは若干異なるものである
(第1の1参照))。
派遣元の事業主、派遣先の事業主双方との間に二重に雇用契約関係が成立していると認められる
場合は、いわゆる在籍型出向と同じであり、派遣元の事業主及び派遣先の事業主がそれぞれ権限と
- 316 -
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
責任を有する事項について、労働基準法等が適用される(第1の1の(4)のロ参照)。
ハ 派遣先が労働基準法等の適用の対象となる事業でない場合(派遣先が事業を行っていない場合)
は、仮に派遣先が直接労働者を雇用する場合にも労働基準法等の適用はないことにかんがみ、特例
の適用はないこととなるので、このような派遣先に労働基準法等の規定が適用されることはない。
この場合には、原則どおり派遣元の事業主が労働基準法等における使用者責任をすべて負うこと
になる。
第10-1図 法第44条以下の特例等の規定が適用される場合
派 遣 元
労働基準法第9条に規定する
事業の事業主(労働者派遣を
業として行う必要はない。)
労働契約関係
労働者派遣契約
派 遣 先
労働基準法第9条に規定する
事業の事業主(同居の親族の
みを使用する事業の事業主を
含む。)
指揮命令関係
(労働契約関係なし。)
労働基準法第9条の労働者
派遣中の労働者
(3)具体的には、次のような特例規定等を通じて、派遣中の労働者の労働条件を確保している(第10-
1表参照)。
イ 労働時間、休憩、休日等の労働者の具体的就業に関連する事項については、派遣先の事業主が責
任を負う。ただし、「労働時間、休日の枠組みの設定」は、派遣元の事業主が行うこととしている。
また、労働基準法第38条の4の規定による裁量労働制及び労働基準法第41条の2の規定による高度
プロフェッショナル制度は、その性質上労働者派遣されている派遣労働者は適用を受けない。
ロ 安全衛生に関する事項については、作業環境の重要な要素である設備等の設置・管理、業務遂行
上の具体的指揮命令に関係することから、原則として派遣先の事業主が措置義務を負うものである
が、一般健康診断等の雇用期間中継続的に行うべき事項については、派遣元の事業主が義務を負う。
ハ 労働者派遣契約に定める就業条件に従って、派遣中の労働者を派遣先の事業主が指揮命令して労
働させたならば、一定の法規定に抵触することとなる場合には、当該労働者派遣をしてはならず、
違反者に対しては罰則を適用する。
ニ 派遣先の事業主が、派遣中の労働者について、特殊健康診断を行った場合には、当該健康診断の
結果を記録した書類を派遣元の事業主に送付しなければならない。
(4)法の施行に当たり、労働基準法等の適用に関する特例等の部分については、職業安定機関が事務を
- 317 -
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
担当することはなく、労働基準監督機関又は雇用均等行政機関が事務を担当することとなっている。
しかしながら、法の適正な施行を確保する観点から職業安定機関及び労働基準監督機関相互間にお
いて通報、通知を行うとともに、相談、苦情に対して迅速かつ適正な対応を図るため、職業安定機関
及び雇用均等行政機関相互間で連絡体制を整備する等、密接な連携を確保する(第14の1の(2)参照)
こととしており、また、職業安定機関が労働者派遣契約(第6参照)の締結、派遣元による派遣契約
の解除等(法第28条)、適正な派遣就業の確保のための派遣元事業主の配慮義務(法第31条)等に係
る適切な指導、改善命令の実施(第49条第1項)等を実施していく上で当該部分について十分な理解
を有することが必要不可欠である。
第10-1表 派遣中の労働者に関する派遣元・派遣先の責任分担
1 労働基準法
派遣元 派遣先
均等待遇
男女同一賃金の原則
強制労働の禁止
労働契約
賃金
1箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイ
ム制、1年単位の変形労働時間制の協定の締結
・届出、時間外・休日労働の協定の締結・届出
、事業場外労働に関する協定の締結・届出、専
門業務型裁量労働制に関する協定の締結・届出
時間外・休日、深夜の割増賃金
年次有給休暇
最低年齢
年少者の証明書
帰郷旅費(年少者)
産前産後の休業
均等待遇
強制労働の禁止
公民権行使の保障
労働時間、休憩、休日
労働時間及び休日(年少者)
深夜業(年少者)
危険有害業務の就業制限(年少者及び妊産婦等
)
坑内労働の禁止(年少者)
坑内業務の就業制限(妊産婦等)
- 318 -
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
徒弟の弊害の排除
職業訓練に関する特例
災害補償
就業規則
寄宿舎
申告を理由とする不利益取扱禁止
国の援助義務
法令規則の周知義務
労働者名簿
賃金台帳
記録の保存
報告の義務
産前産後の時間外、休日、深夜業
育児時間
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
徒弟の弊害の排除
申告を理由とする不利益取扱禁止
国の援助義務
法令規則の周知義務(就業規則を除く)
記録の保存
報告の義務
2 労働安全衛生法
派遣元 派遣先
職場における安全衛生を確保する事業者の責務
事業者等の実施する労働災害の防止に関する措
置に協力する労働者の責務
労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の
勧告等
総括安全衛生管理者の選任等
衛生管理者の選任等
安全衛生推進者の選任等
産業医の選任等
衛生委員会
職場における安全衛生を確保する事業者の責務
事業者等の実施する労働災害の防止に関する措
置に協力する労働者の責務
労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の
勧告等
総括安全衛生管理者の選任等
安全管理者の選任等
衛生管理者の選任等
安全衛生推進者の選任等
産業医の選任等
作業主任者の選任等
統括安全衛生責任者の選任等
元方安全衛生管理者の選任等
店社安全衛生管理者の選任等
安全委員会
衛生委員会
- 319 -
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
安全管理者等に対する教育等
安全衛生教育(雇入れ時、作業内容変更時)
危険有害業務従事者に対する教育
中高年齢者等についての配慮
事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助
健康診断(一般健康診断等、当該健康診断結果
についての意見聴取)
健康診断(健康診断実施後の作業転換等の措置
)
健康診断の結果通知
医師等による保健指導
医師による面接指導等
心理的な負担の程度を把握するための検査等(
検査の実施、結果の通知、医師による面接指導
、当該検査結果の意見聴取、作業転換等の措置
)
安全管理者等に対する教育等
労働者の危険又は健康障害を防止するための措
置
事業者の講ずべき措置
労働者の遵守すべき事項
事業者の行うべき調査等
元方事業者の講ずべき措置
特定元方事業者の講ずべき措置
定期自主検査
化学物質の有害性の調査
安全衛生教育(作業内容変更時、危険有害業務
就業時)
職長教育
危険有害業務従事者に対する教育
就業制限
中高年齢者等についての配慮
事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助
作業環境測定
作業環境測定の結果の評価等
作業の管理
作業時間の制限
健康診断(有害な業務に係る健康診断等、当該
健康診断結果についての意見聴取)
健康診断(健康診断実施後の作業転換等の措置
)
労働時間の状況の把握
病者の就業禁止
受動喫煙の防止
健康教育等
体育活動等についての便宜供与等
- 320 -
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
健康教育等
体育活動等についての便宜供与等
申告を理由とする不利益取扱禁止
報告等
法令の周知
書類の保存等
事業者が行う安全衛生施設の整備等に対す
る国の援助
疫学的調査等
快適な職場環境の形成のための措置
安全衛生改善計画等
機械等の設置、移転に係る計画の届出、審査等
申告を理由とする不利益取扱禁止
使用停止命令等
報告等
法令の周知
書類の保存等
事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国
の援助
疫学的調査等
3 じん肺法
派遣元 派遣先
じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務
粉じんにさらされる程度を軽減させるための措
置
作業の転換
転換手当
作業転換のための教育訓練
政府の技術的援助等
申告を理由とする不利益取扱禁止
報告
事業者及び労働者のじん肺の予防に関する適切
な措置を講ずる責務
じん肺の予防及び健康管理に関する教育
じん肺健康診断の実施*
じん肺管理区分の決定等*
じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務
粉じんにさらされる程度を軽減させるための措
置
作業の転換
作業転換のための教育訓練
政府の技術的援助等
法令の周知*
申告を理由とする不利益取扱禁止
報告
(注)*の規定は、粉じん作業に係る事業場への派遣が終了した後は派遣元に適用する。
4 作業環境測定法
- 321-
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
派遣元 派遣先
作業環境測定士又は作業環境測定機関による作
業環境測定の実施
5 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
派遣元 派遣先
妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益取 妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
扱いの禁止
職場における性的な言動に起因する問題に関す
る雇用管理上の措置
職場における妊娠、出産等に関する言動に起因
する問題に関する雇用管理上の措置
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
職場における性的な言動に起因する問題に関す
る雇用管理上及び指揮命令上の措置
職場における妊娠、出産等に関する言動に起因
する問題に関する雇用管理上及び指揮命令上の
措置
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
6 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
派遣元 派遣先
育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇
、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜
業の制限、所定労働時間の短縮措置等を理由と
する解雇その他不利益取扱いの禁止
職場における育児休業、介護休業等に関する言
動に起因する問題に関する雇用管理上の措置
育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇
、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜
業の制限、所定労働時間の短縮措置等を理由と
する不利益取扱いの禁止
職場における育児休業、介護休業等に関する言
動に起因する問題に関する雇用管理上及び指揮
命令上の措置
2 労働基準法の適用に関する特例等
(1)派遣中の労働者の派遣就業に関しては、次に掲げる規定については、派遣元の使用者のほか、派
遣先の使用者も使用者としての責任を負う(これらの規定に関する罰則の規定も適用される。)(法
第44条第1項)。
①均等待遇の規定(第3条)、②強制労働の禁止の規定(第5条)、③徒弟の弊害排除の規定
(第69条)
(2)派遣中の労働者の派遣就業に関しては、次に掲げる規定については、派遣先の使用者のみが使用者
としての責任を負う(これらの規定に基づいて発する省令の規定及びこれらの規定に関する罰則の規
- 322 -
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
定も適用される。)(法第44条第2項)。
①公民権行使の保障の規定(第7条)、②労働時間の規定(第32条)、③災害等による臨時の必要
がある場合の時間外労働等の規定(第33条)、④休憩の規定(第34条)、⑤休日の規定(第35条)、
⑥時間外及び休日の労働の規定(第36条第1項及び第6項)、⑦労働時間及び休憩の特例の規定(第
40条)、⑧労働時間等に関する規定の適用除外の規定(第41条)、⑨年少者に係る労働時間及び休
日の規定(第60条)、⑲年少者に係る深夜業の規定(第61条)、⑪年少者に係る危険有害業務の就
業制限の規定(第62条)、⑫年少者に係る坑内労働の禁止の規定(第63条)、⑬女性に係る坑内労
働の禁止の規定(第64条の2)、⑭妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限の規定(第64条の3)、
⑮妊産婦に係る時間外労働、休日労働及び深夜業の規定(第66条)、⑱育児時間の規定(第67条)、
⑰生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置の規定(第68条)
なお、この場合における変形労働時間制の定め並びに時間外・休日労働の協定の締結及び届出は派
遣元の使用者が行うこととしており、派遣先の使用者は派遣元の使用者が定めた変形労働時間制によ
り労働させ、また、締結した時間外・休日労働の協定の範囲内において時間外・休日労働をさせるこ
とができる。時間外労働の上限規制の適用が猶予される事業・業務に関する規定(第139条から第142
条まで)は、派遣先の事業・業務について判断することとなるため、派遣元においては、派遣先の事
業や業務の内容を踏まえて、時間外・休日労働の協定を締結する必要がある。
(3)派遣元の使用者は、派遣先の使用者が労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従って派遣中の労
働者を労働させれば、次に掲げる規定に抵触することとなる場合においては、当該労働者派遣をして
はならない(法第44条第3項)。
①労働時間の規定(第32条)、②休憩の規定(第34条)、③休日の規定(第35条)、④時間外労働
及び休日労働の制限の規定(第36条第6項)、⑤労働時間及び休憩の特例の規定(第40条)、⑥年
少者に係る深夜業の規定(第61条)、⑦年少者に係る危険有害業務の就業制限の規定(第62条)、
⑧年少者に係る坑内労働の禁止の規定(第63条)、⑨妊産婦等に係る坑内業務の就業制限の規定(第
64条の2)、⑲妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限の規定(第64条の3)、⑪医業に従事する
医師(医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者に限る。)の時間外労働及び
休日労働の制限の規定(141条第3項)
派遣元の使用者がこれに違反して労働者派遣を行い、派遣先の使用者が違反行為を実行した場合
(規定に抵触すれば足り、故意、処罰は必要ではない。)については、派遣元の使用者が派遣先の使
用者に適用される規定に違反したものとして、これらの規定に係る罰則の規定が適用される(法第44
条第4項)。
(4)労働基準法の適用に関する特例等により適用される同法の規定に関しては、次に掲げる規定は、所
要の読替えを行った上で適用される(これらの規定に関する罰則の規定も適用される。)(法第44条
第5項)。
①監督組織の規定(第99条及び第100条)、②労働基準監督官の権限の規定(第101条及び102
条)、③監督機関に対する申告の規定(第104条)、④報告の義務の規定(第104条の2)、⑤国の
- 323 -
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
援助義務の規定(第105条の2)、⑥法令等の周知義務の規定(第106条)、⑦記録の保存の規定
(第109条)、⑧国及び公共団体についての適用の規定(第112条)
3 労働安全衛生法の適用に関する特例等
(1)次に掲げる規定については、派遣元の事業者のみならず、派遣先の事業者も事業者としての義務を
負う(これらの規定に関する罰則の規定も適用される。)(法第45条第1項)。
①事業者等の責務等の規定(第3条第1項及び第4条)、②総括安全衛生管理者の規定(第10条)、
③衛生管理者の規定(第12条)、④安全衛生推進者等の規定(第12条の2)、⑤産業医等の規定(第
13条及び第13条の2)、⑥衛生委員会の規定(第18条)、⑦安全管理者等に対する教育等の規定(第
19条の2)、⑧作業内容変更時の安全衛生教育の規定(第59条第2項)、⑨危険有害業務従事者に
対する安全衛生教育の規定(第60条の2)、⑲中高年齢者等についての配慮の規定(第62条)、⑪
健康診断実施後の措置の規定(第66条の5第1項)、⑫健康教育等の規定(第69条)、⑬体育活動
等についての便宜供与等の規定(第70条)
(2)派遣中の労働者についての派遣元の事業における安全衛生管理体制に係る次に掲げる規定を派遣
元の事業者に適用する場合、派遣元の事業者の義務の範囲は、(1)により派遣先の事業者に課された義
務以外に限られる(法第45条第2項)。
①総括安全衛生管理者の規定(第10条第1項)、②衛生管理者の規定(第12条第1項)、③安全衛
生推進者等の規定(第12条の2)、④産業医の規定(第13条第1項)、⑤衛生委員会の規定(第18
条第1項)
(3)次に掲げる規定については、派遣先の事業者のみが事業者としての義務を負う(これらの規定に基
づいて発する政・省令の規定及びこれらの規定に関する罰則の規定も適用される)(法第45条第3項
及び第5項)。
①安全管理者の規定(第11条)、②作業主任者の規定(第14条)、③統括安全衛生責任者の規定(第
15条)、④元方安全衛生管理者の規定(第15条の2)、⑤店社安全衛生管理者の規定(第15条の3)、
⑥安全委員会の規定(第17条)、⑦危険防止等のための事業者の講ずべき措置等の規定(第20条か
ら第27条まで及び第31条の3)、⑧事業者の行うべき調査等(第28条の2)、⑨元方事業者等の講
ずべき措置等の規定(第29条から第30条の3まで)、⑲厚生労働省令への委任の規定(第36条(第
30条第1項及び第4項、第30条の2第1項及び第4項並びに第30条の3第1項及び第4項の部分に
限る。))、⑪定期自主検査の規定(第45条(第2項を除く))、⑫化学物質の有害性の調査の規
定(第57条の3から第58条まで)、⑬特別の安全衛生教育の規定(第59条第3項)、⑭指導監督者
に対する安全衛生教育の規定(第60条)、⑮就業制限の規定(第61条第1項)、⑱作業環境測定等
の規定(第65条及び第65条の2)、⑰作業の管理の規定(第65条の3)、⑱作業時間の制限の規定
(第65条の4)、⑲健康診断等の規定(第66条第2項から第5項まで、第66条の3及び第66条の4)、
⑳病者の就業禁止の規定(第68条)、㊧受動喫煙の防止(第68条の2)、⑳快適な職場環境形成の
ため事業者が講ずべき措置の規定(第71条の2)、⑳安全衛生改善計画の規定(第78条及び第79条)、
- 324 -
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
⑳安全衛生診断の規定(第80条)、⑮建設物の設置等に関する計画の届出等の規定(第88条)、⑳
建設物の設置等に関する計画についての厚生労働大臣等の審査等の規定(第89条及び第89条の2)
(4)派遣先の事業に関しては、一定の機械等についての特定自主検査の規定(第45条第2項)は適用さ
れるが、当該検査を実施する者に派遣中の労働者をあててはならない(法第45条第4項)。
(5)派遣元の事業に関する(3)の規定及び特定自主検査の規定(第45条第2項)の適用については、派遣
中の労働者は派遣元労働者と労働契約関係にないものとみなす。これにより、(3)の規定について事業
者が負う義務は、派遣先の事業者のみが負う。また、特定自主検査(第45条第2項)を、派遣元の事
業者は派遣中の労働者に実施させることはできない(法第45条第5項)。
(6)派遣元の事業者は、派遣先の事業者が労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従って派遣中の労
働者を労働させれば、次に掲げる規定に抵触することとなる場合においては、当該労働者派遣をして
はならない(法第45条第6項)。
①特別の安全衛生教育の規定(第59条第3項)、②就業制限の規定(第61条第1項)、③作業時間
の制限の規定(第65条の4)、④病者の就業禁止の規定(第68条)
派遣元の事業者がこれに違反して労働者派遣を行い、派遣先の事業者がこれらの規定に抵触した場
合(規定に抵触する事実があれば足り、処罰は必要でない。)、派遣元の事業者は当該規定に違反し
たものとして、当該規定に係る罰則の規定が適用される(法第45条第7項)。
(7)(1)、(3)及び(4)のほかにも、派遣先の事業に関しては、次に掲げる規定が所要の読替えを行った上
で適用される(法第45条第8項)。
①ジョイントベンチャーについての適用の特例規定(第5条第1項及び第4項)、②安全衛生責任
者の規定(第16条第1項)、③安全衛生委員会の規定(第19条)
(8)派遣元の事業に関し、安全衛生委員会の設置に係る規定(第19条第1項)は、所要の読替えを行っ
た上で適用される(法第45条第9項)。
(9)派遣先の事業者は、第66条第2項、第3項及び第4項の規定により、派遣中の労働者に対し健康診
断を行ったとき、又は当該派遣中の労働者から同条第5項ただし書の規定による健康診断の結果を証
明する書面の提出があったときは、遅滞なくこれらの健康診断の結果を記載した書面を作成し、派遣
元の事業者に送付しなければならない(法第45条第10項)。
また、当該書面の送付を受けた派遣元の事業者は、当該書面を一定期間保存しなければならない(法
第45条第11項)。
これらの規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられ(法第45条第12項)、また、法人の代
表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、これ
らの義務に違反する行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人又は人に対しても同様の
罰金刑が科される(法第45条第13項)。
(10)派遣先の事業者は、(3)の第66条の4の規定により、医師等の意見を聴いたときは、遅滞なく派遣
元の事業者に通知しなければならない(法第45条第14項)。
(11)労働安全衛生法の適用に関する特例等により適用される同法の規定に関しては、次に掲げる規定
- 325 -
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
は、所要の読替えを行った上で適用される(これらの規定に関する罰則の規定も適用される。)(法
第45条第15項)。
①労働災害の防止に関する厚生労働大臣の勧告等の規定(第9条)、②技術上の指針等に関する厚
生労働大臣の指導等の規定(第28条第4項)、③注文者の講ずべき措置の規定(第31条第1項及び第
31条の2)、④注文者の違法な指示の禁止の規定(第31条の4)、⑤請負人の講ずべき措置の規定(第
32条)、⑥機械等貸与者の講ずべき措置の規定(第33条第1項)、⑦建築物貸与者の講ずべき措置の
規定(第34条)、⑧安全衛生教育に関する国の援助に関する規定(第63条)、⑨健康診断実施後の措
置のための指針に関する厚生労働大臣の指導等の規定(第66条の5第3項)、⑲健康の保持増進のた
めの指針に関する厚生労働大臣の指導等の規定(第70条の2第2項)、⑪快適な職場環境の形成のた
めの指針に関する厚生労働大臣の指導等に関する規定(第71条の3第2項)、⑫快適な職場環境の形
成に関する国の援助の規定(第71条の4)、⑬労働基準監督署長及び労働基準監督官の規定(第90条)、
⑭労働基準監督官の権限の規定(第91条第1項及び第92条)、⑮産業安全専門官及び労働衛生専門官
の規定(第93条第2項及び第3項)、⑱労働者の申告の規定(第97条)、⑰使用停止命令等の規定(第
98条第1項及び第99条第1項)、⑱労働災害の再発防止のための講習の指示の規定(第99条の2第1
項及び第2項)、⑲報告等の規定(第100条)、⑳法令の周知の規定(第101条)、⑳ガス工作物等設
置者の義務の規定(第102条)、⑳書類の保存等の規定(第103条第1項)、⑳国の援助の規定(第106
条第1項)、㊧疫学的調査等の規定(第108条の2第3項)、⑳適用除外の規定(第115条第1項)
(12)(1)~(11)まで((10)を除く。)の労働安全衛生法の適用の特例等に違反した者は、労働安全衛生
法においてこれに相当する規定に違反した者と同じく、労働安全衛生法に基づく免許の取消処分事由、
指定の欠格事由等に該当するに至った者として取り扱う(法第45条第16項)。
4 じん肺法の適用に関する特例等
(1)粉じん作業に係る派遣先の事業において常時粉じん作業に従事している又はしたことのある派遣
中の労働者については派遣先の事業者は次に掲げる規定に係る措置を講ずべき義務を負う(これらの
規定に関する罰則の規定も適用される。)(法第46条第1項)
①じん肺の予防の規定(第5条)、②じん肺に関する予防及び健康管理のための教育の規定(第6
条)、③じん肺健康診断の規定(第7条から第9条の2まで)、④労働者の受診義務の規定(第11条)、
⑤事業者によるエックス線写真等の提出の規定(第12条)、⑥じん肺管理区分の決定手続、通知等の
規定(第13条から第16条まで)、⑦ェックス線写真等の提出命令の規定(第16条の2)、⑧じん肺健
康診断に関する記録の作成及び保存等の規定(第17条)、⑨法令の周知の規定(第35条の2)
これにより、派遣先の事業者が負う義務については、派遣元の事業者が負うことはない(法第46条
第2項)。
また、派遣先の事業者が派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行った場合は、その限度におい
て、派遣先の事業者にあっては労働安全衛生法第66条第2項の有害な業務に係る健康診断を、派遣元
の事業者にあっては同条第1項又は第2項の健康診断を行うことを要しない(法第46条第3項)。
- 326 -
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
(2)粉じん作業に係る派遣先の事業において常時粉じん作業に従事している又はしたことのある派遣
中の労働者の派遣就業に関しては、次に掲げる規定については、派遣元の事業者のみならず派遣先の
事業者も事業者としての義務を負う(これらの規定に関する罰則の規定も適用される。)(法第46条
第4項)。
①じん肺健康診断の結果に基づく、労働者の健康保持に関する責務の規定(第20条の2)、②粉じ
んにさらされる程度を低減するための措置の規定(第20条の3)、③作業の転換の規定(第21条)、
④作業転換のための教育訓練の規定(第22条の2)
(3)粉じん作業に係る派遣先の事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、転換手当の規定
(第22条)による義務は派遣元の事業者が負う(法第46条第5項)。
(4)派遣先の事業において常時粉じん作業に従事したことのある労働者であって、現に派遣元の事業に
雇用され、かつ、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者(当該派遣先の事業において現に粉じん
作業以外の作業に常時従事している者を除く。)については、派遣元の事業者が、次に掲げる規定に
係る措置を講ずべき義務を負う(これらの規定に係る罰則の規定も適用される。)(法第46条第6項)。
①じん肺健康診断の実施等の規定(第8条から第11条まで)、②事業者によるエックス線写真等の
提出の規定(第12条)、③じん肺管理区分の決定手続、通知等の規定(第13条及び第14条)、④じん
肺管理区分の決定等の申請の規定(第15条第3項及び第16条)、⑤ェックス線写真等の提出命令の規
定(第16条の2)、⑥記録の作成及び保存の規定(第17条)、⑦じん肺健康診断の結果に基づく、労
働者の健康を保持するための事業者の責務の規定(第20条の2)、⑧作業転換のための教育訓練の規
定(第22条の2)、⑨法令の周知の規定(第35条の2)
(5)派遣先の事業者は、派遣中の労働者に対して、じん肺健康診断を実施し(第7条、第8条、第9条
及び第9条の2)、又は、当該派遣中の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書
面の提出があったときは、じん肺健康診断に関する記録(第17条第1項)に基づいて、この記録の写
しを作成し、これを遅滞なく派遣元の事業者に送付しなければならない。また、派遣先の事業者が都
道府県労働局長から派遣中の労働者に係るじん肺管理区分の決定の通知を受けたときは、当該通知の
内容を記載した書面を作成し、遅滞なくこれを派遣元の事業者に送付しなければならない(法第46条
第7項)。
(6)(5)により書面の送付を受けた派遣元の事業者は、派遣先の事業者による健康診断の結果を記載した
書面については、7年間、じん肺管理区分の決定の通知の内容を記載した書面については3年間、こ
れを保存しなければならない(法第46条第8項)。
(7)派遣元の事業者は、派遣中の労働者で常時粉じん作業に従事するもの(じん肺管理区分が管理
2、管理3又は管理4と決定されている労働者を除く。)が労働安全衛生法第66条第1項の健康診断
又は第2項の健康診断(派遣先の事業者が行うものを除く。)において、じん肺の所見があり、又
はじん肺にかかっている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を派遣先の事業者に通知
しなければならない(法第46条第9項)。
(8)(5)、(6)又は(7)の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(法第46条第10項)。
- 327 -
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
(9)法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関
して、(5)、(6)又は(7)に述べた規定に違反する行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法
人又は人に対しても同様の罰金刑が科せられる(法第46条第11項)。
(10)じん肺法の適用に関する特例等により適用される同法の規定に関しては、次に掲げる規定は、所要
の読替えを行った上で適用される(これらの規定に関する罰則の規定も適用される。)(法第46条第
12項)。
①政府の技術的援助等に関する規定(第32条)、②じん肺診査医、労働基準監督署長及び労働基準
監督官に関する規定(第39条から第43条まで)、③労働者の申告の規定(第43条の2)、及び報告の
規定(第44条)である。
(11)粉じん作業に係る事業を行う派遣元の事業者が、派遣先の事業において常時粉じん作業に従事し
たことのある労働者に対してじん肺健康診断を行った場合は、その限度において、派遣先の事業者に
あっては労働安全衛生法第66条第2項の有害な業務に係る健康診断を、派遣元の事業者にあっては同
条第1項又は第2項の健康診断を行うことを要しない(これらの規定に関する罰則の規定も適用され
る。)(法第46条第13項)。
5 作業環境測定法の適用の特例
(1)派遣中の労働者に関する作業環境測定法の適用については、派遣先の事業者が同法上の事業者に含
まれるものとして次に掲げる規定を適用する(法第47条第1項)。
①作業環境測定の実施等の総則規定(第1条から第4条まで)、②作業環境測定士名簿の閲覧の規
定(第8条第2項)、③行政機関による監督、指導、援助等の雑則の規定(第38条から第51条まで)、
④罰則の規定(第52条から第56条まで)
(2)3の労働安全衛生法の適用の特例等又は(1)の作業環境測定法の適用の特例に違反した者は、労働
安全衛生法又は作業環境測定法においてこれに相当する規定に違反した者と同じく、作業環境測定士
の登録の欠格事由等に該当するに至った者として取り扱う(法第47条第2項)
6 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用の特
例
派遣中の労働者の派遣就業に関しては、次に掲げる規定については、派遣元の事業主のほか、派遣
先の使用者も事業主としての責任を負う(法第47条の2)。
①妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止の規定(第9条第3項)、②職場における
性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮の規定(第11条第1項)、③職場における妊
娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮の規定(第11条の2第1項)、
④妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置の規定(第12条及び第13条第1項)
- 328 -
第9 労働基準法等の適用に関する特例等
7 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用
の特例
派遣中の労働者の派遣就業に関しては、次に掲げる規定については、派遣元の事業主のほか、派遣
先の使用者も事業主としての責任を負う(法第47条の3)。
①育児休業を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止の規定(第10条)、②介護休業を理由とする
解雇その他不利益取扱いの禁止の規定(第16条)、③子の看護休暇を理由とする解雇その他不利益取
扱いの禁止の規定(第16条の4)、④介護休暇を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止の規定(第
16条の7)、⑤所定外労働の制限を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止の規定(第16条の10)、
⑥時間外労働の制限を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止の規定(第18条の2)、⑦深夜業の
制限(第20条の2)、⑧所定労働時間の短縮措置等(第23条の2)、⑨職場における育児休業、介
護休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮の規定(第25条)
- 329 -
第10 紛争の解決
第10 紛争の解決
1 苦情の自主的解決
(1)概要
イ 派遣元事業主は、次の①~⑥に掲げる事項に関し、派遣労働者からの苦情の申出を受けたと
き、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたとき
は、その自主的な解決を図るように努めなければならない(法第47条の4第1項)
① 派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保の措置(第30条の3)
② 一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保の措置(法第30条の4)
③ 雇い入れようとするときの待遇に関する事項の説明(法第31条の2第2項)
④ 労働者派遣をしようとするときの待遇に関する事項の説明(法第31条の2第3項)
⑤ 派遣労働者から求めがあったときの待遇に関する事項の説明(法第31条の2第4項)
⑥ 派遣労働者が待遇に関する事項の説明を求めたことを理由とする不利益な取扱いの禁止
(法第31条の2第5項)
ロ 派遣先は、次の①及び②に掲げる事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、
その自主的な解決を図るように努めなければならない(法第47条の4第2項)。
① 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施(第40条第2項)
② 給食施設、休憩室及び更衣室の利用の機会の付与(法第40条第3項)
(2)意義
イ 派遣労働者からの苦情や派遣労働者と派遣元事業主又は派遣労働者と派遣先の間の紛争(主
張が一致せず、対立している状態をいう。以下同じ。)のうち公正な待遇の確保に関するもの
については、その解決方法が様々であり、本来当事者間で自主的に解決することが望ましいこ
とに鑑み、当該紛争についてまず当事者間で自主的解決の努力を行うこととしたものである。
ロ なお、苦情の自主的解決の努力は、3の紛争の解決の援助や4の調停の開始の要件とされて
いるものではないが、これらの手続の前に行われることが望ましい。
2 紛争の解決の促進に関する特例
1の(1)のイの(力~⑥の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び1の(1)のロ
の(力及び②の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争(以下この章において「待遇関連紛
争」という。)については、個別労働関係紛争解決促進法第4条、第5条及び第12条から第19条の
までの規定は適用せず、法第47条の6から第47条の9までに定めるところによる(法第47条の
5)。
派遣労働者の公正な待遇の確保に関する私法上の紛争は、派遣先の通常の労働者との不合理な待
遇差の是正や差別的取扱いの禁止等に関する紛争であり、その解決に向けては、より広範な検証や制
- 330 -
第10 紛争の解決
度面に関する専門的な知識を要するものであり、事実認定を行った上で必要な見直し案の調停案を示
し、受諾の勧告を行うことが有効であることから、個別労働関係紛争解決促進法の適用を除外し、専
門性を対応できる機能を併せ持った調停等の対象とすることとしたものである。
3 紛争の解決の援助
(1)概要
都道府県労働局長は、待遇関連紛争に関し、これらの紛争の当事者の双方又は一方からその解
決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をす
ることができる(法第47条の6第1項)。
派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が都道府県労働局長に援助を求めたことを理由とし
て、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない(法第47条の6第2項)。
(2)意義
イ 派遣労働者の公正な待遇の確保に関する紛争を簡易で迅速に解決できるようにするため、知
見等を有する都道府県労働局長が、紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告を行うこ
とができることとしたものである。
ロ 「紛争の当事者」とは、現に紛争の状態にある派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先をい
い、第三者である労働組合等は含まれない。
ハ 「助言、指導又は勧告」は、紛争の解決を図るため、当該紛争の当事者に対して具体的な解
決策を提示し、これを自発的に受け入れることを促す手段として定められたものであり、紛争
の当事者にこれに従うことを強制するものではない。
(3)援助を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止
「不利益な取扱い」とは、解雇、配置転換、降格、昇給停止、出勤停止、労働契約の更新拒否
等をいうこと。
4 調停
(1)概要
都道府県労働局長は、待遇関連紛争について、これらの紛争の当事者の双方又は一方から調停
の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員
会に調停を行わせるものとする(法第47条の7第1項)。
派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が調停の申請をしたことを理由として、当該派遣労働
者に対して不利益な取扱いをしてはならない(法第47条の7第2項)。
(2)意義
イ 苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助に加え、公正、中立な第三者
機関による調停による解決を図ることとしたものである。
ロ 「紛争の当事者」とは、3の(2)のロを参照のこと。
- 331-
第10 紛争の解決
ハ 「調停」とは、紛争の当事者の間に第三者が関与し、当事者の互譲によって紛争の現実的な
解決を図ることを基本とするものであり、行為が法律に抵触するか否か等を判定するものでは
なく、むしろ行為の結果生じた損害の回復等について現実的な解決策を提示して、当事者の歩
み寄りにより当該紛争を解決しようとするものであること。
(3)調停の対象となる事案
次の要件に該当する事案については、「当該紛争の解決のために必要があると認め」られない
ものとして、原則として、調停に付すことは適当であるとは認められない。
イ 申請が、当該紛争に係る事業主の措置が行われた日(継続する措置の場合にあってはその
終了した日)から1年以上を経過した紛争に係るものであるとき
ロ 申請に係る紛争が既に司法的救済又は他の行政的救済に係属しているとき(紛争の当事者
双方に、当該手続よりも調停を優先する意向がある場合を除く。)
ハ 集団的な労使紛争に関係したものであるとき
都道府県労働局長が「紛争の解決のために必要がある」か否かを判断するに当たっては、上記
のイ~ハに該当しない場合は、法第47条の4による自主的解決の努力の状況も考慮の上、原則と
して調停を行う必要があると判断されるものである。
(4)調停の申請をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止
「不利益取扱い」とは、3の(3)を参照のこと。
(5)調停の手続
調停の手続については、法第47条の8において準用する男女雇用機会均等法第19条、第20条
第1項及び第21条から第26条までの規定並びに則第46条の2の規定において準用する男女の均
等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第2号)第3条から第12
条までの規定に基づき行われる。
イ 個別労働関係紛争解決促進法第6条第1項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の
会長は、調停委員のうちから、法第47条の7第1項の規定により委任を受けて待遇関連紛争に
ついての調停を行うための会議(以下「派遣労働者待遇調停会議」という。)を主任となって
主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を指名する。また、主任調停委員に事故
があるときは、あらかじめその指名する調停委員が、その職務を代理する。
ロ 派遣労働者待遇調停会議は、調停委員2人以上の出席をもって、主任調停委員が招集する非
公開の会議である。また、派遣労働者待遇調停会議の庶務は、都道府県労働局職業安定部(東
京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、需給調整事業部)において処理する。
ハ 調停を申請しようとする者は、調停申請書を当該調停に係る紛争の当事者(以下「関係当事
者」という。)である労働者に係る事業所(派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争にあって
は派遣労働者を雇用する派遣元事業主の事業所、派遣労働者と派遣先との間の紛争にあっては
派遣労働者が就業する派遣先の事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなけれ
ばならない。都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、そ
- 332 -
第10 紛争の解決
の旨を会長及び主任調停委員に通知すること。また、都道府県労働局長は、委員会に調停を行
わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停
を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を書面によって通知すること。
ニ 調停は、3人の調停委員により行われ、当該調停委員は、委員会のうちから、会長によりあ
らかじめ指名される。
ホ 委員会は、調停のために必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事
業所に雇用される労働者その他の参考人(以下「関係当事者等」という。)の出頭を求め、そ
の意見を聴くことができる。ただし、この「出頭」は強制的な権限に基づくものではなく、相
手の同意によるものであり、必ず関係当事者等(法人である場合には、委員会が指定する者)
により行われることが必要である。「その他の参考人」とは、関係当事者である派遣労働者が
就業している派遣先に雇用されている労働者、当該派遣先で就業する関係当事者ではない派遣
労働者、関係当事者である派遣労働者が雇用されている事業所に過去に雇用されていた者、関
係当事者である派遣労働者と異なる事業所に雇用されている労働者等を指す。
委員会から出頭を求められた関係当事者等は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴って
出頭することができる。補佐人は、主任調停委員の許可を得て陳述を行うことができる。ただ
し、補佐人の陳述は、あくまでも関係当事者等の主張や説明を補足するためのものであり、補
佐人が自ら主張を行ったり、関係当事者等に代わって意思表示を行ったりすることはできな
い。
へ 委員会から出頭を求められた関係当事者等は、主任調停委員の許可を得て当該事件について
意見を述べることができるほか、他人に代理させることができる。他人に代理させることにつ
いて主任調停委員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面
に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して主任調停委員に提出しなければならない。
ト 委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者等に対
し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
チ 委員会は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停委員に行わせること
ができる。「調停の手続の一部」とは、現地調査や、提出された文書等の分析・調査、関係当
事者等からの事情聴取等を指す。また、委員会は、必要があると認めるときは、当該事件の事
実の調査を都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、
需給調整事業部)の職員に委嘱することができる。
リ 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置か
れる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を
代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴くこと。「主要な労働者団体又は事業主
団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者」については、主要な労
働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代
表する者の氏名を求めること。関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名
- 333 -
第10 紛争の解決
は、事案ごとに行うこと。指名を求めるに際しては、管轄区域内の全ての主要な労働者団体及
び事業主団体から指名を求めなければならないものではなく、調停のため必要と認められる範
囲で、主要な労働者団体又は事業主団体のうちの一部の団体の指名を求めることで足りる。委
員会が氏名を求めた場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べ
る者の氏名及び住所を委員会に通知する。
ヌ 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。調停案の
作成は、調停委員の全員一致をもって行う。また、「受諾を勧告する」とは、両関係当事者に
調停案の内容を示し、その受諾を勧めるものであり、その受諾を義務付けるものではない。委
員会は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定め
て行う。
関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印した書面を委員会に提
出しなければならない。この「書面」は、関係当事者が調停案を受諾した事実を委員会に対し
て示すものであって、それのみをもって関係当事者間において民事的効力をもつものではな
い。
ル 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を
打ち切ることができ、その場合、その旨を関係当事者に通知しなければならない。「調停によ
る解決の見込みがないと認めるとき」とは、調停により紛争を解決することが期待し難いと認
められる場合や調停により紛争を解決することが適当でないと認められる場合をいい、具体的
には、調停開始後長期の時間的経過を見ている場合、当事者の一方が調停に非協力的で再三に
わたる要請にもかかわらず出頭しない場合のほか、調停が当該紛争の解決のためでなく労使紛
争を有利に導くために利用される場合等が原則としてこれに含まれる。
(6)時効の完成猶予
調停が打ち切られた場合に、当該調停の申請をした者が打切りの通知を受けた日から30 日以内
に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停申請書を都道府県労働局長に提
出した日(調停の過程において申請人が調停を求める事項の内容を変更又は追加した場合には、
当該変更又は追加したとき)に遡り、時効の完成が猶予される。
(7)訴訟手続の中止
当事者が調停による紛争解決が適当であると考えた場合であって、調停の対象となる紛争のう
ち民事上の紛争であるものについて訴訟が係属しているとき、当事者が和解交渉に専念する環境
を確保することができるよう、受訴裁判所は、訴訟手続を中止することができる。
具体的には、待遇関連紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属
する場合において、次のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがある
ときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨を決定することができ
る。
イ 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。
- 334 -
第10 紛争の解決
ロ イの場合のほか、関係当事者間に調停によって当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
なお、受訴裁判所は、いっでも訴訟手続を中止する旨の決定を取り消すことができる。また、
関係当事者の申立てを却下する決定及び訴訟手続を中止する旨の決定を取り消す決定に対しては
不服を申し立てることができない。
(8)資料提供の要求等
委員会は、当該委員会に継続している事件の解決のために必要があると認めるときは、国の
機関の地方支分部局や都道府県等の地方自治体等の関係行政庁に対し、資料の提供や便宜の供
与等を求めることができる。
- 335 -
第11個人情報保護法の遵守等
第11個人情報保護法の遵守等
1 概要
(1)派遣元事業主による個人情報の適正な取扱いについては、法第24条の3及び第24条の4におい
て、労働者の個人情報の取扱いに関する規定及び秘密を守る義務に関する規定が設けられ、さらに、
「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(第11において「派遣元指針」という。)第2の
10の(1)及び(2)において、派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者(第11において「派遣労
働者等」という。)の個人情報の取扱いに関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事
項が定められている(第5の6及び第7の26参照)。
(2)また、派遣元指針第2の11の(3)において、派遣元事業主による個人情報の保護の一層の促進等
を図る見地から、法に基づく事業実施上の責務の一つとして、派遣元事業主は、個人情報取扱事業
者に該当する場合にあっては、個人情報保護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければなら
ないこととされるとともに、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業
者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めることとされている。
(3)なお、平成29年5月30日に全面施行の個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号。
以下「個人情報保護法等改正法」という。)により、個人情報保護法に違反した派遣元事業主につ
いては、個人情報保護法に基づく個人情報保護委員会による指導・助言等の対象となることとなっ
た。また、法に違反する場合には、法に基づく指導・助言等の対象ともなり得るものである。
2 個人情報保護法等の規定並びに派遣元事業主が講ずべき措置及びその主な留意
点等
派遣元事業主に課せられる義務に係る個人情報保護法及び個人情報保護法施行令の規定並びに派
遣元事業主が講ずべき措置及びその主な留意点等については、以下のとおりであること。
(1)個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主
① 個人情報保護法等の遵守について
派遣元事業主は、派遣元指針第2の11の(3)により、個人情報取扱事業者に該当する場合には、
個人情報保護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならないこととされていること。
具体的には、個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主は、個人情報保護委員会が定める「個
人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」(http://www.ppc.go.jp/personal/1egal/)
等に留意しなければならない。また、法第24条の3及び派遣元指針第2の11の(1)及び(2)
の遵守に当たって留意すべき点は第5の6のとおりであること。
なお、個人情報保護法等改正法により、取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者に対して
も個人情報保護法が適用されることとされている点に留意すること。
- 336 -
第11個人情報保護法の遵守等
② 漏えい等の事案が発生した場合等の対応について
「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」(平成29年個人情報保護委
員会告示第1号)等により対応すること。
(2)個人情報取扱事業者に該当しない派遣元事業主
派遣元事業主は、派遣元指針第2の11の(3)により、個人情報取扱事業者に該当しない場合で
あっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めることとされて
いること。
なお、法第24条の3及び派遣元指針第2の11の(1)及び(2)に定める派遣労働者等の個人情報
の取扱いに係る規定については、個人情報取扱事業者に該当しない派遣元事業主であっても、遵
守する必要があるものであること。
- 337 -
第12 違法行為の防止、摘発
第12 違法行為の防止、摘発
1 概要
労働者派遣事業の適正な運用を確保し労働力需給の適正な調整を図るとともに、派遣労働者の適
正な就業条件を確保することにより、その保護及び雇用の安定を図るため、派遣労働者等からの相談
に対する適切な対応や、派遣元事業主、派遣先等に対する労働者派遣事業制度の周知徹底、指導、助
言及び指示を通じて違法行為の防止を行うとともに法違反を確認した場合には、所要の指導、助言、
指示、行政処分又は告発を行うこととする。
2 労働者等の相談への対応
(1)概要
公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言
その他の援助を行うことができる(法第52条)。
(2)意義
イ 派遣就業に関し、適切な就業条件が確保されていない、あるいは違法行為があるといった相
談が派遣労働者等から公共職業安定所に対して行われた場合には、公共職業安定所は当該問題
事案を解消するための助言を行う。
なお、派遣就業に関する労働者等からの相談については、公共職業安定所で受け付け、助言を
行うものであるが、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する事
実確認、所要の指導及び助言、行政処分等の措置については、原則として都道府県労働局が講ず
るものである(則第55条)。
そのため、違法性の疑いのある事業主に対する指導等に関する相談については、都道府県労働
局で受け付け、公共職業安定所で受け付けた場合には、都道府県労働局の需給調整事業担当の相
談窓口へ誘導する。
ロ 「労働者等」とは、派遣労働者のほか、派遣労働者として雇用されることを予定する者、以
前に派遣労働者として雇用されていた者も含むものである。
(3)不利益取扱いの禁止
労働者派遣を行う事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者が、法又は法に基づく命令の
規定に違反していた場合については、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することが
できるが、当該申告を行ったことを理由として、労働者派遣を行う事業主又は労働者派遣の役務
の提供を受ける者が当該派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことと
されている(法第49条の3)。
なお、不利益取扱いの禁止の規定に違反した場合は、法第60条第2号に該当し、6箇月以下の
懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合がある。
- 338 -
第12 違法行為の防止、摘発
また、派遣元事業主については、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14
条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となり、不利益取扱いの禁止の規定違反による
司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となる。
3 派遣元事業主、派遣先への周知徹底
労働者派遣事業の適正な運営と、派遣労働者の保護を図るためには、労働者派遣事業制度に関す
る正しい理解が必要不可欠であることから、派遣元事業主、派遣先、労使団体等に対するリーフレッ
ト等の作成・配布、労働者派遣事業制度の概要に関する説明会の開催、公共職業安定所内への労働者
派遣事業制度に関する啓蒙・啓発ポスターの掲示、派遣元事業主、派遣先等に対する集団指導の実施
等その啓蒙、啓発を本省、都道府県労働局及び公共職業安定所のすべてにおいて積極的に行うことと
する。
4 指導及び助言
(1)概要
厚生労働大臣は、法(第3章第4節の規定は除く。)の施行に関し必要があると認めるとき
は、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の
適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる(法第
48条第1項)。
(2)意義
イ 当該指導及び助言は、違法行為があり、それが軽微なものである場合に、行政処分又は司法
処分を即時に行使せず、当該事業主等の自主的な改善努力を助長し、違法とは言えないまでも
法の趣旨に反した行為等を改善させ、又は違法行為を行うおそれがある場合にそれを防止する
ためのものである。
ロ 「労働者派遣をする事業主」とは、許可を受け又は届出をした派遣元事業主のほか違法に労
働者派遣事業を行っている事業主及び業として行われるものではない労働者派遣をする事業主
も含むものであり、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」とは、当該労働者派遣をする事業
主から労働者派遣を受けるすべての者をいう。
(3)権限の委任
指導及び助言に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚
生労働大臣が自らその権限を行うことは妨げられない。
5 報告
(1)概要
厚生労働大臣は、法(第3章第4節の規定は除く。)を施行するために必要な限度において、
労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必
- 339 -
第12 違法行為の防止、摘発
要な事項を報告させることができる(法第50条)。
(2)意義
イ 当該報告は、定期報告(法第23条第1項及び第3項。第5の1及び2参照)とは異なり、当
該定期報告だけでは、事業運営の状況及び派遣労働者の就業状況を十分把握できない場合であ
って、違法行為の行われているおそれのある場合等特に必要がある場合について個別的に必要
な事項を報告させるものである。
ロ 「労働者派遣事業を行う事業主」とは、許可を受け又は届出をした派遣元事業主のほか違法
に労働者派遣事業を行っている事業主も含むものであり、「当該事業主から労働者派遣の役務
の提供を受ける者」とは、派遣元事業主に限らず許可を受け又は届出をせず違法に労働者派遣
事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受けている者も含むものである。
ハ 「必要な事項」とは、労働者派遣事業の運営に関する事項及び派遣労働者の就業に関する事
項であり、具体的には、例えば、個々の労働者の就業条件、派遣期間、派遣先における具体的
就業の状況等である。
(3)報告の徴収の手続
必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び理由並びに報告期日を書面により通
知するものとする(則第47条)。
(4)権限の委任
報告に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働
大臣が自らその権限を行うことは妨げられない。
6 立入検査
(1)立入検査の実施
イ 概要
厚生労働大臣は、法(第3章第4節の規定は除く。)を施行するために必要な限度におい
て、職業安定機関の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役
務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類そ
の他の物件を検査させることができる(法第51条第1項)。
ロ 意義
(イ)当該立入検査は、違法行為の申告があり、許可の取消し、事業停止命令等の行政処分をす
るに当たって、その是非を判断する上で必要な場合等5の報告のみでは、事業運営の内容や
派遣労働者の就業の状況を十分に把握できないような場合に、限定的に、必要最小限の範囲
において行われるものである。
立入検査の対象となるのは、当該立入検査の目的を達成するため必要な事業所及び帳簿、
書類その他の物件に限定されるものである。
(ロ)「労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者」
- 340 -
第12 違法行為の防止、摘発
は、5の(2)のロと同様である。
(ハ)「事業所その他の施設」とは、労働者派遣事業を行う事業主の事業所及び当該事業主から
労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設のほか、派遣労働者の就業を管理
する施設等に限られる。
(ニ)「関係者」とは、労働者派遣事業運営の状況や派遣労働者の就業の状況について質問する
のに適当な者をいうものであり、具体的には、派遣労働者、労働者派遣事業を行う事業主、
その雇用する一般の労働者、労働者派遣の役務の提供を受ける者、その雇用する労働者等で
ある。
(ホ)「帳簿、書類その他の物件」とは、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、労働者派遣契約等
はもちろん、その他労働者派遣事業の運営及び派遣労働者の就業に係る労働関係に関する重
要な書類が含まれるものである。
(2)証明書
イ 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を必ず携帯し、関係者に提示しなければなら
ない(法第51条第2項)。
ロ 立入検査のための証明書は、労働者派遣事業立入検査証(様式第14号)によるものとする
(則第48条)。
なお、貼付する写真には、厚生労働省若しくは都道府県労働局の刻印又は厚生労働大臣若しく
は都道府県労働局長の印により割印する。
(3)立入検査の権限
イ 概要
当該立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(法第51条
第3項)。
ロ 意義
職業安定機関は、司法警察員の権限を有せず、当該立入検査の権限は行政による検査のため
に認められたものであり、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないものである。
(4)権限の委任
立入検査に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労
働大臣が自らその権限を行うことは妨げられない。
7 違反の場合の効果
(1)適用除外業務等(第2参照)
イ 適用除外業務について労働者派遣事業を行った者は、法第59条第1号に該当し1年以下の懲
役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
また、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法
第49条第1項)の対象となり、イの司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となる(第13
- 341-
第12 違法行為の防止、摘発
の2参照)。
ロ また、その指揮命令の下に派遣労働者を適用除外業務に従事させた者は、勧告(法第49条の
2第1項)、公表(法第49条の2第2項)の対象となり(第13の3参照)、また、派遣労働者
を適用除外業務に従事させる者へ労働者派遣を行った派遣元事業主は、労働者派遣の停止命令
(法第49条第2項)の対象となる(第13の2参照)。
(2)労働者派遣事業の許可等(第3参照)
イ 許可に関する違反
(イ)労働者派遣事業の許可を受けず、労働者派遣事業を行った者及び偽りその他不正の行為によ
り労働者派遣事業の許可を受けた者は、それぞれ法第59条第2号及び同条第3号に該当し、1
年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある(第13の1参照)。また、法に
違反するものとして、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、
改善命令(法第49条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
(ロ)許可申請関係書類に虚偽の記載をして提出した者は、法第61条第1号に該当し、30万円以下
の罰金に処せられる場合がある(第13の1参照)。また、法に違反するものとして、許可の取消
し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対
象となる(第13の2参照)。
(ハ)第3の1(12)により付された許可の条件に違反した場合、法第14条の規定に該当し、許可の取
消しの対象となる。(第13の2参照)。
ロ 許可の有効期間の更新に関する違反
(イ)労働者派遣事業の許可の有効期間の更新を受けず、引き続き労働者派遣事業を行った者及び
偽りその他不正の行為により労働者派遣事業の許可の有効期間の更新を受けた者は、それぞれ法
第59条第2号及び同条第3号に該当し、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる
場合がある(第13の1参照)。また、法に違反するものとして、許可の取消し(法第14条第1
項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる(第13
の2参照)。
(ロ)許可有効期間更新申請関係書類に虚偽の記載をして提出した者は、法第61条第1号に該当
し、30万円以下の罰金に処せられる場合がある(第13の1参照)。また、法に違反するものとし
て、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49
条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
ハ 変更の届出又は虚偽の届出に関する違反
労働者派遣事業の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、法第61条第2号に該当し、
30万円以下の罰金に処せられる場合がある(第13の1参照)。また、法に違反するものとして、
許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第
1項)の対象となる(第13の2参照)。
- 342 -
第12 違法行為の防止、摘発
二 許可証に関する違反
(イ)許可証を事業所に備え付けず、また、関係者から請求があったときにこれを提示しなかった派
遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命
令(法第49条第1項)の対象となる。なお、許可証の交付を受けた者が、許可証を亡失し、又は
許可証を滅失したにもかかわらず、これに違反して許可証の再交付を受けるため、所定の方法に
より許可証再交付申請書を提出しなかった者は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命
令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
(ロ)許可証の再交付を受けるため、所定の方法により許可証再交付申請書を提出しなかった者は、
許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第
1項)の対象となる(第13の2参照)。
ホ 廃止の届出に関する違反
労働者派遣事業の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は法第61条第2号に該当し、30
万円以下の罰金に処せられる場合がある(第13 の1参照)。また、法に違反するものとして、許
可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1
項)の対象となる(第13の2参照)。
へ 名義貸しに関する違反
労働者派遣事業につき名義貸しを行った者は、法第59条第1号に該当し、1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金に処せられる場合がある(第13の1参照)。また法に違反するものとして、
許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第
1項)の対象となる(第13の2参照)。
(3)事業報告等(第5参照)
イ 事業報告及び収支決算書に関する違反
(イ)事業報告書及び収支決算書が提出期限までに提出されなかった場合、又は法第30条の4第1
項に定める協定を締結した派遣元事業主が、当該協定を事業報告書に添付して提出しなかった場
合には、法第50条の規定に基づき必要な事項の報告を求める(第12の5参照)場合があり、こ
れに従わず報告せず、又は虚偽の報告をした場合は、法第61条第5号に該当し、30万円以下の罰
金に処せられる場合がある(第13の1参照)。
(ロ) また、当該違反をした派遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令
(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となり、(イ)の司法処分を受けた場合
は、許可の取消しの対象となる(第13の2参照)。
ロ 海外派遣の届出に関する違反
(イ)海外派遣の届出を所定の方法により行わなかった場合は、法第61条第2号に該当し、30万円
以下の罰金に処せられる場合がある(第13の1参照)。
(ロ)また、法に違反するものとして、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14
条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となり、(イ)の司法処分を受けた場合は、許可
- 343 -
第12 違法行為の防止、摘発
の取消しの対象となる(第13の2参照)。
ハ 関係派遣先割合報告書に関する違反
(イ)関係派遣先派遣割合報告書が提出期限までに提出されなかった場合(法第23条第3項)又は
法第23条の2に規定する関係派遣先への派遣割合が遵守されていない場合であって、法第48条
第1項の規定による指導又は助言をしてもなお関係派遣先派遣割合報告書が捏出されない又は法
第23条の2の規定に違反している場合には、厚生労働大臣は、法第48条第3項の規定に基づ
き、必要な措置をとるべきことを指示する場合がある。
(ロ) さらに、(イ)の指示を受けたにもかかわらず、なお関係派遣先派遣割合報告書が捏出されない
又は法第23条の2の規定に違反している場合には、許可の取消し(法第14条第1項)の対象と
なる(第13の2参照)。
ニ 関係者への情報提供(情報公開)に関する違反
法第23条第5項に基づく関係者への情報提供を行わなかった場合、派遣元事業主は、許可の取
消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の
対象となる(第13の2参照)。
ホ 労働争議に関する違反
第5の5(3)及び(4)(法第24条、職業安定法第20条)に違反して労働者派遣を行った派遣元事
業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第
49条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
へ 個人情報の保護に関する違反
個人情報の保護に関する規定に違反した場合、派遣元事業主は、許可取消し(法第14条第1
項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる(第13の
2参照)。
ト 秘密を守る義務に関する違反
秘密を守る義務に関する規定に違反した場合、派遣元事業主は、許可取消し(法第14条第1
項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる(第13の
2参照)。
(4)労働者派遣契約(第6参照)
・ 労働者派遣契約の締結に関する違反
労働者派遣契約の締結に当たり、所定の事項を定めず又は所用の手続きを行わなかった場合、
派遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命
令(法第49条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
・ 労働者派遣契約の締結に当たっての比較対象労働者の待遇等に関する情報提供に関する違反
労働者派遣契約の締結に当たり、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者が、所定の方法
により派遣元事業主に対して比較対象労働者の待遇等に関する情報を捏供しなかった場合、当該
者は、勧告(法第49条の2第1項)、公表(法第49条の2第2項)の対象となる(第13の3参
- 344 -
第12 違法行為の防止、摘発
照)。
また、当該比較対象労働者の待遇等に関する情幸酎こ変更があったときに、派遣先が、遅滞なく
当該変更の内容に関する情報を所定の方法により派遣元事業主に捏供しなかった場合、勧告(法
第49条の2第1項)、公表(法第49条の2第2項)の対象となる(第13の3参照)。
派遣元事業主が、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者からの比較対象労働者の待遇等
に関する情報の提供がないにも関わらず、当該者との間で労働者派遣契約を締結した場合は、派
遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令
(法第49条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
また、派遣元事業主が、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から提供された比較対象
労働者の待遇等に関する情報、又は派遣先からの当該情幸酎こ変更があったときの当該変更の内容
に関する情報を所定の期間保存しなかった場合は、派遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第
1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる(第13の
2参照)。
(5)派遣元事業主の講ずべき措置等(第7参照)
イ 特定有期雇用派遣労働者に対する雇用安定措置
(イ)派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して3年間当該労働者派遣に係
る労働に従事する派遣される見込みがある特定有期雇用派遣労働者に対して雇用安定措置を講じ
ない場合(法第30条第2項により読み替えて適用する同条第1項)であって、法第48条第1項
の規定による指導又は助言をしてもなお雇用安定措置を講じない場合には、厚生労働大臣は、法
第48条第3項の規定に基づき、必要な措置をとるべきことを指示する場合がある。
(ロ)さらに、(イ)の指示を受けたにもかかわらず、なお雇用安定措置を講じない場合には、許可の取
消し(法第14条第1項)、事業廃止命令の対象となる(第13の2参照)。
ロ 段階的かつ体系的な教育訓練等
段階的かつ体系的な教育訓練等に関する規定(法第30条の2)に違反した場合、派遣元事業主
は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条
第1項)の対象となる(第13の2参照)。
ハ 不合理な待遇の禁止等
不合理な待遇の禁止等に関する規定(法第30条の3)に違反した場合は、派遣元事業主は、許
可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1
項)の対象となる(第13の2参照)
待遇に関する事項等の説明
労働者を派遣労働者として雇い入れようとするとき、又は労働者派遣をしようとするとき等の
待遇に関する事項等の説明に関する規定(法第31条の2第1項、第2項及び第3項)に違反した
- 345 -
第12 違法行為の防止、摘発
場合、派遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、
改善命令(法第49条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
また、派遣元事業主が、派遣労働者から求めがあったにも関わらず、比較対象労働者との待遇
の相違の内容及び理由等について説明を行わなかった場合、又は、当該求めがあったことを理由
に解雇その他不利益な取扱いを行った場合は、派遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1
項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる(第13の2
参照)。
ホ 派遣労働者であることの明示等
雇入れの際の明示に関する規定(法第32条第1項)及び雇入れ後、派遣労働者とする場合の
明示及び同意に関する規定(法第32条第2項)に違反した場合、派遣元事業主は、許可の取消し
(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象と
なる(第13の2参照)。
なお、これらの規定は、派遣労働者という地位を取得する場合に労働者保護の観点から加えら
れた公法的な規制であり、これに反して明示又は明示及び同意を経ない労働者を労働者派遣した
場合における労働契約又は労働者派遣契約の効果を直接規律するものではない。
へ 派遣労働者に係る雇用制限の禁止
(イ)派遣労働者に係る雇用制限の禁止に関する規定(法第33条)に違反した場合、派遣元事業主
は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49
条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
(ロ)法第38条による準用
派遣労働者に係る雇用制限の禁止は、派遣元事業主以外の事業主が労働者派遣をする場合
も適用される。
ト 就業条件等の明示
(イ)労働者派遣をしようとする場合に、あらかじめ、当該派遣労働者に就業条件等の明示(法
第34条)を行わなかったときは、法第61条第3号に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場
合がある(第13の1参照)。
(ロ) また、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令
(法第49条第1項)の対象となり、(イ)の司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象とな
る(第13の2参照)。
(ハ)就業条件等の明示義務違反は、(イ)及び(ロ)のように司法、行政処分の対象となるが、労働
者派遣契約自体は有効に成立、存続するものである。
(ニ)法第38条による準用
就業条件(ただし、第7の13(4)のイ及びロを除く。)の明示は派遣元事業主以外の事業主
が労働者派遣をする場合にも行わなければならない。
- 346 -
第12 違法行為の防止、摘発
チ 労働者派遣に関する料金の額の明示
労働者派遣に関する料金の額に関する規定(法第34条の2)に違反した場合、派遣元事業主
は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条
第1項)の対象となる(第13の2参照)。
リ 派遣先への通知
(イ)法第35条に基づく派遣先への通知を行わなかった又は通知を所定の方法で行わなかった場
合又は虚偽の通知をした場合(法第35条)は、法第61条第4号に該当し30万円以下の罰金に
処せられる場合がある(第13の1参照)。
(ロ) また、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令
(法第49条第1項)の対象となり、(イ)の司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象とな
る(第13の2参照)。
(ハ)派遣先への通知義務違反は、(イ)及び(ロ)のように司法、行政処分の対象となるが、労働者
派遣契約自体は有効に成立、存続するものである。
ヌ 労働者派遣の期間の制限の適切な運用
(イ)派遣先の事業所単位の期間制限又は派遣労働者の個人単位の期間制限を超えて労働者派遣
を行った場合(法第35条の2及び法第35条の3)は、法第61条第3号に該当し、30万円以下の
罰金に処せられる場合がある。
(ロ)また、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令
(法第49条第1項)の対象となり、(イ)の司法処分を受けた場合は、許可取消しの対象となる
(第13の2参照)。
ル 日雇労働者についての労働者派遣の禁止
日雇労働者についての労働者派遣の禁止に関する規定(法第35条の4)に違反した場合、派遣
元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令
(法第49条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
ヲ 離職した労働者についての労働者派遣の禁止
離職した労働者についての労働者派遣の禁止に関する規定(法第35条の5)に違反した場合、
派遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命
令(法第49条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
ワ 派遣元責任者の選任
(イ)派遣元責任者を選任しなかった場合又は派遣元責任者の選任が所定の要件を満たさず、若
しくは所定の方法により行われていなかった場合(法第36条)は、法第61条第3号に該当し、
30万円以下の罰金に処せられる場合がある(第13の1参照)。
(ロ) また、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令
(法第49条第1項)の対象となり、(イ)の司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となる
(第13の2参照)。
- 347 -
第12 違法行為の防止、摘発
力 派遣元管理台帳
(イ)法第37条に基づく派遣元管理台帳を所定の方法により作成、記載又は保存しなかった場合
(法第37条)は、法第61条第3号に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合がある(第
13の1参照)。
(ロ)また、許可の取消し(法第14条1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法
第49条第1項)の対象となり、(イ)の司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となる
(第13の2参照)。
(6)派遣先の講ずべき措置等(第8参照)
イ 適正な派遣就業の確保等
派遣先が、教育訓練又は福利厚生施設に関する規定(法第40条第2項及び第3項)に違反する
場合は、勧告(法第49条の2第1項)、公表(法第49条の2第2項)の対象となる(第13の3参
照)。
ロ 派遣先責任者の選任
派遣先責任者を選任しなかった場合又は所定の方法により派遣先責任者を選任しなかった場合
(法第41条)は、法第61条第3号に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合がある(第13の
1参照)。
ハ 派遣先管理台帳
法第42条に基づく派遣先管理台帳を所定の方法により作成、記載、保存若しくは通知しなか
った場合(法第42条)、派遣先は、法第61条第3号に該当し、30万円以下の罰金に処される
場合がある(第13の1参照)。
(7)紛争の解決(第10参照)
派遣労働者が、当該派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争に関し、都道府県労働局に援助を
求めたことを理由として、当該派遣元事業主が、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをした
場合は、派遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2
項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
(8)報告
イ 法第50条の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、法第61条第5号に該当し、30万円
以下の罰金に処せられる場合がある(第13の1参照)。
ロ また、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令
(法第49条第1項)の対象となり、イの司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となる
(第13の2参照)。
(9)立入検査
イ 法第51条第1項の立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答
- 348 -
ロ
第12 違法行為の防止、摘発
弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした場合は、法第61条第6号に該当し、30万円以下の罰金に
処せられる場合がある(第13の1参照)。
また、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令
(法第49条第1項)の対象となり、イの司法処分を受けた場合は、許可の取消しの対象となる
(第13の2参照)。
- 349 -
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
1 違法行為による罰則
法の規定(第3章第4節の規定を除く。)に違反する行為に対する罰則は次のとおりである。
罰則適用条項違反の内容 参考箇所 罰則規定 刑罰の内容
第4条第1項適用除外業務について、労働者派遣事 第2の1及び第59条第1号1年以下の懲役又
業を行った者 2 は100万円以下の
第5条第1項厚生労働大臣の許可を受けないで労働第3の1及び第59条第2号罰金
者派遣事業を行った者 2の(2)のイ
偽りその他不正の行為により労働者派 第3の1 第59条第3号
遣事業の許可を受けた者
第5条第2項労働者派遣事業の許可又は許可の有効 第3の1及び第61条第1号30万円以下の罰金
又は第3項(期間の更新の申請書、事業計画書等の 2
第10条第5項書類に虚偽の記載をして提出した者
において準用
する場合を含
む。)
第10条第2項偽りその他不正の行為により労働者派 第3の2 第59条第3号1年以下の懲役又
遣事業の許可の有効期間の更新を受け は100万円以下の
た者 罰金
第11条第1項①労働者派遣事業の氏名等の変更の届 第3の3 第61条第2号30万円以下の罰金
出をせず、又は虚偽の届出をした者
②労働者派遣事業を行う事業所の新設
に係る変更届出の際、事業計画書等
の添付書類に虚偽の記載をして提出
した者
第13条第1項労働者派遣事業の廃止の届出をせず、第3の6
又は虚偽の届出をした者
第14条第2項期間を定めた労働者派遣事業の全部又 第13の2の 第59条第4号1年以下の懲役又
は一部の停止についての厚生労働大臣(2)のロ
の命令に違反した者
第15条 派遣元事業主の名義をもって、他人に 第3の7 第59条第1号
労働者派遣事業を行わせた者
- 350 -
は100万円以下の
罰金
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
第23条第4項海外派遣の届出をせず、又は虚偽の届 第5の3
出をした者
第61条第2号30万円以下の罰金
第34条 労働者派遣をしようとする場合に、あ 第7の13 第61条第3号
らかじめ、当該派遣労働者に就業条件
等の明示を行わなかった者
第35条 労働者派遣をするとき、派遣労働者の 第7の15 第61条第4号
氏名等を派遣先に通知をせず、又は虚
偽の通知をした者
第35条の2 派遣先の事業所等ごとの業務について 第7の16
派遣可能期間の制限に抵触することと
なる最初の日以降継続して労働者派遣
を行った者
第35条の3 派遣先の事業所等における組織単位ご 第7の16
第36条
第37条
第41条
第42条
との業務について、3年を超える期間
継続して同一の派遣労働者に係る労働
者派遣を行った者
派遣元責任者を選任しなかった者 第7の19
派遣元管理台帳を作成若しくは記載せ 第7の20
ず、又はそれを3年間保存しなかった
者
派遣先責任者を選任しなかった者 第8の11
派遣先管理台帳を作成若しくは記載せ 第8の12
ず、それを3年間保存せず、又はその
記載事項(派遣元事業主の氏名及び名
称は除く。)を派遣元事業主に通知し
なかった者
第61条第3号
第49条第1項派遣労働者に係る雇用管理の方法の改 第13の2の 第60条第1号 6箇月以下の懲役
善その他当該労働者派遣事業の運営を(3)
改善するために必要な措置を講ずべき
旨の厚生労働大臣の命令(改善命令)
に違反した者
第49条第2項継続させることが著しく不適当である 第13の2の
と認められる派遣就業に係る労働者派(4)
遣契約による労働者派遣を停止する旨
- 351-
又は30万円以下の
罰金
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
の厚生労働大臣の命令に違反した者
第49条の3
第2項
法又はこれに基づく命令の規定に違反 第12の2の 第60条第2号
する事実がある場合において、派遣労(3)
働者がその事実を厚生労働大臣に申告
したことを理由として、当該派遣労働
者に対して解雇その他不利益な取扱い
をした者
第50条
必要な報告をせず、又は虚偽の報告を 第12の5 第61条第5号30万円以下の罰金
した者
第51条第1項 関係職員の立入検査に際し、立入り若 第12の6 第61条第6号
しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避し、又は質問に対して答弁せず、若
しくは虚偽の陳述をした者
その他
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に
就かせる目的で労働者派遣をした者
第58条
1年以上10年以下
の懲役又は20万円
以上300万円以下
の罰金
(両罰規定) 法人の代表者又は法人若しくは人の代
理人、使用人その他の従業者が、その
法人又は人の義務に関して、第58条か
ら第61条までの違反行為をしたときは
、その法人又は人に対しても、各々の
罰金刑を科す。
第62条
- 352 -
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
2 違法行為による行政処分
(1)概要
派遣元事業主において法(改善命令以外の行政処分については第3章第4節の規定を除く。)に違
反する行為があった場合、派遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第
14条第2項)及び改善命令(法第49条第1項)の行政処分の対象となる。この場合、許可の取消しの
行政処分を行うときは聴聞を行い、事業停止命令及び改善命令の行政処分を行うときは弁明の機会を
付与しなければならない(行政手続法第13条第1項)。
また、派遣先において法第4条第3項の規定に違反する行為があった場合、当該派遣先へ労働者派
遣をする派遣元事業主は労働者派遣の停止命令(法第49条第2項)の行政処分の対象となる。
(2)労働者派遣事業に係る行政処分
イ 許可の取消し
(イ)概要
厚生労働大臣は、派遣元事業主が次のいずれかに該当するときは、労働者派遣事業の許可を取
り消すことができる(法第14条第1項)。
(力 許可の欠格事由のいずれかに該当しているとき。ただし、以下の場合を除く。
a 労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
(法第6条第4号)。
b 労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(当該法人が法第6条第1号又
は第2号に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を
受ける原因となった事項が発生した当時現に法人の役員であった者で、当該取消しの日から
起算して5年を経過しないもの(法第6条第5号)。
C 労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分する日又
は処分しないことを決定する日までの間に労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業
の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過し
ないもの(法第6条第6号)。
d 労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分する日又
は処分しないことを決定する日までの間に労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人であ
る場合において、聴聞の通知の目前60日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理
由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しない
もの(法第6条第7号)。
② 法(第23条第3項、第23条の2、第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項
及び第3章第4節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命
令若しくは処分に違反したとき。
③ 許可の条件(第3の1の(12)参照)に違反したとき。
④ 法第48条第3項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお法第23条第3項、第23条
- 353 -
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反したとき
(第13の5参照)。
(ロ)意義
a 許可の取消しは、当該事業主に労働者派遣事業を引き続き行わせることが適当でない場合
に行うものである。
b 派遣元事業主が2以上の事業所を設けて労働者派遣事業を行っている場合、許可の取消し
の要件のうち(力については、全事業所が対象となることはもちろんであるが、②及び③の要
件についても、一の事業所において違反行為があったときは、当該事業所以外の事業所にお
いても許可が取り消されるものであるので留意しておくこと。
C 許可の取消しの要件の②及び③の「違反」は、職業安定機関が判断するものであり、派遣
元事業主が当該違反を理由に刑を科せられ又は逮捕されている等を前提とする必要はないも
のであるので留意すること。
d 許可の取消しの要件の④は、関係派遣先への派遣割合の報告(法第23条第3項)を行わない
派遣元事業主又は関係派遣先への派遣割合制限(法第23条の2)に違反した派遣元事業主に
対して厚生労働大臣が指導・助言を行い、是正されない場合には、必要な措置をとるべきこ
とを指示することができるとされているが(法第48条第3項)、当該指示にも従わず、なお違
反が是正されない場合である。
(ハ)違反の場合の効果
許可の取消しを受けた事業主が引き続き労働者派遣事業を行った場合は、許可を受けず労働者
派遣事業を行った者として法第59条第2号に該当し、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に
処せられる場合がある。
ロ 事業停止命令
(イ)概要
厚生労働大臣は、派遣元事業主が次のいずれかに該当するときは、期間を定めて当該労働者派
遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる(法第14条第2項)。
① 法(第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第
1項及び第3章第4節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づ
く命令若しくは処分に違反したとき。
② 許可の条件に違反したとき。
(ロ)意義
a 事業停止命令は、当該事業主に事業を引き続き行わせることが適当でないとまではいえな
いような場合について、当該停止期間中に事業運営方法の改善を図るため、また、一定の懲
戒的な意味において行うものである。
b 事業停止命令の要件は、イの(イ)の許可の取消しの②及び③の要件と同一であるが、この場
合に、許可の取消しを行うか、事業停止命令を行うかは、違法性の程度等によって判断する
- 354 -
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
(イの(ロ)のC参照)。
(ハ)権限の委任
事業停止命令に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。ただし、
厚生労働大臣が自らその権限を行うことは妨げられない。
(3)改善命令
イ 概要
厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関し法(第23条第3項、第23条の2及び
第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定を除く。)その他労働に関する法
律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、適正な派遣就業
を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に係る雇用管理
の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ず
ることができる(法第49条第1項)。
ロ 意義
(イ)改善命令は、違法行為そのものの是正を図るのではなく、法違反を起こすような雇用管理体制
その他の労働者派遣事業の運営方法そのものの改善を行わせるものである。
(ロ)「その他労働に関する法律」とは、職業安定法、労働基準法、雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律等の労働に関する法令の規定で法違反が確認できる規定は
全て含まれる。当該違反については、職業安定機関が判断するものである。
(ハ)「適正な派遣就業を確保するため必要があると認める」とは、当該労働関係法規違反が労働者
派遣事業の実施に関する雇用管理体制その他事業運営の問題により生じたと認められる場合であ
る。
(ニ)「雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置」と
は、派遣労働者の保護を図るために当該事業主の雇用管理体制、事業運営方法を改善させるため
の措置であり、具体的には、例えば、派遣元責任者の交代、派遣元責任者の増員、労働者派遣事
業制度に関する教育の充実、派遣先との間における派遣労働者の苦情処理体制の確立等である。
(ホ)なお、他の事業と兼業している事業主については、当該改善命令により当該他の事業は何ら影
響を受けるものではない。
ハ 権限の委任
改善命令に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労
働大臣が自らその権限を行うことは妨げられない。
(4)労働者派遣の停止命令
イ 概要
厚生労働大臣は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者を適用除外業務に従事させている場合
(法第4条第3項の規定違反)において、当該派遣就業を継続させることが著しく不適当であると
認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係わる労働者
- 355 -
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる(法第49条第2項)。
ロ 意義
(イ)労働者派遣の停止命令は、派遣先の法第4条第3項違反の態様が極めて悪質で、当該派遣先に
おける派遣就業を継続させることが労働者保護の観点から著しく不適当であると認められる場合
に、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、即時、当該派遣就業に係る労働者派遣
自体の停止を行わせるものである。
(ロ)「同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるとき」
とは、具体的には、例えば、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に係る派遣就業等労働者保護に
著しく欠ける状態のことである。
(ハ)なお、派遣元事業主は、労働者派遣事業を行っている以上、当該事業に係る派遣労働者の保護
に最大限の責任を負うものであり、継続させることが著しく不適当であると認められる派遣就業
が行われているときには、派遣元事業主に法違反の事実がないとしても、公益的見地から停止命
令をうけるべきものである。
ハ権限の委任
労働者派遣の停止命令に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことは妨げられない。
3 法第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若し
くは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40
条の9第1項の規定に違反している者に対する勧告、公表
(1)概要
労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者において、法第4条第3項、
第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4
項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第1項の規定(第40条の9については平成27年10
月1日より)に違反する行為があった場合、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者は、勧告(法第
49条の2第1項)及び公表(法第49条の2第2項)の措置の対象となる。
(2)法第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40
条の2第1項の規定、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第1項の規定に違反し
ている者に対する勧告
イ 概要
厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に派遣労働者を適用除
外業務に従事させている場合(法第4条第3項の規定違反)、派遣元事業主以外の労働者派遣事業
を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受けている場合(法第24条の2の規定違反)若しくは
派遣先を離職して1年以内の者(60歳以上の定年退職者を除く。)について、当該派遣先が当該者
を派遣労働者として受け入れ、労働者派遣の役務の提供を受けていた場合(法第40条の9第1項違
- 356 -
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
反)又は当該者に法第48条第1項の規定による指導若しくは助言(第12の4参照)をした場合にお
いて、当該者がなお、違法行為を行っており又は違法行為を行うおそれがあると認めるときは、当
該者に対し、これらの規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又はこれらの派遣就業
が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる(法第49条の
2第1項)。
厚生労働大臣は、労働者派遣契約の締結に当たり、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者
が、派遣元事業主に対して比較対象労働者の待遇等に関する情報を捏供しなかった場合又は当該者
に法第48条第1項の規定による指導若しくは助言(第12の4参照)をした場合において、当該者が
なお、違法行為を行っており又は違法行為を行うおそれがあると認めるときは、当該者に対し、こ
れらの規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又はこれらの派遣就業が行われること
を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる(法第49条の2第1項)。
また、厚生労働大臣は、当該比較対象労働者の情幸酎こ変更があったときに、派遣先が、遅滞なく
当該変更の内容に関する情報を派遣元事業主に捏供しなかった場合又は当該者に法第48条第1項の
規定による指導若しくは助言(第12の4参照)をした場合において、当該者がなお、違法行為を行
っており又は違法行為を行うおそれがあると認めるときは、当該者に対し、これらの規定に違反す
る派遣就業を是正するために必要な措置又はこれらの派遣就業が行われることを防止するために必
要な措置をとるべきことを勧告することができる(法第49条の2第1項)。
厚生労働大臣は、派遣先が、教育訓練又は福利厚生施設に関する規定(法第40条第2項及び第3
項)に違反する場合又は当該者に法第48条第1項の規定による指導若しくは助言(第12の4参照)
をした場合において、当該者がなお、違法行為を行っており又は違法行為を行うおそれがあると認
めるときは、当該者に対し、これらの規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又はこ
れらの派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができ
る(法第49条の2第1項)。
厚生労働大臣は、派遣先の事業所その他の派遣就業の場所ごとの業務(第8の5の(3)のイの①
から⑥までに掲げる業務を除く。)について、派遣元事業主から派遣受入期間を超える期間継続し
て労働者派遣の役務の提供を受けている場合(法第40条の2第1項の規定違反)又は当該派遣先に
法第48条第1項の規定による指導若しくは助言(第12の4参照)をした場合において、当該派遣先
がなお、違法行為を行っており又は行うおそれがあると認めるときは、当該派遣先に対し、この規
定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又は当該派遣就業が行われることを防止するた
めに必要な措置をとるべきことを勧告することができる(法第49条の2第1項)。
派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするとき、意見聴取期間に則第33条の3で定めるところ
により、当該派遣先の事業所に、労働組合の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその
労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する
者の意見を聴かなければならないこととされている(法第40条の2第4項)。また、派遣先は、過
半数組合等が異議を述べたときは、派遣可能期間の延長の理由等について説明しなければならない
- 357 -
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
こととされている(法第40条の2第5項)。しかるに、派遣先が過半数組合等からの意見を聴取せ
ずに派遣可能期間を延長した場合、過半数代表に労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者を
選任する若しくは投票、挙手等の民主的な方法による手続きによらず過半数代表者を選出するなど
過半数代表者の選任手続に違反した場合等(法第40条の2第4項規定違反)若しくは過半数組合等
からの異議があったにも関わらず説明をしない場合(法第40条の2第5項規定違反)又は当該者に
法第48条第1項の規定による指導若しくは助言(第12の4参照)をした場合において、当該者がな
お、違法行為を行っており又は違法行為を行うおそれがあると認めるときは、当該派遣先に対し、
必要な措置を講ずべきことを勧告することができる(法第49条の2第1項、第8の7参照)。
なお、意見を聴取した過半数代表者が、使用者の指名等の民主的な方法により選出されたもので
はない場合、派遣可能期間の延長手続のための代表者選出であることを明らかにせずに選出された
場合、管理監督者である場合(管理監督者でない者に該当する者がいない事業所を除く)について
は、事実意見聴取が行われていないものと同視できることから、労働契約申込みみなし制度の適用
があることに留意すること。
ロ 意義
(イ)勧告は、法益侵害性の高い行為、又は指導若しくは助言によっても、なお違法行為を是正しな
い、若しくは違法行為を行う可能性がある悪質な場合に行う。
(ロ)「派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主」とは、許可を受けずに違法に労働者派遣
事業を行う事業主のことである。
(ハ)「違法行為を行うおそれがあると認めるとき」とは、現時点では法違反の状態にはないが、例
えば、これまでに不適正な派遣就業を行わせたことのある者であって、その者における業務の処
理状況、派遣先責任者等の業務の遂行状況、労働者派遣契約の締結状況等から、今後、再び法違
反を犯すおそれがあると判断される場合をいうものである。
(ニ)「是正するために必要な措置」とは、当該違法な派遣就業を行わせることを中止することであ
る。
(ホ)「防止するために必要な措置」とは、具体的には、例えば、派遣労働者が従事していた業務の
処理体制の改善、派遣先責任者等による適正な派遣就業を図るための業務遂行体制の確立等のこ
とである。
ハ 権限の委任
勧告に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働大
臣が自らその権限を行うことは妨げられない。
ニ 勧告実施の手続等
(イ)厚生労働大臣は勧告を行うことを決定したときは、ただちに労働者派遣受入適正実施勧告書
(第16様式集参照)を作成し、管轄都道府県労働局を経由して当該勧告の対象となる者に対して
交付する。
都道府県労働局長は勧告を行うことを決定したときは、ただちに労働者派遣受入適正実施勧告
- 358 -
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
書(第16様式集参照)を作成し、当該勧告の対象となる者に対して交付する。
(ロ)労働者派遣受入適正実施勧告書には、当該勧告に従わない場合は、その旨を公表することがあ
る旨を記載する。
(3)法第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40
条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第1項の規定に違反している
者に対する公表
イ 概要
厚生労働大臣は、(2)の勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったと
きは、その旨を公表することができる(法第49条の2第2項)。
ロ 意義
公表は、公表される者に対する制裁効果に加え、派遣元事業主及び派遣労働者に対する情報提供
・注意喚起及び他の労働者派遣事業主より労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する違法行為の
抑止といった効果を期待することができる。
ハ 公表を行う場合
「勧告を受けた者がこれに従わなかったとき」とは、勧告された必要な措置を講じていない場合
であって、指導によってもこれを改めようとしない場合をいう。
ニ 公表の決定
公表の決定は厚生労働大臣が行う。
4 労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として
行われている場合の勧告
(1)概要
厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を
特定の者に提供することを目的として行われている場合(一定の事由に該当する場合を除く。)であ
って必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的又は内容を変
更するよう勧告することができる(法第48条第2項)。
(2)意義
イ 「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」とは、特定の者に対してのみ
当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行っているものであって、それ以外の者に対し
て、労働者派遣を行うことを目的としていない場合である。
ロ なお、労働者派遣事業を不特定の者に対して行うことを目的として事業運営を行っている場合、
結果として、特定の者に対してしか労働者派遣をすることができなかったときは含まれないもので
ある。
ハ 「特定の者」とは、一つであると複数であるとを問わず対象が特定されていることである。
- 359 -
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
こ この該当の有無は、事業所ごとに判断するものである。
(3)「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」の判断基準等
定款等に記載され具体的に明らかにされている事業目的だけではなく、事業運営の実態にも照らし
客観的に特定の者への労働者派遣を目的としているか否かを判断する。
具体的には、次に掲げるいずれかに該当する場合は、当該労働者派遣事業が「専ら労働者派遣の役
務を特定の者に提供することを目的とする」ものであると判断する。
(力 定款、寄附行為、登記事項証明書等に当該事業の目的が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供
する旨の記載等が行われている場合
② 派遣先の確保のための努力が客観的に認められない(派遣元事業主に複数事業所があり、本社等
で一括して当該派遣事業に係る派遣先の開拓を行っている場合は除く。)場合
「派遣先の確保のための努力が客観的に認められない場合」とは、不特定の者を対象とした派
遣先の確保のための宣伝、広告、営業活動等を正当な理由なく随時行っていない場合である。
「正当な理由」とは、業務そのものが限定的に行われていることから他に派遣先を確保しよう
としてもできない場合又は派遣労働者の人数が足りないことに起因して派遣先の確保ができない
場合(派遣労働者の確保のための努力が客観的に認められる場合に限る。)である。
③ 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者からの労働者派遣の依頼に関し、特定の者以外から
のものについては、正当な理由なく全て拒否している場合
「正当な理由」とは、派遣労働者の確保のための努力が客観的に認められるにもかかわらず派
遣労働者の人数が足りない場合等である。
(4)勧告の対象としない事由
イ 概要
勧告の対象としない事由は、「当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者の
うち、3/10以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇
い入れられた者に限る。)であること。」とする(則第1条の3)。
ロ 意義
(イ)「当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者」とは、専ら労働者派遣の役
務の提供を特定の者に提供することを目的として労働者派遣事業を行う事業所において雇用する
派遣労働者であり、当該派遣元事業主が他の事業所で労働者派遣事業を行っている場合に、当該
他の事業所の派遣労働者は含まないものである。
(ロ)「他の事業主の事業所」とは、当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主以外の事業主の事業所
であり、当該派遣元事業主の事業所は全て含まない。
(ハ)「60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者」とは、当該労働者派遣事業を行う派遣
元事業主以外の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職し又は60歳以上の定年に達した後の
再雇用、勤務延長若しくは出向が終了し離職した後当該労働者派遣事業を行う事業所で雇用され
- 360 -
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
る派遣労働者である。
(5)勧告の内容
(3)により特定の者に対してのみ労働者派遣事業を行うことを目的としていると判断された労働者
派遣事業については、(4)の勧告の対象としない事由に該当しないものの全てに対し「(3)の①から③
までのいずれにも該当しないように事業目的及び運営の方法を変更しなければならない」旨の勧告を
実施する。
(6)権限の委任
勧告に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣
が自らその権限を行うことは妨げられない。
(7)勧告実施の手続等
厚生労働大臣は勧告を行うことを決定したときは、ただちに、次の様式による労働者派遣事業勧告
書を作成し、管轄都道府県労働局を経由して当該勧告の対象となる者に対して交付する。
都道府県労働局長は勧告を行うことを決定したときは、ただちに、次の様式による労働者派遣事業
勧告書を作成し、当該勧告の対象となる者に対して交付する。
なお、「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこと」を
許可条件として付している(第3の1の(12)参照)ことから、違反した場合は、許可の取消し(法第
14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)の対象となるものである。
5 関係派遣先への派遣割合制限違反等に関する指示
(1)概要
厚生労働大臣は、法第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する
同条第1項の規定に違反した派遣元事業主に対し、法第48条第1項の規定による指導又は助言をした
場合において、当該派遣元事業主がなお法第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により
読み替えて適用する同条第1項の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をと
るべきことを指示することができる(法第48条第3項)(第5の2参照)。
(2)指示の対象となる判断基準等
イ 関係派遣先への派遣割合報告書の提出
指示の対象となるのは、「関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2)」を報告期限までに捏
出せず、法第48条第1項の規定による指導又は助言を受けたにもかかわらず、合理的理由なく当該
指導又は助言に従わず、なお当該報告書を提出しなかった場合である。
「合理的理由」とは、例えば、事業年度期間中に関係派遣先の範囲が大幅に変更され、派遣割合
の計算に相当の時間を要さざるを得なくなった場合等である。
ロ 関係派遣先への派遣割合制限
- 361-
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
指示の対象となるのは、関係派遣先への派遣割合制限に違反し、法第48条第1項の規定による指
導又は助言を受けたにもかかわらず、合理的理由なく当該指導又は助言に従わず、なお関係派遣先
への派遣割合制限に違反した場合である。
「合理的理由なく」とは、例えば、以下のような場合である。
(力 派遣先の確保のための努力が客観的に認められない場合
「派遣先の確保のための努力が客観的に認められない場合」とは、不特定の者を対象とした
派遣先の確保のための宣伝、広告、営業活動等を正当な理由なく随時行っていない場合であ
る。
「正当な理由」とは、業務そのものが限定的に行われていることから他に派遣先を確保しよ
うとしてもできない場合又は派遣労働者の人数が足りないことに起因して派遣先の確保ができ
ない場合(派遣労働者の確保のための努力が客観的に認められる場合に限る。)である。
② 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者からの労働者派遣の依頼に関し、関係派遣先以外
からのものについては、正当な理由なく全て拒否している場合
「正当な理由」とは、派遣労働者の確保のための努力が客観的に認められるにもかかわらず
派遣労働者の人数が足りない場合等である。
ハ 特定有期雇用派遣労働者に対する雇用安定措置
指示の対象となるのは、派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して3年
間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に対して雇用安定措
置を講じず、法第48条第1項の規定による指導又は助言を受けたにもかかわらず、合理的理由なく
当該指導又は助言に従わず、なお、当該特定有期雇用派遣労働者の雇用安定措置を行わなかった場
合である。
「合理的理由なく」とは、例えば、雇用安定措置を講ずる努力が客観的に認められない場合であ
る。
「雇用安定措置を講ずる努力が客観的に認められない場合」とは、雇用安定措置を正当な理由
なく適切に講じていない場合である。
「正当な理由」とは、派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元事業主での
無期雇用及びその他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置を、派遣元として
実施する意思はあるが、派遣先の都合により派遣先を提供できるのが数日先であるといった他
律的な要因等により、やむを得ず実施できないような場合をいうものであり、単に経営上の理
由等により実施するのが困難というような派遣元の主観的理由のみでは、正当な理由とは言え
ない。
(3)指示の内容
(2)のイ又はロに該当すると判断された派遣元事業主に対しては、「「関係派遣先派遣割合報告書
(様式第12号-2)」を速やかに提出すること」「関係派遣先への派遣割合制限の違反状態を是正す
るための改善措置を速やかに講ずること」を指示する。
- 362 -
第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表
また、(2)のハに該当すると判断された派遣元事業主に対しては、「特定有期雇用派遣労働者の雇
用安定措置を速やかに講ずること」を指示する。
なお、改善措置を講ずるに当たっては、派遣労働者の雇用の安定を確保することが大前提であり、
例えば、関係派遣先に派遣されている派遣労働者を解雇すること等によって派遣割合制限違反を是正
するようなことはあってはならない。
(4)指示の委任
指示に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣
が自らその権限を行うことは妨げられない。
(5)指示の手続等
厚生労働大臣は指示を行うことを決定したときは、ただちに、労働者派遣事業指示書(第16様式集
参照)を作成し、管轄都道府県労働局を経由して当該指示の対象となる者に対して交付する。
都道府県労働局長は指示を行うことを決定したときは、ただちに、労働者派遣事業指示書(第16様
式集参照)を作成し、当該指示の対象となる者に対して交付する。
なお、当該指示に従わない場合は、許可の取消し(法第14条第1項第4号)の対象となるものであ
る。
- 363 -
第14 無許可で労働者派遣事業を行った事業主の公表
第14 無許可で労働者派遣事業を行った事業主の公表
1概要
労働者派遣事業の許可を受けることなく労働者派遣事業を行う事業主(以下、無許可派遣事業主)
については、適正な事業運営の確保及び派遣労働者の保護が十分に期待できないことから、派遣労
働者になろうとする国民一般や派遣労働者の受入を予定している派遣先事業主に対する情報提供を
目的とし、事業主名等を公表することとする。
本公表は、あくまで、情報提供の目的で実施するものであるところ、第13において違法行為につ
いて勧告を受けた者がこれに従わなかった際にその旨を公表(法第49条の2第2項)する場合のよ
うに、「公表される者に対する制裁効果や童法行為の抑止といった効果」を期待するものではなく、
当該事業主に対する処罰を目的とするものではない。
2 無許可派遣事業主への対応
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、無許可派遣事業主を把握した場合は、法第48条に基づ
き、違法状態の是正を求める指導を行うものであるが、無許可で労働者派遣事業を行っていること
が疑われる事業主については、あらかじめ、当該公表について通告するとともに、法第48条に基
づく指導にあわせて事業主名等の公表を行う。
また、当該公表については、違法状態の是正が明らかとなるまで次項に定める項目について、厚
生労働省、事業主管轄及び、無許可派遣を行っていた事業所を管轄する都道府県労働局のホームペ
ージにおいて公表を行うこととする。
3 公表内容
公表内容は以下のとおりである。
(イ)事業主名
(ロ)事業所名
(ハ)所在地
(ニ)主たる派遣事業の内容
(ホ)許可申請等予定日
- 364 -
第14 無許可で労働者派遣事業を行った事業主の公表
〇〇年〇〇月〇〇日
通
告
書株式会社○○
代表取締役 〇〇 〇〇 殿
労働者派遣事業の実施にあたっては「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
に関する法律」第5条第1項によって、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
当該許可を受けずに労働者派遣事業を行った者は、同法第59条第1項第2号によって、1年以下の
懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなっています。
下記の事実について、貴社の行為は当該許可を受けずに行われている労働者派遣事業に該当するお
それがあります。
当該許可を受けずに労働者派遣事業を実施している者については、労働者派遣制度を利用しようと
する方々への情幸田是供のため社名等を公表することとしていますので、その旨通告するとともに、下
記事実等にご意見がある場合は速やかに○○労働局○○部○○課までご連絡願います。
記
○ 確認した事実
本件の問い合わせ先・報告の送付先
〒〇〇〇一〇〇
住所
○○労働局○○部○○課(室)
電話番号
- 365 -
第15 その他
第15 その他
1 行政機関の連携体制の確立
(1)都道府県労働局間の連携
都道府県労働局は、その管轄する派遣元事業主、派遣先等労働者派遣に係る違法行為の防止、摘発
を全責任をもってこれに当たることは、いうまでもないが、派遣元事業主と当該派遣元事業主に係る
派遣先を管轄する労働局が異なる等の場合においても、一貫した違法行為の防止、摘発が行われ、派
遣労働者の保護と労働者派遣事業の適正な運営を確保することが必要である。
このため、労働局は必要に応じ関係労働局に違法行為に関する通報、調査事務の委嘱を行い、当該
通報、調査事務の委嘱を受けた労働局はそれに対応して報告の徴収、立入検査等を行う等その連携を
図ること。
(2)他の労働行政との連携
イ 労働基準監督行政との連携
法の施行に当たっては労働基準監督行政が法第3章第4節(法第47条の2及び47条の3を除
く。)に係る部分を所管し、同節以外の部分については、職業安定行政が所管することとなる
が、派遣元事業主が労働基準法等の労働基準局所管法令に違反した場合には、職業安定行政にお
いて改善命令、許可の取消し等の処分を実施する必要が生じる場合があり、また、相互に自己の
所管する以外の法規定について違法行為を発見する場合もある。
このため、職業安定行政は労働基準監督行政との相互間で情報提供を行う等密接な連携を確保
し、派遣労働者の保護及び労働者派遣事業の適正な運営の確保を図ることとする。
ロ 雇用均等行政との連携
法第47条の2及び47条の3に係る部分は雇用環境・均等局が所管しているものであり、当該規
定に関連して派遣労働者等から相談、苦情があった場合は、職業安定行政は雇用均等行政と必要
な連絡調整を行い、迅速かつ的確な処理に努めるほか、日頃から職業安定行政及び雇用均等行政
は相互に十分な情報交換に努めることとする。
2 派遣元責任者講習
(1)概要
労働者派遣事業を実施するにあたって、法第36条により選任を義務付けられている派遣元責任者
は、労働者派遣事業の許可の申請の日(当該許可の日以後に選任された者については、選任された
日)前3年以内に、平成27年9月29日厚生労働省告示第392 号(以下「告示」という)により、
厚生労働大臣が、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足る能力を養成する講習を実施できる
機関(以下「講習機関)という。)として定める講習機関による講習(以下「派遣元責任者講習」
- 366 -
第15 その他
という。)を受講しなければならない。
講習機関及び講習等については、以下の通りとする。
(2)講習機関の要件等
イ 告示に定める講習機関は、以下のすべてを満たすものと厚生労働大臣が確認できた機関とす
る。
(イ)労働者派遣事業に関わる講習又は研修等の事業実績(広く一般に受講者を募集して開催され
たものに限る。)を申出の日の属する年度又はその前年度を含む連続する3年において少なく
とも各1回以上有する法人であること。
なお、「労働者派遣事業に関わる講習又は研修等」とは、派遣元責任者講習の講義課目の4
課目のうち3課目以上の内容を網羅しているものであること。ただし、平成27年度における事
業実績に限り、本要領改訂前の講義課目であった「関係法令、制度の動向とポイント」を実施
した場合は、「労働者派遣事業に関わる講習又は研修等」の事業実績に含めて差し支えない。
(ロ)法人及びその役員が、法第6条の各号(労働者派遣事業の許可の欠格事由)に該当しないも
のであること。
(ハ)資産について、債務超過の状況にないこと。
(ニ)労働者派遣事業及び職業紹介事業のいずれについても、自ら営むものでないこと。
(ホ)その他不適当であると判断するに足る理由がないこと。
ロ 講習機関は、申出の際に確認を受けた事項の内容に変更があった場合は、改めて該当する事項
について要件を満たすと確認を受けなければならない。
(3)講習の内容等
イ 受講対象者
派遣元責任者講習は、以下の(イ)から(ハ)の者を対象として実施することとする。
(イ)派遣元事業主又は労働者派遣事業を行おうとする者により派遣元責任者として選任されるこ
とが予定されている者
(ロ)派遣元事業主又は労働者派遣事業を行おうとする者により派遣元責任者に選任されている者
(ハ)その他労働者派遣事業に関する一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者
口 講習の内容等
(イ)講習の内容
講習の内容は、第14-1表に基づき行わなければならない。ただし、各講義課目の時間数が
減少しない限り、講習の内容を充実させることは差し支えない。
また、労働関係法令等の改正や政策に変更が生じたことにより、派遣元責任者への講習の内
容に変更や追加すべき事項が生じた場合においては、指示に従い適切に追加等しなければなら
- 367 -
第15 その他
ない。
(ロ)テキスト・資料の内容
講習で使用するテキスト等については、講習機関において作成、定めるものとするが、第14
-2表に掲げる資料を必ず含めるものとする。
また、内容に不適切な点があると厚生労働大臣が指摘をした場合、すみやかに修正しなけれ
ばならない。
ハ 講習の実施方法等
講習機関は、講習の実施に当たって次の事項を行うものとする。
(イ)講習の日程等
a 派遣元責任者講習実施日程書の登録等
開催予定の講習については、開催日の前々月の末日までに厚生労働省のホームページに掲
載する。このため、講習機関は、厚生労働省のホームページ掲載希望日の1箇月前までに、
派遣元責任者講習実施日程書(様式第19号)により、厚生労働大臣に掲載を申し出なければ
ならない。
厚生労働省は、派遣元責任者講習実施日程書の講習会場に対して、講習会場番号を振り出
す。
なお、厚生労働省ホームページへの掲載申出に当たり、当該ホームページへの掲載申出日
の1箇月後の日の属する月の翌々月の1日から起算して、少なくとも6箇月以上に渡る期間
の開催予定について申し出るものとする。
b 講習の追加・削除、変更等
講習の追加・削除及び、派遣元責任者講習実施日程書の項目の変更については、原則、当
該追加・削除、変更に係る講習の開催日の前々月の末日の1箇月前まで、厚生労働省にホー
ムページの掲載内容の変更を申し出ることができるものとする。その他やむを得ない変更が
ある場合については、随時、申し出ることができることとするが、更新までの期間が短い等
の場合、開催までに反映されない場合がある。
(ロ)受講希望者の募集及び登録
a 募集締切日時については、
(力 特定の日時を定める方法
② あらかじめ定めた定員に達した時点とする方法
③(力又は②のいずれか速いものとする方法
のいずれかの方法をもって定めるものとすること。募集締切日時を経過後に空き定員が生じ
た場合には、厚生労働省のホームページに掲載した募集締切日時にかかわらず、引き続き受
講者の募集を行って差し支えないものであること。
b 受講希望者の登録は、応募順又は募集締切日時後の抽選とし、これ以外の方法により、例
- 368 -
第15 その他
えば、募集開始日前等に一部の受講希望者を対象として優先的な登録等を行ってはならない
ものとする。
ただし、開催日の翌月又は翌々月に派遣元責任者に就任することを予定する者のみに限定
した募集枠を設けることは差し支えないものとする。この場合、限定募集枠に係る募集締切
日時及び受講定員を下記(4)のイ(へ)派遣元責任者講習実施日程書に記載すること。
C 講習機関においては、あらかじめ定めた受講定員に達した後、キャンセル待ちの応募を受
け付けることができるものとする。キャンセル待ちでの受付を行う場合には、あらかじめそ
の方法について定め、明示するとともに、キャンセル待ちの対象となっている受講希望者に
はその旨を通知すること。
(ハ)受講者名簿の作成等
a 開催者番号、講習会場番号、受講者番号、受講年月日、受講者氏名を記載した受講者名簿
(様式第20号)を作成すること。
b 講習終了後、速やかに受講修了者に対し、受講証明書(様式第21号)を交付すること。
受講証明書を交付した受講者には、受講者名簿に受講証明書交付済みの印を押すこと。ま
た、押印済みの受講者名簿は写しを作成しておくこと。
C 受講証明書交付済み及び本人確認の実施済みの印を付した受講者名簿の写しは、講習終了
後2週間以内に厚生労働大臣に提出すること。
d 講習に係る課目ごとの講義時間及び講師の氏名、肩書きを記載した実施報告書を上記ハと
併せて提出すること。なお、実施報告書は写しを作成しておくこと。
e 上記a(厚生労働大臣に提出したものの原本)及びd(写し)の書類については、当該講
習終了後5年間保存すること。
(ニ)受講対象者の限定及び受講料
上記(ロ)のbのただし書による場合を除き、講習機関の従業員、構成員等の関係者、講習
機関の営む事業の利用者その他の特定の者に対象を限定し又は募集枠を設けて講習を実施する
ものではないこと。
なお、受講料については、あらかじめ対象者及び金額を明確にした上で、別に定めをするこ
とができるものとする。ただし、この場合は、上記、派遣元責任者講習実施日程書においてそ
の内容を具体的に記載すること。
(ホ)遅刻、離席等に係る受講証明書交付の取扱い
遅刻又は離席があった者、受講の態度が良好でないものと講習機関が判断した者、本人確認
ができない者に対しては、受講証明書を交付してはならない。ただし、遅刻又は離席の場合に
あっては、その理由が講習機関において真にやむを得ないものと認めるときは、この限りでな
い。
(へ)欠席、遅刻等に係る受講料の取扱い
- 369 -
第15 その他
受講者の欠席、遅刻等の場合における受講料の取扱いについては、あらかじめ講習機関にお
いて定め、明示するものとする。
(ト)講習における休憩時間の確保
講習の実施に当たっては、所定の講義時間とは別に、概ね2時間に10分以上の休憩時間を設
けることとする。
(4)手続き関係
イ 講習実施の申出
講習機関となることを希望する事業者は、次の書類を厚生労働大臣(厚生労働省職業安定局需
給調整事業課を経由。)に提出することとする。
厚生労働大臣が講習機関と認めるまで2箇月程度を要することから余裕をもって関係書類を提
出すること。なお、講習機関となることを希望する場合、事前に需給調整事業課に提出等の相談
をすることが望ましい。
(イ)派遣元責任者講習実施申出書(様式第18号)
(ロ)定款又は寄附行為及び法人登記事項証明書
(ハ)労働者派遣事業に関わる講習又は研修等の事業実績を証する書類(初回の申出時のみ)
(具体的には、①講習又は研修等の日時、場所、受講対象者等が記載された受講者募集案内、
②講習又は研修等のテキスト及び資料、③受講者氏名(所属名を含む。)、講師氏名等を記載
した実施結果を証する書類等)
(ニ)代表者及び役員の履歴書
(ホ)直近年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他資産の内容を証する下
記a及びbの書類
a 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(持分会社に
あっては、社員資本等変動計算書。以下「株主資本等変動計算書等」という。)(税務署に
提出したもの。)
b 資産の内容及びその権利関係を証する書類
(a)最近の事業年度における法人税の納税申告書の写し(税務署の受付印のあるもの(電子
申請の場合にあっては、税務署に受け付けられた旨が確認できるもの。以下同じ。)に限
る。法人税法施行規則別表1及び4は必ず提出すること。)
(なお、連結納税制度を採用している法人については次に掲げる書類
・ 最近の連結事業年度における連結法人税の納税申告書の写し(連結親法人の所轄税務
署の受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表1の2「各連結事業年度分の連結
所得に係る申告書」の写し及び同申告書添付書類「個別帰属額等の一覧表」の写しのみ
でよい。ただし、別表7の2付表2「連結欠損金個別帰属額に関する明細書」が提出さ
- 370 -
第15 その他
れる場合には、その写しを併せて提出させること。)
・ 最近の連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書(申出法人に係るものに限
る。)の写し(税務署に提出したもの。ただし当該届出書の別表にあっては別表4の2
付表「個別所得の金額の計算に関する明細書」の写しのみでよい。))
(b)納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式
(その2)による法人の最近の事業年度における所得金額に関するもの)
(なお、連結納税制度を採用している法人については納税証明書(国税通則法施行令第4
1条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による最近の連結事業年
度における連結所得金額に関するもの))
(へ)派遣元責任者講習実施日程書(様式第19号)
(ト)派遣元責任者講習において配布予定のテキスト及び資料
口 厚生労働大臣は、(2)の要件を満たすと確認した講習機関に対して、講習機関番号を振り出す。
講習機関番号を振り出した講習機関については、厚生労働大臣の告示をもって公表する。
講習機関番号の振り出しを受けた講習機関による受講者の募集は、告示後であって、かつ厚生
労働省のホームページ掲載日以降に開始できるものとする。
ハ 講習機関の名称又は住所が変更となった場合、派遣元責任者講習実施申出書(様式第18号)に
変更後の名称又は住所を記載し申し出るものとする。申出を行うにあたっては、変更後の名称又
は住所を確認する書類として、(4)イ(ロ)の書類を併せて提出すること。
厚生労働大臣は、申出書及び確認書類を確認の上、告示された講習機関の名称又は所在地を変
更するものとする。
ニ 厚生労働大臣の確認を受け、告示された講習機関が、今後講習を実施する見込みがなくなった
場合又は(2)の要件を満たさなくなった場合、派遣元責任者講習廃止申出書(様式第24号)により
申し出るものとする。
厚生労働大臣は、申出書を確認の上、告示から講習機関を削除するものとする。
(5)講習の適正な実施等について
イ 講習機関においては、講習の講義時間、講習で使用するテキスト・資料を当該講習以外の宣伝
等他の目的の手段として利用するものではないこと。
ロ 講習の適正な実施等の観点から必要があると厚生労働省が認めるときは、講習機関に対して報
告を求め、又は調査を行うことができるものとする。報告又は調査を求められた講習機関は、こ
れに応じなければならない。
ハ 報告又は調査に基づき厚生労働省が当該講習機関による派遣元責任者講習について適正に実施
していないと認める場合、講習機関に以下の対応を指示するものとする。
(イ)講習の実施内容の一部又は全部の改善
- 371-
第15 その他
(ロ)講習の一部又は全部の停止
(ハ)その他講習実施に当たっての体制等の一部又は全部の改善
二 指示を受けた講習機関は、ハの指示に対する改善計画を厚生労働大臣に提出するとともに、誠
実に改善計画を履行しなければならない。
また、その結果については、厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
ホ 上記この改善が確認できない場合、ロの報告又は調査に正当な理由なく応じなかった場合、厚
生労働大臣への申出内容に虚偽があった等の場合、(2)の確認を撤回することがあること。
ヘ ホにより(2)の確認を撤回された者については、受講希望者保護の観点から当該事実に係る事業
主名、所在地、撤回の理由等を公表するとともに、撤回された日から3年の間、講習機関となる
ことはできないものであること。
ト 派遣元責任者講習に係る受講者に対する本人確認の徹底
講習の受講及び受講証明書の発行に際して、講習のなりすまし受講を防止するため、受講者の
本人確認の徹底をすること。本人確認は、運転免許証、パスポート等、顔写真付きの公的証明書
又は国民健康保険証、住民基本台帳カード等、公的証明書にて確認を行うことが望ましい。
- 372 -
第15 その他
第14-1表 派遣元責任者講習の内容
派遣元責任者講習は、次の内容により行わなければならない。
ただし、各講義課目の時間数が減少しない限り、講義内容を充実させることは差し支えない。
講義課目 唇尋 講義内容
労働者派遣事業の適 2時間
正な運営の確保及び
派遣労働者の保護等
に関する法律
(力わが国の労働力需給調整の体系(労働者派遣事業、職業
紹介事業、労働者供給事業、募集を含む。)
②法の意義、目的(第1章総則関係)
③適用除外業務(法第4条)
④労働者派遣事業(法第5条)
⑤労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置(法第
5条~第25条)
⑥労働者派遣契約(法第26条~第29条の2)
⑦派遣元事業主の講ずべき措置等(法第30条~第38条)(
「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」及び「日雇
派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び
派遣先が講ずべき措置に関する指針」並びに「短時間・有
期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止
等に関する指針」を含む。)
⑧派遣先の講ずべき措置等(法第39条~第43条)(「派遣
先が講ずべき措置に関する指針」及び「日雇派遣労働者の
雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ず
べき措置に関する指針」並びに「短時間・有期雇用労働者
及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指
針」を含む。)
⑨行政指導、行政処分、罰則等(法第48条~第62条等)
労働基準法等の適用1時間 (力労働基準法及び労働安全衛生法等の適用に関する特例等
に関する特例等につ (法第3章第4節)
いて ②最近の労働基準法等の改正の動向とポイント
労働者派遣事業運営 2時間20(力最近(過去5年間程度とする。以下同じ。)の労働者派
の状況及び派遣元責分 遣事業制度の改正等
任者の職務遂行上の ・法令、指針、労働者派遣事業関係業務取扱要領等
- 373 -
第15 その他
留意点について
②最近の労働者派遣事業の運営状況
・労働者派遣事業報告の集計(厚生労働省公表)からみた
実情(派遣労働者数、料金、賃金等の推移等)
・各種調査による労働者派遣事業の実態
③最近の監督指導状況(厚生労働省公表)を踏まえた事業
運営上の問題点
④派遣元責任者の職務遂行上の留意点
・労働安全衛生法第59条に基づく安全衛生教育に必要とす
る知識の付与
・キャリアコンサルティングの実施に必要とする知識の付
与
・キャリアアップ措置に資するための教育訓練の実施に必
要とする知識の付与
・苦情処理を円滑に行うために必要とする知識の付与
(労使関係法規、労働基準関係法規、派遣労働者からの苦
情に対処するための心がまえ等)
・派遣労働者へ周知・啓発する労働関係法令等
(a)労働基準法(労働契約、賃金、労働時間、休憩、休
日、年次有給休暇、妊産婦等、就業規則)
(b)最低賃金法(最低賃金)
(C)労働安全衛生法(安全衛生教育、健康診断)
(d)雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
等に関する法律(性別を理由とする差別の禁止、婚姻、
妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等、職場
における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上
の措置)、パワーハラスメントに関すること
(e)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律(育児休業、介護休業、子の看護
休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限
、深夜業の制限)
(f)労働契約法(無期労働契約への転換、有期労働契約
の更新、不合理な労働条件の禁止)
(g)労働組合法(不当労働行為)
(h)労働保険制度(雇用保険、労災保険)、社会保険制
- 374 -
第15 その他
度(健康保険、厚生年金)
(上記内容(制度改正があればそれも含む。)について
は、労働者派遣法の概要及び改正の概要と併せ、派遣元
責任者等が雇入れ時等に派遣労働者に周知・啓発するよ
う説明すること。)
⑤事例紹介
(経験者のみを対象とする講習の場合にあっては参加者に
よるディスカッション(講師が指導的なコメントを付する
ことが必要)をもって事例紹介に代えることができる。)
⑥その他派遣元責任者の職務に関して留意が必要な事項
・雇用政策の方向、社会経済情勢一般等
個人情報の保護の取40分
扱いに係る労働者派
遣法の遵守と公正な
採用選考の推進につ
いて
①労働者派遣法、職業安定法等における個人情報の取扱い
②公正な採用選考の推進について
- 375 -
第15 その他
第14-2表 派遣元責任者講習において配付する資料
講習で使用するテキスト等については、講習機関において定めるものとするが、次に掲げる資料を
必ず含めるものとする。
資料の項目 配付する部分等
(力労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律
全部
②労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律施行令
全部
③労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律施行規則
全部
④労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省令
全部
⑤労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関す
る基準を定める告示
全部
⑥労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律第40条の2第1項第2号ロの規定に基づき厚
生労働大臣の定める日数
全部
⑦労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律施行令第1条の規定に基づき厚生労働大臣が
指定する区域を定める告示
全部
⑧派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 全部
⑨派遣先が講ずべき措置に関する指針 全部
⑲日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主
及び派遣先が講ずべき措置に関する指針
全部
⑪職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労
働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等
の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的
確な表示等に関して適切に対処するための指針
全部
⑫労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律施行規則第1条の4第1号の規定に基づき厚
生労働大臣が定める基準
- 376 -
全部
第15 その他
⑬労働者派遣事業関係業務取扱要領 全部
⑭労働基準法
第3条、第5条、第7条、第32条
~第32条の4の2、第33条~第38
条の3、第40条、第41条、第60条
~第63条、第64条の2、第64条の
3、第66条~第69条、第99条~第
102条、第104条、第104条の2、第
105条の2、第106条、第109条、第
112条
⑮労働安全衛生法
第3条第1項、第4条、第5条、
第9条~第19条の2、第20条~第
27条、第28条第4項、第28条の2
、第29条~第32条、第33条第1項
及び2項、第34条、第36条、第45
条、第46条第2項、第56条第6項、
第57条の3~第58条、第59条第2
項及び第3項、第60条、第60条の
2、第61条第1項、第62条、第63
条、第65条~第65条の4、第66条
第2項~第5項、第66条の3、第
66条の4、第66条の5第1項及び
第3項、第68条~第70条、第70条
の2第2項、第71条の2、第71条
の3第2項、第71条の4、第74条
第2項、第75条の3、第75条の4
第2項、第75条の5第4項、第79
条~第80条、第84条第2項、第88
条~第90条、第91条第1項、3項
及び4項、第92条、第93条第2項
及び第3項、第94条第1項、第97
条~第99条、第99条の2第1項及
び第2項、第99条の3第1項、第
100条~第102条、第103条第1項、
- 377 -
第15 その他
第104条、第106条第1項、第108条
の2第3項、第114条、第115条第
1項
⑱じん肺法
第5条~第18条、第20条の2~第
21条、第22条、第22条の2、第32
条、第35条の2、第35条の3、第
39条~第44条
⑰作業環境測定法
第1条~第4条、第6条、第8条
、第12条、第21条、第23条、第32
条、第34条、第38条~第57条
⑱雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に
関する法律
第9条、第11条~第13条
⑲育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福第10条、第16条、第16条の4、第
祉に関する法律 16条の7、第16条の10、第18条の
2、第20条の2、第23条の2、第
25条
⑳「公正な採用選考をめざして」 全部の写し
㊧その他厚生労働省から指示するもの
- 378 -
第15 その他
3 派遣先責任者講習
(1)概要
法第41条により選任を義務づけられている派遣先責任者に対し、関係法令やその職務に関する必
要な知識等を付与することで、派遣先責任者の能力向上を図り、その職務を的確に遂行できるよう
にすることを目的とする。
派遣先責任者講習(以下「講習」という。)が適正に実施されるよう、厚生労働省において、平
成30年3月30日に「派遣先責任者講習の実施に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」と
いう。)を制定しており、ガイドラインに基づき、ガイドラインの定めに従って講習を実施する講
習機関については、(2)の通り、厚生労働省職業安定局需給調整事業課(以下「担当課」という。)
あて申出を行うものとする。
派遣先責任者講習の実施に関するガイドライン
厚生労働省
平成30年3月 30 日制定
1.日的
労働者派遣事業の適正な運営を確保し、派遣労働者の保護等を図るためには、派遣先が、労働者派遣法、
派遣先指針<注1>等に基づき講ずべき措置を適切かつ有効に実施していく必要がある。そのためには、派
遣先が、同法第41条に基づき選任を義務付けられている派遣先責任者の能力向上を図り、派遣先責任者が
その職務を的確に遂行できるようにしていくことが重要である。
派遣先責任者の能力向上を図るに当たっては、関係法令やその職務に関する必要な知識等を付与するため
の派遣先責任者講習(以下「講習」という。)が適正に実施され、派遣先が、派遣先責任者を新たに選任し
たとき、労働関係法令の改正が行われたとき等の機会を捉え、これを派遣先責任者に受講させることが望ま
しい。
本ガイドラインは、こうした考え方の下、平成27~29年度に実施したモデル事業<注2>の実施結果を
踏まえ、講習の内容、講習の実施に当たって留意すべき事項その他必要な事項を定めることにより、講習が
適正に実施されるようにし、派遣先責任者の能力向上を図り、派遣先責任者がその職務を的確に遂行できる
ようにすることを目的とする。
<注1>労働者派遣法:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60
年法律第88号)
派遣先指針:派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)
<注2>「派遣先による派遣労働者の雇用管理改善に資する体制の普及・促進のための派遣先責任者講習モ
デル事業」(平成27~29年度厚生労働省委託事業)
2.講習の内容等
(1)受講対象者
講習は、以下の者を対象として実施する。
ア 派遣先責任者として選任されることが予定されている者
イ 派遣先責任者に選任されている者
ウ その他労働者派遣事業に関する一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者
(2)講習の内容
ア 講習の内容は、別表1「派遣先責任者講習の内容」に基づき行うことを基本とする。ただし、同表
の課目ごとに定める基礎的な知識の習得に充てるべき最低限の時間数を確保し、かつ、合計時間数が
5時間を下回らない限りにおいて、講習をより効果的なものとする観点から、講習の内容を充実させ
- 379 -
第15 その他
ること<注3>又は課目ごとの時間配分を柔軟に行うことは差し支えない。
<注3>例えば、グループワークを実施すること、振り返りの時間を設けること等が考えられる。
イ 労働関係法令の改正や政策に変更が生じたこと等により、アの講習の内容を変更し、又は追加する
必要が生じた場合においては、これを適切に変更等すること。
ウ アの講習の内容については、そのすべてを連続して実施しなければならないものではなく、複数の
時間帯又は目に分割して実施することも差し支えない<注4>。分割して実施する場合には、受講者
の受講状況の管理を適切に行うこと。
<注4>例えば、講習の内容を「制度編」「実務編」のように区分して実施することも差し支えな
い。
エ アの講習の内容については、次の点に配慮することが望ましい。
① 各講義課目において、具体的な事例(例えば、派遣労働者の受入れに際して発生したトラブル
の内容及びその対処方法等)を積極的に取り入れる等、受講者にとって有用な内容にすること。
② ①の事例の取入れに当たっては、可能な限り、受講者の属する派遣先の産業(製造業、サービ
ス業等)や職務(事務職、製品製造・加工職等)、受講者の関心等を踏まえたものとすること。
③ 受講者の理解に資するよう、適宜、映像(ビデオ等)を用いる等の工夫を行うこと。
(3)テキスト・資料の内容
講習で使用するテキスト等は、別表2「派遣先責任者講習で使用するテキスト等の項目例等」を参
考に、講習を実施する者(以下「講習機関」という。)において作成し、定めること。
(4)講師
講師については、各講義課目について十分な知識や経験を有する者とすること。その際、法令の規
定と、派遣労働者の受入れに関する具体的な実務とを関連付けた講義を行うことができるよう、こう
した実務に関する経験を合わせて有する者とすることが望ましい。
3.講習の実施方法等
(1)受講料
ア 受講料については、これを明確に定めるとともに、特定の者に対し不当な差別的取扱いをしないよ
うにすること。
イ 受講者の欠席、遅刻等の場合における受講料の取扱いについても、あらかじめ講習機関において定
め、明示すること。
(2)開催目時等の周知
講習機関は、講習の開催目時、開催場所(講習会場)、定員数、受講料、講師の氏名等について、受
講しようとする者がこれらの情報を容易に得られるよう、講習機関のホームページに掲載するなど適
切な方法で周知すること。
(3)受講者名簿の作成等
ア 講習機関は、受講年月日、受講場所、受講者氏名、受講証明書(修了証)の交付の有無(イ参照)
等を記載した受講者名簿を作成すること。
イ 講習機関は、受講修了者に対し、受講証明書(修了証)を交付するとともに、その旨をアの受講者
名簿に記載しておくこと。
ウ 講習機関は、受講者名簿その他講習の実施に際し作成し、及び取得した記録を一定期間(5年程度
が望ましい)保存しておくこと。
エ 講習の実施に際し取得した個人情報については、その取扱いに十分留意し、適正に管理を行うこ
と。
オ e-ラーニングで講習を実施する場合は、適切な方法で受講者の本人確認を行うとともに、受講状
況の確認、問合せへの対応等についても適切に行うこと。
カ 2(2)ウにより講習の内容を分割して実施する場合には、講習機関及び受講者が受講状況を確認
できるよう、講習の一部を受講した旨の受講証明書の交付を適切に行うこと。また、2(2)アの講
習の内容のすべてを修了した者を受講修了者とすること。なお、一部を受講した段階で、労働関係法
令の改正等により講習の内容に変更があった場合は、当該変更後のもののすべてを終了した者を受講
修了者とすること。
(4)その他
- 380 -
第15 その他
ア 講習機関は、講習の講義時間を、自社の事業の宣伝等講習以外の目的で利用しないこと。講習終了
後に希望者に対し宣伝等を行う場合であっても、不当な誘引とならないようにすること。
イ 講習の適正な実施を確保する観点から、講習機関は、労働者派遣法第6条各号(労働者派遣事業の
許可の欠格事由)に該当しない者であること、資産について債務超過の状況にないこと等、労働者派
遣事業関係業務取扱要領に定める派遣元責任者講習の講習機関の要件<注5>を満たしている者であ
ることが望ましい。
<注5>ただし、派遣元事業主は派遣先における適正な派遣就業の確保を図る責務があること等を
踏まえ、当該要件のうち「労働者派遣事業及び職業紹介事業のいずれについても、自ら営む
ものでないこと。」との要件については、これを満たさなくても差し支えない。
4.厚生労働省への情報提供等
厚生労働省においては、本ガイドラインの定めに従って講習を実施する講習機関を把握し、ホームページ
等を通じて周知するとともに、その後の実施状況等を把握するため、当該講習機関に対し、任意での情報提
供を依頼することとしている。
このため、次に掲げる事項に同意して講習を実施する講習機関は、厚生労働省職業安定局需給調整事業課
(以下「担当課」という。)あて、別に定めるところにより届出を行うこと。
① 講習機関が実施する講習は、すべて本ガイドラインの定めに従ったものとすること。
② 講習の実施状況その他講習に関する情報提供について担当課から協力依頼があった場合には、これに応
ずること。
③ 講習の実施が適正に行われていないと担当課が認める場合(以下「不適正な場合」という。)であって
担当課から改善要請があったときは、これに応ずること。当該要請にもかかわらずなお不適正な場合に
は、受講希望者保護の観点から担当課において当該事実、講習機関名、所在地等の公表を行うことがあ
る。
別表1 派遣先責任者講習の内容
講義課目 悪霊 講義内容
労働者派遣事業の適 1時間
正な運営の確保及び
派遣労働者の保護等
に関する法律
○法の意義・目的を踏まえ、派遣先の講ずべき措置等(法第39条
~第43条及び第47条の4)(「派遣先が講ずべき措置に関する指
針」及び「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業
主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」を含む。)を中心に、
派遣先で理解すべき法令の知識の付与を行う。
労働基準法等の適用 2時間
に関する特例等 (1時間
以上)
○労働基準法等の適用に関する特例等(法第3章第4節)
・派遣先責任者がその職務を果たすにあたっての労働基準法の基
礎、労働安全衛生法の基礎を内容とし、実務と応用に関する知識の
付与を行う。
・労働基準法及び労働安全衛生法において、派遣先が負う使用者責
任について、「特例が設けられている意義」、「派遣先の責任分担の
内容」等、具体例を挙げて講義を行う。
派遣先責任者の職務 2時間
遂行上の留意点 (1時間
以上)
○派遣先責任者の職務遂行上の留意点
○苦情処理を円滑に行うために必要とする知識の付与
(労使関係法規、労働基準関係法規、派遣労働者からの苦情に対処
するための心がまえ等)
○事例紹介(実際に派遣労働者を受け入れて発生したトラブル等と
その対処方法等)。
○その他派遣先責任者の職務に関して留意が必要な事項
備考
講義時間の括弧内の時間数は、基礎的な知識の習得に充てるべき最低限の時間数であり、この最低限の
時間数を確保し、かつ、合計時間数が5時間を下回らない限りにおいて、講習の内容を充実させること又
は課目ごとの時間配分を柔軟に行うことは差し支えない。
- 381-
第15 その他
別表2 派遣先責任者講習で使用するテキスト等の項目例等
講義課目 具体的な項目例
テキスト等の作成に
当たってのポイント
労働者派遣事業
の適正な運営の
確保及び派遣労
働者の保護等に
関する法律
○労働者派遣法の意義、目的、概要等
○派遣先の講ずべき措置等
・労働者派遣契約に関する措置
・適正な派遣就業の確保
・派遣先による均衡待遇の確保
・派遣先の事業所単位の期間制限の適切
な運用
・派遣労働者個人単位の期間制限の適切
な運用
・期間制限を超えて労働者派遣の役務の
提供を受けた場合の取扱い
・特定有期雇用派遣労働者の雇用
・派遣先での正社員化の推進
・離職した労働者についての労働者派遣
の役務の提供の受入れの禁止
・派遣先責任者の選任
・派遣先管理台帳
・労働・社会保険の適用の促進
・関係法令の関係者への周知
・派遣労働者を特定することを目的とす
る行為の禁止
・性別・障害の有無・年齢による差別的
な取扱いの禁止等
・紹介予定派遣
○法の意義・目的や労働者派遣制度の仕
組みなど、制度の理解に必要となる基本
的な部分を含めること。
○法の規定のみならず、「派遣先が講ずべ
き措置に関する指針」の内容も踏まえ、
派遣先が遵守すべき規定を過不足なく含
めること。
○近年の制度改正の趣旨及びその内容に
ついても十分に理解できるよう、テキス
ト等に含めること。
労働基準法等の
適用に関する特
例等
○特例が設けられている意義等
○労働基準法の適用に関する特例
○労働安全衛生法の適用に関する特例等
○じん肺法の適用に関する特例等
○作業環境測定法の適用の特例
○雇用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に関する法律の適用の
特例
○育児休業、介護休業等育児又は家族介
護を行う労働者の福祉に関する法律の適
用の特例
○労働基準法等における使用者責任の原
則と、特例が設けられている意義の双方
を理解できるような内容とすること。
○派遣元と派遣先とで負うべき責任が異
なることを踏まえ、派遣先が負うべき責
任を中心に説明する内容とすること。
派遣先責任者の
職務遂行上の留
意点
○労働者派遣制度の改正状況
○派遣先責任者の職務遂行上の留意点
○苦情処理を円滑に行うために必要とす
る知識の付与
○事例紹介(実際に派遣労働者を受け入
れて発生したトラブル等とその対処方法
等)
○その他派遣先責任者の職務に関して留
意が必要な事項
○具体的な事例を複数含める等、実際に
職務を遂行する上で参考となる内容とす
ること。
- 382 -
第15 その他
関係法令集
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及
び派遣労働者の保護等に関する法律
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及
び派遣労働者の保護等に関する法律施行
令
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及
び派遣労働者の保護等に関する法律施行
規則
○労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準
○派遣元事業主が講ずべき措置に関する
指針
○派遣先が講ずべき措置に関する指針
○日雇派遣労働者の雇用の安定等を図る
ために派遣元事業主及び派遣先が講ずべ
き措置に関する指針
○労働者派遣事業関係業務取扱要領
○労働基準法
○労働安全衛生法
○じん肺法
○作業環境測定法
○雇用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に関する法律
○育児休業、介護休業等育児又は家族介
護を行う労働者の福祉に関する法律
○必ずしも全文を掲載する必要はない
が、制度の理解に必要となる基本的な部
分に関する規定及び派遣先が遵守すべき
規定については、法令上の根拠を確認で
きるようにしておくこと。
備考
受講対象者を特定の業種等に限定した講習を実施する場合において、当該業種等には関係のないことが
明らかな項目については、当該講習に用いるテキストに含めないこととしても差し支えないこと。(例え
ば、じん肺法の適用がない業種に限定した講習を実施する場合に、じん肺法に係る項目をテキストに含め
ないことは差し支えない。)
(2)講習の実施に係る手続
イ 講習実施の申出
ガイドラインの定めに従って講習機関となることを希望する事業者は、次の書類を担当課に提
出すること。なお、提出に当たっては、事前に担当課に提出等の相談をすることが望ましい。
(イ)派遣先責任者講習実施申出書(様式第22号)
(ロ)派遣先責任者講習実施日程書(様式第23号)
(ハ)派遣先責任者講習において配布予定のテキスト及び資料
口 講習機関名等の厚生労働省ホームページへの掲載
上記イにより申出があった講習機関について、厚生労働省ホームページへの掲載を希望する場
合は、提出された書類を基に、講習機関名、所在地、電話番号及び講習の開催日時等の掲載を行
う。なお、掲載に当たっては以下の点に留意すること。
(イ)講習機関名、所在地又は電話番号の変更
- 383 -
第15 その他
講習機関名、所在地又は電話番号が変更となった場合、派遣先責任者講習実施申出書に変更
後の講習機関名等を記載し、速やかに担当課に申し出ること。
(ロ)派遣先責任者講習実施日程書の登録等
開催予定の講習については、開催日の前々月の末日までに厚生労働省のホームページに掲載
する。このため、講習機関は、厚生労働省のホームページ掲載希望日の1箇月前までに、派遣
先責任者講習実施日程書により、担当課に掲載を申し出ること。
なお、厚生労働省ホームページへの掲載申出に当たり、当該ホームページへの掲載申出日の
1箇月後の日の属する月の翌々月の1日から起算して、少なくとも3箇月以上に渡る期間の開
催予定について申し出ることが望ましい。
(ハ)講習の追加・削除、変更等
講習の追加・削除及び、派遣先責任者講習実施日程書の項目の変更については、原則、当該
追加・削除、変更に係る講習の開催日の前々月の末日の1箇月前まで、厚生労働省にホームペ
ージの掲載内容の変更を申し出ることができるものとする。その他やむを得ない変更がある場
合については、随時、申し出ることができることとするが、更新までの期間が短い等の場合、
開催までに反映されない場合がある。
4 民間の協力体制の整備
(1)概要
法の施行に当たっては、行政機関による違法行為の防止、摘発に加え、民間の自主的な活動によ
って労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の保護を図っていくことが必要不可欠である。
このため、上記の観点からの派遣元事業主団体の育成、当該事業主団体を通じての派遣元事業主
への法の周知徹底、指導等が行われるよう努めるとともに、行政機関の違法行為の防止、摘発を補
完するものとして派遣先、派遣労働者等に対する相談援助等を行う協力員を民間から選任し、設置
する等民間の総合的な協力体制を整備するものとする。
(2)労働者派遣事業適正運営協力員
イ 概要
厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門
的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員(以下「協力員」とい
う。)を委嘱することができる(法第53条)。
ロ 目的
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する施策に協力して、派遣元
事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じ、専門的な助言を行うことを目的とする。
ハ 運営
- 384 -
第15 その他
(イ)協力員制度が、派遣労働者、派遣元事業主、派遣先等に広く認識され、積極的に活用される
よう、当該制度周知用ポスターを作成し、公共職業安定所や派遣元事業主団体に配付するほ
か、派遣先責任者研修等においても十分周知するものとする。
(ロ)各公共職業安定所に地域の協力員の氏名、連絡先を記載した名簿を掲示し、又は備え付け、
派遣労働者や派遣元事業主等からの問い合わせに応じるほか、各都道府県労働局においても、
協力員制度の概要や協力員名簿をホームページに掲載すること等により、それらの者が自由に
閲覧できる体制を整える。
(ハ)相談を受けた協力員が、派遣元事業主や派遣先に接触しやすいように、身分証明書を作成
し、協力員の円滑な相談、援助活動の一助とする。
なお、身分証明書は都道府県労働局長が交付する(第15様式集参照)。
(ニ)各都道府県労働局は、「労働者派遣事業適正運営協力員会議」を年1回以上開催することと
し、協力員間の情報交換や協力員への情報提供を十分に行う。
- 385 -
第16 様式集
- 386 -
様式第1号(第1面)
労働者派遣事業
厚 生 労 働 大 臣 殿
許
(日本工業規格A列4)
※許可番号
※ 芸可有効期間更芸年月日 年 月 日
可
許可有効期間更新
申 請 者
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
許 可□
許可有効期間更新口
を申請します。
申請書
第5条第1項
第10条第2項
年 月 日
=
の規定により、下記のとおり
申請者(法人にあっては役員を含む。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
法律第6条各号(個人にあっては第1号から第9号まで、第11号及び第12号)のいずれにも該当しないこと並びに同
法第36条の規定により選任する派遣元責任者は、未成年者でないこと、同法第6条第1号から第8号までのいずれに
も該当しないこと及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する律施行規則第29条の2に
規定する基準に適合することを誓約します。
(ふりがな)
1氏名又は名称
〒(
)
( )
2 住 所
3 大企業、中小企業の別 1 大企業 2 中小企業 4全労働者数
5産業分類 名称 分類番号
6 役員の氏名、役名及び住所(法人の場合)
ふりがま
氏 名
役 名 住 所
㈲凰
収入印紙
(消印しては
ならない。)
-387-
様式第1号(第2面) (日本工業規格A列4)
7労働者派遣事業を行う事業所に関する事項
(ふりがな)
(力事業所の名称
(塾事業所の所在地
〒(
)
( )
③特定製造業務への労働者派遣の実施の有無 有 無
④派遣元責任者の氏名、職名、住所等
(ふりがな)
氏 名
職 名 住 所
[⊃[=]
[⊃[=]
[⊃[=]
⑤詣呈昌詣芸㌫震憲昔謂㌍名及び職名(④⑥派遣元責任者の職務代行者の氏名及び職名 ⑦備考
(ふりがな)
氏 名
職 名
(ふりがな)
氏 名
職 名
⑧事業所枝番号(更新の申請時のみ記載)
・:・
(ふりがな)
(力事業所の名称
(塾事業所の所在地
〒(
)
( )
③特定製造業務への労働者派遣の実施の有無 有 無
④派遣元責任者の氏名、職名、住所等
(ふりがな)
氏 名
職 名 住 所
[⊃[=]
[⊃[=]
[⊃[=]
⑤詣呈昌詣芸㌫震憲漂謂㌍名及び職名(④⑥派遣元責任者の職務代行者の氏名及び職名 ⑦備考
(ふりがな)
氏 名
職 名
(ふりがな)
氏 名
職 名
⑧事業所枝番号(更新の申請時のみ記載)
・:・
8 許可年月日 年 月 日 9 許可番号
10事業開始予定年月日 年 月 日
11その他
-388-
(日本工業規格A列4)
様式第1号(第3面)
記載要領
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※印欄には記載しないこと。
許可を申請するときは、表題中及び第1面上方の「許可有効期間更新」の文字並びに第1面上方
の「第10条第2項」の文字を抹消すること。この場合には、8欄及び9欄には記載しないこと。
許可の有効期間の更新を申請するときは、表題中及び第1面上方の「許可」の文字並びに第1面
上方の「第5条第1項」の文字を抹消すること。事業所枝番号がある場合には、7欄の(参に該当す
る事業所の事業所枝番号を記載すること。なお、10欄には記載しないこと。
第1面上方の申請者欄には、氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)を記名押印又は
署名のいずれかにより記載すること。
3欄は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条
第5項に規定する小規模企業者である場合には「2 中小企業」の数字、その他の企業者である場
合には「1 大企業」の数字をそれぞれ○で囲むこと。
4欄には、申請する目の属する月の前月の末日に雇用している全労働者数を記載すること。
5欄は、申請日時点の日本標準産業分類に基づき記載すること。なお、記載する産業分類は細分
類とすること。
許可の有効期間の更新を申請するときは、6欄の記載は要しないこと。
7欄は、申請者が労働者派遣事業を行おうとする事業所を全て記載すること。所定の欄に記載し
得ないときは、別紙に記載して添付すること。
7欄の③は、該当する文字を○で囲むこと。
なお、「有」の場合には、7欄の④に該当する派遣元責任者の「製造業務専門派遣元責任者」欄
に○印を記載すること。
11 派遣労働者の職業生活の設計に関する相談について、派遣労働者が利用する相談窓口において派
遣元責任者が対応する場合は、7欄の④の「キャリアコンサルティングの担当者」欄に○印を記載
すること。
12 派遣労働者の職業生活の設計に関する相談について、派遣労働者が利用する相談窓口において7
欄の④の派遣元責任者以外の者が対応する場合は、7欄の⑤に当該者の氏名及び職名を記載するこ
と。
13 11欄には、許可の申請又は許可の有効期間の更新の申請に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を
記載すること。
14 収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。
15 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。
16 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法
律(平成27年法律第73号)附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができることとされた
労働者派遣事業にあっては、11欄に届出受理番号及び届出受理年月日を記載すること。
-389-
様式第3号(第1面)
I 計画事業所の概要
労働者派遣事業計画書
(日本工業規格A列4)
ふりがま
1事業所の名称
2 計画対象期間 ~
3 資産等の、’況
区 分 価 額(円) 摘 要
現金・預金
土地・建物
その他
資産額(計)
負債額(計)
4 株主の、’況
氏名又は名称 所有株式数 割合(%)
1
2
3
4
5
その他の株主
合計
名)
名)
5 労働保険等の加入状況
未加入の場合の誓約
(自署によること)
雇用保険 1 有 2 無
①労働保険等の加入状況
健康保険 1 有 2 無
厚生年金保険 1 有 2 無
②労働保険番号
③雇用保険適用事業所番号
ア 当該事業所の派遣労働者数(人)
イ うち雇用保険の未加入派遣労働者数(人)
④事業所整理記号
⑤事業所番号
ア 当該事業所の派遣労働者数(人)
イ うち健康保険の未加入派遣労働者数(人)
ウ うち厚生年金保険の未加入派遣労働者数(人)
6岩墓職業紹介事業との兼業の1
有 2 同時申請・申請中 3 無 許可番号・届出番号
7請負事業との兼業の有無 1有 2 無 まき構内請負の
美施 1有 2 無
8 事業所の面積(最)
9 備考
-390-
様式第3号(第2面)
Ⅱ 労働者派遣計画
1登録制度の実施 1有 2 無
2 派遣労働者として雇用すること等が予定される1日当たり平均人数
(日本工業規格A列4)
計 うち1年以上の雇用予定の者 うち1年未満の雇用予定の者
登録者
(力派遣労働者総数計(人)
②無期雇用派遣労働者(人)
③有期雇用派遣労働者(人)
④日雇派遣労働者(人)
3 労傭拍封 遣の役務の提共を鼻ける の有 の弄 地域
4 指出命令の系統
5 ′半 ミ’音に る、 ̄の、′捗日、な’′こ金 びミ’音、汝lの’′こ金の百
①平均的な1人1目②平均的な1人1目
浣思)当たりの派窓時間)当たりの賃③その他 漂㌍保険料(事業主負鎧戸保険料(事業主負
全派遣業務平均
派遣業務内容
[=⊃
[=⊃
[=⊃
6 労働安全衛生法碑59条の規定に基づく安全衛生教士
教育の内容及び当該内容に係る労働安全
衛生法又は労働安全衛生規則の該当番号
教育の内容
教育の方法の
別
1座学
2 実技
教育の実施主
体の別
1事業主・2
派遣先・3 教
育機関・4 そ
の他
1人当たりの
平均実施時間
軸柵柵柵柵
〓〓l
7 その他の教士訓練(6及び様式碑3号-2に係るものを除く)
訓練の内容
訓練の方法の
別
10JT
2 0FF-JT
訓練の実施主
体の別
1事業主・2
派遣先・3 訓
練機関・4 そ
の他
訓練費負担の
別
1無償(実費
負担なし)・
2 無償(実費
負担あり)・
3 有償
賃金支給の別
1有給(無給
部分なし)・
2 有給(無給
部分あり)・
3 無給
1人当たりの
平均実施時間
回
回
〓
8 6及び7の教士訓練に用いる施設、設備等の概要、教士の実施責壬者の役職・氏名
9海外派遣の予定の有無 1有 2 無
-391-
(日本工業規格A列4)
様式第3号(第3面)
記載要領
I 計画事業所の概要
1 2欄には、事業所で事業開始を予定する目又は許可の有効期間の更新を予定する目及び許可の有効期間の末
日を含む事業年度の終了の目を記載すること。
2 3欄及び4欄には、企業全体の状況を記載すること。
3 3欄には、法人の場合には直近の決算時における資産等の状況について、個人の場合には納税期末日におけ
る事業に係る資産等の状況について記載すること。
4 4欄には、株式会社のみ、持株数の多い順序に従い5名記載すること。
5 5欄の①は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入の有無について該当する数字を○で囲むこと。
また、加入対象となる派遣労働者の不存在(有効期間の更新時においては加入要件を満たさない者の存在を
含む。)による未加入の場合には、加入対象となる派遣労働者の雇用等により加入義務が生じた際に必ず加入
する旨、所定欄に誓約すること。その際には自署にて記載すること。
6 5欄の③のアには、申請日の属する月の前月末目に雇用している全労働者のうち派遣労働者、イには、アの
うち法定の適用除外事由に該当する者も含めた雇用保険未加入の派遣労働者の実人数を記載すること。
7 5欄の⑤のアには、申請日の属する月の前月末目に雇用している全労働者のうち派遣労働者の実人数を記載
すること。イには、アのうち法定の適用除外事由に該当する者も含めた健康保険未加入の派遣労働者の実人数
を、ウには、アのうち法定の適用除外事由に該当する者も含めた厚生年金保険未加入の派遣労働者の実人数を
記載すること。
8 6欄は、民営職業紹介事業との兼業の状況について該当する数字を○で囲むこと。民営職業紹介事業の許可
申請書を同時に提出する場合又は許可の申請をしているが許可又は不許可の処分がされていない場合は、2を
○で囲むこと。既に民営職業紹介事業の許可を受けている場合又は届出を行っている場合は、当該許可番号・
届出番号を記載すること。
9 7欄は、請負事業の実施の有無について該当する数字を○で囲むこと。労働者派遣事業と請負の区別につい
ては、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)を参照
すること。
その際、製造業に分類される事業者であって、構内請負(発注者の事業所構内において、自社の雇用する労
働者を使用し、生産活動を請け負うことをいう。)を実施している場合は、「うち構内請負の実施」の1を○
で囲むこと。
10 事業所において、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正
する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第1項の規定により労働者派遣事業を行う場合は、9欄に、届出
受理番号及び届出受理年月日を記載すること。
Ⅱ労働者派遣計画
1 1欄は、派遣労働者の登録制度の有無について該当する数字を○で囲むこと。この場合において、「登録制
度」とは、労働者派遣をするに際し、登録されている者の中から労働者を期間を定めて雇用し労働者派遣をす
る制度をいうこと。
2 2欄について、「無期雇用派遣労働者」とは、労働者派遣法第30条の2第1項に規定する期間を定めないで雇
用される派遣労働者をいうこと。また、「有期雇用派遣労働者」とは、労働者派遣法第30条第1項に規定する期
間を定めて雇用される派遣労働者をいうこと。
3 2欄について、「日雇派遣労働者」とは、労働者派遣法第35条の4第1項に規定する日々又は30日以内の期
間を定めて雇用される派遣労働者をいうこと。なお、30日以内の期間を定めた契約を更新して通算30日を超え
るような場合も含まれるので留意すること。
-392-
(日本工業規格A列4)
様式第3号(第4面)
4 2欄の①から④までについては、計画対象期間において労働者派遣法第5条第1項の許可を受けて行ってい
る、又は行おうとする労働者派遣事業に係る派遣労働者として雇用していることが予定される1日当たり平均数
を記載すること。
この場合において、「1日当たりの平均数」とは1日当たりの派遣労働者の労働時間数の合計を当該事業所
における通常の労働者(例えば、派遣労働者の雇用管理や派遣先との連絡調整等の業務を行う者がこれに該当
する。)の1人1日当たりの労働時間数で除した数をいうこと。
5 2欄の①、③及び④の「登録者」については、計画対象期間において労働者派遣法第5条第1項の許可を受
けて行っている、又は行おうとする労働者派遣事業に係る登録者(雇用されている者を含み、過去1年を超え
る期間にわたり雇用されたことのない者を除く。)であることが予定される者の1日当たりの平均数を合計欄
に記載すること。
6 4欄は、労働者派遣事業関係業務に従事する者の指揮命令の系統及び派遣元責任者(派遣元責任者の職務代
行者を含む。)の地位を記載すること。
7 5欄には、計画対象期間において派遣労働者を従事させようとする業務の平均及び主な業務別の派遣料金、
賃金額及びその他事業者の負担する金額を記載すること。業務別の状況については、派遣労働者が従事する業
務に該当する日本標準職業分類の分類番号(中分類とすること。)及び具体的な業務内容を記載すること。
8 5欄の①から⑤までには、計画対象期間における労働者派遣に関する平均的な1人1日(8時間として算定
すること。以下この8において同じ。)当たりの労働者派遣に関する料金の額、平均的な1人1日当たりの派
遣労働者の賃金の額及び当該労働者派遣に関して事業主が負担するその他の総額(1人1日当たりの額として
算定した額)、このうち労働保険料及び社会保険料の事業主負担分の額(1人1日当たりの保険料の額として
算定した額)をそれぞれ記載すること。
9 6欄には「労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育」について、7欄には一般教養的な訓練等の
「その他の教育訓練」(6欄及びキャリアアップ措置に係るものを除く)について、それぞれ主な教育訓練計
画を記載すること。
10 6欄及び7欄については教育訓練コース単位で記載すること。6欄については5コースを、7欄については
3コースを本欄に記載すること。
11 6欄について、実施内容が労働安全衛生法第59条第1項の規定に該当する場合は、その内容に合致する労働
安全衛生規則第35条第1項各号のうち該当号数に応じた1~8までの数字を、労働安全衛生法第59条第2項の
規定に該当する場合は9を、同条第3項に該当する場合は10を、その教育の主な内容に応じて最大2つまで記
載すること。
12 6欄の「教育の内容」及び7欄の「訓練の内容」については、「4S(整理・整頓・清掃・清潔)運動」、
「KY(危険予知)活動」、「ヒヤリハット事例の報告」等具体的に記載すること。
13 7欄の訓練の方法のうち、「OJT」とは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を、「OFF-JT」とはそれ以
外の教育訓練をいうこと。
14 労働安全衛生法第59条に基づく安全衛生教育については、事業主の義務として業務時間中に行うものである
ことから、「無償」かつ「有給」で行うべきものであることに留意すること。
15 7欄の「訓練費負担の別」について、「1無償(実費負担なし)」はテキスト代等を含め訓練の全てを無償
で実施すること、「2 無償(実費負担あり)」はテキスト代等の実費負担があるものの原則として無償で実施
すること、「3 有償」はこれら以外をいうこと。
16 7欄の「賃金支給の別」について、「1有給(無給部分なし)」は全ての訓練を受けることに対して給与を
支払うこと、「2 有給(無給部分あり)」は自主的に実施する訓練については無給とする場合があるものの原
則として訓練を受けることに対して給与を支払うこと、「3 無給」は訓練を受けることに対して給与を支払わ
ないことをいうこと。
17 6欄及び7欄の「1人当たりの平均実施時間」については、対象労働者に対して実施予定の平均的な教育訓
練時間を記載すること。
18 8欄の「教育の実施責任者」は、安全衛生教育の実施に関し責任を有する者の地位及び氏名を記載するこ
と。
19 9欄は、海外派遣の予定の有無について、該当する数字を○で囲むこと。
20 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。
-393-
(日本工業規格A列4)
キャリア形成支援制度に関する計画書
様式第3号-2(第1面)
1キャリアコンサルティングの担当者の人数
臣型
計 うち社内の者 うち社外の者
l l
キャリアコンサルタントI l
上記以外の担当者 I l
営業職 I l
その他 I l
計
l l
l -1
[=三:⊃
[=]
[=三⊃
キャリアコンサルティングに関する具体的
な職務経験又はその有する知見
(具体的に記載すること)
2 キャリアコンサルティング窓口
窓口の開設方法 キャリアコンサルティングを行う場所
1事務所内に設置・2 電話での相談窓
口の設置・3 e-mailでの専用窓口の設
置・4 専用WEBサイトの設置・5その他
1社内(本社、支社等を含む)の特定の場
所・2 社内の不特定の場所・3 派遣先の特
定の場所・4 派遣先の不特定の場所・5 社
外・6 その他
備考
□
4 キャリアアップに資する教育訓練
3
キャリアコンサルティングに関するマ
ニュアル等の有無
1 有 2 無
キャリアアップ措置の種別(1
人職時等基礎的訓練、2 職能
別訓練、3 職種転換訓練、4
階層別訓練、5 その他の教育
訓練)
具体的な教育訓練
対象となる派遣労働者の種別(1雇入時・
2 派遣中・3 待機中・4 入社〇年目(階
層別訓練の場合のみ選択のこと)・5 その
他)
1人当たり年間平均実施時間
訓練費負担の
訓練の方法の別
別
10JT
具体的な対象労働者l人月1年可2年可3年中骨20FF ̄JT
1無償(実費
負担なし)・
2 無償(実費
負担あり)・
3 有償
賃金支給の別
1有給(無給
部分なし)・
2 有給(無給
部分あり)・
3 無給
[==⊃
[==⊃
[==⊃
[==⊃
[==⊃
[==⊃
[==コ
ll
コロロロロロロコ
〓 〓二 〓・
ココココココココ
曇会喜三三三欝誓蛋霊鵠雷幣繋詔畏品呈し芦讐J夏雲日日日日
「キャリアアップに資する教育訓練」実施にあたって支払う賃金額(1人1時間当たり平均)
備考
※ 1人当たりの平均実施予定時間が、年間概ね8時間に満たない場合、備考欄にその具体的理由を記載すること
5 上記教育訓練が、キャリアアップに資すると考える理由
[車]
無期雇用派遣労働者への中長期
6聖霊詣遥譜を考慮に入れ 1有 2無
7 上記6の実施にあたってどのようなことを考慮しているのかを具体的に記載すること
8 派遣労働者のキャリアアップ措置に係る教士訓練に用いる施設、設備等の概要
※ 様式第3号の8欄と異なる場合のみ記載すること
教育訓練等の情報を管理した資料の保存期間が労働契約終
9了後3年間以上あること 1有 2 無
10備考
※労働局記載欄
-394-
(日本工業規格A列4)
様式第3号-2(第2面)
記載要領
1 1欄の「キャリアコンサルタント」については、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定する者が行う試験の合格者
の実人数を記載すること。それ以外の者であってキャリアコンサルティングに関する知見を有する者(実務に従事し
ていた者や類似した民間資格を有する者等)については、「上記以外の担当者」の「その他」にその実人数を記載す
ること。
2 1欄の派遣元責任者との兼任状況は「キャリアコンサルティングの担当者」の計の内数を記載すること。
3 1欄のキャリアコンサルティングに関する具体的な職務経験又はその有する知見に関しては、当該キャリアコンサ
ルティングを担当する者が、どのような知見や職務経験を有しているのかについて、「職業能力開発推進者3年
目」、「4年間の人事経験あり」等具体的に記載すること。
なお、キャリアコンサルティングの担当者が複数いる場合については、主な者についてのみ記載すること。
4 2欄について、キャリアコンサルティング窓口の「開設方法」、「キャリアコンサルティングを行う場所」に関し
て該当する番号を全て記載すること。また、「その他」を選択した場合は、その内容を備考欄に記載すること。な
お、窓口未開設の場合は、開設予定の窓口に係る情報を記載すること。
5 3欄について、1を○で囲んだ場合には、キャリアコンサルティングに係るマニュアル又はマニュアルの概要を参
考資料として添付すること。
6 4欄には、計画対象期間において実施する予定の主なキャリアアップに資する教育訓練について、訓練コース単位
で8コースまでを本欄に記載すること。それ以上のコースがある場合は、別紙に記載すること。
7 4欄の「キャリアアップ措置の種別」については、キャリアアップ措置に関する教育訓練の主たる目的に応じて、
該当する番号を記載すること。
8 4欄の「具体的な教育訓練」については、「係長・課長就任研修」、「○○語研修」等実施を計画している訓練が
特定できるよう具体的に記載すること。
9 4欄の「対象となる派遣労働者の種別」には、該当する番号を記載するとともに、「具体的な対象労働者」欄に
「初めて派遣する労働者」、「待機中の者」等、具体的に記載すること。なお、「待機中の者」とは、労働契約は締
結している者であって、派遣先が決まっていない又は派遣先は決まっているが派遣先での就業開始日が到来していな
い者をいい、登録中の者(労働契約を締結していない者)は、キャリアアップに資する教育訓練の対象となる派遣労
働者に含まれないことに留意すること。
10 4欄の「人数」には、キャリアアップに資する教育訓練を実施する予定の全ての派遣労働者数を記載すること。
11 4欄の「1人当たり年間平均実施時間」については、対象となる派遣労働者に対して実施する予定の教育訓練の時
間を記載すること。対象となる派遣労働者に対して、ある訓練を1年目、2年目とそれぞれ段階ごとに行う場合は、
1つの同じコースの中で、それぞれの年数の欄に記載すること。また、同一の派遣労働者に行う同一の訓練であって
も、2年目以降は1年目とは異なるコースに位置づける訓練等の場合は、2つ以上の異なるコースとして、それぞれ
の年数に応じた欄に記載すること。
なお、4年目以降に具体的にどのような教育訓練を実施するかについては、事業主の任意であり、キャリア形成支
援制度があることを明示するため、「4年目以降」欄に「有」と記載しても差し支えないこと。
12 4欄の「OJT」とは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を、「OFF-JT」とはそれ以外の教育訓練をいうこと。
キャリアアップに資する教育訓練としてOJTを実施するに当たっては、派遣先と事前に調整等を行った上で計画的な
OJTを実施しなければならないことに留意すること。
13 4欄の「訓練費負担の別」において、「1無償(実費負担なし)」とは、テキスト代等を含め訓練の全てを無償で
実施することを、「2 無償(実費負担あり)」とは、テキスト代や材料費等の実費負担があるが原則として無償で実
施することを、「3 有償」とは、これ以外をいうこと。
14 4欄の「賃金支給の別」において、「1有給(無給部分なし)」とは、用意した全ての教育訓練の実施に当たって
給与を支払う場合を、「2 有給(無給部分あり)」とは、自主的に実施する教育訓練については無給とする場合があ
るが原則として教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合を、「3 無給」とは、教育訓練の実施時に給与を支払わ
ない場合をいうこと。
15 4欄のキャリアアップに資する教育訓練については、「訓練費負担の別」が「1無償(実費負担なし)」であっ
て、「賃金支給の別」が「1有給(無給部分なし)」であることが派遣元事業主の許可要件であることに留意するこ
と。そのうち、フルタイム勤務の者であって1年以上の雇用見込みのあるものを対象とした訓練については、4欄の
「1人当たり年間平均実施時間」が、年間概ね8時間以上であることが求められることに留意すること。
16 4欄の「「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払う賃金額(1人1時間当たり平均)」欄につい
ては、キャリアアップに資する教育訓練時における賃金の平均額を記載すること。
17 5欄には、実施する教育訓練がキャリアアップに資すると考える理由について具体的に記載すること。
18 無期雇用派遣労働者を雇用する事業主においては、4欄に記載した教育訓練に、「無期雇用派遣労働者への中長期
的なキャリア形成を考慮に入れた訓練」がある場合、6欄の1を○で囲むこと。
19 7欄には、無期雇用派遣労働者への中長期的なキャリア形成を考慮に入れた訓練について、どのようなことを考慮
しているのか具体的に記載すること。
20 9欄には、教育訓練等の情報を管理した資料を、各派遣労働者の労働契約が終了した後3年以上保存する場合には
1を○で囲むこと。
21 労働局記載欄には何も記載しないこと。
22 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。
-395-
(日本工業規格A列4)
年 月 日
雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書
様式第3号-3
雇用保険等の被保険者資格取得の状況について、下記の通り報告します。
(ふりがな)
1事業所の名称
【雇用保険】
2 適用事業所番号 3 派遣労働者のうち、未加入者数(人) 人
4 未加入者の氏名及び未加入の理由
氏 名 佃
未加入の具体的な理由(⑤その他を選択した場合に記載すること)
l l
[==⊃
[==⊃
l l
l l
l l
l l
[==⊃
雇用保険の未加入の理由
(力65歳に達した目以後に雇用される者
(塾1週間の所定労働時間が20時間未満である者
③同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
④昼間学生(労働者派遣法施行令第4条第2項第2号に掲げる者をいう。)
⑤その他(その他を選択した場合は、必ず具体的な理由を記載すること。)
【健康保険・厚生年金保険】
l51芸芸票霊芸記号 I l6l派遣労鷺請、末当笠封 会
7 未加入者の氏名及び未加入の理由
氏 名l種類l佃
未加入の具体的な理由(⑤その他を選択した場合に記載すること)
「健康Il l
l厚生Il l
「健康Il l
l厚生Il l
「健康Il l
l厚生Il l
「健康Il l
l厚生Il l
「健康Il l
l厚生Il l
健、保払・厚生年金保仏の未加入の理由
①1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3未満である者
②1週間の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3未満である者
③1か月の勤務目数が、一般社員の所定労働目数の概ね4分の3未満である者
④ 2か月以内の期間を定めて使用される者
⑤その他(その他を選択した場合は、必ず具体的な理由を記載すること。)
(記載要領)
1 本様式は、派遣労働者のうち、雇用保険等の未加入者がいる場合に提出を要すること。
2 雇用保険等の資格取得状況について、許可又は更新の申請日における状況を本様式に記載すること。
3 1欄は、該当事業所の名称を記載すること。
4 2欄、3欄、5欄及び6欄には、様式第3号5欄において労働保険等の加入状況を記載したものを記載すること。
5 4欄及び7欄には、未加入の理由をそれぞれ①から⑤のうちから選択すること。なお、⑤その他を選択した場合
は、未加入の具体的な理由を必ず記載すること。
6 7欄について、健康保険・厚生年金保険の種類それぞれの状況を記載すること。
7 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。
-396-
様式第4号 (日本工業規格A列4)
許可番号
許可年月日
年
労働者派遣事業許可証
月 日
氏名又は名称
住所
事業所の名称
事業所の所在地
有効期間
年 月
年 月
日から
目まで
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1
項の許可を受けて労働者派遣事業を行う者であることを証明する。
年 月 日
厚 生 労 働 大 臣
事業所枝番号
- 397 -
様式第5号(第1面)
(日本工業規格A列4)
※ 芸交芸年月日 年 月 日
許 可 証 再 交 付 申 請 書
労 働 者 派 遣 事 業 変 更 届 出 書
労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書
厚 生 労 働 大 臣 殿
1
2
3
4
申請者
届出者
年 月 日
[コ
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第8条第3項の規定により下記のとおり
許可証の再交付を申請します。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第11条第1項の規定により下記のとおり
届け出ます。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第11条第4項の規定により下記のとおり
許可証の書換えを申請します。
届出者(法人にあっては役員を含む。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
法律第6条各号(個人にあっては第1号から第9号まで、第11号及び第12号)のいずれにも該当しないことを誓約し
ます。
5 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第36条の規定により選任する派遣元責任
者については、未成年者でないこと、同法第6条第1号から第8号までのいずれにも該当しないこと及び労働者派遣
事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第29条の2に規定する基準に適合することを
誓約します。
1許可番号 2許可年月日 年 月 日
3
(ふりがな)
氏名又は名称
〒(
)
4 住所
( )
(ふりがな)
5 代表者の氏名
(法人の場合)
6
(ふりがな)
事業所の名称
〒(
7 事業所の所在地
)
( )
※
収入印紙
(消印しては
ならない。)
- 398 -
様式第5号(第2面)
(日本工業規格A列4)
8 変更の 内容
変 更 後 変 更 前 変更年月日
①
(ふりがな)
氏名又は名称
年 月 日
〒( )
②住 所
〒( )
l l ll l
年 月 日
(ふりがな)
③代表者の氏名
(法人の場合)
年月日
④票員の氏名及び住骨‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥-1骨
(法人の場合)
[∃
[∃
年 月 日
⑤
(ふりがな)
事業所の名称
年 月 日
〒(
⑥事業所の所在地
)
〒(
l l ll l
)
年月日
⑦賃孟警悪霊務への 開始年月日
年 月 日 終了年月日 年 月 日
.t .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
⑧砦讐譜等者の氏
囲Sl
臣司[コ
.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
囲Sl
臣司[⊃
[∃
[∃
l備考I l備考l
年 月 日
⑨労働者派遣事業を行う事業所の新設
イ事業開始年月日 年 月 日
[コ
(ふりがな)
事業所の名称
〒(
ハ事業所の所在地
)
( )
ニ特定製造業務への労働者派遣の実施の有無 1 有 2 無
- 399 -
様式第5号(第3面)
(日本工業規格A列4)
ホ 派遣元責任者の氏名、職名、住所等
.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-
日 日日
日 日日
= 日日
へ キャリアコンサルティングの担当者の氏名及び職名(ホと同じ者の場合は記載を要しない)
(憲一誓工一十‥‥……1回
因
※
⑩労働者派遣事業を行う事業所の廃止
イ
(ふりがな)
事業所の名称
〒(
ロ事業所の所在地
)
( )
ハ廃止年月日 年 月 日
ー事業所の廃止理
 ̄由
※
9 再交付を申請する理由
※
10 備 考
- 400 -
(日本工業規格A列4)
様式第5号(第4面)
記載要領
1各申請書及び届出書共通事項
(1)※印欄には、記載しないこと。
(2)第1面上方の 憲悪書 欄には、氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)を記名押印又
は署名のいずれかにより記載すること。
(3) 3欄から7欄までには8欄の「変更前」の事項と同一の事項を記載すること。
2許可証の再交付を申請するときの記載方法
(1) 表題「労働者派遣事業変更届出書」及び「労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」並びに
第1面上方の2から5までの全文並びに「届出者」の文字を抹消すること。
(2) 8欄には記載しないこと。
(3) 9欄には、再交付の申請に至った理由を具体的に記載すること。
(4) 収入印紙を申請書の正本にのみ貼り、消印はしないこと。
3労働者派遣事業において、8欄の③、④、⑦又は⑧の事項に係る変更の届出をしようとする場合の記載方法
(1) 表題「許可証再交付申請書」及び「労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」並びに第1面
上方の1及び3の全文並びに「申請者」の文字を抹消すること。また、8欄の③又は④の氏名に係る変
更の届出をしようとする場合を除き、第1面上方の4の全文を、8欄の⑧の氏名に係る変更の届出をし
ようとする場合を除き、第1面上方の5の全文を抹消すること。
(2) 8欄の③又は④に係る変更の届出をしようとする場合には、6欄及び7欄には記載しないこと。
(3) 8欄には、変更に係る事項のみを記載すること。
(4) 9欄には記載しないこと。
(5) 特定製造業務への労働者派遣を実施し、又は実施を予定している場合において、変更後の派遣元責任
者を同時に製造業務専門派遣元責任者として選任する場合には、8欄の⑧の「製造業務専門」欄に○印
を記載すること。
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以
下「労働者派遣法」という。)第30条の2第2項に定める派遣労働者の職業生活の設計に関する相談に
ついて、変更後の派遣元責任者を派遣労働者が利用する相談窓口において対応する者として選任する場
合には、8欄の⑧の「キャリア担当者」欄に○印を記載すること。
(7) 収入印紙を貼る必要はないこと。
4労働者派遣事業において、8欄の①、②、⑤又は⑥の事項に係る変更の届出及び許可証の書換えの申請をしよ
うとする場合の記載方法
(1) 表題「許可証再交付申請書」及び「労働者派遣事業変更届出書」並びに第1面上方1、4及び5の全
文並びに「届出者」の文字を抹消すること。
(2) 8欄の①又は②に係る変更の届出をしようとする場合には、6欄及び7欄には記載しないこと。
(3) 8欄には、変更に係る事項のみを記載すること。
(4) 9欄には記載しないこと。
(5) 収入印紙を申請書の正本にのみ貼り、消印はしないこと。
5労働者派遣事業において、8欄の⑨の事項に係る変更の届出をしようとする場合の記載方法
(1) 表題「許可証再交付申請書」及び「労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」並びに第1面
上方1、3及び4の全文並びに「申請者」の文字を抹消すること。
(2) 8欄の⑨ニは、該当する数字を○で囲むこと。なお、「1 有」の場合には、製造業務専門派遣元責
任者として選任する者について、8欄の⑨ホ「製造業務専門」欄に○印を記載すること。
(3) 労働者派遣法第30条の2第2項に定める派遣労働者の職業生活の設計に関する相談について、派遣元
責任者を派遣労働者が利用する相談窓口において対応する者として選任する場合には、8欄の⑨ホの
「キャリア担当者」欄に○印を記載すること。
(4) 労働者派遣法第30条の2第2項に定める派遣労働者の職業生活の設計に関する相談について、8欄の
⑨ホの派遣元責任者以外の者を派遣労働者が利用する相談窓口において対応する者として選任する場合
には、へに必要事項を記載すること。
(5) 6欄、7欄及び9欄には記載しないこと。
(6) 収入印紙を貼る必要はないこと。
(7)10欄に、労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。
6労働者派遣事業において、8欄の⑲の事項に係る変更の届出をしようとする場合の記載方法
(1) 表題「許可証再交付申請書」及び「労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」並びに第1面
上方1、3、4及び5の全文並びに「申請者」の文字を抹消すること。
(2) 6欄、7欄及び9欄には記載しないこと。
(3) 8欄の⑲ニには、事業所を廃止した理由を具体的に記載すること。
(4) 収入印紙を貼る必要はないこと。
7労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20
号)第8条第2項ただし書きの規定により添付書類を省略する場合は、10欄にその旨を記載すること。
8労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第8条第4項の規定により
添付書類を省略する場合は、10欄にその旨及び変更後の派遣元責任者が当該変更前に派遣元責任者として選任
されていた事業所の名称を記載すること。
9所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。
-401-
様式第8号
厚 生 労 働 大 臣 殿
労働者派遣事業廃止届出書
届出者
(日本工業規格A列4)
年 月 日
=
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第13条第1項の規定により下記
のとおり届け出ます。
1許可番号 2許可年月 日 年 月 日
(ふりがな)
3氏名又は名称
(ふりがな)
4代表者の氏名(法人の場合)
5事業所の名 称(ふりがな) 6事業所の所在地
〒(
)
事業所枝番号
( )
〒(
)
事業所枝番号
( )
〒(
)
事業所枝番号
( )
〒(
)
事業所枝番号
( )
7廃止年月 日 年 月 日
備 考
記載要領
1 届出者欄には、氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)を記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。
2 5欄及び6欄には、事業を廃止した全ての事業所の名称及び所在地を記載すること。
3 備考欄には、事業を廃止した理由を具体的に記載すること。
4 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第
73号)附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができるとされた労働者派遣事業に係る廃止の場合、備考欄に当
該事業に係る届出受理番号及び届出受理年月日を記載すること。
-402-
様式第11号(第1面)
厚 生 労 働 大 臣 殿
労働者派遣事業報告書
(日本工業規格A列4)
許可番号
事業所枝番号
許可年月日 年 月 日
(年度報告)
(6月1日現在の状況報告)
年 月 日
提出者
=
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第1項の規定により、下記のとお
り事業報告書を提出します。
(ふりがな)
1氏名又は名称
〒(
)
( )
2 住 所
(ふりがな)
3 代表者の氏名
(法人の場合)
佼
(ふりがな)
4 事業所の名称
〒(
)
( )
5 事業所の住所
6 大企業、中小企業の別 1 大企業 2 中小企業
7産業分類l名中 牌
8芸葦簑葦完讐語写昆雷び当 ~
9民営職業紹介事業との兼業 1有 2 無 許可・届出番号
10親会社の名称 備考
①労働者派遣事業の許可番号 ②民営職業紹介事業の許可・届出番号
11請負事業の実施 1有 2 無 うち構内請負の実施 1有 2 無
12労働者派遣事業の売上高 13請負事業の売上高
因
※労働局記入欄
-403-
様式第11号(第2面)
I 年度報告
(1)派遣労働者数等雇用実績(実人数)(報告対象期間末日現在)
計票等票空票之謂責聖霊票等票諾牝謂責聖霊
派遣労働者 遣見込みの者 派遣労働者 遣見込みの者
(力全労働者
(塾派遣労働者総計
③無期雇用派遣労働者
④有期雇用派遣労働者
⑤日雇派遣労働者
⑥登録者 ※
※登録制度のある事業主のみ
(②労働者派遣契約の期間別件数(延べ件数)
(2)海外派遣労働者数(実人数)
(日本工業規格A列4)
(3)派遣先に関する事項
(力派遣先事業所数(実数)
総件数1日以下のもの措霊雷孟7日孟豊若君1月措霊雷孟2月孟苦霊若君3月孟苦霊雷孟6月㍊票霊2去筈霊若君3年孟年を超えるも労働者票警約がな
(4)教育訓練(キャリアアップに資するものを除く)の実績
(重労働安全衛生法碑59条の規定に基づく安全衛生教士
教育の内容及び当該内容に係る労
働安全衛生法又は労働安全衛生規教育の方法の
則の該当番号
教育の内容
別
1座学
2 実技
教育の実施主
体の別
1事業主・
2 派遣先・
3 教育機
関・4 その
他
受講した派遣1人当たりの
労働者数 平均実施時間
[〓]
馴
日
日
目口□
目口□
(塾その他の教士訓練((力及び(9)に係るものを除く)
訓練の方法の 訓練の実施主
別 体の別
訓練の内容
主先機 他
業遣練 の
事派訓.そ
123関4
T
T TJ
OJ・FF
O
1
2
訓練費負担の
別
1無償(実
費負担な
し)・2 無
償(実費負担
あり)・3
有償
賃金支給の別
1有給(無
給部分な
し)・2 有
給(無給部分
あり)・3
無給
1人当たりの
平均実施時間
=
日
日
(6)雇用安定措置(法碑30条)の実績
③主な派遣先事業主(取引額上位5社)
氏名又は名称 所在地
(5)紹介予定派遣に関する事項
イ紹介予定口紹介予定ハ紹介予定二紹介予定派遣
軍糖瑚積層貰
(人) (人) 数(人)(人)
期間
対象派遣労働
者数
第1号の措置
(派遣先へ
の直接雇用の
依頼)を講じ
た人数
第2号の措置
(新たな派遣
第3号の措置
(派遣元で派遣
労働者以外の労
うち、派遣先先の提供)を うち、新たな働者として無期
第4号の措置(その他の措置)
を講じた人数
教育訓練(雇
で雇用された講じた人数 派遣先で就業票芸)を講じた監禁慧淵慌詳派遣左記以外のそ
人数 した人数 の他の措置
限る)
第1号から第4
号までのいずれ
の措置も講じな
かった人数
備考
計
3年見込み
2年半から3年未満見込み
2年から2年半未満見込み
1年半から2年未満見込み
1年から1年半未満見込み
1年未満見込み(※1)
※1「1年未満見込み」については、派遣元での通算雇用期間が1年以上の者(登録中の者を含む)に限る。
※2(5)欄の「イ 紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込人数(人)」の内数であること。
-404-
(日本工業規格A列4)
様式第11号(第3面)
(7)派遣料金及び派遣労働者の賃金(1日(8時間当たり)の額)に関する事項
(力 業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金(日雇派遣労働者を除く)
派遣料金(1日(8時間当たり)の額) 派遣労働者の賃金(1日(8時間当たり)の額)
派遣労働者平均
無期雇用 有期雇用
派遣労働者 派遣労働者
派遣労働者平均
無期雇用
派遣労働者
協定対象
派遣労働者
有期雇用
派遣労働者
協定対象
派遣労働者
全業務平均
01~99の合計額/記載業務の合計数
01管理的公務員
02 法人・団体役員
03 法人・団体管理職員
04 その他の管理的職業従事者
05 研究者
06農林水産技術者
3書製造技術者
09 建築・土木・測量技術者
10 情報処理・通信技術者
11その他の技術者
12宗軋歯科医軋獣医軋薬剤
13保健師,助産師,看護師
14 医療技術者
15 その他の保健医療従事者
16社会福祉専門職業従事者
17法務従事者
18誓営‘金融‘保険専門職業従事
19 教員
20 宗教家
21著述家,記者,編集者
22悪霊孟料妄ザイナ一,写真象
23 音楽家,舞台芸術家
24 その他の専門的職業従事者
25 一般事務従事者
26 会計事務従事者
27 生産関連事務従事者
28 営業・販売事務従事者
29 外勤事務従事者
30運輸・郵便事務従事者
31事務用機器操作員
32 商品販売従事者
33販売類似職業従事者
34営業職業従事者
35書庭生活支援サービス職業従事
36介護サービス職業従事者
37 保健医療サービス職業従事者
-405-
(日本工業規格A列4)
様式第11号(第4面)
① 業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金(日雇派遣労働者を除く)(続)
派遣料金(1日(8時間当たり)の額) 派遣労働者の賃金(1日(8時間当たり)の額)
派遣労働者平均
無期雇用 有期雇用
派遣労働者 派遣労働者
派遣労働者平均
無期雇用
派遣労働者
協定対象
派遣労働者
有期雇用
派遣労働者
協定対象
派遣労働者
38 生活衛生サービス職業従事者
39飲食物調理従事者
40接客・給仕職業従事者
41居住施設・ビル等管理人
42 その他のサービス職業従事者
43 ~45
自衛官・司法警察職員等
46農業従事者
47 林業従事者
48漁業従事者
霊生産設備制御・監視従事者
51機械組立設備制御・監視従事者
崇製品製造・加工処理従事者
54機械組立従事者
55機械整備・修理従事者
昌冒製品検査従事者
58機械検査従事者
59 生産関連・生産類似作業従事者
60 鉄道運転従事者
61自動車運転従事者
62 船舶・航空機運転従事者
63 その他の輸送従事者
64 定置・建設機械運転従事者
65 建設躯体工事従事者
66慧芸警芦者(建設躯体工事従事者
67 電気工事従事者
68 土木作業従事者
69 採掘従事者
70 運搬従事者
71清掃従事者
72包装従事者
99 分類不能の職業
-406-
(日本工業規格A列4)
様式第11号(第5面)
(塾 日雇派遣労働者の業務別派遣料金及び賃金
日雇派遣労働者の派遣料金
(1日(8時間当たり)の額)
日雇派遣労働者の賃金
(1日(8時間当たり)の額)
日雇派遣労働者 協定対象派遣労働者
全業務平均
4-1~4-18の合計額/記載業務の合計数
4-1 情報処理システム開発
4-2 機械設計
4-3 事務用機器操作
4-4 通訳、翻訳、速記
4-5 秘書
4-6 ファイリング
4-7 調査
4-8 財務
4-9 貿易
4-10 デモンストレーション
4-11添乗
4-12 受付・案内
4-13 研究開発
4-14 事業の実施体制の企画、立案
4-15 書籍等の制作・編集
4-16 広告デザイン
4-17 0Aインストラクション
4-18 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
(8)マージン率等の情報提供の状況
提供方法 該当する各欄に「O」を記載
インターネット
書類の備付け
その他( )
-407-
(日本工業規格A列4)
様式第11号(第6面)
(9)キャリアアップ措置の実績
(カ キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数
計 うち社内の者 うち社外の者 う雷票悪霊記者
キャリアコンサルティングに
関する職務経験・知見のある者
職務経験あり 知見あり
計 =
キャリアコンサルタント
[=⊃
上記以外の担当者
[=⊃
恒業職l=
区の他l=
② キャリアコンサルティングの実施状況
全派遣労働者数
実施を希望した者の人数 実施した者の人数
計
日日日日日日日日
③ キャリアアップに資する教育訓練(1フルタイム(1年以上雇用見込み)、2 短時間勤務(1年以上雇用見込み)、31年未満雇用見込み)
訓練の内容等
対象となる派遣労働者
(上段)種別
(1雇入時・2派遣中・3待機中・4入社
〇年目・5長期的なキャリア形成を念頭に
置いた内容の教育訓練の対象となる無期雇
用派遣労働者・6その他)
(下段)対象となる派遣労働者数
(上段)実施時間の総計
(受講者数×教育訓練1コマの時間(複数
回実施の場合はその合計))
(下段)受講者の実人数
(各年に同一の訓練を複数回受講した者
は、重複計上しないこと)
ll年月2年可3年可相41年月2年可3年目相可
訓練の方法の別
1計画的なOJT
2 0FF-JT
3 0JT
(計画的なもの以
外)
訓練の実施主体の別 訓練費負担の別
1事業主
2 派遣先
3 訓練機関
4 その他
1無償
(実費負担なし)
2 無償
(実費負担あり)
3 有償
賃金支給の別
1有給
(無給部分なし)
2 有給
(無給部分あり)
3 無給
イ
入職時等基礎的訓練
」」⊥
章章章章 厄日
[凹[凹
ロ
職能別訓練
」」⊥
」」⊥
[凹[凹
ノヽ
職種転換訓練
」」⊥
」」⊥
[凹[凹
階層別訓練
」」⊥
lll F=
[凹[凹
ホ その他の教育訓練
日
」」⊥
目
」」⊥
篭計器賢臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間日日日日1~3年目のaの合計(C)
票㌫㌫厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実日日日日1~3年目のbの合計(d)
琵芸羞雷畜票㌫る基準を満たす教育訓練について1人当たりの平日=日日漂冒豊雷讐歪昌雲孟宗晶誓警)
たす教育訓練
「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額(1人1時間当たり平均)
-408-
(日本工業規格A列4)
様式第11号(第7面)
Ⅱ 6月1日現在の状況報告
1 派遣労働者の実人数
(力 派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数
うち、通算雇用期間が1年以上の派遣労働者 うち、通算雇用期間が1年未満の派遣労働者
派遣労働者計
無期雇用派遣労働者
協定対象
派遣労働者
有期雇用派遣労働者
協定対象
派遣労働者
無期雇用派遣労働者
協定対象
派遣労働者
有期雇用派遣労働者
協定対象
派遣労働者
(塾 業務別派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数((力の内数)
計
無期雇用派遣労働者
協定対象
派遣労働者
有期雇用派遣労働者
協定対象
派遣労働者
01管理的公務員
02法人・団体役員
03法人・団体管理職員
04その他の管理的職業従事者
05研究者
06農林水産技術者
07・08製造技術者
09建築・土木・測量技術者
10情報処理・通信技術者
11その他の技術者
12医師,歯科医師,獣医師,薬剤師
13保健師,助産師,看護師
14医療技術者
15その他の保健医療従事者
16社会福祉専門職業従事者
17法務従事者
18経営・金融・保険専門職業従事者
19教員
20宗教家
21著述家,記者,編集者
22美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者
23音楽家,舞台芸術家
24その他の専門的職業従事者
25一般事務従事者
26会計事務従事者
27生産関連事務従事者
28営業・販売事務従事者
29外勤事務従事者
30運輸・郵便事務従事者
31事務用機器操作員
32商品販売従事者
33販売類似職業従事者
34営業職業従事者
35家庭生活支援サービス職業従事者
36介護サービス職業従事者
37保健医療サービス職業従事者
-409-
(日本工業規格A列4)
様式第11号(第8面)
② 業務別派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数(続)
計
無期雇用派遣労働者
協定対象
派遣労働者
有期雇用派遣労働者
協定対象
派遣労働者
38生活衛生サービス職業従事者
39飲食物調理従事者
40接客・給仕職業従事者
41居住施設・ビル等管理人
42その他のサービス職業従事者
43~45 自衛官・司法警察職員等
46農業従事者
47林業従事者
48漁業従事者
49・50生産設備制御・監視従事者
51機械組立設備制御・監視従事者
52・53製品製造・加工処理従事者
54機械組立従事者
55機械整備・修理従事者
56・57製品検査従事者
58機械検査従事者
59生産関連・生産類似作業従事者
60鉄道運転従事者
61自動車運転従事者
62船舶・航空機運転従事者
63その他の輸送従事者
64定置・建設機械運転従事者
65建設躯体工事従事者
66建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)
67電気工事従事者
68土木作業従事者
69採掘従事者
70運搬従事者
71清掃従事者
72包装従事者
99分類不能の職業
③ 特定製造業務従事者の実人数(①の内数)
特定製造業従事者 計
無期雇用派遣労働者
協定対象
派遣労働者
有期雇用派遣労働者
協定対象
派遣労働者
④ 期間制限の対象外となる労働者派遣に係る派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数((力の内数)
計 無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者
法第40条の2第1項第2号(高齢者)
法第40条の2第1項第3号イ(有期プロジェクト業務)
法第40条の2第1項第3号ロ(目数限定業務)
法第40条の2第1項第4号(育児休業等取得者の代替)
法第40条の2第1項第5号(介護休業取得者の代替)
-410-
(日本工業規格A列4)
様式第11号(第9面)
⑤ 日雇派遣労働者の実人数
日雇派遣労働者 計
i~kに該当しない者
協定対象
派遣労働者
i 高齢者
協定対象
派遣労働者
正 昼間学生 嵐 副業として従事する者 k 主たる生計者でない者
協定対象 協定対象 協定対象
派遣労働者 派遣労働者 派遣労働者
⑥ 特定製造業務従事者である日雇派遣労働者の実人数(⑤i~料の合計)
⑦ 日雇派遣労働者の業務別実人数(⑤の内数)
日雇派遣労働者
協定対象
派遣労働者
日雇派遣労働者
協定対象
派遣労働者
4-1情報処理システム開発
4-2機械設計
4-3事務用機器操作
4-4通訳、翻訳、速記
4-5秘書
4-6ファイリング
4-7調査
4-8財務
4-9貿易
4-10デモンストレーション
4-11添乗
4-12受付・案内
4-13研究開発
4-14事業の実施体制の企画、立案
4-15書籍等の制作・編集
4-16広告デザイン
4-170Aインストラクション
4-18セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
(砂 日雇派遣労働者のうち期間制限の対象外となる業務における派遣労働者の実人数(⑤の内数)
法第40条の2第1項第3号イ(有期プロジェクト業務)
法第40条の2第1項第3号ロ(目数限定業務)
法第40条の2第1項第4号(育児休業等取得者の代替業務)
法第40条の2第1項第5号(介護休業取得者の代替業務)
2 過去1年以内に労働者派遣されたことのある登録者(雇用されている者を含む。)の数
3 雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況
雇用見込みが1年以上の労働者 雇用見込みが1年末満の労働者
無期雇用 有期雇用 無期雇用 有期雇用
派遣労働者 派遣労働者 派遣労働者 派遣労働者
雇用保険
健康保険
厚生年金保険
-411-
(日本工業規格A列4)
様式第11号(第10面)
記載要領
第1面
1 「許可番号」及び「許可年月日」欄には、許可番号等を記入すること。
なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法
律第73号。以下「平成27年改正法」という。)附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができることとされた労
働者派遣事業(以下「旧特定労働者派遣事業」という。)に係る事業所においては、本欄には何も記載せず、14欄に届出
年月日及び届出受理番号を記載すること。
2 第1面上方の提出者欄には、氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)を記名押印又は署名のいずれかにより
記載すること。
3 6欄及び7欄については、許可申請時(更新を受けた事業主にあっては直近の更新時、平成27年9月30日前に一般労働
者派遣事業の許可又は許可の更新を受けた事業所及び旧特定労働者派遣事業に係る事業所においては、報告対象期間(第
1面の8欄をいう。以下同じ。)末日)における企業規模及び日本標準産業分類に基づく産業分類(細分類)を記載する
こと。ただし、7欄については、日本標準産業分類に変更があった場合は、最新の分類に基づいて記載すること。6欄の
「大企業」は中小企業以外のものを指し、「中小企業」は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定
する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者を指すこと。
4 8欄には、年度報告の報告対象期間である、事業年度の開始の目(事業を事業年度の途中で開始した場合にあっては、
当該事業の開始の目)及び当該事業年度の終了の目(事業を事業年度の途中で終了した場合にあっては、当該事業の終了
の目)を記載すること。なお、旧特定労働者派遣事業に係る事業所のうち、事業年度の途中で労働者派遣事業の許可を受
けた事業所については、当該旧特定労働者派遣事業の事業年度の開始の目から当該旧特定労働者派遣事業の廃止日まで及
び労働者派遣事業の許可目から当該労働者派遣事業の事業年度の終了の目までを報告対象期間とする事業報告をそれぞれ
作成し、提出すること。
5 10欄の「親会社」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年
労働省令第20号。以下「労働者派遣法施行規則」という。)第18条の3第2項各号に規定する者をいうこと。当該親会社
が労働者派遣事業の許可番号又は民営職業紹介事業の許可・届出番号を有している場合には、当該番号を記載すること。
なお、当該親会社が、旧特定労働者派遣事業に係る事業所である場合には、14欄に親会社の当該旧特定労働者派遣事業に
係る届出受理番号を記載すること。
6 11欄について、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)により
請負事業となる事業を実施している場合には、1を○で囲むこと。その際、製造業に分類される事業者であって、構内請
負(発注者の事業所構内において、自社の雇用する労働者を使用し、生産活動を請け負うこと)を実施している場合に
は、「うち構内請負の実施」欄の1を○で囲むこと。
7 12欄及び13欄については、決算後の金額を記載すること。
I 年度報告
第2面
1 (1)欄の「派遣労働者数等雇用実績」には、報告対象期間の末日における派遣労働者の実人数を記載すること。
2 (1)欄の③の「無期雇用派遣労働者」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法
律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第30条の2第1項に規定する無期雇用派遣労働者を、「有期
雇用派遣労働者」とは、労働者派遣法第30条第1項に規定する有期雇用派遣労働者をいうこと(以下同じ。)。
3 (1)欄の⑤の「日雇派遣労働者」とは、労働者派遣法第35条の4第1項に規定する日雇派遣労働者をいうこと。な
お、30日以内の期間を定めた契約を更新して通算30日を超えるような場合も含まれることに留意すること(以下同
じ。)。
4 (1)欄の⑥の「登録者」とは、労働者派遣をするに際し、登録されている者の中から期間を定めて雇用した者を派遣
労働者として労働者派遣の対象とする制度(登録制度)に基づいて、派遣労働者になることを目的として派遣元事業主に
登録した者であって、既に雇用されている者を含み、過去1年を超える期間にわたり雇用されたことのない者を除くこ
と。
5 (1)欄の「通算雇用期間が1年以上の派遣労働者」とは、報告対象期間末日において通算雇用期間(実際に雇用され
た期間をいう。以下同じ。)が1年以上である派遣労働者を、「通算雇用期間が1年未満の派遣労働者」とは、報告対象
期間末日において通算雇用期間が1年未満の派遣労働者をいうこと。また、「同じ職場に1年以上派遣見込みの者」と
は、雇用契約期間が通算して1年以上であり、かつ、当該派遣労働者の同じ職場での派遣就業に係る派遣契約が通算して
1年以上である派遣労働者をいうこと。
-412-
(日本工業規格A列4)
様式第11号(第11面)
6 (2)欄については、報告対象期間内に海外派遣した派遣労働者の実人数を記載すること。
7 (3)欄の①欄については、報告対象期間内に派遣先の事業所の実数を記載すること。報告対象期間内に労働者を派遣
しなかった場合は「0」を記載すること。
8 (3)欄の②欄については、報告対象期間内に締結した労働者派遣契約(個別契約)に係る派遣期間について、総件数
(延べ件数)及び内訳としての期間別の件数を記載すること。なお、1つの労働者派遣契約において複数の派遣期間があ
る場合は、それぞれの期間別に計上した件数を記載すること。(3)欄の①欄が「0」であった場合は、「労働者派遣契
約がなかった」欄に○印をすること。
9 (3)欄の③欄については、報告対象期間(第1面の8欄)内における主な派遣先の事業主のうち取引額上位5位まで
の事業主名を記載すること。(3)欄の①欄が「0」の場合及び②欄に「労働者派遣契約がなかった」欄に○印をした場
合には、(3)欄の③欄には記載の必要がないこと。
10 (4)欄中、選択肢として番号を提示している部分については、該当する番号を記載すること。
11 (4)欄については、①欄には「労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育」の報告対象期間内における実績
を、②欄には一般教養としての訓練等の「その他の教育訓練」(安全衛生教育及び派遣労働者のキャリアアップ措置に関
するもの以外の訓練)の報告対象期間内における実績を、それぞれ記載すること。
12 (4)欄の①欄及び②欄については、教育訓練コース単位で記載し、①欄には5コースまでを、②欄には3コースまで
を記載すること。それ以上のコースがある場合は、別紙に記載すること。
13 (4)欄の①欄について、実施内容が労働安全衛生法第59条第1項の規定に該当する場合は、その内容に合致する労働
安全衛生規則第35条第1項各号のうち該当号数に応じた1~8までの数字を、労働安全衛生法第59条第2項の規定に該当
する場合は9を、同条第3項の規定に該当する場合は10を、その訓練の主な内容に応じて最大2つまで記載すること。
14 (4)欄の①欄について、「教育の内容」については、「4S(整理・整頓・清掃・清潔)運動」、「KY(危険予
知)活動」、「ヒヤリハット事例の報告」等具体的に記載すること。
15 (4)欄の①欄及び②欄について、「1人当たりの平均実施時間」には、報告対象期間内に、各コースごとに派遣労働
者が受講した1人当たりの平均実施時間数を記載すること。
16 (4)欄の②欄について、「OJT」とは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を、「OFF-JT」とはそれ以外の教育訓
練をいうこと。
17 (4)欄の②欄について、「訓練費負担の別」において、
練の全てを無償で実施することを、「2 無償(実費負担あり
として無償で実施することを、「3 有償」とは、これ以外を
票㍑
l 」六ノ
「 )、
-V
(実費負担なし)」とは、テキスト代等を含め訓
テキスト代や材料費等の実費負担があるが原則
18 (4)欄の②欄について、「賃金支給の別」において、「1有給(無給部分なし)」とは、用意した全ての教育訓練
の実施に当たって給与を支払う場合を、「2 有給(無給部分あり)」とは、自主的に実施する教育訓練については無給
とする場合があるが原則として教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合を、「3 無給」とは、教育訓練の実施時に
給与を支払わない場合をいうこと。
19 (5)欄について、イには、報告対象期間内に、新たに、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から紹介予定派
遣に係る労働者派遣契約の申込みのあった派遣労働者の実人数を記載し、そのうち報告対象期間内において紹介予定派遣
により労働者派遣された派遣労働者数の実人数をロに記載すること。ハには、報告対象期間内において紹介予定派遣によ
り派遣先に職業紹介された派遣労働者の実人数を記載し、そのうち報告対象期間内において派遣先で雇用された派遣労働
者の実人数を二に記載すること。
20 (6)欄については、報告対象期間内における雇用安定措置の対象派遣労働者(雇用安定措置を講じなかった者を含
む。)及び各雇用安定措置の区分ごとの派遣労働者の延べ人数を記載すること。「3年見込み」、「2年半から3年未満
見込み」、「2年から2年半未満見込み」、「1年半から2年未満見込み」及び「1年から1年半未満見込み」の対象派
遣労働者については、各期間に該当し、かつ当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望している者とするこ
と。同一の派遣労働者が複数の期間の区分に該当する場合は、該当する区分のそれぞれの欄に計上すること。
21 (6)欄の期間の区分は、派遣先の同じ職場への派遣期間の見込みの期間とすること。「同じ職場への派遣期間の見込
み」とは、派遣労働者の派遣就業に係る派遣契約期間を通算したものをいうこと。ただし、派遣契約期間の途中で派遣労
働者の雇用契約が満了したり、当該派遣労働者の派遣先が変わったりした場合については、当該派遣労働者が同じ職場へ
派遣されていた通算期間とすること。
22 (6)欄の「第1号の措置(派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数」、「第2号の措置(新たな派遣先の提供)を
講じた人数」、「第3号の措置(派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇用)を講じた人数」及び「第4号の措置
(その他の措置)を講じた人数」については、同一の派遣労働者に複数の措置を講じた場合においては講じた措置のそれ
ぞれの欄に計上すること。
23 (6)欄の「第4号の措置(その他の措置)を講じた人数」について、「教育訓練(雇用を維持したままのものに限
る)」、「紹介予定派遣」及び「左記以外のその他の措置」については、同一の派遣労働者に複数の措置を講じた場合に
おいては講じた措置のそれぞれの欄に計上すること。
24 (6)欄の「第1号の措置(派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数」について、前年度に派遣先への直接雇用の依
頼を行ったが前年度中には直接雇用に結びつかず、年度を超えて当年度で直接雇用に結びついた場合は、当年度でも引き
続き依頼を行ったものとして、「第1号の措置(派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数」及び「左記のうち、派遣先
で雇用された人数」のそれぞれに当該人数を記載すること。
25 (6)欄の「第4号の措置(その他の措置)を講じた人数」の「左記以外のその他の措置」については、民営職業紹介
事業の許可・届出を行っている派遣元事業主が実施する職業紹介等の措置をいうこと。
-413-
様式第11号(第12面)
(日本工業規格A列4)
第3面から第5面まで
26 (7)欄の①欄及び①の(続)欄並びに②欄の「協定対象派遣労働者」には、厚生労働省職業安定局長の定めるところ
により、労働者派遣法第30条の5に規定する協定対象派遣労働者の実人数を記載すること。
27 (7)欄の①欄及び①の(続)欄には、報告対象期間内における、最新の日本標準職業分類(中分類)に基づく職種に
基づき、該当する派遣労働者(日雇派遣労働者を除く。)の区分及び従事した業務の種類別に応じた実績を所定の欄に記
載すること。なお、「66 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)」、「67 電気工事従事者」等については、一部派
遣禁止業務も含まれていることに留意すること。また、「12 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師」(獣医師を除く。)等
の医療従事者については、紹介予定派遣や産前産後休業の代替等の場合にのみ派遣することが認められていることに留意
すること。
28 (7)欄の②欄及び③欄には、報告対象期間(第1面の8欄)内において、日雇派遣労働者を労働者派遣事業の適正な
運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」という。)
第4条第1項第1号から第18号までに掲げる業務に従事させている場合、従事した業務の種類別に応じた実績を所定の欄
に記載すること。
29 (7)欄の①欄及び①の(続)欄並びに②欄の「派遣料金」については、1人1日当たりの派遣料金(消費税を含
む。)を記載し、報告対象期間内において派遣先から得た派遣料金の総額を派遣労働者が従事した総労働時間数で除した
1時間当たりの金額をもとに、8時間(1日)業務に従事したものとして算定すること(小数点以下は四捨五入)。①欄
及び①の(続)欄の「全業務平均」には、各業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。なお、②欄の
日雇派遣労働者についての「全業務平均」は、労働者派遣法施行令第4条第1号から第18号までに掲げる業務だけでな
く、日雇派遣労働者が従事した全ての業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。
30 (7)欄の①欄及び①の(続)欄並びに②欄の「賃金」(労働基準法第11条で定める給料、手当、賞与その他名称の如
何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいう。)については、1人1日当たりの賃金を記載
し、報告対象期間(第1面の8欄)内において派遣労働者に支払った賃金の総額を派遣労働者が従事した総労働時間数で
除した1時間当たりの金額をもとに8時間(1日)業務に従事したものとして算定すること(小数点以下は四捨五入)。
なお、①欄及び①の(続)欄の「全業務平均」には、各業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。ま
た、②欄の日雇派遣労働者についての「全業務平均」は、施行令第4条第1号から第18号までに掲げる業務だけでなく、
日雇派遣労働者が従事した全ての業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。
31 (8)欄の「マージン率等の情報提供の状況」については、該当する各欄に○印をすること(複数選択可)。
- 414 -
様式第11号(第13面)
第6面
32 (9)キャリアアップ措置の実績については、報告対象期間内において労働者派遣法で求められるキャリアアップ措置
の要件を満たしているものを記載すること。その上で、事業主が独自に実施したキャリアアップ措置についても追加的に
記載してもよいこと。
33 (9)欄の①欄の「キャリアコンサルタント」とは、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定する者が行う試験の合格者
をいうこと。
34 (9)欄の①欄の「うち派遣元責任者との兼任状況」欄は、キャリアコンサルティングの窓口担当者の計の内数を記載
すること。
35 (9)欄の①欄の「キャリアコンサルティングに関する職務経験・知見のある者」欄について、「職務経験あり」と
は、過去において職務としてキャリアコンサルティングの経験がある者、職業能力開発推進者に就任したことがある者、
人事部門で3年以上の経験を積んでいる者等をいうこと。また、「知見あり」とは、過去においてキャリアコンサルティ
ング等についての職務経験はないがその知識を有する者をいう。
36 (9)欄の②欄の「実施した者の人数」については、①欄の担当者が行うキャリアコンサルティングを受けた実人数を
記載すること。
37 (9)欄の③欄については、1年以上の雇用見込みのあるフルタイム勤務の者、1年以上の雇用見込みのある短時間勤
務の者又は1年未満の雇用見込みである者ごとに別業にして記載すること。なお、「1フルタイム(1年以上雇用見込
み)」、「2 短時間勤務(1年以上雇用見込み)」、「31年未満雇用見込み」のいずれかに該当する番号に○印を付
けること。
38 (9)欄の③欄イ~ホについては、訓練の種類別に訓練コース単位で記載すること。記載欄以上のコースがある場合、
別紙に記載すること。
39 (9)欄の③欄の「訓練の内容等」欄には、「係長・課長就任研修」、「○○語研修」等訓練が特定できるよう具体的
に記載すること。
40 (9)欄の③欄の「対象となる派遣労働者」欄の上段については、該当する「種別」の番号を最大2つまで記載するこ
と。この際、登録中の者は、キャリアアップに資する教育訓練の対象となる派遣労働者に含まれないことに留意するこ
と。
「対象となる派遣労働者」欄の下段については、各年ごとの対象となる派遣労働者の実人数をそれぞれ記載すること。
「対象となる派遣労働者」について、「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」は、受講済みとして扱
い、「対象となる派遣労働者数」に算入しなくてもよいこと。
41 (9)欄の③欄の「(上段)実施時間の総計」については、各受講者に対する教育訓練実施時間の各年の1年間の合計
(受講者数×教育訓練1コマの時間(複数回実施の場合は、その合計))を記載すること。対象となる派遣労働者に対し
て、ある訓練を1年目、2年目とそれぞれ段階ごとに行う場合は、1つの同じコースの中で、それぞれの年数の欄に記載
すること。また、同一の派遣労働者に行う訓練であっても、2年目以降は1年目とは異なるコースに位置づける訓練等の
場合は、2つ以上の異なるコースとして、それぞれの年数に応じた欄に記載すること。
おって、39の「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」を受講済みとした訓練については、当該者は
実際には訓練を受講していないので、「(上段)実施時間の総計」に算入することはできないものであること。
「(下段)受講者の実人数」欄には、各年ごとの受講者の実人数を記載すること。各年に同一の訓練を複数回受講した
者は、同年内に重複計上しないこと(例えば、1年目と2年目に同一の訓練を複数回受講した者は、それぞれの年数の欄
に1人ずつ計上すること)。
42 (9)欄の③欄の「OJT」とは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を、「OFF-JT」とはそれ以外の教育訓練のこと
をいうこと。キャリアアップに資する教育訓練としてOJTを実施するに当たっては、派遣先と事前に調整等を行った上で
計画的なOJTを実施しなければならないことに留意すること。
43 (9)欄の③欄の「訓練費負担の別」において、「1無償(実費負担なし)」とは、テキスト代等を含め教育訓練の全
てを無償で実施することを、「2 無償(実費負担あり)
無償で実施することを、「3 有償」とは、これ以外をい
」六ノ
とは、テキスト代や材料費等の実費負担があるが原則として
こ
と
44 (9)欄の③欄の「賃金支給の別」において、「1有給(無給部分なし)」とは、用意した全ての教育訓練の実施に
当たって給与を支払う場合を、「2 有給(無給部分あり)」とは、自主的に実施する教育訓練については無給とする場
合があるが原則として教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合を、「3 無給」とは、教育訓練の実施時に給与を支
払わない場合をいうこと。
45 (9)欄の③欄の「厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間」については、
「各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の総計」の合計」を「各年ごとの厚生労働大臣が
定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人数」で除して算出された数字を記載すること。また、合計する各年ごとの訓
練実施時間は、「訓練の方法の別」が「1計画的なOJT」又は「2 0FF-JT」、「訓練費負担の別」が「1無償(実費負
担なし)」、「賃金支給の別」が「1有給(無給部分なし)」である等、法で定めるキャリアアップに関する要件を満
たすもの(厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練)のみを合計したものであること。なお、フルタイム勤務の者で
あって1年以上の雇用見込みのあるものについては、1年で概ね8時間以上とすることとされていること。
46 (9)欄の③欄の「1~3年目のaの合計(C)」及び「1~3年目のbの合計(d)」については、それぞれ1年目
から3年目までの値を合計した数字を記載すること。
また、「1~3年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間(C÷d)」に
は、上述の(C)を(d)で除して算出された数字を記載すること。
47 (9)欄の③欄については、上記44を満たさないものであっても派遣労働者のキャリアアップに資すると事業主が実施
した全ての訓練について記載すること。ただし、上記44を満たしていない場合、都道府県労働局による指導の対象となる
可能性があることに留意すること。
48 (9)欄の③欄の「「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額(1人1時間当たり平均)」
については、キャリアアップに資する教育訓練時に支払った賃金の平均額を記載すること。
- 415 -
(日本工業規格A列4)
様式第11号(第14面)
記載要領
Ⅱ 6月1日現在の状況報告
第7面から第9面まで
1 1欄の①欄の「派遣労働者の実人数」には、報告の対象となる6月1日現在(6月1日が日曜日に当たる場
合は6月2日現在とし、土曜日に当たる場合は6月3日現在とする。以下同じ。)において派遣していた派遣
労働者の実人数を記載すること。
2 1欄の①欄、②欄、③欄及び⑤欄の「協定対象派遣労働者」には、厚生労働省職業安定局長の定めるところ
により、労働者派遣法第30条の5に規定する協定対象派遣労働者の実人数を記載すること。
3 1欄の②欄及び②の(続)欄の「業務別派遣労働者の実人数」には、報告の対象となる6月1日現在、最新
の日本標準職業分類(中分類)に基づく職種に基づき、該当する派遣労働者の区分及び従事した業務の種類別
に応じた実績を所定の欄に記載すること。複数種類の業務に従事した派遣労働者については、報告の対象とな
る6月1日現在においてもっとも多く従事した業務に従事したものとすること。なお、「66 建設従事者(建
設躯体工事従事者を除く)」、「67 電気工事従事者」等については、一部派遣禁止業務も含まれていること
に留意すること。また、「12 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師」(獣医師を除く。)等の医療従事者につい
ては、紹介予定派遣や産前産後休業の代替等の場合にのみ限定して派遣が認められていることに留意するこ
と。
4 1欄の③欄の「特定製造業務従事者の実人数」には、報告の対象となる6月1日現在において労働者派遣法
附則第4項の「特定製造業務」に従事した派遣労働者の実人数を記載すること。
5 1欄の④欄の「期間制限の対象外となる労働者派遣に係る派遣労働者の実人数」には、6月1日現在におけ
る労働者派遣法第40条の2第1項第2号から第5号までに該当する労働者派遣に係る派遣労働者(日雇派遣労
働者を除く。)の実人数(1欄の①欄に記載した派遣労働者計の内数)を記載すること。なお、複数の事項に
該当する派遣労働者については、報告の対象となる6月1日現在においてもっとも該当する事項に記載するこ
と。
6 1欄の⑤欄の「日雇派遣労働者の実人数」のうち、「高齢者」とは労働者派遣法施行令第4条第2項第1号
に掲げる者のことをいい、「昼間学生」とは同項第2号に掲げる者のことをいい、「副業として従事する者」
とは同項第3号に該当する者であって労働者派遣法施行規則第28条の3第1項第1号に該当するもののことを
いい、「主たる生計者でない者」とは労働者派遣法施行令第4条第2項第3号に該当する者であって労働者派
遣法施行規則第28条の3第1項第2号に該当するものをいうこと。当該日雇派遣労働者が、複数の種類に該当
する場合、もっとも主たる理由と考えられるものに算定すること。
7 1欄の⑥欄の「特定製造業務従事者である日雇派遣労働者の実人数」には、6月1日現在における労働者派
遣法附則第4項の「特定製造業務」に従事していた日雇派遣労働者の実人数(1欄の⑤欄に記載した日雇派遣
労働者計の内数)を記載すること。
8 1欄の⑦欄の「日雇派遣労働者の業務別実人数」には、6月1日現在における労働者派遣法施行令第4条第
1項第1号から第18号までに掲げる業務に従事している日雇派遣労働者の実人数(1欄の⑤欄に記載した日雇
派遣労働者計の内数)を記載すること。なお、複数種類の業務に従事した日雇派遣労働者については、報告の
対象となる6月1日現在においてもっとも多く従事した業務に従事したものすること。
9 1欄の⑧欄の「日雇派遣労働者のうち期間制限の対象外となる派遣労働者の実人数」には、6月1日現在に
おける労働者派遣法第40条の2第1項第3号から第5号までに該当する労働者派遣に係る日雇派遣労働者の実
人数(1欄の⑤欄に記載した日雇派遣労働者計の内数)を記載すること。なお、複数の事項に該当する派遣労
働者については、報告の対象となる6月1日現在においてもっとも該当する事項に記載すること。
10 2欄には、6月1日現在において労働者派遣事業に係る登録者であった者の実数(同日に派遣されている労
働者を含み、過去1年以内において派遣されたことがない派遣労働者を除く。)を記載すること。
11 3欄には、報告の対象となる6月1日現在において派遣していた派遣労働者について、それぞれの保険の種
類ごとに、適用されている者の実数を記載すること。なお、6月1日現在において派遣していない者は除かれ
ることに留意すること。
12 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。
-416-
様式第12号(表面)
厚 生 労 働 大 臣 殿
労働者派遣事業収支決算書
提出者
(日本工業規格A列4)
年 月 日
[コ
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第1項の規定により下記のとお
り収支決算書を提出します。
決算対象期間
年 月 日 から
年 月 日 まで
1許可番号 2許可年月 日 年 月 日
(ふりがな)
3氏名 又 は名 称
(ふりがな)
4事業所の名 称
〒(
5事業所の所在地
)
( )
6資産等の状況
科 目 金 額(円) 備考
現金・預金
土地・建物
その他
資産額(計)
負債額(計)
7収支の状況
科 目 売上高(円) 営業利益(円)経常利益(円)当期純利益(円) 備考
総事業
労働者派遣事業
請負事業
その他の人材関連事業
その他の事業
回
- 417 -
(日本工業規格A列4)
様式第12号(裏面)
記載要領
1 表面上方の提出者欄には、氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)を記名押
印又は署名のいずれかにより記載すること。
2 決算対象期間は、事業年度の開始の目及び当該事業年度の終了の目を記載すること。
3 6欄及び7欄を記載する代わりに、貸借対照表及び損益計算書を添付することとしても
よいこと。ただし、セグメントごとの状況がわかるものが望ましいこと。
4 6欄を記載する場合において、個人の場合には納税期末日における事業に関する資産等
の状況について記載すること。
5 7欄を記載する場合、セグメントごとの売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益を
記入すること。ただし、その他の人材関連事業及びその他の事業については、売上高のみ
の記載でよいこと。
6 7欄を記載する場合において、労働者派遣事業又は請負事業を含む人材関連事業等につ
いて各事業に係る収支の状況を決算上分離できないときは、分離して記載する必要はな
く、「その他の人材関連事業」に記載すること。その場合、備考欄にその旨記載するこ
と。
7 6欄及び7欄の記載又は貸借対照表及び損益計算書については、当該事業年度の決算手
続を経ているものであること。
8 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。
9 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改
正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第1項の規定により引き続き行うことがで
きることとされた労働者派遣事業にあっては、備考欄に当該事業に係る届出受理番号及び
届出受理年月日を記載すること。
- 418 -
様式第12号-2(表面)
厚 生 労 働 大 臣 殿
関係派遣先派遣割合報告書
提 出 者
(日本工業規格A列4)
年 月 日
=
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第3項の規定により関
係派遣先への派遣割合に係る報告を提出します。
報告対象期間
年 月 日から
年 月 日まで
(力許可番号
(塾許可年月日 年 月 日
(ふりがな)
③ 氏名又は名称
(ふりがな)
④1雷雲謁告)
⑤ 住所
(法人にあっては主たる事
務所の所在地)
〒(
)
( )
1 労働者派遣実績報告
①労働者派遣の実績(総労働時間)
②富㌣うち、関係派遣先への労働者派遣の実績(総労働時
③富㌣うち、定年退職者の労働者派遣の実績(総労働時
④関係派遣先への派遣割合(%)(※1、※2)
※1(②-③)÷①×100で算出した値を記入
※2 小数点以下第1位未満切り捨て
2 連結決算導入の有無 1 有 2 無
3 備考
-419-
(日本工業規格A列4)
様式第12号-2(裏面)
記載要領
1 報告対象期間は、事業年度の開始の目(事業を事業年度の途中で開始した場合にあっては当該事
業の開始の目)及び当該事業年度の終了の目を記載すること。
2 表面上方の提出者欄には、氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)を記名押印又は署
名のいずれかにより記載すること。
3 1の①欄には、報告対象期間において、派遣労働者が労働者派遣により業務に従事した労働時間
数の総合計を記載すること。
4 1の②欄及び④欄における「関係派遣先」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号。以下「労働者派遣法施行規則」と
いう。)第18条の3第1項各号に掲げる者をいうこと。
5 1の③欄における「定年退職者」とは、60歳以上の定年に達したことにより退職した者であって
当該派遣元事業主に雇用されている者のことをいうこと。
6 1の④欄については、②欄の数から③欄の数を減じた数を①欄の数で除して得た値(小数点以下
1位未満は切り捨て)を記載すること。
7 2欄は、該当する数字を○で囲むこと。なお、「2 無」である場合には、派遣元事業主の親会
社等の名称及び派遣元事業主の親会社等の子会社等の名称を記載した書類を添付すること。この場
合において、「派遣元事業主の親会社等」とは、労働者派遣法施行規則第18条の3第2項に規定す
る者のことを、「派遣元事業主の親会社等の子会社等」とは、同条第3項に規定する者のことをい
うこと。
8 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法
律(平成27年法律第73号)附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができることとされた
労働者派遣事業にあっては、備考欄に当該事業に係る届出受理番号及び届出受理年月日を記載する
こと
-420-
様式第13号
厚 生 労 働 大 臣 殿
海外派遣届 出書
届出者
(日本工業規格A列4)
年 月 日
[コ
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第4項の規定によ
り下記のとおり届け出ます。
1許可番号 2 許可年月 日
3 事業所枝番号
(ふりがな)
4 氏名 又 は名 称
5(ふりがな)
代表者の氏名
(法人の場合)
(ふりがな)
6 事業所の名 称
〒(
7 事業所の所在地
)
( )
8海外派遣予定者数計 人
海外派遣の期間 派遣先事業所の名称濫遣先事業所の所在慧票差讐詣従事す海外派遣予定者数
年
午
年
「
月 月 月 月
ら で ら で
か ま か ま
日 日 日 日
大
人
記載要領
1 届出者欄には、氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)を記名押印又は署名のいずれかにより
記載すること。
2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第
20号)第23条の規定により定めた事項の書面の写しを添えること。
3 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。
4 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成
27年法律第73号)附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができることとされた労働者派遣事業に
あっては、備考欄に当該事業に係る届出受理番号及び届出受理年月日を記載すること。
- 421-
(日本工業規格B列8)
様式第14号(第48条関係)(表面)
ノ賊一
方吊
ロ
Jノ ̄
労働者派遣事業立入検査証
写
真
官 職
氏 名
年 月 日生
上記の者は、労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第51
条第1項の規定により立入検査をする職員であ
ることを証明する。
年 月 日
厚生労働大臣又は都道府県労働局長
三
(日本工業規格B列8)
様式第14号(裏面)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(抄)
第51条 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、労働
者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所そ
の他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させること
ができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示し
なければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら
ない。
第56条 この法律に定め厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部
を都道府県労働局長に委任することができる。
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
六 第51条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(抄)
第55条 次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事
業を行う事業所の所在地並びに労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他派遣就業
の場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らそ
の権限を行うことを妨げない。
七 法第51条の規定による立入検査
- 422 -
様式第15号
労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について
厚生労働大臣 殿
(○○労働局長 経由)
労働者派遣事業の許可申請を行うにあたり、当社の状況について以下のとおり自己チェックをいたしました。
〇〇年〇〇月〇〇日
住所
代表者役職
代表者名
(自己チェック実施者:自署であること)
役職
氏名
印
1原則の事項
質問 回答
労働者派遣法、労働基準法その他の法律を遵守する □はい □いいえ
欠格事由に該当する事項はない □はい □いいえ
専ら派遣として行う事業ではない □はい □いいえ
過去3年以内に派遣元責任者講習を受講した派遣元責任者を
規定の人数配置している
□はい □いいえ
個人情報の管理について規定の措置を実施している □はい □いいえ
□はい □いいえ
以下のいずれかの財産的基礎を満たしている 傭たしている項目に
もチェック)
□大企業、中小企業
(右の中小企業を除く)
基準資産額2,000万円以
上、基準資産額が負債の
総額の7分の1以上、現
預金1,500万円以上
□(1事業所のみの)中小企業
常時雇用している派遣労働者が
10人以下、基準資産額1,000万円
以上、基準資産額が負債の総額の
7分の1以上、現預金800万円以
上
□(1事業所のみの)中小企業
常時雇用している派遣労働者が5人
以下、基準資産額500万円以上、基準
資産額が負債の総額の7分の1以上、
現預金400万円以上
事業所はおおむね20I撼以上ある □はい □いいえ
雇用している派遣労働者について
□雇用期間が無期の派遣労働者のみを雇用している
□雇用期間が有期の派遣労働者のみを雇用している
□雇用期間が無期の派遣労働者と有期の派遣労働者をどちらも雇用している
派遣労働者を労働保険、社会保険に加入させている □はい □いいえ
- 423 -
様式第15号
2 許可要件に関する特記事項
質問 回答
派遣労働者のキャリア形成支援制度の事項
実施する教育訓練は、その雇用する全ての派遣労働者を対
象としている
□はい □いいえ
実施する教育訓練は、有給かつ無償で行われるものである □はい □いいえ
実施する教育訓練は、派遣労働者のキャリアアップに資す
る内容のものとなっている
□はい □いいえ
派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練が含
まれている
□はい □いいえ
(無期雇用派遣労働者を雇用する事業主のみ)
無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的
なキャリア形成を念頭に置いた内容のものである
□はい □いいえ
担当者を配置したキャリアコンサルティングの相談窓口を
設置しており、希望をすれば、雇用するすべての派遣労働
者が利用できる
□はい □いいえ
キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規
定されている
□はい □いいえ
派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練が行われ、教育
訓練は、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の
提供がある
□はい □いいえ
実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込
みの派遣労働者一人当たり、少なくとも最初の3年間は、
毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会の提供がある
□はい □いいえ
教育訓練に関する事項等に関する情報として、段階的かつ
体系的な教育訓練計画の内容についての情報をインターネ
ットの利用その他適切な方法により提供している
□はい □いいえ
派遣元事業主は、派遣労働者のキャリアアップ措置に関す
る実施状況等、教育訓練等の情報を管理した資料を労働契
約終了後3年間は保存している
□はい □いいえ
- 424 -
様式第15号
質問 回答
派遣労働者に関する就業規則・労働契約の記載事項
教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金
を支払うことを原則とする規定がある
□はい □いいえ
無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由と
して解雇をすることができる規程や、有期雇用派遣労働者
についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続して
いる派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを
理由として解雇をすることができる旨の規定がない
□はい □いいえ
無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働
契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者につい
て、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべ
き事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基
づく手当を支払う規定がある
□はい □いいえ
3 その他の事項
質問 回答
その他
既に事業を行っている者であって、雇用安定措置の義務を
免れることを目的とした行為を行っており、労働局から指
導され、それを是正していない者ではない
□はい □いいえ
派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施
が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備して
いる
□はい □いいえ
(記入にあたっての注意)
本票は、あくまでも許可申請内容に対する自己チェックを目的としています。
このため、すべての事項が「はい」であったとしても、審査の結果如何では自己チェックの結果とは異なるこ
とがあります。
- 425 -
様式第16号
厚生労働大臣 殿
住所
代表者
年 月 日
=
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
法律第7条第1項第4号の財産的基礎に関する要件についての誓約書
この度の労働者派遣事業の許可の申請にあたって、当社は1つの事業所のみからなる
中小企業であり、また、常時雇用する派遣労働者は10人以下の予定です。
このため、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第7条第1項第4号の要件である財産的基礎に関する要件について、資産の総額から負
債の総額を控除した額を2,000万円から1,000万円に緩和すること等とする、「当分の間
の措置」に基づいて申請いたします。
当社は、許可有効期間中において、本要件を満たすことを誓約いたします。
- 426 -
様式第16号
厚生労働大臣 殿
住所
代表者
年 月 日
=
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
法律第7条第1項第4号の財産的基礎に関する要件についての誓約書
この度の労働者派遣事業の許可の申請にあたって、当社は1つの事業所のみからなる
中小企業であり、また、常時雇用する派遣労働者は5人以下の予定です。
このため、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第7条第1項第4号の要件である財産的基礎に関する要件について、資産の総額から負
債の総額を控除した額を2,000万円から500万円に緩和すること等とする、「3年間の暫
定措置」に基づいて申請いたします。
当社は、許可有効期間中において、本要件を満たすことを誓約いたします。
- 427 -
様式第17号
労働者派遣事業
許
許可有効期間更新 3年間の暫定措置
年
可申請の 当分の間の措置
に関する常時雇用する派遣労働者数の報告について
厚 生 労 働 大 臣 殿
提出者
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
法律
霊可有効期間更宗口の申請における資産要件で 浣漂芸温
とおり常時雇用する派遣労働者数について報告します。
第5条第1項
第10条第2項
月 日
[コ
の規定による
としていただきたいことから、下記の
1許可番号 2 許可年月日 年 月 日
(ふりがな)
3氏名又は名称
(ふりがな)
4事業所の名称
〒(
5事業所の所在地
)
( )
1 2 3 4 5 6
常時雇用す
年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 る派遣労働
者数
6芸完蒜手る派
7 8 9 10 11 12
年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月
7備考
(記入要領)
1 許可申請時は、表題中及び上方の「許可有効期間更新」の文字並びに「第10条第2項」の文字を抹消するこ
と。また、許可の有効期間更新時は、表題中及び上方の「許可」の文字並びに第上方の「第5条第1項」の文字
を抹消すること。
2 「当分の間の措置」で申請する者は、表題中及び上方の「3年間の暫定措置」の文字を抹消すること。また、
「3年間の暫定措置」で申請する者は、上方の「当分の間の措置」の文字を抹消すること。
3 「1許可番号」及び「2 許可年月日」欄は許可有効期間更新の場合のみ記入すること。
4 「常時雇用する派遣労働者数」について、特定労働者派遣事業を実施していた事業主等、既に派遣労働者の雇
用実績がある事業主については、過去1年間の派遣労働者数を平均して常時雇用する派遣労働者数を算出するこ
と。新規に事業を実施する事業主等、常時雇用する派遣労働者がいない事業主については、事業計画における予
定者数を記載すること。
5 過去1年間の派遣労働者数を平均して常時雇用する派遣労働者数を算出するにあたって、小数点第1位を切り
捨てること。
6 常時雇用する派遣労働者数は、事業計画書のⅡ労働者派遣計画の派遣労働者総数計(人)と一致すること。4
の事業所にあって、計画書の派遣労働者数と異なる場合は、備考欄にその理由を具体的に記載すること。
- 428 -
(日本工業規格A列4)
年 月 日
派遣元責任者講習実施申出書
申出者名(講習機関名)
代表者名
住 所
電話番号
[コ
様式第18号
厚生労働大臣 殿
標記について、派遣元責任者講習を実施いたしたく申し出ますので、よろ
しくお取り計らい下さい。
申出者(役員を含む。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
労働者の保護等に関する法律第6条各号のいずれにも該当しないことを誓約
します。
-429-
(日本工業規格A列4)
※開催者番号
派遣元責任者講習実施日程書
年 月 日
様式第19号
厚生労働大臣 殿
以下の実施日程により派遣元責任者講習を実施いたしたく申し出ますので、貴省
ホームページへの掲載について、よろしくお取り計らい下さい。
申出者名(講習機関名)
わ
募合
応間
窓
せ
口先
匿恒朋恒法矩腸中細裾針裾集当暦集当受講中
61
日日日日日日
[Ⅱ
日日日日日日
[Ⅱ
日日日日日日
[Ⅱ
日日日日日日
[Ⅱ
日日日日日日
[Ⅱ
日日日日日日
61
日日日日日日
[Ⅱ
日日日日日日
[Ⅱ
日日日=日日
回目日日日日=日日
(記載要領)
1
2
3
通し番号順に記入すること。所定の欄に記載し得ないときは、欄を追加し11番以降の通し
番号を付けること。
実施申出書は、厚生労働省職業安定局需給調整事業課から電子媒体で配付する様式に記入
し、書面及び電子媒体により提出すること。
※欄は厚生労働省において番号を付与するものであるので、講習機関においては記入しな
いこと
- 430 -
(日本工業規格A列4)
派遣元責任者講習受講者名簿
開催者番号
申出者名(講習機関名)
代表者名
住 所
電話番号
=
講習会場番号
受講年月日
様式第20号
厚生労働大臣 殿
コ
受講者番号 受講者氏名 備考
□
回
回
□
回
因
□
回
回
[:亘]
(記載要領)
1
23
4
5
受講者名簿は、厚生労働省職業安定局需給調整事業課から電子媒体で配付する様式に記入
し、書面及び電子媒体(印は省略するものとする)により提出すること。
開催者番号及び講習会場番号は、講習実施申出の際に厚生労働省から付与したものを記入
すること。
受講者番号は、各講習ごとに付与すること。
1講習会ごとに作成すること。
所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。
- 431-
様式第21号
(日本工業規格A列4)
派遣元責任者講習受講証明書
殿
生年月日
年 月 日、○○県において、派遣元責任者講習を
受講したことを証明する。
年 月 日
講習機関の代表者
[⊃
番号(
)
(記載要領)
番号の欄には、左から順に開催者番号、講習会場番号、受講者番号を記載
し、各番号の間に-を記載すること。
-432-
(日本工業規格A列4)
年 月 日
派遣先責任者講習実施申出書
様式第22号
厚生労働省職業安定局需給調整事業課 御中
申出者名(講習機関名)
代表者名
住 所
電話番号
[コ
標記について、次の(力から③までに掲げる事項に同意して、派遣先責任者講習
を実施いたしたく申し出ますので、よろしくお取り計らい下さい。
なお、申出者(役員を含む。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律第6条各号のいずれにも該当しないことを申し添
えます。
(力申出者が実施する講習は、すべて平成30年3月30日厚生労働省制定「派遣先責
任者講習の実施に関するガイドライン」の定めに従ったものとすること。
②講習の実施状況その他講習に関する情報提供について厚生労働省職業安定局需
給調整事業課(以下「担当課」という。)から協力依頼があった場合には、これ
に応ずること。
③講習の実施が適正に行われていないと担当課が認める場合(以下「不適正な場
合」という。)であって担当課から改善要請があったときは、これに応ずるこ
と。当該要請にもかかわらずなお不適正な場合には、受講希望者保護の観点から
担当課において当該事実、講習機関名、所在地等の公表を行うことがあること。
-433-
(日本工業規格A列4)
年 月 日
派遣先責任者講習実施日程書
様式第23号
厚生労働省職業安定局需給調整事業課 御中
以下の実施日程により派遣先責任者講習を実施いたしたく申し出ますので、貴省ホームページへの掲載に
ついて、よろしくお取り計らい下さい。
申出者名(講習機関名)
わ
募合
応間
窓
せ
口先
回
開催目時 開催断 講習内容 受講定員(漂覧)募集開始日募集締那 受講料
賀8
[Ⅱ
[Ⅱ
[Ⅱ
[Ⅱ
[Ⅱ
[Ⅱ
[Ⅱ
[Ⅱ
□
(記載要領)
1 通し番号順に記入すること。所定の欄に記載し得ないときは、欄を追加し11番以降の通し番号を付けること。
2 実施申出書は、厚生労働省職業安定局需給調整事業課から電子媒体で配付する様式に記入し、書面及び電子媒体により
提出すること。
3 講習内容には、平成30年3月30日厚生労働省制定「派遣先責任者講習の実施に関するガイドライン」の別表1「派遣先
責任者講習の内容」で定める講義課目ごとに講義時間(単位:分)を記載すること(例:労働者派遣法(90))。また、
別表1の講義課目以外に独自の取組みを行う場合は、当該取組みの名称及び講義時間を記載すること(例:グループワー
ク(60))。
- 434 -
(日本工業規格A列4)
年 月 日
派遣元責任者講習廃止申出書
開催者番号
申出者名(講習機関名)
代表者名
住 所
電話番号
=
様式第24号
厚生労働大臣 殿
標記について、派遣元責任者講習を廃止いたしたく申し出ますので、よろし
くお取り計らい下さい。
-435-
(日本工業規格A列4)
厚生労働省発職号
年 月 日
労働者派遣事業
殿
不 許 可
許可有効期間不更新
通知書
厚生労働大臣 [∃
年 月 日付けの労働者派遣事業に係る申請については、下記の理由により、
許
可
許可有効期間更新
しない。
なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規
定により、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内(ただし、処分の
あった日の翌日から起算して1年以内)に厚生労働大臣に対し、審査請求をすることがで
きる。
また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に
より、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内(ただし、処分の
あった日の翌日から起算して1年以内)に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起す
ることができる。ただし、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請
求に対する裁決があったことを知った日の翌日から6箇月以内(ただし、裁決のあった日
の翌日から起算して1年以内)に提起することができる。
記
(理由)
- 436 -
年 月 日
労働者派遣事業許可条件通知書
殿
厚生労働大臣 [∃
年 月 日付け許可番号 の許可は下記の理由により次の許可条件を付し
て行う。
なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規
定により、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内(ただし、処分の
あった日の翌日から起算して1年以内)に厚生労働大臣に対し、審査請求をすることがで
きる。
また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に
より、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内(ただし、処分の
あった日の翌日から起算して1年以内)に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起す
ることができる。ただし、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請
求に対する裁決があったことを知った日の翌日から6箇月以内(ただし、裁決のあった日
の翌日から起算して1年以内)に提起することができる。
(許可条件)
(力 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこ
と。
② 派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議
の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行うものではない
こと。
③ 労働保険・社会保険の適用基準を満たす派遣労働者の適正な加入を行うものである
こと。
④ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと。ま
た、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続してい
る派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと。
⑤ 労働者派遣事業を行う事業所を新設する場合においても、「許可基準」の所定の要
件を満たすこと。
⑥ また、労働者派遣事業を行う事業所を新設する場合にあっては、届出を行うに先
立って、事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に事業計画の概要及び派遣元責任者
となる予定の者等について説明を行うこと。
記
((力、②、③及び④の理由)
労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資
すると認められる雇用慣行を考慮する必要があるため。
(⑤及び⑥の理由)
許可後に届出により新設される労働者派遣事業を行う事業所においても、適正な事
業運営を確保する必要があるため。
- 437 -
(派遣労働者用;常用、有期雇用型)
労働条件通知書
年 月 日
事業場名称・所在地
使用 者職 氏名
殿
契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり( 年 月 日~ 年 月 日)
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入
1 契約の更新の有無
[自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他( )]
2 契約の更新は次により判断する。
〔
契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 ・能力
会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況
その他(
)〕
無期転換申込権が発生しない期間:I(高度専門)・Ⅱ(定年後の高齢者)
I 特定有期業務の開始から完了までの期間( 年 箇月(上限10年))
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間
就業の場所
従事すべき
業務の内容
【有期雇用特別措置法による特例の対象者(高度専門)の場合】
特定有期業務( 開始日: 完了日: )
始業、終業の
時刻、休憩時
間、就業時転
換((1)~(5)
のうち該当す
るもの一つに
○を付けるこ
と。)、所定時
間外労働の有
無に関する事
項
1 始業・終業の時刻等
(1)始業( 時 分) 終業( 時 分)
【以下のような制度が労働者に適用される場合】
(2)変形労働時間制等;( )単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の
組み合わせによる。
)
「[、、、
業業業
ムロムロムロ
ムHダ ムHダ ムHメ
(時 分)終業(時 分)(適用日
(時 分)終業(時 分)(適用日
(時 分)終業(時 分)(適用日
フレックスタイム制・始業及び終業の時刻は労働者の決定に
)))る
ね
委
(ただし、フレキシブルタイム(始業) 時 分から 時 分、
(終業) 時 分から 時 分、
コアタイム 時 分から 時 分)
(4)事業場外みなし労働時間制;始業(時 分)終業(時 分)
(5)裁量労働制;始業(時 分)終業(時 分)を基本とし、労働者の決定に委ね
る。
○詳細は、就業規則第 条~第 条、第 条~第 条、第 条~第 条
2 休憩時間( )分
3 所定時間外労働の有無
(有 (1過 時間、1箇月 時間、1年 時間),無)
4 休日労働(有 (1箇月 日、1年 目), 無)
休 日
及び
勤 務 日
・定例日;毎週 曜日、国民の祝日、その他(
・非定例日;過・月当たり 日、その他(
・1年単位の変形労働時間制の場合一年間 日
(勤務日)
毎週( )、その他( )
○詳細は、就業規則第 条~第 条、第 条~第 条
)
)
休 暇1年次有給休暇 6箇月継続勤務した場合→ 日
継続勤務6箇月以内の年次有給休暇 (有・無)
→ 箇月経過で 日
時間単位年休(有・無)
2 代替休暇(有・無)
3 その他の休暇 有給(
無給(
)
)
○詳細は、就業規則第 条~第 条、第 条~第 条
(次頁に続く)
-438-
賃
金 1 基本賃金 イ 月給( 円)、ロ 日給( 円)
ハ 時間給( 円)、
ニ 出来高給(基本単価 円、保障給 円)
ホ その他( 円)
へ 就業規則に規定されている賃金等級等
2 諸手当の額又は計算方法
イ( 手当 円 /計算方法:
ロ( 手当 円 /計算方法:
ハ( 手当 円 /計算方法:
ニ( 手当 円 /計算方法:
3 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
イ 所定時間外、法定超 月60時間以内( )%
月60時間超 ( )%
所定超 ( )%
ロ 休日 法定休日( )%、法定外休日( )%
ハ 深夜(
4 賃金締切日(
5 賃金支払日(
6 賃金の支払方法(
( (
ヽ ヽ
日 日
月月
毎毎
一一
%))
)
)一毎月 日
)一毎月 日
)
7 労使協定に基づく賃金支払時の控除(無,有( ))
8 昇給(有(時期、金額等 ), 無)
9 賞与(有(時期、金額等 ), 無)
10 退職金(有(時期、金額等 ) 無)
))))
退職に関す 1 定年制 (有 ( 歳), 無)
る事項 2 継続雇用制度(有( 歳まで), 無)
3 自己都合退職の手続(退職する 日以上前に届け出ること)
4 解雇の事由及び手続
〔
○詳細は、就業規則第 条~第 条、第 条~第 条
]
そ の 他 ・社会保険の加入状況(厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他( ))
・雇用保険の適用(有, 無)
’その他〔 〕
・具体的に適用される就業規則名( )
1
1
1
1
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です言
l
労働契約法第18条の規定により、有期労働契約(平成25年4月1日以降に開始するもi
の)の契約期間が通算5年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か -
ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない 一
労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合!
l
は、この「5年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなりl
-..」
ます
l
※ 以上のほかは、当社就業規則による。
※ 登録型派遣労働者に対し、本通知書と就業条件明示書を同時に交付する場合、両者の記載事項のうち一致
事項について、一方を省略して差し支えないこと。
※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。
-439-
【記載要領】
1.労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成
し、本人に交付すること。
2.各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。
3.下線部、破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示する
ことが労働基準法により義務付けられている事項であること。また、退職金に関
する事項、臨時に支払われる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきもの
に関する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及
び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事
項については、当該事項を制度として設けている場合には口頭又は書面により明
示する義務があること。
4.労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。
また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新
の有無及び更新する場合又はしない場合の判断の基準(複数可)を明示すること。
(参考) 労働契約法第18条第1項の規定により、期間の定めがある労働契
約の契約期間が通算5年を超えるときは、労働者が申込みをすること
により、期間の定めのない労働契約に転換されるものであること。こ
の申込みの権利は契約期間の満了目まで行使できること。
5.「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後の
ものを記載することで足りるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的
に明示することは差し支えないこと。
また、有期雇用特別措置法による特例の対象者(高度専門)の場合は、同法に
基づき認定を受けた第一種計画に記載している特定有期業務(専門的知識等を必
要とし、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務)の内
容並びに開始日及び完了日も併せて記載すること。なお、特定有期業務の開始日
及び完了日は、「契約期間」の欄に記載する有期労働契約の開始日及び終了日と
は必ずしも一致しないものであること。
6.「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する
事項」の欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。
また、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合に
は、次に留意して記載すること。
・変形労働時間制:適用する変形労働時間制の種類(1年単位、1か月単位等)
を記載すること。その際、交替制でない場合、「・交替制」を
=で抹消しておくこと。
・フレックスタイム制:コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時
間帯の開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及
びフレキシブルタイムがない場合、かっこ書きを=で抹消
しておくこと。
・事業場外みなし労働時間制:所定の始業及び終業の時刻を記載すること。
・裁量労働制:基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業………・を基本とし、」
の部分を=で抹消しておくこと。
・交替制:シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制
でない場合、「( )単位の変形労働時間制・」を=で抹消しておく
こと。
7.「休日及び勤務日」の欄については、所定休日又は勤務目について曜日又は目
を特定して記載すること。
-440-
8.「休暇」の欄については、年次有給休暇は6箇月間勤続勤務し、その間の出
勤率が8割以上であるときに与えるものであり、その付与目数を記載すること。
時間単位年休は、労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するもの
であり、その制度の有無を記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定
超えとなる所定時間外労働が1箇月60時間を超える場合に、法定割増賃金率の
引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与えるものであり、その制度の
有無を記載すること。(中小事業主を除く。)
また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、
目数(期間等)を記載すること。
9.前記6、7及び8については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合
においては、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始
業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される
就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。
10.「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただ
し、就業規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該
等級等を明確に示すことで足りるものであること。
・法定超えとなる所定時間外労働については2割5分、法定超えとなる所定時間
外労働が1箇月60時間を超える場合については5割(中小事業主を除く。)、
法定休日労働については3割5分、深夜労働については2割5分、法定超えと
なる所定時間外労働が深夜労働となる場合については5割、法定超えとなる所
定時間外労働が1箇月60時間を超え、かつ、深夜労働となる場合については
7割5分(中小事業主を除く。)、法定休日労働が深夜労働となる場合につい
ては6割を超える割増率とすること。
・破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。
・昇級、賞与が業績等に基づき支給されない可能性がある場合や、退職金が勤続
年数に基づき支給されない可能性がある場合は、制度としては「有」を明示しつ
つ、その旨を明示すること。
11.「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を
具体的に記載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場
合においては、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示す
ことで足りるものであること。
(参考) なお、定年制を設ける場合は、60歳を下回ってはならないこと。
また、65歳未満の定年の定めをしている場合は,高年齢者の65歳
までの安定した雇用を確保するため,次の①から③のいずれかの措置
(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があること。
①定年の引上げ ②継続雇用制度の導入 ③定年の定めの廃止
12.「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇
用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及
び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に
関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設け
ている場合に記入することが望ましいこと。
13.各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で
就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しな
いこと。
* この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様
式どおりとする必要はないこと。
-441-
(派遣労働者用:日雇型)
労働条件通知書
年 月 日
事業場名称・所在地
使用 者職 氏名
殿
就 労 日 年 月 日
就業の場所
従事すべき
業務の内容
始業、終業の1 始業( 時 分) 終業( 時
分)
時刻、休憩時 2 休憩時間( )分
間、所定時間 3 所定時間外労働の有無(有 ( 時間)、 無)
外労働の有無
に関する事項
賃 金
1 基本賃金 イ 時間給( 円)、ロ 日給( 円)
ハ 出来高給(基本単価 円、保障給 円)
ニ その他( 円)
2 諸手当の額又は計算方法
イ( 手当 円 /計算方法:
ロ( 手当 円 /計算方法:
3 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
イ 所定時間外、法定超( )%、所定超( )%、
ロ 深夜( )%
))
))
4 賃金支払日( )-(就業当日・その他(
( )-(就業当日・その他(
5 賃金の支払方法( )
:6 労使協定に基づく賃金支払時の控除(無 有( ))
そ の 他 ・社会保険の加入状況(厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他( ))
・雇用保険の適用(有, 無)
・具体的に適用される就業規則名( )
’その他〔 ]
※ 以上のほかは、当社就業規則による。
※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。
-442-
【記載要領】
1.労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成
し、本人に交付すること。
2.各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。
3.下線部、破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示する
ことが労働基準法により義務付けられている事項であること。また、労働者に負
担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、災害補償及び業務
外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項については、当該事項を
制度として設けている場合には口頭又は書面により明示する義務があること。
また、日雇の労働契約についても、労働契約の更新をする場合があるものは、
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を書面により明示すること
が労働基準法により義務付けられていること。
4.「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、具体的かつ詳
細に記載すること。
5.「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。
・ 法定超えとなる所定時間外労働については2割5分、深夜労働については2
割5分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については5割
を超える割増率とすること。
・破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。
6.「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇
用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及
び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に
関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設け
ている場合に記入することが望ましいこと。
また、労働契約を更新する場合があるものについては、「期間の定めのある労
働契約を更新する場合の基準」を記入すること。
(参考) 労働契約法第18条第1項の規定により、期間の定めがある労働契
約の契約期間が通算5年を超えるときは、労働者が申込みをすること
により、期間の定めのない労働契約に転換されるものであること。こ
の申込みの権利は契約期間の満了目まで行使できること。
7.各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で
就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しな
いこと。
* この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様
式どおりとする必要はないこと。
-443-
モデル就業条件明示書
平成 年 月 日
事業所 名 称
所在地
使用者 職氏名
殿
次の条件で労働者派遣を行います。
印
業務内容
事業所、部署名
就業場所 所在地 (電話番号 )
組織単位
指揮命令者 職名 氏名
派遣期間
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
:(派遣先の事業所における期間制限に抵触する目)平成 年 月 日 :
L.________________________________________________________________l
L(組織単位における期間制限に抵触する目) 平成 年 月 日:
なお、派遣先の事業所における派遣可能期間の延長について、当該手続を適正に行っていない場合や派遣労働者
個人単位の期間制限の抵触日を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合は、派遣先は労働契約申込みみなし制
度の対象となる。
就業日
就業日及び就業時間就業時間 時 分から 時 分まで
(うち休憩時間 時 分から 時 分まで)
安全及び衛生
時間外労働及び休日時間外労働(無/有)→(1日 時間/過 時間/月 時間)
労働 休日労働(無/有)→(1月 回)
派遣元責任者 職名 氏名 (電話番号 )
派遣先責任者 職名 氏名 (電話番号 )
福利厚生施設の利用
等
苦情の処理・申出先申出先 派遣元:職名 氏名 (電話番号
派遣先:職名 氏名 (電話番号
派遣契約解除の場合
の措置
派遣先が派遣労働者
を雇用する場合の紛
争防止措置
備 考
- 444 -
モデル就業条件明示書記載要領
1 各欄において複数項目の一を選択する場合には該当項目に○印を付すこと。
2 「業務内容」欄には、派遣先において従事する業務の内容、その業務に必要とされる能力
等を具体的に記載すること。
3 「就業の場所」欄には、主な就業場所を記載するものとし、それ以外に出張等により就業
の場所が異なることがある場合には、備考欄に記載すること。
4 「組織単位」欄には、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織であり、
かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有している組織を記載す
ること。
5 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所等の業務について、派遣先が派遣
可能期間の制限に抵触することとなる最初の目を「派遣期間」欄の 缶趣すること。
(派遣先の事業所単位の期間制限の抵触目)
また、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所におけ
る組織単位の業務について派遣元事業主が期間の制限に抵触することとなる最初の目を組
l ̄ ̄ ̄ ̄
織単位欄の L日_j内に記載すること。(個人単位の期間制限の抵触目)
なお、組織単位における期間制限の抵触目は延長されることはないこと。
6 「就業日」は、具体的な曜日又は目を記載すること。
7 「安全及び衛生」欄には、次の事項のうち、派遣労働者が派遣先において業務を遂行する
に当たって、当該派遣労働者の安全、衛生を確保するために必要な事項に関し、就業条件を
記載すること。
・危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項(例えば、危険有害業務に従事さ
せる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止する措
置の内容等)
・健康診断の実施等健康管理に関する事項(例えば、有害業務従事者に対する特別な健康
診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等)
・換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項
・安全衛生教育に関する事項(例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容
等)
・免許の取得、技能講習の終了の有無等就業制限に関する事項(例えば、就業制限業務を
行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等)
・安全衛生管理体制に関する事項
・ その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項
8 「時間外・休日労働」については、6の派遣就業をする目以外の目に派遣就業をさせるこ
とができ、又は派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨
の定めを労働者派遣契約において行った場合には、当該派遣就業をさせることができる目又
は延長することができる時間数を記載すること。
なお、労働者派遣契約においてこの定めをする場合には、当該定めの内容が派遣元事業主
と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における36協定により定められている内容
の範囲内であることが必要である。
9 「派遣先責任者」は、派遣先責任者の選任を要しない場合であっても、派遣先責任者が選
任されている場合には記載すること。
10 「福利厚生施設の利用等」欄には、派遣先が派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施
設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーショ
ン等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便
宜を提供する旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、その定めを記載すること。
11「苦情の処理・申出先」欄には、派遣労働者から苦情の申出を受けた場合の苦情の処理に
ついて、労働者派遣契約に定めた苦情の申出先、苦情の処理方法、派遣元事業主と派遣先の
連携体制等を具体的に記載すること。
12 「派遣契約解除の場合の措置」欄には、派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由による
労働者派遣契約の解除が行われた場合には派遣先と連携して新たな就業機会の確保を図るこ
と、労働者派遣契約の解除に伴う解雇を行った場合には労働基準法等に基づく責任を果たす
- 445 -
こと等派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を具体的に記載すること。
13 「派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置」欄には労働者派遣の役務の提供を
受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、
その雇用意思を事前に労働者派遣をする者に対し示すこと、当該者が職業紹介を行うことが
可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者
派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置を記載すること。
14 「備考」欄
① 政令第4条第1項各号で定める業務について労働者派遣を行う場合は、政令の号番号を
記載すること。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場
合は、この限りではない。
「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、
(i)無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合
(の 契約期間が31日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合
(の(a)又は(b)の労働者派遣に限る場合
のいずれかであり、かつその旨を「備考」欄に記載すること。
(塾 派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣を行う場合は、それぞれ必要事項を
「備考」欄に記載すること。
・ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務について労働者派遣を行う場合
は、その旨を記載すること。
・ その業務が1か月間に行われる目数が当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の
労働者の1か月間の所定労働目数に比し相当程度少なくかつ月10日以下である業務につ
いて労働者派遣を行う場合は、(i)その旨、(ii)当該派遣先においてその業務が1か月間に
行われる目数、(iii)当該派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働目数を記載すること
・ 産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、
派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の目
を記載すること。
・ 介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先におい
て休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の目を記載する
こと
③ 紹介予定派遣に係る労働者派遣である場合には、(i)紹介予定派遣である旨、(ii)紹介予定
派遣を得て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無等の労働者派
遣契約において定めた紹介予定派遣に関する事項、(iii)紹介予定派遣を受けた派遣先が、職
業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受ける者を雇用しなかった場合
には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面、ファクシミリ又は電子メ
ール(ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場
合に限る。)により、派遣労働者に対して明示する旨、(iv)紹介予定派遣を経て派遣先が雇
用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間
に含めて算入する場合はその旨を「備考」欄に記載すること。
④ 労働者派遣に関する料金の額を記載する場合は、次のいずれかを日額、月額等わかるよ
うにした上で「備考」欄に記載すること。
・ 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
・ 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の
平均額
⑤ 該当する各法令に基づき、健康保険被保険者資格取得届、厚生年金保険被保険者資格取得
届、雇用保険被保険者資格取得届の書類が行政機関に提出されていない場合は、その理由
を記載すること。
15 個々の派遣労働者に明示される就業条件は、労働者派遣契約の定めた就業条件の範囲内で
なければならないこと。
- 446 -
モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)
(派遣労働者名)殿
(派遣元事業主の事業所の名称) (派遣元事業主の事業所の所在地)
電話 (電話番号)
次の条件で労働者派遣を行います。
業務内容 (業務内容)
就業場所 (就業場所の名称) (就業場所の所在地)
組織単位
指揮命令者 (指揮命令者の職名) (指揮命令者の氏名)
派遣期間 (派遣期間の開始日)から(派遣期間の終了日)まで
派遣先の事業所における期間制限抵触日
組織単位の期間制限抵触日
※派遣先の事業所における派遣可能期間の延長について、当該手続を適正に行っていない場
合や派遣労働者個人単位の期間制限の抵触目以降労働者派遣の役務の提供を受けた場合
は、派遣先は労働契約申込みみなし制度の対象となる。
就業日 (就業日)
就業時間 (就業開始時間)から(就業終了時間)まで
休憩時間 (休憩開始時間)から(休憩終了時間)まで
安全及び衛生 (安全及び衛生に関すること)
時間外労働 (有又は無) (1日、1過又は1月当たりの時間数)
休日労働 (有又は無)
派遣元責任者 (派遣元責任者の職名) (派遣元責任者の氏名)
派遣先責任者 (派遣先責任者の職名) (派遣先責任者の氏名)
福利厚生施設の利用等 (福利厚生施設の利用等に関すること)
苦情の処理・申出先 派遣元 (処理・申出先の職名) (処理・申出先の氏名)
(処理・申出先の電話番号)
派遣先 (処理・申出先の職名) (処理・申出先の氏名)
(処理・申出先の電話番号)
派遣契約解除の場合の措置 (派遣契約解除の場合の措置に関すること)
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
備考
- 447 -
モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)記載要領
1 派遣労働者の使用する携帯電話において受信することのできる最大の文字数を考慮し、最
大の文字数を超える場合においては、分割して送信すること。
2 携帯電話の画面においては、1行に表示できる文字数が少ないことから、派遣労働者が就
業条件を確認しやすくするため、項目ごとに改行するとともに、項目間においては1行空け
ること。
3 カッコが付されているものについては、カッコをはずしてカッコ内の事項を具体的にメー
ル本文に記載すること。また、カッコが付されていないものについては、そのままメール本
文に記載すること。
4 「業務内容」欄には、派遣先において従事する業務の内容、その業務に必要とされる能力
等を具体的に記載すること。
5 「就業の場所」欄には、主な就業場所を記載するものとし、それ以外に出張等により就業
の場所が異なることがある場合には、備考欄に記載すること。
6 「組織単位」欄には、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織であり、
かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有している組織を記載す
ること。
7 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所等の業務について、派遣先が派遣可
能期間の制限に抵触することとなる最初の日を「派遣先の事業所における期間制限抵触日」
欄に記載すること。
8 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織
単位の業務について派遣元事業主が期間の制限に抵触することとなる最初の日を「組織単位
の期間制限抵触日」欄に記載すること。
9 「就業日」は、具体的な曜日又は日を記載すること。
10 「安全及び衛生」欄には、次の事項のうち、派遣労働者が派遣先において業務を遂行する
に当たって、当該派遣労働者の安全、衛生を確保するために必要な事項に関し、就業条件を
記載すること。
・ 危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項(例えば、危険有害業務に従事さ
せる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止する措
置の内容等)
・ 健康診断の実施等健康管理に関する事項(例えば、有害業務従事者に対する特別な健康
診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等)
・ 換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項
・ 安全衛生教育に関する事項(例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容
等)
・免許の取得、技能講習の終了の有無等就業制限に関する事項(例えば、就業制限業務を
行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等)
・ 安全衛生管理体制に関する事項
・ その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項
11「時間外・休日労働」については、その有無を記載すること。また、9の派遣就業をする
日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は派遣就業の開始の時刻から終了の時刻まで
の時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、当該派
遣就業をさせることができる日又は延長することができる1日当たり、1過当たり又は1月
当たりの時間数を記載すること。
なお、労働者派遣契約においてこの定めをする場合には、当該定めの内容が派遣元事業主
と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における36協定により定められている内容
の範囲内であることが必要である。
12 「派遣先責任者」は、派遣先責任者の選任を要しない場合であっても、派遣先責任者が選
任されている場合には記載すること。
13 「福利厚生施設の利用等」欄には、派遣先が派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施
設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーショ
ン等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便
宜を提供する旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、その定めを記載すること
14 「苦情の処理・申出先」欄には、派遣労働者から苦情の申出を受けた場合の苦情の処理に
ついて、労働者派遣契約に定めた苦情の申出先、苦情の処理方法、派遣元事業主と派遣先の
連携体制等を具体的に記載すること。
15 「派遣契約解除の場合の措置」欄には、派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由による
労働者派遣契約の解除が行われた場合には派遣先と連携して新たな就業機会の確保を図るこ
と、労働者派遣契約の解除に伴う解雇を行った場合には労働基準法等に基づく責任を果たす
- 448 -
こと等派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を具体的に記載すること。
16 「派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置」欄には労働者派遣の役務の提供を
受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、
その雇用意思を事前に労働者派遣をする者に対し示すこと、当該者が職業紹介を行うことが
可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後
に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置を記載すること
17 「備考」欄
① 政令第4条第1項各号で定める業務について労働者派遣を行う場合は、政令の号番号を
記載すること。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかで
ある場合は、この限りではない。
「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、
(i)無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合
(の 契約期間が31日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合
(の(a)又は(b)の労働者派遣に限る場合
のいずれかであり、かつその旨を「備考」欄に記載すること。
② 派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣を行う場合は、それぞれ必要事項
を「備考」欄に記載すること。
・ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務について労働者派遣を行う場合
は、その旨を記載すること。
・ その業務が1か月間に行われる日数が当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の
労働者の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なくかつ月10日以下である業務につ
いて労働者派遣を行う場合は、(i)その旨、(の当該派遣先においてその業務が1か月
間に行われる日数、(の当該派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働日数を記載す
ること。
・ 産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は
派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日
を記載すること。
・ 介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先におい
て休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載するこ
と
③ 紹介予定派遣に係る労働者派遣である場合には、(i)紹介予定派遣である旨、(の紹介
予定派遣を得て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無等の労働
者派遣契約において定めた紹介予定派遣に関する事項、(の紹介予定派遣を受けた派遣先
が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受ける者を雇用しなかっ
た場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面、ファクシミリ又は
電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望
した場合に限る。)により、派遣労働者に対して明示する旨、(k)紹介予定派遣を経て派
遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を
勤務期間に含めて算入する場合はその旨を「備考」欄に記載すること。
④ 労働者派遣に関する料金の額を記載する場合は、次のいずれかを日額、月額等わかるよ
うにした上で「備考」欄に記載すること。
・ 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
・ 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の
平均額
⑤ 該当する各法令に基づき、健康保険被保険者資格取得届、厚生年金保険被保険者資格
取得届、雇用保険被保険者資格取得届の書類が行政機関に提出されていない場合は、
その理由を記載すること。
18 個々の派遣労働者に明示される就業条件は、労働者派遣契約の定めた就業条件の範囲内で
なければならないこと
- 449 -
(日本工業規格A列4)
厚生労働省発職派 号
年 月 日
労働者派遣受入適正実施勧告書
厚 生 労 働 大 臣 印
○ ○ 労 働 局 長 印
殿
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第49条の2
第1項の規定に基づき、下記の理由により 年 月 日
の事業所において、下記の事項を実施するよう勧告する。
なお、この勧告に従わない場合には、その旨を公表することがあることを申し添える。
記
- 450 -
(日本工業規格A列4)
厚生労働省発職派 号
年 月 日
労 働 者 派 遣 事 業 勧 告 書
殿
厚 生 労 働 大 臣 印
○ ○ 労 働 局 長 印
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第48条
第2項の規定に基づき、 年 月 日
許 可、許可番号
届出受理、届出受理番号
の事業所において、下記の事項を実施するよう勧告する。
記
- 451 -
(日本工業規格A列4)
厚生労働省発職派 号
年 月 日
労 働 者 派 遣 事 業 指 示 書
殿
厚 生 労 働 大 臣 印
○ ○ 労 働 局 長 印
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第48条
第3項の規定に基づき、 年 月 日
下記の事項を実施するよう指示する。
なお、この指示に従わない場合には、
添える。
許可を取り消す
事業廃止を命じる
記
の事業主において、
ことがあることを申し
- 452 -
身分証明証
No.
下記の者は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保
護等に関する法律第53条第1項により厚生労働大臣の委嘱した労働者
派遣事業適正運営協力員であることを証明する。
氏 名 (年 月 日生)
任 期 年 月 日まで
発行 日 年 月 日
所在地 〇〇〇〇〇
発行者 ○○労働局長
(注意事項)
この証明書の記載事項の訂正したものは無効とする。
この証明書の有効期間は表面の任期の終了日までとする。
この証明書は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
この証明書を紛失したときは、直ちに発行者に届け出なければならない。
この証明書は、新たな証明書の交付を受けたとき、任期を終了したとき、
又は退任したときには直ちに返納しなければならない。
(労働者派遣事業適正運営協力員について)
労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及
び派遣労働者の保護等に関する施策に協力して、労働者派遣をする事業主、
労働者派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれら
の者に対する専門的な助言を行う。
労働者派遣事業適正運営協力員は、正当な理由がある場合でなければ、そ
の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。労働者派遣事業
適正運営協力員でなくなった後においても、同様とする。
- 453 -
様式第25号
(派遣元)
御中
[ここに入力]
(派遣先)
比較対象労働者の待遇等に関する情報提供
[ここに入力]
平成 年 月 日
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第7
項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。
1.比較対象労働者の職務の内容(業務の内容及び責任の程度)、当該職務の内容及び配置の
変更の範囲並びに雇用形態
(1)業務の内容
① 職種:
② 中核的業務:
③ その他の業務:
(2)責任の程度
① 権限の範囲
② トラブル・緊急対応:
③ 成果への期待・役割:
④ 所定外労働
(⑤ その他
(3)職務の内容及び配置の変更の範囲
① 職務の内容の変更の範囲:
② 配置の変更の範囲:
(4)雇用形態
例1:正社員(年間所定労働時間〇時間)
例2:有期雇用労働者(年間所定労働時間〇時間、通算雇用期間〇年)
例3:仮想の通常の労働者(年間所定労働時間〇時間)
-454-
)
様式第25号
2.比較対象労働者を選定した理由
比較対象労働者:
(理由)
く参考:チェックリスト>
[ここに入力]
[ここに入力]
比較対象労働者(次の①~⑥の優先順位により選出) 対象者の有無
(○○「×)
① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範
囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通
常の労働者
③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と
同一である見込まれる通常の労働者
④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一
であると見込まれる通常の労働者
⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者
※ 派遣先の通常の労働者との問で短時間・有期雇用労
働法等に基づく均衡が確保されている者に限る。
⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるた
めに新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合に
おける当該通常の労働者(仮想の通常の労働者)
※ 派遣先の通常の労働者との問で適切な待遇が確保さ
れている者に限る。
-455-
様式第25号
[ここに入力]
[ここに入力]
3.待遇の内容等
(1)比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合に
はその旨)
(2)比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的
(3)待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項
(待遇の種類)
(待遇の (待遇の性質・目的) (待遇決定に当たって考慮した事項)
内容)
① 基本給
② 賞与
③ 役職手当:制度○
④ 特殊作業手当:制度○
⑤ 特殊勤務手当:制度○
⑥ 精皆勤手当:制度○
⑦ 時間外労働手当(法定割増率以上):制度○
⑧ 深夜及び休日労働手当(法定割増率以上):制度○
⑨ 通勤手当:制度〇
一456-
様式第25号
[ここに入力]
[ここに入力]
⑩ 出張旅費:制度○
⑪ 食事手当:制度○
⑪ 単身赴任手当:制度○
⑱ 地域手当:制度○
⑭ 食堂:施設○
⑮ 休憩室:施設○
⑪ 更衣室:施設○
⑰ 転勤者用社宅:制度○
⑱ 慶弔休暇:制度○
⑯ 健康診断に伴う勤務免除及び有給:制度○
⑳ 病気休職:制度○
⑪ 法定外の休暇(慶弔休暇を除く):制度○
⑫ 教育訓練:制度〇
一457-
様式第25号
[ここに入力]
[ここに入力]
⑬ 安全管理に関する措置及び給付:制度○
⑭ 退職手当:制度○
⑮ 住宅手当:制度○
⑳ 家族手当:制度○
⑰ 〇〇〇:制度○
※ 個々の待遇に係る制度がある場合には、(1)~(3)の事項を情報提供することが必
要であり、当該制度がない場合には、制度がない旨を情報提供することが必要。
制度がない場合には、表形式ではなく、制度がない個々の待遇をまとめて記載するこ
とでも差し支えない。
く制度がない旨の記載例>
○○手当、○○手当、○○手当、○○休暇については、制度がないため、支給等し
ていない。
※ 提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象
労働者の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第26条第7項違反と
して、派遣先(労働者派遣の役務の提供を受ける者)の勧告及び公表の対象となる場合
があるため、正確に情報提供すること。
※ 派遣元は、派遣先から提供された比較対象労働者の待遇等に関する情報のうち個人情
報に該当するものの保管及び使用について、派遣労働者の待遇の確保等の目的の範囲に
限ること。個人情報に該当しない待遇情報の保管及び使用等についても、派遣労働者の
待遇の確保等の目的の範囲に限定する等適切な対応が必要となること。
また、比較対象労働者の待遇等に関する情報は労働者派遣法第二十四条の四の秘密を
守る義務の対象となるため、派遣元は、正当な理由なく、当該情報を他に漏らしてはな
らないこと。
これらに違反する派遣元は、指導等の対象となることに留意すること。
-458-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が1人の場合)
(派遣元)
〇〇〇株式会社 御中
・:・
は留意点
平成△年△月△日
(派遣先)
□□□株式会社
役職
比較対象労働者の待遇等に関する情報提供
氏名
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第7
項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。
1.比較対象労働者の職務の内容(業務の内容及び責任の程度)、当該職務の内容及び配置の
変更の範囲並びに雇用形感【則第24条の4第1項第1号関係】:
(1)業務の内容
① 職種:衣服・身の回り品販売店員:く厚生労働省編職業細分類323-04>
匪 例えば、厚生労働省編職業細分類により記載言
ト・HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH⊥一日目HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH1
匪
例として細分類を記載しているのは、業務の内容が同一であるかどうかの判断を綱
;分類を目安として行うこととしていることによる言
L______________________________________________________________________________________________________________________________________________J
② 中核的業務:品出し、レジ、接客
③ その他の業務:クレーム対応
:※ 中核的業務以外の比較対象労働者が従事する業務を記載。
(2)責任の程度
① 権限の範囲 :副リーダー(◇等級中◇等級)
(仕入れにおける契約権限なし、部下2名)
② トラブル・緊急対応:リーダー不在である問の週1回程度対応
③ 成果への期待・役割:個人単位で月の売上げ目標30万円
④ 所定外労働 :週2回、計5時間程度(品出しのため)
(⑤ その他
匪「その他」については、責任の程度を指すものがあれば記朝
一459-
)
様式第25 (記入例:比較対象労働者が1人の場合)
・:・
は留意点
(3)職務の内容及び配置の変更の範囲
① 職務の内容の変更の範囲:他の服飾品の販売に従事する可能性あり
リーダー又は店長まで昇進する可能性あり
② 配置の変更の範囲:2~3年に1回程度、転居を伴わない範囲で人事異動あり
(4)雇用形態
例1:正社員(年間所定労働時間◇時間)
例2:有期雇用労働者(年間所定労働時間◇時間、通算雇用期間◇年)
例3:仮想の通常の労働者(年間所定労働時間◇時間)
2.比較対象労働者を選定した理由【則第24条の4第1項第2号関係】:
L______________________________________________________________________________________________________J
比較対象労働者:業務の内容が同一である通常の労働者(該当する10名中の1名)
:【以下の参考のXの③】
L___________________________________________________________________
(理由)
受け入れようとする派遣労働者と職務の内容及び配置の変更の範囲又は職務の内容
が同一である通常の労働者はいないが、業務の内容が同一である通常の労働者がいるた
め。
く参考:チェックリスト>
比較対象労働者(次の①~⑥の優先順位により選出) 対象者の有無
(○○「×)
① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範 ×
園が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通 ×
常の労働者
③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と ○
同一である見込まれる通常の労働者
④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一
であると見込まれる通常の労働者
⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者
⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるた
めに新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合に
おける当該通常の労働者(仮想の通常の労働者)
-460-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が1人の場合)
※!点線固みは留意点
3.待遇の内容等
(1)比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合に
はその旨):【則第24条の4第1項第3号関係】:
L______________________________________________________________________________________________________J
(2)比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目醐【則第24条の4第m
L________________________________________________________________
臨4号関係】:
L____________________________________J
(3)待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項【則第24条の4第1項第5号関
L_________________________________________________________________________________________
転】:
(待遇の種類)
(待遇の (待遇の性質・目的) (待遇決定に当たって考慮した事項)
内容)
① 基本給
20万円
/月
・労働に対する基本的な対
債として支払われるもの
・労働者の能力の向上のた
めの努力を促進する目的
・長期勤続を奨励する目的
能力・経験、勤続年数を考慮。
能力・経験:定型的な販売業務の処理、ク
レーム対応が可能
勤続年数:1年目(入社後4か月)
② 賞与
40万円
/年
・会社の利益を分配するこ
とによって、社員の士気を
高める目的
基本給額、支給月数により算定
個人業績に係る評価を考慮
個人業績:B評価(「特に優秀」、「優秀」、
「普通」の三段階評価の中評価)
③ 役職手当:制度有
2万円
/月
・一般社員にはない特別な
責任と役割に応じて支給
されるもの
・一定の責任と役割の履行
を促進する目的
責任の程度を考慮
役職:副リーダー
④ 特殊作業手当:制度無
⑤ 特殊勤務手当:制度無
-461-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が1人の場合)
※!点線固みは留意点
⑥ 精皆勤手当
0円
・一定数の業務を行う人数
を確保するための皆勤を
奨励する目的
責任の程度と意欲を考慮し、部下がいな
い場合であり、かつ無欠勤の場合に一律
1万円を支給
責任の程度:部下2名
欠勤の有無:無欠勤
⑦ 時間外労働手当(法定割増率以上):制度無
⑧ 深夜及び休日労働手当(法定割増率以上):制度無
⑨ 通勤手当:制度有
2万円 ・通勤に要する交通費を補 通勤距離を考慮
(実費) 填する目的
/月
⑩ 出張旅費:制度有
0円 ・出張に要する交通費を補 出張距離を考慮
填する目的 出張なし
⑪ 食事手当:制度無
⑪ 単身赴任手当:制度無
⑱ 地域手当:制度無
⑭ 食堂:施設有
食堂無
・業務の円滑な遂行に資す
る目的
就業する事業所に食堂があるか否かを考
慮し、食堂がある場合には利用の機会を
付与
就業する事業所:A支店(食堂無)
-462-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が1人の場合)
※!点線固みは留意点
⑮ 休憩室:施設無
⑪ 更衣室:施設有
利用可
・業務の円滑な遂行に資す
る目的
就業する事業所に更衣室があるか否かを
考慮し、更衣室がある場合には利用の機
会を付与
就業する事業所:A支店(更衣室有)
⑰ 転勤者用社宅:制度有
利用無
・住居を確保し、転勤に伴う
負担を軽減する目的
職務の内容及び人材活用の範囲を考慮
し、転勤がある場合に提供
職務の内容及び人材活用の範囲:転勤を
伴う人事異動なし
⑱ 慶弔休暇:制度有
10日/年
冠婚葬祭への参加を促進 勤続年数を考慮
することで就業継続や業 勤続1年以上の者に一律10日/年付与
務能率の向上を図る目的
⑯ 健康診断に伴う勤務免除及び有給:制度無
⑳ 病気休職:制度無
⑪ 法定外の休暇(慶弔休暇を除く):制度無
⑫ 教育訓練:制度有
接客に関・職務の遂行に必要な技能
する教育 又は知識を習得する目的
訓練
業務の内容を考慮。
接客に従事する場合には、6か月に1回、
希望者に限り、接客に関する基礎を習得
するための教育訓練を実施
⑬ 安全管理に関する措置及び給付:制度無
-463-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が1人の場合)
※!点線固みは留意点
⑭ 退職手当:制度有
0円 ・長期勤続を奨励する目的
・退職後の生活を保障する
目的
基本給額、勤続年数、離職理由により算定
勤続3年であって、会社都合により退職
した場合は、基本給額1か月分の退職手
当を支給
勤続年数:2年目(入社後1年3か月)
⑮ 住宅手当:制度無
⑳ 家族手当:制度有
1万円 ・労働者の家族を扶養する 扶養家族の人数を考慮し、扶養家族1人
/月 ための生活費を補助する につき1万円を支給(上限3万円)
目的 扶養家族:1人
⑰ ◇◇◇:制度◇
※ 個々の待遇に係る制度がある場合には、(1)~(3)の事項を情報提供することが
必要であり、当該制度がない場合には、制度がない旨を情報提供することが必要。
制度がない場合には、表形式ではなく、制度がない個々の待遇をまとめて記載するこ
とでも差し支えない。
く制度がない旨の記載例>
◇◇手当、◇◇手当、◇◇手当、◇◇休暇については、制度がないため、支給等し
ていない。
※ 提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象
労働者の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第26条第7項違反と
して、派遣先(労働者派遣の役務の提供を受ける者)の勧告及び公表の対象となる場合
があるため、正確に情報提供すること。
-464-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が複数の場合)
(派遣元)
〇〇〇株式会社 御中
・:・
は留意点
平成△年△月△日
(派遣先)
□□□株式会社
役職
比較対象労働者の待遇等に関する情報提供
氏名
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第7
項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。
1.比較対象労働者の職務の内容(業務の内容及び責任の程度)、当該職務の内容及び配置の
変更の範囲並びに雇用形感【則第24条の4第1項第1号関係】:
(1)業務の内容
① 職種:衣服・身の回り品販売店員:く厚生労働省編職業細分類323-04>
匪 例えば、厚生労働省編職業細分類により記載言
ト・HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH⊥一日目HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH1
匪
例として細分類を記載しているのは、業務の内容が同一であるかどうかの判断を綱
;分類を目安として行うこととしていることによる言
L______________________________________________________________________________________________________________________________________________J
② 中核的業務:品出し、レジ、接客
③ その他の業務:クレーム対応
:※ 中核的業務以外の比較対象労働者が従事する業務を記載。
(2)責任の程度
① 権限の範囲 :副リーダー(◇等級中◇等級)
(仕入れにおける契約権限なし、部下1~3名)
② トラブル・緊急対応:リーダー不在である問の週1~2回程度対応
③ 成果への期待・役割:個人単位で月の売上げ目標20~50万円
④ 所定外労働 :週0~3回、計0~6時間程度(品出しのため)
(⑤ その他
匪「その他」については、責任の程度を指すものがあれば記朝
一465-
)
様式第25 (記入例:比較対象労働者が複数の場合)
・:・
は留意点
(3)職務の内容及び配置の変更の範囲
① 職務の内容の変更の範囲:他の服飾品の販売に従事する可能性あり
リーダー又は店長まで昇進する可能性あり
② 配置の変更の範囲:2~3年に1回程度、転居を伴わない範囲で人事異動あり
(4)雇用形態
例1:正社員(年間所定労働時間◇時間)
例2:有期雇用労働者(年間所定労働時間◇時間、通算雇用期間◇年)
例3:仮想の通常の労働者(年間所定労働時間◇時間)
2.比較対象労働者を選定した理由【則第24条の4第1項第2号関係】:
L______________________________________________________________________________________________________J
比較対象労働者:業務の内容が同一である通常の労働者(該当する6名)
:【以下の参考のXの③】
L___________________________________________________________________
(理由)
受け入れようとする派遣労働者と職務の内容及び配置の変更の範囲又は職務の内容
が同一である通常の労働者はいないが、業務の内容が同一である通常の労働者がいるた
め。
く参考:チェックリスト>
比較対象労働者(次の①~⑥の優先順位により選出) 対象者の有無
(○○「×)
① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範 ×
園が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通 ×
常の労働者
③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と ○
同一である見込まれる通常の労働者
④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一
であると見込まれる通常の労働者
⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者
⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるた
めに新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合に
おける当該通常の労働者(仮想の通常の労働者)
-466-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が複数の場合)
※!点線固みは留意点
3.待遇の内容等
(1)比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合に
はその旨):【則第24条の4第1項第3号関係】:
L______________________________________________________________________________________________________J
(2)比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目醐【則第24条の4第m
L________________________________________________________________
臨4号関係】:
L____________________________________J
(3)待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項【則第24条の4第1項第5号関
L_________________________________________________________________________________________
転】:
(待遇の種類)
(待遇の (待遇の性質・目的) (待遇決定に当たって考慮した事項)
内容)
① 基本給
平均21万
円/月
又は
20~22万
円/月
・労働に対する基本的な対
債として支払われるもの
・労働者の能力の向上のた
めの努力を促進する目的
・長期勤続を奨励する目的
能力・経験、勤続年数を考慮。
能力・経験:定型的な販売業務の処理、ク
レーム対応が可能
勤続年数:2年目(入社後1年3か月)
② 賞与
平均42万
円/年
又は
32~62 万
円/年
・会社の利益を分配するこ
とによって、社員の士気を
高める目的
基本給額、支給月数により算定
個人業績に係る評価を考慮
個人業績:A~C評価(「特に優秀」、「優
秀」、「普通」の三段階評価)
③ 役職手当:制度有
2万円
/月
・一般社員にはない特別な
責任と役割に応じて支給
されるもの
・一定の責任と役割の履行
を促進する目的
責任の程度を考慮
役職:副リーダー
④ 特殊作業手当:制度無
-467-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が複数の場合)
※!点線固みは留意点
⑤ 特殊勤務手当:制度無
⑥ 精皆勤手当
0円
・一定数の業務を行う人数
を確保するための皆勤を
奨励する目的
責任の程度と意欲を考慮し、部下がいな
い場合であり、かつ無欠勤の場合に一律
1万円を支給
責任の程度:部下2名
欠勤の有無:無欠勤
⑦ 時間外労働手当(法定割増率以上):制度無
⑧ 深夜及び休日労働手当(法定割増率以上):制度無
⑨ 通勤手当:制度有
2~3
万円
(実費)
/月
・通勤に要する交通費を補 通勤距離を考慮
填する目的
⑩ 出張旅費:制度有
0円 ・出張に要する交通費を補 出張距離を考慮
填する目的 出張なし
⑪ 食事手当:制度無
⑪ 単身赴任手当:制度無
⑱ 地域手当:制度無
-468-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が複数の場合)
※!点線固みは留意点
⑭ 食堂:施設有
食堂有
又は
食堂無
・業務の円滑な遂行に資す
る目的
就業する事業所に食堂があるか否かを考
慮し、食堂がある場合には利用の機会を
付与
就業する事業所:A支店(食堂無)、B支
店(食堂有)
⑮ 休憩室:施設無
⑪ 更衣室:施設有
利用可
・業務の円滑な遂行に資す
る目的
就業する事業所に更衣室があるか否かを
考慮し、更衣室がある場合には利用の機
会を付与
就業する事業所:A支店・B支店(更衣室
有)
⑰ 転勤者用社宅:制度有
利用無
・住居を確保し、転勤に伴う
負担を軽減する目的
職務の内容及び人材活用の範囲を考慮
し、転勤がある場合に提供
職務の内容及び人材活用の範囲:転勤を
伴う人事異動なし
⑱ 慶弔休暇:制度有
0~10 日
/年
冠婚葬祭への参加を促進 勤続年数を考慮
することで就業継続や業 勤続1年以上の者に一律10日/年付与
務能率の向上を図る目的
⑯ 健康診断に伴う勤務免除及び有給:制度無
⑳ 病気休職:制度無
⑪ 法定外の休暇(慶弔休暇を除く):制度無
-469-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が複数の場合)
※!点線固みは留意点
⑫ 教育訓練:制度有
接客に関
する教育
訓練を実
施又は実
施せず
・職務の遂行に必要な技能
又は知識を習得する目的
業務の内容を考慮。
接客に従事する場合には、6か月に1回、
希望者に限り、接客に関する基礎を習得
するための教育訓練を実施
⑬ 安全管理に関する措置及び給付:制度無
⑭ 退職手当:制度有
0円
・長期勤続を奨励する目的
・退職後の生活を保障する
目的
基本給額、勤続年数、離職理由により算定
勤続3年であって、会社都合により退職
した場合は、基本給額1か月分の退職手
当を支給
勤続年数:2年目(入社後1年3か月)
⑮ 住宅手当:制度無
⑳ 家族手当:制度有
平均0.5万・労働者の家族を扶養する 扶養家族の人数を考慮し、扶養家族1人
円/月
又は
0~1万
円/月
ための生活費を補助する につき1万円を支給(上限3万円)
目的 扶養家族:0~1人
⑰ ◇◇◇:制度◇
※ 個々の待遇に係る制度がある場合には、(1)~(3)の事項を情報提供することが
必要であり、当該制度がない場合には、制度がない旨を情報提供することが必要。
制度がない場合には、表形式ではなく、制度がない個々の待遇をまとめて記載するこ
とでも差し支えない。
く制度がない旨の記載例>
◇◇手当、◇◇手当、◇◇手当、◇◇休暇については、制度がないため、支給等し
ていない。
-470-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が複数の場合)
※!点線固みは留意点
※ 提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象
労働者の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第26条第7項違反と
して、派遣先(労働者派遣の役務の提供を受ける者)の勧告及び公表の対象となる場合
があるため、正確に情報提供すること。
-471-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が標準的なモデルの場合)
(派遣元)
〇〇〇株式会社 御中
・:・
は留意点
平成△年△月△日
(派遣先)
◇◇◇株式会社
役職
比較対象労働者の待遇等に関する情報提供
氏名
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第7
項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。
1.比較対象労働者の職務の内容(業務の内容及び責任の程度)、当該職務の内容及び配置の
変更の範囲並びに雇用形感【則第24条の4第1項第1号関係】:
(1)業務の内容
① 職種:衣服・身の回り品販売店員:く厚生労働省編職業細分類323-04>
匪 例えば、厚生労働省編職業細分類により記載言
ト・HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH⊥一日目HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH1
匪
例として細分類を記載しているのは、業務の内容が同一であるかどうかの判断を綱
;分類を目安として行うこととしていることによる言
L______________________________________________________________________________________________________________________________________________J
② 中核的業務:品出し、レジ、接客
③ その他の業務:クレーム対応
:※ 中核的業務以外の比較対象労働者が従事する業務を記載。
(2)責任の程度
① 権限の範囲 :副リーダー(◇等級中◇等級)
(仕入れにおける契約権限なし、部下1~3名)
② トラブル・緊急対応:リーダー不在である問の週1~2回程度対応
③ 成果への期待・役割:個人単位で月の売上げ目標20~50万円
④ 所定外労働 :週0~3回、計0~6時間程度(品出しのため)
(⑤ その他
匪「その他」については、責任の程度を指すものがあれば記朝
一472-
)
様式第25 (記入例:比較対象労働者が標準的なモデルの場合)
・:・
は留意点
(3)職務の内容及び配置の変更の範囲
① 職務の内容の変更の範囲:他の服飾品の販売に従事する可能性あり
リーダー又は店長まで昇進する可能性あり
② 配置の変更の範囲:2~3年に1回程度、転居を伴わない範囲で人事異動あり
(4)雇用形態
例1:正社員(年間所定労働時間◇時間)
例2:有期雇用労働者(年間所定労働時間◇時間、通算雇用期間◇年)
例3:仮想の通常の労働者(年間所定労働時間◇時間)
2.比較対象労働者を選定した理由【則第24条の4第1項第2号関係】:
L______________________________________________________________________________________________________J
比較対象労働者:業務の内容が同一である通常の労働者(標準的なモデル)
:【以下の参考のXの③】
L___________________________________________________________________
(理由)
受け入れようとする派遣労働者と職務の内容及び配置の変更の範囲又は職務の内容
が同一である通常の労働者はいないが、業務の内容が同一である通常の労働者がいるた
め。
く参考:チェックリスト>
比較対象労働者(次の①~⑥の優先順位により選出) 対象者の有無
(○○「×)
① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範 ×
園が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通 ×
常の労働者
③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と ○
同一である見込まれる通常の労働者
④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一
であると見込まれる通常の労働者
⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者
⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるた
めに新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合に
おける当該通常の労働者(仮想の通常の労働者)
-473-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が標準的なモデルの場合)
※!点線固みは留意点
3.待遇の内容等
(1)比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合に
はその旨):【則第24条の4第1項第3号関係】:
L______________________________________________________________________________________________________J
(2)比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目醐【則第24条の4第m
L________________________________________________________________
臨4号関係】:
L____________________________________J
(3)待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項【則第24条の4第1項第5号関
L_________________________________________________________________________________________
転】:
(待遇の種類)
(待遇の内容)
(待遇の性質・目的) (待遇決定に当たって考慮した事項)
① 基本給
・正社員賃金規程「別表第1」の賃金表のうち、「1級1号俸」から「1級10号俸」
までを適用。
・級及び号俸は、正社員賃金規程別表第2の職能等級表により決定。
・半期ごとに評価を行い、その結果により、職能等級の上昇の有無・程度を決定。
・勤続1年につき、0.25万円の加算。
く別途、別表第1及び別表第2を提供>
・労働に対する基本的な対債として支払
われるもの
・労働者の能力の向上のための努力を促
進する目的
・長期勤続を奨励する目的
能力・経験、勤続年数を考慮。
能力・経験:定型的な販売業務の処理、ク
レーム対応が可能
勤続年数:2年目(入社後1年3か月)
② 賞与
・基本給2か月分に、個人業績に係る評価係数(※)を乗じた額を支給
※ 評価係数は、A評価(特に優秀):1.2、B評価(優秀):1.0、C評(普通):0.8
・会社の利益を分配することによって、社
員の士気を高める目的
基本給額、支給月数により算定
個人業績に係る評価を考慮
個人業績:A~C評価(「特に優秀」、「優
秀」、「普通」の三段階評価)
-474-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が標準的なモデルの場合)
※!点線固みは留意点
③ 役職手当:制度有
リーダー5万円/月、副リーダーに3万円/月を支給
・一般社員にはない特別な責任と役割に 責任の程度を考慮
応じて支給されるもの 役職:副リーグ一
・一定の責任と役割の履行を促進する目
的
④ 特殊作業手当:制度無
⑤ 特殊勤務手当:制度無
⑥ 精皆勤手当
部下がおらず、かつ無欠勤の場合に一律1万円/月を支給
・一定数の業務を行う人数を確保するた 責任の程度:部下1~3名
めの皆勤を奨励する目的 欠勤の有無:無欠勤、欠勤1日
⑦ 時間外労働手当(法定割増率以上):制度無
⑧ 深夜及び休日労働手当(法定割増率以上):制度無
⑨ 通勤手当:制度有
・実費を支給(上限5万円/月)
・通勤に要する交通費を補填する目的 通勤距離を考慮
⑩ 出張旅費:制度有
・出張に要する交通費を全額支給
・出張に要する交通費を補填する目的 出張距離を考慮
出張なし
-475-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が標準的なモデルの場合)
※!点線固みは留意点
⑪ 食事手当:制度無
⑪ 単身赴任手当:制度無
⑱ 地域手当:制度無
⑭ 食堂:施設有
就業する事業所に食堂がある場合には、利用の機会を付与
・業務の円滑な遂行に資する目的
就業する事業所に食堂があるか否かを考
慮
就業する事業所:A支店(食堂無)、B支
店(食堂有)
⑮ 休憩室:施設無
⑪ 更衣室:施設有
就業する事業所に更衣室がある場合には、利用の機会を付与
・業務の円滑な遂行に資する目的
就業する事業所に更衣室があるか否かを
考慮
就業する事業所:A支店・B支店(更衣室
有)
⑰ 転勤者用社宅:制度有
転勤があり、かつ就業する事業所が転勤者用社宅を保有している場合に提供
・住居を確保し、転勤に伴う負担を軽減す 職務の内容及び人材活用の範囲
る目的 職務の内容及び人材活用の範囲:転勤を
伴う人事異動なし
-476-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が標準的なモデルの場合)
※!点線固みは留意点
⑱ 慶弔休暇:制度有
勤続1年以上の者に一律10日/年付与
冠婚葬祭への参加を促進することで就 勤続年数を考慮
業継続や業務能率の向上を図る目的 勤続年数:2年目(入社後1年3か月)
⑯ 健康診断に伴う勤務免除及び有給:制度無
⑳ 病気休職:制度無
⑪ 法定外の休暇(慶弔休暇を除く):制度無
⑫ 教育訓練:制度有
接客に従事する場合には、6か月に1回、希望者に限り、接客に関する基礎を習得す
るための教育訓練を実施
・職務の遂行に必要な技能又は知識を習 業務の内容を考慮。
得する目的 業務の内容:品出し、レジ、接客
⑬ 安全管理に関する措置及び給付:制度無
⑭ 退職手当:制度有
勤続3年以上の場合に支給
・長期勤続を奨励する目的 基本給額、勤続年数、離職理由により算定
・退職後の生活を保障する目的 勤続年数:2年目(入社後1年3か月)
⑮ 住宅手当:制度無
-477-
様式第25 (記入例:比較対象労働者が標準的なモデルの場合)
※!点線固みは留意点
⑳ 家族手当:制度有
扶養家族1人につき1万円を支給(上限3万円)
・労働者の家族を扶養するための生活費 扶養家族の人数を考慮。
を補助する目的 扶養家族:0~1人
⑰ ◇◇◇:制度◇
※ 個々の待遇に係る制度がある場合には、(1)~(3)の事項を情報提供することが
必要であり、当該制度がない場合には、制度がない旨を情報提供することが必要。
制度がない場合には、表形式ではなく、制度がない個々の待遇をまとめて記載するこ
とでも差し支えない。
く制度がない旨の記載例>
◇◇手当、◇◇手当、◇◇手当、◇◇休暇については、制度がないため、支給等し
ていない。
※ 提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象
労働者の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第26条第7項違反と
して、派遣先(労働者派遣の役務の提供を受ける者)の勧告及び公表の対象となる場合
があるため、正確に情報提供すること。
-478-
様式第26号
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(イメージ)
○○人材サービス株式会社と○○人材サービス労働組合は、労働者派遣法第30条の4第
1項の規定に関し、次のとおり協定する。
(対象となる派遣労働者の範囲)←屠1号御される威遣労彪者の屋盈/ナ屠6号√そ
の倣厚二生労廟省令’こ定める事風の一部
第1条 本協定は、派遣先でプログラマーの業務に従事する従業員(以下「対象従業員」
という。)に適用する。
2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリ
ア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。
3 00人材サービス株式会社は、対象従業員について、-の労働契約の契約期間中に、
特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しないものとする。
(賃金の構成)
第2条 対象従業員の賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通
勤手当及び退職手当とする。
(賃金の決定方法)←屠2号イ償金の顔居古漬ノ
第3条 対象従業員の基本給及び賞与の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労
働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表1の「2」の
とおりとする。
(1)比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、「平成〇〇年〇月〇日
職発第〇〇〇〇〇号「労働者派遣法第30条の4第1項第2号イの同種の業務に従事
する一般の労働者の平均的な賃金の額について(仮称)」」(以下「通達」という。)に
定める「平成〇年賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)の「プログラマー」
碁。好の(夕~③の場合にば、その朗を労強鑑定に忍者することを求める予.定
(夕 戯摩ごとに賃金盾遥基本戯憫蒼と戯業安定業励紺を好い分ける場合
② 戯業安居業卿を用いる場合であって、好のよ 仁麒媚を好い分ける場合
廟と√書房大分者何の中郷ば小が凰
√中分数と√芳彦中脚の小分数/
③ 戯業安定局長通知で示したデ」夕以ガの鰭の公式瘡計又ば潜古顔計を用いる場合
(2)通勤手当については、基本給及び賞与とは分離し、第6条のとおりとする。
(3)地域調整については、就業地が北海道内に限られることから、通達に定める「地域
指数」の「北海道」により調整
第4条 対象従業員の基本給及び賞与は、次の各号に掲げる条件を満たした別表2のとお
りとする。
-479-
様式第26号
(1)別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上である
こと
(2)別表2の各等級の職務と別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃
金の額との対応関係は次のとおりとすること
Aランク:10年
Bランク:3年
Cランク:0年
碁㍉戯原潜において戯虜の筈腰上基準虐遜び基準超に彪カ・廊露許聾者数を乗じた盾とを対
応させ丁度慶する場合の「卿である
2 00人材サービス株式会社は、第9条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同
じ職務の内容であったとしても、その経験の蓄積・能力の向上があると認められた場合
には、基本給額の1~3%の範囲で能力手当を支払うこととする。
また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に
応じた派遣就業の機会を提示するように努めるものとする。 ←屠2号口脚容筈
の席上があった場合の賃金の改善ノ
ブ好 屠2号口聯容等の席上が為った場合の賃金の改善ノのノ坤容にば、上君の鰭に右岸々
合方:渚が考えられる
第5条 対象従業員の時間外労働手当、深夜・休日労働手当は、社員就業規則第〇条に準
じて、法律の定めに従って支給する。
第6条 対象従業員の通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
第7条 対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の
平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表3のとおりとする。
(1)退職手当の受給に必要な最低勤続年数:
通達に定める「平成28年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)の「退職一時金
受給のための最低勤続年数」において、最も回答割合の高かったもの(自己都合退
職及び会社都合退職のいずれも3年)
(2)退職時の勤続年数ごと(3年、5年、10年、15年、20年、25年、30年、33年)の
支給月数:
「平成28年中小企業の賃金・退職金事情」の大学卒の場合の支給率(月数)に、同
調査において退職手当制度があると回答した企業の割合をかけた数値として通達に
定めるもの
第8条 対象従業員の退職手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表4のとおりとす
る。ただし、退職手当制度を開始した平成○年以前の勤続年数の取扱いについては、
労使で協議して別途定める。
(1)別表3に示したものと比べて、退職手当の受給に必要な最低勤続年数が同年数以下
であること
-480-
様式第26号
(2)別表3に示したものと比べて、退職時の勤続年数ごとの退職手当の支給月数が同月
数以上であること
(賃金の決定に当たっての評価)←屠3号償金の顔居に当たっての鍬
第9条 賞与の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価の方法は社員就業
規則第〇条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、別表2の備考1のとお
り、賞与額を決定する。
(賃金以外の待遇)←屠4号償金以外の存軋
第10条 教育訓練(次条に定めるものを除く。)、福利厚生その他の賃金以外の待遇につい
ては正社員と同一とし、社員就業規則第〇条から第〇条までの規定を準用する。
(教育訓練)←屠5号傍観
第11条 労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づ
き別途定める「○○社教育訓練実施計画」に従って、着実に実施する。
(その他)
第12条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。
(有効期間)←屠6号√その倣厚二生労廟省令’こ定める事凰
第13条 本協定の有効期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの〇年間とす
る。
平成〇年〇月〇日
○○人材サービス株式会社 取締役人事部長 〇〇〇〇 印
○○人材サービス労働組合 執行委員長 〇〇〇〇 印
-481-
様式第26号
別表1 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額
(基本給及び賞与の関係)
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値
l o年Il1年「2年「3年Il5年IllO可20可
1
プロ 通達に定
ゲラ める賃金
マー 構造基本
※1 統計調査
1,160 1,349 1,449 1,538 1,632 1,885 2,339
地域
2 調整
※2
(北海道)
91.7
1,064 1,237 1,329 1,410 1,497 1,729 2,145
記入上の注意
※1 賃金構造基本統計調査又は職業安定業務統計の対応する職種について、基準値及び基準値に能力
経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
※2 派遣先事業所の所在する場所に応じて、通達に定める地域指数を乗じた数値を記載
-482-
様式第26号
別表2 対象従業員の基本給及び賞与の額
等級
職務の内容
基本給
額
(※1)
賞与額 合計額
(※2) (※4)
Aランク
上級プログラマー
(AI関係等高度
なプログラム言語
を用いた開発)
1,600~ 320 1,920
Bランク
中級プログラマー
(Webアプリ作成
等の中程度の難易
度の開発)
対応する一
般の労働者
の平均的な
賃金の額
(※3)
対応する
一般の労
働者の能
力・経験
1,729 10年
1,250~ 250 1,500 ≧ 1,410 3年
初級プログラマー
(Excelのマクロ
Cランク 等、簡易なプログ1,000~ 200 1,200
ラム言語を用いた
開発)
1,064 0年
(備考)
1 賞与については、半期ごとの勤務評価の結果により、A評価(標準より優秀)
であれば基本給額の25%相当、B評価(標準)であれば基本給額の20%相当、
C評価(標準より物足りない)であれば基本給額の15%相当を支給する。
2 未だ勤務評価を実施していない対象従業員については、C評価(標準より物足
りない)とみなして支給する。
3 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっ
ては、賞与額は標準的な評価であるB評価の場合の額によることとする。
-483-
様式第26号
記入上の注意
※1 派遣労働者の基本給及び各種手当(賞与、超過勤務手当、通勤手当(分離して比較する場合)
及び退職手当を除く)の合計を時給換算したものを記載。勤務評価の結果、その経験の蓄積・能
力の向上があると認められた場合には、1~3%の範囲で能力手当を加算
※2 賞与額は半期ごとの支給であったとしても時給換算したものを記載
※3 それぞれの等級の職務の内容が何年の能力・経験に相当するかの対応関係を労使で定め、それ
に応じた同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額を記載
※4 基本給額と賞与額の合計額を記載。この合計額が対応する同種の業務に従事する一般の労働
者の平均的な賃金の額と同額以上になっていることを確認
※ 協定締結後に厚労省が公表する賃金データが改訂された場合、別表2と別表4に定め
る賃金の額は、改訂後の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額
以上であることを確認した旨の書面を添付すること。
-484-